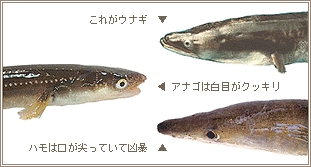新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2016年03月04日
フロリダ沖のでっかい魚がでかすぎる件
米国フロリダ沖に生息するハタ科のイタヤラは、体重360キロにもなる巨大な魚。生息数が一時より回復しつつあり、漁の再開を求める声が上がり始めた。
ハタ科の魚、イタヤラは沈没船やサンゴ礁に集まって、餌を食べ、ともに過ごす。体重360キロ、全長3メートル近くになることもある大魚で、旧約聖書の巨人にちなんでゴリアテ・グルーパーとも呼ばれる。
イタヤラは、かつて米国南部沖やカリブ海、ブラジル沿岸に数万匹が生息していたが、長年にわたる乱獲の結果、数が激減。一時は1000匹を下回ったのではとの推測もある。
ところが現在、フロリダ沖の海域では生息数が回復しつつある。そこで、漁業者や生物学者、地元当局の間で、法律に基づく保護の対象から外すべきか否か、議論が高まっているのだ。
“出無精”な習性が災いして生息数が激減
フロリダ州立大学のクリス・コーニッグは数十年にわたってイタヤラを捕獲してきた。食べるためでも、釣果を自慢するためでもない。彼は魚を釣り上げると体長や体重を測定し、DNAや年齢を調べるために、ひれの一部を切り取る。さらに胃の内容物を採取したり、産卵の兆候がないか生殖器官を確認したりする。その後、追跡用タグを埋め込んでから海に戻すのだ。
長年の地道な取り組みにより、イタヤラが姿を現す場所や時期、健康状態などの情報が蓄積されてきた。コーニッグは、妻で研究仲間でもあるフェリシア・コールマンとともに、この魚の状況を把握したい考えだ。
イタヤラの習性も数が減った一因だ。「この魚はほとんど動きません」とコーニッグは話す。餌が豊富で、身を隠せる「サンゴ礁にしがみついている」ため、簡単に捕まってしまうのだ。
ある時期まで、イタヤラを食べていたのはフロリダ・キーズなどの限られた地域だけだった。だが、1980年代に入り、ほかの魚が減ると、イタヤラは全米各地のメニューに加わるようになる。また、レジャーの釣り人にも人気で、数千匹が命を落とした。寿命が長く、成熟が遅いイタヤラは、こうして絶滅の危機に追い込まれた。
現在、フロリダ沿岸ではイタヤラの捕獲は禁止されている。「行政側は保護へと大きく傾いています」と、キーウェスト市の市会議員トニー・ヤニスは話す。「大量のマリフアナを所持するより、イタヤラを1匹捕まえる方が厳しく処罰されるほどです」
漁業者の多くはイタヤラの数が大幅に回復していると主張し、漁の邪魔をされて困ると不満を漏らす。「イタヤラは、私たちの釣り針にかかったハタやフエダイをたびたび横取りするんです」と、漁師兼ガイドのジム・トマスは話す。「ロブスターもです。実にもったいない」
【観覧注意】ピラニアの捕食スピードを検証する動画
UFOに猫耳が生えたような深海のアイドル、メンダコ。満場一致でセンターになるレベルの可愛さ!
人類が立ち入ることを許されない地、深海。そこでは、いつも見慣れている生き物さえも、信じられない姿で生活をしています。
そのなかでも、「深海のアイドル」として人気なのがメンダコ。その姿はまさに耳が生えたUFO。カメラマンの「cute!!!」の叫び。
まずは、深海という場所を知りましょう。最初の映像は深海のカメラマン達の1日。
深さは700mです。無人探索機「かいこう」であれば深海7,000mまで行けるので、そこまで深くを感じないかもしれませんが、実際は700mもぐることも非常に大変な作業。2時間かけてゆっくり海底に下りていきます。
沖縄の海のように生き物の宝庫であれば良いのですが、深海はそんな派手なものではありません。眠気に戦いながらじっと生き物が現れるのを待ちます。
この映像のなかで、3分くらいから、メンダコと呼ばれる生き物が出てきます。
この生き物、名前の通り「タコ」なのですが、さすが深海。姿かたちがいわゆるタコではありません。
なぜか耳みたいなものをつけており、さらに足が1本1本しっかり分かれていません。まさに猫耳付きのUFOという表現が1番似合います。ちなみにこの耳は「ヒレ」だそうです。
ブニブニとした体は、あまりに柔らかく、陸上に上げるとペシャンコになってしまうそう。
こちらは江ノ島水族館のメンダコさん。動きが可愛いです。
普段は深海に生息し、同じく深海の海老などを捕食しているメンダコ。
このメンダコは食べると「海水を飲んでいる」ような感覚になるらしいんだ。非常にまずいということだよ。しかもシンナーのようなキッツイ匂いがするから、網にかかるとすぐに捨てられちゃうんだって
そのなかでも、「深海のアイドル」として人気なのがメンダコ。その姿はまさに耳が生えたUFO。カメラマンの「cute!!!」の叫び。
まずは、深海という場所を知りましょう。最初の映像は深海のカメラマン達の1日。
深さは700mです。無人探索機「かいこう」であれば深海7,000mまで行けるので、そこまで深くを感じないかもしれませんが、実際は700mもぐることも非常に大変な作業。2時間かけてゆっくり海底に下りていきます。
沖縄の海のように生き物の宝庫であれば良いのですが、深海はそんな派手なものではありません。眠気に戦いながらじっと生き物が現れるのを待ちます。
この映像のなかで、3分くらいから、メンダコと呼ばれる生き物が出てきます。
この生き物、名前の通り「タコ」なのですが、さすが深海。姿かたちがいわゆるタコではありません。
なぜか耳みたいなものをつけており、さらに足が1本1本しっかり分かれていません。まさに猫耳付きのUFOという表現が1番似合います。ちなみにこの耳は「ヒレ」だそうです。
ブニブニとした体は、あまりに柔らかく、陸上に上げるとペシャンコになってしまうそう。
こちらは江ノ島水族館のメンダコさん。動きが可愛いです。
普段は深海に生息し、同じく深海の海老などを捕食しているメンダコ。
このメンダコは食べると「海水を飲んでいる」ような感覚になるらしいんだ。非常にまずいということだよ。しかもシンナーのようなキッツイ匂いがするから、網にかかるとすぐに捨てられちゃうんだって
グッピーの歴史
最初のグッピーの発見者は誰なの?
グッピーが世界で初めて紹介されたのが1850年頃と言われています。
日本の歴史上だとちょうど幕末時代の時代ですね。
イギリスの植物学者レクメア・グッピー氏が南米北部のトリニダード(現:トリニダード・トバゴ共和国)へ植物採集に行ったところ、
トリニダード(現:トリニダード・トバゴ共和国)には大変珍しい植物で溢れており
この地方の川や沼には色彩で活発に泳ぎ回っている小さな魚を発見し、
その英物を祖国のイギリスに持ち帰ったのが、グッピーが世界に登場した歴史の1ページ目になります。
発見者のレクメア・グッピー氏の名前が由来です。
トリニダード・トバゴ共和国ってどんな国?
トリニダード(現:トリニダード・トバゴ共和国)は、
北米のカリブ海の小アンティル諸島南部に位置するトリニダード島とトバゴ島の
二島と属領からなる共和制国家で、イギリス連邦加盟国です。
近隣諸国やアメリカとの関係が深いほか、旧宗主国のイギリスとの関係が深く、
イギリス連邦加盟国である。国際連合に加盟している。
1962年に独立したばかりの独立国です。
その国からイギリスの植物学者レクメア・グッピー氏が現地で
採取した生物をイギリスに持ち帰った事によってグッピーの情報が世界に広がりました。
グッピーをイギリスに持ち帰るのが大変だった
トリニダード・トバゴ共和国から祖国イギリスに持ち帰るのは大変だったそうです。
当時は飛行機など存在しない時代です。
1か月の航海を終えてグッピーをイギリスに持ち帰りました。
当時はグッピーが初めてイギリスにやってきた時は大変騒ぎになったそうです。
確かにそうですよね、今では私達は世界中の珍しい魚達を水族館で見る事も出来るし
インターネットが発達した今日、気になる魚の生態もキーボードを叩けば安易に調べることが出来ますが
当時はそんな技術がないので今まで見たことないような大変美しい魚を見たい人は多かったようです。
更にイギリス人が驚いた事にトリニダード・トバゴ共和国から1か月も船に揺られてきたにもかかわらず
グッピーは、ほとんど無事で元気がよかったとの記録も残っております。
この記録から読み取れるようにグッピーたちは環境への順応性の強さを物語っていますね。
グッピーが日本にやってきたのはいつなの?
グッピー達が日本にやってきたのは1920年(大正9年)頃と言われています。
そして10年後の1930年頃には、日本橋の三越や銀座の千疋屋にグッピーは陳列されていたそうです。
世界では戦争が真っただ中の日本で三越や銀座の千疋屋にも陳列されていた
高級熱帯魚をとても一般市民が買えるような品物ではなかったです。
では、いつから一般市民にも飼えるようになったのか・・・
日本が第2次世界大戦で負けポツダム宣言(1945年)をした3年後
1948年頃から日本でもグッピーが誰にでも飼えるようになりました。
当時のグッピーのほとんどが野生タイプで、稀にアメリカ陸軍兵士が缶詰で持ってきてたと記録されています。
グッピーが最も美しかった時代は日本人が一番頑張ってた時期
日本は戦争に負け敗戦国となりましたがそんな敗戦国を世界中の国が驚きました。
それが有名な日本の高度経済成長期です。
この頃の日本は日本経済が飛躍的に成長を遂げ日本の「精神の復興期」の時代でもあって
グッピーはもちろん、他の観賞魚、植物も動物もすべて美しかった時代です。
そんな時代を生き抜いた先人たちは美しい物に魅力されました。
軍用イルカの歴史−ネイビー・ドルフィン−
1.軍用イルカの活躍
アメリカとロシアはこれまで軍隊でイルカなどを訓練していました。訓練の内容は、水中で迷ったダイバーの救出、或いは海面下の機雷の捜索を行っていました。しかし、ロシアは1990年代の初めにこれを終了しています。
アメリカ海軍は今でもサンディエゴの基地でイルカ及びアシカの訓練を続けています。イルカの寿命は約30年です。これまで海軍は任務の遂行ができなくなって引退したイルカをマリンパークなどに提供したこともあります。海軍は1960年代以来、海獣類を訓練しており、現在でも約100頭のイルカおよびアシカを飼っています。大部分はサンディエゴの基地で飼育されています。
海軍はこれまで約35年間に海獣類の飼育技術や病気の治療、そして繁殖の技術など多くを学びましたが、これらの論文は機密にせずに公開されていて水族館で飼育されている海獣類の管理にもこの情報が役立たれています。また、さらに民間人など無差別殺人を引きおこす機雷の掃海や重要海域で軍用・民間用の船舶を破壊するテロ行為を防ぐためにイルカ・アシカが使われていて、あくまで平和的な活動にのみ使われています。そして海軍は、これらの任務はイルカやアシカの能力でしか実現できないと言っています。
一方、海軍では最先端の技術を使って、海獣達を使わない活動も視野に入れていて、海獣類のバイオセンサーを超える機器の開発にも力を入れています。
こうした軍用イルカの存在を心配するグループもいて、WDCS(クジラ・イルカ保護学会)は、軍用イルカの扱いに疑問を投げています。この作戦でイルカが傷つく可能性があるのでは?、賢いイルカに対し間違った使い方をしているのではないか? との懸念もあるのです。例えばイラク戦争に使用されるイルカとアシカは、行動が制限されることや精神的ストレスで、自然界のイルカより寿命の低下、乳児の高死亡率などがあると説明しています。
その間にも、米海軍のイルカは、バルト海、アラスカ、ハワイ、フロリダ、ペルシャ湾、ベトナム。またイラク戦争の中でも使用されてきました。
これらの展開で海軍は、イルカ・アシカの船での移動、ヘリコプターでの輸送などを経験し、より良い輸送方法の模索、輸送ダメージの軽減をはかる輸送容器の改良などを行ってきました。
こうした様々な問題を含みながらも、人類が初めてイルカとのコミュニケーションがとられた軍用イルカ、あるいはネービー・ドルフィンとも呼ばれるこのプロジェクトを学んでみましょう。ここでは、新しい話題から徐々に昔の情報へさかのぼっていきます。
2.2007年
2007年2月 米海軍はワシントン州の海軍基地にイルカ・アシカを実戦配備したと発表しました。ワシントン州シアトルの近くにあるキトサップ・バンゴール海軍基地。同海軍基地は潜水艦基地という性格上、海上での警備活動に加えて海中での警備活動(不審者の侵入)の必要性が重視されたので、テロを抑えるためにイルカ・アシカが配備されたました。
配備されたイルカ・アシカはサンディエゴにある海軍哺乳類教育センターで特殊訓練が行われ、その一期生がシアトルへ送られました。最終的に30頭ほどのアシカと大西洋のバンドウイルカを送ることになっています。送られるアシカ・イルカはこの特殊な任務に適性を持っています。イルカの驚くようなソナー能力を駆使して、許可を得ないスイマーやダイバーの存在を知らせることができます。イルカはこのような不審者を見つけると、不審者発見の信号を放して、ここに不審者がいたという位置発信器が発信を開始するのです。一方、アシカはその発信器に音を頼りに近づき口のハーネスに長いロープを付けて、水中の不審者に近づき、後方から不審者の脚部をカフスで拘束する技術を教えています。こうして水中の不審者を探しだすことができます。さらにはロープを引いて不審者を引き上げることもできます。
海軍では今後も海中警備任務の他にも、機雷除去任務などに特殊訓練を受けたイルカ・アシカを使う意向です。また、海軍では現在、特殊訓練を受けたイルカ・アシカが環境に与える影響度を調査しています。これはその海域の野生のイルカとの問題や病気の感染などであり、広くパブリックオピニオンも受け入れるとしています。
3.2005年
これまでアメリカ海軍の"軍用イルカ"は小説「イルカの日」のイメージをダブらせて、イルカやアシカが爆弾を抱えた"動物兵器"ではないかと取り上げられてきた経緯があります。また、2005年にはハリケーン・カトリーナの襲来でフロリダの施設から逃げ出した軍用イルカが、毒矢を装備していたのではないかと大きくメディアに取り上げられました。 いずれも英国の同一新聞記者が記事にしていて、根拠がうすい記事であったようです。
4.2003年
イラク戦争では、クエートに近いイラクのウムスカル湾の機雷の掃海に米海軍のイルカが出動しました。イラクへ支援するための船舶が入港できないと復興作業に支障をきたすからです。この任務はとても重要な任務でした。海軍では70頭のイルカと20頭のアシカを訓練していますが、この内9頭(8頭の記事もある)のイルカがイラクに派遣されました。サンディエゴからペルシャ湾までは空輸され、ペルシャ湾では艦船のイルカプールの中で移送されました。さらに現場への移送ではヘリコプターが使われています。
最初の展開は3月26日で、2頭のイルカがウムスカル湾の機雷の設置された海域を捜索しました。海域では機雷の捜索よりも野生のイルカがいると2頭のイルカが襲われる危険の方が高いと言われています。
任務はイラクが設置した機雷約100機の設置位置を探すこと、探したら機雷の位置を知らせるために機雷の周りを旋回すること、旋回することで掃海艇に機雷の位置が判るようイルカには位置情報発信器が取り付けられていました。そして機雷は撤去され、復興のための船舶の出入りが行えるようになりました。
5.1990年代
冷戦状態が終えて、米海軍の海獣プログラムは徹底的に縮小されて行きました。そしてサンディエゴのトレーニングセンターを除いてハワイとフロリダの施設は全て閉鎖されました。こうして103頭のイルカは70頭だけになりました。この時、海軍は50万ドルを使ってイルカを自然の生息地へ戻すための計画に使われました。退役したイルカが自然の中で生活するための"リハビリ訓練"が必要なのです。また、退役した一部は水族館などへの提供が申し出られましたが、4件の問い合わせしかありませんでした。1994年の終わりにフロリダ、キーの近くに3頭のイルカを飼育して自然の海へ戻す教育が行われました。
そしてさらに、1992年には海獣プログラムの機密扱いは解除され、多くのイルカが退役しました。この退役したイルカを海へ戻すことの論争が大きな話題になりました。
バンドウイルカは海面下の機雷の掃海を行っていました。イルカはエコロケーションで機雷を見つけ、機雷の近くにウエイトの付いたロープラインを置いていました。一方、アシカは海底の落下物にリカバリー装置を取り付ける訓練を行っていました。これらは水中処分隊のダイバーと連携で行われています。
機雷の掃海訓練では最初にダイバーが行って、最後にはイルカ・アシカによって残った機雷がないか掃海されていました。また、他の訓練では、バンドウイルカによる警戒水域の確保が行われていました。
これらの機雷の掃海と警戒水域の確保はベトナム戦争(1960?75年)で実戦配備され、警戒水域の確保が行われました。警戒水域の確保では、警戒水域をイルカがゆっくり泳いで警戒し、許可を得ない人の侵入があれば警備員に知らせる。或いは侵入をブロックすることができます。しかし、ベトナム戦争では、よく言われるようにイルカが侵入者を武器で襲う訓練や活動は一切行っていないそうです。
1997年にソ連の海軍が訓練したウクライナのイルカは、今、アメリカにいて、自閉症で情緒不安定の子供の治療のために活躍しています。
6.1980年代
米海軍の海獣プログラムは、800万ドルの予算を使って多数のアシカとベルーガ(シロイルカ)・クジラ、そしてイルカは100頭以上も飼育・訓練して全盛期を迎えました。
1986年には、議会が部分的に海獣保護法(1972年)を撤廃し、野生のイルカを国防目的で捕獲していました。海軍は機雷処理ユニットを拡張し、さらに繁殖プログラムを構築しました。
1986-88年にはペルシャ湾へ出動しましたが、6頭のイルカで機雷の掃海、警戒水域の警備を行いました。任務はペルシャ湾、バーレーンの湾内警備、クエートの石油施設で行われました。この内、イルカの「スキッピー」は細菌感染で現地において死亡しました。
1980年代の後半にはワシントン州での警戒水域の警備の計画がありましたが、動物愛護団体などからメキシコ湾で捕らえられたイルカを冷たい水域の北部へ配置することはイルカを傷つけるとして海軍を訴訟しました。結果的に海軍はこのプロジェクトを放棄しました。
1994年までに基本的に異なる水温環境にイルカを移動させることはなくなりました。海軍は緊急時を除けば温度20度の差の範囲内としました。
7.1960年代
米海軍の海獣プログラムは2つのゴールから1960年に始まりました。最初に、海軍は、障害物を検知するより効率的な方法を開発するため、イルカ、ベルーガ、及びクジラの水面下のソナー能力を研究していました。加えて、船舶および潜水艦の速度を改善するために、高速で泳ぐイルカを研究しました。
海軍は、さらに、海底の落下物の捜索のためにイルカなどの口で保持されたカメラを使用して、捜索を行う訓練をイルカ、ベルーガ・クジラ、アシカおよび他の海獣を訓練しました。特にイルカは、ベトナム戦争とペルシャ湾の中で何回か使用されました。この海獣プログラムは、冷戦中に最も多く使用されていました。ソ連の軍関係でも水面下を支配するために同様の研究と海獣類の訓練を行っていました。
1965年には、海獣プログラムの最初の活動が行われました。それは海底居住実験の「シーラブ計画」でした。カリフォルニア、ラ・ホヤ沖の海底で生活しているアクアノート(ダイバー)にメールや機材をイルカの「タフィー」が運んだり、迷ったダイバーをハビタート(居住基地)へ連れ戻す役割を担っていました。「タフィー」は日に何回も水深60mまで潜って最初の海獣システムの演習を成功に導きました。
1965?75年の間にカムラン湾の警戒水域の確保に5頭のイルカが派遣されました。この時も不法侵入者に対して殺人機器を使ったのではないかと報道されましたが、根拠の薄い報道と判断されました。
1975年 イルカプログラムの成功でアシカ、ベルーガ、クジラを導入しました。このプロジェクトは海底に落とした機器の回収を迅速に、確実に、安価で行うことでした。アシカは水深200mまでの落下物(ミサイル)を回収することができました。他の動物であるベルーガ、クジラはイルカ・アシカより深い水深、さらに低い水温でも活動できることができました。
この成果による予算増加にともなってイルカを捕獲して訓練イルカを増加させたのです。
ダイエットに 美容に 女性にこそすっぽん
女性の強い見方「すっぽん」
すっぽんと言えば滋養強壮・スタミナ食材というイメージですが・・・。
すっぽんは鰻と同様、女性に食べて頂きたい食材としてご紹介します。

お肌にコラーゲン
まずは、コラーゲン。 すっぽんの甲羅の周り、2センチほどは柔らかくなっています。
これをエンペラと言いますが、ここはコラーゲンの固まりです。
これを煮詰めて一晩置いて冷めるとひっくり返しても落ちないくらいプルプルになります。
疲労回復・ダイエットに
また、すっぽんには天然の良質なアミノ酸がふんだんに含まれていて、体内では作る
事が出来ないアミノ酸成分もたくさん含んでいます。
こらはダイエットにそして美容に、強い見方です。
若さと健康維持に
また動物性でありながら植物性に近いすっぽんの脂は、オイレン酸、リノール酸、DHA
EPAなど不飽和脂肪酸を多く含みます。不飽和脂肪酸は悪玉コレステロールを減少
させてくれる若さと健康の源です。
いかがですか。 女性にこそ食べて頂きたい理由がお分かりいただけたでしょうか。
女性の皆様、夏こそすっぽんで美貌と健康を手に入れましょう。
すっぽんと言えば滋養強壮・スタミナ食材というイメージですが・・・。
すっぽんは鰻と同様、女性に食べて頂きたい食材としてご紹介します。

お肌にコラーゲン
まずは、コラーゲン。 すっぽんの甲羅の周り、2センチほどは柔らかくなっています。
これをエンペラと言いますが、ここはコラーゲンの固まりです。
これを煮詰めて一晩置いて冷めるとひっくり返しても落ちないくらいプルプルになります。
疲労回復・ダイエットに
また、すっぽんには天然の良質なアミノ酸がふんだんに含まれていて、体内では作る
事が出来ないアミノ酸成分もたくさん含んでいます。
こらはダイエットにそして美容に、強い見方です。
若さと健康維持に
また動物性でありながら植物性に近いすっぽんの脂は、オイレン酸、リノール酸、DHA
EPAなど不飽和脂肪酸を多く含みます。不飽和脂肪酸は悪玉コレステロールを減少
させてくれる若さと健康の源です。
いかがですか。 女性にこそ食べて頂きたい理由がお分かりいただけたでしょうか。
女性の皆様、夏こそすっぽんで美貌と健康を手に入れましょう。
謎だらけのフライフィッシングの創始者と言われるジュリアナ・バーナーズ
巷ではフライフィツシングの創始者はジュリアナ・バーナーズとされています。
現存する最古の釣りの指南書と言われる「釣魚論」は1496年にイギリスで出版され、その作者は貴族階級出身の修道院の尼僧である女性だったとのこと。
彼女はこの本の中で世の紳士たちに釣りをすることを勧めていて、世界中の釣り師に「フライフィッシングの母」と呼ばれています。
アイザック・ウォルトンの「釣魚大全」にも紹介されているフライのほとんどはジュリアナ・バーナーズの「釣魚論」を踏襲したもの。
だが、このジュリアナ・バーナーズは謎だらけの人物でもあるのだ。
その当時の時代背景や習慣・風習からして女性がフライフィッシングをすることに疑問を持つ方も少なくはないだろう。
だから、「実はフランスの本の翻訳ではないか?」だとか、「ジュリアナではなくジュリアンという男性ではないか?」という噂もあがった。
諸説プンプンな中、今現在落ち着いているのは、
セント・オールバンズ市の尼僧、
またはソップウェルと言う町の修道院の副尼僧長・・だったという説。
いずれにせよ尼僧で、高貴な生まれの美人だった・・・・と言われ続けてきた。
だが、これらのことを覆すような異説も近年登場している。
彼女は実在の人物ではなく、本の著者は「釣魚論」の出版に携わったウインキン・デウォルデという人物ではないか?と言うことなのです。
「釣魚論」はそれ以前からあったさまざまな原稿をまとめたものなので、ウインキン・デウォルデは自分の名前を出すのは避けて、
女性の著者名で出版したという説が浮上している。
ジュリアナ・バーナーズが実在のにそうなのか、実は男性の著者なのかは、はっきりとは分っていない。
これまで言われ続けてきたことが真っ赤なウソとは思いたくもないが、1500年頃の時代の女性がフライフィッシングをやること自体疑問符を持つ方も少なくないはず。
この本を読めばますます、懐疑的になるかも??
大好きだけど意外と知らない「マグロ」のこと
日本人のマグロの人気は相変わらずですね。 この「マグロ」、食べることには興味がありますが、その生態やなどはあまり知られていないですね。 今回は人気のマグロについて解説してみましょう。


実は”出世魚”なんです。
マグロはスズキ目サバ科の魚で、サバやカツオ、サワラの親類です。
このうちマグロ属は
ホンマグロ、ビンナガ(ビンチョウ)、メバチ、キハダ、タイセイヨウマグロ、ミナミマグロ(インドマグロ)、コシナガの7種類があります。
マグロ一族は、すべて熱帯の海で5月から6月ごろ産卵します。
種類によってそれぞれ産卵する場所が異なり、ホンマグロは地中海やメキシコ湾など、ミナミマグロはジャワ島の南方、キハダやメバチは赤道付近に産卵場所があるといわれています。
また、小型のビンナガは太平洋広域で産卵するといわれています。
それぞれの産卵場所では、まずメスが海面付近でゆっくりと群れ、輪を描くように泳ぎながら産卵します。
ビンナガマグロで80万〜260万粒、大きなクロマグロは930万〜4000万粒も産卵するといいます。
続いて、オスが群れながらそこに精子を振りかけます。
受精卵はそのまま海面に浮遊します。
透明な卵なので、他の魚に気付かれることはありません。
そして、わずか1日で孵化するといわれています。
キハダやメバチは赤道付近に産卵場所があるマグロの稚魚は黒潮にのって回遊し、夏から秋にかけて相模湾などにやってきます。
この時期、この相模湾でも、80〜90センチ前後のマグロがつれることがあります。
この相模湾などで釣れるメジと呼ばれるマグロはホンマグロの幼魚。
静岡では、このマグロの成長に合わせてその呼び名が変わります。
メジカッコ → メジカ → メジ → クロシビ → シビ
と呼び名が変化していくのです。
マグロも『出世魚』なんです。
江戸時代には下級の食べ物だった
マグロは今でこそ高級魚。
おすし屋さんで、トロでも注文しようものなら、その美味しさが舌先に残る余韻も吹き飛ぶくらいの「お会計」となりますね。
しかし、江戸時代にはこれがまったく下級の食べ物であったとされています。
『本朝食鑑』には
「凡そ士以外の人は食べないものである」とあり
『魚鑑』には
「肉赤く血点あり、味いよからず」とあり、
さらに『古今料理集』には
「まぐろ、下魚也。 賞翫に用いず」とそっけない表現がされています。
特に「トロ」は脂肪が強いため敬遠され、すし屋でも赤身のほうが値段が高かったといわれています。
当時、武家は赤身を好み、脂身であるトロは庶民や肉体労働者が食べればよいとばかりに捨てられていたといいます。
江戸庶民の味 『ネギマ鍋』
それならばと江戸時代に庶民が考えたのが『ネギマ鍋』です。
”ネギ”は葱をさします。
”マ”はマグロという説と、マグロの脂を移した葱を主役で食べる”間つなぎ”でマグロを食べたことから”ネギマ”となったという説があります。
食べ方は、すき焼きと同じように2種類があり、平鍋で割り下を具が浸るほどに入れて食べる方法と、深鍋にたっぷりの割り下を入れて煮込む方法があったといいます。
いずれにせよ、脂の乗った『トロ』の旨味と栄養が江戸庶民の活力源であったことは間違いないですね。
マグロが高級魚になったのは昭和30年代から
マグロは明治のころまではそれほど高級な魚ではなかったようです。
それが、近年のように高級化していったのは、日本人の食生活が脂っこくなった昭和30年代以降といわれています。
この頃、ついにトロが赤身を追い抜き、ホンマグロの大トロともなれば、とても庶民の口には入らない高値の花となっていくのでした。
トロが多いのはホンマグロですが、それでも200キロ以上の大物からでも、わずか15キロ位しか採れません。
市場の卸価格で、ホンマグロのトロはキロ当たり何万円もします。
胸ビレからアゴにかけてのカマの部分である大トロ(別名カマサキ)となれば当然それ以上の値段になります。
通常我々が食べているのはホンマグロではなく、メバチマグロがほとんどです。
しかしこのメバチマグロ、魚体が小さく、トロにあたる腹肉部は薄いため、トロはほとんどありません。 やはりその希少性から高値になるというわけですね。
まとめ
最近では、回転寿司などでマグロが安く食べられるようになりました。 トロも比較的安く食べられるようにはなりましたが、たまには”本物”のトロを食べてみたいですね。 そのためにはまず、『お金持ちのスポンサー』を探すところから始めましょうか?
実は”出世魚”なんです。
マグロはスズキ目サバ科の魚で、サバやカツオ、サワラの親類です。
このうちマグロ属は
ホンマグロ、ビンナガ(ビンチョウ)、メバチ、キハダ、タイセイヨウマグロ、ミナミマグロ(インドマグロ)、コシナガの7種類があります。
マグロ一族は、すべて熱帯の海で5月から6月ごろ産卵します。
種類によってそれぞれ産卵する場所が異なり、ホンマグロは地中海やメキシコ湾など、ミナミマグロはジャワ島の南方、キハダやメバチは赤道付近に産卵場所があるといわれています。
また、小型のビンナガは太平洋広域で産卵するといわれています。
それぞれの産卵場所では、まずメスが海面付近でゆっくりと群れ、輪を描くように泳ぎながら産卵します。
ビンナガマグロで80万〜260万粒、大きなクロマグロは930万〜4000万粒も産卵するといいます。
続いて、オスが群れながらそこに精子を振りかけます。
受精卵はそのまま海面に浮遊します。
透明な卵なので、他の魚に気付かれることはありません。
そして、わずか1日で孵化するといわれています。
キハダやメバチは赤道付近に産卵場所があるマグロの稚魚は黒潮にのって回遊し、夏から秋にかけて相模湾などにやってきます。
この時期、この相模湾でも、80〜90センチ前後のマグロがつれることがあります。
この相模湾などで釣れるメジと呼ばれるマグロはホンマグロの幼魚。
静岡では、このマグロの成長に合わせてその呼び名が変わります。
メジカッコ → メジカ → メジ → クロシビ → シビ
と呼び名が変化していくのです。
マグロも『出世魚』なんです。
江戸時代には下級の食べ物だった
マグロは今でこそ高級魚。
おすし屋さんで、トロでも注文しようものなら、その美味しさが舌先に残る余韻も吹き飛ぶくらいの「お会計」となりますね。
しかし、江戸時代にはこれがまったく下級の食べ物であったとされています。
『本朝食鑑』には
「凡そ士以外の人は食べないものである」とあり
『魚鑑』には
「肉赤く血点あり、味いよからず」とあり、
さらに『古今料理集』には
「まぐろ、下魚也。 賞翫に用いず」とそっけない表現がされています。
特に「トロ」は脂肪が強いため敬遠され、すし屋でも赤身のほうが値段が高かったといわれています。
当時、武家は赤身を好み、脂身であるトロは庶民や肉体労働者が食べればよいとばかりに捨てられていたといいます。
江戸庶民の味 『ネギマ鍋』
それならばと江戸時代に庶民が考えたのが『ネギマ鍋』です。
”ネギ”は葱をさします。
”マ”はマグロという説と、マグロの脂を移した葱を主役で食べる”間つなぎ”でマグロを食べたことから”ネギマ”となったという説があります。
食べ方は、すき焼きと同じように2種類があり、平鍋で割り下を具が浸るほどに入れて食べる方法と、深鍋にたっぷりの割り下を入れて煮込む方法があったといいます。
いずれにせよ、脂の乗った『トロ』の旨味と栄養が江戸庶民の活力源であったことは間違いないですね。
マグロが高級魚になったのは昭和30年代から
マグロは明治のころまではそれほど高級な魚ではなかったようです。
それが、近年のように高級化していったのは、日本人の食生活が脂っこくなった昭和30年代以降といわれています。
この頃、ついにトロが赤身を追い抜き、ホンマグロの大トロともなれば、とても庶民の口には入らない高値の花となっていくのでした。
トロが多いのはホンマグロですが、それでも200キロ以上の大物からでも、わずか15キロ位しか採れません。
市場の卸価格で、ホンマグロのトロはキロ当たり何万円もします。
胸ビレからアゴにかけてのカマの部分である大トロ(別名カマサキ)となれば当然それ以上の値段になります。
通常我々が食べているのはホンマグロではなく、メバチマグロがほとんどです。
しかしこのメバチマグロ、魚体が小さく、トロにあたる腹肉部は薄いため、トロはほとんどありません。 やはりその希少性から高値になるというわけですね。
まとめ
最近では、回転寿司などでマグロが安く食べられるようになりました。 トロも比較的安く食べられるようにはなりましたが、たまには”本物”のトロを食べてみたいですね。 そのためにはまず、『お金持ちのスポンサー』を探すところから始めましょうか?
クジラは水族館で見られる?
クジラを水族館で見てみたいというのは誰もが思うことだと思います。さて私たちが思う典型的な「クジラ」が水族館で飼育されているところはあるのでしょうか?
そもそもクジラとは?
慣例的な呼称としてクジラというのは4mを超えるイルカやクジラの仲間のことを指しています。
となると「日本でクジラを飼育している水族館はありますか?」という質問には一応ありますと答えることができます。
例えば鴨川シーワールドでは4mをゆうに超えるシャチが飼育されていますよね。
ただ多くの人がクジラといわれて想像するマッコウクジラやシロナガスクジラのような巨大なクジラとなると日本、いや世界でもお目に書かれません・・・。
クジラが飼育された例
一度アメリカで保護されたクジラの赤ちゃんが飼育されていたことはありますが、成体が飼育されたという実例はないと思います。
今はいませんが水族館の三津シーパラダイスではミンククジラというクジラの一種が飼育されていました。
ミンククジラはシャチと同じくらいの大きさを誇ります。
あとはオキゴンドウやシロイルカくらいですかね。
オキゴンドウはアクアワールド・大洗やくじらの博物館、沖縄美ら海水族館などで飼育されています。
そもそもクジラとは?
慣例的な呼称としてクジラというのは4mを超えるイルカやクジラの仲間のことを指しています。
となると「日本でクジラを飼育している水族館はありますか?」という質問には一応ありますと答えることができます。
例えば鴨川シーワールドでは4mをゆうに超えるシャチが飼育されていますよね。
ただ多くの人がクジラといわれて想像するマッコウクジラやシロナガスクジラのような巨大なクジラとなると日本、いや世界でもお目に書かれません・・・。
クジラが飼育された例
一度アメリカで保護されたクジラの赤ちゃんが飼育されていたことはありますが、成体が飼育されたという実例はないと思います。
今はいませんが水族館の三津シーパラダイスではミンククジラというクジラの一種が飼育されていました。
ミンククジラはシャチと同じくらいの大きさを誇ります。
あとはオキゴンドウやシロイルカくらいですかね。
オキゴンドウはアクアワールド・大洗やくじらの博物館、沖縄美ら海水族館などで飼育されています。
マツコ&有吉の怒り新党「新三大○○調査会」で紹介された「新三大市場に出回らない”旨すぎる地魚”で紹介された、「アカタツ」「マツカサウオ」「エソ」を解説
マツコ&有吉の怒り新党といえば、マツコデラックスさんと有吉弘行さん、夏目三久さんの三人によるトークバラエティーですね。 番組の後半に「新三大○○調査会」というコーナーがあります。 私も毎週楽しく拝見しています。 先日のテーマは「新三大市場には出回らない”旨すぎる地魚”。 各地の変わった魚が三種類紹介されました。
徳島県 「アカタチ」
番組内では別名「巫女の帯」と紹介されました。
正式名称は「アカタチ」でスズキ目アカタチ科の魚です。
体長20〜50cmで日本では赤い魚鯛のものがほとんど。
海底に棲み、穴を掘って身を隠し、頭だけを出して餌を狙います。
しゃくれたアゴと細長く赤い綺麗な魚体が特徴の白身魚。
番組では塩焼きにして食べていましたが、三枚に卸し、天ぷらにしても美味です。
番組のスタッフが食べて「キンメダイのような味」と言っていましたね。
加工魚として蒲鉾などの練り製品になることが多いため、一般の市場には出回らない魚です。
瀬戸内地域では「オビウオ」と呼ばれています。
静岡県 「マツカサウオ」
番組内では、定置網で獲る様子を流していました。
なかなか獲れず、取材3日目にやっと捕獲に成功した希少魚です。
番組内では姿蒸しにし、ウロコをはぎとって食べてましたね。
「肝がバターのようだ」 と有識者の水産ジャーナリスト西潟正人さん。
この魚キンメダイ目マツカサウオ科の魚。
成魚でも体長15cm程度の小型の魚です。
下顎に「発光器」があり、光る魚なんです。
この発光器を光らせて餌をおびき寄せて捕食する、チョウチンアンコウのような習性があるようです。
番組でも解説されたように体色は薄い黄色で前進を硬いウロコで覆われ、鎧を纏ったような姿なため、英名は「ナイトフィッシュ」「アーマーフィッシュ」「パイナップルフィッシュ」と呼ばれています。
あまり食用とすることはないため、生体を水族館で見るくらいでしょうか。
市場で見ることもほとんどない珍しい魚であることは間違いありませんね。
和歌山県 エソ
この魚は上記の2種類に比べ、魚市場では比較的定期で見かけます。
しかし、そのほとんどは、加工されます。
代表的な加工品は「蒲鉾」ですね。
とくに、国内の産地の明確なものは高級かまぼことして珍重されています。
スーパーなどで販売されているかまぼこにも原料表示に「エソ」と書いてあるのをみかけます。
この魚はヒメ目エソ科の魚で、その特徴は
細長い魚体と大きな口と硬いウロコでしょうか。
全国的砂地の海底に生息しており、砂浜からの投げ釣りなどで外道として釣れることがあります。
小骨が多い魚で全身に小骨があり、番組内でも、1尾を卸しても5〜6切れの刺身しか取れなかったように、三枚に卸しても、骨がない場所はごく一部です。
また番組内で、卸した身をミキサーですり身にしていたように家庭で食べる場合も、
三枚に卸し、皮をとってすり身にしたものを、丸めて天ぷらや、蒸し物にするのがおすすめです。
まとめ
三種類の魚は確かにスーパーなどではほとんど見かけない魚ですね。
釣りに出かけた際に運よくこれらの魚が釣れた場合にぜひご賞味ください。
今回の番組では、三種類の魚も面白く紹介されていましたが、私が最も興味をもったのは、番組内で「軽量カップ」でウーロンハイ飲んでいた有識者の水産ジャーナリスト西潟正人さんでした。
徳島県 「アカタチ」
番組内では別名「巫女の帯」と紹介されました。
正式名称は「アカタチ」でスズキ目アカタチ科の魚です。
体長20〜50cmで日本では赤い魚鯛のものがほとんど。
海底に棲み、穴を掘って身を隠し、頭だけを出して餌を狙います。
しゃくれたアゴと細長く赤い綺麗な魚体が特徴の白身魚。
番組では塩焼きにして食べていましたが、三枚に卸し、天ぷらにしても美味です。
番組のスタッフが食べて「キンメダイのような味」と言っていましたね。
加工魚として蒲鉾などの練り製品になることが多いため、一般の市場には出回らない魚です。
瀬戸内地域では「オビウオ」と呼ばれています。
静岡県 「マツカサウオ」
番組内では、定置網で獲る様子を流していました。
なかなか獲れず、取材3日目にやっと捕獲に成功した希少魚です。
番組内では姿蒸しにし、ウロコをはぎとって食べてましたね。
「肝がバターのようだ」 と有識者の水産ジャーナリスト西潟正人さん。
この魚キンメダイ目マツカサウオ科の魚。
成魚でも体長15cm程度の小型の魚です。
下顎に「発光器」があり、光る魚なんです。
この発光器を光らせて餌をおびき寄せて捕食する、チョウチンアンコウのような習性があるようです。
番組でも解説されたように体色は薄い黄色で前進を硬いウロコで覆われ、鎧を纏ったような姿なため、英名は「ナイトフィッシュ」「アーマーフィッシュ」「パイナップルフィッシュ」と呼ばれています。
あまり食用とすることはないため、生体を水族館で見るくらいでしょうか。
市場で見ることもほとんどない珍しい魚であることは間違いありませんね。
和歌山県 エソ
この魚は上記の2種類に比べ、魚市場では比較的定期で見かけます。
しかし、そのほとんどは、加工されます。
代表的な加工品は「蒲鉾」ですね。
とくに、国内の産地の明確なものは高級かまぼことして珍重されています。
スーパーなどで販売されているかまぼこにも原料表示に「エソ」と書いてあるのをみかけます。
この魚はヒメ目エソ科の魚で、その特徴は
細長い魚体と大きな口と硬いウロコでしょうか。
全国的砂地の海底に生息しており、砂浜からの投げ釣りなどで外道として釣れることがあります。
小骨が多い魚で全身に小骨があり、番組内でも、1尾を卸しても5〜6切れの刺身しか取れなかったように、三枚に卸しても、骨がない場所はごく一部です。
また番組内で、卸した身をミキサーですり身にしていたように家庭で食べる場合も、
三枚に卸し、皮をとってすり身にしたものを、丸めて天ぷらや、蒸し物にするのがおすすめです。
まとめ
三種類の魚は確かにスーパーなどではほとんど見かけない魚ですね。
釣りに出かけた際に運よくこれらの魚が釣れた場合にぜひご賞味ください。
今回の番組では、三種類の魚も面白く紹介されていましたが、私が最も興味をもったのは、番組内で「軽量カップ」でウーロンハイ飲んでいた有識者の水産ジャーナリスト西潟正人さんでした。