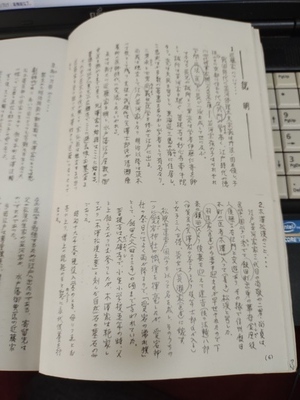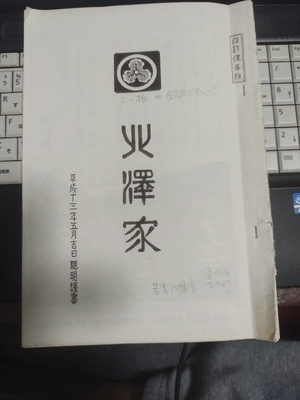2020年10月05日
SONY ソニー社名変更⇒「ソニーグループ」2021年4月

写真・日経電子版2020/10/5
昭和の生まれで、日本の家電メーカーが世界中を席巻した時代に、私はそのただ中で働いていた。
その時代に、カラーテレビが生まれた。ソニーだけは他社と違ってトリニトロンというブラウン管を使っていた。その映像は、色が最も良く出ていたし、画面の4隅が曲がらずに、真っ直ぐ映っているのもソニーだけだった。私がTVを買うには。ソニーと決めていた。それは液晶画面になり、40インチを買うまで続いた。
65インチを買う時に、ソニーは選ばなかった。理由がある。今の日本の家電メーカーがシロモノ家電(生活に直結している電化製品)を造ると、人件費の安い海外の工場を使っても、どうしても高くなってしまって、世界市場を席巻できない。
それだけでなく、日本製の安心感だけに期待した経営では赤字になってしまう。
無理もない、日本は人件費が高くアメリカやヨーロッパのような成熟した社会になってしまった。ソニーでは今も液晶テレビを造っている。映し出す技術はソニー製でも、画面は他社からの供給に頼っている。調べると、小型は台湾メーカー、大型画面はシャープ製になっていた。まあそれでも仕方ない、価格はと調べると、どうしても気軽に手を出せる価格帯ではないのだった。そして、店頭で家電を扱っている方たちの「私がTVを選ぶなら・・・」というような記事を、ネットで見ることができる今では、何がメリットで、どの点がデメリットなのか、全体としてどうなっているのか分かる。それで映像はソニーという考え方をしなくなった。でも、ソニーには頑張ってもらいたい。
私は、バリアブルコンデンサーのメーカーで働いたことがある。バブル以前のこと。その時代革新的な技術で先陣を切っていたソニーの技術陣に憧れていたし、尊敬していた。それは、資金調達でも斬新だった。
頑張れSONYそれは今でも変わらない。
ソニー社名変更の舞台裏 「第2の創業」に再挑戦
RE:SONY(1) 新型コロナ 日経産業新聞 コラム(ビジネス) ネット・IT エレクトロニクス 2020/10/5 2:00日本経済新聞 電子版
ソニーが「第2の創業」に再挑戦する。2021年4月、「ソニーグループ」に社名を変える。かつて出井伸之元社長は「リ・ジェネレーション」を掲げ、IT(情報技術)革命の時代で飛躍を目指したが、ソニーは変化に対応しきれずに長い低迷のトンネルに入った。経営の混乱を脱した今、混沌とする世界で勝ち残るため、「RE:SONY」に走り出した。進化の先に何を見据えるのか。現場を追う。
■新本社の役割、「管理」ではなく「支援」
5月19日午前、新型コロナウイルスの影響でリモートで開いた取締役会。「多岐にわたる事業をまとめる本社を再定義する」。吉田憲一郎会長兼社長が最終的に自ら決めた社名変更は、社外取締役にすぐに賛同された。共同創業者の盛田昭夫氏が約60年前に周囲の反対を押し切って「東京通信工業」から「ソニー」に社名を変えたのとは対照的だった。
企業の根幹を変える重要な決定がすんなり通ったのは、準備が入念だったためだ。
「ソニー本社が担うべき役割は何か」。吉田氏はこの数カ月前まで側近と議論を重ねてきた。懐刀の十時裕樹副社長や、研究開発(R&D)を担う勝本徹副社長、法務の神戸司郎専務、人事の安部和志専務ら今の本社執行役のメンバーだ。
名は体を表す。吉田氏がこだわったのは、本社の新しい役割を理解される社名だった。
吉田氏が13年にソネット(現ソニーネットワークコミュニケーションズ)社長から平井一夫前社長に請われ、ソニーに復帰して以来、繰り返してきた言葉がある。「事業を強くする」というメッセージだ。安部氏は「新会社はポートフォリオ経営のような事業を管理する役割ではないため、ホールディングスという名称を使わない点ははっきりしていた」と振り返る。
新社名のソニーグループは月並みな名称だが、「事業を強く伸ばしていく。それを支援する本社」(安部氏)という深い思いを込めた。事業を伸ばすグループ会社と支える本社。両者がグループ全体の価値を上げるというベクトルを合わせるため、質実剛健な堅実経営をスタイルとする吉田氏は細部まで目を光らす。
「SONYの成長は引き続き事業がけん引していくべきだ。それにふさわしい事業責任者の職位を考えて欲しい」。吉田氏は経営体制の刷新にあたり、安部氏にこう命じた。グループ会社に遠心力が働きすぎない仕掛け作りが狙い。安部氏が出した答えが、6月に導入した「上席事業役員」という新たな建て付けだ。
ソニーは平井改革で全事業の分社化を実行し、各事業に責任感と規律を与えた。その後、事業トップにも「専務」「常務」といった肩書を付け、本社の役員と同じ職位を持たせた。遠心力と求心力の両立をめざした試みだった。
安部氏は「それをさらに進化させるのが上席事業役員だ」と語る。「各事業の独立した経営者であると同時に、ソニーグループ全体の価値を高める役割を託されている」(安部氏)。上席事業役員でソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のジム・ライアン社長は「吉田氏からは独立した事業とグループ全体の価値をともに最大化するように言われている」と話す。
■社名変更で祖業のエレキを再定義
社名変更のもうひとつの狙いは、祖業のエレクトロニクス事業の再定義だ。「真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設」と設立趣意書でうたわれたように、「SONY」のブランドや競争力の源泉はエレキで磨かれた技術だった。
吉田氏は創業の理念を踏まえつつ、未来を見据え、新たなソニーのあり方を「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパニー」に解釈し直した。新たな定義に合わせ、「変えてはいけないものと、変えるべきものを議論した結果、エレキの技術をグループ全体に展開させると捉え直した」(安部氏)
ソニーの商号は21年4月、エレキ事業を束ねる中間持ち株会社のソニーエレクトロニクスが継承する。「ハードウエアがSONYのブランドを作ってきた主役だ」(吉田氏)という敬意と、今後もブランドを裏打ちするテクノロジーを生み出す役割は変わらないという期待も込めた。
「『ソニー株式会社』の歴史の重みと商号を引き継ぐ大きな責任を感じている」。大看板を託されたソニーエレクトロニクスの石塚茂樹社長は設立趣意書を読み込み、同期の高木一郎副社長と祖業の新たな理念を練った。
「世界中の人と社会に、テクノロジーの追求と新たなチャレンジによって、『感動』と『安心』を提供し続ける」。新たな理念は、創業者の開拓精神を継ぎつつ、ソニーグループをテクノロジーで引っ張る責務を明確に打ち出した。
成長のけん引役がエンタメとなるなか、米ディズニーや米ネットフリックスなど世界の競合に勝るソニーの強みは、テクノロジーの基盤にある。ソニーグループは、これまでよりもテクノロジーのグループ全体での活用を強く志向していく。
「事業全体をまとめる会社を作ったとき、研究開発はどうあるべきだろうか」。勝本氏は吉田氏から機構改革にあたり、何度か相談を受けていた。「3〜5年先のソニーグループを想像し、そのときに必要となる技術を準備する役割ではないでしょうか」。勝本氏は吉田氏にこう進言した。背景には過去の研究開発への反省があった。
映画や音楽、金融などでもデジタル化が進み、エレキの技術を生かせる可能性が広がっていたが、過去はエレキのための技術という側面が強かった。
勝本氏はR&Dの役割を「事業会社が将来を描いて飛躍するのをサポートする立ち位置だ」と説明する。ここでもポイントは支援する、という役割だ。長期的に必要な技術を議論し、多岐にわたる事業の現場に行き渡らせて価値を生む。
ソニーのR&Dは日本に軸足を置いていたが、勝本氏は映画の本拠である米国にR&Dセンターを設けるなど、事業の現場の近くで体制を拡充してきた。日本でも音楽事業のオフィスを技術者が出入りする。こうした取り組みを一層加速する。
■「ホールディング・カンパニー」の設立を目指した出井改革
ソニーがグループ経営をめざしたのは初めてではない。「最も心残りなのは、本社としての『ホールディング・カンパニー』を作り出すことができなかったことだ」。出井氏は自らの経営をこう振り返った。新社名まで決めていたが、機構改革を実現できなかった。出井氏は理由として「社員の『ソニー株式会社』に対する強烈な偶像意識があった」ことを挙げた。
「『ソニー株式会社』に対するアタッチメント(愛着)が強すぎる」。吉田氏も13年、ソニーに復帰したときに似た感情を抱いた。未完に終わったグループ再編を社長室長として間近で見ていた吉田氏。過去の教訓を踏まえ、再編のアプローチを変えた。出井氏は本社の役割として「アクティブ・インベスター」を掲げたが、吉田氏が打ち出したのは「サポーター」だった。投資家ではなく、支援者に徹する意図を明確にし、未完のグループ再編をやり遂げる。
安部氏は「シナジーやポートフォリオ見直しの結果として価値を生むのではなく、少数意見であっても気にせず異質なモノが交わり、イノベーションを起こしていくのを支援する。それがソニーグループの使命」と語る。ソニーは創業以来、「個性」や「多様性」を重視してきた。
例えば、経営の多様性では、ソニーグループで世界最大の音楽出版会社、ソニー/ATVミュージックパブリッシング会長兼最高経営責任者(CEO)でソニーの上席事業役員も兼務するジョン・プラット氏は、米大手音楽事業会社では唯一の黒人トップだ。ソニー・ミュージックグループが中心となり、6月に100億円規模の「グローバルソーシャルジャスティスファンド」を立ち上げ、反人種差別や社会正義に向けた活動を支援している。「本社は多様性が生み出す価値の創出を後押しする」(安部氏)という。
■強すぎる独立意識、グループ戦略の司令塔として課題
ただ、ソニーはグループ会社の独立意識が高く、開発した技術を全面展開したり、連携したりするスピードやスケールの追求が十分ではなかった。
例えば、コロナ禍で注目されるVR(仮想現実)。SIEが16年に「プレイステーション(PS)VR」として展開を始めたが、映画や音楽などとの連携は限定的にとどまる。
米フェイスブックはVRを「次世代メディアのプラットフォーム」と位置づけ、VR端末の開発やAR(拡張現実)技術に血道を上げる。ソニーのVRはゲームの箱庭としての扱いから脱し切れず、スピードが鈍い。環境変化に素早く対応するため、支援にとどまらず、時にはグループを束ねる司令塔としての機能をどう備えるかは課題だ。
新たな経営の枠組みを持続可能にしていく備えも欠かせない。今の経営執行部は平井改革で苦楽をともにしたメンバーが中心。次の世代にどう移行していくかを真剣に考える局面に差し掛かる。
「次はどういう場を与えるべきか」。ソニーは次世代を託すべき有望な人材を社内で選抜し、どういった経験を積ませるべきか議論を始めた。幹部候補は次世代とその次を担う人材の2つの層を選ぶ。現在の能力だけなく、将来の伸びしろも考慮する。本人にも明確には伝えておらず、候補の入れ替わりもあるという。
創業者の井深大氏は「企業石垣論」を唱えた。「丸や三角、四角など様々な形状の石が組み合わさり、初めてきれいな石垣となる。企業も同じだ。人間を適材適所に置き、互いに補い合ってこそ、初めて強力な企業という石垣となる」とし、「同時に一つの石が欠ければ石垣全体が崩れることを忘れてはならない」と語った。
「より良いソニーを残す」ことを自らの使命とした吉田氏。新たなソニーが飛躍できるか否か。土台となる新しい石垣作りにかかっている。
■「エレキの技術、金融やエンタメでも展開」
ソニーで研究開発(R&D)の司令塔を務める勝本徹副社長と、人事・総務の責任者である安部和志専務に機構改革の狙いなどを聞いた。
――ソニーのR&Dを取り巻く環境はどう変化していますか。
「ソニーはエレクトロニクス事業で技術を磨いて蓄積してきた。その技術が最も強みを発揮するのはデジタル化したエレキの製品だった。R&Dセンターのふるさとは祖業のエレキだという考え方は残っている。だが、ゲームや金融などグループの様々なコンテンツや商品がデジタル化してきた。こうした背景があり、エレキで培った技術が他の事業でも光るようになってきた」
――これまでグループの縦割りが課題でした。
「当社は色々な場所でシナジーと言っていたが、異なる事業同士で親密な付き合いはしていなかった。だが前社長の平井一夫氏が『同じ釜の飯を食って話せ』と言ってから、数年で急速に人間関係がしっかりしてきた。それが吉田体制で加速した。エンジニアがエレキ以外のビジネスの最前線に行くようになり、現場で困っていることが直接分かるようになった」
――新型コロナウイルスでR&Dの方向性は変わりましたか。
「当社は研究テーマとして『リアリティー』と『リアルタイム』に力を入れてきたが、コロナで『リモート』を含めた『3R』が重要になっている。3〜5年で色々な仕込みをしようと思っていたことが、数カ月で起こっている。当社は映画や音楽などリモート技術を磨ける現場を持っている」
「一方で中長期についても予算の一定額を振り分ける。R&Dセンターの予算の5%以内を中長期のテーマに充てている。R&Dセンターだけでテーマを設定すると、足元で脚光を浴びる研究テーマに資金を使いたくなる。『イノベーションのジレンマ』を防ぐため、外部の人を交えたアドバイザリーボードで中身を確認する」
――祖業のエレキで培った技術をどう進化させますか。
「少なくとも画像センサーを中心とするセンシングの領域は当社にとって非常に重要だ。今までは2次元で映像を撮って2次元でテレビにきれいな映像を流していた。これからは3次元で空間を把握し、何らかのデバイスで3次元で表示する時代が来るだろう。今は過渡期だが、そういった観点でもハードウエアは重要だと思う」
――世界では米グーグルなど巨大IT(情報技術)企業が量子コンピューターでしのぎを削ります。
「量子コンピューターのハードウエアやアルゴリズムを開発するよりも、使い方で世界一をめざす。ソニーにとっては技術の目利きができてビジネスに応用できる方が重要だ。人工知能(AI)でも新しいアルゴリズムで世界一は狙っていない。世界一のエンジニアや研究者を抱えるが、それは先端技術をうまく使いこなすためだ」。
――R&Dの今後の課題は何でしょうか。
「日本の会社ではない、という意識をもっと強く持った方が良いと思う。当社のエンターテインメント事業は主要拠点が米国にあるほか、これからビジネスが伸びるのはインドや中国だ。今も実際に意識は東京主体から変わりつつある。グローバル化や多様性を強みにしていきたい」
■「個の集まりが生む多様性で競争力を強化」
――ソニーグループに社名変更するのはどうしてでしょうか。
「エレクトロニクスはソニーの競争力の源泉で、テクノロジーが育てられた土壌だ。そのエレキを見直しながら、変えてはならないものと、変えるべきものをしっかり議論した。『ソニー株式会社』に対する愛着などの意識は変えないといけない。育ててもらったエレキから一歩卒業し、グループ全体に技術を展開していく」
「ソニーグループに期待するのはこれまでの持ち株会社のようなポートフォリオ経営で事業を管理する役割ではない。『ホールディングス』を社名に使わないでおこう、というのははっきりしていた。個々の事業を強く伸ばす。それを支援する本社であるべきだという思いがあった」
――平井一夫前社長のときは分社化を進めていました。
「当時は分社化という経営施策で自立を促すという軸があった。一定の成果があったが、その後は事業責任者がソニー本社の役員として同等の職位を持った。さらにそれを進化させるのが新たな職位である『上席事業役員』だ。各事業の独立した経営者であると同時に、ソニーグループ全体の価値を高める役割を託されている」
――新型コロナウイルスで働き方はどう変わるのでしょうか。
「コロナは想定外に大きな環境変化だ。ある意味で個を重視する人事戦略を最も顕在化できる環境だと思っている。一人ひとりに何を期待して、どういうアウトプットを出して欲しいかが明確になる。本質を追求する良いチャンスで、新しい働き方や会社との向き合い方が出てくる」
――若手社員を成果に応じて高給で処遇する制度を導入しています。
「若手の人たちには基本的な仕事からやらせる、という前提を取り除くために抜てきする制度を作った。ソニーの人事戦略の特徴は個人の力を最大限に発揮してもらうことに尽きると思っている。それは創業以来変わっていない。新体制で『個』の集まりが生む多様性の競争力を明確にしたい」
――新体制でグループ経営を担える人材をどう育てるべきでしょうか。
「ソニーグループが各社を支援する役割を果たそうとすると、事業のことを理解したメンバーで構成しないといけない。本社と事業会社の人材交流は今まで以上に促進していく必要があり、その中から次を担える人材を育てていくべきだと思っている。背景には我々がそういう場のおかげで色々な経験をさせてもらったという認識がある」
――外部から経営人材を招く可能性もあるのでしょうか。
「内部の人材と経験の価値は大きいと思っている。それを大事にしていきたい。ただ外部の専門性を二次的にみているわけではない。専門性が必要なときには常にオープンでいたい」
(企業報道部 清水孝輔)
【このカテゴリーの最新記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10248076
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック