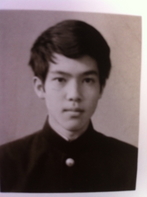2016年05月28日
第225回 新婚気分
文●ツルシカズヒコ
『神近市子自伝 わが愛わが闘争』には「私が葉山の宿に着いたのは、夜になっていた。大正五年十一月八日のことである」と記されているが、「十一月八日」は十一月七日の誤記である。
日蔭茶屋に着いた神近が、出て来た女中さんに「大杉さんご夫妻はみえていますか?」と訊ねると、出で来た女中さんは無邪気にみえていると答え、そのまま奥二階の部屋に案内した。
廊下の唐紙は開いていた。
「お客さまでございます」
と女中さんは声をかけ、すぐにそこから消えるように廊下を帰っていった。
大杉が神近を見たときの当惑顔で、女中さんはハッとしたようだった。

大杉氏は湯上がりの浴衣姿で、タバコをふかしながらチャブ台の前に坐っていた。
野枝女史も風呂からあがったばかりのようすで、肌脱ぎになって鏡台の前で化粧をしていた。
チラと私のほうを見るなり、露骨にいやな顔をして肩を入れたきり、無言で化粧をつづけた。
気まずい空気だった。
私と大杉氏とは、互いに意味をなさない弁解をしあった。
(『神近市子自伝 わが愛わが闘争』_p158)
三人分の夕食が揃ったが、大杉が箸を取って何か口に入れただけで、野枝は箸を取らなかった。
神近は無理にひと口食べたが、とても咽喉を通らなかった。
野枝がいきなりちゃぶ台を離れ、「あたし帰る」と言って、支度を始めた。
大杉は止めなかった。
神近は勝手にしろと思い、口を挟まなかった。
自動車が来ると、野枝は何も言わずに部屋を出て行った。
大杉と神近、ふたりの食事は味気ないものだった。
つとめてさりげなくあれこれ友達の噂や知人の話をしていても、フッと話が途絶えると、ふたりはお互いの心を探り合っていることを感じた。
神近は一杯のご飯を詰め込むように食べ、大杉はややよく食べた。
形ばかりの食事が終わったころ、女中さんが電話だと言ってきた。
野枝からの電話だった。
大杉が部屋から出ていって、かなりの時間がたち、ようやく部屋に戻った大杉が言った。
「伊藤が東京の部屋の鍵を忘れたというんだ。逗子の駅まで届けてくれと言っている」
神近は口には出さなかったが、それが仕組まれたことだと感じた。
「困ったお嬢さんだよ。ちょっと届けてくるからね。君は先に休んでいらっしゃい」
大杉はドテラのまま自動車を呼んで出て行った。
二人は……一種の新婚気分にひたっていたのだろう。
私は、その気分をわざわざこわしに来た闖入者であることは明らかだった。
野枝女史が突然帰ったのは、私に対する無言の抗議にほかならないことも、これまた明らかだった。
鍵を忘れたというのも、出ていくときすでに彼女の計算にあったことだろう。
野枝女史は、それほど賢いところを持っている人だった。
福四万館にはむろん合鍵というものがあるだろうし、駅に着いたときに思い出したというのも偶然すぎる。
(『神近市子自伝 わが愛わが闘争』_p159~160)
「福四万館」と書いてあるがこれは「菊富士ホテル」の誤記である。
さらに『神近市子自伝 わが愛わが闘争』では、野枝がこの夜(十一月七日)そのまま帰京したふうに記しているが、実際は日蔭茶屋に戻り、翌日(十一月八日)の朝に帰京しているので、これも誤記である。
さらに『神近市子自伝 わが愛わが闘争』では、神近が大杉を刺したのは神近が日蔭茶屋にやって来た日の夜と記述されている。
つまり『神近市子自伝 わが愛わが闘争』は、十一月七日と八日の出来事が混同して記されているのである。
重大な事実誤認をしている同書だが、ともかくその記述に沿って、刃傷沙汰にいたり神近が自首するまでを追ってみたい。
神近はなんとか話し合いで解決したかったが、大杉の反応に唖然とした。
「君の話はわかっているよ。金だろう。金は返すよ、金さえ返せばいいんだろう」
大杉がもう少し人間的な扱いをしてくれると期待していた神近は、全面的に裏切られたと思った。
寝床に入っても、神近は眠れなかった。
このとき、私が大杉氏の寝床にはいろうとしたと伝えられている。
おそらく、それは大杉氏が自分で書いたものから出たのだろうと思うが、それは半睡の状態にあった大杉氏の錯覚だろう。
が、私が大杉氏の手を引っぱって起こしたことは事実だった。
(『神近市子自伝 わが愛わが闘争』_p160~161)
神近が言った。
「私たち、いろいろ話し合ってみたほうがいいと思います」
大杉は無言だった。
「あなたは、私に言うことがあるはずです。たとえば、この状態は自分の予想していなかったことだとか……」
クルッと向こうむきに枕をかえて、大杉が言った。
「我慢がならないなら、好きにするさ。何も言うことはないよ」
神近は洗いざらい憤懣をぶちまけた。
大杉の理論が雲散霧消してしまったこと、その原因の一端は野枝の無責任な態度にあること、大杉の行為は好色な男の行為と一分の違いもないこと。
さらに、神近は野枝の大杉への経済的な依存のために、保子夫人の窮乏が深まっているのに、おめおめと旅行をして歩く良心のなさを詰問した。
大杉は憤った。
そして、高畠素之が口癖のように言いふらしていた「大杉のヘボ理論で日本の革命ができるなら、俺は坊主になってみせる!」という言葉を、神近が引き合いに出したとき、大杉の怒りは頂点に達した。
大杉氏は起きあがった。
「ぼくが金を借りているものだから、君はそれをカサにきて暴言を吐くんだな。さあ、金は返す。これでわれわれは他人だ。あしたは帰ってくれ。帰らないなら、ぼくが帰る!」
そういうなり畳みの上にあり金を叩きつけた。
(『神近市子自伝 わが愛わが闘争』_p162)
「お化を見た話」『引かれものの唄』「豚に投げた真珠」にも、大杉がその場に金を叩きつけたという記述はない。
さらに大杉を刺した後の神近の行動について、こう記されている。
私は短刀を海の中にほうり投げた。
そして海にはいって死のうとした。
が、なまじ水泳ができるものだから、いくら深みにはいって水を飲んでも、ひとつもがくと浮かび上がってしまう。
私は砂浜に上がって、ズブ濡れの着物を絞ると、そにまま逗子の町のほうに向かって歩き出した。
十二時を過ぎていたが、町にはまだ人通りがあった。
通りすがりの人に派出所の場所を聞き、赤いランプを灯した交番をさがしあてた。
扉をあけて巡査が顔を出した。
「殺人をしてきました。検挙してください」
巡査は愕然として身構えるふうだった。
「短刀は持っていないだろうな?」
私が両手を広げて見せると、巡査はやっと中に入れてくれた。
(『神近市子自伝 わが愛わが闘争』_p164)
大杉を刺した後の神近の行動が、『引かれものの唄』「豚に投げた真珠」とはずいぶん違っている。
『引かれものの唄』は日蔭茶屋事件の直後に執筆され、事件の一年後に出版されている。
「豚に投げた真珠」は事件の六年後に執筆されて『改造』に掲載された。
これらに比較して、事件の五十六年後に出版された『神近市子自伝 わが愛わが闘争』に記述されている事実関係の信憑性は低いと判断せざるを得ない。
※明治・大正・昭和歴史資料全集. 犯罪篇 下卷
★『神近市子自伝 わが愛わが闘い』(講談社・1972年3月24日)
●あきらめない生き方 詳伝・伊藤野枝 index
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image