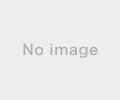2015年11月23日
読書感想文『真実』 おすすめの文章と自分なりの感情
今回のブログでは私「小谷中広之」が読んだ本の中で気に入った文章を紹介するとともに私「小谷中広之」がその文章に対して感じたこと(感情)を書き、少しでも皆様の何かのきっかけになれればこのうえない喜びです(定期的に読書感想文は更新していきます)
決して細かくは書くことはありませんのでご了承ください
私「小谷中広之」が感じた文章を書きたいと思っております
今回のご紹介する本は、ゼロプラス様の「まるわかり 宇宙の真実」です
気になる文章
●ソ連が1961年に宇宙飛行士ガガーリンを宇宙に送り込み、人類初となる宇宙飛行に成功すると、アメリカは1969年にアポロ宇宙船によって、アームストロングとオルドリンという二人の宇宙飛行士を月面へと運ぶことで対抗した
○小谷中広之の感情・・・宇宙への挑戦、この時代の両国の宇宙への情熱は相当なものだったのだろう
●国際宇宙ステーションは、1998年に打ち上げられたロシア製の「ザーリャ」(日の出)という基本機能モジュールに、各国がスペースシャトルやロケットを使って40数回に分けて打ち上げた様々なモジュールを結合する方法で建設
○小谷中広之の感情・・・初の結合に成功した瞬間、その仕事に携わった人達の歓喜を想像するとこちらまでテンションが上がってしまう
●ビッグバン宇宙論が生まれた大きな要因となったのは、アメリカの天文学者エドウィンハッブルによる研究出る。ハッブルは1929年、天体観測によって地球に対して多くの天体が遠ざかっていることを発見し、宇宙が拡張していることを証明した。宇宙が拡張して拡がっていくということは、過去は特定の一点に凝縮されていたという強力な証拠となった
宇宙誕生から現在に至るまで、ずっと拡張を続けているということだ。これは観測によって確認されており、この瞬間も宇宙は拡張を続けている
○小谷中広之の感情・・・いまこの瞬間も拡張はとまらずに進んでいる
この拡張はいつまで続いて、いつ終わり、どのような結末なのだろうか
●銀河は形状によって「渦巻き銀河」「楕円銀河」「不規則銀河」の3タイプ
○小谷中広之の感情・・・私たちが住んでいる地球がある天の川銀河は渦巻銀河のようだ
●1970年代、この現象について研究していたアメリカの天文学者ヴェラルービン博士は、宇宙空間には観測することができない何らかの物質が存在しており、これが星の速度に影響を与えていると考えた。宇宙空間に正体不明の物質が存在しているという考えは1930年代から存在していたが、彼女の提唱によってこの物体の存在は再び天文学上で脚光を浴び、謎の物質は「ダークマター」と呼ばれるようになった
○小谷中広之の感情・・・暗黒物質=ダークマター
観測できない物質、何なのだろうか?自分が生きている間に、この謎が解けてくれるのか
●恒星の数は約3000個以上
恒星は水素やヘリウムなどを主成分とした巨大なガスの集合体で、内部で核融合反応を繰り返すことによって光、熱、紫外線、X線などのエネルギーを生み出している。星の色は表面温度を表しており、3000℃程度の天体は赤く、6000度程度で黄色、1万度程度で白くなり、さらに高温の天体は青白い光を放つ
○小谷中広之の感情・・・水素やヘリウムなどのガスは、いつ、どのようにして生まれたのだろうか
●巨大な質量の星が寿命を迎えるときには、大規模な爆発を起こして粉々に吹き飛ぶ。この爆発を「超新星」という
太陽の30倍以上の質量を持つ恒星が超新星爆発を起こした場合、爆発と同時に中心核は急激に収縮し、「ブラックホール」が誕生すると考えられている
ブラックホールが持つ重力は非常に強大で、ある一定の距離以内では重力を振り切るために必要な速度が光速を超えてしまうため、光すら外に出ることができなくなってしまう。ブラックホールの中心から、光をも捕まえてしまうポイントまでの距離を「シュヴァルツシルト半径」と呼び、シュバルツシルト半径によって形成される球体の面を相対性理論の概念で「事象の地平面」と呼ぶ
○小谷中広之の感情・・・光が外に出られない状態とはどのような風景なのだろうか、もちろん肉眼で確認することは不可能に近いかもしれない
ブラックホールに吸い込まれたらどこまで行ってしまうのだろうか
●中性子星は巨大な構成の中心核が重力によって直径20キロメートルほどに圧縮されて誕生した天体である
初めて観測されたのは1967年で、この時見つかった中性子星は一定の間隔で光を発していたため、この天体は「パルサー」と呼ばれた
○小谷中広之の感情・・・昔の車の名前や、スロットの機種など宇宙用語はいたるところで使用されているのだ
「クエーサー」とは、地球から数十億光年以上離れた遠方にありながら、恒星のように明るい光を放つ天体
一般的なクエーサーが放つ光量は太陽の10兆倍にもなり、宇宙空間に存在する天体の中では最も明るい部類である
○小谷中広之の感情・・・太陽の10兆倍、全く想像ができない
●太陽も決して永遠ではない。太陽活動貸しから約45億年が経過し、核にある水素はほぼ半分を使い果たしている
今後は約50億年にわたり水素を使って燃え続け、やがて今の100倍に拡張して他の太陽系の惑星を飲み込む
○小谷中広之の感情・・・つまり100倍に拡張をしたら、私たちが住むこの地球をも飲み込んでしまうのだろう
金星を飲み込むとしたらどうなるのか。金星は灼熱の星、硫酸の雨が降るが治療に到達する前に蒸発してしまうほどの星である。その金星と太陽が合体したらとんでもないことが起きそうだ
●水星
もっとも太陽に近いところを回る惑星
日中の最高気温は430℃に上昇。しかし、その後は88日間の夜が訪れ、最低気温はマイナス170度にまで下がってしまう
1973年、アメリカの無人探査茎マリナー10号が、初めて水星に接近
○小谷中広之の感情・・・日中と夜間の寒暖の差が激しすぎる星だ
●金星
一日の長さは117日。惑星では唯一好転と自転の方向が逆で太陽は西から昇る
大気の96%が二酸化炭素
大気圧の上には約30キロメートルの厚みを持つ硫酸の雲がある。時に硫酸の雨が降るが、気温が高いために途中で蒸発し、地表に到達することはない
○小谷中広之の感情・・・太陽が西から昇り、東に沈む
昔バカボンというアニメの主題歌で「西から昇ったお日様が東〜にしず〜む」という歌詞があったが、あれはもしかしたら金星のことを歌っていたのかもしれない
●地球
地球誕生の頃、自転周期は約5時間で、6億年前には22時間まで遅くなった。これは、月や太陽の引力寄る「潮汐作用」で動く海水が自転より遅く、摩擦によって自転エネルギーを吸い取るためである。10億年後には、地球の自転周期は31時間になると予測されている
○小谷中広之の感情・・・一日が31時間になったとしたら、一日24時間の今の日本人の平均寿命でいったら大きく下回ることになりそうだ
●月
直径は地球の4分の1、惑星に対する衛星の比率としては太陽系で最も大きい。太陽が当たる昼間の地表温度は107℃、夜間はマイナス153度と差はあるが、大気は地球の10分の1でほぼ真空状態
現在、毎年3.8cmずつ地球から遠ざかっている
○小谷中広之の感情・・・月と地球の間もまた拡張しながら遠ざかっているのだ
●木星
木星は、地球の11倍の直径と318倍の質量を持つ、太陽系最大の惑星
成分の多くは太陽系と同じ水素とヘリウムのガス
木星周辺には強力な磁気圏があるため、地球以外でオーロラが発生する唯一の惑星
○小谷中広之の感情・・・地球上でのオーロラすら見たことがないが、この木星のオーロラも生きている間に見てみたい
●天王星
天王星の発見は1781年
イギリスの天文学者のウィリアムハーシェルによって新天体であると認識された
直径は地球の約4倍
太陽から遠いため平均気温はマイナス205度。質量の80%以上は凍ったガスで構成されている
○小谷中広之の感情・・・ガスも凍ってしまうのか
●1970年2月11日にL-4Sロケット5号機によって打ち上げられ、日本初の人工衛星となったのが「おおすみ」
元々数日の寿命で設計されていたおおすみだが、予想以上に電池の温度が上昇したため15時間ほどで信号は途絶え、わずか1日足らずで役目を終えた。ただその後も地球を回り続け、2003年8月2日にアフリカ上空で大気圏へ突入し燃え尽きている
○小谷中広之の感情・・・鹿児島県の大隅半島で打ち上げられた「おおすみ」
●「宇宙ゴミ」として認識されているスペースデブリ。これはその任務を終えたり、宇宙空間で破損してバラバラになった人工衛星やロケットの破片のこと
○小谷中広之の感情・・・いつかこの地球上でのごみ問題が深刻化するように、宇宙ゴミの問題も地球に住んでいる皆の問題になりそうだ
●1989年には、アポロ群の小惑星アスクレピウスが地球のわずか70万キロメートルの位置を通過したとして話題になった。もし、衝突していれば広島型原爆430万発に相当する爆発を引き起こしたと計算された
こうした地球に衝突する可能性のある天体は「地球近傍(キンボウ)天体(NEO)」と呼ばれる
もし事前に地球に衝突する小惑星の存在をキャッチできたとして、人類はこれを防ぐことはできるのだろうか
仮にうまく命中させて、破壊に成功したとしても、核ミサイルの威力が小さければ、破壊された小惑星の断片がお互いの重力によって集まり、すぐに元に戻ってしまう可能性が高い
2009年にカリフォルニアのローレンスリバモア国立研究所が行った試算によれば、直径1メートルの小惑星でも、確実に粉砕するためには広島型原爆の60倍にあたる、900キロトンの規模の核兵器が必要であり、小惑星サイズによっては、地球のすべての核兵器を集めても破壊できない可能性もある
また、破壊するのではなく、小惑星の近くで核ミサイルを爆破させたり、宇宙ロケットを衝突させたりして、軌道そのものを変えてしまうという方法もある
ただし、こちらに関しては、思い通りの軌道へ誘導することは困難とされている
○小谷中広之の感情・・・地球に巨大隕石衝突、その瞬間の自分の感情はどのようなものになるのだろうか、あまりにも想定外すぎて、想像の範囲を超えすぎて、ただただ呆然とたたずんでいるのだろうか
●もしスペースシャトル内で水をこぼしてしまった場合はどうなるのか
無重力化では水の表面に張力が働くため、水は丸く変形する
水は空中を浮遊するが、回収しようとしても、球体となった水はちょっとした衝撃で四散してしまうため、一筋縄ではいかない
また、水には人間の肌とくっつきやすいという特性があり、万一こぼれた水が顔を覆ってしまうと、なかなかはがすことができず、鼻から肺へと水が入っておぼれてしまう可能性もある
さらに問題なのが、シャトル内の精密機器に入った場合で、これが原因で機器が故障してしまい、最悪の場合だと取り返しのつかない事態にもなりかねない
こうしたことから、宇宙飛行士たちが水分をとる際は、もし横に倒しても絶対に中身がこぼれないよう、2重構造の容器にストローを使うなど、これでもかというほどの注意を払っている
○小谷中広之の感情・・・宇宙でも、地球上でも些細なことが大きな事故になる
ここまで読んでいただきありがとうございます。読んでいただいた方の人生での何かのお役に立てればとても嬉しいです
この本の他の文章が気になった方下記のサイトで購入可能です。
 まるわかり宇宙の真実 137億年の謎に迫る |
タグ:ゼロプラス 様
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4318805
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック