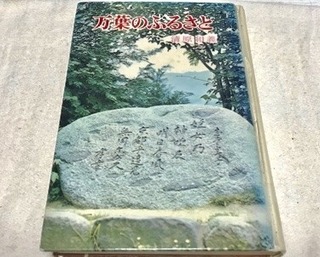2019年07月01日
『七夕の恋の調べ』
雨は、彦星が漕ぐ船の水しぶき。千三百年前の日本人の感性

七月七日の『七夕の日』
晴れたら『織姫』と『彦星』は逢える
雨が降ったら逢えない
そんな事を思い浮かべつつ空を見上げ、天の川の川向かいに光る二つの星を探す人、短冊に自分の思いを乗せて笹に結ぶ人、思い思いに楽しむ七夕
『七夕』は幻想的であり、人の『思い』が、いつも以上にやさしく現れる日
それぞれに思いを馳せながら楽しむ『七夕』ですが、雨の降る日、はたして織姫と彦星は逢えているのでしょうか?
有名な『かささぎ伝説』では、雨で水かさの増した川に、かささぎの群れがやって来て、翼を広げて橋を作り、織姫と彦星が逢えるようにしてくれたり
また、『催涙雨(さいるいう)』といって、七夕の日に降る雨は、織姫と彦星が、逢えた喜びに流す、『うれし涙』だ、というお話しもあります
どちらのお話しも、七夕の日に雨が降っても、『織姫と彦星は逢える』という、嬉しい内容です
そのような、有名なお話しがある中、それとはまた違う、全く別の解釈をしていた人達が、遥かむかしの日本にいました
『万葉人(まんようびと)』です
今より約千三百年前の日本で、万葉人は『七夕』に独自の感性を取り入れ、それを『歌(和歌)』に詠んでいます
雨の日も含め、空の色々の様子を、広い心で詠んだ万葉人の『七夕の歌』を、『万葉のふるさと(清原和義著)』の中で紹介されている歌の中から、三首あげたいと思います
まず初めに気になる『雨の日』の歌を
続けて、『雲』、『霧』、と詠んでいきます
早漕ぐ船の 櫂の散沫かも
"このゆうべ ふりくるあめは ひこぼしの
はやこぐふねの かいのちりかも"
一年に一度のこの夜に降ってくる雨は、彦星が織姫のもとへ早く漕いでいる船の
櫂(かい)の上げる水しぶきであろうか
織女の 天つ領布かも
"あきかぜの ふきただよわす しらくもは
たなばたつめの あまつひれかも"
この秋風に吹き漂っているあの白雲は、織女の領布だろうか
※領布(ひれ)は、肩から掛ける
ショールの様なもの
天の河原に 霧の立てるは
"ひこぼしの つまむかえぶね こぎづらし
あまのかわらに きりのたてるは"
織姫を迎えに行く彦星の船が漕ぎ出したらしい。天の川の河原に霧が立っている
空を見上げ、秋風に漂う白雲を見ては『あれは織姫の領布(ひれ)かも』と、想い描いてみたり
天の川に霧が立っていれば、それは彦星が織姫を迎える船を漕ぎ出した為に立っているのだな、と想い
そして『雨』は、彦星が織姫に逢いたくて逢いたくて、早く船を漕ぐものだから、その櫂(かい)が水しぶきを上げてそれが降って来ているのだと、そんな風に想いを馳せているのです
星は、遥か彼方にあるもの
雨が降っても、それが天の川に降るなどとは思いもせず、『七夕の日に降る雨は、きっと天の川から降ってきているのだ』。そう、万葉人は思い描いたのではないでしょうか
元々、中国から来た『七夕』
それを万葉人が、日本人ならではの解釈をし『歌(和歌)』に残してくれていた事で、今から千三百年前という遥か昔に、祖先が『七夕』へ馳せた想いというものを、感じる事ができます
そして、これからは、『七夕の日』に、もし雨が降ったとしても
あぁ、これは、彦星が織姫に早く逢いたくて、急いで船を漕いでいるんだなぁ
と、思う事ができそうです
更に、降る雨が激しければ激しいほど、彦星の織姫に対する想いが、より伝わってくる気がします
参考引用文献(図書館利用)
『万葉のふるさと』清原和義著
ポプラ・ブックス
画像
photographer『torstensimon』
by pixabay
<追記>
記事にある『かささぎ伝説』は、中国の伝説にある「かささぎが翼を広げて作った橋」とか「宮中の階段」とかいう意味で、それが七夕に融合されたものだと思われるのですが、この中国の『かささぎ』の伝説を、見事に『和歌』に取り入れたものが、残されています
詠んだ人は『壬生忠岑(みぶのただみね)』古今集の四人の選者のうちの一人です
時の右大臣、藤原定国(ふじわらさだくに)に仕えていた忠岑。ある夜、酒に酔った勢いで、定国が左大臣藤原時平の屋敷へ押しかけました。酔った定国に対し、時平は「今頃、どこの帰りなのだ」と定国に問いただしました。その時、定国に代わって忠岑が、
かささぎの 渡せる橋の 霜の上を
夜半(よは)に踏み越え ことさらにこそ
「夜中に霜の降りた橋を踏み越えてわざわざやってきたのです」
という意味の歌を詠みました。それを聞いた時平はすっかり関心し、そのあと定国、忠岑、時平の三人で夜通し酒を飲んだという事です
古今集の選者でもあり、小倉百人一首にも歌が入っている壬生忠岑ですが、生まれた年も、亡くなった年もわかっていないという事です
(参考引用文献『百人一首物語(司代隆三著)』)
初回入会から30日間無料お試し!![]()
![]()
![]()