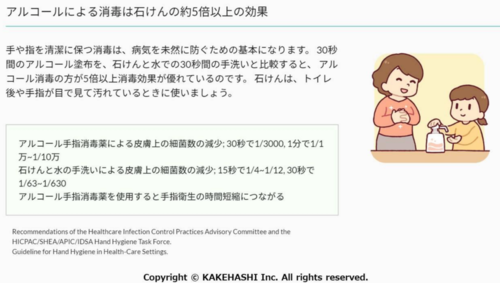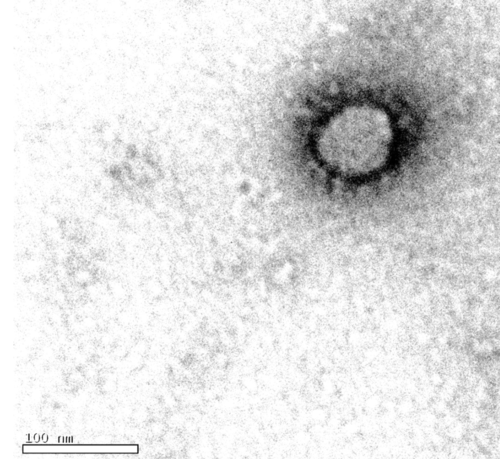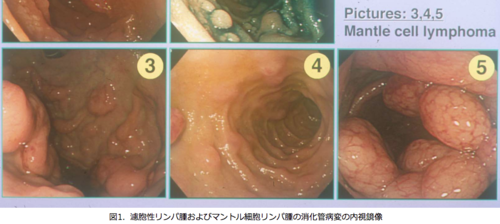2019年04月29日
迅速診断登場で「検査を信じるか、医師を信じるか」の時代に?
その通りだな、と納得されましたー小児科に進まれた先生方は偉いなといつも感じてます!(6ヶ月小児外科をかじった一般消化器外科医談)
迅速診断登場で「検査を信じるか、医師を信じるか」の時代に?【平成の医療史30年◆小児科編】
日本外来小児科学会会長・横田俊一郎氏―Vol. 3
平成の医療史30年2019年3月26日 (火)配信 一般内科疾患小児科疾患一般外科疾患
日本外来小児科学会会長の横田俊一郎氏による、外来小児科の平成30年間の振り返り。
小児科外来ではこの30年にワクチン以外にも、大きく変わった2つの診療として「迅速診断キット」と「抗菌薬処方」を挙げる。
「“検査を信じるか、医師を信じるか”みたいに、みんなが迅速診断に振り回される時代になっている気がする」と苦笑する。(聞き手・まとめ:m3.com編集部・坂口恵/2019年1月取材、全4回連載)
発熱患者の診察前に検査が完了?!
――「ワクチン以外にも、外来小児科で大きく変わった診療が2つある」と横田氏。その一つが「迅速検査キット」だそうだ。
迅速検査キットの皮切りは溶連菌でした。
一番、大きな変化をもたらしたのは、やはりインフルエンザの迅速診断キットでしょうね。
最初は保険適用がなかったので、自分で買ってやっていました。初めは「これでインフルエンザ陽性が分かるのか」なんてびっくりしていました(笑)。
もちろん、疾患が早く見つかることは悪いことではないし、日本式に早く診断して薬を使っているから重症例や死亡例が少ないという意見も間違っていないのかな、とは思います。
でも、最近はあまりにも検査に偏り過ぎているというのかな……。
「患者が熱が出て、診療所に来たら、医師の診察前に看護師がもう検査を済ませていた」なんて話も聞いたりします(苦笑)。
――自身は臨床診断と迅速検査をどう使い分けているのだろうか。
臨床診断はもちろん行いますが、中には、ニュースなどの影響か「検査さえすれば、すぐに分かるでしょう」みたいなことを言う方もいます。
例えば家族が既にかかっていて、患者に症状がある場合は「これはインフルエンザということにしましょう。
迅速検査では陰性と出ることもありますし、それはそれで混乱するでしょう?」というふうに、検査の限界を説明して納得してもらうこともあります。
やはり、医師の技量というか、それをきちんと使えるようになることが重要で、臨床診断があってこその迅速検査だと思います。
『みんなが迅速検査に振り回され過ぎている時代に』なっているような気がします。
「検査を信じるか、医師の診断を信じるか」みたいなね(笑)。
抗菌薬の処方様式が変わりにくい理由
――外来小児科で大きく変わった診療の3つ目は「抗菌薬」だそうだ。
日本外来小児科学会でも、感染症や公衆衛生の専門家の話を聞くなど、抗菌薬適正使用の動きは随分盛んにはなっていると思います。
ただ、全国に行き届いているかというと、まだ課題はあるかもしれません。
ちなみに、私の研修医時代は「ペリアクチン、アスベリン、ビソルボン」とか、「喉が赤かったり、熱があったりしたらケフレックス」などと習っていました。
『今の若い医師は、もう教育が変わっているので抗菌薬を全然使わない』ですよね。
『逆に』言うと、私たちくらいの年の、『長くやっている医師がなかなか変わらない』というのがあると思います。
――医師の抗菌薬の処方行動が変わりにくい要因を、横田氏は次のように分析する。
医師は自分で診療を始めてしまうと、大きな間違いがあったり、困ったりしたことがない限り、自分の診療スタイルを変えにくい性質があるのだと思います。
いろいろな研究から、抗菌薬によって腸内細菌の種類や数が大きく変わっていろいろな疾患につながる可能性が指摘されています。
一方、抗菌薬を使ったから平均寿命が短くなったというわけでもなく、多くの人が長生きするようになりました。
とはいえ、抗菌薬の適正使用も考えていかないと、
『耐性菌が増えてはいざというときに抗菌薬が使えなくなります』。
こうしたことも、私自身は日本外来小児科学会の活動を介して教わりました。
例えば、武内一先生(現 佛教大学教授)が香川県の小豆島中央病院に勤務していた当時、上気道炎への全てのセフェム系抗菌薬の使用を中止し、『ペニシリン系抗菌薬を厳格な適応の上でのみ使用』したところ、『5年で耐性菌がほぼゼロ』になったと報告しました(外来小児科1999; 2: 51-56)。
薬局で自分の抗菌薬処方量を確認
――草刈章氏(埼玉県・くさかり小児科)ら5人の小児科医は、小児科での抗菌薬使用がまだ一般的だった2005年に「小児上気道炎および関連疾患に対する抗菌薬使用ガイドライン-私たちの提案-」と題するGood Practice Guideを発表(外来小児科 2005; 8:146-173)。当時、小児科医の間で大きな反響を呼んだ。
この研究が基になって、西村龍夫先生(大阪府・にしむら小児科)や深澤満先生(福岡県・ふかざわ小児科)らも、髄膜炎や抗菌薬の適正使用に関する研究を報告するようになりました。
とても面白い先生方で、いつも良い刺激を受けています。私自身も「抗菌薬の不適切な使用は耐性菌出現の観点から良くない」とは分かっていました。
最初は普通の風邪には出さなくなっていたのですが、
徐々に「中耳炎も出さなくてもほとんどは自然経過で治る」と自分で確認して、処方がだんだん変わってきたというのが本当のところです。
以前は「出さなかったら、患者の状態が悪くなるのではないか……」と懸念していたのですが、やっぱり自分で「抗菌薬を処方しなくてもきちんと治る、大丈夫」と分かってくると出さなくなる。
自院近くの薬局、この地域(神奈川県小田原市)だと当院の患者の大部分は決まった薬局に取りに行くのですが、そこに頼んで自分の抗菌薬の処方量を確認してもらい、随分減っていることがあらためて分かりました。
――「抗菌薬を使わないで様子を見る」ことが可能なのは、かかりつけ医ならではだろうか。
かかりつけ医だから「念のため」と不要かもしれない抗菌薬を使わずに、その後の様子までを確認しやすいのは大きいかもしれません。近くに市立病院があって常勤の小児科医が10人くらいいるので、かかりつけの患者に何かあれば、いつでも引き受けてもらえる安心感もありますね。
迅速診断登場で「検査を信じるか、医師を信じるか」の時代に?【平成の医療史30年◆小児科編】
日本外来小児科学会会長・横田俊一郎氏―Vol. 3
平成の医療史30年2019年3月26日 (火)配信 一般内科疾患小児科疾患一般外科疾患
日本外来小児科学会会長の横田俊一郎氏による、外来小児科の平成30年間の振り返り。
小児科外来ではこの30年にワクチン以外にも、大きく変わった2つの診療として「迅速診断キット」と「抗菌薬処方」を挙げる。
「“検査を信じるか、医師を信じるか”みたいに、みんなが迅速診断に振り回される時代になっている気がする」と苦笑する。(聞き手・まとめ:m3.com編集部・坂口恵/2019年1月取材、全4回連載)
発熱患者の診察前に検査が完了?!
――「ワクチン以外にも、外来小児科で大きく変わった診療が2つある」と横田氏。その一つが「迅速検査キット」だそうだ。
迅速検査キットの皮切りは溶連菌でした。
一番、大きな変化をもたらしたのは、やはりインフルエンザの迅速診断キットでしょうね。
最初は保険適用がなかったので、自分で買ってやっていました。初めは「これでインフルエンザ陽性が分かるのか」なんてびっくりしていました(笑)。
もちろん、疾患が早く見つかることは悪いことではないし、日本式に早く診断して薬を使っているから重症例や死亡例が少ないという意見も間違っていないのかな、とは思います。
でも、最近はあまりにも検査に偏り過ぎているというのかな……。
「患者が熱が出て、診療所に来たら、医師の診察前に看護師がもう検査を済ませていた」なんて話も聞いたりします(苦笑)。
――自身は臨床診断と迅速検査をどう使い分けているのだろうか。
臨床診断はもちろん行いますが、中には、ニュースなどの影響か「検査さえすれば、すぐに分かるでしょう」みたいなことを言う方もいます。
例えば家族が既にかかっていて、患者に症状がある場合は「これはインフルエンザということにしましょう。
迅速検査では陰性と出ることもありますし、それはそれで混乱するでしょう?」というふうに、検査の限界を説明して納得してもらうこともあります。
やはり、医師の技量というか、それをきちんと使えるようになることが重要で、臨床診断があってこその迅速検査だと思います。
『みんなが迅速検査に振り回され過ぎている時代に』なっているような気がします。
「検査を信じるか、医師の診断を信じるか」みたいなね(笑)。
抗菌薬の処方様式が変わりにくい理由
――外来小児科で大きく変わった診療の3つ目は「抗菌薬」だそうだ。
日本外来小児科学会でも、感染症や公衆衛生の専門家の話を聞くなど、抗菌薬適正使用の動きは随分盛んにはなっていると思います。
ただ、全国に行き届いているかというと、まだ課題はあるかもしれません。
ちなみに、私の研修医時代は「ペリアクチン、アスベリン、ビソルボン」とか、「喉が赤かったり、熱があったりしたらケフレックス」などと習っていました。
『今の若い医師は、もう教育が変わっているので抗菌薬を全然使わない』ですよね。
『逆に』言うと、私たちくらいの年の、『長くやっている医師がなかなか変わらない』というのがあると思います。
――医師の抗菌薬の処方行動が変わりにくい要因を、横田氏は次のように分析する。
医師は自分で診療を始めてしまうと、大きな間違いがあったり、困ったりしたことがない限り、自分の診療スタイルを変えにくい性質があるのだと思います。
いろいろな研究から、抗菌薬によって腸内細菌の種類や数が大きく変わっていろいろな疾患につながる可能性が指摘されています。
一方、抗菌薬を使ったから平均寿命が短くなったというわけでもなく、多くの人が長生きするようになりました。
とはいえ、抗菌薬の適正使用も考えていかないと、
『耐性菌が増えてはいざというときに抗菌薬が使えなくなります』。
こうしたことも、私自身は日本外来小児科学会の活動を介して教わりました。
例えば、武内一先生(現 佛教大学教授)が香川県の小豆島中央病院に勤務していた当時、上気道炎への全てのセフェム系抗菌薬の使用を中止し、『ペニシリン系抗菌薬を厳格な適応の上でのみ使用』したところ、『5年で耐性菌がほぼゼロ』になったと報告しました(外来小児科1999; 2: 51-56)。
薬局で自分の抗菌薬処方量を確認
――草刈章氏(埼玉県・くさかり小児科)ら5人の小児科医は、小児科での抗菌薬使用がまだ一般的だった2005年に「小児上気道炎および関連疾患に対する抗菌薬使用ガイドライン-私たちの提案-」と題するGood Practice Guideを発表(外来小児科 2005; 8:146-173)。当時、小児科医の間で大きな反響を呼んだ。
この研究が基になって、西村龍夫先生(大阪府・にしむら小児科)や深澤満先生(福岡県・ふかざわ小児科)らも、髄膜炎や抗菌薬の適正使用に関する研究を報告するようになりました。
とても面白い先生方で、いつも良い刺激を受けています。私自身も「抗菌薬の不適切な使用は耐性菌出現の観点から良くない」とは分かっていました。
最初は普通の風邪には出さなくなっていたのですが、
徐々に「中耳炎も出さなくてもほとんどは自然経過で治る」と自分で確認して、処方がだんだん変わってきたというのが本当のところです。
以前は「出さなかったら、患者の状態が悪くなるのではないか……」と懸念していたのですが、やっぱり自分で「抗菌薬を処方しなくてもきちんと治る、大丈夫」と分かってくると出さなくなる。
自院近くの薬局、この地域(神奈川県小田原市)だと当院の患者の大部分は決まった薬局に取りに行くのですが、そこに頼んで自分の抗菌薬の処方量を確認してもらい、随分減っていることがあらためて分かりました。
――「抗菌薬を使わないで様子を見る」ことが可能なのは、かかりつけ医ならではだろうか。
かかりつけ医だから「念のため」と不要かもしれない抗菌薬を使わずに、その後の様子までを確認しやすいのは大きいかもしれません。近くに市立病院があって常勤の小児科医が10人くらいいるので、かかりつけの患者に何かあれば、いつでも引き受けてもらえる安心感もありますね。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8760595
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック