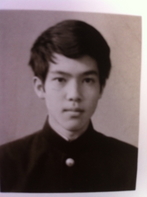2016年03月30日
第59回 新らしき女の道
文●ツルシカズヒコ
『青鞜』一九一三年一月号の附録(特集)は「新らしい女、其他婦人問題に就いて」だった。
『元始、女性は太陽であった 平塚らいてう自伝(下巻)』(p422~423)によれば、この特集を組んだ目的はまず対外的なもので、ジャーナリズムや世間の「新しい女」攻撃に対する反撃だった。
そして対内的には「私は新らしい女ではない」という逃げ腰の社員に対する、自分たちの覚悟の表明だった。
この特集には八人が寄稿しているが、らいてうはエレン・ケイ著『恋愛と結婚』の翻訳(連載第一回)、野枝は「新らしき女の道」を寄稿した。
大杉栄の妻、堀保子も「私は古い女です」を寄稿して、男女関係は法律で決める性質のものではないなど夫婦別姓を論じているが、大杉豊『日録・大杉栄伝』(p100)によれば大杉が代筆した原稿らしい。
野枝の「新らしき女の道」は、因習に立ち向かう先導者として茨の道を歩む決意表明である。

新らしい女は今迄の女の歩み古した足跡を何時までもさがして歩いては行かない。
新らしい女には新らしい女の道がある。
新らしい女は多くの人々の行き止まつた処より更に進んで新らしい道を先導者として行く。
先導者としての新らしき女の道は畢竟(ひつきよう)苦しき努力の連続に他ならないのではあるまいか。
(「新しき女の道」/『青鞜』1913年1月号・第3巻第1号附録/『定本 伊藤野枝全集 第二巻』_p13~14)
野枝は水野葉舟(みずの・ようしゅう)『妹に送る手紙』の感想も書いている。
書いてある事なども自分には同感の点が多かつた。
何(ど)うかしたら女学校の倫理教科書よりもずつと面白くて得る処も多い。
かう云ふ手紙を貰つて教育されて行くお澪さんは幸福な人だ。
(「寄贈書籍紹介」/『青鞜』1913年1月号・第3巻第1号/『定本 伊藤野枝全集 第二巻』_p15)
堀場清子『青鞜の時代』(p133)によれば、『青鞜』同号(第三巻第一号)は原阿佐緒が青鞜社の社員になったことを報じている。
野枝は大森町森ヶ崎の富士川旅館で催された、『青鞜』新年会には出席しなかった。
森ヶ崎で催された新年会は大分集まつて賑やかだつたと後で聞いた。
私は其日往かなかつた。
紅吉の家から帰りに引き込んだ風邪と、それ以上にもつと一番大きな理由をなしたものは、私の貧乏であつた。
私は其時大森までの電車賃は勿論の事、其処から掛つて来た呼び寄せの電報に返事をすることさへ出来なかつのだ。
私は、私の三畳の室の机の前に火鉢を抱へて、終日書物と首つ引きをして暮した。
時々私は賑やかな集まりの様を思ひ出しはしたけれど、直にまた書物の興味に誘ひ込まれた。
其日の事は自分で其席へ出なかつたせいか、後で話を聴いても余り面白い事もなかつたと見えて一向私の頭には残らなかつた。
(「雑音」/『大阪毎日新聞』1916年2月8日/『大杉栄全集別冊 伊藤野枝全集』_p75~76/『定本 伊藤野枝全集 第一巻』_p164)
辻一家は東京府北豊島郡巣鴨町上駒込四一一番地に住んでいたが、辻は自宅や周りの様子について、こう書いている。
その家は丘の上に建てられていました。
間数は僅か三間で六畳と三畳と四畳半という極めてささやかな家でしたが、植木家が家主だけあって、家の造りが極めて瀟洒で、庭が比較的広く、庭木も椿とか南天とか紫陽花とかさまざまな種類が植えられていました。
四畳半が茶の間で、それが玄関のあがり口にありましたが、親しい訪問客は門を入ると左側の枝折(しお)りがありましたから、そこから中の六畳に通すことにしていました。
奥の三畳がつまり私の初めて見つけ出した理想的な書斎だったのです。
その部屋は中廊下に隔てられた茶室風な離れで、押入れも床の間も廻り縁もついた立派に独立した部屋だったのです。
私はこの三畳の部屋にひとり立て籠って妄想を逞しくしたり、雑書を乱読したりすることをなによりの楽しみにしていました。
勿論、部屋の装飾といってはなにもありませんでした。
僅かに床柱に花が投げ込まれていた位なものです。
しかし床の間には竹田(ちくでん)の描いた墨絵の観音と、その反対の壁には神代杉の額縁に填められたスピノザの肖像がかかっていました。
その軸も肖像も両(ふた)つながら私のながい間愛好してきたものです……。
今でも私はその郊外の閑居で過ごした夏の夕暮の情景を忘れることが出来ません。
丘の下は一帯のヴァレイで、人家も極めて少なく、遥かに王子の飛鳥山を望むことが出来ました。
なんという寺か忘れましたが、谷の向こう側にあるその寺から夕暮にきこえてくる梵鐘の音は実に美しい響きをそのあたりに伝えました。
樹々の間から洩れて来る斜陽、蜩の声、ねぐらにかえる鳥の姿、近くの牧場からきこえてくる山羊の声――私はひとり丘の上に彳立(たたず)んで、これらの情趣を心ゆくまで味わったのでした。
(「書斎」/『辻潤全集 第二巻』_p158~159)
『青鞜』二月号の附録(特集)は、前号と同様に「新しい女、其他婦人問題に就いて」である。
この二月号が二月八日に発禁処分になった。
「御苦労様な事 雑誌青鞜の発売禁止 安寧秩序を害すとて」という見出しで、『読売新聞』が報じている。
野枝の新聞デビューのコメントも載っている。
雑誌『青鞜』の二月号は八日午前八時安寧秩序を害するものと認定されて大浦新内相から発売を禁止された
内務省書記官の石原磊三氏に何処が「安寧秩序を害す」に相当するかを訊ねたが従来抵触する点に就いては発表しないことになつて居ると許(ばか)りで更に要領を得ない、
編輯主任の平塚明子女史……には多分彼(あ)れでせう位の見当は付いて居らうと……昨日の午後三時頃、曙町に女史を訪ふた、
女史は南面の暖かい座敷で語る、
『今朝駒込署の警官が見えて発売禁止になりましたと言置いて帰りましただけで理由も何も解りませんでした……或は福田英子さんの「婦人問題」には共産主義の分子を含むで居る様にも見えないこともありませぬが、でなくば伊藤野枝子さんの「此の頃の感想」かも知れません、何んにせよ、私としては御苦労様な事と思ひます位なものです、「此の頃の感想」の内容は教育家に対する反対と結婚問題に就いてゞ御座います、くはしくは御当人に伺つて下さい』
さて其の御当人の野枝子さんにくわしい事を訊ねたならばイタクはにかむで居たが、軈(やが)てさも思ひ切つた様に、
『畢竟(つまり)学校なぞで先生から教へられる倫理に反対したので、例令(たとへ)境遇に甘んぜよと教へても甘んじられないと刃向ひ、或は結婚に就いては人の手を借りたり叉は目的や要求のある結婚を排斥したのです、つまり恋愛以外の結婚をです』と却々(なかなか)大儀さうに語つた
(『読売新聞』1913年2月9日・3面)
野枝のコメントからすると、「此の頃の感想」のこのあたりが当局を刺戟したようだ。
私には結婚といふものが馬鹿々々しい事に思へて仕方がない。
少くても在来の型のやうな結婚法には満足する事は出来ぬしもう少し人間の自覚が出来て来たらきつと人手を借りての馬鹿々々しい結婚法では満足してゐられなくなる筈だ。
今迄の女は皆意久地なしだ。
怠惰者(なまけもの)だ。
詰らない目の前ばかりの安逸や幸福を得たいが為めにすべて自己を失した木偶(でく)のみだ。
そしてそれ等の女の教育をする者も同じ女だ。
(「此の頃の感想」/『青鞜』1913年2月号・第3巻第2号/『定本 伊藤野枝全集 第二巻』_p19~20)
『元始、女性は太陽であった 平塚らいてう自伝(下巻)』(p434~436)によれば、福田英子「婦人問題の解決」は徹底した共産制こそが人間(男女ともども)を解放し恋愛や結婚の自由を可能にするといった論文で、特に過激なところはなかったが、福田と平民社との関係が当局を刺戟したらしい。
平民社はすでに解散していたが、あの大逆事件の記憶はまだ生々しかったのである。
前年十二月に第二次西園寺内閣が軍部の圧迫で倒れ、第三次桂内閣が成立していたが、その弾圧政策だった。
『青鞜』の発禁は前年四月号の荒木郁子「手紙」に次いで、二度目だった。
この発禁により、らいてうとその父・定二郎の間でひと悶着起きた。
会計検査院に勤務する高級官吏の定二郎は天皇崇拝者であり、国家への忠誠ひと筋の人だった。
その父がらいてうに、こう言い放ったという。
「今後も社会主義者のものを出さなければならないようなら、雑誌を出すのをやめてほしい。もしやめられないなら、家を出ていってやれ」
「家を出ていってやれ」という父の言葉が、らいてうの心に強く残った。
※王子滝野川 ※王子滝野川2
※原阿佐緒記念館
★『元始、女性は太陽であった 平塚らいてう自伝(下巻)』(大月書店・1971年9月6日)
★大杉豊『日録・大杉栄伝』(社会評論社・2009年9月16日)
★『定本 伊藤野枝全集 第二巻』(學藝書林・2000年5月31日)
★『定本 伊藤野枝全集 第一巻』(學藝書林・2000年3月15日)
★『大杉栄全集別冊 伊藤野枝全集』(大杉栄全集刊行会・1925年12月8日)
★『辻潤全集 第二巻』(五月書房・1982年6月15日)
★堀場清子『青鞜の時代ーー平塚らいてうと新しい女たち』(岩波新書・1988年3月22日)
●あきらめない生き方 詳伝・伊藤野枝 index
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image