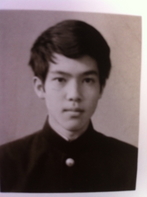2016年05月15日
第175回 婦人矯風会
文●ツルシカズヒコ
「死灰の中から」によれば、大杉は七月末に野枝が出産のために帰郷したことは知っていた。
大杉は忙しかったので、野枝が帰郷する一ヶ月ほど前から彼女に会う機会はなかった。
十月、大杉は第二次『近代思想』を復活号として発刊した。
大杉豊『日録・大杉栄伝』によれば、宮嶋資夫が調布に移転して発行人となり、編集人・大杉、印刷人・荒畑である。
しかし、『近代思想』は十一月号、十二月号と連続して発禁になった。
十二月十五日、大杉と保子は逗子町桜山に移転した。
『近代思想』発行人としての、保証金減額のためである。
大杉はこの夏以降の野枝との関係については、こう書いている。

七月の末に彼女はTと一緒に九州へ行つた。
又妊娠してゐるやうだつたから、多分郷里で生むつもりで行つたんだらうと思つた。
彼女からは、此の逗子に来てからは、ただ一度はがきが来ただけだつた。
僕も其の時に一度だけ、はがきを出しただけだつた。
時々僕は、彼女の二通の手紙を出しては彼女に親しんだ。
しかし、先きに云つた程の恋の熱情も起らず、又其の熱情を生んだセンテイメンタルな幻想も余程薄らいで了つた。
僕は毎週一回、二三日づつ上京して、友人の家を泊り歩いてゐた。
そして……僕の家に出入りし、僕等の集会にも来、雑誌の手伝ひもしてゐた、T新聞婦人記者I子とあはい恋に戯れてゐた。
(「死灰の中から」/『新小説』1919年9月号/大杉栄全集刊行会『大杉栄全集 第三巻』/日本図書センター『大杉栄全集 第12巻』)
「傲慢狭量にして不徹底なる日本婦人の公共事業に就いて」解題(『定本 伊藤野枝全集 第二巻』)によれば、大正天皇即位の大典を前に、一九一五年四月に開かれた日本基督教婦人矯風会第二十三回大会において、同会は席上に醜業婦を同席させない、六年後に公娼を全廃するという二項目を決議した。
野枝は「傲慢狭量にして不徹底なる日本婦人の公共事業に就いて」を『青鞜』十二月号に書き、上流階級の婦人たちによって組織された婦人団体の慈善を「虚栄のための慈善」と批判し、その一例として「婦人矯風会」をあげ、同会の決議に異議を唱えた。
そもそも野枝の売買春に対する考えは、そう簡単にこの世の中からなくせるものではないというところからスタートしている。
……実は偉大なる自然力の最も力強い支配の下にある不可抗力である。
それは到底わづかな人間の意力や手段では誤魔化せない正真正銘のねうちを失ふことのない力である。
……あゝした業が社会に認められてるのは誰でもが云ふ通りに矢張り男子の本然要求と長い歴史がその根を固いものにしてゐる。
それは必ず存在する丈けの理由を持つてゐるのである。
(「傲慢狭量にして不徹底なる日本婦人の公共事業に就いて」/『青鞜』1915年12月号・第5巻第11号/『定本 伊藤野枝全集 第二巻』_p292)
公娼と私娼に関しては、「婦人矯風会」はまず公娼廃止を主張しているが、野枝は公娼より私娼の方が社会の風俗をよりいっそう乱すと主張している。
……いまはしい恐るべき病毒の伝染と云ふこと、それから世間の子女をたやすくさういふ商売に導き入れると云ふこと、一寸(ちょっと)考へた丈けでもよほど社会に悪影響を及ぼす力は私娼の方にありさうに私には思はれる。
(「傲慢狭量にして不徹底なる日本婦人の公共事業に就いて」/『青鞜』1915年12月号・第5巻第11号/『定本 伊藤野枝全集 第二巻』_p293)
要するに野枝は、この時点では公娼制度を必要悪と考えていたのだろう。
この野枝の書いた文章をきっかけに、『青鞜』の最後を飾る廃娼論争が起きることになる。
野枝と辻がふたりの子供を連れて帰京したのは十二月五日、六日、そのあたりである。
らいてうが第一子、長女・曙生(あけみ)を出産したのは十二月九日だった。
難産だったため、らいてうの病室には面会謝絶の札が出されたが、それを無視して毎日のように産褥のらいてうに新聞記者が取材に押しかけた。
恋愛の自由、新しい性の道徳を唱え、因襲結婚に反抗し、法律上の結婚を拒否しているらいてうが、ついに私生児を生んだ……というニュースのネタになったのである。
野枝も憤っている。
見舞いに来てくれた伊藤野枝さんはひどく憤慨して、「なんて失礼な非常識な奴でしょう。私がいるとき来たらうんと言ってやる」と、涙さえ浮かべていました。
(『元始、女性は太陽であった 平塚らいてう自伝(下巻)』_p583)
大杉は毎週日曜日に開かれるフランス文学研究会の講義をするため、毎週一回、二、三日ずつ上京し友人の家を泊まり歩いていた。
大杉はフランス文学研究会と平民講演会に出席していた神近と顔を合わせることが多くなり、ふたりの仲は急接近した。
『日録・大杉栄伝』によれば、大杉は十二月二十日に広尾の神近の家で半日過ごし、十二月二十六日には神近の家に泊まった。
神近が大杉に惹かれている自分を意識したのは、このころからだった。
(※十二月二十日)私共は静かに話しました。
大杉さんはその前夜あつた文士の或る会合で、ある先輩が自分と私との関係が可笑しいと云ひ出した事だの……自分の気持の話をされました。
そして大杉さんに対しては好く戯談を云つてゐた私が「噂を事実にやりますかね」と軽く諧けたのも私は云ひ落しますまい。
……半分は平生の軽い戯談と、半分は打つ突つて行かうと為る気持で云つた事も。
半日を種々な話に過して、一緒に家を出かけました。
途中で用を足してから逗子に帰るあの人を新橋に見送りました。
恋人同士の様だと笑い乍ら。
それで次の日曜日(※十二月二十六日)に私は大杉さんと二人になる機会を造へ様と決心しました。
その日曜日は丁度雑誌の校正の出る日で、私は以前から校正丈は手伝つてゐましたから、仏蘭西語が済むと一緒に印刷所に出かけました。
そして仕事を少しやつて、大杉さんの親しい日本橋の或る料理屋に食事に行く事にしました。
かうして私は極めて静かな気持で恋愛に入つて行きました。
(神近市子「三つの事だけ」/『女の世界』1916年6月号/安成二郎『無政府地獄- 大杉栄襍記』_p93~94)
この年の秋、大杉が初めて麻布区霞町の神近の家に泊まったときのことを、神近はこう回想している。
……庭木戸の鈴が鳴って、ヒョッコリ大杉栄氏がはいってきたのである。
秋の日はつるべ落としといわれるとおり、あたりは早くも暮れそめていた。
「尾行はまいてきた。ただおなかがへった」
私はありあわせのパンに果物程度の簡単な支度をしてあげ、紅茶をいれた。
むろん、それを食べてすぐ帰られるものと思っていたのだが、大杉氏はなかなか腰をあげようとせず、やがてポツリといわれた。
「きょうは泊まっていってもいいんだ」
……なにか精神的な借りがあって、無下には断わりきれないような感じだった。
あるいは、無意識のうちに大杉氏に恋をしていたのかもしれない。
その日以来、何度も同じ状態がくり返された。
(『神近市子自伝 わが愛わが闘争』_p144~145)
★大杉豊『日録・大杉栄伝』(社会評論社・2009年9月16日)
★『大杉栄全集 第三巻』(大杉栄全集刊行会・1925年7月15日)
★『大杉栄全集 第12巻』(日本図書センター・1995年1月25日)
★『定本 伊藤野枝全集 第二巻』(學藝書林・2000年5月31日)
★『元始、女性は太陽であった 平塚らいてう自伝(下巻)』(大月書店・1971年9月6日)
★安成二郎『無政府地獄- 大杉栄襍記』(新泉社・1973年10月1日)
★『神近市子自伝 わが愛わが闘い』(講談社・1972年3月24日)
●あきらめない生き方 詳伝・伊藤野枝 index
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image