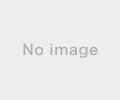2016年04月25日
読書感想文『病気にならない』 おすすめの文章と自分なりの感情
今回のブログでは私「小谷中広之」が読んだ本の中で気に入った文章を紹介するとともに私「小谷中広之」がその文章に対して感じたこと(感情)を書き、少しでも皆様の何かのきっかけになれればこのうえない喜びです(定期的に読書感想文は更新していきます)
決して細かくは書くことはありませんのでご了承ください
私「小谷中広之」が感じた文章を書きたいと思っております
今回のご紹介する本は、新谷弘実様の「病気にならない生き方」です
新谷弘実様 1935年福岡生まれ 順天堂大学医学部卒業 アルバートアインシュタイン医科大学外科教授 ベスイスラエル医科大学外科教授
気になる文章
●健康でいられるか否かは、その人の食事、生活習慣しだい
○小谷中広之の感情・・・様々な健康情報が流れる世の中、しっかりと自分で考え判断し選択しなければならなくなっている
その上で基本となる判断基準は、「全ての人間に合う健康法はない」ということ
●肉を食べなければ身体が大きくならないというのもウソです。ゾウやキリンはライオンやトラの何倍もの大きい差がありますが、彼らは草食動物です
ただし、動物性タンパク質をたくさん食べると人間の成長が早くなるということは事実です。最近の子供達の成長スピードが速いのは、動物性たんぱくの摂取が増えたためと考えられています
しかし、ここにも動物食の危険な落とし穴があります。それは「成長」はある年齢を超えた時点で「老化」と呼ばれる現象に変わるということです。つまり、成長を早める動物食は、別の言い方をすれば、老化を早める食事ということになるのです
○小谷中広之の感情・・・和食を基本とした食生活を心がける
●牛乳ほど消化の悪い食べ物はないと言っても過言ではありません
牛乳に含まれるたんぱく質の約八割を占める「カゼイン」は、胃に入るとすぐに固まってしまい、消化がとても悪いのです。さらに、市販の牛乳はその成分がホモゲナイズ(均等化)されています。「ホモゲナイズ」というのは、搾乳した牛乳の脂肪分を均等化させるために拡販することを言います。なぜホモゲナイズするのがいけないかというと、撹拌するときに牛乳に空気が混じり、乳脂肪分が過酸化脂質になってしまうからです
過酸化脂質というのは文字通り「酸化がとても進んだ油」という意味です。わかりやすく言えば「錆びた油」です
そのさびた油を含んだ牛乳を、今度は100度以上の高温で殺菌します
市販の牛乳というのは、脂肪分は参加し、蛋白質も高温のために変質しているという、ある意味で最悪の食べ物なのです
その証拠に、市販の牛乳を母牛のお乳代わりに子牛に飲ませると、4,5日で死んでしまう
子供達の食事から、すぐに牛乳と乳製品を全てカットするように指示しました
すると案の定、血便も下痢も、アトピーすらもピッタリ治ったのです
妊娠中の母親が牛乳を飲むと、子供にアトピーが出やすくなるという研究結果とも一致
○小谷中広之の感情・・・乳製品をやめた場合の副作用とはなんだろうか!?
まず一番考えられるのが乳製品会社への利益不振、そしてそこで働く人達の減給やリストラなどによって生活への影響、さらには消費力の低下が起こり国内総生産は減り国にダメージが発生する
しかし、乳製品をやめたその穴は、新たな何かがスタートし新たな雇用が産まれる可能性を秘めているだろう
●マグロやカツオなど赤身の魚と呼ばれる物は、その名の通り筋肉組織が「赤色」をしていますが、これは筋肉が「ミオグロビン」という特殊なたんぱく質を多く含んでいるからです
ミオグロビンは、代謝に必要な時まで細胞内に酸素を蓄えることができるので、イルカやクジラ、アザラシなど長時間、水に潜っていることが必要な動物の筋肉によく見られます。一般的に動物の肉が赤い色をしているのも、このミオグロビンのためです
このミオグロビンを多く含んでいるため、赤身の魚は、おろして身が空気に触れるとすぐに酸化してしまう。これが赤みの魚の良くないと言われる理由です
ところが、DHAやEPAといった抗酸化物質は赤身のほうが多く持っているのです
赤みを食べる際に気を付けたいのは、鮮度の良いものを選ぶ
○小谷中広之の感情・・・お刺身を購入する際には、刺身用で売られているものではなくブロックで売られているものにしよう
出来れば、魚が丸々売っているものを買えれば良いが
食べ切れなければ棄てることになるのなら購入せずブロックにしよう
●子供は育った家庭の「習慣」を無意識のうちに放り込まれて育ちます
子供が親と同じ病気を発症しやすいのは、遺伝子として病気の原因を受け継いだからではなく、病気の原因となった生活習慣を受け継いだ結果なのです
遺伝的要素は持って生まれた者です。でも習慣は「努力と意志の力」で変えることができるのです。そして、週間の積み重ねによって遺伝的要素はプラスにもマイナスにも変わっていくのです。自分を救う「良い習慣」は、あなたの次世代をも救うものだということをぜひ覚えておいてください
○小谷中広之の感情・・・つまり、親の良い習慣を取り入れ、自分の体を使い自分なりの良い習慣を取り入れて、その習慣を一つの財産として子孫へと残していく
残しておく方法はやはり文章として残しておくことが良いだろう
ここまで読んでいただきありがとうございます。読んでいただいた方の人生での何かのお役に立てればとても嬉しいです
この本の他の文章が気になった方下記のサイトで購入可能です。
 病気にならない生き方 |
タグ:新谷弘実 様
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4960166
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック