�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B
�L��
�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B
posted by fanblog
2019�N06��25��
�f��u�v�����T�p�^�v���L�V�R�v���̉p�Y��`��
�u�v�����T�p�^�v(Viva Zapata!)�@1952�N�A�����J
�ēG���A�E�J�U��
�r�{�W�����E�X�^�C���x�b�N
�B�e�W���[�E�}�N�h�i���h
���y�A���b�N�X�E�m�[�X
�q�L���X�g�r
�}�[�����E�u�����h�@�A���\�j�[�E�N�C��
�W���Z�t�E���C�Y�}��
�J���k���ۉf��Վ剉�j�D��(�}�[�����E�u�����h)
��25��A�J�f�~�[�����j�D���(�A���\�j�[�E�N�C��)

20���I�����̃��L�V�R�B
�|���t�B���I�E�f�B�A�X�哝�̂ɂ��ƍِ����̂��ƁA�n��Ɣ_���Ƃ̊Ԃɓy�n���ɂ���ޒn��ւ̕s���������オ��A�_�������̓f�B�A�X�哝�̂ɒ��i�ɋy�Ԃ��ƂɂȂ�܂��B
�n��Ƃ̖��͍ٔ��ɑi����ƌ����哝�̂̌��t�ɁA�_�������͔[�����Ĉ����グ�悤�Ƃ��܂����A��l�����A���̏�����낤�Ƃ��Ȃ���҂����܂����B
�u�ٔ������āA��x�ł��_�����n��ɏ��������Ƃ����邩�v
�Ǝ�҂͌����܂��B
�����Č��������̂��Ƃ������ƁA��҂͂��̏�𗧂����낤�Ƃ��܂����A�哝�͔̂ނ��Ăю~�߁A�u���O�̖��O��?�v�Ɛu���܂��B
��҂͓����܂��B�u�T�p�^�B�G�~���A�[�m�E�T�p�^�v
�_�������̖���̒��ɃT�p�^�̖��O���������哝�̂́A�ނ̖��O�����ۂň݂͂܂��B
�f��`���̂��̃V�[���́A��ɃT�p�^�����͂̍��ɂ����Ƃ��ɎЉ�I����ɂ����鎩�Ȗ����̕����Ƃ��ďd�v�ȈӖ������̂ł����A����͌�̂��b���B


����������
�p���`���E���B�����Ƌ��Ƀ��L�V�R�v���̕��_���Ƃ��Ă��̖���y�����G�~���A�[�m�E�T�p�^�B
�f��́A�v���̔��[�ƁA��Ƀf�B�A�X�哝�̂̎��C�ƂƂ��Ɋv���̉p�Y�ƂȂ����T�p�^�̎p�������ƒǂ��Ȃ���A���ӂɒ��݁A����̒��ňÎE�����T�p�^�̔������A�}�[�����E�u�����h�A�A���\�j�[�E�N�C���Ȃǂ̖��D�����̔M���ɂ���ĕ`���Ă䂫�܂��B

���L�V�R�v���́A�t�����X�v���Ȃǂ������ł���悤�ɗl�X�Ȑ��͂��䓪���Đ����������Ă䂫�܂��B
�f�B�A�X�哝�̂̈����ƁA�f�B�A�X�ƑΗ�����t�����V�X�R�E�}�f���̃A�����J�ւ̖S���B�v���̗����҂ł��������}�f���ƃT�p�^�̊m���B�܂��A�哝�̂ƂȂ����}�f�����E���A���͂��L���锽�v���̊���r�N�g���A�[�m�E�E�G���^���R�B
�E�G���^������œ|���邽�߂Ɏ������ꂽ�l�X�Ȋv���R�ƁA���̏W���̂ł���쌛�v���R�B
�쌛�v���R�k���t�c�𗦂���t�����V�X�R�E���B����(�p���`���E���B����)�B
�쌛�v���R�̎w���I����ł���A��Ƀ��B������T�p�^�ƑΗ����邱�ƂɂȂ�x�k�X�e�B�A�[�m�E�J�����T�B
�������A�f��u�v�����T�p�^�v�̓��L�V�R�v�����ڂ����m��Ȃ��Ă�������Ղ����e�ɂȂ��Ă��܂��B
�r�{��S�������̂��m�[�x�����w�܍�ƃW�����E�X�^�C���x�b�N�B
�u�{��̕����v�u��\���l�Ɛl�ԁv�u�G�f���̓��v�ȂǁA�l�Ԃ̓��ʂɐ[�����ݍ��앗�́u�v�����T�p�^�v�ł��\���ɔ�������Ă��āA�n�����Ɖh���A���Ɨ���A����邱�Ƃ̂Ȃ���������̔��R�Ƃ������A�X�^�C���x�b�N���̐��������Ƃ����l�ԃh���}���W�J����Ă����܂��B


����������
�ḗu�~�]�Ƃ������̓d�ԁv�̖����G���A�E�J�U���B
�J�U���Ƃ����ƁA�ǂ����Ă��n���E�b�h�̐Ԏ��ɂƂ��Ȃ������I�w�i����肴������Ă��܂��܂����A1998�N�ɍs��ꂽ�A�J�f�~�[�܂̎����ŁA�f��E�ɑ��钷�N�̌��J�Ƃ��āu���_�܁v���^����ꂽ�Ƃ��A�吨�̔���̒��ŁA�ꕔ����̓u�[�C���O���N���A�j�b�N�E�m���e�B�A�G�h�E�n���X�Ȃǂ͜�R�Ƃ����\��̂܂܁A�\������J�U�������߂Ă����̂��ƂĂ���ۂɎc���Ă��܂��B
�����������Ƃ�����܂����A�u�v�����T�p�^�v���̂��̂͗D�ꂽ�f�悾�Ǝv���܂����A�}�[�����E�u�����h�͂������A�T�p�^�̌Z���[�t�F�~�I�������A�����j�D�܂���܂����A���\�j�[�E�N�C���̑e��ō����Ȗ����A�킢�����Ȃ��������邱�Ƃ̂Ȃ��s���̒n�ʂ���v���̈Ӌ`���������A��ł���T�p�^�Ƃ̊m���̉���h���Ȃ���E����Ă��܂��ߌ��̒j���[�t�F�~�I�́A�ł��l�Ԃ������l�Ԃ̓T�^�ł���A�u�v�����T�p�^�v�̒��ŋ���Ȉ�ۂ��c���܂����B

����Ȉ�ۂƂ������Ƃł́A���f�B�A�X�哝�̔h�̐��͂̒������������������A�Ō�ɂ̓T�p�^�𗠐��Ă��܂��t�F���i���h�E�A�M�[�����������W���Z�t�E���C�Y�}���B
�u007/�h�N�^�[�E�m�I�v(1962�N)�ł́A�����m�I���m�������ċ���Ȉ�ۂ��c���A�h�N�^�[�E�m�I�̃C���[�W��1973�N�́u�R����h���S���v�̈����~�X�^�[�E�n���ɂ��̂܂p����Ă��܂��B
�����A�f��Ƃ��Ă̓t�F���i���h�E�A�M�[���̐l�ԑ����C�}�C�`������Â炩�����̂���_�ł����A�I�Ղ̃T�p�^�ÎE�̏�ʂ́u�������ɖ����͂Ȃ��v(1968�N)�̃��X�g�ɂȂ���s��ȃV�[���ł����B
�������ߎS�Ȍ��ʂƂ��ďI���̂ł͂Ȃ��A�T�p�^�̈��n���R�֓���������A�p�Y�ƂȂ����T�p�^�����n�̈�ۂƂ��Đl�X�̋L���Ɏc�邱�Ƃ��Î��������X�g�͏G��ł����B
�NjL
�n�����_���o�g�ŕ��ӂƂ��ĕ`���ꂽ�G�~���A�[�m�E�T�p�^�ł����A���ۂɂ͗T���Ȕ_�ꏊ�L�҂̑��q�ŁA�u���W���A�I�G���[�g�ł��������悤�ł����瓖�R�Ȃ��當�ӂł͂Ȃ������͂��B
�n�������ӂƂ����̂́A�v���𐬂������錴���͉͂��w�ɐ�����_���K���ł��邱�Ƃ��������悤�Ƃ����̂��A�n�����_���̒����琶�܂ꂽ�p�Y�Ƃ��Đe���݂₷�����o�����Ƃ����̂��B
������ɂ��Ă��A���ӂł��邱�ƂŁA�_�̏�̉p�Y�Ƃ������́A���O���\����p�Y�Ƃ��čD�������Ă��̂͂������ł��B





�ēG���A�E�J�U��
�r�{�W�����E�X�^�C���x�b�N
�B�e�W���[�E�}�N�h�i���h
���y�A���b�N�X�E�m�[�X
�q�L���X�g�r
�}�[�����E�u�����h�@�A���\�j�[�E�N�C��
�W���Z�t�E���C�Y�}��
�J���k���ۉf��Վ剉�j�D��(�}�[�����E�u�����h)
��25��A�J�f�~�[�����j�D���(�A���\�j�[�E�N�C��)

20���I�����̃��L�V�R�B
�|���t�B���I�E�f�B�A�X�哝�̂ɂ��ƍِ����̂��ƁA�n��Ɣ_���Ƃ̊Ԃɓy�n���ɂ���ޒn��ւ̕s���������オ��A�_�������̓f�B�A�X�哝�̂ɒ��i�ɋy�Ԃ��ƂɂȂ�܂��B
�n��Ƃ̖��͍ٔ��ɑi����ƌ����哝�̂̌��t�ɁA�_�������͔[�����Ĉ����グ�悤�Ƃ��܂����A��l�����A���̏�����낤�Ƃ��Ȃ���҂����܂����B
�u�ٔ������āA��x�ł��_�����n��ɏ��������Ƃ����邩�v
�Ǝ�҂͌����܂��B
�����Č��������̂��Ƃ������ƁA��҂͂��̏�𗧂����낤�Ƃ��܂����A�哝�͔̂ނ��Ăю~�߁A�u���O�̖��O��?�v�Ɛu���܂��B
��҂͓����܂��B�u�T�p�^�B�G�~���A�[�m�E�T�p�^�v
�_�������̖���̒��ɃT�p�^�̖��O���������哝�̂́A�ނ̖��O�����ۂň݂͂܂��B
�f��`���̂��̃V�[���́A��ɃT�p�^�����͂̍��ɂ����Ƃ��ɎЉ�I����ɂ����鎩�Ȗ����̕����Ƃ��ďd�v�ȈӖ������̂ł����A����͌�̂��b���B
����������
�p���`���E���B�����Ƌ��Ƀ��L�V�R�v���̕��_���Ƃ��Ă��̖���y�����G�~���A�[�m�E�T�p�^�B
�f��́A�v���̔��[�ƁA��Ƀf�B�A�X�哝�̂̎��C�ƂƂ��Ɋv���̉p�Y�ƂȂ����T�p�^�̎p�������ƒǂ��Ȃ���A���ӂɒ��݁A����̒��ňÎE�����T�p�^�̔������A�}�[�����E�u�����h�A�A���\�j�[�E�N�C���Ȃǂ̖��D�����̔M���ɂ���ĕ`���Ă䂫�܂��B

���L�V�R�v���́A�t�����X�v���Ȃǂ������ł���悤�ɗl�X�Ȑ��͂��䓪���Đ����������Ă䂫�܂��B
�f�B�A�X�哝�̂̈����ƁA�f�B�A�X�ƑΗ�����t�����V�X�R�E�}�f���̃A�����J�ւ̖S���B�v���̗����҂ł��������}�f���ƃT�p�^�̊m���B�܂��A�哝�̂ƂȂ����}�f�����E���A���͂��L���锽�v���̊���r�N�g���A�[�m�E�E�G���^���R�B
�E�G���^������œ|���邽�߂Ɏ������ꂽ�l�X�Ȋv���R�ƁA���̏W���̂ł���쌛�v���R�B
�쌛�v���R�k���t�c�𗦂���t�����V�X�R�E���B����(�p���`���E���B����)�B
�쌛�v���R�̎w���I����ł���A��Ƀ��B������T�p�^�ƑΗ����邱�ƂɂȂ�x�k�X�e�B�A�[�m�E�J�����T�B
�������A�f��u�v�����T�p�^�v�̓��L�V�R�v�����ڂ����m��Ȃ��Ă�������Ղ����e�ɂȂ��Ă��܂��B
�r�{��S�������̂��m�[�x�����w�܍�ƃW�����E�X�^�C���x�b�N�B
�u�{��̕����v�u��\���l�Ɛl�ԁv�u�G�f���̓��v�ȂǁA�l�Ԃ̓��ʂɐ[�����ݍ��앗�́u�v�����T�p�^�v�ł��\���ɔ�������Ă��āA�n�����Ɖh���A���Ɨ���A����邱�Ƃ̂Ȃ���������̔��R�Ƃ������A�X�^�C���x�b�N���̐��������Ƃ����l�ԃh���}���W�J����Ă����܂��B
����������
�ḗu�~�]�Ƃ������̓d�ԁv�̖����G���A�E�J�U���B
�J�U���Ƃ����ƁA�ǂ����Ă��n���E�b�h�̐Ԏ��ɂƂ��Ȃ������I�w�i����肴������Ă��܂��܂����A1998�N�ɍs��ꂽ�A�J�f�~�[�܂̎����ŁA�f��E�ɑ��钷�N�̌��J�Ƃ��āu���_�܁v���^����ꂽ�Ƃ��A�吨�̔���̒��ŁA�ꕔ����̓u�[�C���O���N���A�j�b�N�E�m���e�B�A�G�h�E�n���X�Ȃǂ͜�R�Ƃ����\��̂܂܁A�\������J�U�������߂Ă����̂��ƂĂ���ۂɎc���Ă��܂��B
�����������Ƃ�����܂����A�u�v�����T�p�^�v���̂��̂͗D�ꂽ�f�悾�Ǝv���܂����A�}�[�����E�u�����h�͂������A�T�p�^�̌Z���[�t�F�~�I�������A�����j�D�܂���܂����A���\�j�[�E�N�C���̑e��ō����Ȗ����A�킢�����Ȃ��������邱�Ƃ̂Ȃ��s���̒n�ʂ���v���̈Ӌ`���������A��ł���T�p�^�Ƃ̊m���̉���h���Ȃ���E����Ă��܂��ߌ��̒j���[�t�F�~�I�́A�ł��l�Ԃ������l�Ԃ̓T�^�ł���A�u�v�����T�p�^�v�̒��ŋ���Ȉ�ۂ��c���܂����B

����Ȉ�ۂƂ������Ƃł́A���f�B�A�X�哝�̔h�̐��͂̒������������������A�Ō�ɂ̓T�p�^�𗠐��Ă��܂��t�F���i���h�E�A�M�[�����������W���Z�t�E���C�Y�}���B
�u007/�h�N�^�[�E�m�I�v(1962�N)�ł́A�����m�I���m�������ċ���Ȉ�ۂ��c���A�h�N�^�[�E�m�I�̃C���[�W��1973�N�́u�R����h���S���v�̈����~�X�^�[�E�n���ɂ��̂܂p����Ă��܂��B
�����A�f��Ƃ��Ă̓t�F���i���h�E�A�M�[���̐l�ԑ����C�}�C�`������Â炩�����̂���_�ł����A�I�Ղ̃T�p�^�ÎE�̏�ʂ́u�������ɖ����͂Ȃ��v(1968�N)�̃��X�g�ɂȂ���s��ȃV�[���ł����B
�������ߎS�Ȍ��ʂƂ��ďI���̂ł͂Ȃ��A�T�p�^�̈��n���R�֓���������A�p�Y�ƂȂ����T�p�^�����n�̈�ۂƂ��Đl�X�̋L���Ɏc�邱�Ƃ��Î��������X�g�͏G��ł����B
�NjL
�n�����_���o�g�ŕ��ӂƂ��ĕ`���ꂽ�G�~���A�[�m�E�T�p�^�ł����A���ۂɂ͗T���Ȕ_�ꏊ�L�҂̑��q�ŁA�u���W���A�I�G���[�g�ł��������悤�ł����瓖�R�Ȃ��當�ӂł͂Ȃ������͂��B
�n�������ӂƂ����̂́A�v���𐬂������錴���͉͂��w�ɐ�����_���K���ł��邱�Ƃ��������悤�Ƃ����̂��A�n�����_���̒����琶�܂ꂽ�p�Y�Ƃ��Đe���݂₷�����o�����Ƃ����̂��B
������ɂ��Ă��A���ӂł��邱�ƂŁA�_�̏�̉p�Y�Ƃ������́A���O���\����p�Y�Ƃ��čD�������Ă��̂͂������ł��B

�y���̃J�e�S���[�̍ŐV�L���z
2019�N06��08��
�f��u�����F�i���g: �h���肵�ҁv���Q����͉̂䂩�_��
�u�����F�i���g: �h���肵�ҁv(The Revenant)�@
�@2015�N�A�����J
�ēA���n���h���E�S���U���X�E�C�j�����g�D
����}�C�P���E�p���N
�r�{�}�[�N�EL�E�X�~�X�@
�@�A���n���h���E�S���U���X�E�C�j�����g�D
�B�e�G�}�j���G���E���x�c�L
�q�L���X�g�r
�@���I�i���h�E�f�B�J�v���I�@�g���E�n�[�f�B
��88��A�J�f�~�[�܊ē�/�剉�j�D��(���I�i���h�E�f�B�J�v���I)
�B�e���
19���I�����A�A�����J�J��̖k�����B
���A�҂̔��l�Ɛ�Z���������Ƃ̊Ԃɕ����̐₦�Ȃ���������A�Ɋ��n�т��ړ����Ȃ����𑱂���є�n���^�[�̈�c�����܂����B
�n���^�[�̈�l�ŁA���q�̃z�[�N(�t�H���X�g�E�O�b�h���b�N)�Ƌ��Ɉ�c�ɉ�����Ă����q���[�E�O���X(���I�i���h�E�f�B�J�v���I)�́A��̏e�����t������Z���̏P���ɑ����A�����̋]���҂��o���Ȃ���A�c�菭�Ȃ��Ȃ����n���^�[�̈�c�Ƌ��ɖ����炪��D�œ����L�т܂��B


�w�����[(�h�[�i���E�O���[�\��)������Ƃ����s�́A���Ԃ̂��鋏�Z����������Ƃ���̂ł����A�s����͌������R�x�n�сB
���H���Ƃ邩�A�D�Ő�����邩�Ń����邱�ƂɂȂ�܂����A�K�C�h�Ƃ��Ă̒m���ƌo���̖L�x�ȃO���X�̈ӌ��ɏ]���A�D�͊댯���Ƃ������ƂŁA���H���Ƃ邱�ƂɂȂ�܂��B
�擪�ɗ����A�����������Ă����O���X�͎q�F�Ƒ����B
�q�F�̋߂��ɂ͐e�F��������́B�A�b�Ǝv���Ԃ��Ȃ��O���X�͐e�F�̏P�����܂��B
����͌F�̒��ł��ł��������r���Ƃ����O���Y���[(�D�F�F�A�q�O�}�̈���)�ł����B
���X�ȃO���Y���[�̏P�������O���X�́A�����������A���̍���܂��A�����Ă���̂��s�v�c�Ȃقǂ̏d�����܂��B

�m���̑̂�S����Ȃ���O���X�ƈ�s�͎R���z���悤�Ƃ��܂����A�厩�R�̓�H�ŁA���łɃO���X�͈�s�̑���܂Ƃ��ƂȂ��Ă��܂��Ă���A�ő��O���X�̎��͔������Ȃ��Ƃ݂������w�����[�̒�Ăɂ���āA�O���X�̎����Ŏ��悤�t�B�b�c�W�F�����h(�g���E�n�[�f�B)�ɖ����A�t�B�b�c�W�F�����h�ƃO���X�̑��q�z�[�N�ƔN�Ⴂ�W��(�E�B���E�|�[���^�[)�̎O�l���c���A�O���X�̎������͂��������ŋA�҂���悤�����܂��B
���˂Ă���O���X�ɓG�ӂ�����Ă����t�B�b�c�W�F�����h�́A�����������ق����є珤��̕����O������A�z�[�N���E���A�O���X��u������ɂ��ăW���ƂƂ��ɂ��̏�𗧂�����܂��B
�ڂ̑O�ő��q�̃z�[�N���E����A�ЂƂ�u������ɂ��ꂽ�O���X�̓t�B�b�c�W�F�����h�ւ̕��Q�̋S�Ɖ����A�Ս��ȑ厩�R�̒��A�m���̑̂ł̃T�o�C�o�����n�܂�A�t�B�b�c�W�F�����h�Ƃ̎����ւƕ���͓W�J����Ă䂫�܂��B

�����܂ł��l�I�Ȋ��z
�����ȂƂ���A�l�I�ɂ͎^�ۗ��_�̍��݂���f��ł��B
�܂��A�J��������Ɉړ����Ă��邽�߂ɗ����������Ȃ��A�������L�p�����Y�𑽗p���Ă�������Ă��邩��A�ƂĂ����邳�������܂��B
�X�g�[���[���̂̓V���v���ȕ��Q���ł���Ȃ���A�Ƃ���ǂ���}�������@���ρA�є�̎�◐�l�ɂ�������j�I�w�i�A�܂��A�O���X�Ɛ�Z���ł���ނ̍ȂƂ̊W�Ȃǂ��f��S�̂��|�p�I�v�f�̒��ɗn�������܂�Ă��邽�߁A���鑤�ɑi����Ƃ������͊ē̓Ƃ�悪��Ȉ�ۂ��܂����B


�������A�����������}�C�i�X�̈�ۂ����������ʁA�{����Nj����悤�Ƃ���ē̈Ӑ}�ƁA�o�ꂷ��o�D�����̔M���A���Ƀq���[�E�O���X�����������I�i���h�E�f�B�J�v���I�̖��ҍ��ɂ͍�����Ȃ����������܂����B
���I�i���h�E�f�B�J�v���I�́u�{�[�C�Y�E���C�t�v(1993�N)�̂��납��f���炵�����Z�͂̂���q�ǂ����Ǝv���Ă����̂ł����A�u�^�C�^�j�b�N�v(1997�N)�ň�C�ɃX�^�[�_���ɂ̂��オ���Ă��܂����̂��A�������Ă��̐l�ɂƂ��Ă͂悭�Ȃ����ʂɂȂ��Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B
�u���I�l�v�u���I�l�v�ƌĂ�n�߂ď��N���ۂ�������Ȃ��C���[�W���]�܂�Ă����悤�ł�����A��O���]�ރC���[�W��ۂ��Ă�����A���܂ł����N�̂悤�ȃf�B�J�v���I�͑听�ł��Ȃ����낤�Ȃ��A�Ǝv���Ă����̂��u�M�����O�E�I�u�E�j���[���[�N�v(2002�N)�u�L���b�`�E�~�[�E�C�t�E���[�E�L�����v(2002�N)�ŏ��X�ɕω��������n�߁A�u�A�r�G�C�^�[�v(2004�N)�u�f�B�p�[�e�b�h�v(2006�N)�u�u���b�h�E�_�C�������h�v(2006�N)�ő�l�̒j�ւƕϖe�𐋂����̂͂������B
�����A�u�����F�i���g�v�ł͐�����H���A���������ɂ�������V�[���́A�Ȃɂ������܂ł��Ȃ��Ă��A�Ƃ��v���܂������A�����܂ł��邱�Ƃɂ���ĉՍ��ȃT�o�C�o���̌������A��萶�X�����`����Ă����̂��������ł��B

�s�N�s�N�Ɠ����Ă��鐶��������H�ׂ�V�[���ł́A���ɕ������R���Ă������A�ł��Ԃ������Ȃ����Ǝv���܂������A�Ɋ��̒n���ł͂��̂܂ܐH�ׂ�K���ł��������̂��A���̂܂܂̂ق����h�{���͍����炵���ł�����B
���Ȃ݂Ɏ��͐������V���E�I�����̂܂ܐH�ׂ�u�V���E�I�̗x��H���v���o���������Ƃ�����܂����A���̒��ŃO�j���O�j�������C���������ɕ����āA��x����ł�߂����Ƃ�����܂��B
���I�i���h�E�f�B�J�v���I�A�債�������ł����A�{���u�����������āA���ߌ��ȕ����ւ����Ȃ����Ƒ����S�z�ɂȂ�܂��B
�l�I�ɂ͍�i�̎^�ۂ���������u�����F�i���g: �h���肵�ҁv�ł����A�厩�R�ɐ^����������g�͋����f��ł��邱�ƂɊԈႢ�͂Ȃ��A�J�����̓����߂������邳�����������Ƃ͏�q���܂������A���̃J�������Ƃ炦���厩�R�̕��i�������ł������̂������ł��B
�܂��A���̉f��̃e�[�}�ł�����̂��ȁA�Ǝv����A�l�Ԃ������邱�Ƃ̎��O�B�O���Y���[�ɑ̂��Y�^�Y�^�ɂ���Ď����̔������l�Ԃ��A�Ս��Ȏ��R�̒��ŁA�ǂ�����Đ������т邱�Ƃ��ł����̂��A�����̌֒��͂���ɂ���A���Q�Ƃ������O�����������Ȃ��A�������܂��ꂽ���̉��́A������Đ��ւ̊�Ղݏo�����Ƃ��ł�����̂ł���Ƃ������Ƃ��l��������ꂽ�f��ł����B





�@2015�N�A�����J
�ēA���n���h���E�S���U���X�E�C�j�����g�D
����}�C�P���E�p���N
�r�{�}�[�N�EL�E�X�~�X�@
�@�A���n���h���E�S���U���X�E�C�j�����g�D
�B�e�G�}�j���G���E���x�c�L
�q�L���X�g�r
�@���I�i���h�E�f�B�J�v���I�@�g���E�n�[�f�B
��88��A�J�f�~�[�܊ē�/�剉�j�D��(���I�i���h�E�f�B�J�v���I)
�B�e���
19���I�����A�A�����J�J��̖k�����B
���A�҂̔��l�Ɛ�Z���������Ƃ̊Ԃɕ����̐₦�Ȃ���������A�Ɋ��n�т��ړ����Ȃ����𑱂���є�n���^�[�̈�c�����܂����B
�n���^�[�̈�l�ŁA���q�̃z�[�N(�t�H���X�g�E�O�b�h���b�N)�Ƌ��Ɉ�c�ɉ�����Ă����q���[�E�O���X(���I�i���h�E�f�B�J�v���I)�́A��̏e�����t������Z���̏P���ɑ����A�����̋]���҂��o���Ȃ���A�c�菭�Ȃ��Ȃ����n���^�[�̈�c�Ƌ��ɖ����炪��D�œ����L�т܂��B
�w�����[(�h�[�i���E�O���[�\��)������Ƃ����s�́A���Ԃ̂��鋏�Z����������Ƃ���̂ł����A�s����͌������R�x�n�сB
���H���Ƃ邩�A�D�Ő�����邩�Ń����邱�ƂɂȂ�܂����A�K�C�h�Ƃ��Ă̒m���ƌo���̖L�x�ȃO���X�̈ӌ��ɏ]���A�D�͊댯���Ƃ������ƂŁA���H���Ƃ邱�ƂɂȂ�܂��B
�擪�ɗ����A�����������Ă����O���X�͎q�F�Ƒ����B
�q�F�̋߂��ɂ͐e�F��������́B�A�b�Ǝv���Ԃ��Ȃ��O���X�͐e�F�̏P�����܂��B
����͌F�̒��ł��ł��������r���Ƃ����O���Y���[(�D�F�F�A�q�O�}�̈���)�ł����B
���X�ȃO���Y���[�̏P�������O���X�́A�����������A���̍���܂��A�����Ă���̂��s�v�c�Ȃقǂ̏d�����܂��B

�m���̑̂�S����Ȃ���O���X�ƈ�s�͎R���z���悤�Ƃ��܂����A�厩�R�̓�H�ŁA���łɃO���X�͈�s�̑���܂Ƃ��ƂȂ��Ă��܂��Ă���A�ő��O���X�̎��͔������Ȃ��Ƃ݂������w�����[�̒�Ăɂ���āA�O���X�̎����Ŏ��悤�t�B�b�c�W�F�����h(�g���E�n�[�f�B)�ɖ����A�t�B�b�c�W�F�����h�ƃO���X�̑��q�z�[�N�ƔN�Ⴂ�W��(�E�B���E�|�[���^�[)�̎O�l���c���A�O���X�̎������͂��������ŋA�҂���悤�����܂��B
���˂Ă���O���X�ɓG�ӂ�����Ă����t�B�b�c�W�F�����h�́A�����������ق����є珤��̕����O������A�z�[�N���E���A�O���X��u������ɂ��ăW���ƂƂ��ɂ��̏�𗧂�����܂��B
�ڂ̑O�ő��q�̃z�[�N���E����A�ЂƂ�u������ɂ��ꂽ�O���X�̓t�B�b�c�W�F�����h�ւ̕��Q�̋S�Ɖ����A�Ս��ȑ厩�R�̒��A�m���̑̂ł̃T�o�C�o�����n�܂�A�t�B�b�c�W�F�����h�Ƃ̎����ւƕ���͓W�J����Ă䂫�܂��B

�����܂ł��l�I�Ȋ��z
�����ȂƂ���A�l�I�ɂ͎^�ۗ��_�̍��݂���f��ł��B
�܂��A�J��������Ɉړ����Ă��邽�߂ɗ����������Ȃ��A�������L�p�����Y�𑽗p���Ă�������Ă��邩��A�ƂĂ����邳�������܂��B
�X�g�[���[���̂̓V���v���ȕ��Q���ł���Ȃ���A�Ƃ���ǂ���}�������@���ρA�є�̎�◐�l�ɂ�������j�I�w�i�A�܂��A�O���X�Ɛ�Z���ł���ނ̍ȂƂ̊W�Ȃǂ��f��S�̂��|�p�I�v�f�̒��ɗn�������܂�Ă��邽�߁A���鑤�ɑi����Ƃ������͊ē̓Ƃ�悪��Ȉ�ۂ��܂����B
�������A�����������}�C�i�X�̈�ۂ����������ʁA�{����Nj����悤�Ƃ���ē̈Ӑ}�ƁA�o�ꂷ��o�D�����̔M���A���Ƀq���[�E�O���X�����������I�i���h�E�f�B�J�v���I�̖��ҍ��ɂ͍�����Ȃ����������܂����B
���I�i���h�E�f�B�J�v���I�́u�{�[�C�Y�E���C�t�v(1993�N)�̂��납��f���炵�����Z�͂̂���q�ǂ����Ǝv���Ă����̂ł����A�u�^�C�^�j�b�N�v(1997�N)�ň�C�ɃX�^�[�_���ɂ̂��オ���Ă��܂����̂��A�������Ă��̐l�ɂƂ��Ă͂悭�Ȃ����ʂɂȂ��Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B
�u���I�l�v�u���I�l�v�ƌĂ�n�߂ď��N���ۂ�������Ȃ��C���[�W���]�܂�Ă����悤�ł�����A��O���]�ރC���[�W��ۂ��Ă�����A���܂ł����N�̂悤�ȃf�B�J�v���I�͑听�ł��Ȃ����낤�Ȃ��A�Ǝv���Ă����̂��u�M�����O�E�I�u�E�j���[���[�N�v(2002�N)�u�L���b�`�E�~�[�E�C�t�E���[�E�L�����v(2002�N)�ŏ��X�ɕω��������n�߁A�u�A�r�G�C�^�[�v(2004�N)�u�f�B�p�[�e�b�h�v(2006�N)�u�u���b�h�E�_�C�������h�v(2006�N)�ő�l�̒j�ւƕϖe�𐋂����̂͂������B
�����A�u�����F�i���g�v�ł͐�����H���A���������ɂ�������V�[���́A�Ȃɂ������܂ł��Ȃ��Ă��A�Ƃ��v���܂������A�����܂ł��邱�Ƃɂ���ĉՍ��ȃT�o�C�o���̌������A��萶�X�����`����Ă����̂��������ł��B

�s�N�s�N�Ɠ����Ă��鐶��������H�ׂ�V�[���ł́A���ɕ������R���Ă������A�ł��Ԃ������Ȃ����Ǝv���܂������A�Ɋ��̒n���ł͂��̂܂ܐH�ׂ�K���ł��������̂��A���̂܂܂̂ق����h�{���͍����炵���ł�����B
���Ȃ݂Ɏ��͐������V���E�I�����̂܂ܐH�ׂ�u�V���E�I�̗x��H���v���o���������Ƃ�����܂����A���̒��ŃO�j���O�j�������C���������ɕ����āA��x����ł�߂����Ƃ�����܂��B
���I�i���h�E�f�B�J�v���I�A�債�������ł����A�{���u�����������āA���ߌ��ȕ����ւ����Ȃ����Ƒ����S�z�ɂȂ�܂��B
�l�I�ɂ͍�i�̎^�ۂ���������u�����F�i���g: �h���肵�ҁv�ł����A�厩�R�ɐ^����������g�͋����f��ł��邱�ƂɊԈႢ�͂Ȃ��A�J�����̓����߂������邳�����������Ƃ͏�q���܂������A���̃J�������Ƃ炦���厩�R�̕��i�������ł������̂������ł��B
�܂��A���̉f��̃e�[�}�ł�����̂��ȁA�Ǝv����A�l�Ԃ������邱�Ƃ̎��O�B�O���Y���[�ɑ̂��Y�^�Y�^�ɂ���Ď����̔������l�Ԃ��A�Ս��Ȏ��R�̒��ŁA�ǂ�����Đ������т邱�Ƃ��ł����̂��A�����̌֒��͂���ɂ���A���Q�Ƃ������O�����������Ȃ��A�������܂��ꂽ���̉��́A������Đ��ւ̊�Ղݏo�����Ƃ��ł�����̂ł���Ƃ������Ƃ��l��������ꂽ�f��ł����B

2019�N06��05��
�f��u����Γ~�̂����߁v�NJ��ւ̔��R
�u����Γ~�̂����߁v(The Last Detail)�@
�@1973�N�A�����J
�ēn���E�A�V���r�[
�r�{���o�[�g�E�^�E��
����_�����E�|�j�N�T��
�B�e�}�C�P���E�`���b�v�}��
�q�L���X�g�r
�@�W���b�N�E�j�R���\���@�����f�B�E�N�G�C�h
�@�I�[�e�B�X�E�����O�@�L�������E�P�C��
�J���k���ۉf��Վ剉�j�D���(�W���b�N�E�j�R���\��)
1969�N�́u�C�[�W�[�E���C�_�[�v�œ��p���������W���b�N�E�j�R���\�����u�t�@�C�u�E�C�[�W�[�E�s�[�Z�X�v(1970�N)�u���̎�l�v(1971�N)�Ȃǂ��o�ăJ���k���ۉf��ՂŎ剉�j�D�܂��ˎ~�߂��A�����J���E�j���[�V�l�}�̏G��B

�A�����J�����o�[�W�j�A�B�A���E�ő���ւ�m�[�t�H�[�N�C�R��n�B
�C�R���m���o�_�X�L�[�i�W���b�N�E�j�R���\���j�ƃ}���z�[���i�I�[�e�B�X�E�����O�j�̓�l�ɁA�߂�Ƃ����V�����|�[�c�}�X�C�R�Y�����Ɍ쑗����C��������܂��B
�쑗�̔C���Ȃǃ����C�̂Ȃ������o�_�X�L�[�ł������A�쑗���Ԉ�T�ԕ��̓������x�������Ƃ������ƂŁA�T�b�T�ƌ쑗�����܂��Ďc��̓�����V�тɎg�����Ɗ��l�́A�ӋC�g�X�ƌ쑗�C���ɂ�����܂��B


�쑗�����V����8�N�̌Y���������n���ꂽ�����N�̃��h�E�Y(�����f�B�E�N�G�C�h)�B
�啿�ȑ̊i�Ɏ����킸�C�̎セ���ȃ��h�E�Y�́A��n�ɐݒu����Ă���������̒�����40�h���𓐂��߂�8�N�̌Y�����|�[�c�}�X�C�R�Y�����ő��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B
�u�ł��{���͓��Ⴂ�Ȃ��v���h�E�Y�͌����܂��B�u�������Ƃ��������Ȃv
�u�c�����8�N���v�o�_�X�L�[�͈��R�Ƃ��܂��B
���h�E�Y�����t���悤�Ƃ���������́A���P�Ƃł���i�ߊ��v�l���ݒu�������̂ŁA���̂��߂ɂ��Ƃ���ƍ߂Ƃ��Ă̏d�含��тт��Ƃ������܂����A�킸��40�h���̂��߂ɋM�d�ȐN�����Y�����ő���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ������h�E�Y�Ƀo�_�X�L�[�͓�����o���܂��B
���h�E�Y�ւ̈���݂ƁA�R���Ƃ����g�D�ւ̕��肪�o�_�X�L�[�̒��ōL����A�|�[�c�}�X�������O�ɓr�����Ԃ����āA�N���̊y���݂�l�������h�E�Y�ɋ����悤�Ƃ��܂��B
�C�̎ア���h�E�Y�ɁA�����̎咣��ʂ����鋭���������悤�ƁA���X�g�����ł͒����Ƃ͈�����H�����o���ꂽ���h�E�Y�ɁA������ς�������A�Ɣ�������A����ł́A�����N�ɂ͎��͏o���Ȃ��ƌ����o�[�e���_�[�Ɋ낤���e�Ŕ������悤�Ƃ�����B
����ȃo�_�X�L�[�ɐU��ꂽ�`�̃}���z�[���́A
�u�啨�Ԃ��!�v�ƃo�_�X�L�[�Ɉꊅ�B
�V�����ƂȂ����o�_�X�L�[�ł������A���̌���O�l�ŁA����m��Ȃ����h�E�Y�̂��߂ɔ��t�w(�L�������E�P�C��)�𐢘b������A�z�e���Ő����Ԃꂽ��A�C����������ɃP���J��������A�^�~�̃j���[���[�N��{�X�g���ł��낢��ȑ̌������Ȃ���|�[�c�}�X�ւ̗��𑱂��܂��B


�c�菭�Ȃ��Ȃ������Ԃ��̕��������Ńo�[�x�L���[���n�߂�O�l�B
�������E���āA�j���[���[�N�̓��@���@(�ɂ���傤���イ)�̉��Ŋo�����u�얳���@�@�،o�v(�i���~���E�z�[�����Q�L���[)�̑�ڂ������Ȃ��異����܂�A���̏�𗧂����낤�Ƃ��郁�h�E�Y�B
���h�E�Y�̓����ɋC�Â����o�_�X�L�[�ƃ}���z�[���́A����Ƃ̂��ƂŃ��h�E�Y����艟�����A�|�[�c�}�X�C�R�Y�����փ��h�E�Y�������n���܂��B
�쑗�̔C�����I�����o�_�X�L�[�ƃ}���z�[���ɂ́A�������h�E�Y�̂��Ƃ͓��ɂȂ��A��������n�܂�C�R�̐������҂��Ă���̂ł��B

����������
60�N��̌㔼����n�܂����A�����J���E�j���[�V�l�}�̗���́A�u�������ɖ����͂Ȃ��v(1967�N)�u���Ɓv(1967�N)�u�C�[�W�[�E���C�_�[�v(1969�N)�u�����Ɍ������Č���!�v(1969�N)�Ȃǖ���⌆��𐔑����c���܂����B
�������������ŁA�ǂ��炩�Ƃ����Βn���ȃ��[�h���[�r�[�̈�ۂ����������߂��u����Γ~�̂����߁v�͕��݂��錆��Q�ɔ䂵�Ĉ�����֑ނ��Ă��銴������܂����B
�Ȃ������I�Ɏn�܂����x�g�i���푈���D�������ăA�����J�����Ŕ���^�������܂������Ƃ�w�i�ɁA����܂ł͖���`�A�͋�������邱�Ƃ̑��������A�����J�f��́A�̐��ւ̔��R�A�g�����̎��Ȃ����킩��̓����A���C�͂Ȏ�҂ȂǁA�l�Ԑ���Љ�̕��̑��ʂ�Nj������f�悪�嗬�ƂȂ��Ă����܂��B
�u����Γ~�̂����߁v�ɂ������������A�������Ă��ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����킪�`����A����́A���h�E�Y�̐H����A����ł̂����Ɍ�����o�_�X�L�[�̔��R�S剝���o���̑ԓx�ȂǁA�ς��悤�Ƃ��Ă��ς��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��g�D�̐��ւ̕s���������o�������R�ł���A�コ���狭���ւ̕ϖe�𐋂������̂悤�Ɍ��������h�E�Y�����ǂ͌Y��������ƂȂ��Ă��܂����͊��ƕNJ����f��̃N���C�}�b�N�X���܂��B
�������A�u����Γ~�̂����߁v�ɂ́A��肫��Ȃ������Ƃ������́A�ނ���u�₩�Ȍ㖡���c��̂́A�������Ȃ��������t���R���悤�Ƃ����҂̎p���A�����̋������ĂԂ��߂��Ǝv���܂��B

�܂��A�NJ��̒��Ő����Ă䂭�����Ȃ�������������Ă��܂����Ƃ��邩�̂悤�ȃ��X�g�V�[���́A���s�I�Ȃق�ꂳ�Ɠ����ɍ��Ɩh�q�̔C�ɓ����邳���₩�Ȍւ�̂悤�Ȃ��̂��_�Ԍ������C�����܂����B
�e��ł͂��邪��Ɍ�����ʂ��������o�_�X�L�[�B�����I�ŏ펯�Ƃ̃}���z�[���B�̂����͐l��{�傫�����ɋC�̏��������h�E�Y�B
�O�ҎO�l�̌����������h�^�o�^�������I�ȃ��[�h���[�r�[�ł���Ȃ���A�����}�C�P���E�`���b�v�}�����B�e�ēɓ����������V���g���A�j���[���[�N�A�{�X�g�����ꂼ��̐^�~�̕��i�͉f��ɕ���̉A�e�Ɖ��s����^���Ă��܂��B
����́uThe Last Detail�v�B���̂܂ܖg�Ō�̏ڍׁh�ł����ADetail�ɂ͌R���p��Łg�������h�̈Ӗ�������炵���A�f��ł́g�C���h�Ɩ�Ă����悤�ł��B
�u����Γ~�̂����߁v�Ƃ����M��͂悭�o���Ă���Ǝv���܂��B
�ǂ����炩���߂̃C���[�W���o���̂��A�o�_�X�L�[�����O�l���������𒅂Ă��邱�Ƃ���u�����߂̐�������v�̃C���[�W�ɂȂ������̂��A�����̓��`���[�h�E�o�b�N�́u�����߂̃W���i�T���v�����E�I�x�X�g�Z���[�ɂȂ������Ƃ���̘A�z�Ȃ̂��A����͂Ƃ������A�u����Γ~�̂����߁v�Ƃ����M��ɂ͍��荂�����w�I�ȃC���[�W���L����܂��B





�@1973�N�A�����J
�ēn���E�A�V���r�[
�r�{���o�[�g�E�^�E��
����_�����E�|�j�N�T��
�B�e�}�C�P���E�`���b�v�}��
�q�L���X�g�r
�@�W���b�N�E�j�R���\���@�����f�B�E�N�G�C�h
�@�I�[�e�B�X�E�����O�@�L�������E�P�C��
�J���k���ۉf��Վ剉�j�D���(�W���b�N�E�j�R���\��)
1969�N�́u�C�[�W�[�E���C�_�[�v�œ��p���������W���b�N�E�j�R���\�����u�t�@�C�u�E�C�[�W�[�E�s�[�Z�X�v(1970�N)�u���̎�l�v(1971�N)�Ȃǂ��o�ăJ���k���ۉf��ՂŎ剉�j�D�܂��ˎ~�߂��A�����J���E�j���[�V�l�}�̏G��B

�A�����J�����o�[�W�j�A�B�A���E�ő���ւ�m�[�t�H�[�N�C�R��n�B
�C�R���m���o�_�X�L�[�i�W���b�N�E�j�R���\���j�ƃ}���z�[���i�I�[�e�B�X�E�����O�j�̓�l�ɁA�߂�Ƃ����V�����|�[�c�}�X�C�R�Y�����Ɍ쑗����C��������܂��B
�쑗�̔C���Ȃǃ����C�̂Ȃ������o�_�X�L�[�ł������A�쑗���Ԉ�T�ԕ��̓������x�������Ƃ������ƂŁA�T�b�T�ƌ쑗�����܂��Ďc��̓�����V�тɎg�����Ɗ��l�́A�ӋC�g�X�ƌ쑗�C���ɂ�����܂��B
�쑗�����V����8�N�̌Y���������n���ꂽ�����N�̃��h�E�Y(�����f�B�E�N�G�C�h)�B
�啿�ȑ̊i�Ɏ����킸�C�̎セ���ȃ��h�E�Y�́A��n�ɐݒu����Ă���������̒�����40�h���𓐂��߂�8�N�̌Y�����|�[�c�}�X�C�R�Y�����ő��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B
�u�ł��{���͓��Ⴂ�Ȃ��v���h�E�Y�͌����܂��B�u�������Ƃ��������Ȃv
�u�c�����8�N���v�o�_�X�L�[�͈��R�Ƃ��܂��B
���h�E�Y�����t���悤�Ƃ���������́A���P�Ƃł���i�ߊ��v�l���ݒu�������̂ŁA���̂��߂ɂ��Ƃ���ƍ߂Ƃ��Ă̏d�含��тт��Ƃ������܂����A�킸��40�h���̂��߂ɋM�d�ȐN�����Y�����ő���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ������h�E�Y�Ƀo�_�X�L�[�͓�����o���܂��B
���h�E�Y�ւ̈���݂ƁA�R���Ƃ����g�D�ւ̕��肪�o�_�X�L�[�̒��ōL����A�|�[�c�}�X�������O�ɓr�����Ԃ����āA�N���̊y���݂�l�������h�E�Y�ɋ����悤�Ƃ��܂��B
�C�̎ア���h�E�Y�ɁA�����̎咣��ʂ����鋭���������悤�ƁA���X�g�����ł͒����Ƃ͈�����H�����o���ꂽ���h�E�Y�ɁA������ς�������A�Ɣ�������A����ł́A�����N�ɂ͎��͏o���Ȃ��ƌ����o�[�e���_�[�Ɋ낤���e�Ŕ������悤�Ƃ�����B
����ȃo�_�X�L�[�ɐU��ꂽ�`�̃}���z�[���́A
�u�啨�Ԃ��!�v�ƃo�_�X�L�[�Ɉꊅ�B
�V�����ƂȂ����o�_�X�L�[�ł������A���̌���O�l�ŁA����m��Ȃ����h�E�Y�̂��߂ɔ��t�w(�L�������E�P�C��)�𐢘b������A�z�e���Ő����Ԃꂽ��A�C����������ɃP���J��������A�^�~�̃j���[���[�N��{�X�g���ł��낢��ȑ̌������Ȃ���|�[�c�}�X�ւ̗��𑱂��܂��B
�c�菭�Ȃ��Ȃ������Ԃ��̕��������Ńo�[�x�L���[���n�߂�O�l�B
�������E���āA�j���[���[�N�̓��@���@(�ɂ���傤���イ)�̉��Ŋo�����u�얳���@�@�،o�v(�i���~���E�z�[�����Q�L���[)�̑�ڂ������Ȃ��異����܂�A���̏�𗧂����낤�Ƃ��郁�h�E�Y�B
���h�E�Y�̓����ɋC�Â����o�_�X�L�[�ƃ}���z�[���́A����Ƃ̂��ƂŃ��h�E�Y����艟�����A�|�[�c�}�X�C�R�Y�����փ��h�E�Y�������n���܂��B
�쑗�̔C�����I�����o�_�X�L�[�ƃ}���z�[���ɂ́A�������h�E�Y�̂��Ƃ͓��ɂȂ��A��������n�܂�C�R�̐������҂��Ă���̂ł��B

����������
60�N��̌㔼����n�܂����A�����J���E�j���[�V�l�}�̗���́A�u�������ɖ����͂Ȃ��v(1967�N)�u���Ɓv(1967�N)�u�C�[�W�[�E���C�_�[�v(1969�N)�u�����Ɍ������Č���!�v(1969�N)�Ȃǖ���⌆��𐔑����c���܂����B
�������������ŁA�ǂ��炩�Ƃ����Βn���ȃ��[�h���[�r�[�̈�ۂ����������߂��u����Γ~�̂����߁v�͕��݂��錆��Q�ɔ䂵�Ĉ�����֑ނ��Ă��銴������܂����B
�Ȃ������I�Ɏn�܂����x�g�i���푈���D�������ăA�����J�����Ŕ���^�������܂������Ƃ�w�i�ɁA����܂ł͖���`�A�͋�������邱�Ƃ̑��������A�����J�f��́A�̐��ւ̔��R�A�g�����̎��Ȃ����킩��̓����A���C�͂Ȏ�҂ȂǁA�l�Ԑ���Љ�̕��̑��ʂ�Nj������f�悪�嗬�ƂȂ��Ă����܂��B
�u����Γ~�̂����߁v�ɂ������������A�������Ă��ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����킪�`����A����́A���h�E�Y�̐H����A����ł̂����Ɍ�����o�_�X�L�[�̔��R�S剝���o���̑ԓx�ȂǁA�ς��悤�Ƃ��Ă��ς��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��g�D�̐��ւ̕s���������o�������R�ł���A�コ���狭���ւ̕ϖe�𐋂������̂悤�Ɍ��������h�E�Y�����ǂ͌Y��������ƂȂ��Ă��܂����͊��ƕNJ����f��̃N���C�}�b�N�X���܂��B
�������A�u����Γ~�̂����߁v�ɂ́A��肫��Ȃ������Ƃ������́A�ނ���u�₩�Ȍ㖡���c��̂́A�������Ȃ��������t���R���悤�Ƃ����҂̎p���A�����̋������ĂԂ��߂��Ǝv���܂��B

�܂��A�NJ��̒��Ő����Ă䂭�����Ȃ�������������Ă��܂����Ƃ��邩�̂悤�ȃ��X�g�V�[���́A���s�I�Ȃق�ꂳ�Ɠ����ɍ��Ɩh�q�̔C�ɓ����邳���₩�Ȍւ�̂悤�Ȃ��̂��_�Ԍ������C�����܂����B
�e��ł͂��邪��Ɍ�����ʂ��������o�_�X�L�[�B�����I�ŏ펯�Ƃ̃}���z�[���B�̂����͐l��{�傫�����ɋC�̏��������h�E�Y�B
�O�ҎO�l�̌����������h�^�o�^�������I�ȃ��[�h���[�r�[�ł���Ȃ���A�����}�C�P���E�`���b�v�}�����B�e�ēɓ����������V���g���A�j���[���[�N�A�{�X�g�����ꂼ��̐^�~�̕��i�͉f��ɕ���̉A�e�Ɖ��s����^���Ă��܂��B
����́uThe Last Detail�v�B���̂܂ܖg�Ō�̏ڍׁh�ł����ADetail�ɂ͌R���p��Łg�������h�̈Ӗ�������炵���A�f��ł́g�C���h�Ɩ�Ă����悤�ł��B
�u����Γ~�̂����߁v�Ƃ����M��͂悭�o���Ă���Ǝv���܂��B
�ǂ����炩���߂̃C���[�W���o���̂��A�o�_�X�L�[�����O�l���������𒅂Ă��邱�Ƃ���u�����߂̐�������v�̃C���[�W�ɂȂ������̂��A�����̓��`���[�h�E�o�b�N�́u�����߂̃W���i�T���v�����E�I�x�X�g�Z���[�ɂȂ������Ƃ���̘A�z�Ȃ̂��A����͂Ƃ������A�u����Γ~�̂����߁v�Ƃ����M��ɂ͍��荂�����w�I�ȃC���[�W���L����܂��B

2019�N05��14��
�f��u�~�b�h�i�C�g�E�G�N�X�v���X�v�o���S������]�Ƌ��C�̐��E
�u�~�b�h�i�C�g�E�G�N�X�v���X�v
�@(Midnight Express)�@1978�N�A�����J
�ēA�����E�p�[�J�[
�r�{�I�����@�[�E�X�g�[��
����r���[�E�w�C�Y
���y�W�����W�I�E�����_�[
�B�e�}�C�P���E�Z���V��
�q�L���X�g�r
�@�u���b�h�E�f�C�r�X�@�A�C���[���E�~���N���@
�@�W�����E�n�[�g�@�����f�B�E�N�G�C�h
�A�J�f�~�[��/�r�F�܃I�����@�[�E�X�g�[���@��ȏ��
�S�[���f���O���[�u��/��i��/�����j�D�܃W�����E�n�[�g

�`����Ă����͍̂��Ƃƌl�B�����ǂ����ڂ������ƂƂ�������ȏW���̂̒��ł͌l�̗͂͂��܂�ɂ��������A��͂ł����Ȃ��B
���l�̃X�[�U��(�A�C���[���E�~���N��)�Ɠ�l�Ńg���R�֊ό����s�ɏo�������A�����J�N�r���[(�u���b�h�E�f�C�r�X)�B
�A���ɂ������āA�r���[�̓n�V�V(����̈��)���A������Ȃ��������A�Ƃ������y���C�����Ŗ{���֎����������Ƃ��܂��B
�r���[�̕��Ɋ����t����ꂽ�n�V�V�͐Ŋւ�ʂ蔲���A�����Ƃ��Ȃ�����̂܂܋�`�����ї����Đ��������̂ł��傤���A���������̃g���R�ł̓e�����������A��s��͂��̂��̂����x���̐����~����A��s�@�ɓ��悷��҂̓{�f�B�`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�܂���B
���Ǝ����Ƃ����܂����A�n�V�V�͔�������ăr���[�͑ߕ߂���A�X�[�U�������͓����������ċA�����܂��B

�r���[�͌Y��������ƂȂ�̂ł����A���͂�������ŁA����1970�N�A�r���[�̖{���A�����J�̓��`���[�h�E�j�N�\���������B
�g���R�Ƃ̍����𐳏퉻���Ă��Ȃ��A�����J�ɂ͔Ɛl�����n����Ⴊ�Ȃ��A�r���[�̓g���R�̖@���ɂ���ċ�4�N�̌Y���������n����܂��B
�Ȋ��̌Y�����̒��Ńr���[�͖͔͎��Ƃ���3�N��ς��A�悤�₭�ߕ��̓����߂Â����Ǝv�����̂����̊ԁA����o�ł𐭍�Ƃ��Čf����g���R���{�́A�O���l�ɑ��Č����������ŗՂޕ��j�ɐ�ւ��A�r���[�͂��̌������߂̂��ߍٔ��̂�蒼���ɂȂ�A30�N�̌Y���ɉ����B����ɏI�g�Y�ւƉ�������܂��B
�\�͂Ɛ�]�̒��Ŕp�l���l�ƂȂ����r���[�Ɏc���ꂽ�Ō�̎�i�́u�[����}(�~�b�h�i�C�g�E�G�N�X�v���X)���E���v�ɏ�邱�Ƃ����ł����B

�}�����ꂽ��
����҃r���[�E�w�C�Y�̎��̌�����ɂ������̉f��́A�u�G���[���E�n�[�g�v�u�~�V�V�b�s�[�E�o�[�j���O�v�Ȃǂ̋S�˃A�����E�p�[�J�[�̎���������C�����ΎG�����ӂ�鐶���̔M�C�ɖ����A���ɁA�g���R���{����R�c���������Ƃ�����A���L����Y���Ă������Ȗ����̂������ς̂悤�ȊX���݂̕`�ʂ́A��l���r���[�̈��������̂܂܌������������̂悤�ȃJ�I�X�̐��E��`���o���Ă��܂��B


������Ƃ����o���S�ŋ�4�N�̎��Y����n���ɂȂ��Ă��܂��|���A���t�̒ʂ��Ȃ��O���ł̍ٔ��Ƃ䂪�i�@���x�A����ɂ͌l�̐l���͖�������A���Ƃ̐���̒��ňÍ��̐l���ɗ������ސ�]���ƌY�������ɖ�������\�͂̓r���[��p�l���l�ɂ��Ă��܂��̂ł����A���̒��ŁA�l�ԂƂ��Ă̂ЂƂ̖����`����Ă��܂��B
����́A�}�����ꂽ���̖��ł��B
����������
���{�̘b�ŁA��������O����������ゾ�������ɋ��Y�}�̊����������ƂƂ��đߕ߂���A�������Ԃ��S�u���̒��ŕ�炵�āA���̌�ߕ����ꂽ�ނ́A�����̘b�������w�Ŋw������ɍu�������������ł��B�r���A��l�̊w��������Ȏ�������܂����B
�u���̂悤�Ȓ��ŁA���I�ȗ~���ɂ��Ă͂ǂ̂悤�ɏ�������Ă����̂ł����v
��������ނ͒��ق��A���肰�Ȃ��b���]�����Ƃ������Ƃł��B
�l�ԂɂƂ��Đ��I�ȗ~�]�͐؎��Ȗ��ł��B
���ƂɌY�����Ȃǂɂ�����O�E����u�₳�ꂽ���E�ł́A����͌����ɕ\���Ǝv���܂��B
�u�A���r�A�̃������X�v��u�X�P�A�N���E�v�Ȃǂł��`���b�ƕ`����Ă��܂����A�l�X�ȉf��ł͋����{�ʂ̕`�����ł͂����Ă��A���グ���邱�Ƃ͑����悤�Ɏv���܂��B


�u�~�b�h�i�C�g�E�G�N�X�v���X�v�̌㔼�B
�p�l���l�ɂȂ����r���[�̌��ɗ��l�̃X�[�U�����ʉ�ɂ���ė��܂��B
�K���X�z���̉�b�B
����ȕ\��Ńr���[�̓X�[�U���ɕ���E���ł����悤���݂܂��B
�˘f���Ȃ�����X�[�U���͑O���J���A�`�̂������[���r���[�̖ڂ̑O�ɁB
�r���[�̓X�[�U���̋��ɐG��悤�Ƃ��܂����A�K���X�z���Ȃ̂ŐG�邱�Ƃ͂ł��܂���B
����ȕ\��̂܂܁A�r���[�͎��ԍs�ׂ��n�߂�̂ł����A���̂�����͌��Ă��ĐȂ��ł��B
���_�͕a��ł��l�Ԃ̎��{�\�I�ȗ~�]�����͐������A���ꂪ�������Ēɂ܂����p�Ƃ��Ă��炯�o����܂��B
�u�v���g�[���v�u7��4���ɐ��܂�āv�ŃA�J�f�~�[�܂̊ē܂���܂��Ă���Љ�h�̃I�����@�[�E�X�g�[���̋r�{�ƁA�ē̃A�����E�p�[�J�[�̕`���ΎG����܂�Ȃ��g���R�̊X���݂�Y�����ł̋��C�̐��E�B
�ӂƂ����o���S�Ő�]�̕��֒ǂ������|����`��������ł��B






�@(Midnight Express)�@1978�N�A�����J
�ēA�����E�p�[�J�[
�r�{�I�����@�[�E�X�g�[��
����r���[�E�w�C�Y
���y�W�����W�I�E�����_�[
�B�e�}�C�P���E�Z���V��
�q�L���X�g�r
�@�u���b�h�E�f�C�r�X�@�A�C���[���E�~���N���@
�@�W�����E�n�[�g�@�����f�B�E�N�G�C�h
�A�J�f�~�[��/�r�F�܃I�����@�[�E�X�g�[���@��ȏ��
�S�[���f���O���[�u��/��i��/�����j�D�܃W�����E�n�[�g

�`����Ă����͍̂��Ƃƌl�B�����ǂ����ڂ������ƂƂ�������ȏW���̂̒��ł͌l�̗͂͂��܂�ɂ��������A��͂ł����Ȃ��B
���l�̃X�[�U��(�A�C���[���E�~���N��)�Ɠ�l�Ńg���R�֊ό����s�ɏo�������A�����J�N�r���[(�u���b�h�E�f�C�r�X)�B
�A���ɂ������āA�r���[�̓n�V�V(����̈��)���A������Ȃ��������A�Ƃ������y���C�����Ŗ{���֎����������Ƃ��܂��B
�r���[�̕��Ɋ����t����ꂽ�n�V�V�͐Ŋւ�ʂ蔲���A�����Ƃ��Ȃ�����̂܂܋�`�����ї����Đ��������̂ł��傤���A���������̃g���R�ł̓e�����������A��s��͂��̂��̂����x���̐����~����A��s�@�ɓ��悷��҂̓{�f�B�`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�܂���B
���Ǝ����Ƃ����܂����A�n�V�V�͔�������ăr���[�͑ߕ߂���A�X�[�U�������͓����������ċA�����܂��B

�r���[�͌Y��������ƂȂ�̂ł����A���͂�������ŁA����1970�N�A�r���[�̖{���A�����J�̓��`���[�h�E�j�N�\���������B
�g���R�Ƃ̍����𐳏퉻���Ă��Ȃ��A�����J�ɂ͔Ɛl�����n����Ⴊ�Ȃ��A�r���[�̓g���R�̖@���ɂ���ċ�4�N�̌Y���������n����܂��B
�Ȋ��̌Y�����̒��Ńr���[�͖͔͎��Ƃ���3�N��ς��A�悤�₭�ߕ��̓����߂Â����Ǝv�����̂����̊ԁA����o�ł𐭍�Ƃ��Čf����g���R���{�́A�O���l�ɑ��Č����������ŗՂޕ��j�ɐ�ւ��A�r���[�͂��̌������߂̂��ߍٔ��̂�蒼���ɂȂ�A30�N�̌Y���ɉ����B����ɏI�g�Y�ւƉ�������܂��B
�\�͂Ɛ�]�̒��Ŕp�l���l�ƂȂ����r���[�Ɏc���ꂽ�Ō�̎�i�́u�[����}(�~�b�h�i�C�g�E�G�N�X�v���X)���E���v�ɏ�邱�Ƃ����ł����B

�}�����ꂽ��
����҃r���[�E�w�C�Y�̎��̌�����ɂ������̉f��́A�u�G���[���E�n�[�g�v�u�~�V�V�b�s�[�E�o�[�j���O�v�Ȃǂ̋S�˃A�����E�p�[�J�[�̎���������C�����ΎG�����ӂ�鐶���̔M�C�ɖ����A���ɁA�g���R���{����R�c���������Ƃ�����A���L����Y���Ă������Ȗ����̂������ς̂悤�ȊX���݂̕`�ʂ́A��l���r���[�̈��������̂܂܌������������̂悤�ȃJ�I�X�̐��E��`���o���Ă��܂��B
������Ƃ����o���S�ŋ�4�N�̎��Y����n���ɂȂ��Ă��܂��|���A���t�̒ʂ��Ȃ��O���ł̍ٔ��Ƃ䂪�i�@���x�A����ɂ͌l�̐l���͖�������A���Ƃ̐���̒��ňÍ��̐l���ɗ������ސ�]���ƌY�������ɖ�������\�͂̓r���[��p�l���l�ɂ��Ă��܂��̂ł����A���̒��ŁA�l�ԂƂ��Ă̂ЂƂ̖����`����Ă��܂��B
����́A�}�����ꂽ���̖��ł��B
����������
���{�̘b�ŁA��������O����������ゾ�������ɋ��Y�}�̊����������ƂƂ��đߕ߂���A�������Ԃ��S�u���̒��ŕ�炵�āA���̌�ߕ����ꂽ�ނ́A�����̘b�������w�Ŋw������ɍu�������������ł��B�r���A��l�̊w��������Ȏ�������܂����B
�u���̂悤�Ȓ��ŁA���I�ȗ~���ɂ��Ă͂ǂ̂悤�ɏ�������Ă����̂ł����v
��������ނ͒��ق��A���肰�Ȃ��b���]�����Ƃ������Ƃł��B
�l�ԂɂƂ��Đ��I�ȗ~�]�͐؎��Ȗ��ł��B
���ƂɌY�����Ȃǂɂ�����O�E����u�₳�ꂽ���E�ł́A����͌����ɕ\���Ǝv���܂��B
�u�A���r�A�̃������X�v��u�X�P�A�N���E�v�Ȃǂł��`���b�ƕ`����Ă��܂����A�l�X�ȉf��ł͋����{�ʂ̕`�����ł͂����Ă��A���グ���邱�Ƃ͑����悤�Ɏv���܂��B
�u�~�b�h�i�C�g�E�G�N�X�v���X�v�̌㔼�B
�p�l���l�ɂȂ����r���[�̌��ɗ��l�̃X�[�U�����ʉ�ɂ���ė��܂��B
�K���X�z���̉�b�B
����ȕ\��Ńr���[�̓X�[�U���ɕ���E���ł����悤���݂܂��B
�˘f���Ȃ�����X�[�U���͑O���J���A�`�̂������[���r���[�̖ڂ̑O�ɁB
�r���[�̓X�[�U���̋��ɐG��悤�Ƃ��܂����A�K���X�z���Ȃ̂ŐG�邱�Ƃ͂ł��܂���B
����ȕ\��̂܂܁A�r���[�͎��ԍs�ׂ��n�߂�̂ł����A���̂�����͌��Ă��ĐȂ��ł��B
���_�͕a��ł��l�Ԃ̎��{�\�I�ȗ~�]�����͐������A���ꂪ�������Ēɂ܂����p�Ƃ��Ă��炯�o����܂��B
�u�v���g�[���v�u7��4���ɐ��܂�āv�ŃA�J�f�~�[�܂̊ē܂���܂��Ă���Љ�h�̃I�����@�[�E�X�g�[���̋r�{�ƁA�ē̃A�����E�p�[�J�[�̕`���ΎG����܂�Ȃ��g���R�̊X���݂�Y�����ł̋��C�̐��E�B
�ӂƂ����o���S�Ő�]�̕��֒ǂ������|����`��������ł��B

2019�N04��27��
�f��u�z�̂�����ꏊ�v�L���������߂��N�̗��Ɣj��
�u�z�̂�����ꏊ�v(A Place in the Sun)�@
�@1951�N�A�����J
�ēW���[�W�E�X�e�B�[�����X
����Z�I�h�A�E�h���C�T�[
�r�{�}�C�P���E�E�B���\��
�@�@�n���[�E�u���E��
�B�e�E�B���A���EC�E�����[
���y�t�����c�E���b�N�X�}��
�q�L���X�g�r
�@�����S�����[�E�N���t�g�@�G���U�x�X�E�e�C���[�@
�@�V�F���[�E�E�B���^�[�X
��24��A�J�f�~�[��/�ē�/�B�e��/�r�F��/��ȏ�/��6������

�`���t�̕�e�Ɠ�l����̕n���������𑗂��Ă����W���[�W�E�C�[�X�g�}��(�����S�����[�E�N���t�g)�́A�����H����o�c���Ă��锌���̃`���[���Y�E�C�[�X�g�}���Ƌ��R�ɏo��A�����̉�ЂɌق��邱�ƂɂȂ�܂��B
�P���ȗ����Ƃ̎d����^����ꂽ�W���[�W�ł������A�����ňꏏ�ɓ����A���X�E�g���b�v(�V�F���[�E�E�B���^�[�X)�ƒm�荇���A�Г������͋ւ����Ă͂��܂������A���݂��Ɏ䂩�ꂠ������l�́A������A�A���X�̕����ň����߂������ƂɂȂ�܂��B
����Ȓ��A�����̓@��̃p�[�e�B�[�ɏ����ꂽ�W���[�W�́A�������ߏ�A���W�F���E���B�b�J�[�X(�G���U�x�X�E�e�C���[)�Əo��A���e�ƕx�ƒm����������A���W�F���ɃW���[�W�͎䂩��A�܂��A���W�F�����W���[�W�̖��͂Ɏ䂩��āA��l�͗��ɗ����Ă䂫�܂��B
�A���W�F���Ƃ̌�������W���[�W�ł������A�����փA���X�̔D�P���m�炳��A�����𔗂�A���X�ɁA�Â��n���������̐����ւ̋��|���������W���[�W�́A����ŃA���W�F���̔��e�ƕx���i���Ɏ������Ƃ�����A�Ă̌ɂ̓{�[�g�̓]�����̂��������Ƃ�m��A�{�[�g�̓]�����ăA���X���E�Q���悤�ƍl���܂��B





�Z�I�h�A�E�h���C�T�[�̒��ҏ����u�A�����J�̔ߌ��v������Ƃ������̉f��́A����̎�������`�A���{��`�ɑ�\�����A�����J�Љ�̈Â���ʂ����e�������e�Ƃ͕�����ς��A�n�����N�̗��������ɁA�x��ǂ����߂Ȃ�����A���ǂ͔j�łɎ��炴��Ȃ������N�̔ߌ���`��������ł��B
�Ⴓ�Ƃ������͉̂�(�����)����Ƃ��₷���A�Ƃ�킯�ِ��ɑ��鐫�~�A�j���ł���Ώ����ɑ��鐫�I�ȗ~���́A��D���l���邱�ƂȂ��~�]�ɑi�����ꍇ�A�]�ނ��Ƃ̂Ȃ��D�P�Ƃ����d��ȉߎ��ɂȂ����Ă��܂��܂��B

�W���[�W�E�C�[�X�g�}�����A���X�E�g���b�v�ɐڋ߂����͎̂�y�ȗ����V�Y�A�����������Ă��܂��ΐ��I�~�]��������Ƃ��Ăł����B
��������̈ӎu�ȂǏ��߂���Ȃ��A���~��������ł悩�����̂ł��B
����������̓A���X�̐S�������A���ɒǂ�����Ă��܂����ʂƂȂ������Ƃ�(�A���X��l�ł͂Ȃ��A�����̎q�ǂ����܂߂�Γ�l�̎�)�A���Ƃ����ꂪ���R�̎��̂���h���������̂ł������Ƃ��Ă��A���X�̎E�Q���l���Ă������Ƃ͎����Ȃ̂�����ƁA�W���[�W�͎��Y������Ă䂫�܂��B
���͂Ɣ��M�̉��Z�w
�h���C�T�[�́u�A�����J�̔ߌ��v�̎�l���N���C�h(�u�z�̂�����ꏊ�v�ł̓W���[�W)�͎��͂̏ɂ��܂��Ή��ł����A���f�͂ɖR�������n���䂦�ɔj�łɂ�����̂ł����A������������l���������S�����[�E�N���t�g�͊����ɕ\���B
���Ɍɏ��o�����{�[�g�̒��ŃA���X�E�Q����Y����\��́A������ʂ̉A�e�̌��ʂ������ċْ������ɓx�ɍ��܂������V�[���ł����B
�V�F���[�E�E�B���^�[�X�͌�Ɂu�����[�^�v(1962�N)�ŁA�n���o�[�g�����ɋ����䂩��Ȃ���A�����͖��̃h�����X�ɐS��D���Ă��邱�Ƃ�m���Đ�]���A���̎������Ă��܂��Ƃ����A�A���X�Ǝ����悤�Ȗ��ǂ���ŋ�����ۂ��c���Ă��܂�����A���A�ŋ�Y���鏗�������n�}��܂��B
�u�|�Z�C�h���E�A�h�x���`���[�v(1972�N)�ł͋���Ȍ��h�o�D�ɍ������āA�j���̒B�҂ȃI�o������ő傫�ȑ��݊��������Ă���܂����B


�����̑㖼���Ƃ��ăn���E�b�h�ɌN�Ղ����G���U�x�X�E�e�C���[�̓W���[�W�𖣘f���鏗���A���W�F���Ƃ��āA�Â��d�X�����u�z�̂�����ꏊ�v�ɂ����āA�܂��ɗz�̂������Ă��閾�邢��ւ̉Ԃ̂悤�ȑ��݊�������Ă��܂����B
�����āA���t�Â������Ȃ���W���[�W�̔ƍ߂ɉs�����锗�^�̉��Z�ŋ�����ۂ��c�����n�������t�����N�E�}�[���E�̃��C�����h�E�o�[�B
�e���r�V���[�Y�u�S�x���A�C�A���T�C�h�v�ł́A�Ԉ֎q�ɏ��Ȃ���ƍ߂ɗ����������T���t�����V�X�R�s�x�̌Y�������̎p�͓��{�ł��傫�Șb��ɂȂ�܂����B
����Ɖf�扻�̋��Ԃ�
�u�A�����J�̔ߌ��v��1931�N�Ɂu�Q���̓V�g�v�u�����b�R�v�Ȃǂ̖����W���Z�t�E�t�H���E�X�^���o�[�O�ēɂ���ĉf�扻����܂������A����������ꂸ�����h���}�ɌX���߂������Ƃ������ăZ�I�h�A�E�h���C�T�[�̓{����A���s��Ƃ��ꂽ���Ƃ��������̂ł��傤�A���̔��Ȃ��炩�u�z�̂�����ꏊ�v�ł͑薼�E�o��l���̖��O�����ׂĕύX���āA�Ɨ����������f��Ƃ��čĉf�扻�������Ƃ��ǂ������̂��Ǝv���܂��B
�Ȃ��A����́u�A�����J�̔ߌ��v��ǂ�ł���ƁA��l�����ł̎E�l�̂��ƁA�X�̒��S����̂ł����A���˂Ɍ��ꂽ�ۈ����ɎE�l�ƂƂ��ĕ߂܂��Ă��܂��܂��B
��l���̓����o�H��A�Ȃ��ނ��E�l�ƂƂ��ĒǐՂ���Ă����̂��͐����̂Ȃ��܂܁A�ٔ��ƂȂ��Ă��܂��̂ł����A�f��u�z�̂�����ꏊ�v�ł͂��̂����肪�L�b�`���Ɛ�������Ă��āA�������₷���W�J�ƂȂ��Ă��܂��B
�h���C�T�[�͔ƍߐ����͂��܂���ɂ����A�����܂ł���l�����Ƃ����߂ƁA�������芪���A�����J�Љ��`�����Ƃɏd����u�����悤�ł��B





�@1951�N�A�����J
�ēW���[�W�E�X�e�B�[�����X
����Z�I�h�A�E�h���C�T�[
�r�{�}�C�P���E�E�B���\��
�@�@�n���[�E�u���E��
�B�e�E�B���A���EC�E�����[
���y�t�����c�E���b�N�X�}��
�q�L���X�g�r
�@�����S�����[�E�N���t�g�@�G���U�x�X�E�e�C���[�@
�@�V�F���[�E�E�B���^�[�X
��24��A�J�f�~�[��/�ē�/�B�e��/�r�F��/��ȏ�/��6������

�`���t�̕�e�Ɠ�l����̕n���������𑗂��Ă����W���[�W�E�C�[�X�g�}��(�����S�����[�E�N���t�g)�́A�����H����o�c���Ă��锌���̃`���[���Y�E�C�[�X�g�}���Ƌ��R�ɏo��A�����̉�ЂɌق��邱�ƂɂȂ�܂��B
�P���ȗ����Ƃ̎d����^����ꂽ�W���[�W�ł������A�����ňꏏ�ɓ����A���X�E�g���b�v(�V�F���[�E�E�B���^�[�X)�ƒm�荇���A�Г������͋ւ����Ă͂��܂������A���݂��Ɏ䂩�ꂠ������l�́A������A�A���X�̕����ň����߂������ƂɂȂ�܂��B
����Ȓ��A�����̓@��̃p�[�e�B�[�ɏ����ꂽ�W���[�W�́A�������ߏ�A���W�F���E���B�b�J�[�X(�G���U�x�X�E�e�C���[)�Əo��A���e�ƕx�ƒm����������A���W�F���ɃW���[�W�͎䂩��A�܂��A���W�F�����W���[�W�̖��͂Ɏ䂩��āA��l�͗��ɗ����Ă䂫�܂��B
�A���W�F���Ƃ̌�������W���[�W�ł������A�����փA���X�̔D�P���m�炳��A�����𔗂�A���X�ɁA�Â��n���������̐����ւ̋��|���������W���[�W�́A����ŃA���W�F���̔��e�ƕx���i���Ɏ������Ƃ�����A�Ă̌ɂ̓{�[�g�̓]�����̂��������Ƃ�m��A�{�[�g�̓]�����ăA���X���E�Q���悤�ƍl���܂��B

�Z�I�h�A�E�h���C�T�[�̒��ҏ����u�A�����J�̔ߌ��v������Ƃ������̉f��́A����̎�������`�A���{��`�ɑ�\�����A�����J�Љ�̈Â���ʂ����e�������e�Ƃ͕�����ς��A�n�����N�̗��������ɁA�x��ǂ����߂Ȃ�����A���ǂ͔j�łɎ��炴��Ȃ������N�̔ߌ���`��������ł��B
�Ⴓ�Ƃ������͉̂�(�����)����Ƃ��₷���A�Ƃ�킯�ِ��ɑ��鐫�~�A�j���ł���Ώ����ɑ��鐫�I�ȗ~���́A��D���l���邱�ƂȂ��~�]�ɑi�����ꍇ�A�]�ނ��Ƃ̂Ȃ��D�P�Ƃ����d��ȉߎ��ɂȂ����Ă��܂��܂��B

�W���[�W�E�C�[�X�g�}�����A���X�E�g���b�v�ɐڋ߂����͎̂�y�ȗ����V�Y�A�����������Ă��܂��ΐ��I�~�]��������Ƃ��Ăł����B
��������̈ӎu�ȂǏ��߂���Ȃ��A���~��������ł悩�����̂ł��B
����������̓A���X�̐S�������A���ɒǂ�����Ă��܂����ʂƂȂ������Ƃ�(�A���X��l�ł͂Ȃ��A�����̎q�ǂ����܂߂�Γ�l�̎�)�A���Ƃ����ꂪ���R�̎��̂���h���������̂ł������Ƃ��Ă��A���X�̎E�Q���l���Ă������Ƃ͎����Ȃ̂�����ƁA�W���[�W�͎��Y������Ă䂫�܂��B
���͂Ɣ��M�̉��Z�w
�h���C�T�[�́u�A�����J�̔ߌ��v�̎�l���N���C�h(�u�z�̂�����ꏊ�v�ł̓W���[�W)�͎��͂̏ɂ��܂��Ή��ł����A���f�͂ɖR�������n���䂦�ɔj�łɂ�����̂ł����A������������l���������S�����[�E�N���t�g�͊����ɕ\���B
���Ɍɏ��o�����{�[�g�̒��ŃA���X�E�Q����Y����\��́A������ʂ̉A�e�̌��ʂ������ċْ������ɓx�ɍ��܂������V�[���ł����B
�V�F���[�E�E�B���^�[�X�͌�Ɂu�����[�^�v(1962�N)�ŁA�n���o�[�g�����ɋ����䂩��Ȃ���A�����͖��̃h�����X�ɐS��D���Ă��邱�Ƃ�m���Đ�]���A���̎������Ă��܂��Ƃ����A�A���X�Ǝ����悤�Ȗ��ǂ���ŋ�����ۂ��c���Ă��܂�����A���A�ŋ�Y���鏗�������n�}��܂��B
�u�|�Z�C�h���E�A�h�x���`���[�v(1972�N)�ł͋���Ȍ��h�o�D�ɍ������āA�j���̒B�҂ȃI�o������ő傫�ȑ��݊��������Ă���܂����B
�����̑㖼���Ƃ��ăn���E�b�h�ɌN�Ղ����G���U�x�X�E�e�C���[�̓W���[�W�𖣘f���鏗���A���W�F���Ƃ��āA�Â��d�X�����u�z�̂�����ꏊ�v�ɂ����āA�܂��ɗz�̂������Ă��閾�邢��ւ̉Ԃ̂悤�ȑ��݊�������Ă��܂����B
�����āA���t�Â������Ȃ���W���[�W�̔ƍ߂ɉs�����锗�^�̉��Z�ŋ�����ۂ��c�����n�������t�����N�E�}�[���E�̃��C�����h�E�o�[�B
�e���r�V���[�Y�u�S�x���A�C�A���T�C�h�v�ł́A�Ԉ֎q�ɏ��Ȃ���ƍ߂ɗ����������T���t�����V�X�R�s�x�̌Y�������̎p�͓��{�ł��傫�Șb��ɂȂ�܂����B
����Ɖf�扻�̋��Ԃ�
�u�A�����J�̔ߌ��v��1931�N�Ɂu�Q���̓V�g�v�u�����b�R�v�Ȃǂ̖����W���Z�t�E�t�H���E�X�^���o�[�O�ēɂ���ĉf�扻����܂������A����������ꂸ�����h���}�ɌX���߂������Ƃ������ăZ�I�h�A�E�h���C�T�[�̓{����A���s��Ƃ��ꂽ���Ƃ��������̂ł��傤�A���̔��Ȃ��炩�u�z�̂�����ꏊ�v�ł͑薼�E�o��l���̖��O�����ׂĕύX���āA�Ɨ����������f��Ƃ��čĉf�扻�������Ƃ��ǂ������̂��Ǝv���܂��B
�Ȃ��A����́u�A�����J�̔ߌ��v��ǂ�ł���ƁA��l�����ł̎E�l�̂��ƁA�X�̒��S����̂ł����A���˂Ɍ��ꂽ�ۈ����ɎE�l�ƂƂ��ĕ߂܂��Ă��܂��܂��B
��l���̓����o�H��A�Ȃ��ނ��E�l�ƂƂ��ĒǐՂ���Ă����̂��͐����̂Ȃ��܂܁A�ٔ��ƂȂ��Ă��܂��̂ł����A�f��u�z�̂�����ꏊ�v�ł͂��̂����肪�L�b�`���Ɛ�������Ă��āA�������₷���W�J�ƂȂ��Ă��܂��B
�h���C�T�[�͔ƍߐ����͂��܂���ɂ����A�����܂ł���l�����Ƃ����߂ƁA�������芪���A�����J�Љ��`�����Ƃɏd����u�����悤�ł��B

2019�N04��20��
�f��u�����v�~�X�e���[������ޑ�l�̃��u���}���X
�u�����v(Notorious)�@1946�N �A�����J
�ēA���t���b�h�E�q�b�`�R�b�N
�r�{�x���E�w�N�g
�B�e�e�b�h�E�e�Y���t
�q�L���X�g�r
�P�[���[�E�O�����g�@�C���O���b�h�E�o�[�O�}���@
�N���[�h�E���C���Y

�ЂƂ�̒j���X�p�C�e�^�ōٔ��ɂ������A�L�߂�鍐����܂��B���̖��A���V�A�E�n�o�[�}��(�C���O���b�h�E�o�[�O�}��)�͕��e�̈����S��M�������A�X�p�C�̖��Ƃ��ĎЉ����̖ڂ��������邱�ƂɂȂ�܂��B
����̂Ȃ��߂��݂�{��炷���߂ɊJ�����p�[�e�B�[�ň�����Ă��܂����A���V�A�ł������A�����ŕ��Â��Ɏ��͂̌������C�ɂ��邱�ƂȂ���������ł���ЂƂ�̒j�ɐS���䂩��܂��B
���̒j�f�u����(�P�[���[�E�O�����g)�̓X�p�C�g�D�̑S�e�����ނ��߁A�X�p�C�e�^�ŗL�߂ƂȂ����n�o�[�}���̖��A���V�A�ɐڋ߂��Ă���FBI�{�����ŁA���e�̉����𐰂炷���ߗ͂�݂��Ăق����ƃA���V�A�ɋ��͂�v�����܂��B
�ꎞ�̓f�u�����ɑ��đ����݂̖ڂ������Ă����A���V�A�ł������A��l�͂������䂩�ꂠ�����ɂȂ�A����߂����ɐg��C���Ȃ���A�A���V�A�͔閧�g�D�̉A�d�̉Q���ւƔ�э���ł䂭���ƂɂȂ�܂��B
�������A�A���V�A�ƃf�u�����̗��́A�g�D�𑩂˂�A���N�T���_�[�E�Z�o�X�`����(�N���[�h�E���C���Y)�ɋ߂Â��ɂ�A�Z�o�X�`�����Ƃ̌�����]�V�Ȃ����ꂽ�A���V�A�̋]���ɂ���Ĕj�ǂ��}���邱�ƂɂȂ�܂��B

���ƔC������������A���V�A�ƃf�u�����́A�g�D���E�������ʂɏW�߂Ă��邱�Ƃ�˂��~�߂܂����A�A���V�A��FBI�̃X�p�C���ƋC�Â����Z�o�X�`�����́A�A���V�A�̈��ݕ��ɏ��ʂ��ł����A�a�����ĎE�Q���悤�Ɛ}��܂��B


��l�̃��u���}���X
�u�����v���ŏ������Ƃ��ɂ́A�q�b�`�R�b�N�ɂ͒��������s�삾�Ǝv���܂����B
�ٔ��̔����V�[���Ŏn�܂邱�̉f��́A�e�^�҂͍������X�p�C�炵���A�Ƃ������Ƃ������邾���ŁA�����炵�����������Ȃ��A�܂��A�f�u�����ƃA���V�A�̌��т��������ɂ����v�����A�����̃X�p�C�f��̈�ۂ��܂����B
���ꂪ�ς�����̂̓Z�o�X�`����(�N���[�h�E���C���Y)���o�ꂵ�Ă���ł��傤���B
�Z�o�X�`�����̓A���V�A�̕��̗F�l�ŁA���˂Ă���A���V�A�ւ̑z�����߂Ă����Z�o�X�`�����̓A���V�A�Ɍ����𔗂�܂��B
�A���V�A�ƃf�u�����̗��͎v��ʕ����ւƓ����n�߁A���i�ɑς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��f�u�����̐S���ƁA�����]���ɂ��Ă��C���Ɍ������킴��Ȃ��A���V�A�̐S��́A���ƂƂ����d�ׂ̒��Őg�����̎��Ȃ��ł��邾���ɁA�]�v�ɒɁX�������`����Ă��܂��B

���i���ȋ^�S���Q�����S�̈łł������j���̎p���P�[���[�E�O�����g�ƃC���O���b�h�E�o�[�O�}���������ɕ\���B
���ɃC���O���b�h�E�o�[�O�}���̖��͍͂ۗ����Ă��āA�u�J�T�u�����J�v(1942�N)�̃G���K���g���Ƃ͈���������������������A���e�ƋC�i�̓��ʂŐ��̊��тɖ����������̖��͂ɂ��ӂ�Ă��āA�o�[�O�}���̖��͂ɂ���āu�����v�̊����x�������Ȃ����Ƃ����Ă��������炢�B
������Ղ���㔼�ɂ����Ẵq�b�`�R�b�N�炵���T�X�y���X�̖ʔ����͌����܂ł��Ȃ��̂ł����A�P�[���[�E�O�����g���K�i���i�����ɋ삯�オ���Ă䂭�D�u����p�ɂ͋����܂����B
�X�p�C�T�X�y���X�ɑ�l�̃��u���}���X�����A���邢�͂��̋t��������܂��A�Ƃɂ����������C���𖡂키�悤�ȋɏ�̉f��ł��邱�ƂɊԈႢ�͂���܂���B





�ēA���t���b�h�E�q�b�`�R�b�N
�r�{�x���E�w�N�g
�B�e�e�b�h�E�e�Y���t
�q�L���X�g�r
�P�[���[�E�O�����g�@�C���O���b�h�E�o�[�O�}���@
�N���[�h�E���C���Y

�ЂƂ�̒j���X�p�C�e�^�ōٔ��ɂ������A�L�߂�鍐����܂��B���̖��A���V�A�E�n�o�[�}��(�C���O���b�h�E�o�[�O�}��)�͕��e�̈����S��M�������A�X�p�C�̖��Ƃ��ĎЉ����̖ڂ��������邱�ƂɂȂ�܂��B
����̂Ȃ��߂��݂�{��炷���߂ɊJ�����p�[�e�B�[�ň�����Ă��܂����A���V�A�ł������A�����ŕ��Â��Ɏ��͂̌������C�ɂ��邱�ƂȂ���������ł���ЂƂ�̒j�ɐS���䂩��܂��B
���̒j�f�u����(�P�[���[�E�O�����g)�̓X�p�C�g�D�̑S�e�����ނ��߁A�X�p�C�e�^�ŗL�߂ƂȂ����n�o�[�}���̖��A���V�A�ɐڋ߂��Ă���FBI�{�����ŁA���e�̉����𐰂炷���ߗ͂�݂��Ăق����ƃA���V�A�ɋ��͂�v�����܂��B
�ꎞ�̓f�u�����ɑ��đ����݂̖ڂ������Ă����A���V�A�ł������A��l�͂������䂩�ꂠ�����ɂȂ�A����߂����ɐg��C���Ȃ���A�A���V�A�͔閧�g�D�̉A�d�̉Q���ւƔ�э���ł䂭���ƂɂȂ�܂��B
�������A�A���V�A�ƃf�u�����̗��́A�g�D�𑩂˂�A���N�T���_�[�E�Z�o�X�`����(�N���[�h�E���C���Y)�ɋ߂Â��ɂ�A�Z�o�X�`�����Ƃ̌�����]�V�Ȃ����ꂽ�A���V�A�̋]���ɂ���Ĕj�ǂ��}���邱�ƂɂȂ�܂��B

���ƔC������������A���V�A�ƃf�u�����́A�g�D���E�������ʂɏW�߂Ă��邱�Ƃ�˂��~�߂܂����A�A���V�A��FBI�̃X�p�C���ƋC�Â����Z�o�X�`�����́A�A���V�A�̈��ݕ��ɏ��ʂ��ł����A�a�����ĎE�Q���悤�Ɛ}��܂��B
��l�̃��u���}���X
�u�����v���ŏ������Ƃ��ɂ́A�q�b�`�R�b�N�ɂ͒��������s�삾�Ǝv���܂����B
�ٔ��̔����V�[���Ŏn�܂邱�̉f��́A�e�^�҂͍������X�p�C�炵���A�Ƃ������Ƃ������邾���ŁA�����炵�����������Ȃ��A�܂��A�f�u�����ƃA���V�A�̌��т��������ɂ����v�����A�����̃X�p�C�f��̈�ۂ��܂����B
���ꂪ�ς�����̂̓Z�o�X�`����(�N���[�h�E���C���Y)���o�ꂵ�Ă���ł��傤���B
�Z�o�X�`�����̓A���V�A�̕��̗F�l�ŁA���˂Ă���A���V�A�ւ̑z�����߂Ă����Z�o�X�`�����̓A���V�A�Ɍ����𔗂�܂��B
�A���V�A�ƃf�u�����̗��͎v��ʕ����ւƓ����n�߁A���i�ɑς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��f�u�����̐S���ƁA�����]���ɂ��Ă��C���Ɍ������킴��Ȃ��A���V�A�̐S��́A���ƂƂ����d�ׂ̒��Őg�����̎��Ȃ��ł��邾���ɁA�]�v�ɒɁX�������`����Ă��܂��B

���i���ȋ^�S���Q�����S�̈łł������j���̎p���P�[���[�E�O�����g�ƃC���O���b�h�E�o�[�O�}���������ɕ\���B
���ɃC���O���b�h�E�o�[�O�}���̖��͍͂ۗ����Ă��āA�u�J�T�u�����J�v(1942�N)�̃G���K���g���Ƃ͈���������������������A���e�ƋC�i�̓��ʂŐ��̊��тɖ����������̖��͂ɂ��ӂ�Ă��āA�o�[�O�}���̖��͂ɂ���āu�����v�̊����x�������Ȃ����Ƃ����Ă��������炢�B
������Ղ���㔼�ɂ����Ẵq�b�`�R�b�N�炵���T�X�y���X�̖ʔ����͌����܂ł��Ȃ��̂ł����A�P�[���[�E�O�����g���K�i���i�����ɋ삯�オ���Ă䂭�D�u����p�ɂ͋����܂����B
�X�p�C�T�X�y���X�ɑ�l�̃��u���}���X�����A���邢�͂��̋t��������܂��A�Ƃɂ����������C���𖡂키�悤�ȋɏ�̉f��ł��邱�ƂɊԈႢ�͂���܂���B

2019�N04��08��
�f��u����ꂽ�I���v�A�����j�̋�Y�ƍĐ�
�u����ꂽ�I���v(The Lost Weekend)�@
�@1945�N �A�����J
�ēr���[�E���C���_�[
�r�{�`���[���Y�E�u���P�b�g
�@�@�r���[�E���C���_�[
����`���[���Y�ER�E�W���N�\��
�q�L���X�g�r
�@���C�E�~�����h�@�W�F�[���E���C�}���@
�@�t�B���b�v�E�e���[
��18��A�J�f�~�[�܍�i��/�剉�j�D��(���C�E�~�����h)
�J���k���ۉf��ՃO�����v��

�h���E�o�[�i��(���C�E�~�����h)�͍�ƂƂ��Ă̐����𑗂��Ă��܂����A�˔\���ł��Ȃ��܂܃X�����v�Ɋׂ�A�A���R�[���ւƓ����������Ƃ���A���̂܂ܔ����o���Ȃ��Ȃ�A�A���R�[�����łƂȂ��āA�Z(�e���[�E�o�[�i��)�̐��b�ɂȂ��Ă��܂��B
�Z�͒�̂��߂ɏI���𗘗p���ēc�ɂ֘A��o�����Ƃ��܂��B�c�ɂ̐Â��Ȋ����A���R�[�����ł̒�̌��N�ɂ͗ǂ����ʂނƍl��������ł��B
�������A����Ȓ�v���̌Z�̌v������A�������]����h���͏o���̓����A�������߂Ē������܂悢�A�T���̌v���䖳���ɂ��Ă��܂��܂��B
�{�����Z�̓h�����c���A��l�œc�ɂւƏo�����čs���܂��B
��! ��! ��! �@���̂��Ƃ������ɂȂ��Ȃ����h���͋����Ȃ��Ȃ�A��Ƃ̐����ł���^�C�v���C�^�[�܂Ŏ��ɓ���ċ����H�ʂ��悤�Ƃ��܂��B


���̌�A�ӂƂ����͂��݂ŊK�i����]�������h���͕a�@�֔�������A�A���R�[�����Ŋ��҂̎{�݂Ɏ��e����܂��B
�قǂȂ����Ď{�݂���E�������h���ł������A�₪�ăA���R�[�����Ŏғ��L�̌��o�Ǐ����悤�ɂȂ�A�����ɐ�]�����h���̓s�X�g�����E��}�낤�Ƃ��܂��B





�A���R�[�����łɊׂ����j�̋�Y�Ɛ�]�A�����čĐ��܂ł�`���������r���[�E���C���_�[�ēɂ�錆��ł��B
�����g�������D���ŁA�������̃E�C�X�L�[�}�Ȃ̂ŁA���̉f����ςĂ���Ƃ₽��ƃE�C�X�L�[�����݂����Ȃ�܂��B
�قƂ�ǖ����A��(�E�C�X�L�[)�����܂Ȃ����͂Ȃ��Ƃ������炢�������Ă��܂����A�����̖ڕW�������āA�����B������܂ł͎�����߂悤�Ǝv�����Ƃ������āA1���A2���͋֎�������̂ł����A����ς���܂Ȃ��Ƃ������Ē��q�������A�������ƈ���ŁA�������Ɛ����ς���āA�������Ɗo�܂����Ƃɂ��ĖڕW�ɂ��ǂ�����肵�Ă܂�����A���������ăA���R�[���ˑ��ǂȂ̂��A�P�Ɉӎu���ア�����Ȃ̂��A�c�����A��҂̂ق��Ȃ̂ł��傤�B


��Ƃł���h���E�o�[�i���͏����������Ȃ��Ȃ������Ƃ�����ɓM��Ă��܂��܂��B
�f��̓h���̍s����ǂ��ēW�J���Ă䂫�܂����A����Ƌ��Ƀh������芪���l�X���悭�`����Ă���Ǝv���܂��B
��l�͂�͂�h���̌Z�B
��̌��N���C�����ēc�ɂɘA��o�����Ƃ���D�������Z����ŁA�ǂ��������E�ƂȂ̂��͕`����Ă͂��܂��A�m�I�ȕ��e����͎Љ�I�ȍ����̐E�Ƃł��邱�Ƃ�����܂��B
����ɁA�h���̓���݂̎���̓X��i�b�g(�n���[�h�E�_�E�V�����@)�B
�^�C�v���C�^�[�����ɓ���悤�Ƃ����h���̌��ցA�Y�ꕨ���ƌ�������Ƀ^�C�v���C�^�[��͂��ɗ���i�b�g�̑��݂́A�h���E�o�[�i���̍Đ�����̏d�v�ȍ��i���Ȃ��Ă��܂��B
�����ė��l�w����(�W�F�[���E���C�}��)�B
�A�������Ɣ������h�������̂Ă邱�ƂȂ��A�Ō�̍Ō�܂Ńh���̗��������M����w�����̎p�́A���C(���Ȃ�)�Ƃ������c�̋��������A�݂�Ȃ����̂ĂĂ����͌��̂ĂȂ��A����ȋ����M�O�ɗ��ł����ꂽ�������Ǝv���܂����B
���Ȃ݂ɃW�F�[���E���C�}������̓A�����J���O����40��哝�̃��i���h�E���[�K���̍ŏ��̉�����ł��������l�ł��B
�l�Ԃ͈�l�ł͐�����ꂸ�A�����̎��͂̐l�ԊW�ɂ���Ď�������(�͂���)�܂�Ă������̂ł�����܂��B
�h���E�o�[�i�����A�������甲���o�����̂̓h�������̈ӎu�ɂ����̂ł͂Ȃ��A�����Ɋւ��l�X�Ȑl�����ɂ���āA��l�̐l�Ԃ̍Đ����\�ɂȂ����Ƃ����܂��B
�u����ꂽ�I���v�͎Љ�̒��ŁA�l�ԓ��m�̊ւ�荇���ɂ���Đ�]�����]�ւƓ�����邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ������Ă���錆��ł��B








�@1945�N �A�����J
�ēr���[�E���C���_�[
�r�{�`���[���Y�E�u���P�b�g
�@�@�r���[�E���C���_�[
����`���[���Y�ER�E�W���N�\��
�q�L���X�g�r
�@���C�E�~�����h�@�W�F�[���E���C�}���@
�@�t�B���b�v�E�e���[
��18��A�J�f�~�[�܍�i��/�剉�j�D��(���C�E�~�����h)
�J���k���ۉf��ՃO�����v��

�h���E�o�[�i��(���C�E�~�����h)�͍�ƂƂ��Ă̐����𑗂��Ă��܂����A�˔\���ł��Ȃ��܂܃X�����v�Ɋׂ�A�A���R�[���ւƓ����������Ƃ���A���̂܂ܔ����o���Ȃ��Ȃ�A�A���R�[�����łƂȂ��āA�Z(�e���[�E�o�[�i��)�̐��b�ɂȂ��Ă��܂��B
�Z�͒�̂��߂ɏI���𗘗p���ēc�ɂ֘A��o�����Ƃ��܂��B�c�ɂ̐Â��Ȋ����A���R�[�����ł̒�̌��N�ɂ͗ǂ����ʂނƍl��������ł��B
�������A����Ȓ�v���̌Z�̌v������A�������]����h���͏o���̓����A�������߂Ē������܂悢�A�T���̌v���䖳���ɂ��Ă��܂��܂��B
�{�����Z�̓h�����c���A��l�œc�ɂւƏo�����čs���܂��B
��! ��! ��! �@���̂��Ƃ������ɂȂ��Ȃ����h���͋����Ȃ��Ȃ�A��Ƃ̐����ł���^�C�v���C�^�[�܂Ŏ��ɓ���ċ����H�ʂ��悤�Ƃ��܂��B
���̌�A�ӂƂ����͂��݂ŊK�i����]�������h���͕a�@�֔�������A�A���R�[�����Ŋ��҂̎{�݂Ɏ��e����܂��B
�قǂȂ����Ď{�݂���E�������h���ł������A�₪�ăA���R�[�����Ŏғ��L�̌��o�Ǐ����悤�ɂȂ�A�����ɐ�]�����h���̓s�X�g�����E��}�낤�Ƃ��܂��B

�A���R�[�����łɊׂ����j�̋�Y�Ɛ�]�A�����čĐ��܂ł�`���������r���[�E���C���_�[�ēɂ�錆��ł��B
�����g�������D���ŁA�������̃E�C�X�L�[�}�Ȃ̂ŁA���̉f����ςĂ���Ƃ₽��ƃE�C�X�L�[�����݂����Ȃ�܂��B
�قƂ�ǖ����A��(�E�C�X�L�[)�����܂Ȃ����͂Ȃ��Ƃ������炢�������Ă��܂����A�����̖ڕW�������āA�����B������܂ł͎�����߂悤�Ǝv�����Ƃ������āA1���A2���͋֎�������̂ł����A����ς���܂Ȃ��Ƃ������Ē��q�������A�������ƈ���ŁA�������Ɛ����ς���āA�������Ɗo�܂����Ƃɂ��ĖڕW�ɂ��ǂ�����肵�Ă܂�����A���������ăA���R�[���ˑ��ǂȂ̂��A�P�Ɉӎu���ア�����Ȃ̂��A�c�����A��҂̂ق��Ȃ̂ł��傤�B
��Ƃł���h���E�o�[�i���͏����������Ȃ��Ȃ������Ƃ�����ɓM��Ă��܂��܂��B
�f��̓h���̍s����ǂ��ēW�J���Ă䂫�܂����A����Ƌ��Ƀh������芪���l�X���悭�`����Ă���Ǝv���܂��B
��l�͂�͂�h���̌Z�B
��̌��N���C�����ēc�ɂɘA��o�����Ƃ���D�������Z����ŁA�ǂ��������E�ƂȂ̂��͕`����Ă͂��܂��A�m�I�ȕ��e����͎Љ�I�ȍ����̐E�Ƃł��邱�Ƃ�����܂��B
����ɁA�h���̓���݂̎���̓X��i�b�g(�n���[�h�E�_�E�V�����@)�B
�^�C�v���C�^�[�����ɓ���悤�Ƃ����h���̌��ցA�Y�ꕨ���ƌ�������Ƀ^�C�v���C�^�[��͂��ɗ���i�b�g�̑��݂́A�h���E�o�[�i���̍Đ�����̏d�v�ȍ��i���Ȃ��Ă��܂��B
�����ė��l�w����(�W�F�[���E���C�}��)�B
�A�������Ɣ������h�������̂Ă邱�ƂȂ��A�Ō�̍Ō�܂Ńh���̗��������M����w�����̎p�́A���C(���Ȃ�)�Ƃ������c�̋��������A�݂�Ȃ����̂ĂĂ����͌��̂ĂȂ��A����ȋ����M�O�ɗ��ł����ꂽ�������Ǝv���܂����B
���Ȃ݂ɃW�F�[���E���C�}������̓A�����J���O����40��哝�̃��i���h�E���[�K���̍ŏ��̉�����ł��������l�ł��B
�l�Ԃ͈�l�ł͐�����ꂸ�A�����̎��͂̐l�ԊW�ɂ���Ď�������(�͂���)�܂�Ă������̂ł�����܂��B
�h���E�o�[�i�����A�������甲���o�����̂̓h�������̈ӎu�ɂ����̂ł͂Ȃ��A�����Ɋւ��l�X�Ȑl�����ɂ���āA��l�̐l�Ԃ̍Đ����\�ɂȂ����Ƃ����܂��B
�u����ꂽ�I���v�͎Љ�̒��ŁA�l�ԓ��m�̊ւ�荇���ɂ���Đ�]�����]�ւƓ�����邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ������Ă���錆��ł��B

2019�N03��29��
�f��u�u���b�W�E�I�u�E�X�p�C�v�������̕ߗ�������
�u�u���b�W�E�I�u�E�X�p�C�v(Bridge of Spies)�@
�@2015�N �A�����J
�ēX�e�B�[�����E�X�s���o�[�O
�r�{�}�b�g�E�`���[�}��
�@�@�C�[�T���E�R�[�G��
�@�@�W���G���E�R�[�G��
�B�e���k�X�E�J�~���X�L�[
�q�L���X�g�r
�@�g���E�n���N�X�@�}�[�N�E���C�����X�@
�@�G�C�~�[�E���C�A��
��88��A�J�f�~�[��/�j���[���[�N�f���]�Ƌ�������j�D��(�}�[�N�E���C�����X)

�������w�c
1945�N�ɑ���E��킪�I�����A�폟���̎�]���W�܂��������^��k����A���̐��E�͕�������ւƓ����n�߂܂��B
���̎�v�ȑΗ����ƂȂ����̂��A���卑�ƂȂ����A�����J���\�Ƃ��鎩�R��`�����ƁA�\�r�G�g�A�M��Ƃ���Љ��`���ł����B
�A�W�A�ł͒��N�����B���[���b�p�͎�Ƀh�C�c���ΏۂƂȂ��āA�k�Ɠ�A���邢�͐��Ɠ��ɕ��f�B�A�����J�I���R��`�ƃ\�r�G�g�̎Љ��`�I�C�f�I���M�[�͑S���[���b�p���������݁A�����I�E�o�ϓI�ɂ��قȂ������l�ς��������������[���b�p�ւƕϗe���Ă䂫�܂��B
�A�����J�ƃ\�A�̑Η��͐����݂̂Ȃ炸�A�R���I�ɂ��������Η��B
�����̖k�吼�m���@�\(NATO)�ɑ��ē����̃����V�������@�\�����܂�A�ă\�̊j�~�T�C���̊J���Ɣz���͈�G�����ْ̋���ԂւƓ˂��i��ł䂫�܂��B
��������������C�M���X�l�̍�ƂŃW���[�i���X�g�̃W���[�W�E�I�[�E�F����1947�N�ɁA�₽���푈�u���v�ƌĂт܂����B





�W�F�[���Y�E�h�m���@��(�g���E�n���N�X)�͖@���������ŕی��ٔ��Ȃǂ�S������ٌ�m�B
�ނ͂�����A�\�A�̒�����Ƃ��đߕ߂��ꂽ���h���t�E�A�x��(�}�[�N�E���C�����X)�̍��I�ٌ�l���˗�����܂��B
����1957�N�A�������̐^�������B
�h�m���@���͌Y���������牓�������Ă��邱�Ƃ�A�G���l�ٌ̕���������ꍇ�̎Љ�I���A�������݂̂Ȃ��ٔ��ł��邱�Ƃ��l����ƕs�����o���܂����A�ٌ�m�Ƃ��Ă̐E���ɏ����A�����邱�Ƃɂ��܂��B
�S�u����K��A�A�x���Ɩʉ���h�m���@���́A������ł���Ȃ���|�p�ƂƂ��Ă̊�����A�x���̗���������������A�������ꂸ�A���Ƃɒ�����s�������Ƃ���ԓx�ɗF��ɂ������������A�ٔ��ł̖��ߔ����ɖz�����܂����A���R���̕]���͗L�߁B
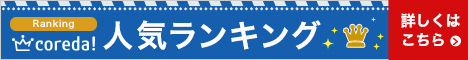

���Y�����͖�(�܂ʂ�)�ꂳ���悤�Ƃ���h�m���@���͔����ɂ��������A�߂������A�X�p�C�̌������������ꍇ�̐l���Ƃ��ăA�x���̌��Y��v���B
�h�m���@���̔S�苭�����͌���t���A�A�x���̎��Y�����͑ނ����Ē����Y���m�肵�܂��B
����A�p�L�X�^���̃A�����J�R��R��n�ł�U-2��@�@�ɂ��\�A�ւ̒�@��s���s���悤�Ƃ��Ă���A��n�����ї������p�C���b�g�̂ЂƂ�t�����V�X�E�Q�[���[�E�p���[�Y���т̓\�A��S-75�n��~�T�C���̍U�����Č��Ă���A�\�A�̕ߗ��ƂȂ��Ă��܂��܂��B
����ɁA�x�������ł͓����h�C�c�����ǂ̌��݂��i�߂��A�A�����J�l�w���Ōo�ϊw���U����t���f���b�N�E�v���C���[(�E�B���E���W���[�X)�́A���l�ƈꏏ�ɓ��h�C�c���琼�h�C�c�֓����ׂ��A�nj��݂̍����ɏ悶�ĒE�o�����݂܂����A�h�C�c�R���m�Ɏ~�߂��A�߂���Ă��܂��܂��B

�h�m���@���̕ߗ������̗\�z�͊��������ēI�������`�ɂȂ�A�\�A���̃A�x���ƁA�A�����J���̃p���[�Y�ƃv���C���[�̌�����������ׂ��h�m���@���͓��x�������������܂����ACIA��KGB�����藐��ĈÖ钆�Ō��͓�q�B
CIA�̗v���̓A�x���p���[�Y�̈�Έ�̌������Ƃ����咣�ɑ��A�h�m���@���͂����܂Ńp���[�Y�ƃv���C���[���܂߂���Γ�̌����咣�B
�����O�̔S�苭���Ńh�m���@���͕ߗ������̌��𑱂��A�A�x���p���[�Y�A�����ăv���C���[���܂߂���Γ�̌����������܂��B
�����ꏊ�̓h�C�c�E���N�����u���N����u�����f���u���N�A�x�������ւƗ����n�[�t�F����ɉ˂���O���[�j�b�P���B
�������w�c���Λ����鋴�̏�Ő�������̓A�x���A��������p���[�Y�̎p������܂����A������l�����͂��̃v���C���[�̎p�������Ȃ��܂܁A�ߗ��������i�߂��悤�Ƃ��܂����A�\�A���̈Ӑ}���@�����h�m���@���̓M���M���܂Ō��𐧎~�A���͌��Ǝv���܂������c�c�c�B


�������\���̕ߗ������h���}
�薼����́A�Ö�X�p�C�A�N�V�����f��Ƃ�����ۂ��܂����A�A�����J�ƃ\�A�̒�����̌������s��ꂽ�j�������ƂɁA���Ƃ����d����C���̕Y������̒��ŁA���Ƃ�C�f�I���M�[�����l�ԓ��m�̐M����F���`�����d���ȃq���[�}���h���}�ł���Ƃ����܂��B
���ɁA�A�J�f�~�[�܂��n�߂Ƃ��Đ��X�̏܂𑍂Ȃ߂ɂ��������j�D��܂̃}�[�N�E���C�����X�̉��Z�͑f���炵���A����������T(������)��A��ƂƂ��Ă̑�z�����˔\�������Ă��郋�h���t�E�A�x���Â��Ȍ|�p�ƂƂ��ĕ\���B
�S�u���̒��ŁA�h�m���@�����������ꂽ�Ǝv���郉�W�I���痬���V���X�^�R�[���B�`�̉��y���A�������S�̒��ɐ��ݍ���ł����悤�ɒ�������p�A���N����̑̌����h�m���@���̒u���ꂽ����Əd�ˍ��킹�Č���ʂ���́A���Â��Ȍ|�p�Ƃł���Ɠ����ɋ����M�O�̎�����ł���A�h�m���@���ɑ���M�����萶���n�߂��ۓI�ȃV�[���ł����B
��펞��͔j��I�Ȑ푈���N���邱�Ƃ��Ȃ��A1991�N�̃\�A����ɂ����͏I�����܂������A�X�p�C�̌������s��ꂽ�O���[�j�b�P�����������̏ے��Ƃ��Ċό��n������Ă���悤�ɁA��펞����������ސ�������̂́A�����Ă��܂����A���邢�͎�������Â�����̉Ƒ��Ƃ��Ă݂̍���A�F��A�l�ԓ��m�̂Ȃ��肪�����c���Ă�������ł���A�u�u���b�W�E�I�u�E�X�p�C�v�͂������������̂����܂߂ĕ`��������ł��B





�@2015�N �A�����J
�ēX�e�B�[�����E�X�s���o�[�O
�r�{�}�b�g�E�`���[�}��
�@�@�C�[�T���E�R�[�G��
�@�@�W���G���E�R�[�G��
�B�e���k�X�E�J�~���X�L�[
�q�L���X�g�r
�@�g���E�n���N�X�@�}�[�N�E���C�����X�@
�@�G�C�~�[�E���C�A��
��88��A�J�f�~�[��/�j���[���[�N�f���]�Ƌ�������j�D��(�}�[�N�E���C�����X)

�������w�c
1945�N�ɑ���E��킪�I�����A�폟���̎�]���W�܂��������^��k����A���̐��E�͕�������ւƓ����n�߂܂��B
���̎�v�ȑΗ����ƂȂ����̂��A���卑�ƂȂ����A�����J���\�Ƃ��鎩�R��`�����ƁA�\�r�G�g�A�M��Ƃ���Љ��`���ł����B
�A�W�A�ł͒��N�����B���[���b�p�͎�Ƀh�C�c���ΏۂƂȂ��āA�k�Ɠ�A���邢�͐��Ɠ��ɕ��f�B�A�����J�I���R��`�ƃ\�r�G�g�̎Љ��`�I�C�f�I���M�[�͑S���[���b�p���������݁A�����I�E�o�ϓI�ɂ��قȂ������l�ς��������������[���b�p�ւƕϗe���Ă䂫�܂��B
�A�����J�ƃ\�A�̑Η��͐����݂̂Ȃ炸�A�R���I�ɂ��������Η��B
�����̖k�吼�m���@�\(NATO)�ɑ��ē����̃����V�������@�\�����܂�A�ă\�̊j�~�T�C���̊J���Ɣz���͈�G�����ْ̋���ԂւƓ˂��i��ł䂫�܂��B
��������������C�M���X�l�̍�ƂŃW���[�i���X�g�̃W���[�W�E�I�[�E�F����1947�N�ɁA�₽���푈�u���v�ƌĂт܂����B

�W�F�[���Y�E�h�m���@��(�g���E�n���N�X)�͖@���������ŕی��ٔ��Ȃǂ�S������ٌ�m�B
�ނ͂�����A�\�A�̒�����Ƃ��đߕ߂��ꂽ���h���t�E�A�x��(�}�[�N�E���C�����X)�̍��I�ٌ�l���˗�����܂��B
����1957�N�A�������̐^�������B
�h�m���@���͌Y���������牓�������Ă��邱�Ƃ�A�G���l�ٌ̕���������ꍇ�̎Љ�I���A�������݂̂Ȃ��ٔ��ł��邱�Ƃ��l����ƕs�����o���܂����A�ٌ�m�Ƃ��Ă̐E���ɏ����A�����邱�Ƃɂ��܂��B
�S�u����K��A�A�x���Ɩʉ���h�m���@���́A������ł���Ȃ���|�p�ƂƂ��Ă̊�����A�x���̗���������������A�������ꂸ�A���Ƃɒ�����s�������Ƃ���ԓx�ɗF��ɂ������������A�ٔ��ł̖��ߔ����ɖz�����܂����A���R���̕]���͗L�߁B
���Y�����͖�(�܂ʂ�)�ꂳ���悤�Ƃ���h�m���@���͔����ɂ��������A�߂������A�X�p�C�̌������������ꍇ�̐l���Ƃ��ăA�x���̌��Y��v���B
�h�m���@���̔S�苭�����͌���t���A�A�x���̎��Y�����͑ނ����Ē����Y���m�肵�܂��B
����A�p�L�X�^���̃A�����J�R��R��n�ł�U-2��@�@�ɂ��\�A�ւ̒�@��s���s���悤�Ƃ��Ă���A��n�����ї������p�C���b�g�̂ЂƂ�t�����V�X�E�Q�[���[�E�p���[�Y���т̓\�A��S-75�n��~�T�C���̍U�����Č��Ă���A�\�A�̕ߗ��ƂȂ��Ă��܂��܂��B
����ɁA�x�������ł͓����h�C�c�����ǂ̌��݂��i�߂��A�A�����J�l�w���Ōo�ϊw���U����t���f���b�N�E�v���C���[(�E�B���E���W���[�X)�́A���l�ƈꏏ�ɓ��h�C�c���琼�h�C�c�֓����ׂ��A�nj��݂̍����ɏ悶�ĒE�o�����݂܂����A�h�C�c�R���m�Ɏ~�߂��A�߂���Ă��܂��܂��B

�h�m���@���̕ߗ������̗\�z�͊��������ēI�������`�ɂȂ�A�\�A���̃A�x���ƁA�A�����J���̃p���[�Y�ƃv���C���[�̌�����������ׂ��h�m���@���͓��x�������������܂����ACIA��KGB�����藐��ĈÖ钆�Ō��͓�q�B
CIA�̗v���̓A�x���p���[�Y�̈�Έ�̌������Ƃ����咣�ɑ��A�h�m���@���͂����܂Ńp���[�Y�ƃv���C���[���܂߂���Γ�̌����咣�B
�����O�̔S�苭���Ńh�m���@���͕ߗ������̌��𑱂��A�A�x���p���[�Y�A�����ăv���C���[���܂߂���Γ�̌����������܂��B
�����ꏊ�̓h�C�c�E���N�����u���N����u�����f���u���N�A�x�������ւƗ����n�[�t�F����ɉ˂���O���[�j�b�P���B
�������w�c���Λ����鋴�̏�Ő�������̓A�x���A��������p���[�Y�̎p������܂����A������l�����͂��̃v���C���[�̎p�������Ȃ��܂܁A�ߗ��������i�߂��悤�Ƃ��܂����A�\�A���̈Ӑ}���@�����h�m���@���̓M���M���܂Ō��𐧎~�A���͌��Ǝv���܂������c�c�c�B
�������\���̕ߗ������h���}
�薼����́A�Ö�X�p�C�A�N�V�����f��Ƃ�����ۂ��܂����A�A�����J�ƃ\�A�̒�����̌������s��ꂽ�j�������ƂɁA���Ƃ����d����C���̕Y������̒��ŁA���Ƃ�C�f�I���M�[�����l�ԓ��m�̐M����F���`�����d���ȃq���[�}���h���}�ł���Ƃ����܂��B
���ɁA�A�J�f�~�[�܂��n�߂Ƃ��Đ��X�̏܂𑍂Ȃ߂ɂ��������j�D��܂̃}�[�N�E���C�����X�̉��Z�͑f���炵���A����������T(������)��A��ƂƂ��Ă̑�z�����˔\�������Ă��郋�h���t�E�A�x���Â��Ȍ|�p�ƂƂ��ĕ\���B
�S�u���̒��ŁA�h�m���@�����������ꂽ�Ǝv���郉�W�I���痬���V���X�^�R�[���B�`�̉��y���A�������S�̒��ɐ��ݍ���ł����悤�ɒ�������p�A���N����̑̌����h�m���@���̒u���ꂽ����Əd�ˍ��킹�Č���ʂ���́A���Â��Ȍ|�p�Ƃł���Ɠ����ɋ����M�O�̎�����ł���A�h�m���@���ɑ���M�����萶���n�߂��ۓI�ȃV�[���ł����B
��펞��͔j��I�Ȑ푈���N���邱�Ƃ��Ȃ��A1991�N�̃\�A����ɂ����͏I�����܂������A�X�p�C�̌������s��ꂽ�O���[�j�b�P�����������̏ے��Ƃ��Ċό��n������Ă���悤�ɁA��펞����������ސ�������̂́A�����Ă��܂����A���邢�͎�������Â�����̉Ƒ��Ƃ��Ă݂̍���A�F��A�l�ԓ��m�̂Ȃ��肪�����c���Ă�������ł���A�u�u���b�W�E�I�u�E�X�p�C�v�͂������������̂����܂߂ĕ`��������ł��B

2019�N03��21��
�f��u�z���R�[�X�g-�A�h���t�E�q�g���[�̐���-�v�@�����̒���
�u�z���R�[�X�g-�A�h���t�E�q�g���[�̐���-�v(Amen.)�@2002�N
�t�����X/�h�C�c/���[�}�j�A/�A�����J
�ēR�X�^���K�u���X
�r�{�R�X�^���K�u���X�@
���샍���t�E�z�[�z�t�[�g�u�_�̑㗝�l�v
�B�e�p�g���b�N�E�u���V�F
�q�L���X�g�r
�@�E�����b�q�E�g�D�N���@�}�`���[�E�J�\���B�b�c�@
�@�E�����b�q�E�~���[�G
![LOrdre-et-la-Morale-Mathieu-Kassovitz-et-Ulrich-Tukur-dans-Amen[1].jpg](/2810/file/LOrdre-et-la-Morale-Mathieu-Kassovitz-et-Ulrich-Tukur-dans-Amen5B15D-thumbnail2.jpg)
������uAmen�v�B
�L���X�g�����E�ɂ�����F��̌��t�̌�ɏ����錾�t������ƂȂ��Ă��܂��B
��̂ɂ����ċF��̌��t�́u���Ȃ�(�_)�̉��������܂��悤�Ɂv�A�܂��́A��(�_)�ɑ��銴�ӂ̌��t�Œ��߂������邱�Ƃ������̂ł����A���̌�ɁA���F�̌��t�Ƃ��āu�A�[�����v���������A��������܂��悤�ɁA�����ł��A�Ƃ������Ӗ��������܂��B
���肩�画��悤�ɁA�u�z���R�[�X�g-�A�h���t�E�q�g���[�̐���-�v�͏@�����e�[�}�Ƃ��āA�o�`�J�����i�`�X�E�h�C�c�̃��_���l���Q�ɑ��Ĕ��̐������o���Ȃ������Ƃ����j�������ƂɁA�Љ�h�̋����R�X�^���K�u���X�����g�ӗ~��ł��B


�i�`�X�e�q�����тŁA���w�҂Ƃ��Ĉ��������E�ۂ��錤���Ȃǂ������Ȃ��Ă����N���g�E�Q���V���^�C��(�E�����b�q�E�g�D�N��)�́A�m�I��Q�����Â������̐��_��Q�҂Ƌ��Ɂg�a���h�Ƃ��������ň��y��������ꂽ���Ƃ�m��܂��B
�i�`�X�ɂ��g�]�܂����炴��҂����h�̎�����̖��E�A�u��Q�Ґ�Ōv��v�ł����B

����ɂ�����A�Q���V���^�C���́A��t�ŏ㊯�̏��Z(�E�����b�q�E�~���[�G)��ɘA����A�������e���Ń��_���l�̑�ʋs�E��ڌ����܂��B
�i�`�X�̔؍s��ڂ̓�����ɂ��A�����P�ʂ̃��_���l�����X�ƃK�X������ɂȂ邱�Ƃ�m�����Q���V���^�C���͋s�E����߂�����ׂ��A�g�_�̑㗝�l�h�ł���@���E�ɗ��낤�Ƃ��܂��B
�v���e�X�^���g�̐M�҂ł���Q���V���^�C���́A���Ԃ����Ƙb�������̏��݂��܂����A�N�����ނ̈ӌ��Ɏ���݂�����R����Ă��܂��܂��B
�J�g���b�N�̑��{�R�ł���o�`�J���ɑi���邵���Ȃ��ƍl�����Q���V���^�C���̓��[�}�@�����̊O�����ɐڐG���܂����A�����ł�����ɂ��ꂸ�A�ꎞ�͗��_���܂����A���R�ɂ����̏�ɂ����Ⴂ�C���m���J���h(�}�`���[�E�J�\���B�b�c)�́A�Q���V���^�C���Ƌ��Ƀi�`�X�̔؍s��H���~�߂�킢���J�n���܂��B
������i�`�X�̐e�q�����ł���Q���V���^�C���͎��Ȗ���������Ȃ�����o�`�J���ւ̐ڐG�𑱂��A�@���ւ̐��������݂܂����A�@���s�E�X12���̓i�`�X�ƓG�ΊW�ɂȂ邱�Ƃ�����A�Q���V���^�C���̑i����ނ��Ă��܂��܂��B

�Í��̎���ɂ�������̏���
16���I�Ƀ}���e�B���E���^�[���n�߂��@�����v�́A�����̃��[�}�E�J�g���b�N����ɑ���R�c�̐��ł�����܂����B
�}���A���q�A�N���X�}�X�̃~�T(�N���X�}�X�̓L���X�g�̒a�����ł͂Ȃ��A�Ñネ�[�}�̑��z���q�Ɋ�Â��Ă��܂�)�A���ȋ�����ȂǁA�_�̌��t��������̌��Ђ����߂邱�ƂɎ������A�����Ă����J�g���b�N����ɑ��Ĕ��̐����������̂ł��B
�v���e�X�^���g(�R�c�����)�ƌĂꂽ�}���e�B���E���^�[�̓J�g���b�N����痣��A�v���e�X�^���g�Ƃ��Đ_�̌��t�g�����h�����ɏ@�����v�𐄂��i�߂Ă䂫�܂��B
�f��u�z���R�[�X�g-�A�h���t�E�q�g���[�̐���-�v�́A�i�`�X�ɂ�郆�_���l�̑�ʋs�E�ɂ����āA���̒�R�������Ȃ������@���E(���Ƀ��[�}�E�J�g���b�N����)���̂��̂��w�e�����f��ł���Ƃ����܂��B


�f���炵���d���ȉf���ŁA�o�D�̉��Z���f���炵�����̂ł������A��͂�A���炩�̌`�ŋs�E�̃V�[���͗~���������Ǝv���܂��B�������e���ŃQ���V���^�C�����ǂ̌�����s�E�̗l�q�������ʂł́A�Q���V���^�C���̕\��ł��ׂĂ�����Ă䂭�̂ł����A�e�q�����ł��鎩��̗���ƁA���������Ă܂ŋs�E����߂����悤�Ƃ���S����N�b�L���ƕ����яオ�点�邽�߂ɂ́A�u�V���h���[�̃��X�g�v(1993�N)�ɂ�����Ԃ����̏����̂悤�ȃV���{���b�N�ȉf�����A�ڂ�w(����)�������Ȃ�悤�ȁA�S�ɓ˂��h����V�[�����K�v���Ǝv���܂����B
�������o�D�����̉��Z�͊����Ȃ��̂ŁA���ł��Ⴋ�C���m���J���h�̃}�`���[�E�J�\���B�b�c�̏�M�Ə@���̐�]���ɑł��̂߂����p�͋�����ۂɎc��܂����B
�@���E�̍ō����ЂƂ����ǂ��l�ԎЉ�̂ЂƂ̑g�D�̂ɂ������A���[���b�p��Ȋ������A�h���t�E�q�g���[������i�`�X�E�h�C�c�ɑ��ĕېg�Ɩ��͂����炯�o���Ă��܂����̂́A����Ӗ��A�d���̂Ȃ����Ƃ������̂�������܂��A�_�̖��ɒl���Ȃ����_���c���Ă��܂����Ƃ����܂��B
�h���I�ȉf�������Ȃ����A�o�D�̉��Z�����Ȃ�̌��ǂ�����߂܂��B���ꂾ���ɗ]�v�Ȏh���ɘf�킳�ꂸ�ɏ@���Ƃ����e�[�}��Nj����邱�Ƃ��ł���Ƃ������_������A�R�X�^���K�u���X�����̂�������l�����Ă����̂�������܂���B
�ł��u�z���R�[�X�g-�A�h���t�E�q�g���[�̐���-�v�Ƃ����M��ɂ͎���Ђ˂肽���Ȃ�܂��B
�g�z���R�[�X�g(��ʋs�E)�h�̏�ʂ͏o�Ă��܂��A�q�g���[���̂��̂��o�ꂵ�Ȃ�����ł��B�Ƃ����Č��肻�̂܂܂Ɂu�A�[�����v�ł͉������悭������܂��ˁB�薼���l����̂�������̂ł��B





�t�����X/�h�C�c/���[�}�j�A/�A�����J
�ēR�X�^���K�u���X
�r�{�R�X�^���K�u���X�@
���샍���t�E�z�[�z�t�[�g�u�_�̑㗝�l�v
�B�e�p�g���b�N�E�u���V�F
�q�L���X�g�r
�@�E�����b�q�E�g�D�N���@�}�`���[�E�J�\���B�b�c�@
�@�E�����b�q�E�~���[�G
![LOrdre-et-la-Morale-Mathieu-Kassovitz-et-Ulrich-Tukur-dans-Amen[1].jpg](/2810/file/LOrdre-et-la-Morale-Mathieu-Kassovitz-et-Ulrich-Tukur-dans-Amen5B15D-thumbnail2.jpg)
������uAmen�v�B
�L���X�g�����E�ɂ�����F��̌��t�̌�ɏ����錾�t������ƂȂ��Ă��܂��B
��̂ɂ����ċF��̌��t�́u���Ȃ�(�_)�̉��������܂��悤�Ɂv�A�܂��́A��(�_)�ɑ��銴�ӂ̌��t�Œ��߂������邱�Ƃ������̂ł����A���̌�ɁA���F�̌��t�Ƃ��āu�A�[�����v���������A��������܂��悤�ɁA�����ł��A�Ƃ������Ӗ��������܂��B
���肩�画��悤�ɁA�u�z���R�[�X�g-�A�h���t�E�q�g���[�̐���-�v�͏@�����e�[�}�Ƃ��āA�o�`�J�����i�`�X�E�h�C�c�̃��_���l���Q�ɑ��Ĕ��̐������o���Ȃ������Ƃ����j�������ƂɁA�Љ�h�̋����R�X�^���K�u���X�����g�ӗ~��ł��B
�i�`�X�e�q�����тŁA���w�҂Ƃ��Ĉ��������E�ۂ��錤���Ȃǂ������Ȃ��Ă����N���g�E�Q���V���^�C��(�E�����b�q�E�g�D�N��)�́A�m�I��Q�����Â������̐��_��Q�҂Ƌ��Ɂg�a���h�Ƃ��������ň��y��������ꂽ���Ƃ�m��܂��B
�i�`�X�ɂ��g�]�܂����炴��҂����h�̎�����̖��E�A�u��Q�Ґ�Ōv��v�ł����B

����ɂ�����A�Q���V���^�C���́A��t�ŏ㊯�̏��Z(�E�����b�q�E�~���[�G)��ɘA����A�������e���Ń��_���l�̑�ʋs�E��ڌ����܂��B
�i�`�X�̔؍s��ڂ̓�����ɂ��A�����P�ʂ̃��_���l�����X�ƃK�X������ɂȂ邱�Ƃ�m�����Q���V���^�C���͋s�E����߂�����ׂ��A�g�_�̑㗝�l�h�ł���@���E�ɗ��낤�Ƃ��܂��B
�v���e�X�^���g�̐M�҂ł���Q���V���^�C���́A���Ԃ����Ƙb�������̏��݂��܂����A�N�����ނ̈ӌ��Ɏ���݂�����R����Ă��܂��܂��B
�J�g���b�N�̑��{�R�ł���o�`�J���ɑi���邵���Ȃ��ƍl�����Q���V���^�C���̓��[�}�@�����̊O�����ɐڐG���܂����A�����ł�����ɂ��ꂸ�A�ꎞ�͗��_���܂����A���R�ɂ����̏�ɂ����Ⴂ�C���m���J���h(�}�`���[�E�J�\���B�b�c)�́A�Q���V���^�C���Ƌ��Ƀi�`�X�̔؍s��H���~�߂�킢���J�n���܂��B
������i�`�X�̐e�q�����ł���Q���V���^�C���͎��Ȗ���������Ȃ�����o�`�J���ւ̐ڐG�𑱂��A�@���ւ̐��������݂܂����A�@���s�E�X12���̓i�`�X�ƓG�ΊW�ɂȂ邱�Ƃ�����A�Q���V���^�C���̑i����ނ��Ă��܂��܂��B

�Í��̎���ɂ�������̏���
16���I�Ƀ}���e�B���E���^�[���n�߂��@�����v�́A�����̃��[�}�E�J�g���b�N����ɑ���R�c�̐��ł�����܂����B
�}���A���q�A�N���X�}�X�̃~�T(�N���X�}�X�̓L���X�g�̒a�����ł͂Ȃ��A�Ñネ�[�}�̑��z���q�Ɋ�Â��Ă��܂�)�A���ȋ�����ȂǁA�_�̌��t��������̌��Ђ����߂邱�ƂɎ������A�����Ă����J�g���b�N����ɑ��Ĕ��̐����������̂ł��B
�v���e�X�^���g(�R�c�����)�ƌĂꂽ�}���e�B���E���^�[�̓J�g���b�N����痣��A�v���e�X�^���g�Ƃ��Đ_�̌��t�g�����h�����ɏ@�����v�𐄂��i�߂Ă䂫�܂��B
�f��u�z���R�[�X�g-�A�h���t�E�q�g���[�̐���-�v�́A�i�`�X�ɂ�郆�_���l�̑�ʋs�E�ɂ����āA���̒�R�������Ȃ������@���E(���Ƀ��[�}�E�J�g���b�N����)���̂��̂��w�e�����f��ł���Ƃ����܂��B
�f���炵���d���ȉf���ŁA�o�D�̉��Z���f���炵�����̂ł������A��͂�A���炩�̌`�ŋs�E�̃V�[���͗~���������Ǝv���܂��B�������e���ŃQ���V���^�C�����ǂ̌�����s�E�̗l�q�������ʂł́A�Q���V���^�C���̕\��ł��ׂĂ�����Ă䂭�̂ł����A�e�q�����ł��鎩��̗���ƁA���������Ă܂ŋs�E����߂����悤�Ƃ���S����N�b�L���ƕ����яオ�点�邽�߂ɂ́A�u�V���h���[�̃��X�g�v(1993�N)�ɂ�����Ԃ����̏����̂悤�ȃV���{���b�N�ȉf�����A�ڂ�w(����)�������Ȃ�悤�ȁA�S�ɓ˂��h����V�[�����K�v���Ǝv���܂����B
�������o�D�����̉��Z�͊����Ȃ��̂ŁA���ł��Ⴋ�C���m���J���h�̃}�`���[�E�J�\���B�b�c�̏�M�Ə@���̐�]���ɑł��̂߂����p�͋�����ۂɎc��܂����B
�@���E�̍ō����ЂƂ����ǂ��l�ԎЉ�̂ЂƂ̑g�D�̂ɂ������A���[���b�p��Ȋ������A�h���t�E�q�g���[������i�`�X�E�h�C�c�ɑ��ĕېg�Ɩ��͂����炯�o���Ă��܂����̂́A����Ӗ��A�d���̂Ȃ����Ƃ������̂�������܂��A�_�̖��ɒl���Ȃ����_���c���Ă��܂����Ƃ����܂��B
�h���I�ȉf�������Ȃ����A�o�D�̉��Z�����Ȃ�̌��ǂ�����߂܂��B���ꂾ���ɗ]�v�Ȏh���ɘf�킳�ꂸ�ɏ@���Ƃ����e�[�}��Nj����邱�Ƃ��ł���Ƃ������_������A�R�X�^���K�u���X�����̂�������l�����Ă����̂�������܂���B
�ł��u�z���R�[�X�g-�A�h���t�E�q�g���[�̐���-�v�Ƃ����M��ɂ͎���Ђ˂肽���Ȃ�܂��B
�g�z���R�[�X�g(��ʋs�E)�h�̏�ʂ͏o�Ă��܂��A�q�g���[���̂��̂��o�ꂵ�Ȃ�����ł��B�Ƃ����Č��肻�̂܂܂Ɂu�A�[�����v�ł͉������悭������܂��ˁB�薼���l����̂�������̂ł��B

2019�N03��19��
�f��u�L�[�g���̒T��w����v��y�f��̌��_
�u�L�[�g���̒T��w����v(SHERLOCK JR.)
�@1924�N �A�����J
�ēE�剉�o�X�^�[�E�L�[�g��
�B�e�G���W���E���X���[�@�o�C�����E�t�[�N
�r�{�N���C�h�E�u���b�N�}���@
�@�@�W�[���EC�E�n���F�b�c�@
�@�@�W���Z�t�E�~�b�`�F��
�q�L���X�g�r
�L���X�����E�}�N�K�C�A�@�W���[�E�L�[�g��

�`���b�v�������l���̈�������I�E�Љ�I���h�����̒��ɕ\�������̂ɑ��A�o�X�^�[�E�L�[�g���͂����܂Ŋϋq���y���܂��邽�߂ɂ̂݉f�������Ă���Ƃ����܂��B
�������A���̕\�����@��100�N�߂��o�������݂ł������ĐF�邱�ƂȂ��A��y�f��̌��_�Ƃ��āA����҂��y���܂��Ă���܂��B


����́u�V���[���b�N�E�W���j�A�v�B
��l��(�o�X�^�[�E�L�[�g��)�͉f��ق̉f�ʋZ�t���G�p�W�B�V���[���b�N�E�z�[���Y�̂悤�Ȗ��T��ɂȂ邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B
����Ȕނ͗��̃��C�o�����d�g��݂ɂ���Ďw�֓D�_�̌��^���A���l(�L���X�����E�}�N�K�C�A)�̕��e���玩��ւ̗���������֎~����܂��B
�ӋC�����̎�l���B
�œ������C���̂܂d�����̉f��̉f�ʒ��ɋ���������Ă��܂��܂��B
����͖��Ȃ̂��A���̕����Ȃ̂��A��������l���̑̂��������l�̎�l��������A���d�s�v�c�ȕ��ꂪ�W�J����Ă䂫�܂��B

�f��`���́A�������肪���Ȋ쌀�Ŏn�܂�܂����A��l���̑̂��������ꂽ�u�Ԃ���A�A�C�f�A�Ɏ����A�C�f�A�A�A�N�V�����Ɏ����A�N�V�������l�ߍ��܂ꂽ�L�[�g���̐��E�ւƓ˓����Ă����܂��B
���낢��ȃA�C�f�A�����ڂł����A�܂����������̂��A��l�����f��̒��֓����Ă��܂���ʁB�f��ƌ����̋��E���A�b�T���Ɣ�щz���Ă��܂���z�V�O�Ȓ��z�ŁA����͌�ɃE�f�B�E�A�������u�J�C���̎��̃o���v�Ɏ�����A�Ⴆ�Ȃ��q���C��(�~�A�E�t�@���[)���̌�����َ����̗�����ł���A�f��^�̂ł�����܂����B
�l�X�ȃg���b�N�������̂ŁA�ҏW�̋Z�p�͂Ƃ��A�܂��Ɉ�u�̑��킴���o�ꂷ�邩�Ǝv���A�W���b�L�[�E�`�F�����^���̃A�N�V�����Ɏ����A�N�V�����B����\��ɂ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ��낪�o�X�^�[�E�L�[�g���̂������Ƃ���B
50���ɖ����Ȃ���f���Ԃ̒��ɁA�M���O����A�N�V��������A30�N��̃t�@�b�V�����E�Z���X����肵���悤�ȁA���T��ɕ������L�[�g���̂�����ꊴ�o����ŁA���x���Ă��O�������܂���B
��y���_���ڂ̗��������Ɋy���߂�f��ł��B





�@1924�N �A�����J
�ēE�剉�o�X�^�[�E�L�[�g��
�B�e�G���W���E���X���[�@�o�C�����E�t�[�N
�r�{�N���C�h�E�u���b�N�}���@
�@�@�W�[���EC�E�n���F�b�c�@
�@�@�W���Z�t�E�~�b�`�F��
�q�L���X�g�r
�L���X�����E�}�N�K�C�A�@�W���[�E�L�[�g��

�`���b�v�������l���̈�������I�E�Љ�I���h�����̒��ɕ\�������̂ɑ��A�o�X�^�[�E�L�[�g���͂����܂Ŋϋq���y���܂��邽�߂ɂ̂݉f�������Ă���Ƃ����܂��B
�������A���̕\�����@��100�N�߂��o�������݂ł������ĐF�邱�ƂȂ��A��y�f��̌��_�Ƃ��āA����҂��y���܂��Ă���܂��B
����́u�V���[���b�N�E�W���j�A�v�B
��l��(�o�X�^�[�E�L�[�g��)�͉f��ق̉f�ʋZ�t���G�p�W�B�V���[���b�N�E�z�[���Y�̂悤�Ȗ��T��ɂȂ邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B
����Ȕނ͗��̃��C�o�����d�g��݂ɂ���Ďw�֓D�_�̌��^���A���l(�L���X�����E�}�N�K�C�A)�̕��e���玩��ւ̗���������֎~����܂��B
�ӋC�����̎�l���B
�œ������C���̂܂d�����̉f��̉f�ʒ��ɋ���������Ă��܂��܂��B
����͖��Ȃ̂��A���̕����Ȃ̂��A��������l���̑̂��������l�̎�l��������A���d�s�v�c�ȕ��ꂪ�W�J����Ă䂫�܂��B

�f��`���́A�������肪���Ȋ쌀�Ŏn�܂�܂����A��l���̑̂��������ꂽ�u�Ԃ���A�A�C�f�A�Ɏ����A�C�f�A�A�A�N�V�����Ɏ����A�N�V�������l�ߍ��܂ꂽ�L�[�g���̐��E�ւƓ˓����Ă����܂��B
���낢��ȃA�C�f�A�����ڂł����A�܂����������̂��A��l�����f��̒��֓����Ă��܂���ʁB�f��ƌ����̋��E���A�b�T���Ɣ�щz���Ă��܂���z�V�O�Ȓ��z�ŁA����͌�ɃE�f�B�E�A�������u�J�C���̎��̃o���v�Ɏ�����A�Ⴆ�Ȃ��q���C��(�~�A�E�t�@���[)���̌�����َ����̗�����ł���A�f��^�̂ł�����܂����B
�l�X�ȃg���b�N�������̂ŁA�ҏW�̋Z�p�͂Ƃ��A�܂��Ɉ�u�̑��킴���o�ꂷ�邩�Ǝv���A�W���b�L�[�E�`�F�����^���̃A�N�V�����Ɏ����A�N�V�����B����\��ɂ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ��낪�o�X�^�[�E�L�[�g���̂������Ƃ���B
50���ɖ����Ȃ���f���Ԃ̒��ɁA�M���O����A�N�V��������A30�N��̃t�@�b�V�����E�Z���X����肵���悤�ȁA���T��ɕ������L�[�g���̂�����ꊴ�o����ŁA���x���Ă��O�������܂���B
��y���_���ڂ̗��������Ɋy���߂�f��ł��B









