新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2019年09月18日
映画「クレオパトラ」-愛と野望の悲劇
「クレオパトラ」(Cleopatra) 1963年アメリカ
監督ジョセフ・L・マンキーウィッツ
脚本シドニー・バックマン
ラナルド・マクドゥガル
ジョセフ・L・マンキーウィッツ
撮影レオン・シャムロイ
音楽アレックス・ノース
〈キャスト〉
エリザベス・テイラー レックス・ハリソン
リチャード・バートン マーティン・ランドー
第36回アカデミー賞/美術賞/撮影賞/衣装デザイン賞/視覚効果賞受賞

世界史を彩(いろど)る絶世の美女クレオパトラ。
もちろん、写真が残っているわけでもありませんし、その容姿を実際に見た人は2000年以上昔に亡くなっているのですから、クレオパトラが本当はどんな姿かたちをしていたのかは想像するしかありません。
当時の硬貨にクレオパトラの横顔の肖像が使われていて、それほどの美女でもなかったようだ、後世の作り話として美女とされたという話もありますが、人を惹きつける魅力を持っていたことはたしかなようです。
美女の宝庫のようなハリウッド映画界でも、クレオパトラを演じられる女優はそういなかった中で、当時ハリウッドきっての美女エリザベス・テイラーが100万ドルという破格の出演料で古代の王女を演じたのですが、美貌はいうに及ばず、周囲を圧するカリスマ性、恋と野望に燃える戦乱の美女を存在感たっぷりに見せてくれました。


20世紀フォックスが社運を賭けて作り上げた壮大な歴史ロマン大作。
空前のスケールと堂々たる風格。
20万人を超えるエキストラなど、30年代から続いたハリウッドの黄金期に陰りが見え始めた中で、その底力を見せつけた超大作です。
でも、ひとつ気になるのが、シェイクスピアの戯曲「ジュリアス・シーザー」「アントニーとクレオパトラ」でよく知られた英語表記の名前シーザーは、現在ではユリウス・カエサルが主に使われるようになっていて、ラテン語のこの方が当時の発音に近いからという理由のようですが、映画の登場人物たちは「シーザー」と呼んでいるのに、字幕では「カエサル」であったり「ユリウス」であったりするのは、なんかヘンだな、と思ったりします。
歴史上の人物の名前は、作家や歴史家によって呼び方を変えられたりしますし、日本でも、小谷城の城主で織田信長の妹、お市の方の夫である浅井長政(あさいながまさ)が現在では“あざいながまさ”と濁音になったりしてますしね。
ここでは英語の表記そのままに「ジュリアス・シーザー」を用いることにします。




紀元前48年。
エジプト最後の王朝となるプトレマイオス朝は政局の混乱にあります。
そんな中でクレオパトラ(エリザベス・テイラー)は弟のプトレマイオス13世(リチャード・オサリヴァン)と共同統治を行いますが、プトレマイオス13世を支持する宮廷側近たちから疎(うと)まれはじめたクレオパトラは王宮から追放の憂き目にあいます。
一方、ジュリアス・シーザー(レックス・ハリソン)は「ファルサルスの戦い」で敵対するポンペイウスを破り、エジプトへ逃亡していたポンペイウス追討のためにアレクサンドリアへ入城します。
エジプトと信頼関係にあるローマ帝国の執政シーザーがアレクサンドリアに来ていることを知ったクレオパトラは、暗殺を恐れて絨毯の中に身を隠すという奇策を用いてシーザーと密かに会い、同盟と支援の後ろ盾を得ます。

クレオパトラをひと目見たシーザーは、その美貌と知性に惹かれ、野望を秘めたクレオパトラはシーザーの愛人として同盟の結束を図ると同時にエジプトのファラオ(王)として返り咲きます。
イタリア半島を制圧し、覇権を拡大して強大な勢力となったローマ帝国の実力者シーザーでしたが、絶大な権力を手にしたことで独裁色を強めだしたシーザーに対して元老院は激しく反発。
信任の厚かったブルータスにも見限られたシーザーは元老院議員たちの手によって惨殺されてしまいます。
シーザーと共にローマに滞在していたクレオパトラは、シーザー暗殺を知るとエジプトへ帰りますが、シーザーを失ったローマは内政の混乱を深めていきます。
紀元前42年。
分裂したローマ帝国は自由主義・共和主義を標榜するブルータス(ケネス・ヘイグ)らが率いる軍と、シーザーの片腕として知られるマーク・アントニー(リチャード・バートン)率いる三頭政治側の軍が「フィリッピの戦い」で激突。
アントニーが勝利を収めますが、エジプトがブルータス側を支援していたことで、アントニーはクレオパトラとの会談に臨みます。
かつてシーザーを魅了したクレオパトラの美貌は色あせることなく、アントニーはその魅力に惹かれてゆき、クレオパトラもまた、軍人でありながら人間的弱さを持ったアントニーに惹かれ、二人は激しい恋に落ちていきます。
クレオパトラとの関係からアントニーはエジプトに接近。
ローマでは、シーザーの後継として頭角を現し始めたオクタヴィアン(ロディ・マクドウォール)が軍を掌握。
東のアントニー、西のオクタヴィアンと勢力が二分したローマは、紀元前31年、「アクティウムの海戦」で雌雄を決することになります。
クレオパトラのエジプトはアントニー側の支援に回りますが、結果はアントニー側の敗北となり、圧倒的なオクタヴィアンの勢力の前になすこともなくアントニーは自決を図りますが、急所を外れたために死にきれず、宮殿に閉じこもっていたクレオパトラの横で息を引き取ります。
アントニーの死を看取ったクレオパトラもまた、イチジクの籠に潜(ひそ)ませたコブラに腕を噛ませ、アントニーの後を追います。




4時間を超える超大作で、映画は前半と後半に分かれています。
前半ではシーザーとクレオパトラの出会いから、クレオパトラのローマ入城、ローマ帝国の内紛とシーザー暗殺へと、歴史的な流れを追って話は進みます。
見どころは何といってもクレオパトラのローマ入城です。
シーザーとの間に出来た息子(後のプトレマイオス15世)を横に従えて、周囲を圧する貫禄でローマへ入る場面は圧倒的なスケール。
この場面だけで何本かの映画を撮れるのではないかと思うような豪華で華やか、躍動感あふれる場面です。

シーザー亡き後の後半へ入ると、前半でひ弱に見えたオクタヴィアン(実際に虚弱体質だったらしい)が徐々に実力をつけ、シーザーの片腕とされたアントニーとの確執と全面戦争へと展開していきます。
後半の最大の見どころは、オクタヴィアン勢力対アントニー派による“アクティウムの海戦”で、ギリシャの西、古代都市アクティウムを本拠地として、その沖合いで行われた海戦でアントニーは屈辱的な敗戦の憂き目に遭うのですが、コンピューター・グラフィックスなど使わない時代の撮影技術は素晴らしく、史劇を得意とする往年のハリウッドの面目躍如たるものがあります。




監督は、脚本家でもあり製作も手掛けるジョセフ・L・マンキーウィッツ。
監督としては「三人の妻への手紙」(1949年)、「イヴの総て」(1950年)などの女性を中心としたメロドラマに本領を発揮したものが多いです。
「クレオパトラ」前半でもシーザーとクレオパトラのラブロマンスに重点が置かれ、クレオパトラの野望がからんだロマンスが展開されています。
マーク・アントニーに「聖衣」(1953年)、「史上最大の作戦」(1962年)のリチャード・バートン。
オクタヴィアンに「わが谷は緑なりき」(1941年)、「マクベス」(1948年)のロディ・マクドウォール。
子役から出発したマクドウォールは、ジョン・フォード監督による「わが谷は緑なりき」のモーガン家の末っ子ヒューの愛らしい少年役が素晴らしく、学校で教師にいじめられたヒューを見た谷の人たちが憤慨し、学校に乗り込んで教師を殴り倒すシーンはジョン・フォードらしい浪花節的名場面で、名作「わが谷は緑なりき」の中にあってマクドウォールの愛らしさが際立っていました。
もう一人、マーク・アントニーの側近で片腕でもあるルフィオを演じたマーティン・ランドー。
「クレオパトラ」の前作「北北西に進路を取れ」(1959年)では悪役でしたが、アントニーの片腕として時には激しくアントニーに意見をするルフィオは、忠実な部下であり、また友人でもあり、最後には味方がすべてアントニーを離れていく中で、最後までアントニーに忠実であり続けて殺されるルフィオは日本のサムライを見るようで、特に印象に強く残りました。




リチャード・バートンとエリザベス・テイラーの不倫騒動や、製作上の不手際、撮影上のゴタゴタなど、何かと問題の多かった「クレオパトラ」ですが、舞台裏の話はちょっと脇へ置いておいて。
4時間を超える大作ですが、愛と野望の悲劇として必見の価値はあります。





監督ジョセフ・L・マンキーウィッツ
脚本シドニー・バックマン
ラナルド・マクドゥガル
ジョセフ・L・マンキーウィッツ
撮影レオン・シャムロイ
音楽アレックス・ノース
〈キャスト〉
エリザベス・テイラー レックス・ハリソン
リチャード・バートン マーティン・ランドー
第36回アカデミー賞/美術賞/撮影賞/衣装デザイン賞/視覚効果賞受賞

世界史を彩(いろど)る絶世の美女クレオパトラ。
もちろん、写真が残っているわけでもありませんし、その容姿を実際に見た人は2000年以上昔に亡くなっているのですから、クレオパトラが本当はどんな姿かたちをしていたのかは想像するしかありません。
当時の硬貨にクレオパトラの横顔の肖像が使われていて、それほどの美女でもなかったようだ、後世の作り話として美女とされたという話もありますが、人を惹きつける魅力を持っていたことはたしかなようです。
美女の宝庫のようなハリウッド映画界でも、クレオパトラを演じられる女優はそういなかった中で、当時ハリウッドきっての美女エリザベス・テイラーが100万ドルという破格の出演料で古代の王女を演じたのですが、美貌はいうに及ばず、周囲を圧するカリスマ性、恋と野望に燃える戦乱の美女を存在感たっぷりに見せてくれました。
20世紀フォックスが社運を賭けて作り上げた壮大な歴史ロマン大作。
空前のスケールと堂々たる風格。
20万人を超えるエキストラなど、30年代から続いたハリウッドの黄金期に陰りが見え始めた中で、その底力を見せつけた超大作です。
でも、ひとつ気になるのが、シェイクスピアの戯曲「ジュリアス・シーザー」「アントニーとクレオパトラ」でよく知られた英語表記の名前シーザーは、現在ではユリウス・カエサルが主に使われるようになっていて、ラテン語のこの方が当時の発音に近いからという理由のようですが、映画の登場人物たちは「シーザー」と呼んでいるのに、字幕では「カエサル」であったり「ユリウス」であったりするのは、なんかヘンだな、と思ったりします。
歴史上の人物の名前は、作家や歴史家によって呼び方を変えられたりしますし、日本でも、小谷城の城主で織田信長の妹、お市の方の夫である浅井長政(あさいながまさ)が現在では“あざいながまさ”と濁音になったりしてますしね。
ここでは英語の表記そのままに「ジュリアス・シーザー」を用いることにします。
紀元前48年。
エジプト最後の王朝となるプトレマイオス朝は政局の混乱にあります。
そんな中でクレオパトラ(エリザベス・テイラー)は弟のプトレマイオス13世(リチャード・オサリヴァン)と共同統治を行いますが、プトレマイオス13世を支持する宮廷側近たちから疎(うと)まれはじめたクレオパトラは王宮から追放の憂き目にあいます。
一方、ジュリアス・シーザー(レックス・ハリソン)は「ファルサルスの戦い」で敵対するポンペイウスを破り、エジプトへ逃亡していたポンペイウス追討のためにアレクサンドリアへ入城します。
エジプトと信頼関係にあるローマ帝国の執政シーザーがアレクサンドリアに来ていることを知ったクレオパトラは、暗殺を恐れて絨毯の中に身を隠すという奇策を用いてシーザーと密かに会い、同盟と支援の後ろ盾を得ます。

クレオパトラをひと目見たシーザーは、その美貌と知性に惹かれ、野望を秘めたクレオパトラはシーザーの愛人として同盟の結束を図ると同時にエジプトのファラオ(王)として返り咲きます。
イタリア半島を制圧し、覇権を拡大して強大な勢力となったローマ帝国の実力者シーザーでしたが、絶大な権力を手にしたことで独裁色を強めだしたシーザーに対して元老院は激しく反発。
信任の厚かったブルータスにも見限られたシーザーは元老院議員たちの手によって惨殺されてしまいます。
シーザーと共にローマに滞在していたクレオパトラは、シーザー暗殺を知るとエジプトへ帰りますが、シーザーを失ったローマは内政の混乱を深めていきます。
紀元前42年。
分裂したローマ帝国は自由主義・共和主義を標榜するブルータス(ケネス・ヘイグ)らが率いる軍と、シーザーの片腕として知られるマーク・アントニー(リチャード・バートン)率いる三頭政治側の軍が「フィリッピの戦い」で激突。
アントニーが勝利を収めますが、エジプトがブルータス側を支援していたことで、アントニーはクレオパトラとの会談に臨みます。
かつてシーザーを魅了したクレオパトラの美貌は色あせることなく、アントニーはその魅力に惹かれてゆき、クレオパトラもまた、軍人でありながら人間的弱さを持ったアントニーに惹かれ、二人は激しい恋に落ちていきます。
クレオパトラとの関係からアントニーはエジプトに接近。
ローマでは、シーザーの後継として頭角を現し始めたオクタヴィアン(ロディ・マクドウォール)が軍を掌握。
東のアントニー、西のオクタヴィアンと勢力が二分したローマは、紀元前31年、「アクティウムの海戦」で雌雄を決することになります。
クレオパトラのエジプトはアントニー側の支援に回りますが、結果はアントニー側の敗北となり、圧倒的なオクタヴィアンの勢力の前になすこともなくアントニーは自決を図りますが、急所を外れたために死にきれず、宮殿に閉じこもっていたクレオパトラの横で息を引き取ります。
アントニーの死を看取ったクレオパトラもまた、イチジクの籠に潜(ひそ)ませたコブラに腕を噛ませ、アントニーの後を追います。
4時間を超える超大作で、映画は前半と後半に分かれています。
前半ではシーザーとクレオパトラの出会いから、クレオパトラのローマ入城、ローマ帝国の内紛とシーザー暗殺へと、歴史的な流れを追って話は進みます。
見どころは何といってもクレオパトラのローマ入城です。
シーザーとの間に出来た息子(後のプトレマイオス15世)を横に従えて、周囲を圧する貫禄でローマへ入る場面は圧倒的なスケール。
この場面だけで何本かの映画を撮れるのではないかと思うような豪華で華やか、躍動感あふれる場面です。

シーザー亡き後の後半へ入ると、前半でひ弱に見えたオクタヴィアン(実際に虚弱体質だったらしい)が徐々に実力をつけ、シーザーの片腕とされたアントニーとの確執と全面戦争へと展開していきます。
後半の最大の見どころは、オクタヴィアン勢力対アントニー派による“アクティウムの海戦”で、ギリシャの西、古代都市アクティウムを本拠地として、その沖合いで行われた海戦でアントニーは屈辱的な敗戦の憂き目に遭うのですが、コンピューター・グラフィックスなど使わない時代の撮影技術は素晴らしく、史劇を得意とする往年のハリウッドの面目躍如たるものがあります。
監督は、脚本家でもあり製作も手掛けるジョセフ・L・マンキーウィッツ。
監督としては「三人の妻への手紙」(1949年)、「イヴの総て」(1950年)などの女性を中心としたメロドラマに本領を発揮したものが多いです。
「クレオパトラ」前半でもシーザーとクレオパトラのラブロマンスに重点が置かれ、クレオパトラの野望がからんだロマンスが展開されています。
マーク・アントニーに「聖衣」(1953年)、「史上最大の作戦」(1962年)のリチャード・バートン。
オクタヴィアンに「わが谷は緑なりき」(1941年)、「マクベス」(1948年)のロディ・マクドウォール。
子役から出発したマクドウォールは、ジョン・フォード監督による「わが谷は緑なりき」のモーガン家の末っ子ヒューの愛らしい少年役が素晴らしく、学校で教師にいじめられたヒューを見た谷の人たちが憤慨し、学校に乗り込んで教師を殴り倒すシーンはジョン・フォードらしい浪花節的名場面で、名作「わが谷は緑なりき」の中にあってマクドウォールの愛らしさが際立っていました。
もう一人、マーク・アントニーの側近で片腕でもあるルフィオを演じたマーティン・ランドー。
「クレオパトラ」の前作「北北西に進路を取れ」(1959年)では悪役でしたが、アントニーの片腕として時には激しくアントニーに意見をするルフィオは、忠実な部下であり、また友人でもあり、最後には味方がすべてアントニーを離れていく中で、最後までアントニーに忠実であり続けて殺されるルフィオは日本のサムライを見るようで、特に印象に強く残りました。
リチャード・バートンとエリザベス・テイラーの不倫騒動や、製作上の不手際、撮影上のゴタゴタなど、何かと問題の多かった「クレオパトラ」ですが、舞台裏の話はちょっと脇へ置いておいて。
4時間を超える大作ですが、愛と野望の悲劇として必見の価値はあります。

【このカテゴリーの最新記事】
2019年09月09日
映画「東京暮色」ー 二人の姉妹を通して家族のあり方を探る小津安二郎の秀作
「東京暮色」(1957年, 昭和32年) 松竹
監督 小津安二郎
脚本 野田高梧
小津安二郎
撮影 厚田雄春
音楽 斎藤高順
戦後の混乱期を抜け出し、落ち着きと静けさを取り戻し始めた東京。
日々の暮らしを営む平凡な家族、二人の姉妹を通して次第に失われてゆく家族のあり方を、ゆったりとした静かな視点で描いた名匠小津安二郎の秀作。





杉山周吉(笠智衆)は実直な銀行員。
でも彼には最近、小さな心配事があります。
夫との間がうまくいっていないのか、娘の孝子(原節子)が小さな娘を連れて家に帰っているのです。
妻もなく、独り身の周吉にとっては娘の孝子が家にいてくれるのは何かとありがたいし、孫娘の顔を毎日見られるのもうれしい。
しかし、孝子の夫である沼田(信欣三)を引き合わせたのは他ならぬ周吉本人であってみれば、一度、沼田にも会って相談をしてみようと思ったりしています。
周吉には孝子のほかにもう一人娘がいます。
孝子の妹、明子(有馬稲子)です。
その明子は最近、叔母である重子(杉村春子)に理由も言わず金を借りに行っていて、重子からその話を聞かされた周吉は、またひとつ悩みが増えました。
明子は大きな問題を抱えています。
交際相手の大学生、木村(田浦正巳)と肉体関係を持ち、妊娠してしまったのです。
木村との結婚などはおぼつかず、中絶手術のための金が必要になったのです。

明子は木村にも相談しようとしますが、木村は逃げ回っているのか行方がわからず、木村の友人たちが集まる雀荘へも足を運びますが、木村の行方は皆目つかめません。
雀荘の主人相島(中村伸郎)とも親しくなった明子は、相島の妻喜久子(山田五十鈴)とも知り合い、明子を見た喜久子は、明子が自分の娘ではないかと迷いはじめます。
もともと周吉の妻だった喜久子は、周吉が朝鮮の京城へ赴任していたころ、周吉の部下と関係を持ち、夫と二人の娘を捨てて家を出てしまっていたのです。
母親の顔を覚えていない明子でしたが、姉の孝子は喜久子をよく覚えていました。
何かと明子によくしようとする喜久子に、孝子は厳しい拒絶の言葉を投げつけます。
そんなことはまるで知らない周吉は、孝子の夫の沼田に会い、沼田とたわいもない雑談を交わし、帰宅します。
ようやく町の食堂で木村に会えた明子は、煮え切らない木村の態度に腹を立て、木村の頬を張り倒して店を飛び出しましたが、悲劇はその直後に明子を襲います。




あらすじだけを追っていくと、とても暗い話のようで、実際に小津作品の中で“失敗作”と見なす傾向もあったようですが、私はとてもそうは思えず、むしろ秀作だと思いますし、小津本人も自信があったようです。
小津作品の常連であり、父と娘の関係を演じることの多い笠智衆と原節子さんは、ちょっと控えめにして、望まぬ妊娠に直面して苦悩する明子を前面に押し出しました。
美人の有馬稲子さんは終始、思いつめた厳しい表情で登場しますが、それをやわらげる効果を発揮しているのが背景に流れる明るい音楽です。
音楽もそうなのですが、飲み屋の主人の浦辺粂子さんを始めとして、そこの客であったり、雀荘の主人の中村伸郎、バーの客など、脇役が飄々(ひょうひょう)としていますし、登場人物すべてに個性を持たせているので、暗さを相殺(そうさい)する効果が随所に配されています。




特筆すべきは“昭和の大女優”と形容される山田五十鈴さん。
かつて周吉の部下と関係を持って、家庭を捨てて逃げた喜久子。
いまでは雀荘の相島の女房としてつましい生活を送る喜久子は、図らずも二人の娘に出会い、心騒ぐものがあるとはいえ、娘たちは立派に成人して、姉の孝子は結婚して娘もいる。そんな中へ、どの面(ツラ)下げて母親です、と言えるものではない。
そんな、あきらめに似た、それでもやっぱり母親として娘たちと話をしてみたい、そういう心の葛藤を表面に出さず、胸の奥底にあるうもれ火を一人でかき回しながら寂しさに耐えているような、うつむき加減にじっと考え込む喜久子の表情はとてもいい。

小津作品では「東京暮色」一本だけになりましたが、山田五十鈴さんは黒澤作品にいくつか出演していて、「東京暮色」と同じ年の昭和32年には「蜘蛛の巣城」「どん底」。4年後の昭和36(1961)年には「用心棒」と続くのですが、「東京暮色」の喜久子が静かに耐える女性であったのに対し、黒澤作品ではギラギラした強烈な悪女を演じました。
特に「どん底」で香川京子さんの髪をつかんで引きずり回す、嫉妬深い悪女ぶりは強烈でしたし、「蜘蛛の巣城」では能面のように無表情ながら、夫の鷲津武時に謀反を仕向ける陰性の悪女がとても印象的でした。


「東京暮色」で秀逸だと思うのは、ラスト近くの駅のシーンです。
明子が死に、姉の孝子には「お母さんなんて大っ嫌い!」と厳しい言葉を投げつけられ、つくづく東京がイヤになった喜久子は、夫の相島と二人で北海道で暮らす決心をします。
そして出発の日。
相島と二人で汽車に乗り込んだ喜久子は、相島の勧める酒を口に運びながら窓の外を眺めています。
汽車の時間を孝子に知らせてあった喜久子は、孝子が見送りに来てくれるのを待っているのです。
プラットホームでは大学生の集団が、寮歌なのか応援歌なのか、その大きい声がホームに延々と響いています。
孝子がいつやって来るだろうかと、喜久子は窓の外が気になって仕方がない。
「来やしないよ」ポツリと相島が言います。
喜久子は黙って窓の外を眺めています。
孝子は喜久子を許すことなく、ホームへは現れません。
並みの映画であれば、ホームの片隅で喜久子を見送る孝子の姿が描かれるのかもしれませんが、小津は孝子と喜久子の母子関係に妥協の余地を与えていません。
しかし、明子の死と、実母である喜久子の背徳に対する憎しみを経験した孝子は、自分の娘に明子と同じ寂しさを味合わせたくない気持ちから、沼田の元へ帰る決心をします。
そして、孝子と孫娘が去って静かになった朝を迎えた周吉は、一人、いつものように出勤してゆくのです。
小津安二郎らしい、静かで味わい深いラストです。





監督 小津安二郎
脚本 野田高梧
小津安二郎
撮影 厚田雄春
音楽 斎藤高順
戦後の混乱期を抜け出し、落ち着きと静けさを取り戻し始めた東京。
日々の暮らしを営む平凡な家族、二人の姉妹を通して次第に失われてゆく家族のあり方を、ゆったりとした静かな視点で描いた名匠小津安二郎の秀作。

杉山周吉(笠智衆)は実直な銀行員。
でも彼には最近、小さな心配事があります。
夫との間がうまくいっていないのか、娘の孝子(原節子)が小さな娘を連れて家に帰っているのです。
妻もなく、独り身の周吉にとっては娘の孝子が家にいてくれるのは何かとありがたいし、孫娘の顔を毎日見られるのもうれしい。
しかし、孝子の夫である沼田(信欣三)を引き合わせたのは他ならぬ周吉本人であってみれば、一度、沼田にも会って相談をしてみようと思ったりしています。
周吉には孝子のほかにもう一人娘がいます。
孝子の妹、明子(有馬稲子)です。
その明子は最近、叔母である重子(杉村春子)に理由も言わず金を借りに行っていて、重子からその話を聞かされた周吉は、またひとつ悩みが増えました。
明子は大きな問題を抱えています。
交際相手の大学生、木村(田浦正巳)と肉体関係を持ち、妊娠してしまったのです。
木村との結婚などはおぼつかず、中絶手術のための金が必要になったのです。

明子は木村にも相談しようとしますが、木村は逃げ回っているのか行方がわからず、木村の友人たちが集まる雀荘へも足を運びますが、木村の行方は皆目つかめません。
雀荘の主人相島(中村伸郎)とも親しくなった明子は、相島の妻喜久子(山田五十鈴)とも知り合い、明子を見た喜久子は、明子が自分の娘ではないかと迷いはじめます。
もともと周吉の妻だった喜久子は、周吉が朝鮮の京城へ赴任していたころ、周吉の部下と関係を持ち、夫と二人の娘を捨てて家を出てしまっていたのです。
母親の顔を覚えていない明子でしたが、姉の孝子は喜久子をよく覚えていました。
何かと明子によくしようとする喜久子に、孝子は厳しい拒絶の言葉を投げつけます。
そんなことはまるで知らない周吉は、孝子の夫の沼田に会い、沼田とたわいもない雑談を交わし、帰宅します。
ようやく町の食堂で木村に会えた明子は、煮え切らない木村の態度に腹を立て、木村の頬を張り倒して店を飛び出しましたが、悲劇はその直後に明子を襲います。
あらすじだけを追っていくと、とても暗い話のようで、実際に小津作品の中で“失敗作”と見なす傾向もあったようですが、私はとてもそうは思えず、むしろ秀作だと思いますし、小津本人も自信があったようです。
小津作品の常連であり、父と娘の関係を演じることの多い笠智衆と原節子さんは、ちょっと控えめにして、望まぬ妊娠に直面して苦悩する明子を前面に押し出しました。
美人の有馬稲子さんは終始、思いつめた厳しい表情で登場しますが、それをやわらげる効果を発揮しているのが背景に流れる明るい音楽です。
音楽もそうなのですが、飲み屋の主人の浦辺粂子さんを始めとして、そこの客であったり、雀荘の主人の中村伸郎、バーの客など、脇役が飄々(ひょうひょう)としていますし、登場人物すべてに個性を持たせているので、暗さを相殺(そうさい)する効果が随所に配されています。
特筆すべきは“昭和の大女優”と形容される山田五十鈴さん。
かつて周吉の部下と関係を持って、家庭を捨てて逃げた喜久子。
いまでは雀荘の相島の女房としてつましい生活を送る喜久子は、図らずも二人の娘に出会い、心騒ぐものがあるとはいえ、娘たちは立派に成人して、姉の孝子は結婚して娘もいる。そんな中へ、どの面(ツラ)下げて母親です、と言えるものではない。
そんな、あきらめに似た、それでもやっぱり母親として娘たちと話をしてみたい、そういう心の葛藤を表面に出さず、胸の奥底にあるうもれ火を一人でかき回しながら寂しさに耐えているような、うつむき加減にじっと考え込む喜久子の表情はとてもいい。

小津作品では「東京暮色」一本だけになりましたが、山田五十鈴さんは黒澤作品にいくつか出演していて、「東京暮色」と同じ年の昭和32年には「蜘蛛の巣城」「どん底」。4年後の昭和36(1961)年には「用心棒」と続くのですが、「東京暮色」の喜久子が静かに耐える女性であったのに対し、黒澤作品ではギラギラした強烈な悪女を演じました。
特に「どん底」で香川京子さんの髪をつかんで引きずり回す、嫉妬深い悪女ぶりは強烈でしたし、「蜘蛛の巣城」では能面のように無表情ながら、夫の鷲津武時に謀反を仕向ける陰性の悪女がとても印象的でした。
「東京暮色」で秀逸だと思うのは、ラスト近くの駅のシーンです。
明子が死に、姉の孝子には「お母さんなんて大っ嫌い!」と厳しい言葉を投げつけられ、つくづく東京がイヤになった喜久子は、夫の相島と二人で北海道で暮らす決心をします。
そして出発の日。
相島と二人で汽車に乗り込んだ喜久子は、相島の勧める酒を口に運びながら窓の外を眺めています。
汽車の時間を孝子に知らせてあった喜久子は、孝子が見送りに来てくれるのを待っているのです。
プラットホームでは大学生の集団が、寮歌なのか応援歌なのか、その大きい声がホームに延々と響いています。
孝子がいつやって来るだろうかと、喜久子は窓の外が気になって仕方がない。
「来やしないよ」ポツリと相島が言います。
喜久子は黙って窓の外を眺めています。
孝子は喜久子を許すことなく、ホームへは現れません。
並みの映画であれば、ホームの片隅で喜久子を見送る孝子の姿が描かれるのかもしれませんが、小津は孝子と喜久子の母子関係に妥協の余地を与えていません。
しかし、明子の死と、実母である喜久子の背徳に対する憎しみを経験した孝子は、自分の娘に明子と同じ寂しさを味合わせたくない気持ちから、沼田の元へ帰る決心をします。
そして、孝子と孫娘が去って静かになった朝を迎えた周吉は、一人、いつものように出勤してゆくのです。
小津安二郎らしい、静かで味わい深いラストです。

2019年09月05日
映画「何がジェーンに起こったか?」嫉妬と憎悪,サイコミステリーの傑作
「何がジェーンに起こったか?」
(What Ever Happened to Baby Jane?)
1962年 アメリカ
製作・監督ロバート・アルドリッチ
原作ヘンリー・ファレル
脚本ルーカス・ヘラー
撮影アーネスト・ホーラー
〈キャスト〉
ベティ・デイヴィス ジョーン・クロフォード
ヴィクター・ブオノ
第35回アカデミー賞衣装デザイン賞(白黒)
「ベラクルス」(1954年)、「特攻大作戦」(1967年)、「北国の帝王」(1973年)など、男性的で骨太い作品を得意とするロバート・アルドリッチが、愛憎に満ちた姉妹の確執をテーマに、そこから生じたミステリーに挑んだ傑作。
アカデミー賞を始めとして、カンヌ国際映画祭やゴールデングローブ賞など数々の賞にノミネートをされるなど、作品の質の高さは評価されましたが、何しろ1962年は「アラビアのロレンス」が作品賞を始めとして7部門を受賞するなど圧倒的な存在感を見せつけ、「奇跡の人」「アラバマ物語」「戦艦バウンティ」「史上最大の作戦」といったそうそうたる作品の並んだ時期だっただけに、衣装デザイン賞のみの受賞に沈みましたが、主演のベティ・デイヴィス、ジョーン・クロフォードの火花を散らす演技と、ヒッチコックばりのサスペンスとスリラーの展開は、とにかく見応えがあります。





1917年、世界的には第一次世界大戦が終結に向かい始め、ロシア革命が勃発し、映画の世界ではチャーリー・チャップリンがその才能を発揮していたころ、ショービジネスの世界では一人の少女が愛らしい歌と踊りを披露して観客の喝采を浴びていました。
その名は“ベイビー・ジェーン・ハドソン”。
観客の熱烈なリクエストに応えて彼女が歌う曲は「パパに手紙を」。
しかし、華やかな舞台の陰でジェーンに冷たい視線を送る少女がいました。
ジェーン・ハドソンの姉、ブランチです。
舞台での愛らしい仕草とは反対に、傲慢な態度の目立つジェーンでしたが、ドル箱の少女スターは周囲からはチヤホヤされています。
そんなジェーンへの嫉妬が憎しみともいえる心境へブランチを追いやっているのです。


時は流れ、大人の女性へと成長したジェーン(ベティ・デイヴィス)とブランチ(ジョーン・クロフォード)は映画の世界で活躍を始めます。
しかし、少女時代とは対照的に、抜群の美貌と演技力でスターの地位を築いた姉のブランチでしたが、大した演技力を持たない妹のジェーンは映画界から爪弾(つまはじ)きにされていきます。
そしてある夜、自宅の前で自動車事故が起こり、酒に酔ったジェーンが姉のブランチを轢き殺そうとしたものだと新聞は報じます。
ここが、この映画のミステリーの発端となるところで、車を運転していたのが誰で、衝突されたのが誰なのか、両方ともに女性であるということの他には一切明らかにされていません。
話は変わって、ハリウッドにあるジェーンとブランチの家。
自動車事故から長い年月が過ぎ去り、華やかな映画スターの面影の消えかけたブランチは事故による脊髄損傷から車イスの生活を送り、白い厚化粧のジェーンが姉の世話をしています。
二人の間にわだかまるのは、自動車事故の加害者としてのジェーンの負い目による姉への奉仕と、妹のジェーンの助けを借りなければ食事も満足にとれない、妹に対する弱みを持つ車イスのブランチ。
少女時代の華やかさを取り戻そうと夢見るジェーンは、当時の人気曲「パパに手紙を」でカムバックを果たすべく専属のピアニスト、エドウィン・フラッグ(ヴィクター・ブオノ)を雇い、レッスンに励みます。
しかし、酒に溺れ、老いて自分の醜さを鏡の中に見出すようになったジェーンは、少なからず病み始めていた精神が加速度を増し、ブランチに対する支配力を強めて陰湿な虐待へとエスカレートしてゆきます。

通いの家政婦エルヴァイラ(メイディ・ノーマン)はジェーンの態度に不審を抱き、ブランチの窮状を救おうとしますが、それに気づいたジェーンに殺害されてしまいます。
手首をロープで縛られて自由を失ったブランチは衰弱し、死が目前に迫ってゆきます。





少女時代の嫉妬と羨望は大人になってから完全に逆転し、骨肉であるがゆえに、出来のいい姉への憎悪と老醜に対する怯えに支配され、徐々に正気を失ってゆくジェーンを演じたベティ・デイヴィスは、「化石の森」(1936年)、「黒蘭の女」(1938年)などの美貌からは想像できない、何かに取り憑かれたかのような狂気の演技でアカデミー賞主演女優賞にノミネート。

対するジョーン・クロフォードはサイレントの時代から活躍していた女優ですが、やはり「大砂塵」(1954年)が最も印象が強いです。
ベティ・デイヴィスの鬼気迫る演技の陰に隠れがちになってしまいましたが、暴君と化してゆく妹に怯えるジョーン・クロフォードの演技は、見ている側にもその怖さが直(じか)に伝わる迫真性があり、特に、主治医に助けを求めるために不自由な足を引きずって階段を降り、電話にすがりつく場面はサスペンス映画の極致です。
姉妹の確執を描いた映画ですが、実生活でもベティ・デイヴィスとクロフォードはかなり仲が悪かったらしく、それが映画にも反映されているのでしょうか。
でも、「お熱いのがお好き」(1959年)でのマリリン・モンローとトニー・カーティスも実生活では不仲だったようですから、お熱い恋人同士を演じた彼らの演技力も大したものです。




「何がジェーンに起こったか?」はミステリーとサイコスリラーの要素を併せ持った映画で、最後の最後まで自動車事故の真実が明らかにされることはなく、この二人の身の上に何が起こったのか、ミステリーはミステリーのままでドラマは進行し、そしてついに、ラストの浜辺で死に瀕したブランチの口から事故の真実が語られてゆきます。
しかし、ブランチの告白を聞いているジェーンはすでに正気を失っていて、明るい太陽と輝く夏の海辺、そこに、6歳当時の自分に戻って踊るジェーン、やせ衰えた体を砂浜に横たえて死を待つブランチという、狂気と死の構図は、真夏の海水浴客との対比の中で、姉妹の確執の醜悪さがひときわ浮き彫りにされています。





最後に、ジェーンの専属ピアニストとして雇われることになるエドウィン。
ジェーンに気があるような、ないような、売れないピアニストなのでジェーンに気に入られようと気のある素振りをしているのか、そんな態度を母親のデリラにたしなめられる気の弱い太ったピアニスト。
この親子のやり取りはときにユーモラスで、このあたりもヒッチコックをお手本にしているのかな、と思わせるものがあります。
ジェーンの異常さに気づき、部屋に監禁されて死にかけているブランチを発見しながら、慌てふためいて逃げてしまうダメ男を演じたヴィクター・ブオノは助演男優賞にノミネート。
受賞は「渇いた太陽」のエド・ベグリーにさらわれましたが、「何がジェーンに起こったか?」の緊張した展開の中で、母親のデリラと行きずりの男との間に生まれた出自を持ち、母親に反抗をしながらも、なんとなく人生に妥協してしまっているエドウィンには不思議で奇妙な存在感がありました。







(What Ever Happened to Baby Jane?)
1962年 アメリカ
製作・監督ロバート・アルドリッチ
原作ヘンリー・ファレル
脚本ルーカス・ヘラー
撮影アーネスト・ホーラー
〈キャスト〉
ベティ・デイヴィス ジョーン・クロフォード
ヴィクター・ブオノ
第35回アカデミー賞衣装デザイン賞(白黒)
「ベラクルス」(1954年)、「特攻大作戦」(1967年)、「北国の帝王」(1973年)など、男性的で骨太い作品を得意とするロバート・アルドリッチが、愛憎に満ちた姉妹の確執をテーマに、そこから生じたミステリーに挑んだ傑作。
アカデミー賞を始めとして、カンヌ国際映画祭やゴールデングローブ賞など数々の賞にノミネートをされるなど、作品の質の高さは評価されましたが、何しろ1962年は「アラビアのロレンス」が作品賞を始めとして7部門を受賞するなど圧倒的な存在感を見せつけ、「奇跡の人」「アラバマ物語」「戦艦バウンティ」「史上最大の作戦」といったそうそうたる作品の並んだ時期だっただけに、衣装デザイン賞のみの受賞に沈みましたが、主演のベティ・デイヴィス、ジョーン・クロフォードの火花を散らす演技と、ヒッチコックばりのサスペンスとスリラーの展開は、とにかく見応えがあります。

1917年、世界的には第一次世界大戦が終結に向かい始め、ロシア革命が勃発し、映画の世界ではチャーリー・チャップリンがその才能を発揮していたころ、ショービジネスの世界では一人の少女が愛らしい歌と踊りを披露して観客の喝采を浴びていました。
その名は“ベイビー・ジェーン・ハドソン”。
観客の熱烈なリクエストに応えて彼女が歌う曲は「パパに手紙を」。
しかし、華やかな舞台の陰でジェーンに冷たい視線を送る少女がいました。
ジェーン・ハドソンの姉、ブランチです。
舞台での愛らしい仕草とは反対に、傲慢な態度の目立つジェーンでしたが、ドル箱の少女スターは周囲からはチヤホヤされています。
そんなジェーンへの嫉妬が憎しみともいえる心境へブランチを追いやっているのです。
時は流れ、大人の女性へと成長したジェーン(ベティ・デイヴィス)とブランチ(ジョーン・クロフォード)は映画の世界で活躍を始めます。
しかし、少女時代とは対照的に、抜群の美貌と演技力でスターの地位を築いた姉のブランチでしたが、大した演技力を持たない妹のジェーンは映画界から爪弾(つまはじ)きにされていきます。
そしてある夜、自宅の前で自動車事故が起こり、酒に酔ったジェーンが姉のブランチを轢き殺そうとしたものだと新聞は報じます。
ここが、この映画のミステリーの発端となるところで、車を運転していたのが誰で、衝突されたのが誰なのか、両方ともに女性であるということの他には一切明らかにされていません。
話は変わって、ハリウッドにあるジェーンとブランチの家。
自動車事故から長い年月が過ぎ去り、華やかな映画スターの面影の消えかけたブランチは事故による脊髄損傷から車イスの生活を送り、白い厚化粧のジェーンが姉の世話をしています。
二人の間にわだかまるのは、自動車事故の加害者としてのジェーンの負い目による姉への奉仕と、妹のジェーンの助けを借りなければ食事も満足にとれない、妹に対する弱みを持つ車イスのブランチ。
少女時代の華やかさを取り戻そうと夢見るジェーンは、当時の人気曲「パパに手紙を」でカムバックを果たすべく専属のピアニスト、エドウィン・フラッグ(ヴィクター・ブオノ)を雇い、レッスンに励みます。
しかし、酒に溺れ、老いて自分の醜さを鏡の中に見出すようになったジェーンは、少なからず病み始めていた精神が加速度を増し、ブランチに対する支配力を強めて陰湿な虐待へとエスカレートしてゆきます。

通いの家政婦エルヴァイラ(メイディ・ノーマン)はジェーンの態度に不審を抱き、ブランチの窮状を救おうとしますが、それに気づいたジェーンに殺害されてしまいます。
手首をロープで縛られて自由を失ったブランチは衰弱し、死が目前に迫ってゆきます。
少女時代の嫉妬と羨望は大人になってから完全に逆転し、骨肉であるがゆえに、出来のいい姉への憎悪と老醜に対する怯えに支配され、徐々に正気を失ってゆくジェーンを演じたベティ・デイヴィスは、「化石の森」(1936年)、「黒蘭の女」(1938年)などの美貌からは想像できない、何かに取り憑かれたかのような狂気の演技でアカデミー賞主演女優賞にノミネート。

対するジョーン・クロフォードはサイレントの時代から活躍していた女優ですが、やはり「大砂塵」(1954年)が最も印象が強いです。
ベティ・デイヴィスの鬼気迫る演技の陰に隠れがちになってしまいましたが、暴君と化してゆく妹に怯えるジョーン・クロフォードの演技は、見ている側にもその怖さが直(じか)に伝わる迫真性があり、特に、主治医に助けを求めるために不自由な足を引きずって階段を降り、電話にすがりつく場面はサスペンス映画の極致です。
姉妹の確執を描いた映画ですが、実生活でもベティ・デイヴィスとクロフォードはかなり仲が悪かったらしく、それが映画にも反映されているのでしょうか。
でも、「お熱いのがお好き」(1959年)でのマリリン・モンローとトニー・カーティスも実生活では不仲だったようですから、お熱い恋人同士を演じた彼らの演技力も大したものです。
「何がジェーンに起こったか?」はミステリーとサイコスリラーの要素を併せ持った映画で、最後の最後まで自動車事故の真実が明らかにされることはなく、この二人の身の上に何が起こったのか、ミステリーはミステリーのままでドラマは進行し、そしてついに、ラストの浜辺で死に瀕したブランチの口から事故の真実が語られてゆきます。
しかし、ブランチの告白を聞いているジェーンはすでに正気を失っていて、明るい太陽と輝く夏の海辺、そこに、6歳当時の自分に戻って踊るジェーン、やせ衰えた体を砂浜に横たえて死を待つブランチという、狂気と死の構図は、真夏の海水浴客との対比の中で、姉妹の確執の醜悪さがひときわ浮き彫りにされています。

最後に、ジェーンの専属ピアニストとして雇われることになるエドウィン。
ジェーンに気があるような、ないような、売れないピアニストなのでジェーンに気に入られようと気のある素振りをしているのか、そんな態度を母親のデリラにたしなめられる気の弱い太ったピアニスト。
この親子のやり取りはときにユーモラスで、このあたりもヒッチコックをお手本にしているのかな、と思わせるものがあります。
ジェーンの異常さに気づき、部屋に監禁されて死にかけているブランチを発見しながら、慌てふためいて逃げてしまうダメ男を演じたヴィクター・ブオノは助演男優賞にノミネート。
受賞は「渇いた太陽」のエド・ベグリーにさらわれましたが、「何がジェーンに起こったか?」の緊張した展開の中で、母親のデリラと行きずりの男との間に生まれた出自を持ち、母親に反抗をしながらも、なんとなく人生に妥協してしまっているエドウィンには不思議で奇妙な存在感がありました。

2019年08月07日
映画「日の名残り」すれ違ってゆく男女の悲哀を描いた秀作
「日の名残り」(The Remains of the Day)
1993年イギリス
監督ジェームズ・アイヴォリー
原作カズオ・イシグロ
脚本ルイース・プラワー・ジャブバーラ
撮影トニー・ピアース・ロバーツ
音楽リチャード・ロビンズ
〈キャスト〉
アンソニー・ホプキンス エマ・トンプソン
クリストファー・リーブ ジェームズ・フォックス
第66回アカデミー賞主演男優賞、主演女優賞、
監督賞、美術賞他8部門ノミネート




ノーベル賞作家カズオ・イシグロの同名小説を映画化。
台頭するナチス・ドイツに対する政治的判断を誤った貴族の没落を背景に、あまりにも謹厳で職務への忠実さゆえに愛をつかむことのできなかった男と、彼への愛を秘めながら、もう一歩を踏み出すことのできなかった女。
お互いに分かり過ぎるほど気持ちが分かっていながら、すれ違ってゆく男女の悲哀を、「眺めのいい部屋」「モーリス」の名匠ジェームズ・アイヴォリーが重厚に描いた秀作です。

1958年イギリス、イングランド東部オックスフォード。
広大な屋敷、ダーリントン・ホールの以前の持ち主ダーリントン卿(ジェームズ・フォックス)はすでに亡く、現在はアメリカ人の富豪ルイス(クリストファー・リーブ)の手に渡っています。
ダーリントン卿の元で長く執事を務めていたジェームズ・スティーブンス(アンソニー・ホプキンス)は、ダーリントン・ホールの持ち主が変わった現在も執事としてルイスに仕えています。
そんなある日、以前の女中頭ミス・ケントン(エマ・トンプソン)からスティーブンスのもとに手紙が届きます。
娘も成長して手が離れたから、もう一度働かせてもらいたい、といった内容に加えて、結婚生活の陰りをうかがわせる文面にスティーブンスの気持ちはゆらぎ、彼女の元へ出かける決心をします。
ダーリントン・ホールから外の世界へ出たことのないスティーブンスにルイスは車を貸し与え、
「世界を見たほうがいい」と言うルイスに対して、スティーブンスはこう応えます。
「世界のほうから、ここへやってきていましたから」
そして物語は20年前へとさかのぼってゆきます。

1938年、ダーリントン・ホールでは世界の要人が集まり、第一次世界大戦後の莫大な賠償金を負わされたドイツに対する扱いをどうするかで議論が戦わされています。
ダーリントン・ホールの持ち主ダーリントン卿はドイツへの復興援助を主張し、満場の同意を得ますが、それに真っ向から反対をしたのがアメリカ人のルイスでした。
若手の政治家として頭角を現し始めたルイスは、政治は貴族のようなシロウトがするものではなく、プロに任せるべきだと反論。満場の失笑を買います。
しかし、その年の3月にナチス・ドイツはオーストリアを併合。
11月には「水晶の夜」と呼ばれるユダヤ人への迫害が始まります。
時代が大きく動いてゆく中で、ダーリントン・ホールに新しい女中頭が採用されます。
勝気ではあるけど仕事熱心な女性、ミス・ケントンです。
初対面の面接からいきなり悪感情を持ったスティーブンスとミス・ケントンでしたが、厳格な中にも繊細な一面をのぞかせるスティーブンスにミス・ケントンは次第に興味を持ち始めます。


執事という仕事の中で最も重要な特性は“品格”だと考えるスティーブンスは、その言葉通り、柔らかな物腰と穏やかな話しぶりの中に、禁欲的な気高さを感じさせる風格を備えた男性でしたが、男女間の恋愛については、低俗な恋愛小説から学び取ることしかできない、生身の女性心理を理解できない男でもありました。
やがてミス・ケントンは以前からの同僚であったベン(ティム・ピゴット・スミス)に求婚され、スティーブンスへの密かな想いに迷い苦しみながら、ベンとの結婚に踏み切り、町を去ってゆきます。
世界は大きく動き、親ナチスの姿勢を鮮明にしていたダーリントン卿はユダヤ人排斥にも加担しますが、貴族的な人間性を失うことのなかった彼は自分の罪を悔い、世間からも非難を浴びながら次第に正気を失ってゆき、静かに世を去ります。
……そして20年後。
ミス・ケントンからの手紙を受け取ったスティーブンスは彼女との再会を果たしますが、孫の誕生と世話のためにダーリントン・ホールでの仕事ができなくなったことを彼女に告げられ、雨のそぼ降るバス停で、再会を約束することもなく、バスに乗り込んだミス・ケントンをスティーブンスは黙って見つめ、滲む窓ガラスに映るミス・ケントンの涙をこらえた表情が次第に遠ざかってゆきます。





今や名優の域に達したアンソニー・ホプキンスですが、かつて出演した「ジャガーノート」(1974年)、「エレファント・マン」(1980年)などの作品にヒット作はあったものの、神経質なイギリス人といった印象で存在感に乏しく、目立つような俳優ではなかったのですが、それがどうしたことか、突然、強烈な個性派俳優として名を挙げたのが「羊たちの沈黙」(1991年)の高度な知性と異常な精神病を併せ持ったハンニバル・レクター博士でした。
それからの活躍は、ハンニバル・レクターとアンソニー・ホプキンスがダブッて見えるほど強烈なレクター博士のイメージがつきまといました。
本作「日の名残り」ではアカデミー賞の主演男優賞にはノミネートで終わりましたが、その落ち着いた物腰からにじみ出る仕事に対する禁欲的な姿勢と、逆に恋愛に関しては臆病なほど内向的なスティーブンスの人間性は、それまでの自信に満ち溢れたレクター博士のようなキャラクターとは打って変わった人物像を作り上げました。
ミス・ケントンに「ハワーズ・エンド」(1992年)、「父の祈りを」(1993年)、「いつか晴れた日に」(1995年)など、数々の主演女優賞に名前の挙がる実力派のエマ・トンプソン。
個人的には「日の名残り」と同年の作品である「父の祈りを」で演じた女性弁護士ギャレス・ピアースの熱演がとても印象に残っています。
ダーリントン卿に「インドへの道」(1984年)、「ロシア・ハウス」(1990年)、「パトリオット・ゲーム」(1992年)のジェームズ・フォックス。
富豪のアメリカ人、ルイスに「スーパーマン」シリーズ、「デストラップ・死の罠」(1982年)のクリストファー・リーブ。
クリストファー・リーブは1995年に落馬事故を起こし、脊髄損傷のため車イス生活を余儀なくされましたが、以後も社会活動など精力的な活動を続けていましたが、2004年に心不全を発症、惜しまれながら52歳で世を去っています。




第一次から第二次への世界大戦を背景としていますが、物語の主な舞台となるのはダーリントン・ホールで、世界の趨勢(すうせい)という大局的な渦の中ですれ違う男女の恋を、20年の空白を経ながらも結局は別れてしまわなければならない悲哀を描いています。
でも、湿っぽく終わるのではなくて、ミス・ケントンと別れ、ダーリントン・ホールへ戻ったスティーブンスがルイスと一緒に部屋へ迷い込んだ鳩を逃がしてやるラストは、暗さから明るさへと解き放たれてゆくダーリントン・ホールを象徴しているようで、爽やかな後味を残しました。




1989年に英国最高の栄誉ある文学賞といわれるブッカー賞を受賞したカズオ・イシグロの同名小説を映画化したものですが、映画は原作より一歩踏み込んだといいますか、スティーブンスとミス・ケントンのロマンスは、原作では遠い日のほろ苦い思い出としてポツリポツリと語られるのに対し、映画ではかなり掘り下げて描かれました。
原作のテーマ性と格調の高さを損ねることなく描かれた恋愛映画と見ることもできますが、男女のロマンスを前面に出したことで映画的な成功を収めたといえます。
映画に劣らず原作はかなり感動的です。
大英帝国の過去の栄光と、その中心的役割を果たしたダーリントン・ホールでの国際会議。
イギリスの美しい田舎の風景と共に、そこに生活する素朴な人々との交流を通して、スティーブンスが過去を回想するという形式で語られてゆきます。
大きく動いてゆく時代の中で、ダーリントン卿とスティーブンスの主従関係を軸に描かれた小説「日の名残り」は、偉大な執事としての特質「品格」をストイックなまでに追究したスティーブンスと、没落してゆく貴族社会の華やかな過去の想い出、また、ミス・ケントンとの淡いロマンスと永遠の別れなどが溶け合って、深い哀愁を帯びた感動を与えてくれます。





1993年イギリス
監督ジェームズ・アイヴォリー
原作カズオ・イシグロ
脚本ルイース・プラワー・ジャブバーラ
撮影トニー・ピアース・ロバーツ
音楽リチャード・ロビンズ
〈キャスト〉
アンソニー・ホプキンス エマ・トンプソン
クリストファー・リーブ ジェームズ・フォックス
第66回アカデミー賞主演男優賞、主演女優賞、
監督賞、美術賞他8部門ノミネート
ノーベル賞作家カズオ・イシグロの同名小説を映画化。
台頭するナチス・ドイツに対する政治的判断を誤った貴族の没落を背景に、あまりにも謹厳で職務への忠実さゆえに愛をつかむことのできなかった男と、彼への愛を秘めながら、もう一歩を踏み出すことのできなかった女。
お互いに分かり過ぎるほど気持ちが分かっていながら、すれ違ってゆく男女の悲哀を、「眺めのいい部屋」「モーリス」の名匠ジェームズ・アイヴォリーが重厚に描いた秀作です。

1958年イギリス、イングランド東部オックスフォード。
広大な屋敷、ダーリントン・ホールの以前の持ち主ダーリントン卿(ジェームズ・フォックス)はすでに亡く、現在はアメリカ人の富豪ルイス(クリストファー・リーブ)の手に渡っています。
ダーリントン卿の元で長く執事を務めていたジェームズ・スティーブンス(アンソニー・ホプキンス)は、ダーリントン・ホールの持ち主が変わった現在も執事としてルイスに仕えています。
そんなある日、以前の女中頭ミス・ケントン(エマ・トンプソン)からスティーブンスのもとに手紙が届きます。
娘も成長して手が離れたから、もう一度働かせてもらいたい、といった内容に加えて、結婚生活の陰りをうかがわせる文面にスティーブンスの気持ちはゆらぎ、彼女の元へ出かける決心をします。
ダーリントン・ホールから外の世界へ出たことのないスティーブンスにルイスは車を貸し与え、
「世界を見たほうがいい」と言うルイスに対して、スティーブンスはこう応えます。
「世界のほうから、ここへやってきていましたから」
そして物語は20年前へとさかのぼってゆきます。

1938年、ダーリントン・ホールでは世界の要人が集まり、第一次世界大戦後の莫大な賠償金を負わされたドイツに対する扱いをどうするかで議論が戦わされています。
ダーリントン・ホールの持ち主ダーリントン卿はドイツへの復興援助を主張し、満場の同意を得ますが、それに真っ向から反対をしたのがアメリカ人のルイスでした。
若手の政治家として頭角を現し始めたルイスは、政治は貴族のようなシロウトがするものではなく、プロに任せるべきだと反論。満場の失笑を買います。
しかし、その年の3月にナチス・ドイツはオーストリアを併合。
11月には「水晶の夜」と呼ばれるユダヤ人への迫害が始まります。
時代が大きく動いてゆく中で、ダーリントン・ホールに新しい女中頭が採用されます。
勝気ではあるけど仕事熱心な女性、ミス・ケントンです。
初対面の面接からいきなり悪感情を持ったスティーブンスとミス・ケントンでしたが、厳格な中にも繊細な一面をのぞかせるスティーブンスにミス・ケントンは次第に興味を持ち始めます。
執事という仕事の中で最も重要な特性は“品格”だと考えるスティーブンスは、その言葉通り、柔らかな物腰と穏やかな話しぶりの中に、禁欲的な気高さを感じさせる風格を備えた男性でしたが、男女間の恋愛については、低俗な恋愛小説から学び取ることしかできない、生身の女性心理を理解できない男でもありました。
やがてミス・ケントンは以前からの同僚であったベン(ティム・ピゴット・スミス)に求婚され、スティーブンスへの密かな想いに迷い苦しみながら、ベンとの結婚に踏み切り、町を去ってゆきます。
世界は大きく動き、親ナチスの姿勢を鮮明にしていたダーリントン卿はユダヤ人排斥にも加担しますが、貴族的な人間性を失うことのなかった彼は自分の罪を悔い、世間からも非難を浴びながら次第に正気を失ってゆき、静かに世を去ります。
……そして20年後。
ミス・ケントンからの手紙を受け取ったスティーブンスは彼女との再会を果たしますが、孫の誕生と世話のためにダーリントン・ホールでの仕事ができなくなったことを彼女に告げられ、雨のそぼ降るバス停で、再会を約束することもなく、バスに乗り込んだミス・ケントンをスティーブンスは黙って見つめ、滲む窓ガラスに映るミス・ケントンの涙をこらえた表情が次第に遠ざかってゆきます。

今や名優の域に達したアンソニー・ホプキンスですが、かつて出演した「ジャガーノート」(1974年)、「エレファント・マン」(1980年)などの作品にヒット作はあったものの、神経質なイギリス人といった印象で存在感に乏しく、目立つような俳優ではなかったのですが、それがどうしたことか、突然、強烈な個性派俳優として名を挙げたのが「羊たちの沈黙」(1991年)の高度な知性と異常な精神病を併せ持ったハンニバル・レクター博士でした。
それからの活躍は、ハンニバル・レクターとアンソニー・ホプキンスがダブッて見えるほど強烈なレクター博士のイメージがつきまといました。
本作「日の名残り」ではアカデミー賞の主演男優賞にはノミネートで終わりましたが、その落ち着いた物腰からにじみ出る仕事に対する禁欲的な姿勢と、逆に恋愛に関しては臆病なほど内向的なスティーブンスの人間性は、それまでの自信に満ち溢れたレクター博士のようなキャラクターとは打って変わった人物像を作り上げました。
ミス・ケントンに「ハワーズ・エンド」(1992年)、「父の祈りを」(1993年)、「いつか晴れた日に」(1995年)など、数々の主演女優賞に名前の挙がる実力派のエマ・トンプソン。
個人的には「日の名残り」と同年の作品である「父の祈りを」で演じた女性弁護士ギャレス・ピアースの熱演がとても印象に残っています。
ダーリントン卿に「インドへの道」(1984年)、「ロシア・ハウス」(1990年)、「パトリオット・ゲーム」(1992年)のジェームズ・フォックス。
富豪のアメリカ人、ルイスに「スーパーマン」シリーズ、「デストラップ・死の罠」(1982年)のクリストファー・リーブ。
クリストファー・リーブは1995年に落馬事故を起こし、脊髄損傷のため車イス生活を余儀なくされましたが、以後も社会活動など精力的な活動を続けていましたが、2004年に心不全を発症、惜しまれながら52歳で世を去っています。
第一次から第二次への世界大戦を背景としていますが、物語の主な舞台となるのはダーリントン・ホールで、世界の趨勢(すうせい)という大局的な渦の中ですれ違う男女の恋を、20年の空白を経ながらも結局は別れてしまわなければならない悲哀を描いています。
でも、湿っぽく終わるのではなくて、ミス・ケントンと別れ、ダーリントン・ホールへ戻ったスティーブンスがルイスと一緒に部屋へ迷い込んだ鳩を逃がしてやるラストは、暗さから明るさへと解き放たれてゆくダーリントン・ホールを象徴しているようで、爽やかな後味を残しました。
1989年に英国最高の栄誉ある文学賞といわれるブッカー賞を受賞したカズオ・イシグロの同名小説を映画化したものですが、映画は原作より一歩踏み込んだといいますか、スティーブンスとミス・ケントンのロマンスは、原作では遠い日のほろ苦い思い出としてポツリポツリと語られるのに対し、映画ではかなり掘り下げて描かれました。
原作のテーマ性と格調の高さを損ねることなく描かれた恋愛映画と見ることもできますが、男女のロマンスを前面に出したことで映画的な成功を収めたといえます。
映画に劣らず原作はかなり感動的です。
大英帝国の過去の栄光と、その中心的役割を果たしたダーリントン・ホールでの国際会議。
イギリスの美しい田舎の風景と共に、そこに生活する素朴な人々との交流を通して、スティーブンスが過去を回想するという形式で語られてゆきます。
大きく動いてゆく時代の中で、ダーリントン卿とスティーブンスの主従関係を軸に描かれた小説「日の名残り」は、偉大な執事としての特質「品格」をストイックなまでに追究したスティーブンスと、没落してゆく貴族社会の華やかな過去の想い出、また、ミス・ケントンとの淡いロマンスと永遠の別れなどが溶け合って、深い哀愁を帯びた感動を与えてくれます。

2019年07月21日
映画「アラバマ物語」静かな感動と郷愁の名作
「アラバマ物語」(To Kill a Mockingbird)
1962年アメリカ
監督ロバート・マリガン
原作ハーパー・リー
脚色ホートン・フート
音楽エルマー・バーンスタイン
撮影ラッセル・ハーラン
〈キャスト〉
グレゴリー・ペック メアリー・バダム
フィリップ・アルフォード
& ロバート・デュヴァル
第35回アカデミー賞主演男優賞(グレゴリー・ペック)/脚色賞/美術賞受賞
いろいろな映画を数多く見ていると、ときどき、とても心に残る映画があります。「アラバマ物語」はそうした中の一本で、最初見たときよりも二回目、二回目見たときよりも三回目、三回目よりも四回目と回数が増えるにしたがって深い感動を与えてくれる稀有な映画です。
原題の「To Kill Mockingbird」のMockingbirdはモノマネ鳥、あるいはマネシツグミとも訳され、北アメリカの中部から南に広く分布するこの鳥は、その名前の通り、たくさんの種類の鳥や動物、車の警笛まで美しい声で真似をすることで知られています。
美しい声で鳴くだけで、人間に害を加えることのないマネシツグミを殺すということは、罪のない無力な人間に対する迫害を示唆する、この映画の主要なテーマでもあり、それは映画の中で主人公のアティカス・フィンチが娘にやさしく語りかける場面に現れます。

1932年、アメリカ南部アラバマ州の田舎町。
3年前の1929年10月に起きたニューヨーク・ウォール街の株価大暴落に端を発した世界恐慌の波が地方の片田舎にも押し寄せる中、少女スカウト(メアリー・バダム)と兄のジェム(フィリップ・アルフォード)は元気に遊びまわっています。
スカウトとジェムの前に突然現れた少年ディル(ジョン・メグナ)とも仲良しになり、意気投合した3人は近所に住む風変りな男“ブー”の正体を知りたくて、ある晩、ブーの家に忍び込もうとします。
誰もその顔を見たことのないブーは恐ろしい怪人のイメージをもって知られ、壊れたフェンスのすき間からブーの庭に忍び込んだジェムは、明かりのついていない真っ暗な部屋の中を隙見しようとしますが、その時近づいてきた足音に驚き、フェンスの外で待っているスカウトとディルの元へ逃げ帰ろうします。
しかし、ズボンに引っかかったフェンスが外れず、ジェムはズボンをその場で脱ぎ捨て、一目散に家へ逃げ帰ります。
後に、そのズボンはきちんと畳んでその場に置いてあったことを知ったジェムたちは、“ブー”に対する不可解な謎を深めることになります。

いたずら盛りのジェムとスカウトの父アティカス・フィンチ(グレゴリー・ペック)は弁護士。
妻に先立たれたアティカスは、子どもたちが母親のいない寂しさを抱えていることは知っていますが、現在の自分の置かれている状況に黙って従っています。
そんなある日、貧農で白人のボブ・ユーエル(ジェームズ・アンダーソン)の娘メイエラ(コリン・ウィルコックス)が黒人のトム・ロビンソン(ブロック・ピーターズ)から暴行を受けたと主張し告訴。
アティカスは知人の判事から、誰も引き受け手のいないトム・ロビンソンの弁護を依頼されます。
黒人への差別が激しいことで知られる南部の土地柄、アティカスは弁護の依頼に戸惑いながらも引き受けることにします。
弁護を引き受けたアティカスに対する一部地元住民の反発は激しく、警察署へまで押し寄せた住民たちはトムへの集団リンチに及ぼうとするまで事態は悪化しますが、機転を利かせたスカウトの言葉が殺気立った住民の気勢を削(そ)ぐことになります。
そして裁判の日……。





よくいわれているように、「アラバマ物語」の主人公アティカス・フィンチはアメリカ人が選んだ「アメリカ映画のヒーロー」として、インディ・ジョーンズやジェームズ・ボンドを抜いて堂々の一位になっています。
ちなみに5位が「真昼の決闘」のウィル・ケーンなので、アティカス・フィンチとウィル・ケーンの共通性、選ばれた理由というのは分かる気がします。
勝てる望みの少ない事柄に対して、自分がやらなければ誰も引き受ける者がいないと分かったとき、ウィル・ケーンは死を覚悟して、アティカス・フィンチは人種偏見の激しい迫害を受けて、裁判に負ければ弁護士として無能の烙印を押されかねない状況の中で、決して気負うことなく、淡々と事に当たります。
ウィル・ケーンはかろうじて決闘に勝利しますが、アティカスは全面敗訴します。


人種差別の色濃い南部で、白人のメイエラに対する暴行事件の裁判は、被告のトム・ロビンソンが黒人であるにもかかわらず、十二人の陪審員すべてが白人という極端な不合理の中で行われます。
メイエラの顔の傷跡から、彼女に暴行を加えたのは左利きの男であるとアティカスは断定。被告のトムは左手が不自由であり、メイエラの父ボブ・ユーエルが左利きであることから、トムを巻き込んだ娘と父の争いが原因であり、被告のトムは無実であることが明らかになっていきます。
アティカスは陪審員席に向かって、公正な判断を下すよう滔々(とうとう)と説得を試みます。
しかし、十二人の陪審員全員が下した判決の結果は、トムの有罪でした。

判決後の場面は、この映画の最も感動的なシーンといってもいいと思います。
閉廷して静かになった法廷、アティカスは弁護席でひとり書類を片づけています、傍聴席の二階ではそれを見守る大勢の黒人たち、アティカスの二人の子ども、ジェムとスカウトもその中に混じっています、書類を片づけ終わって法廷を後にするアティカスを二階の全員が黙って見送ります。
誰かが拍手をするわけでもなく、二階の傍聴席の黒人たちにアティカスが応えるでもなく、裁判に負けたアティカスが静かに去っていくこの場面は、アティカス・フィンチに対する黒人たちの敬意がよく表れていて、数多くある映画の名シーンの中でも、ひときわ秀逸なシーンのひとつといえます。
後に被告のトムは護送中に逃走し、威嚇のために発砲した警察官の銃弾がそれてトムは死亡。
二審に望みをつないでいたアティカスは失意に沈みます。




アティカス・フィンチは人並み外れた特別な人間ではありません。体力の衰えを感じ始めた中年のやもめ男です。
温厚で誠実な人柄で知られ、弱い者に対するいたわりの心を持つ優しい男でもあります。
有り体にいってしまえば、どこにでもいる平凡な男ともいえますが、狂犬を射殺する射撃の腕を持っている反面、唾を吐きかけられたボブ・ユーエルへの憤怒をグッと抑える自制心の強さは、並の人間にはなかなか真似ることのできない一面です。
しかし、この人の素晴らしいところは、黒人蔑視の根強い排他的な土地で、誰も引き受ける者のいない弁護を引き受け、周囲からの迫害にも遭いながら、自らの責任や正義を声高に叫ぶこともなく淡々と行動していくところにあります。




監督は「九月になれば」(1961年)、「ジャングル地帯」(1962年)のロバート・マリガン。
後の「おもいでの夏」(1970年)では、思春期の少年の性の目覚めとほろ苦さを、爽やかな感性で描いています。
製作は、「コールガール」(1971年)、「大統領の陰謀」(1976年)、「ソフィーの選択」(1982年)など、社会派の監督として名高いアラン・J・パクラ。
アティカス・フィンチに、「ローマの休日」(1953年)、「白鯨」(1956年)、「大いなる西部」(1958年)など、出演作に名作・傑作の多いハリウッドを代表する大スター、グレゴリー・ペック。
アティカスの娘スカウトに、「サタデー・ナイト・フィーバー」(1977年)でヒットをとばし、「ウォー・ゲーム」(1983年)、「ブルーサンダー」(1983年)、「アサシン」(1993年)などの軽快なアクション映画を得意とするジョン・バダム監督の妹メアリー・バダム。
成長したスカウトが少女時代を回想するという形式で描かれるこの映画は、法廷劇を主軸にしながら、スカウトの視点でとらえた大人の世界と、古タイヤなどで生き生きと遊びまわる子どもたちの世界を、郷愁を込めて描いた名作です。







1962年アメリカ
監督ロバート・マリガン
原作ハーパー・リー
脚色ホートン・フート
音楽エルマー・バーンスタイン
撮影ラッセル・ハーラン
〈キャスト〉
グレゴリー・ペック メアリー・バダム
フィリップ・アルフォード
& ロバート・デュヴァル
第35回アカデミー賞主演男優賞(グレゴリー・ペック)/脚色賞/美術賞受賞
いろいろな映画を数多く見ていると、ときどき、とても心に残る映画があります。「アラバマ物語」はそうした中の一本で、最初見たときよりも二回目、二回目見たときよりも三回目、三回目よりも四回目と回数が増えるにしたがって深い感動を与えてくれる稀有な映画です。
原題の「To Kill Mockingbird」のMockingbirdはモノマネ鳥、あるいはマネシツグミとも訳され、北アメリカの中部から南に広く分布するこの鳥は、その名前の通り、たくさんの種類の鳥や動物、車の警笛まで美しい声で真似をすることで知られています。
美しい声で鳴くだけで、人間に害を加えることのないマネシツグミを殺すということは、罪のない無力な人間に対する迫害を示唆する、この映画の主要なテーマでもあり、それは映画の中で主人公のアティカス・フィンチが娘にやさしく語りかける場面に現れます。

1932年、アメリカ南部アラバマ州の田舎町。
3年前の1929年10月に起きたニューヨーク・ウォール街の株価大暴落に端を発した世界恐慌の波が地方の片田舎にも押し寄せる中、少女スカウト(メアリー・バダム)と兄のジェム(フィリップ・アルフォード)は元気に遊びまわっています。
スカウトとジェムの前に突然現れた少年ディル(ジョン・メグナ)とも仲良しになり、意気投合した3人は近所に住む風変りな男“ブー”の正体を知りたくて、ある晩、ブーの家に忍び込もうとします。
誰もその顔を見たことのないブーは恐ろしい怪人のイメージをもって知られ、壊れたフェンスのすき間からブーの庭に忍び込んだジェムは、明かりのついていない真っ暗な部屋の中を隙見しようとしますが、その時近づいてきた足音に驚き、フェンスの外で待っているスカウトとディルの元へ逃げ帰ろうします。
しかし、ズボンに引っかかったフェンスが外れず、ジェムはズボンをその場で脱ぎ捨て、一目散に家へ逃げ帰ります。
後に、そのズボンはきちんと畳んでその場に置いてあったことを知ったジェムたちは、“ブー”に対する不可解な謎を深めることになります。

いたずら盛りのジェムとスカウトの父アティカス・フィンチ(グレゴリー・ペック)は弁護士。
妻に先立たれたアティカスは、子どもたちが母親のいない寂しさを抱えていることは知っていますが、現在の自分の置かれている状況に黙って従っています。
そんなある日、貧農で白人のボブ・ユーエル(ジェームズ・アンダーソン)の娘メイエラ(コリン・ウィルコックス)が黒人のトム・ロビンソン(ブロック・ピーターズ)から暴行を受けたと主張し告訴。
アティカスは知人の判事から、誰も引き受け手のいないトム・ロビンソンの弁護を依頼されます。
黒人への差別が激しいことで知られる南部の土地柄、アティカスは弁護の依頼に戸惑いながらも引き受けることにします。
弁護を引き受けたアティカスに対する一部地元住民の反発は激しく、警察署へまで押し寄せた住民たちはトムへの集団リンチに及ぼうとするまで事態は悪化しますが、機転を利かせたスカウトの言葉が殺気立った住民の気勢を削(そ)ぐことになります。
そして裁判の日……。

よくいわれているように、「アラバマ物語」の主人公アティカス・フィンチはアメリカ人が選んだ「アメリカ映画のヒーロー」として、インディ・ジョーンズやジェームズ・ボンドを抜いて堂々の一位になっています。
ちなみに5位が「真昼の決闘」のウィル・ケーンなので、アティカス・フィンチとウィル・ケーンの共通性、選ばれた理由というのは分かる気がします。
勝てる望みの少ない事柄に対して、自分がやらなければ誰も引き受ける者がいないと分かったとき、ウィル・ケーンは死を覚悟して、アティカス・フィンチは人種偏見の激しい迫害を受けて、裁判に負ければ弁護士として無能の烙印を押されかねない状況の中で、決して気負うことなく、淡々と事に当たります。
ウィル・ケーンはかろうじて決闘に勝利しますが、アティカスは全面敗訴します。
人種差別の色濃い南部で、白人のメイエラに対する暴行事件の裁判は、被告のトム・ロビンソンが黒人であるにもかかわらず、十二人の陪審員すべてが白人という極端な不合理の中で行われます。
メイエラの顔の傷跡から、彼女に暴行を加えたのは左利きの男であるとアティカスは断定。被告のトムは左手が不自由であり、メイエラの父ボブ・ユーエルが左利きであることから、トムを巻き込んだ娘と父の争いが原因であり、被告のトムは無実であることが明らかになっていきます。
アティカスは陪審員席に向かって、公正な判断を下すよう滔々(とうとう)と説得を試みます。
しかし、十二人の陪審員全員が下した判決の結果は、トムの有罪でした。

判決後の場面は、この映画の最も感動的なシーンといってもいいと思います。
閉廷して静かになった法廷、アティカスは弁護席でひとり書類を片づけています、傍聴席の二階ではそれを見守る大勢の黒人たち、アティカスの二人の子ども、ジェムとスカウトもその中に混じっています、書類を片づけ終わって法廷を後にするアティカスを二階の全員が黙って見送ります。
誰かが拍手をするわけでもなく、二階の傍聴席の黒人たちにアティカスが応えるでもなく、裁判に負けたアティカスが静かに去っていくこの場面は、アティカス・フィンチに対する黒人たちの敬意がよく表れていて、数多くある映画の名シーンの中でも、ひときわ秀逸なシーンのひとつといえます。
後に被告のトムは護送中に逃走し、威嚇のために発砲した警察官の銃弾がそれてトムは死亡。
二審に望みをつないでいたアティカスは失意に沈みます。
アティカス・フィンチは人並み外れた特別な人間ではありません。体力の衰えを感じ始めた中年のやもめ男です。
温厚で誠実な人柄で知られ、弱い者に対するいたわりの心を持つ優しい男でもあります。
有り体にいってしまえば、どこにでもいる平凡な男ともいえますが、狂犬を射殺する射撃の腕を持っている反面、唾を吐きかけられたボブ・ユーエルへの憤怒をグッと抑える自制心の強さは、並の人間にはなかなか真似ることのできない一面です。
しかし、この人の素晴らしいところは、黒人蔑視の根強い排他的な土地で、誰も引き受ける者のいない弁護を引き受け、周囲からの迫害にも遭いながら、自らの責任や正義を声高に叫ぶこともなく淡々と行動していくところにあります。
監督は「九月になれば」(1961年)、「ジャングル地帯」(1962年)のロバート・マリガン。
後の「おもいでの夏」(1970年)では、思春期の少年の性の目覚めとほろ苦さを、爽やかな感性で描いています。
製作は、「コールガール」(1971年)、「大統領の陰謀」(1976年)、「ソフィーの選択」(1982年)など、社会派の監督として名高いアラン・J・パクラ。
アティカス・フィンチに、「ローマの休日」(1953年)、「白鯨」(1956年)、「大いなる西部」(1958年)など、出演作に名作・傑作の多いハリウッドを代表する大スター、グレゴリー・ペック。
アティカスの娘スカウトに、「サタデー・ナイト・フィーバー」(1977年)でヒットをとばし、「ウォー・ゲーム」(1983年)、「ブルーサンダー」(1983年)、「アサシン」(1993年)などの軽快なアクション映画を得意とするジョン・バダム監督の妹メアリー・バダム。
成長したスカウトが少女時代を回想するという形式で描かれるこの映画は、法廷劇を主軸にしながら、スカウトの視点でとらえた大人の世界と、古タイヤなどで生き生きと遊びまわる子どもたちの世界を、郷愁を込めて描いた名作です。

2019年07月16日
映画「影の軍隊」レジスタンスの活動家たちの悲劇
「影の軍隊」(L' ARMEE DES OMBRES)
1969年 フランス
脚本・監督ジャン=ピエール・メルヴィル
原作ジョゼフ・ケッセル
撮影ピエール・ロム
音楽エリック・ド・マルサン
美術テオバール・ムーリッス
〈キャスト〉
リノ・ヴァンチュラ シモーヌ・シニョレ
ジャン=ピエール・カッセル
巨匠ジャン=ピエール・メルヴィル監督によるドイツ占領下でのフランス、レジスタンスに身を投じた活動家たちの悲劇を、明るさを排した重厚な映像美の中に徹底したリアリズムで描き切った傑作。

1942年10月20日。
一人の男がジープに乗せられ、収容所に連れられてきます。
男の名前はフィリップ・ジェルビエ(リノ・ヴァンチュラ)、土木技師。
収容所に入れられたジェルビエは、同じ部屋に収容されている数人の男、そして収容所に入れられている人間たちの国籍を冷静に観察していきます。
ある夜、ジェルビエは同じ部屋の若者から脱走の話を持ちかけられますが、計画を実行に移す間もなくパリのゲシュタポ本部へと身柄を移されたジェルビエは、隣に座っている男に、ここから逃げるよう勧め、ドイツ兵の注意が男に集中した隙を狙って逃走します。
ジェルビエという男の冷徹な非情さが表現されたここまでの描写は、ほとんど何の説明もないまま淡々と進行していきます。


パリの凱旋門の前をドイツ兵が行進するシーンで始まるこの映画は、パリはすでに陥落し、フランスはドイツの占領下に置かれていることが判るだけで、ジェルビエの行動が何を意味しているのかは判然としません。
ぬかるんだ田舎道。寒々とした収容所。静かなパリの夜を逃走するジェルビエの靴音。沈鬱な男たちの表情。ユトリロの絵画を見るような風景描写。
ムダなセリフを省き、男たちの行動だけですべてを語らせるジャン=ピエール・メルヴィルの美学は、退廃的ともいえる雰囲気の中で動き出していきます。
逃走に成功したジェルビエはマルセイユに向かい、仲間と接触してひとりの若者ドゥナ(アラン・リボール)をアパートの一室に連れ込みます。
ジェルビエと仲間のフェリックス(ポール・クローシェ)、ル・ビゾン(クリスチャン・バルビエール)、ル・マスク(クロード・マン)は、ドゥナを椅子に座らせ、ジェルビエを密告した罪により処刑をしようとします。
最初はピストルで殺そうとしますが、隣室との壁が薄く、音が聞こえるといけないというので、絞殺に切りかえて行われます。
かなり陰惨なこのシーンも、ジェルビエたちの組織の背景がよく分からないので、事情が呑み込めないままメルヴィルの世界に入ってゆくのですが、やがてそれはドラマが進行するにつれて明らかになっていきます。

ドイツ占領下のフランス、といってもフランス全土が反ナチスだったわけではなく、当然ながら親ナチスも存在したわけで、そのあたりはルイ・マル監督の秀作「ルシアンの青春」(1973年)でもフランス社会の複雑な陰影が描かれています。
当時のフランス政府は“ヴィシー政権”。
フランスの首都パリから列車で4時間ほどの中部アリエ県の町ヴィシーに臨時政府を置いたことからそう呼ばれました。
ヴィシー政権を主導したのは第一次世界大戦の英雄フィリップ・ペタン元帥。
ペタンは、フランスの主権存続のためにドイツ・イタリアと休戦協定を結び、ドイツとの友好関係を築こうとします。
一方、49歳の若さで少将となった国防次官のシャルル・ド・ゴールはドイツとの徹底抗戦を主張。
ド・ゴールはロンドンへ逃れ、イギリスの協力を得るためにウィンストン・チャーチルとの交渉を始め、フランス全土にドイツに対する抵抗運動(レジスタンス)を呼びかけます。
フランス国内ではドイツ軍が駐留し、ヒトラーとの友好関係を結ぼうとするヴィシー政権はレジスタンスの取り締まりを強化。
ジェルビエたちはそのような内政状況の中で地下へ潜り、息をひそめるようにして活動をしていることになります。
しかも、レジスタンスといっても一枚岩ではなく、右派もいれば左派もいるといった、身内の内部対立を抱えた組織であったことがうかがえます。


映画「影の軍隊」では、密告した仲間を処刑したり、ドイツ軍に捕まって拷問を受けたり、仲間同士の暗殺があったりと、表面には出にくい組織の内情が描かれていきます。
「大列車作戦」(1964年)のバート・ランカスターのように機関銃を撃ちまくって暴れ回るわけでもなく、「情婦マノン」(1949年)のミシェル・オークレールのように恋人と一緒に国外へ逃亡するわけでもありません。
裏切りと密告、拷問と死が日常となっている彼ら(レジタンスの活動家)にとって、信頼できる仲間の存在は絶対であり、仲間が死の危険に陥ったときには命がけで救おうとします。
そのひとつを象徴するエピソードがジェルビエの逮捕です。
ゲシュタポに逮捕され、銃殺寸前の瞬間に煙幕が立ち込め、隙を狙って建物から下りてきたロープにジェルビエはつかまります。
さらに、そこからジェルビエを引き上げる手が伸び、その手に必死につかまるジェルビエ。
手と手のクローズアップは「影の軍隊」の全編を通して最も象徴的であり、感動的です。
ジェルビエ救出作戦を指導したのはパリに住む女性活動家マチルド(シモーヌ・シニョレ)。
尊敬と信頼関係で結ばれるジェルビエとマチルドは中年男女の大人の恋を思わせる雰囲気を醸し出しますが、そのマチルドが逮捕されてしまったとき、ジェルビエは冷然とマチルドを殺すことを仲間に命じます。
マチルドの娘の身元をゲシュタポに握られ、娘への愛情からマチルドが仲間を密告することをジェルビエは恐れたからなのですが、感情の入り込む余地のない鉄の規律を絶対とする組織の非情さ、その非情さがなければレジスタンスを戦い抜くことが難しい、ナチス支配下の極度に緊張した社会情勢が伝わってきます。
その後、マチルドは路上で射殺され、グループのボスであったリュック・ジャルディ(ポール・ムーリス)を始め、ジェルビエと仲間たちすべては逮捕や処刑によって命を落とすことが映画のラストで示されます。
やり切れなさの残るラストですが、同時に、暗黒の時代を命を懸けて走り続けた活動家たちの切なさが胸に迫るラストでもあります。

監督はジャン=ピエール・メルヴィル。
前作「サムライ」(1967年)では人気絶頂のアラン・ドロンを起用。
ドロンはそれまでの甘さをそぎ落とし、暗黒街に生きる孤独な殺し屋を好演して映画は大ヒット。
メルヴィルはフィルムノワールの代表的監督として日本でもよく知られるようになりました。
主役のジェルビエに「死刑台のエレベーター」(1958年)、「モンパルナスの灯」(1958年)の名優リノ・ヴァンチュラ。
パリの女性活動家マチルドに「嘆きのテレーズ」(1952年)、「悪魔のような女」(1955年)の名女優シモーヌ・シニョレ。
パリのゲシュタポ本部を逃走したジェルビエが逃げ込んだ理髪店の店主に、「山猫」(1963年)、「冒険者たち」(1967年)で味わいのある演技を見せたセルジュ・レジアニが特別出演。
ポール・ムーリス、ポール・クローシェなど、フランス映画界に欠かせない名脇役たちが顔をそろえたフィルムノワールの傑作です。





1969年 フランス
脚本・監督ジャン=ピエール・メルヴィル
原作ジョゼフ・ケッセル
撮影ピエール・ロム
音楽エリック・ド・マルサン
美術テオバール・ムーリッス
〈キャスト〉
リノ・ヴァンチュラ シモーヌ・シニョレ
ジャン=ピエール・カッセル
巨匠ジャン=ピエール・メルヴィル監督によるドイツ占領下でのフランス、レジスタンスに身を投じた活動家たちの悲劇を、明るさを排した重厚な映像美の中に徹底したリアリズムで描き切った傑作。

1942年10月20日。
一人の男がジープに乗せられ、収容所に連れられてきます。
男の名前はフィリップ・ジェルビエ(リノ・ヴァンチュラ)、土木技師。
収容所に入れられたジェルビエは、同じ部屋に収容されている数人の男、そして収容所に入れられている人間たちの国籍を冷静に観察していきます。
ある夜、ジェルビエは同じ部屋の若者から脱走の話を持ちかけられますが、計画を実行に移す間もなくパリのゲシュタポ本部へと身柄を移されたジェルビエは、隣に座っている男に、ここから逃げるよう勧め、ドイツ兵の注意が男に集中した隙を狙って逃走します。
ジェルビエという男の冷徹な非情さが表現されたここまでの描写は、ほとんど何の説明もないまま淡々と進行していきます。
パリの凱旋門の前をドイツ兵が行進するシーンで始まるこの映画は、パリはすでに陥落し、フランスはドイツの占領下に置かれていることが判るだけで、ジェルビエの行動が何を意味しているのかは判然としません。
ぬかるんだ田舎道。寒々とした収容所。静かなパリの夜を逃走するジェルビエの靴音。沈鬱な男たちの表情。ユトリロの絵画を見るような風景描写。
ムダなセリフを省き、男たちの行動だけですべてを語らせるジャン=ピエール・メルヴィルの美学は、退廃的ともいえる雰囲気の中で動き出していきます。
逃走に成功したジェルビエはマルセイユに向かい、仲間と接触してひとりの若者ドゥナ(アラン・リボール)をアパートの一室に連れ込みます。
ジェルビエと仲間のフェリックス(ポール・クローシェ)、ル・ビゾン(クリスチャン・バルビエール)、ル・マスク(クロード・マン)は、ドゥナを椅子に座らせ、ジェルビエを密告した罪により処刑をしようとします。
最初はピストルで殺そうとしますが、隣室との壁が薄く、音が聞こえるといけないというので、絞殺に切りかえて行われます。
かなり陰惨なこのシーンも、ジェルビエたちの組織の背景がよく分からないので、事情が呑み込めないままメルヴィルの世界に入ってゆくのですが、やがてそれはドラマが進行するにつれて明らかになっていきます。

ドイツ占領下のフランス、といってもフランス全土が反ナチスだったわけではなく、当然ながら親ナチスも存在したわけで、そのあたりはルイ・マル監督の秀作「ルシアンの青春」(1973年)でもフランス社会の複雑な陰影が描かれています。
当時のフランス政府は“ヴィシー政権”。
フランスの首都パリから列車で4時間ほどの中部アリエ県の町ヴィシーに臨時政府を置いたことからそう呼ばれました。
ヴィシー政権を主導したのは第一次世界大戦の英雄フィリップ・ペタン元帥。
ペタンは、フランスの主権存続のためにドイツ・イタリアと休戦協定を結び、ドイツとの友好関係を築こうとします。
一方、49歳の若さで少将となった国防次官のシャルル・ド・ゴールはドイツとの徹底抗戦を主張。
ド・ゴールはロンドンへ逃れ、イギリスの協力を得るためにウィンストン・チャーチルとの交渉を始め、フランス全土にドイツに対する抵抗運動(レジスタンス)を呼びかけます。
フランス国内ではドイツ軍が駐留し、ヒトラーとの友好関係を結ぼうとするヴィシー政権はレジスタンスの取り締まりを強化。
ジェルビエたちはそのような内政状況の中で地下へ潜り、息をひそめるようにして活動をしていることになります。
しかも、レジスタンスといっても一枚岩ではなく、右派もいれば左派もいるといった、身内の内部対立を抱えた組織であったことがうかがえます。
映画「影の軍隊」では、密告した仲間を処刑したり、ドイツ軍に捕まって拷問を受けたり、仲間同士の暗殺があったりと、表面には出にくい組織の内情が描かれていきます。
「大列車作戦」(1964年)のバート・ランカスターのように機関銃を撃ちまくって暴れ回るわけでもなく、「情婦マノン」(1949年)のミシェル・オークレールのように恋人と一緒に国外へ逃亡するわけでもありません。
裏切りと密告、拷問と死が日常となっている彼ら(レジタンスの活動家)にとって、信頼できる仲間の存在は絶対であり、仲間が死の危険に陥ったときには命がけで救おうとします。
そのひとつを象徴するエピソードがジェルビエの逮捕です。
ゲシュタポに逮捕され、銃殺寸前の瞬間に煙幕が立ち込め、隙を狙って建物から下りてきたロープにジェルビエはつかまります。
さらに、そこからジェルビエを引き上げる手が伸び、その手に必死につかまるジェルビエ。
手と手のクローズアップは「影の軍隊」の全編を通して最も象徴的であり、感動的です。
ジェルビエ救出作戦を指導したのはパリに住む女性活動家マチルド(シモーヌ・シニョレ)。
尊敬と信頼関係で結ばれるジェルビエとマチルドは中年男女の大人の恋を思わせる雰囲気を醸し出しますが、そのマチルドが逮捕されてしまったとき、ジェルビエは冷然とマチルドを殺すことを仲間に命じます。
マチルドの娘の身元をゲシュタポに握られ、娘への愛情からマチルドが仲間を密告することをジェルビエは恐れたからなのですが、感情の入り込む余地のない鉄の規律を絶対とする組織の非情さ、その非情さがなければレジスタンスを戦い抜くことが難しい、ナチス支配下の極度に緊張した社会情勢が伝わってきます。
その後、マチルドは路上で射殺され、グループのボスであったリュック・ジャルディ(ポール・ムーリス)を始め、ジェルビエと仲間たちすべては逮捕や処刑によって命を落とすことが映画のラストで示されます。
やり切れなさの残るラストですが、同時に、暗黒の時代を命を懸けて走り続けた活動家たちの切なさが胸に迫るラストでもあります。

監督はジャン=ピエール・メルヴィル。
前作「サムライ」(1967年)では人気絶頂のアラン・ドロンを起用。
ドロンはそれまでの甘さをそぎ落とし、暗黒街に生きる孤独な殺し屋を好演して映画は大ヒット。
メルヴィルはフィルムノワールの代表的監督として日本でもよく知られるようになりました。
主役のジェルビエに「死刑台のエレベーター」(1958年)、「モンパルナスの灯」(1958年)の名優リノ・ヴァンチュラ。
パリの女性活動家マチルドに「嘆きのテレーズ」(1952年)、「悪魔のような女」(1955年)の名女優シモーヌ・シニョレ。
パリのゲシュタポ本部を逃走したジェルビエが逃げ込んだ理髪店の店主に、「山猫」(1963年)、「冒険者たち」(1967年)で味わいのある演技を見せたセルジュ・レジアニが特別出演。
ポール・ムーリス、ポール・クローシェなど、フランス映画界に欠かせない名脇役たちが顔をそろえたフィルムノワールの傑作です。

2019年07月12日
映画「ファイナル・カウントダウン」世界最強の原子力空母ニミッツが真珠湾攻撃直前のハワイ沖へタイムスリップ
「ファイナル・カウントダウン」
(The Final Countdown) 1980年アメリカ
監督ドン・テイラー
脚本デイヴィッド・アンブローズ
ピーター・パウエル
ゲイリー・デーヴィス
トーマス・ハンター
音楽ジョン・スコット
撮影ヴィクター・J・ケンパー
〈キャスト〉
カーク・ダグラス マーティン・シーン
キャサリン・ロス チャールズ・ダーニング
1945年の第二次世界大戦の終結と、東西冷戦下で予想される第三次世界大戦の勃発。そのような中で世界の覇権を目指そうとするアメリカは軍事力を強化。
1958年には世界初の原子力空母「エンタープライズ」が建造を開始して1961年に就役。続く1975年には原子力空母「ニミッツ」が就役します。
長距離空対空ミサイルを搭載したF-14トムキャットなどの艦上戦闘機を搭載した「ニミッツ級」は現在でも「海に浮かぶ都市」と形容され世界最大・最強を誇っています(F-14トムキャットは2006年に退役)。
「ファイナル・カウントダウン」は、その原子力空母「ニミッツ」がハワイ沖を航行中に、1941年の日本海軍による真珠湾攻撃直前にタイムスリップしてしまうお話し。
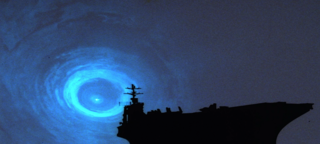
1980年。
民間人のウォーレン・ラスキー(マーティン・シーン)が「ニミッツ」乗艦のために海軍のヘリに乗り込むところから物語は始まります。
彼は大手企業タイドマン社からニミッツの視察を命じられた人物で、海軍基地に停まっている車の中にはラスキーの乗艦を見守るタイドマン社の社長の人影。
ラスキーは社長に挨拶をしようと近寄りますが、挨拶は拒まれます。
この顔の見えない謎の人物はストーリーのオチとして最後に再び登場するのですが、それはそれとして。
ハワイ沖を航行中のニミッツに乗り込んだラスキーは艦長のマシュー・イーランド海軍大佐(カーク・ダグラス)に迎えられ、あてがわれた部屋へと案内されます。
その日の気象予報では好天のはずだったのが、突如雷雲が発生したとの気象係の連絡をイーランドは受けます。
気温も下がり、気圧は急激に下がっていきます。荒れ模様となった天候の中、危険を感じたイーランドは真珠湾へ引き返そうとしますが、突如として海上に巨大な渦巻きが発生してニミッツを飲み込みます。

計器類は故障。気圧の急激な低下によるものか、低周波の影響なのか、乗員のすべてが極度の頭痛に襲われる中、しばらくして渦巻きは消え、海上は再び穏やかさを取り戻します。
レーダーは正常に戻り、音声をとらえますが、それは現在使われていない旧式の暗号で、ソ連とアメリカ、それにドイツが開戦したというものでした。
第三次世界大戦の勃発かと緊張の走る中、ラジオからはすでに亡くなっているはずのジャック・ベニーの放送が流れています。
イーランドはE-2早期警戒機を飛ばし周囲の状況を偵察しようとしますが、戻って来たE-2がとらえた航空写真には、1941年当時そのままに“アリゾナ”“ウェストバージニア”“テネシー”などの戦艦が真珠湾に無傷で停泊しています。


ニミッツ上空を飛来する日本のゼロ戦。
洋上には時代遅れのヨットが一隻。
不可解な事態にラスキーはタイムスリップを予感しますが、状況を飲み込めない乗員との間で激しい議論が戦わされる中、ゼロ戦が洋上のヨットを攻撃し始めます。
ヨット救出のためにニミッツから飛び立ったF-14はゼロ戦とのドッグファイトを展開しますが、いくらゼロ戦が無敵の格闘性能を誇っているとはいえ、近代兵器を装備し、マッハの速度を持つトムキャットの敵ではなく、2機のゼロ戦はあえなく撃墜されてしまいます。
ゼロ戦に攻撃されて転覆したヨットから救出されたのは、1944年の大統領選挙の候補とされている民主党の上院議員サミュエル・S・チャップマン(チャールズ・ダーニング)と、彼の秘書ローレル(キャサリン・ロス)、そしてローレルの愛犬チャーリー。
救出されたチャップマンは次期大統領と目されている人物で、彼は本来、1941年12月7日に行方不明になるはずでした。
そのまま生存していれば、1944年の次期大統領は民主党のフランクリン・ルーズベルトではなくサミュエル・S・チャップマンが大統領職に就くことになります。
すでに歴史に介入してしまった「ニミッツ」。
さらにイーランドは、撃墜したゼロ戦の戦闘員で捕虜となったシムラの口から、日本海軍の空母6隻が千島列島を離れ、真珠湾へ進撃していることを知ります。
歴史的事実である日本軍の真珠湾攻撃を翌日の未明に控え、イーランドは歴史に介入するか否かの決断を迫られますが、軍人としての責務を果たす、として介入を決断。
中国全土を完全制覇した高い空戦性能を持つゼロ戦を擁して連戦連勝の勢いに乗る日本海軍対F-14などの最新鋭の要撃・攻撃機を擁する原子力空母「ニミッツ」の決戦は、最終的な秒読み“ファイナル・カウントダウン”に入ってゆきます。






製作費2000万ドルの巨費を投じ、アメリカ海軍の全面的な協力のもとに作られた「ファイナル・カウントダウン」は、アメリカ国民が最も屈辱を感じるとされる日本海軍による「真珠湾攻撃」の前日に、アメリカが誇る世界最強の原子力空母「ニミッツ」がハワイ沖にタイムスリップをするという、いわば時空を超えた雪辱戦が展開される、というストーリー。
監督は「トム・ソーヤーの冒険」(1973年)、「ドクター・モローの島」(1977年)のドン・テイラー。
この人は俳優としても「花嫁の父」(1950年)、「第十七捕虜収容所」(1953年)などの出演作があります。
ニミッツの艦長に「炎の人ゴッホ」(1956年)、「OK牧場の決斗」(1957年)、「スパルタカス」(1960年)などの大スター、カーク・ダグラス。
ニミッツの視察に乗り込むウォーレン・ラスキーに、「地獄の逃避行」(1973)、「地獄の黙示録」(1979年)のマーティン・シーン。
マーティン・シーンはテレンス・マリックの監督デビュー作「地獄の逃避行」の主役以降、あまりパッとしない俳優でしたが、「地獄の黙示録」の主役がスティーブ・マックイーンやハリソン・フォードらの相次ぐ降板によって主役の座をつかみ、後には「ウォール街」(1987年)で息子で三男のチャーリー・シーンと共演するなど、数多くの映画に出演。
しかし映画「ファイナル・カウントダウン」の主役は、カーク・ダグラスでもマーティン・シーンでもありません。
主役は原子力空母ニミッツであり、F-14トムキャットであるといってもいいと思います。

タイムスリップを題材にしたSF映画ですが、過去に遡(さかのぼ)ることに対するタイムパラドックスにおける問題とか(ラスキーと乗員との論争はありますが)、複雑な話はワキへ置いといて、原子力空母ニミッツやF-14トムキャットなど、すべて本物を使った迫力は圧倒的で、そのために、アメリカの軍事力を誇示したいだけの映画と見られても仕方のない面はあります。
私は以前、陸上自衛隊明野駐屯地(三重県)での航空ショーをのぞきに行ったことがありますが、間近で見る対戦車ヘリAH-1Sコブラや、F-2、F-15といった戦闘機の迫力に驚いたことがあります。
現在の主流であるステルス戦闘機のF-35はずんぐりむっくりした体型になってしまいましたが、「ファイナル・カウントダウン」に登場するF-14トムキャットは、そのしなやかな機体から人気は高く、退役した現在でも人気の衰えていない艦上戦闘機です。
すべてが本物志向の「ファイナル・カウントダウン」(さすがにゼロ戦はニセモノですが)、ストーリー的にはやや肩透かしをくらう面は否めませんが、コンピューターグラフィックスに頼らない本物の迫力を楽しめる映画です。





(The Final Countdown) 1980年アメリカ
監督ドン・テイラー
脚本デイヴィッド・アンブローズ
ピーター・パウエル
ゲイリー・デーヴィス
トーマス・ハンター
音楽ジョン・スコット
撮影ヴィクター・J・ケンパー
〈キャスト〉
カーク・ダグラス マーティン・シーン
キャサリン・ロス チャールズ・ダーニング
1945年の第二次世界大戦の終結と、東西冷戦下で予想される第三次世界大戦の勃発。そのような中で世界の覇権を目指そうとするアメリカは軍事力を強化。
1958年には世界初の原子力空母「エンタープライズ」が建造を開始して1961年に就役。続く1975年には原子力空母「ニミッツ」が就役します。
長距離空対空ミサイルを搭載したF-14トムキャットなどの艦上戦闘機を搭載した「ニミッツ級」は現在でも「海に浮かぶ都市」と形容され世界最大・最強を誇っています(F-14トムキャットは2006年に退役)。
「ファイナル・カウントダウン」は、その原子力空母「ニミッツ」がハワイ沖を航行中に、1941年の日本海軍による真珠湾攻撃直前にタイムスリップしてしまうお話し。
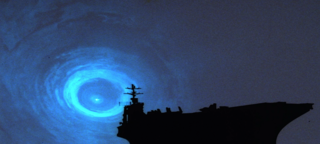
1980年。
民間人のウォーレン・ラスキー(マーティン・シーン)が「ニミッツ」乗艦のために海軍のヘリに乗り込むところから物語は始まります。
彼は大手企業タイドマン社からニミッツの視察を命じられた人物で、海軍基地に停まっている車の中にはラスキーの乗艦を見守るタイドマン社の社長の人影。
ラスキーは社長に挨拶をしようと近寄りますが、挨拶は拒まれます。
この顔の見えない謎の人物はストーリーのオチとして最後に再び登場するのですが、それはそれとして。
ハワイ沖を航行中のニミッツに乗り込んだラスキーは艦長のマシュー・イーランド海軍大佐(カーク・ダグラス)に迎えられ、あてがわれた部屋へと案内されます。
その日の気象予報では好天のはずだったのが、突如雷雲が発生したとの気象係の連絡をイーランドは受けます。
気温も下がり、気圧は急激に下がっていきます。荒れ模様となった天候の中、危険を感じたイーランドは真珠湾へ引き返そうとしますが、突如として海上に巨大な渦巻きが発生してニミッツを飲み込みます。

計器類は故障。気圧の急激な低下によるものか、低周波の影響なのか、乗員のすべてが極度の頭痛に襲われる中、しばらくして渦巻きは消え、海上は再び穏やかさを取り戻します。
レーダーは正常に戻り、音声をとらえますが、それは現在使われていない旧式の暗号で、ソ連とアメリカ、それにドイツが開戦したというものでした。
第三次世界大戦の勃発かと緊張の走る中、ラジオからはすでに亡くなっているはずのジャック・ベニーの放送が流れています。
イーランドはE-2早期警戒機を飛ばし周囲の状況を偵察しようとしますが、戻って来たE-2がとらえた航空写真には、1941年当時そのままに“アリゾナ”“ウェストバージニア”“テネシー”などの戦艦が真珠湾に無傷で停泊しています。
ニミッツ上空を飛来する日本のゼロ戦。
洋上には時代遅れのヨットが一隻。
不可解な事態にラスキーはタイムスリップを予感しますが、状況を飲み込めない乗員との間で激しい議論が戦わされる中、ゼロ戦が洋上のヨットを攻撃し始めます。
ヨット救出のためにニミッツから飛び立ったF-14はゼロ戦とのドッグファイトを展開しますが、いくらゼロ戦が無敵の格闘性能を誇っているとはいえ、近代兵器を装備し、マッハの速度を持つトムキャットの敵ではなく、2機のゼロ戦はあえなく撃墜されてしまいます。
ゼロ戦に攻撃されて転覆したヨットから救出されたのは、1944年の大統領選挙の候補とされている民主党の上院議員サミュエル・S・チャップマン(チャールズ・ダーニング)と、彼の秘書ローレル(キャサリン・ロス)、そしてローレルの愛犬チャーリー。
救出されたチャップマンは次期大統領と目されている人物で、彼は本来、1941年12月7日に行方不明になるはずでした。
そのまま生存していれば、1944年の次期大統領は民主党のフランクリン・ルーズベルトではなくサミュエル・S・チャップマンが大統領職に就くことになります。
すでに歴史に介入してしまった「ニミッツ」。
さらにイーランドは、撃墜したゼロ戦の戦闘員で捕虜となったシムラの口から、日本海軍の空母6隻が千島列島を離れ、真珠湾へ進撃していることを知ります。
歴史的事実である日本軍の真珠湾攻撃を翌日の未明に控え、イーランドは歴史に介入するか否かの決断を迫られますが、軍人としての責務を果たす、として介入を決断。
中国全土を完全制覇した高い空戦性能を持つゼロ戦を擁して連戦連勝の勢いに乗る日本海軍対F-14などの最新鋭の要撃・攻撃機を擁する原子力空母「ニミッツ」の決戦は、最終的な秒読み“ファイナル・カウントダウン”に入ってゆきます。
製作費2000万ドルの巨費を投じ、アメリカ海軍の全面的な協力のもとに作られた「ファイナル・カウントダウン」は、アメリカ国民が最も屈辱を感じるとされる日本海軍による「真珠湾攻撃」の前日に、アメリカが誇る世界最強の原子力空母「ニミッツ」がハワイ沖にタイムスリップをするという、いわば時空を超えた雪辱戦が展開される、というストーリー。
監督は「トム・ソーヤーの冒険」(1973年)、「ドクター・モローの島」(1977年)のドン・テイラー。
この人は俳優としても「花嫁の父」(1950年)、「第十七捕虜収容所」(1953年)などの出演作があります。
ニミッツの艦長に「炎の人ゴッホ」(1956年)、「OK牧場の決斗」(1957年)、「スパルタカス」(1960年)などの大スター、カーク・ダグラス。
ニミッツの視察に乗り込むウォーレン・ラスキーに、「地獄の逃避行」(1973)、「地獄の黙示録」(1979年)のマーティン・シーン。
マーティン・シーンはテレンス・マリックの監督デビュー作「地獄の逃避行」の主役以降、あまりパッとしない俳優でしたが、「地獄の黙示録」の主役がスティーブ・マックイーンやハリソン・フォードらの相次ぐ降板によって主役の座をつかみ、後には「ウォール街」(1987年)で息子で三男のチャーリー・シーンと共演するなど、数多くの映画に出演。
しかし映画「ファイナル・カウントダウン」の主役は、カーク・ダグラスでもマーティン・シーンでもありません。
主役は原子力空母ニミッツであり、F-14トムキャットであるといってもいいと思います。

タイムスリップを題材にしたSF映画ですが、過去に遡(さかのぼ)ることに対するタイムパラドックスにおける問題とか(ラスキーと乗員との論争はありますが)、複雑な話はワキへ置いといて、原子力空母ニミッツやF-14トムキャットなど、すべて本物を使った迫力は圧倒的で、そのために、アメリカの軍事力を誇示したいだけの映画と見られても仕方のない面はあります。
私は以前、陸上自衛隊明野駐屯地(三重県)での航空ショーをのぞきに行ったことがありますが、間近で見る対戦車ヘリAH-1Sコブラや、F-2、F-15といった戦闘機の迫力に驚いたことがあります。
現在の主流であるステルス戦闘機のF-35はずんぐりむっくりした体型になってしまいましたが、「ファイナル・カウントダウン」に登場するF-14トムキャットは、そのしなやかな機体から人気は高く、退役した現在でも人気の衰えていない艦上戦闘機です。
すべてが本物志向の「ファイナル・カウントダウン」(さすがにゼロ戦はニセモノですが)、ストーリー的にはやや肩透かしをくらう面は否めませんが、コンピューターグラフィックスに頼らない本物の迫力を楽しめる映画です。

2019年07月06日
映画「ゾンビ」-ゾンビ映画の元祖
「ゾンビ」(Dawn of the Dead)
1979年 イタリア/アメリカ
脚本・監督・編集ジョージ・A・ロメロ
撮影マイケル・ゴーニック
音楽ダリオ・アルジェント
ゴブリン
〈キャスト〉
デヴィッド・エムゲ ケン・フォリー
ゲイラン・ロス スコット・H・ライニガー
「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」(1968年)に次ぐジョージ・A・ロメロ監督によるホラー映画で、その後のゾンビのイメージを決定づけた、ゾンビ映画のルーツとも呼ぶべき作品。

死者がよみがえり、全米各地で人間を襲い始め、襲われて死体となった人間も次々とよみがえって人間を襲う、ゾンビ化した死者たちの群れ。
増え続ける「生きた死者」たちの街に見切りをつけたテレビ局のスティーブン(デヴィッド・エムゲ)は、恋人のフラニー(ゲイラン・ロス)とヘリでの脱出を考えています。
一方、スティーブンの友人でSWAT隊員のロジャー(スコット・H・ライニガー)は、アパートの暴徒制圧に駆り出され、銃撃戦の最中、ゾンビと化した暴徒の群れとの死闘の末に同僚の隊員ピーター(ケン・フォリー)とともに辛くも切り抜け、スティーブンたちと街からの脱出を図ります。
4人を乗せてヘリは飛び立ちますが、燃料が足りず、途中の給油所に立ち寄りながらもゾンビに襲われ、壊滅状態の都市を後にしながら、とある郊外の無人のショッピングモールに留まることになります。
モールの中にはゾンビたちが動きまわっていましたが、店内の食品や品物はそのまま残っており、事態が収束に向かうまでの間、4人はゾンビたちとのにらみ合いを続けなからも安全なショッピングモールに身を隠します。
郊外に続々と押し寄せるゾンビたちを避けながら、モールをふさぐため大型トラックを移動中にロジャーが襲われ、瀕死の体を横たえていましたが、やがて死亡。

ほどなくモールにはギャング団が現れ、ピーターは静観していましたが、略奪をほしいままにするギャング団に激怒したスティーブンが発砲。
ゾンビの大群も入り乱れる中、激しい銃撃戦となり、ピーターの活躍によってギャング団は退散しますが、スティーブンはゾンビに襲われ、襲われた者がゾンビ化することを恐れたピーターは、スティーブンの頭を撃ち抜きます。
生き残ったフラニーとピーターでしたが、押し寄せるゾンビの大群を前にしてピーターは自殺を決意。
フラニーはヘリに乗り込み、飛行の準備を始めてピーターを待ちますが、ゾンビの群れは数を増して夜明けの郊外を埋め尽くし始め……。






ブードゥー教の儀式に起源を持つことで知られる「死者の蘇り」は、永遠不滅の肉体を希求する土着信仰と結びついて混じり合い育っていったものと思われ、ヨーロッパのドラキュラやフランケンシュタインも思想の根っ子は同じところにあるのでしょう。
しかし、ドラキュラやフランケンシュタインが怪奇性の中にもロマンティックな雰囲気を漂わせているのに対し、ゾンビは不気味で残酷で、ハッキリ言ってキモチ悪い。なにしろ生きた人間の肉を食べるのですから(内臓もね)。
もっとも、世界的にみれば人肉食(カニバリズム)は古くから各地で行われていたようですから、死者とカニバリズムは相性がいいのでしょう。

死んでよみがえった人間が一人でもいたら怖くて大変だと思うのですが、それを大量に登場させ、襲い来る蘇った死者の群れからいかに脱出するかというのは、一種のサバイバルゲームでもあるわけで、理屈抜きに面白いです(見ているほうは)。
邦題では「ゾンビ」になっていますが、原題は「Dawn of the Dead」。
「死者の夜明け」なので、文字通り、死んだ人間がよみがえるわけですが、死者ですから肉体は腐乱しているし、動き方もぎこちない。だから意外と簡単にやっつけられるのですが、やっかいなのは、ゾンビに噛みつかれると、噛みつかれた人間もゾンビ化して次々と増殖を始める。
簡単にやっつけられるとはいえ、大量に襲い掛かられれば、なす術もなく噛みつかれて内臓を引きづり出され、ムシャムシャと食べられるわけですから、おぞましくも怖い話です。
無名だったジョージ・A・ロメロの名前を一躍世界に知らしめたこの映画、途中、ショッピングモールのシーンでは中だるみもありましたが、ヘリの羽根で頭のてっぺんを切り飛ばされるゾンビの怖さとユーモア、ロジャーとピーターのSWAT隊員コンビの軽快さ、意外と魅力的なゲイラン・ロス、乱入するギャング団との銃撃戦など、おぞましい怖さの中に60年代のマカロニ・ウエスタンを思わせる娯楽性にあふれています。





1979年 イタリア/アメリカ
脚本・監督・編集ジョージ・A・ロメロ
撮影マイケル・ゴーニック
音楽ダリオ・アルジェント
ゴブリン
〈キャスト〉
デヴィッド・エムゲ ケン・フォリー
ゲイラン・ロス スコット・H・ライニガー
「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」(1968年)に次ぐジョージ・A・ロメロ監督によるホラー映画で、その後のゾンビのイメージを決定づけた、ゾンビ映画のルーツとも呼ぶべき作品。

死者がよみがえり、全米各地で人間を襲い始め、襲われて死体となった人間も次々とよみがえって人間を襲う、ゾンビ化した死者たちの群れ。
増え続ける「生きた死者」たちの街に見切りをつけたテレビ局のスティーブン(デヴィッド・エムゲ)は、恋人のフラニー(ゲイラン・ロス)とヘリでの脱出を考えています。
一方、スティーブンの友人でSWAT隊員のロジャー(スコット・H・ライニガー)は、アパートの暴徒制圧に駆り出され、銃撃戦の最中、ゾンビと化した暴徒の群れとの死闘の末に同僚の隊員ピーター(ケン・フォリー)とともに辛くも切り抜け、スティーブンたちと街からの脱出を図ります。
4人を乗せてヘリは飛び立ちますが、燃料が足りず、途中の給油所に立ち寄りながらもゾンビに襲われ、壊滅状態の都市を後にしながら、とある郊外の無人のショッピングモールに留まることになります。
モールの中にはゾンビたちが動きまわっていましたが、店内の食品や品物はそのまま残っており、事態が収束に向かうまでの間、4人はゾンビたちとのにらみ合いを続けなからも安全なショッピングモールに身を隠します。
郊外に続々と押し寄せるゾンビたちを避けながら、モールをふさぐため大型トラックを移動中にロジャーが襲われ、瀕死の体を横たえていましたが、やがて死亡。

ほどなくモールにはギャング団が現れ、ピーターは静観していましたが、略奪をほしいままにするギャング団に激怒したスティーブンが発砲。
ゾンビの大群も入り乱れる中、激しい銃撃戦となり、ピーターの活躍によってギャング団は退散しますが、スティーブンはゾンビに襲われ、襲われた者がゾンビ化することを恐れたピーターは、スティーブンの頭を撃ち抜きます。
生き残ったフラニーとピーターでしたが、押し寄せるゾンビの大群を前にしてピーターは自殺を決意。
フラニーはヘリに乗り込み、飛行の準備を始めてピーターを待ちますが、ゾンビの群れは数を増して夜明けの郊外を埋め尽くし始め……。
ブードゥー教の儀式に起源を持つことで知られる「死者の蘇り」は、永遠不滅の肉体を希求する土着信仰と結びついて混じり合い育っていったものと思われ、ヨーロッパのドラキュラやフランケンシュタインも思想の根っ子は同じところにあるのでしょう。
しかし、ドラキュラやフランケンシュタインが怪奇性の中にもロマンティックな雰囲気を漂わせているのに対し、ゾンビは不気味で残酷で、ハッキリ言ってキモチ悪い。なにしろ生きた人間の肉を食べるのですから(内臓もね)。
もっとも、世界的にみれば人肉食(カニバリズム)は古くから各地で行われていたようですから、死者とカニバリズムは相性がいいのでしょう。

死んでよみがえった人間が一人でもいたら怖くて大変だと思うのですが、それを大量に登場させ、襲い来る蘇った死者の群れからいかに脱出するかというのは、一種のサバイバルゲームでもあるわけで、理屈抜きに面白いです(見ているほうは)。
邦題では「ゾンビ」になっていますが、原題は「Dawn of the Dead」。
「死者の夜明け」なので、文字通り、死んだ人間がよみがえるわけですが、死者ですから肉体は腐乱しているし、動き方もぎこちない。だから意外と簡単にやっつけられるのですが、やっかいなのは、ゾンビに噛みつかれると、噛みつかれた人間もゾンビ化して次々と増殖を始める。
簡単にやっつけられるとはいえ、大量に襲い掛かられれば、なす術もなく噛みつかれて内臓を引きづり出され、ムシャムシャと食べられるわけですから、おぞましくも怖い話です。
無名だったジョージ・A・ロメロの名前を一躍世界に知らしめたこの映画、途中、ショッピングモールのシーンでは中だるみもありましたが、ヘリの羽根で頭のてっぺんを切り飛ばされるゾンビの怖さとユーモア、ロジャーとピーターのSWAT隊員コンビの軽快さ、意外と魅力的なゲイラン・ロス、乱入するギャング団との銃撃戦など、おぞましい怖さの中に60年代のマカロニ・ウエスタンを思わせる娯楽性にあふれています。

2019年07月05日
映画「ソイレント・グリーン」環境汚染と人口増加の未来
「ソイレント・グリーン」(Soylent Green)
1973年アメリカ
監督リチャード・フライシャー
原案ハリイ・ハリスン
脚本スタンリー・R・グリーンバーグ
撮影リチャード・H・クライン
第2回アボリアッツ国際ファンタスティック映画祭グランプリ受賞
〈キャスト〉
チャールトン・ヘストン エドワード・G・ロビンソン
チャック・コナーズ リー・テイラー・ヤング

2022年、人口増加と環境汚染による温暖化によって食料は枯渇し、住むところを失った人々が路上や建物に溢れ、“温室効果”による、むせ返るような息苦しさの中で生きる人々をよそに、一部の特権階級は高級住宅街のマンションで贅沢な生活を享受している激しい格差が生まれたニューヨーク。
本物の肉や魚、新鮮な野菜はなくなり、人々はソイレント社が作る“ソイレント・レッド”、“ソイレント・イエロー”などの高栄養食品で生き延びていました。
そして、さらに新製品として海中プランクトンから作る食料“ソイレント・グリーン”の配給が決定される中、高級マンションで殺人事件が起きます。
殺されたのは富豪の弁護士ウィリアム・R・サイモンソン(ジョセフ・コットン)。

ニューヨーク市警殺人課14分署のソーン刑事(チャールトン・ヘストン)が調査に乗り出し、殺人事件はチンピラの犯行と見せかけたプロの仕業とにらんだソーンは、サイモンソンのボディーガード、タブ・フィールディング(チャック・コナーズ)が手引きをしたと考え、タブの身辺の調査を始めます。
一方、ソーンの同居人で“本”と呼ばれる老人ソル(エドワード・G・ロビンソン)は、サイモンソンがソイレント社の委員会の重要人物であることを突き止めます。
ソイレント社の大きな暗い謎が次第に判明するにつれ、希少価値のプランクトンから作る“ソイレント・グリーン”は配給が滞るようになり、市民の間では怒りと暴動が広がり、混乱の中でソーンは何者かに命を狙われるようになります。






ハリウッドが得意とする近未来映画ですが、高度に発達したテクノロジーや、きらびやかな未来都市といったようなSF感あふれる世界ではなく、70年代から見た50年後はこうなのか、と思われる人口増加と環境汚染による食料問題と居住空間の悪化、そうした日常性が皮膚感覚に訴えるかのような暑く澱(よど)んだ空気感として伝わってきます。。
ベースとなったのはハリイ・ハリスンの小説「人間がいっぱい」。
急速な人口増加による食料不足や住宅の不足といった混乱の中で起きる殺人事件を、1999年のニューヨークを舞台に描いています。
出版は1966年なので、ほぼ30年後の未来を想定しています。
20世紀初頭に約20億人だった地球の人口は1987年に50億人を超え、国連の人口白書によれば2011年にはすでに70億人を突破しています。
だから世界的な食料不足に直面しているのか、というわけでもありませんし、現在の日本では食べられるのに捨てられている“食品ロス”は年間632万トンにのぼっています。
一方で、世界的には慢性的な栄養不足に苦しむ人々がアジアやアフリカで増加している現実があります。
食料危機の背景には政治的な問題があったり、干ばつや水害などの自然災害によるものがあったりします。
現在の世界では地球の温暖化による台風の大型化を始めとして、広範囲な赤潮の発生による水産資源の悪化、頻発する山火事、森林の砂漠化、熱波、夏の異常高温、河川の枯渇、海面の上昇による陸地の縮小、これらは今日的な問題でもあり、人々の生活と命を脅(おびや)かすものですが、中でも病害虫による作物への被害は深刻な食料危機になると予測されています。


「ソイレント・グリーン」の食料不足の背景のひとつとして環境汚染があります。映画的世界の話ですが、こういう世界になったらどうなるのだろうという、ちょっと怖い結末を迎える映画です。
人口が多いということは就職状況も厳しいわけで、刑事であるソーンは失業の不安を抱えながら、サイモンソン殺人事件を追いかけることになります。
この刑事ソーンは職権を利用しながら、手に入りにくい肉や野菜、サイモンソンの部屋から頂戴したバーボンなどをちゃっかりと持ち帰り、ソルとの食事を楽しむのですが、この場面は特に印象の深いものになっています。
本物の肉や野菜を目にしたときのソルの驚きと感情の高ぶり、バーボンを口にした歓び、すでに遠い過去になってしまった、当たり前の食事をする満ち足りた幸福感がよく表れていて、これは名優エドワード・G・ロビンソンの名演技によるものでしょうけど、失われてしまった人間らしい生活に涙するソルの心情がよく表現されたいいシーンでした。
あまりにも格差の激しくなった社会の中で、電気すら乏しい生活のソーンとソルは自転車を漕いで自家発電に頼るという、未来社会というよりは産業革命の時代に逆戻りしたような生活環境。

やがてソルは“ホーム”に入り、大自然の雄大な映像とベートーヴェンの交響曲第6番「田園」を聴きながら死を迎えるのですが、ソルの死はソイレント社の作る「ソイレント・グリーン」の秘密をソーンに暗示するものであり、その秘密を知ったソーンも凶弾に倒れることになります。
監督は「海底二万哩」(1954年)、「ミクロの決死圏」(1966年)、「ドリトル先生不思議な旅」(1967年)などの名匠リチャード・フライシャー。
チャールトン・ヘストンは「ボウリング・フォー・コロンバイン」(2002年)以降、全米ライフル協会会長として負のイメージがついてしまいましたが、「十戒」(1956年)、「ベン・ハー」(1959年)、「エル・シド」(1961年)などの史劇で見せた、たくましい男性像は、登場するだけでスクリーンに厚みがあります。
エドワード・G・ロビンソンは数多くの映画に出演していて、特に「キー・ラーゴ」(1948年)の貫禄たっぷりのギャングのボスがとても印象的だったのですが、「ソイレント・グリーン」が遺作になってしまいました。







1973年アメリカ
監督リチャード・フライシャー
原案ハリイ・ハリスン
脚本スタンリー・R・グリーンバーグ
撮影リチャード・H・クライン
第2回アボリアッツ国際ファンタスティック映画祭グランプリ受賞
〈キャスト〉
チャールトン・ヘストン エドワード・G・ロビンソン
チャック・コナーズ リー・テイラー・ヤング

2022年、人口増加と環境汚染による温暖化によって食料は枯渇し、住むところを失った人々が路上や建物に溢れ、“温室効果”による、むせ返るような息苦しさの中で生きる人々をよそに、一部の特権階級は高級住宅街のマンションで贅沢な生活を享受している激しい格差が生まれたニューヨーク。
本物の肉や魚、新鮮な野菜はなくなり、人々はソイレント社が作る“ソイレント・レッド”、“ソイレント・イエロー”などの高栄養食品で生き延びていました。
そして、さらに新製品として海中プランクトンから作る食料“ソイレント・グリーン”の配給が決定される中、高級マンションで殺人事件が起きます。
殺されたのは富豪の弁護士ウィリアム・R・サイモンソン(ジョセフ・コットン)。

ニューヨーク市警殺人課14分署のソーン刑事(チャールトン・ヘストン)が調査に乗り出し、殺人事件はチンピラの犯行と見せかけたプロの仕業とにらんだソーンは、サイモンソンのボディーガード、タブ・フィールディング(チャック・コナーズ)が手引きをしたと考え、タブの身辺の調査を始めます。
一方、ソーンの同居人で“本”と呼ばれる老人ソル(エドワード・G・ロビンソン)は、サイモンソンがソイレント社の委員会の重要人物であることを突き止めます。
ソイレント社の大きな暗い謎が次第に判明するにつれ、希少価値のプランクトンから作る“ソイレント・グリーン”は配給が滞るようになり、市民の間では怒りと暴動が広がり、混乱の中でソーンは何者かに命を狙われるようになります。
ハリウッドが得意とする近未来映画ですが、高度に発達したテクノロジーや、きらびやかな未来都市といったようなSF感あふれる世界ではなく、70年代から見た50年後はこうなのか、と思われる人口増加と環境汚染による食料問題と居住空間の悪化、そうした日常性が皮膚感覚に訴えるかのような暑く澱(よど)んだ空気感として伝わってきます。。
ベースとなったのはハリイ・ハリスンの小説「人間がいっぱい」。
急速な人口増加による食料不足や住宅の不足といった混乱の中で起きる殺人事件を、1999年のニューヨークを舞台に描いています。
出版は1966年なので、ほぼ30年後の未来を想定しています。
20世紀初頭に約20億人だった地球の人口は1987年に50億人を超え、国連の人口白書によれば2011年にはすでに70億人を突破しています。
だから世界的な食料不足に直面しているのか、というわけでもありませんし、現在の日本では食べられるのに捨てられている“食品ロス”は年間632万トンにのぼっています。
一方で、世界的には慢性的な栄養不足に苦しむ人々がアジアやアフリカで増加している現実があります。
食料危機の背景には政治的な問題があったり、干ばつや水害などの自然災害によるものがあったりします。
現在の世界では地球の温暖化による台風の大型化を始めとして、広範囲な赤潮の発生による水産資源の悪化、頻発する山火事、森林の砂漠化、熱波、夏の異常高温、河川の枯渇、海面の上昇による陸地の縮小、これらは今日的な問題でもあり、人々の生活と命を脅(おびや)かすものですが、中でも病害虫による作物への被害は深刻な食料危機になると予測されています。
「ソイレント・グリーン」の食料不足の背景のひとつとして環境汚染があります。映画的世界の話ですが、こういう世界になったらどうなるのだろうという、ちょっと怖い結末を迎える映画です。
人口が多いということは就職状況も厳しいわけで、刑事であるソーンは失業の不安を抱えながら、サイモンソン殺人事件を追いかけることになります。
この刑事ソーンは職権を利用しながら、手に入りにくい肉や野菜、サイモンソンの部屋から頂戴したバーボンなどをちゃっかりと持ち帰り、ソルとの食事を楽しむのですが、この場面は特に印象の深いものになっています。
本物の肉や野菜を目にしたときのソルの驚きと感情の高ぶり、バーボンを口にした歓び、すでに遠い過去になってしまった、当たり前の食事をする満ち足りた幸福感がよく表れていて、これは名優エドワード・G・ロビンソンの名演技によるものでしょうけど、失われてしまった人間らしい生活に涙するソルの心情がよく表現されたいいシーンでした。
あまりにも格差の激しくなった社会の中で、電気すら乏しい生活のソーンとソルは自転車を漕いで自家発電に頼るという、未来社会というよりは産業革命の時代に逆戻りしたような生活環境。

やがてソルは“ホーム”に入り、大自然の雄大な映像とベートーヴェンの交響曲第6番「田園」を聴きながら死を迎えるのですが、ソルの死はソイレント社の作る「ソイレント・グリーン」の秘密をソーンに暗示するものであり、その秘密を知ったソーンも凶弾に倒れることになります。
監督は「海底二万哩」(1954年)、「ミクロの決死圏」(1966年)、「ドリトル先生不思議な旅」(1967年)などの名匠リチャード・フライシャー。
チャールトン・ヘストンは「ボウリング・フォー・コロンバイン」(2002年)以降、全米ライフル協会会長として負のイメージがついてしまいましたが、「十戒」(1956年)、「ベン・ハー」(1959年)、「エル・シド」(1961年)などの史劇で見せた、たくましい男性像は、登場するだけでスクリーンに厚みがあります。
エドワード・G・ロビンソンは数多くの映画に出演していて、特に「キー・ラーゴ」(1948年)の貫禄たっぷりのギャングのボスがとても印象的だったのですが、「ソイレント・グリーン」が遺作になってしまいました。

2019年07月02日
映画「殺人者たち」愛と裏切りのハードボイルド
「殺人者たち」(The Killers) 1964年アメリカ
監督ドナルド・シーゲル(ドン・シーゲル)
原案アーネスト・ヘミングウェイ
脚本ジーン・L・クーン
撮影リチャード・L・ローリングス
音楽ジョニー・ウィリアムズ(ジョン・ウィリアムズ)
〈キャスト〉
リー・マーヴィン アンジー・ディキンソン
ジョン・カサヴェテス クルー・ギャラガー

ピッタリしたスーツに黒いサングラスの男が二人。
一人は長身で中年のいかつい風貌の男。もう一人は中肉中背の若い伊達男。
二人は無言のまま盲学校のドアを開け、受付にいた盲人の女性に訊ねます。
「ジョニーはどこだ?」
返答に窮する女性を殴り倒し、ジョニーの居場所を突き止めると、二人は真っ直ぐ教室へと向かい、盲学校の教師ジョニー・ノース(ジョン・カサヴェテス)を射殺します。
大混乱の盲学校から抜け出し、ひと仕事を終えた殺し屋の二人、チャーリー・ストロム(リー・マーヴィン)とリー(クルー・ギャラガー)でしたが、チャーリーは殺した相手であるジョニーの態度に不審を抱きます。
「どうしてヤツは逃げなかったんだ?」
チャーリーは続けます。「普通は逃げるはずだ。オレたちが来たことは受付が連絡してるはずだからな」
ジョニーに対するチャーリーの疑問は、ジョニーの友人で元レースメカニックだったアール・シルヴェスター(クロード・エイキンズ)の口を強引に割らせたことにより、次第に判明してゆくことになります。

元レーサーのジョニー・ノースは、運命の女シーラ・ファー(アンジー・ディキンソン)と出会い、恋に落ちたジョニーはシーラの虜となってしまいます。
やがて、シーラにそそのかされるまま現金強盗グループの一団に加わったジョニーは、仲間を裏切り、強奪した100万ドルとともにシーラとの逃避行を図ります。
ジョニーの謎とともに100万ドルの行方を追い始めたチャーリーとリーはシーラの居場所を突き止め、やがて謎の真相をつかむことになります。






原案となったのはアーネスト・ヘミングウェイの短編「殺し屋」。
レストランに現れた殺し屋二人組が、ボクサーであるオーリー・アンダースンの命を狙っていることを知った店の主人が、命の危険をアンダースンに知らせてやろうとするものの、アンダースンはベッドに横になったまま部屋から出ようとしなかった、というストーリー。
面白そうなワリには、あまりパッとしない話を膨らませて1946年にロバート・シオドマク監督、バート・ランカスター主演で「殺人者」として映画化。
さらにそれを変形させ、ふくらませてリメイクしたのが本作「殺人者たち」です。
監督はドン・シーゲル。
後の1971年に「ダーティハリー」が大ヒットして世界的名声を獲得しますが、50年代、60年代の初期にはまだB級映画の監督でしかなかったドン・シーゲル。
しかし、「汚れた顔の天使」(1938年)、「カサブランカ」(1942年)などで知られるマイケル・カーティスや「暗黒街の顔役」(1932年)、「リオ・ブラボー」(1959年)などの硬派の巨匠ハワード・ホークスの下で積み重ねた経験は、当時ロック界のスーパースター、エルヴィス・プレスリーを起用して演技派として注目させた「燃える平原児」(1960年)を始め、大スターの片鱗を見せ始めていたスティーブ・マックイーンと組んだ「突撃隊」(1962年)などのアクションを中心とした無駄のない演出は「殺人者たち」で炸裂することになります。
キャストも個性豊かで、「リバティ・バランスを撃った男」のリー・マーヴィンを始め、「オーシャンと十一人の仲間」のアンジー・ディキンソン。後に「グロリア」(1980年)のヒットで監督として名高いジョン・カサヴェテス。「続・荒野の七人」などの名脇役クロード・エイキンズ。
そして、「殺人者たち」を最後に映画界を去って政界へと軸足を移し、カリフォルニア州知事を経て1981年に第40代アメリカ合衆国大統領となるロナルド・レーガン。

強奪した現ナマを追って二転三転する愛と裏切りのハードボイルド。
「死の接吻」(1947年)の冷酷非情な殺し屋トミー・ユードー(リチャード・ウィドマーク)を思わせる情け容赦のない二人の殺し屋たち。
乾いた空気感と軽快なテンポで貫かれてはいるのですが、難点は、ところどころに挿入されるジョニー・ノースの過去の回想で、ジョニーと恋人のシーラとのロマンスは冗長になってしまっていて、ドン・シーゲルらしくない中だるみなのですが、それも計算に入っていたのか、中だるみの不満が逆にメリハリとなって、後半からのたたみ込むようなテンポと一気呵成のラストに結びつく展開は、映画全体からみれば交響曲的な構成といえるかもしれません。
ロナルド・レーガンさんは大統領としての印象が強すぎて、俳優としてはイマイチの評価のようですが、「殺人者たち」では強盗団の黒幕として貫禄タップリの演技で、特にリー・マーヴィンを相手にしてのラストの銃撃戦はなかなかのものです。


特筆すべきはやっぱりリー・マーヴィンでしょうか。
「乱暴者」(1953年)で、マーロン・ブランドに対抗する暴走族のリーダーで注目され、「リバティ・バランスを撃った男」ではジョン・ウェインを向こうに回す悪役ぶり。
「殺人者たち」の翌年の「キャット・バルー」(1965年)でキャサリン(ジェーン・フォンダ)を救う酔いどれガンマンと殺し屋の二役を演じて第38回アカデミー賞主演男優賞を受賞。
「殺人者たち」では、よくしゃべる無鉄砲なクルー・ギャラガーとは対照的に、寡黙で冷静な殺し屋ながら、どことなくダンディな雰囲気を漂わせた、中年の落ち着きを持った男の魅力にあふれていました。
レストランで相棒のリーと食事をするシーンで、オレは要らないからとリーにステーキを押しやり、後になって、やっぱり食べようと、いったん押しやったステーキを食べるシーンはなんだか妙に好きで印象に残っています。





監督ドナルド・シーゲル(ドン・シーゲル)
原案アーネスト・ヘミングウェイ
脚本ジーン・L・クーン
撮影リチャード・L・ローリングス
音楽ジョニー・ウィリアムズ(ジョン・ウィリアムズ)
〈キャスト〉
リー・マーヴィン アンジー・ディキンソン
ジョン・カサヴェテス クルー・ギャラガー

ピッタリしたスーツに黒いサングラスの男が二人。
一人は長身で中年のいかつい風貌の男。もう一人は中肉中背の若い伊達男。
二人は無言のまま盲学校のドアを開け、受付にいた盲人の女性に訊ねます。
「ジョニーはどこだ?」
返答に窮する女性を殴り倒し、ジョニーの居場所を突き止めると、二人は真っ直ぐ教室へと向かい、盲学校の教師ジョニー・ノース(ジョン・カサヴェテス)を射殺します。
大混乱の盲学校から抜け出し、ひと仕事を終えた殺し屋の二人、チャーリー・ストロム(リー・マーヴィン)とリー(クルー・ギャラガー)でしたが、チャーリーは殺した相手であるジョニーの態度に不審を抱きます。
「どうしてヤツは逃げなかったんだ?」
チャーリーは続けます。「普通は逃げるはずだ。オレたちが来たことは受付が連絡してるはずだからな」
ジョニーに対するチャーリーの疑問は、ジョニーの友人で元レースメカニックだったアール・シルヴェスター(クロード・エイキンズ)の口を強引に割らせたことにより、次第に判明してゆくことになります。

元レーサーのジョニー・ノースは、運命の女シーラ・ファー(アンジー・ディキンソン)と出会い、恋に落ちたジョニーはシーラの虜となってしまいます。
やがて、シーラにそそのかされるまま現金強盗グループの一団に加わったジョニーは、仲間を裏切り、強奪した100万ドルとともにシーラとの逃避行を図ります。
ジョニーの謎とともに100万ドルの行方を追い始めたチャーリーとリーはシーラの居場所を突き止め、やがて謎の真相をつかむことになります。
原案となったのはアーネスト・ヘミングウェイの短編「殺し屋」。
レストランに現れた殺し屋二人組が、ボクサーであるオーリー・アンダースンの命を狙っていることを知った店の主人が、命の危険をアンダースンに知らせてやろうとするものの、アンダースンはベッドに横になったまま部屋から出ようとしなかった、というストーリー。
面白そうなワリには、あまりパッとしない話を膨らませて1946年にロバート・シオドマク監督、バート・ランカスター主演で「殺人者」として映画化。
さらにそれを変形させ、ふくらませてリメイクしたのが本作「殺人者たち」です。
監督はドン・シーゲル。
後の1971年に「ダーティハリー」が大ヒットして世界的名声を獲得しますが、50年代、60年代の初期にはまだB級映画の監督でしかなかったドン・シーゲル。
しかし、「汚れた顔の天使」(1938年)、「カサブランカ」(1942年)などで知られるマイケル・カーティスや「暗黒街の顔役」(1932年)、「リオ・ブラボー」(1959年)などの硬派の巨匠ハワード・ホークスの下で積み重ねた経験は、当時ロック界のスーパースター、エルヴィス・プレスリーを起用して演技派として注目させた「燃える平原児」(1960年)を始め、大スターの片鱗を見せ始めていたスティーブ・マックイーンと組んだ「突撃隊」(1962年)などのアクションを中心とした無駄のない演出は「殺人者たち」で炸裂することになります。
キャストも個性豊かで、「リバティ・バランスを撃った男」のリー・マーヴィンを始め、「オーシャンと十一人の仲間」のアンジー・ディキンソン。後に「グロリア」(1980年)のヒットで監督として名高いジョン・カサヴェテス。「続・荒野の七人」などの名脇役クロード・エイキンズ。
そして、「殺人者たち」を最後に映画界を去って政界へと軸足を移し、カリフォルニア州知事を経て1981年に第40代アメリカ合衆国大統領となるロナルド・レーガン。

強奪した現ナマを追って二転三転する愛と裏切りのハードボイルド。
「死の接吻」(1947年)の冷酷非情な殺し屋トミー・ユードー(リチャード・ウィドマーク)を思わせる情け容赦のない二人の殺し屋たち。
乾いた空気感と軽快なテンポで貫かれてはいるのですが、難点は、ところどころに挿入されるジョニー・ノースの過去の回想で、ジョニーと恋人のシーラとのロマンスは冗長になってしまっていて、ドン・シーゲルらしくない中だるみなのですが、それも計算に入っていたのか、中だるみの不満が逆にメリハリとなって、後半からのたたみ込むようなテンポと一気呵成のラストに結びつく展開は、映画全体からみれば交響曲的な構成といえるかもしれません。
ロナルド・レーガンさんは大統領としての印象が強すぎて、俳優としてはイマイチの評価のようですが、「殺人者たち」では強盗団の黒幕として貫禄タップリの演技で、特にリー・マーヴィンを相手にしてのラストの銃撃戦はなかなかのものです。
特筆すべきはやっぱりリー・マーヴィンでしょうか。
「乱暴者」(1953年)で、マーロン・ブランドに対抗する暴走族のリーダーで注目され、「リバティ・バランスを撃った男」ではジョン・ウェインを向こうに回す悪役ぶり。
「殺人者たち」の翌年の「キャット・バルー」(1965年)でキャサリン(ジェーン・フォンダ)を救う酔いどれガンマンと殺し屋の二役を演じて第38回アカデミー賞主演男優賞を受賞。
「殺人者たち」では、よくしゃべる無鉄砲なクルー・ギャラガーとは対照的に、寡黙で冷静な殺し屋ながら、どことなくダンディな雰囲気を漂わせた、中年の落ち着きを持った男の魅力にあふれていました。
レストランで相棒のリーと食事をするシーンで、オレは要らないからとリーにステーキを押しやり、後になって、やっぱり食べようと、いったん押しやったステーキを食べるシーンはなんだか妙に好きで印象に残っています。










