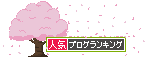2018年04月30日
学習もリズムが大事、天王山の夏休みを前にして。

連休真っ只中ですね。娘は前の記事(記述を制する者は受検を制す?3月から5月ころ)に書いたように、昨年の5/3〜7はe塾のGW合宿に行っていました。今年は3連休+4連休ですから、1日2日を挟んで、前・後期でみっちり行われるようです。
* * * * *
前回、夏休み前のことについて書きましたが、思い出したので、少し補足したいと思います。
模試や問題集、参考書など色々と手を出しましたが、加えて、学習リズムの見直しを図りました。GW合宿で、「長時間勉強できるんだ」という自分の限界(と思っていたライン)を超える体験ができましたが、家庭では相変わらずダラダラと勉強し、休憩も長々と取るなどメリハリがきいていませんでした。
そこで、実際の受検時における時間感覚を養うためにも、家庭学習を1コマ45分としました。e塾の復習やテスト直しだけでなく、学校の宿題などもこのスパンとし、終わらなくても一旦45分経過で休憩するというルールです。これにより、一日の予定も立てやすくなりました。予定表どおりできたかどうかは別として…
また、時間も心もまだゆとりがあったので、中学受検のメリデメの整理、志望校を選ぶ理由の分析を行いました。
受検のメリットは、中学校での勉強進度、学び(体験)の機会、高校受験の有無、部活動の豊富さなど。デメリットは通学時間、小学校時代の友人関係、そして、そもそも時間や労力を掛けてチャレンジしても報われない可能性がある、ということを中心に整理しました。
「高校受験の有無」に関連して、私は付属中がある私立校へ高校から入学しましたので、当時の体験も踏まえ、中高一貫校の内進組と外部組は3年間じゃなかなか馴染まないという話もしました。特に今は、中高一貫化が進み、そもそも高校からの入学が無い、もしくは定員が少ない状況のようですから、その傾向がより顕著ではないかと思うのです。高校しかない都立の上位校を目指すのであれば話は別ですが、小6の段階でそこまでイメージすることは困難で、目標にはできなかったというのが正直なところです。
志望校を選ぶ理由については、なぜ〇〇中が面白いと感じたのか、いわゆる「なぜなぜ分析」的な方法で、掘り下げて分析をしました。「なぜ」を繰り返すことで、真の原因・理由にたどり着こうとするものです。「Q:なぜ、〇〇中は面白いのか?」「A:生徒たちが楽しそうに取り組んでいるから。」→「Q:では、なぜ、楽しく取り組めるのか?」「A:きっと、自分たちが本当にやりたいことをやっているから。」…
理由を整理したうえで、「中学を受検できるのは小6の2月3日だけ。進みたい気持ちがあるならチャレンジしてみては。ただし、家族は協力するが、可能性を広げるのは自分自身。理系の強化と学習・生活のリズムが大事」と確認しました。
試行錯誤をくり返し、通知表をもらい、夏休みに突入です。
にほんブログ村で
公立中高一貫校受験の
ブログをチェック!
【このカテゴリーの最新記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/7604522
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック