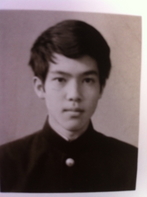2016年03月22日
第37回 野生
文●ツルシカズヒコ
出奔した野枝に対する親族のフォローが気になるが、矢野寛治『伊藤野枝と代準介』(p74)によれば、代準介とキチが上京し野枝に翻意を促したが「ノエと辻はすでに深い関係となっており、しばらく間を置き、熱の冷めるのを待つことにした」とある。
平塚らいてう宛てに、九州の未知の少女から長い手紙が届いたのは、 一九一二(明治四十五)年晩春のころだった。
切手三枚を貼ったペン字の重たい封筒だった。
差出人は「福岡県糸島郡今宿 伊藤野枝」。
それは自分の生い立ち、性質、教育、境遇ーーことに現在肉親たちから強制されている結婚の苦痛などを訴えたもので、そこには道徳、習俗に対する半ば無意識な反抗心が、息苦しいまで猛烈に渦巻いておりました。
そして、自分はもうこれ以上の圧迫に堪えられないから、最後の力をもって肉親たちに反抗して、自分に忠実な正しい道につこうと決心している。
近いうち上京してお訪ねするから、ぜひ会ってほしいと書いてありました。
細かなペン字で、びっしり書きこまれたこの長い手紙は、ひとり合点の思いあがった調子ではありましたが、文章もよく、字も立派なこと、生一本の真面目さによって、青鞜社にくる多くの手紙のなかで格段に印象に残るものでした。
(『元始、女性は太陽であったーー平塚らいてう自伝(下巻)』_p404)

野枝の「あきらめない生き方・その三」の始動である。
またしても野枝は手紙を書く文才、すなわち「手紙作家」の才によって、らいてうに強烈なインパクトを与えたのである。
野枝からの手紙が来てから何日後かに、本郷区駒込曙町の自宅にいたらいてうは、女中さんからこう告げられた。
「伊藤さんという方がお見えになりました」
「どんな方?」
「十五、六ほどのお守(も)りさんのような方です」
……この人があのしっかりした手紙を書いた人とは、どうしても思われません。
小柄ながっちりとしたからだに、赤いメリンスの半幅帯を貝の口にぴんと結んだ野枝さんの感じは、これで女学校を出ているのかと思うほど子どもらしい感じでした。
健康そうな血色のいいふっくりした丸顔のなかによく光る眼は、彼女が勝気な、意地っぱりの娘であることを物語っています。
その黒目勝ちの大きく澄んだ眼は、教養や聡明さに輝くというより、野生の動物のそれのように、生まれたままの自然さでみひらかれていました。
話につれて丸い鼻孔をふくらませる独特の表情や、薄く大きい唇が波うつように歪んで動くのが、人工で装ったものとはまったく反対の、じつに自然なものを身辺から発散させています。
生命力に溢れるこの少女が、初対面のわたくしに悪びれもせず、自分のいいたいだけのことを、きちんと筋道立てていう態度には……情熱的な魅力が感じられるのでした。
(『元始、女性は太陽であった 平塚らいてう自伝(下)』_p404)
野枝は苦痛と闘い、婚家を飛び出し、上野高女の英語教師だった辻の家に世話になっていることなど、らいてうに書いた手紙の内容をより具体的に話した。
らいてうは勇敢に因習に立ち向かう野枝に対して、青鞜社がなんらかの力になるべきであると思った。
らいてうに会ってみることを野枝に勧めたのは、辻だった。
僕は新聞の記事によつてらいてう氏にインテレストを持ち「青鞜」を読んで、頼もしく思つた。
野枝さんにすすめてらいてう氏を訪問させて相談させてみることを考へた。
(「ふもれすく」/『婦人公論』1924年2月号_p9/『ですぺら』_p184/『辻潤全集 第一巻』_p389)
野枝が住所を今宿にしたのは、その方がらいてうの同情を誘えると考えたからだと言われている。
『青鞜』の創刊は前年、一九一一(明治四十四)年九月であるが、創刊からの読者だった辻に勧められて、野枝も『青鞜』を読んでいただろう。
一九一二年(明治四十五)年)七月二十日、明治天皇の病気を報じる号外が出た。
七月三十日、午前〇時四十三分、明治天皇崩御。
実際の崩御は七月二十九日、二十二時四十三分だったが、諸々の都合で翌日にしたという。
山川菊栄は後に、この日をこう回想している。
明治四十五(一九一二)年七月三十日の夜は、すばらしい月夜でした。
その日、明治天皇は世を去りました。
私はひとりで二階に寝ていましたが、あけ放した窓からは月の光が水のように蚊帳の中まで流れこむ。
ああ明治は終った、明日からは新しい日がくる、今日までのあらゆるいやなことが一夜のうちにこの月の光に洗い去られて、明日からはすばらしく美しい、明るい日がくる、と私はかってな夢をえがいて、子供のころの遠足の前夜のようにうきうきした気分で寝入りました。
(山川菊栄『女二代の記ーーわたしの半自叙伝』/山川菊栄『おんな二代の記』_p192~193)
「伊藤野枝年譜」(『定本 伊藤野枝全集 第四巻』)によれば、明治が終わり大正になった七月末ごろ、野枝は今宿に帰郷していた。
自ら末松福太郎との離婚の話し合いをするためである。
出奔事件の解決がまだついていないので、一度郷里に帰りトラブルを解決してくるといって、平塚らいてう宅を辞した野枝は、今宿かららいてうに手紙を書いた。
それには、帰った日から毎日のように理解のない周囲の人たちから残酷に責め立てられ、以前にも増した苦しみで逃れる道がない。
幾度も死の決心をしたが、このままでは死ぬこともできない。
このごろはもう極度の疲労のため、体をこわしている。
ひとり海岸に出て、涙を流すばかりだというようなことが、思い迫った調子で書いてありました。
とても普通の手段では抜けられないから、家人の隙を窺って再度の家出をしようと思うが、その旅費をなんとか都合して送ってほしいということでした。
(『元始、女性は太陽であった 平塚らいてう自伝(下)』_p405~406)
★矢野寛治『伊藤野枝と代準介』(弦書房・2012年10月30日)
★『元始、女性は太陽であった 平塚らいてう自伝(下巻)』(大月書店・1971年9月6日)
★『辻潤全集 一巻』(五月書房・1982年4月15日)
★山川菊栄『女二代の記ーーわたしの半自叙伝』(日本評論新社・1956年5月30日)
★山川菊栄『おんな二代の記』(岩波文庫・2014年7月16日)
★『定本 伊藤野枝全集 第四巻』(學藝書林・2000年12月15日)
●あきらめない生き方 詳伝・伊藤野枝 index
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image