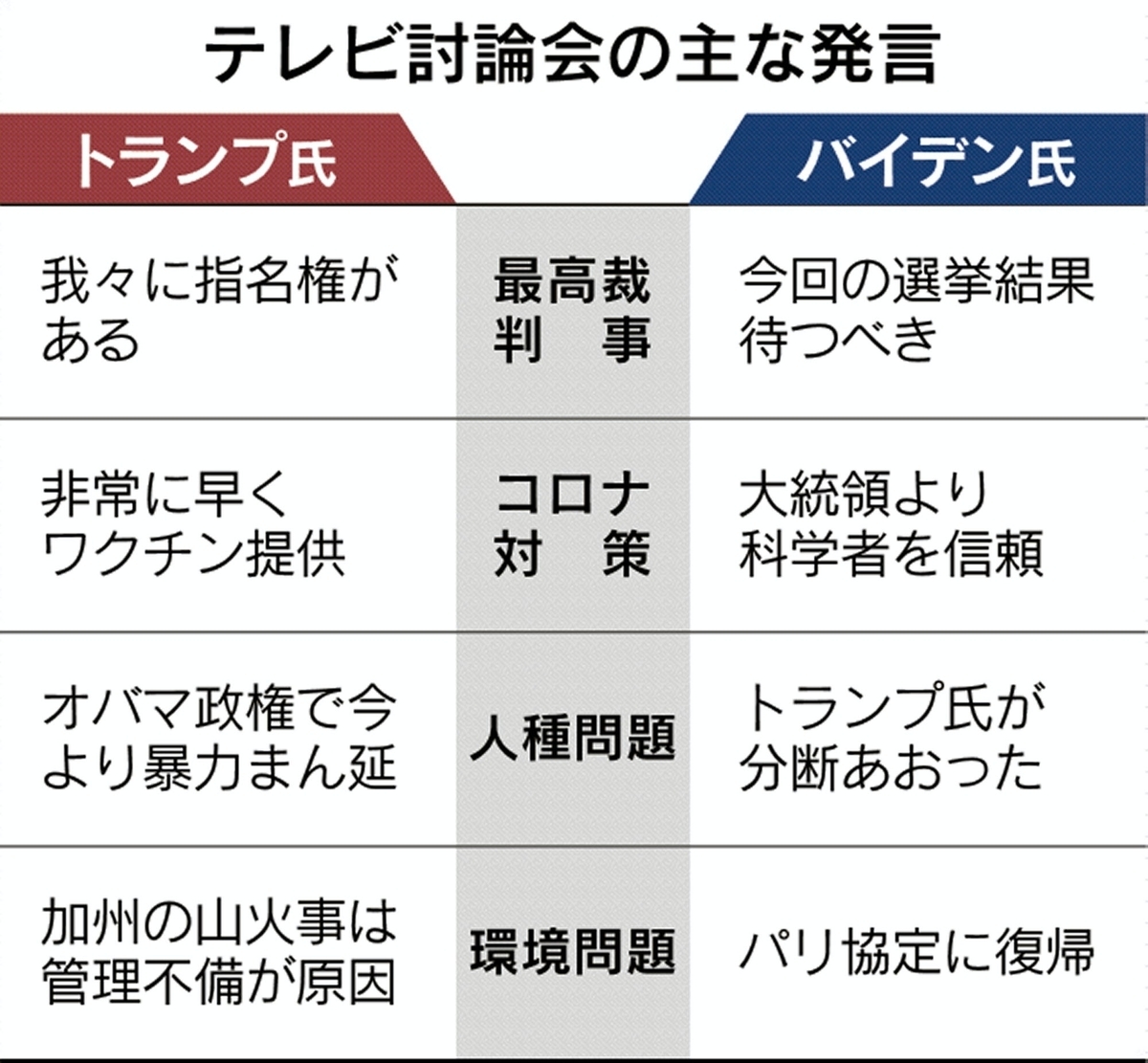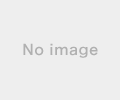2020年07月08日
【経済ニュース7/07 金融リテラシーを上げて1歩上の自分へ(^^♪】
こんばんは
1.アップル、次期iPhone全機種に有機EL 脱・液晶加速
2.東京都内で新たに106人感染 新型コロナ
3.米、TikTokの使用禁止を検討 情報流出を問題視
4.NYダウ反落で始まる 新型コロナ懸念で利益確定の売り
5.サムスン、スマホ首位暗雲 出荷台数4〜6月3割減
2.東京都内で新たに106人感染 新型コロナ
3.米、TikTokの使用禁止を検討 情報流出を問題視
4.NYダウ反落で始まる 新型コロナ懸念で利益確定の売り
5.サムスン、スマホ首位暗雲 出荷台数4〜6月3割減
6.ブラジル大統領、新型コロナで陽性反応
7..アマゾンなど巨人ITが最高値 成長見込みマネー集中
8.個人の景況感、落ち込み最大 雇用・賃金に不安
9.香港国家安全法、米IT大手に影 ネット自由に影響も
10.ユーロ圏成長率を下方修正 20年マイナス8.7%に 欧州委
11.中国ネット大手の新浪、MBO検討 米ナスダック上場
12.豪メルボルン都市圏で外出規制 8日深夜から
7..アマゾンなど巨人ITが最高値 成長見込みマネー集中
8.個人の景況感、落ち込み最大 雇用・賃金に不安
9.香港国家安全法、米IT大手に影 ネット自由に影響も
10.ユーロ圏成長率を下方修正 20年マイナス8.7%に 欧州委
11.中国ネット大手の新浪、MBO検討 米ナスダック上場
12.豪メルボルン都市圏で外出規制 8日深夜から
1.アップル、次期iPhone全機種に有機EL 脱・液晶加速
米アップルは2020年後半に発売するスマートフォン「iPhone」の全新機種に高精細で軽量の有機ELパネルを採用する見通しだ。これまでは液晶パネルと併用していたが、韓国サムスン電子など競合他社が搭載機種を増やしており方針を転換する。脱液晶の流れが加速し、部品や素材メーカーを含めたパネル産業の構造転換につながりそうだ。サプライヤーなど複数の関係者が明らかにした。
2.東京都内で新たに106人感染 新型コロナ
東京都は7日、新型コロナウイルスの感染者が新たに106人確認されたと発表した。新規感染者が100人以上になるのは6日連続。都内の感染者の累計は6973人となった。
都によると、新規感染者106人のうち、20〜30代は70人に上り、全体の6割超を占めた。ホストクラブやキャバクラなど「夜の繁華街」での感染は23人とみられ、新宿エリアだけで14人いた。感染経路が不明のケースは47人、無症状者は22人だった。ほかにも職場内や家庭内で感染したケースが目立った。
夜の街での感染例が相次ぐ新宿区など一部の区では、接客を伴う飲食店の従業員に症状がなくても検査を受けるよう促している。都は夜の街への外出や県境をまたぐ移動を控えるよう都民に呼び掛けている。
3.米、TikTokの使用禁止を検討 情報流出を問題視
ポンペオ米国務長官は6日放送のFOXニュースのインタビューで、米国内でのショート動画アプリ「TikTok」の利用禁止を検討していると明らかにした。TikTokの情報が中国政府に吸い上げられている可能性があると指摘した。
ポンペオ氏は「中国の携帯電話向けアプリの問題に関し、米国はきちんと取り組む。(禁止を)考えている」と語った。他の中国製アプリも使用禁止の対象になり得るとの認識を示した。
TikTokは中国企業の北京字節跳動科技(バイトダンス)が運営し、米国内での利用者は3000万人以上いるとみられている。米議会ではかねて米国の利用者の情報が中国政府に渡っているのではないかとの懸念が指摘されていた。
TikTokはインドが他の中国製アプリを含めて使用を禁止したほか、オーストラリアも禁止を検討している。
米国では、トランプ大統領が6月に南部オクラホマ州で開いた選挙集会にTikTokの利用者らが欠席を前提に大量の申し込みを呼びかけたとされ、大量の空席が発生する一因と指摘されたことがある。
4.NYダウ反落で始まる 新型コロナ懸念で利益確定の売り
7日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落して始まった。午前9時35分現在は前日比200ドル66セント安の2万6086ドル37セントで推移している。ダウ平均は前日までの5営業日で1200ドルあまり上げ、3週間ぶりの高値で終えていた。新型コロナウイルスの感染拡大への懸念はくすぶっており、いったん利益を確定する売りに押されている。
テキサスやカリフォルニアなど米国の一部の州ではコロナ感染の再拡大を受けて経済活動の再開を一時停止しており、米景気には先行き不透明感も残る。化学のダウやクレジットカードのアメリカン・エキスプレス、金融のゴールドマン・サックスなど前日に上昇が目立った景気敏感株の下げが目立つ。コロナ感染が業績を直撃する空運株やクルーズ船株が売られ、航空機のボーイングも3%前後下げている。
一方、コロナ感染が業績の逆風になりにくいハイテク株は底堅い。スマートフォンのアップルとソフトウエアのマイクロソフトは買いが先行し、連日で上場来高値を更新。前日に初めて3000ドルの大台に乗せたネット通販のアマゾン・ドット・コムは朝方に上場来高値を更新した後、前日終値を挟んでもみ合っている。
5.サムスン、スマホ首位暗雲 出荷台数4〜6月3割減
サムスン電子が4〜6月期のスマートフォン世界シェアで、中国の華為技術(ファーウェイ)に首位を明け渡す可能性が高まった。新型コロナウイルスの感染拡大で同期間の出荷台数が前年同期比で約3割減ったもようで、微減のファーウェイと明暗を分けた。スマホの販売不振は業績全体に響くが、コロナの収束以外に復活の糸口は見えない。
サムスンが7日発表した4〜6月期の連結決算速報値は、営業利益が8兆1千億ウォン(約7300億円)と前年同期に比べて23%増えた。売上高は同7%減の52兆ウォンだった。新型コロナの影響でテレビ会議や遠隔授業といったオンライン需要が伸び、半導体メモリーの価格が上昇。投資家の事前予想を超える増益幅となった。
サムスンにとっては手放しで喜べる状況にはない。スマホの出荷台数が過去最大の落ち込みになったためだ。
サムスンは公表していないが、複数の調査会社によると、4〜5月のサムスンのスマホ出荷台数は前年同期比で約4割減の3千万台程度。6月は欧米で経済再開の動きが広がったが、4〜5月の減少分を補えなかった。
韓国SK証券の試算では、4〜6月期のファーウェイの出荷台数は5500万台。対してサムスンは5100万台にとどまり、同期間はファーウェイが初めて首位に立ったもようだ。
これまでスマホ世界首位の座は、サムスンと米アップルが競ってきた。新型iPhoneの発売効果でクリスマス商戦がある10〜12月期にアップルが首位となることはあったが、サムスンがすぐに奪還してきた。
強みは販売地域のバランスに加え、1年に10機種以上の新製品を出すなど幅広い客層を取り込んできたことにある。20万円の折り畳みスマホなど高性能機種をそろえて先進国で稼ぐとともに、新興国向けに1台2万円を切るモデルも用意し、ここ数年は年間3億台の出荷台数を維持してきた。
今回はサムスンの弱点でもある世界最大市場の中国が命運を握った。サムスンの中国でのシェアは1%未満にとどまるが、ファーウェイは中国が全体の6割に上る。同国が欧米よりも早期に経済再開に踏み切ったことで、両社の差が生まれた。
シェア争いに敗れたことより大きな構造問題も潜む。スマホ端末は売上高全体の4割超を占めるが、その部品の主要調達先は自社の半導体、ディスプレー部門でもある。アップル向けの有機ELパネル販売は今後も拡大する見通しだが、自社のスマホが売れなければ、売上高20兆円を超える巨大企業全体の収益が大幅に縮みかねない。
サムスンは起爆剤と位置付ける利幅の大きい旗艦モデル「ギャラクシーノート」の発売を8月に控える。その売れ行きは、経済再開の是非を決めるコロナの感染動向にかかっている。
一方、初の世界首位となったとみられるファーウェイも、盤石とは言いがたい。なかでも海外での同社に対する風当たりは強まるばかりだ。
特に米政府による規制で、米グーグルのアプリを使えなくなった影響が大きい。ファーウェイは独自アプリを充実させて消費者に訴えるが、既にグーグルのアプリを使い慣れた顧客がサムスンなど他社スマホに流出しているのが現状だ。
また中国に次ぐ巨大市場であるインドでは、国境紛争のあおりを受けて中国製品のボイコット運動が広がる。同市場首位の小米(シャオミ)やファーウェイが販売低迷に陥り、2位のサムスンが「漁夫の利」を得る構図となっている。このため、ファーウェイのトップは4〜6月期だけの「四半期天下」に終わる可能性もある。
米調査会社IDCの6月時点の試算では、20年の世界のスマホ出荷台数は前年比12%減と過去最大の落ち込みとなる見通し。サムスン、ファーウェイを含めた主要企業すべてが前年比でマイナス成長となる可能性が高く、勝者なきシェア競争に終わりはみえない。
6.ブラジル大統領、新型コロナで陽性反応
ブラジルのボルソナロ大統領は7日、新型コロナウイルスの検査を受けて陽性反応が出たと発表した。65歳のボルソナロ氏は新型コロナを「ただの風邪」だと主張し、マスクを着用せずに支持者らと接触していた。
ボルソナロ氏は6日、38度の高熱など新型コロナの症状が出たため、病院で肺の検査を受け、コロナの検査を受けると明らかにしていた。ボルソナロ氏は7日昼、テレビ番組の取材に応じており、重症ではないとアピールしている。
7..アマゾンなど巨人ITが最高値 成長見込みマネー集中
米巨大ITの株価上昇が続いている。6日の米株式市場では時価総額首位を争うアップルとマイクロソフト、アマゾン・ドット・コムの3社がそろって上場来高値を更新した。上位5社の時価総額合計は全体の2割を超え、成長が見込める企業への一極集中が進む。資金力を生かしたM&A(合併・買収)も目立ち、規制当局は寡占の弊害にも目を向け始めた。
アマゾンは3〜5月にかけて物流施設や
小売店従業員らの時給や残業代を一時的に引き上げるなど、利益圧迫要因もある。今後3〜5年の業績見通しを基に目標株価を算定するアナリストが上昇を続ける株価に追随し、目標株価を切り上げている格好だ。「ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)では説明できない」(米証券ミラー・タバックのマシュー・マリー氏)との声も漏れる。
アマゾンの時価総額は1兆5000億ドル(約160兆円)と、首位のアップル(1兆6200億ドル)や2位のマイクロソフト(1兆5900億ドル)に迫る。
新型コロナウイルスの影響を受けにくく、成長が続くとみられている大型ハイテク株にはそろって資金が流入している。QUICK・ファクトセットによると3社にアルファベット、フェイスブックを加えた5社の時価総額は、S&P500種株価指数の採用銘柄合計の2割を超える。
豊富な資金力を武器に各社はM&Aの分野でも存在感を高める。米調査会社のCBインサイツによると5社が過去10年間で手掛けた案件は500件を超え、その前の10年間に比べ2.6倍に増えた。6月下旬にはアマゾンが自動運転技術の開発を手掛ける米ズークスの買収を決めたばかりだ。
人材や知的財産の獲得競争で優位に立ち、各種サービスにおける市場支配力を強める巨人ITに対し規制当局は懸念を強める。米下院司法委員会は6日、アマゾンとアップル、グーグル、フェイスブックの4社のトップが反トラスト法(独占禁止法)調査に関連して27日に議会証言すると発表した。米司法省や米連邦取引委員会(FTC)はIT大手が反トラスト法に違反していないかどうかを過去のM&A案件に遡って調査している。
独禁当局などの調査でIT大手の側に競争を阻害する意図があったと判断されれば、過去のM&Aの承認も取り消せるとの指摘も一部の法学者から出る。米国でこうした規制強化の動きが勢いづけば、大型ハイテク株が主導する米相場にも影響を与えるおそれがある。
8.個人の景況感、落ち込み最大 雇用・賃金に不安
個人の景況感が急速に冷え込んでいる。日銀が7日発表した6月の生活意識に関するアンケート調査で、前回の3月調査と比べた景況感の悪化幅が過去最大となった。新型コロナウイルスによる経済の停滞が雇用・賃金の不安を招いており、個人消費の本格回復の妨げになる懸念もある。
日銀の調査は四半期に1度、全国の20歳以上の個人を対象に実施する。今回の有効回答者数は2423人(回答率60.6%)だった。調査期間は5月8日〜6月3日で、緊急事態宣言を受けた外出や営業の自粛の影響が色濃く表れた。
景気が1年前より「良くなった」と答えた割合から「悪くなった」を引いた景況感判断指数(DI)は前回から34.9ポイント下がり、マイナス71.2になった。リーマン・ショック後の2009年9月以来約11年ぶりの低水準に沈んだ。落ち込み幅は06年に今の調査方法になってから最大だ。
背景にあるのが所得面での不安の高まりだ。収入DI(1年前より「増えた」から「減った」を引いた値)はマイナス30.2と5年半ぶりの低水準。落ち込み幅は7.2ポイントとやはり最大だ。
実際に個人の賃金は減少が目立つ。厚生労働省が7日発表した5月の毎月勤労統計調査(速報)によると、現金給与総額は前年同月比2.1%減の26万9341円だった。残業時間の減少で所定外給与が25.8%減の1万4601円と大幅に減ったのが響いた。
残業の削減は企業や個人の働き方改革が進んだ面もあり、中長期的には日本全体の生産性向上につながりうる。現状では収入の減少が先行し、個人の景況感の悪化につながっているとみられる。
日銀調査からは個人消費の慎重姿勢もうかがえる。支出DIは13.4ポイント下がってプラス11と約7年ぶりの低水準になり、落ち込み幅は最大を更新した。総務省が7日発表した5月の家計調査をみても、2人以上の世帯の消費支出は前年同月比16.2%減と4月(11.1%減)からさらに細った。
消費支出は週ごとに分析すると、4月27日〜5月3日の前年同期比26.4%減を底に持ち直しに転じている。緊急事態宣言が全面解除された5月25〜31日の週は1.7%減にとどまった。経済活動の再開や政府による1人10万円の給付金などを下支えに、個人消費は最悪期を脱しつつあるようにみえる。
国内総生産(GDP)の半分以上を占める個人消費が本格的に持ち直すには、家計の不安心理が払拭されるかどうかがカギとなる。日銀調査では1年後の景況感を示すDIがマイナス27.7と14.5ポイント上昇し、約2年ぶりの水準まで改善した。対照的に1年後の収入や支出を示すDIは一段と悪化している。個人が先行きになお慎重な様子が垣間見える。
7月に入って東京都内を中心にコロナの感染者は再び増え始めた。「消費者は不要不急の外出を控えやすくなる」(SMBC日興証券の宮前耕也氏)。「失業予備軍」である休業者は5月時点で423万人と高水準で、企業収益の低迷が長引けば失業者が現実に急増する懸念もある。大和総研の山口茜氏は「家計の節約志向が強いなか、消費がコロナ以前の水準に戻るまでは相当な時間を要する」と指摘する。
9.香港国家安全法、米IT大手に影 ネット自由に影響も
グーグルなど米IT(情報技術)大手が香港当局への利用者情報の提供を一時中止した。各社は香港国家安全維持法で利用者の監視強化を求められ、人権侵害につながる事態を懸念する。事業活動が制限され、インターネットの自由が損なわれる可能性もある。
グーグルとフェイスブック、ツイッターの3社は6日までに、香港当局などへの利用者情報の提供を一時的に止めた。香港メディアはビデオ会議システム「Zoom(ズーム)」の運営会社も香港当局への情報提供を一時中止したと報じた。
背景にあるのは反体制活動を禁じる香港国家安全法の施行に伴う規制強化への懸念だ。香港政府は6日、「国家安全維持委員会」の初会合で、捜査令状なしの家宅捜索を認めるなど捜査手続きの詳細を決めた。ネット上の情報が国家安全に危害を加えると判断すれば、プラットフォーム業者に削除やアクセス制限を求めることもできる。
ロイター通信は中国の北京字節跳動科技(バイトダンス)が運営する動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」が香港から撤退すると報じた。これまで香港で使えたのは海外版アプリで、中国当局の検閲を受けないと同社は説明してきた。
米IT各社は表現の自由など人権保護と各国での法令順守のバランス確保に苦心してきた。グーグルは検閲を求める中国当局と折り合えず2010年から中国本土の検索サービスが使えなくなり、フェイスブックやツイッターもネット利用者が世界最多の中国で利用できない。
香港には本土のようなネット規制がなく、当局もフェイスブックなどのSNS(交流サイト)を積極的に活用してきた。若者の間ではネットが自由に使えなくなる懸念が高まっている。香港記者協会の楊健興主席は7日の記者会見で「オンラインの言動を監視するもので、報道機関にも大きな影響がある」と話した。
今後、香港と中国本土の一体化が進むと、IT大手の立場は難しくなる。監視強化の求めに応じないとネット接続の強制的な遮断などにより香港での事業活動が難しくなる可能性がある。一方で要求を受け入れると米国で利用者や社員から「人権を侵害している」との反発を招きかねない。
グーグルなどは香港や中国の事業から得る収益が限定的だが、中国圏に基盤を持つ企業への影響はより深刻だ。アップルは昨年、中国共産党が問題視したスマートフォンの地図アプリの提供を中止し、米国などで批判を浴びた。米国がけん引する「自由なネット」と検閲を前提とする中国のネットの溝が深まり、企業が「踏み絵」を迫られる場面が増えている。
10.ユーロ圏成長率を下方修正 20年マイナス8.7%に 欧州委
欧州連合(EU)の欧州委員会は7日、経済見通しを発表した。ユーロ圏の実質成長率を2020年は前年比マイナス8.7%、21年は6.1%のプラスに転じると予測し、5月時点からぞれぞれ下方修正した。新型コロナウイルスの打撃が大きいスペインなど南欧の落ち込みが深刻だ。
予測通りならば、20年のユーロ圏の縮小幅は比較可能な1996年以来で最大となる。前回のマイナス成長は2013年のマイナス0.2%。
欧州委は5月時点で20年を7.7%減、21年は6.3%増と予測していた。主要国の20年の成長率をみると、域内最大の経済規模を持つドイツは5月時点の6.5%から6.3%にマイナス幅が縮小。一方、フランスやイタリア、スペインはマイナス幅が拡大した。いずれも2桁のマイナス成長になる見通しだ。
仏伊などは新型コロナの被害が他地域に比べて大きく、多くの死者を出した。その結果、外出制限や営業規制などの期間もドイツよりも長く、経済活動が停滞。南欧諸国の回復の遅れがユーロ圏全体の足を引っ張った。移動などの制限措置は緩和されつつあるが、そのペースは欧州委の予想より遅かった。
ジェンティローニ欧州委員(経済政策担当)は記者会見で「我々は共通のショックに見舞われたが、(回復などの)状況が国によって違うのがリスクだ」と述べた。迅速な景気回復に向けて、EU各国が議論している「復興基金」の早急な合意が欠かせないと訴えた。
一方、欧州委は5月と6月のデータから「最悪の事態が終わった可能性を示唆している」と分析した。IHSマークイットによると、ユーロ圏の総合購買担当者景気指数(PMI)は4月(13.6)を底に6月は48.5と、好不況を判断する節目の50に迫る。夏以降は緩やかな回復軌道にのる見通しだ。オランダのING銀行は4〜6月期の成長率が前期比42%(年率換算)減ったのち、7〜9月期はプラス47%のV字回復を予測する。
21年は反転するが、20年のマイナス分を取り戻すには至らない。各国政府は今後も国民に「社会的距離」をとり続けるよう求めるなどコロナの感染が増加する前のような経済社会にすぐに戻るのは難しい。米国や南米などでは感染が増え続けており、供給網への影響が続く可能性は高い。足元の失業率の悪化幅は小さいが、政策頼みの面が強く、自律的な景気回復に戻らないと、雇用環境が悪化するリスクがある。
この予測は新型コロナに伴う様々な制限が徐々に緩和されることを前提としており、欧州委は「下方へのリスクが極めて高い」と説明した。感染の「第2波」がきて再び制限措置が導入されるなど状況次第で、一段と数値が下振れする可能性に言及した。
11.中国ネット大手の新浪、MBO検討 米ナスダック上場
中国版ツイッター「微博(ウェイボ)」を運営する同国ネット大手の新浪がMBO(経営陣が参加する買収)による株式の非公開化を検討していることを明らかにした。同社は現在、米ナスダックに上場している。米上場の中国企業を巡っては、香港取引所への回帰が進むなど米国離れが加速している。
新浪によると、曹国偉董事長(日本の会長にあたる)兼最高経営責任者(CEO)が率いる企業から6日付で株式の非公開化の提案を受けた。1株41ドルで株式を取得する内容となっており、2日の終値から1割強上乗せした価格となる。発表を受けて6日の終値は40.54ドルで終了した。
中国メディアによると、提案に基づく企業価値は27億ドル(約2900億円)になるという。新浪は特別委員会を設置し、非公開化について検討する。新浪は微博やポータルサイトを運営し、2000年に米ナスダックに上場。ネット大手のアリババ集団は新浪の傘下企業に約3割出資する。
6月には米ナスダックに上場するネット大手、京東集団(JDドットコム)やネットイースが香港取引所に重複上場を果たしたばかり。新浪もMBOが実現すれば、香港や中国本土への上場を検討する可能性がある。
中国企業の「米国離れ」が相次ぐ要因は米国の締め付け強化だ。米当局は長年、米上場の中国企業の監査体制を問題視してきたが、中国側は国内法を盾に、米当局への詳細な監査資料の開示を拒否してきた。ただナスダックは5月末、中国企業を念頭に、新規上場ルールの厳格化を発表した。新浪のMBOについてもこうした事情を考慮したもようだ。
12.豪メルボルン都市圏で外出規制 8日深夜から
オーストラリア南東部ビクトリア州のアンドリュース州首相は7日、同州にある同国第2の都市メルボルンで新型コロナウイルスの感染が拡大しているという理由で、同都市圏に8日深夜から6週間、外出規制を導入すると発表した。対象となる人口は約490万人。
アンドリュース氏によると、州内では7日、191人の新規感染者が確認された。対象の住民は、生活必需品の買い物、運動、通勤や通学などを除き自宅にとどまることが求められ、都市圏への出入りも規制される。飲食店は持ち帰りと宅配に営業を制限する。
ビクトリア州は感染拡大を受け、1日深夜にメルボルン郊外の10地域に外出規制を導入した。4日に対象地域を拡大したが感染抑制のメドがたたないため、対象をメルボルン都市圏に拡大する。
ビクトリア州は6日、豪州の最大都市シドニーがあるニューサウスウェールズ(NSW)州との州境をスペイン風邪が流行した1919年以来の閉鎖に踏み切ると決めた。ビクトリア州の西にある南オーストラリア州との州境も事実上閉鎖している。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10012005
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック