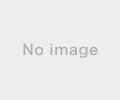2015年07月26日
読書感想文『老病』 おすすめの文章と自分なりの感情
今回のブログでは私「小谷中広之」が読んだ本の中で気に入った文章を紹介するとともに私「小谷中広之」がその文章に対して感じたこと(感情)を書き、少しでも皆様の何かのきっかけになれればこのうえない喜びです(定期的に読書感想文は更新していきます)
決して細かくは書くことはありませんのでご了承ください
私「小谷中広之」が感じた文章を書きたいと思っております
今回のご紹介する本は、浅野浩様の「老病ニモマケズー老年期の病とどう向き合うのかー」です
浅野浩様。1941年名古屋生まれ。1967年金沢大学医学部卒業。1998年慈生会病院病院長。現在、同名誉病院長
気になる文章
●65歳を過ぎますと癌、心臓病、脳血管障害、呼吸器障害などの臓器の障害の他に、骨、関節などの運動機能障害が少しずつ現れてきます。そしてこうした身体の障害とともに、精神的活力の低下を経験することとなります。アルツハイマー病はその典型でしょうか。普通の物忘れとは異なって、自分の人生の歩みに近い過去の記憶のほうから先に消去されていく病気で、少しずつ進んでいきます
○小谷中広之の感情・・・私は今現在で33歳、しかし65歳という年齢まで後32年しかありません。32年後にはまた新たの病気が誕生し、今までは直せなかった病気が直せるようになっていると思います。しかし、32年ごの自分の健康状態を今から少しでも意識して行動することは、自分の将来の夢には大きく関わってきます。70歳までに宇宙移住計画のためにも
●「対象喪失」の時代。人生での自己の存在価値を与えてくれていたものが次々と失われていきます。定年退職により社会的生活から離れ、「社会においての存在」感を失います。加齢とともに、同世代の友人、そして同伴者の死に直面します。こうして自己の存在を確信していた「対象喪失」が訪れることにより、一人の「孤立した」人間となるのです
○小谷中広之の感情・・・高齢者の方たちの存在価値を見出すような、サービス業を考えよう
●痴呆は、軽い状態から重いものへと数年の間に徐々に進みます。
病状の進行を遅らせていくことが大切でしょう。
大切なことは、個人や家族が、精神的な活動を維持できる環境を整備していくことにあります、それには、「親しい知人、家族との交流を保つこと」「読み、書き、話す習慣をつけ、新しい記憶を定着させる努力をする」「残された人生を楽しく過ごす趣味、遊びをもつこと」
○小谷中広之の感情・・・痴呆症は、身近である。これから先自分の両親がならないと決まってはいない。知識と行動は必ず必要となると、考えよう
●ものを書こうとすると手が震えて困る。医学用語で「本能性振戦」
本能性振戦の場合は震え以外の症状はないのですが、パーキンソン病では、脳の錐体外路系と言って、骨格筋の緊張や身体のバランス、運動時の姿勢反射などの調節をつかさどる脳基底核の障害のために、震えや筋の固縮(こわばり)の他に、表情の乏しさ(「無動症」といいます)や小刻み前屈歩行して動作が緩慢となるなどの様々な症状を伴います。日本で10万人余りの人々が登録されている神経難病の一つで、60歳前後で発症し、徐々に進行します。
パーキンソン病は神経難病
○小谷中広之の感情・・・パーキンソン病の方がいたら、少し気をかけよう。転びそうになったら、手を差し伸べられるような気持ちをもとう
●大半の頭痛の悩みは、脳の血行などの機能的障害によるもの。年に数回繰り返しますが、持続時間は数時間から長くても2〜3日で軽快してしまいます。この機能性頭痛としては「片頭痛」「緊張型頭痛」「群発頭痛」の3つ
○小谷中広之の感情・・・頭痛持ちの方は、自分の頭痛を知ろう
●高齢となりますと「抑うつ状態」という気分障害をしばしば経験します。一説では70歳以上の20%の人がこれを認める。
二週間以上抑うつ気分が持続し、食欲の撃退、睡眠障害などの身体症状やイライラ感、思考集中力の減退など精神活動の抑制を伴う場合、これを「うつ病」と呼んでいます
○小谷中広之の感情・・・抑うつは、気分が沈んで何もやる気が起きない状態。これが続くとうつになってしまう。その前に何かできることはないのだろうか。やる気を起こすのではなく、行動を促してやる気を起こさせる方法を考えてみよう。その人(抑うつの人)が抑うつ状態になる前の楽しかった場所や、行動パターンを聞きだして、実際にその場所に連れていってあげてみてはどうだろうか。
自分が「ん!?もしかしたら俺、ここのところ気分が沈み気味でやる気が起きない日が多いな」と思ったら、とりあえずなにか行動してみよう。散歩、ジョギング、料理、外食、景色を見に行くなんでもいいから、思いついたアクティブな行動をとってみよう
●リウマチ関節炎、難病。
30〜40代で発病し、女性に多く、男性の三倍の頻度で現れます。病気の進行は、約30%の方が関節の障害も軽く自然軽減し、その他の方では数十年の間に関節の炎症を繰り返し、全身の関節の変形が進んでいくようです。
この関節炎の活動は、特殊な例を除いて、多くは60歳を過ぎますと寛解(カンカイ)と言われる安定した状態となります。しかし長期の関節障害による運動能力の低下のために、骨粗鬆症、骨の老化による変形が同時に進んでいる場合が多く認められます。
高齢者のリウマチ性関節炎では、運動能力が低下しているほかに、長期間副腎皮脂ホルモン剤を服用されていることなどによって骨粗鬆症が進行しています。そのため、転倒などの強い外力が加わらない軽い動作でも骨折を生じてしまいます
○小谷中広之の感情・・・転倒などでも骨折をしてしまうのであれば周りがケアしていこう。しかし過剰なケアはより一層悪化させてしまいかねない。適度とはどのくらいなのだろうか。声をかけられてから動くのか、声をかけてほしそうな信号をとらえることが出るだろうか、とらえられれば声をかける前に動ける
●嚥下性肺炎。摂食嚥下障害は、食事が思うように取れなくなるという状態。嚥下動作のときに、軌道に食べ物や唾液などの異物が入ると咳き込むわけですが、これは咳嗽(ガイソウ)反射という自律神経の動作によります。最近の老年病学の活動では、この自律神経の反射経路の障害が高齢者に多く認められ、このため「嚥下性肺炎」が生じるとされています。恒例となると、飲み込むときの嚥下反射と軌道への食べ物が流れるのを防ぐ咳嗽反射の両方の機能が低下し、嚥下性肺炎を生じやすくするわけです。
「嚥下性肺炎」の予防として、簡単なことでは次のような方法が挙げられます。「夜、就寝前には口腔内を清潔にする」「冷水でのうがいなどの練習を行う」「腹式呼吸を中心とした嚥下体操をする」
○小谷中広之の感情・・・就寝前には口腔内を清潔とは、しっかり歯を磨き、こまめにうがいを心掛けることなのか
●高齢となり、突然起こる「めまい発作」の多くは、脳の中枢神経の障害がなく、内耳にあります平衡感覚期の障害よるもの
○小谷中広之の感情・・・高齢者で、めまい発作の症状のある人を見かけたら、専門医に受信することをすすめよう
●高齢者の声変わり。
思春期の男子の声変わりは、「アダムのリンゴ」と呼ばれる。
病気による「しわがれ声」についても注意しなければなりません。70歳以上の高齢者で長く続くしわがれ声では、喉頭ガンを頭に入れる必要があります。
高齢となり長く続くしわがれ声を経験されるときには、老人性変化の他に喉頭そのものや、内臓疾患なども頭に入れて専門医を受診なさるべきです
○小谷中広之の感情・・・身近な高齢者の方の声に注意してみよう
●60代を過ぎてきますと、白内障という眼のレンズにある水晶体の老化による視力障害が出てきます。一説によりますと60代で70%、70代で90%、80代以上では100%の人にこれを認めるといわれています
○小谷中広之の感情・・・自分も必ず年をとり、白内障治療または、白内障手術をする日が来るだろう
●慢性肝炎の八割近くがC型ウィルスの感染によるもの。
B型やA型のウィルスと異なって、肝臓での炎症反応が非常に緩やかですが、徐々に進行していくタイプである。初感染から20〜30年の歳月を経て肝臓病が発病するわけですが、70%ほどの方は無症状のままで、30%ほどの方が肝硬変や肝臓がんに移行するといわれています
○小谷中広之の感情・・・ A型肝炎は先進国では上下水道などの整備により感染者は激減。
B型肝炎、肝硬変や肝臓がんをおこす。 毎年約2万人がかかっています。 非常に感染力が強いウイルスで、感染経路はB型肝炎を持った母親からの分娩の時に子どもにうつったり(母子感染)、父親や家族や友人、ウイルスに汚染された血液の輸血や性行為などでの感染が。
●80歳までに男性では半分、女性では三分の一が何らかの癌になることが推定される。
日本人の高齢者で最も多いがんは、胃癌、肺癌、大腸癌、肝癌の順となり、男性では前立腺癌、女性では乳癌、子宮癌が多く認められます
○小谷中広之の感情・・・癌保険の必要性を感じるとともに、もっと大切なのは年に一度の人間ドッグで早期発見
●インフルエンザの流行は、毎年12月から2月の冬期に認められます。この理由としては、ウィルスの生存条件としては、湿度の低い乾燥した気候が必要で、50%以下の湿度が条件であるといわれています
○小谷中広之の感情・・・去年は9月後半から翌年の5月の半ば頃までR-1を一日一本飲んでいて、インフルエンザにはならなかった。R-1がすべてではないが、一理あるかもしれない
●心臓の拍動は、毎分、安静な時で60回ほど規則正しく行われていますが、これは自律神経によって調整されているため、運動や興奮などで毎分160前後に心拍数が増加することがあります。心臓の拍動は、生涯を通して約120億回繰り返されると推計されていますから、上手に心臓を使えば100〜120歳までの寿命があるということになります
○小谷中広之の感情・・・120億回、今現在は何回くらいの拍動なのだろうか
●心臓は、ほかの臓器と同じように、ポンプとしての仕事をするために、血液の供給を必要としています。冠状動脈がその役割を補っていますが、その動脈が動脈硬化などによって狭くなり、血流障害を生じると狭心症や心筋梗塞を発病します。心臓は他の臓器と異なって酸素消費量が大きいため、75%以上の冠状動脈の狭窄が生じると血流不足となり、症状が出現します。このことから狭心症や心筋梗塞を虚血性心臓病と称しています。
冠状動脈の動脈硬化は30代から徐々に始まり、65歳を過ぎますと大半の成人に多少の差はありますが動脈硬化が認められるといわれています
○小谷中広之の感情・・・簡単に無料に、しかも誰かの役に立てる血液検査の方法は「献血」だ。献血に行こう。あなたの血液を必要としている人が必ずいる。自分の血液が献血でなくなったても、その分だけまた新しい血液が自分の体に誕生するのだから
●エコノミークラス症候群の予防には、飛行機搭乗前に軽い食事をするのが良いといわれています。そして飛行中は水分を十分とることや、遠慮なくお手洗いに行くなどして体を動かすことも必要です。座席は窓側よりは通路側とし、移動が気軽にできるようにすることもよいかもしれません
○小谷中広之の感情・・・飛行中に限らず、座り仕事のときは意識的に立って運動する時間を適度にもうけよう
●糖尿病。
日本では平安時代にすでに「飲水病」とか「渇き病」という言葉で伝えられています。
当時から、「飲水病」の誘因は美食、美酒の食生活にあると注意されていた
○小谷中広之の感情・・・食事の管理を徹底していますと息苦しい。しかし、少しは気を使おう。病気なってからでは遅いのだから
●お尻の部分の皮膚が黒くただれている、これは褥瘡(床ずれ)。脳血管障害をもつ高齢者にしばしば認められるものです。
褥瘡(ジョクソウ)は、寝たきりとなった状態の患者さんの多くは、仙骨部(お尻の上の部分)、大腿骨の大転子部(腰の両脇の部分)、踵部(かかと)など骨が突起したところの皮膚には発病します。皮膚の同じ場所に長時間圧力が加わり、このため皮下の組織の血行障害が起きて皮膚の損傷となるものです。
褥瘡の予防のためには、まず第一に食事摂取を安定させ、栄養状態を改善すること。
二番目は、体位変換を一日6回以上行うなど、長時間皮膚が圧迫を受けないよう工夫すること。
三番目に必要なことは、スキンケア
○小谷中広之の感情・・・その他にも精神的なケアも必要であろう。自分には何もできない場合でも、話し相手にはなってあげられるだろう
●「死」を目前にしたときにそれを受け入れることは、私たち凡人にとっては容易なことではありません。
「死の受容」に至る過程は5段階あるようです。
1、病気(病名)の否認
2、怒り
3、何かによって死を先延ばしにするという取引の試み
4、抑鬱という喪失への心的葛藤
5、第一〜第四段階のすべてを乗り越えて、死の受け入れ
○小谷中広之の感情・・・死の受容患者さんの親族の方にも同じような過程が起こるのではないだろうか
●「良医とはどんな医者か」について鎌田實医師は、「話をよく聞く、わかりやすく説明してくれる」、「家族の気持ち、患者の悲しみ、辛さを理解してくれる」など患者の立場に立ってコミュニケーションをとることのできる医師。
患者としては十分な説明を受け、納得いくようにして治療方針などを決める「自己責任」が求められています
○小谷中広之の感情・・・接しやすく、話しやすく、親身になってくれる医師を見つけたら大切にしよう
ここまで読んでいただきありがとうございます。読んでいただいた方の人生での何かのお役に立てればとても嬉しいです
浅野浩様「老病ニモマケズ」
この本の他の文章が気になった方下記のサイトで購入可能です。
タグ:浅野浩 様
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/3971692
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック