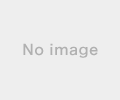2016年04月14日
初めてのバラ栽培 害虫の駆除
暖かくなり新芽が芽吹くころになると
新芽の部分に色々な害虫が発生します。
良くつきやすい害虫とその対処を紹介します。
新芽の部分に色々な害虫が発生します。
良くつきやすい害虫とその対処を紹介します。
①アブラムシ

【主な症状・特徴】
野菜苗や果樹苗や庭木などでも、よく見かける小さな虫。
黒点病に並ぶほどに、あらゆる植物に発生が多い困ったサンです。
緑や黒色の小さな虫が、若い葉の裏や蕾に群がって樹液を吸います。
葉がしわしわになったりで、見栄えも悪くなりますし、
酷いと生長も悪くなります。
排泄物が「すす病」の原因になり、
「他のウィルス病」などを媒介し二次病害の原因にもなる上、
アブラムシは短期間でよく増えるので、放っておくと大変です。
【発生時期】
4~11月頃(早春~初夏・秋頃)。7、8月の暑い時期はあまり見られないです。
【対処法】
なるべく早くに発見し、捕殺や薬剤散布などをします。
数が少ない場合は何とか手で取れないこともないですが、
いかんせん相手が細かいので苦労します。
但し、薬をまく場合、同じ薬剤を続けてかけると
耐性ができてしまうので、時々薬品を変える事も必要です。
消毒散布後2日後くらいの朝、ホースの水圧で死骸は吹き飛ばします。
※ 春先は薬剤の抵抗が強く、効きにくいとも言われています。
なるべく数が少ないうちに手で取ってしまってください。
【ワンポイント】
アブラムシはきらきらと光る光を嫌う性質があります。
鉢の土の表面にアルミホイルを敷くとアブラムシが
発生しにくいです、一度試して下さい。
【予防・対処薬剤】
・アセフェート(オルトラン)
・トリホリンエアゾル(オルトランC)
・ピリミホスメチル(アクテリック)乳剤
・プロチオホス(トクチオン)乳剤
・ベニカX
・ベニカDスプレー
・マラソン乳剤
・MEP(スミチオン)乳剤
(※上記は一例です)
②チュウレンジバチの幼虫

【主な症状・特徴】
成虫が飛んできて幹に産卵し、幹の産卵痕は、縦にすっぱりと裂けてしまいます。
痕は治りかけの傷のように、裂けたふちが盛り上がって見栄えが悪くなります。
孵化した幼虫は、旺盛な食欲であっという間に若い葉を食べてしまいます。
しかも、1枚の葉に集団でとりつくので、大本の葉脈を残して
食べつくしてしまうまでに、さほど時間がかからないです。
頭が黒やオレンジで、胴体の緑色の幼虫が、葉のふちについてモリモリ食べます‥‥
【発生時期】
4月~11月頃。だいたい、春から秋にかけての期間に発生します。
バラを育てたことのある方なら、おそらく一度は目にした事がある虫です。
【対処法】
成虫にも薬剤は効きますが、飛んでくるので完全に駆除するのが難しいです。
被害にあった葉は取り払い、幼虫は、見つけたら捕殺します。
数が多いときには薬剤をまいてやってください。
【対処薬剤】
・マラソン乳剤・オルトラン
・スミチオン
・ピリダフェンチオン(オフナック)乳剤
(※上記は一例です)
③バラゾウムシ

【主な症状・特徴】
小型のアリほどの大きさ(3~5mm位)の、
口が象の鼻のように伸びた甲虫がこれです。
蕾や新芽が小さいうちに産卵して、産卵箇所より先が、
ちりちりと黒く焦げたように枯れさせてしまいます。
他には、長い口で汁を吸い、蕾がうなだれ枯れるなどの被害も出ます。
【発生時期】
5~6月頃。7~10月にも発生することがあり、どこからか飛んできます。
【対処法】
小さいので難しいですが、可能であれば捕殺します。
意外と増殖が早く、放っておくと増えますので早めに薬剤をまいてください。
アブラムシや他のものと同じく、同じ薬品を連続して散布すると
抵抗力がついてしまうので、薬剤は散布のたびに変えると良いです。
また、しんなりした蕾や枯れた部分などを放置すると、
それをエサに幼虫が育つので、速やかに除去しておくと予防になります。
【対処薬剤】
・MEP(スミチオン)乳剤
・アセフェート(オルトラン)
・生薬のジックニーム
(※上記は一例です)
④ハダニ

【主な症状・特徴】
肉眼では見えにくい小さな虫が、葉の裏などに引っ付いて樹液を吸い、
吸われた部分が白い斑点になり、
葉が黄色くなったり、表面が白っぽいカスリ状になって落葉します。
他には、新芽がちぢれて大きくならなかったり、
ダニの種類によってはクモの巣状になることもあります。
【発生時期】
4月~11月頃。気温の低い時期は発生しにくいです。
特に夏期の高温乾燥時の被害が目立ちます。
【対処法】
見つけたらすぐ症状の出た葉を取り除き、
対応薬剤を3日間隔くらいで3~4回ほどまきます。
※ 同じものを連続して散布すると、やはり抵抗力がついてしまうので、
アブラムシ同様、薬剤は散布のたびに変えたほうが良いです。
※ 治まらずに全ての葉が落ちてしまったら、症状の出ている葉を整理して、
軽く切り戻して追肥を与えます。
新芽が伸びてきたら薬剤を散布して、再発を予防します。
ダニは水が苦手。風通しがよく、定期的に葉が雨などで洗われるような場合 は
ハダニはほとんど出ません。
定期的にホースなどの水で勢いよく葉を洗い流す(葉水をかける)
だけでずいぶん予防になります。
※やりすぎると蒸れるので、カビやアブラムシ発生の原因になります。
ほどほどに!
【対処薬剤】
・ケルセン
・粘着くん液剤
・フェンピロキシメート水和剤(ダニトロン フロアブル)
・酸化フェンブタスズ(オサダン)水和剤
・アミトラズ(ダニカット)乳剤
・石灰硫黄合剤(冬季、幹のひだや根元に浸透させるとよいです)
・ジックニーム
・ハダニ用薬剤
(※上記は一例です)
⑤カミキリムシ

【主な症状・特徴】
株元に木くずのようなものが出ていたら、この虫がどこかにいます。
あっという間にバラを枯らす恐ろしい害虫です。
成虫は茎の皮や新芽を食べて、それより先を枯らしてしまいます。
幼虫はもっと酷く、幹や根の内部を食べながら3年目にさなぎになります。
枝や幹の内部を食べ進んでいくため、その部分が空洞になり、
それより先の部分は枯れます。
ですから成虫よりも、幹に潜り込み中心をくりぬいてしまう幼虫のほうが
厄介と言え、最悪、幹が折れてしまいます。
【発生時期】
5月~9月頃(※成虫や、新しく発生した幼虫を良く見かける時期)。
幼虫は2~3年かけて育つので、発生時期は「通年」と考えてもらってもよいです。
(新しく発生したものは8~9月に確認可能です)
成虫は5~7月に多いので、捕殺するならこの時期です。
【対処法】
成虫は、春過ぎ~初夏にかけて、発見しだい捕殺をするようにして、
しばらく他の成虫が来ないかを警戒しておきます。
株元に木くずのようなものが出ていたら、幼虫がいる可能性があります。
潜んでいると思われる穴を探し、
1.針金などで中の幼虫を刺して、息の根を止める
2.穴に殺虫剤を(100倍程度に希釈して)スポイト注入&塞ぐ
3.穴に薬剤をスプレー&何かできっちり塞ぐ
4.穴を薬剤を染み込ませた綿などで塞ぐ
‥‥などして退治します。
もしもまだ株元に「おがくずのようなフン」が溜まっていたら要注意。
失敗か、他にもいる可能性があるので、怪しい穴を探して上記の対処を行ってください。周囲などに、卵を産み付けそうな枯れ枝などがないか確認をし、掃除をしておくと予防になります。
万が一、残念ながら完全に枯死してしまった場合、
新しい幼虫が発生しないうちに、速やかに片付けてあげてください。
【対処薬剤】
・スミチオン乳剤
・アリアトールA
・市販の殺虫剤
(※上記は一例です)
⑥コガネムシ/甲虫類

【主な症状・特徴】
10~15mmのつやつやした虫が飛来して蕾や花弁を食い荒らします。
花にもぐりこんで食い荒らすほか、葉や茎も食べます。
(白や黄色の、明るい花色のものが被害を受けやすいとも言われます)
幼虫は(路地ならさほど問題はないが)鉢栽培の場合、
鉢の中で動き回り、根をかじって枯死させることがあります。
【発生時期】
春~秋頃。幼虫は8~10月頃、成虫は5~9月頃に発生します。
【対処法】
■成虫の場合――
発見しだい(もしくは誘引罠(市販/自主制作)を使って)、
捕まえてとどめをさしてください。または薬剤を木とその周囲に散布して下さい。
朝涼しい時間帯に株を揺すると寝ていたコガネムシが落ちますので、
そいつを捕まえてとどめをさします。
■幼虫の場合――
鉢物で急速に生育が衰えた場合は、被害を受けていることがあるので、
苗を抜き、食害されている場合は古土を捨てて新しい用土で植え込むようにしてやります。被害にあった苗が元気になるまでは、半日陰で管理するといいです。
【対処薬剤】
■幼虫――
・ダイアジノン粒剤
■成虫――
・スミチオン
・マラソン
・アクテリック乳剤
(※上記は一例です)
これから害虫たちも活発に成って来ます
害虫たちに負けないように毎日の観察を怠らず
見つけたら被害の無いうちに対処しましょう。
害虫たちに負けないように毎日の観察を怠らず
見つけたら被害の無いうちに対処しましょう。
タグ:初めてのバラ栽培