月曜日。半分の月がのぼる空二次創作の日です。
前回、弾が切れたと言いましたが・・・
天啓が降りましたwww
いや~、一昨日のテレビでひじきは伊勢の名物とかやってるの見たらピキーンとね。
ネタって、何処に落ちてるか分かりませんね。アンテナは広げとくもんです。なんなりと。
~と、言う訳で即興ですが、何とか掲載。
今回はコミカルな感じにしてみようかなとか思っています。
派手なキャラ崩壊とかはありませんが、一応そこんとこ了承の程を。
ではでは。
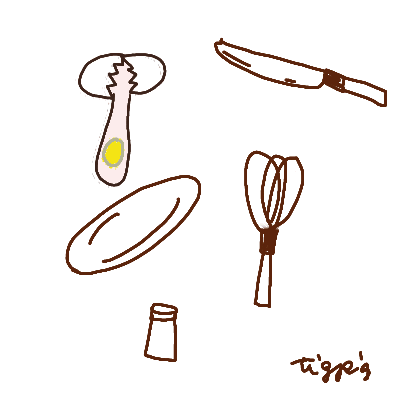
 |
新品価格 |
―1―
ガタガタ・・・ゴトンッ・・・ドン、ガタッ・・・
耳に聞こえてくる、妙に騒がしく、そして妙に重い音。
それを聞きながらまんじりともせず、戎崎裕一は座布団の上で正座をしていた。
日は5月も半ばの日曜日。
時は昼間の11時。
場所は秋庭里香の家。
そして戎崎裕一が座っているのは、その茶の間の一席。
件の物音は、茶の間に隣接する台所から聞こえていた。
一体、何が起こっているのか。
答えは簡単。
秋庭里香が料理をしているのである。
何故か。
それも簡単。
戎崎裕一に食させるためである。
一人の少女が、恋人に食させるために料理をしている。
なんら、不自然な事ではない。
むしろ、男にとってはこれ以上ない、幸福なシチュエーションの一つであると言えるだろう。
にも関わらず、戎崎裕一の心境は穏やかではなかった。
その額には脂汗が浮き、強張った様に正座した膝に添えられた手は、カタカタと小刻みに震えている。
その様はまるで、刑の執行を待つ死刑囚の様である。
ガタンッ
台所で、また大きな音がした。
戎崎裕一は、思わずビクリと飛び上がった。
さて、何ゆえこの様な事態におちいっているのか。
話は一週間前の日曜日にさかのぼる。
その日、戎崎裕一は自分の家で、秋庭里香といっしょにテレビを見ていた。
何の変哲もない、ありふれたホームドラマである。
戎崎裕一と秋庭里香は、何時も通りに会話を交わし、時にドラマの内容に突っ込みを入れながら穏やかな時を過ごしていた。
しかし、突如その空気が一変した。
原因は、戎崎裕一の何気ない一言。
ドラマで、主人公の恋人が主人公に夕食を作ってあげるシーンが流れたのである。
それを見た戎崎裕一は一言、「いいなぁ・・・。」と漏らした。
別に何か他意があったわけではない。
ただ何となく、視覚から入った情報が漠然と抱いていた願望を口から押し出しただけである。
しかし、それが秋庭里香の耳に入ってしまった。
「裕一、ご飯作って欲しいの?」
「え、あ、いや、別にそういう訳じゃ・・・」
咄嗟に口をついて出た言葉が、さらにまずかった。
「何、それ?あたしじゃ出来ないって言うの!?」
秋庭里香の語気が、あからさまに剣呑なものになる。
こりゃいかんと思ったが、もう遅い。
「いや、そういう訳でも・・・」
「じゃあ、どういう意味!?」
秋庭里香に迫られ、戎崎裕一はしどろもどろになった。その態度が、さらに秋庭里香の神経を逆撫でする。
「やっぱり、出来ないと思ってるんだ・・・。」
「いや、だから・・・」
“いや”ばかりを連発する戎崎裕一に、ついに苛立ちが頂点に至ったのか、秋庭里香はグワッと立ち上がった。
「分かった!!それじゃあ、作ってあげる!!」
呆然と見上げる戎崎裕一を見下ろしながら、秋庭里香は高らかにそう宣言した。
―2―
その後、何やかやがあって、Xデーは一週間後の日曜日という事になった。
何の事はない。その日の昼間が双方の親が不在であり、お互いの昼飯時が空いていたからである。
秋庭里香の機嫌を損ねてしまった事を悔いつつも、戎崎裕一の内心は浮き立っていた。
当然かもしれない。
たった二人で恋人の手料理を食するなど、およそ男性にとっては嬉しい事この上ないシチュエーションの一つである。
瓢箪から駒とは、正にこの様な事なのだろう。
何だかんだ言いながら、その点においては戎崎裕一はハッピーだったのである。
“その日”が来るまでは・・・。
“その日”、戎崎裕一は親友である世古口司から呼び出された。
大事な話があるというのである。それも、ただ“大事”なのではなく、“重大”な話だと言う。
話を聞いた時、正直戎崎裕一は気が乗らなかった。
理由は簡単。
戎崎裕一本人の気が滅入っていたからである。
その理由も簡単。
今週に入ってから、放課後に秋庭里香と一緒の時間を過ごしていなかったのだ。
一緒に帰ろうと誘うと、用事があるからと断られてしまう。
それじゃ付き合うと言うと、ついて来ないでとつっけんどんにされる始末である。
どうした事だろう。
何か気に障る事でもしただろうか。
何しろ、相手はあの秋庭里香である。
一体、何で鼻を曲げられるか分かったものじゃないのである。
あれよこれよと考えるのにいっぱいいっぱいで、正直これ以上厄介事を背負い込みたくはなかったのだ。
これが同じ“重大な話”でも、もう一人の友人の山西保の話であれば、どうせくだらないものだと蹴っ飛ばす事も出来る。というか、間違いなくそうする。
しかし、今回の相手は世古口司である。
彼が“重大”というからには、本当に“重大”なのだ。
彼は大事な親友である。
その頼みを無下に断る訳にもいくまい。
少なからずの嫌な予感を覚えながら、戎崎裕一は促されるまま世古口司についていった。
階段の踊り場の、人気のない場所まで来ると、世古口司は戎崎裕一に向き直った。
世古口司の目が、伏目がちに戎崎裕一を見つめる。
真剣な表情であった。
悲壮感すら感じさせる表情であった。
世古口司はしばし無言で戎崎裕一を見つめていたが、やがて何かを決心したかの様にこんな事を切り出した。
「裕一、里香ちゃんの事、好きなんだよね!?」
「・・・は?」
戎崎裕一は呆気にとられた。
どんな大事を告げられるのか緊張して来て見れば、今更何を言っているのだこの男は。
しかし、世古口司は依然として真剣な表情のままである。
「好きなんだよね!?」
彼にしては珍しく、語調を強めて再び訊いて来た。
戎崎裕一の肩をガシッと掴み、顔を寄せてくる。
世古口司は大きい。その温厚な性格故いつもは目立たないが、いざこんな風に迫られると凄い迫力と威圧感である。
そこらへんの格好だけの不良なら、目を合わせて10秒も持たずに逃げ出すだろう。
「お、おう。あ、当たり前だろ。」
その迫力に押される様に、戎崎裕一はそう答えた。
それを聞いた世古口司はホッとした様で、それでいてどこか悲しげな眼差しを戎崎裕一に向けた。
「な・・・何だよ?」
「裕一、落ち着いて聞いてね・・・。」
そう言うと、世古口司はポケットから何やらガサゴソと紙を取り出した。
それは数枚のコピー用紙であった。
それを無言で、戎崎裕一に渡す。
見てみると、それには何やら画像がコピーされてあった。
恐らく、携帯で撮った写真をパソコンに取り込み、プリントアウトしたものだろう。
しかし、これは何だろう。
テーブルの上に、一枚の深皿が置いてある。
それは分かる。
問題は、その中身だ。
深皿の底に鎮座し、湯気を立てているそれは、実に奇怪な物体だった。
色は一言で言えば、黒である。しかしただの黒ではない。色の濃い場所薄い場所。青味がかかった場所もあれば紫っぽい場所もある。
形状は何とも形容しがたい。強いて言えば、瓶詰めの海苔の佃煮が一番近いかもしれない。しかしそれを言えば、海苔の佃煮の方が憤慨のあまり卒倒するだろう。
全体的にベチャッとした印象かつ、妙なネトネト感が見て取れ、箸を突き立てたらそのまま立っていそうだ。所々、妙な突起物がピョンピョンと飛び出しているあたりが、見た目の気味の悪さに拍車をかけている。
・・・総じて言えば何と言うか、本能的に強い忌避感を覚える様な代物であった。
「・・・何だよ?これ・・・。」
「・・・の・・・だよ・・・。」
戎崎裕一の問いに、世古口司はボソボソと答えた。
妙にくぐもった声であり、よく聞こえない。
「は?何だって?」
戎崎裕一はもう一度訊いた。
「・・・の・・った・・り・・・だよ・・・。」
まだはっきり聞こえない。
何か、口にする事すら躊躇している様な感じである。
「は?」
戎崎裕一の再三の詰問に、世古口司はついに決心した様に、声を大にしていった。
「里香ちゃんの作った料理だよ!!」
世古口司の言葉は、そのまま稲妻の如き戦慄となって戎崎裕一の身体を貫いた。
続く
【このカテゴリーの最新記事】


.jpg?2023-01-2212:27:19)
