2014年01月03日
「1分間速読法ーあなたも1冊1分で本がよめる!」 石井貴士
タイトルが衝撃的である。10分ならばまだ理解できるが、1分間は想像すらできない。
大概の速読を謳う本では具体的なテクニックには言及しない。呼吸法や眼球トレーニングどまりで、末尾で著者の速読教材・教室へのアクセスが載っているだけ、80%は無意味な宣伝文句ばかりだ。書籍の体をなして店頭に並び澄ましている分、情報商材よりもタチが悪い。
本書はそんな「速読」業界からやってきたにしては、かなり良質な方である。きちんと速読自体のテクニックに触れられているからだ。200ページちょっとあるが、核心は150ページ以降を読めばよい。右手で本を持ち、左手でめくる際、周辺視野で見開き2ページを0.5秒で眺め飛ばすそうである。また、1分間読書法に至るための3段階の自主トレーニング法が載っているのがよい。ほかの部分は大して意味がない精神論や商売文句だが、1冊の中にしっかりと中身もあるから優良である。
肝心の速読法の効果だが、まだ訓練中なのでまだわからない。読むのではなくめくるのだと著者は言い、理解しようとするから他の速読は遅いのだと説く。この速読は、読後なんとなくわかってはいるが、うまく答えられない状態というように読後の理解をとらえ、既存の速読のように内容を記憶せんばかりの理解には興味を示していないのだが、読書自体の意義は書物から何かをつかみ取ることである。その点についての詳しい言及が欲しいところである。
本書の速読法が実践性・普遍性に富むものかは、時間が数年後証明するであろう。ただ、詐欺まがいではないタイプの新たな速読本が出たことは喜ぶべきことである。
速読
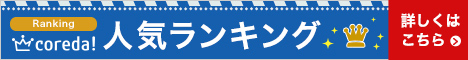

大概の速読を謳う本では具体的なテクニックには言及しない。呼吸法や眼球トレーニングどまりで、末尾で著者の速読教材・教室へのアクセスが載っているだけ、80%は無意味な宣伝文句ばかりだ。書籍の体をなして店頭に並び澄ましている分、情報商材よりもタチが悪い。
本書はそんな「速読」業界からやってきたにしては、かなり良質な方である。きちんと速読自体のテクニックに触れられているからだ。200ページちょっとあるが、核心は150ページ以降を読めばよい。右手で本を持ち、左手でめくる際、周辺視野で見開き2ページを0.5秒で眺め飛ばすそうである。また、1分間読書法に至るための3段階の自主トレーニング法が載っているのがよい。ほかの部分は大して意味がない精神論や商売文句だが、1冊の中にしっかりと中身もあるから優良である。
肝心の速読法の効果だが、まだ訓練中なのでまだわからない。読むのではなくめくるのだと著者は言い、理解しようとするから他の速読は遅いのだと説く。この速読は、読後なんとなくわかってはいるが、うまく答えられない状態というように読後の理解をとらえ、既存の速読のように内容を記憶せんばかりの理解には興味を示していないのだが、読書自体の意義は書物から何かをつかみ取ることである。その点についての詳しい言及が欲しいところである。
本書の速読法が実践性・普遍性に富むものかは、時間が数年後証明するであろう。ただ、詐欺まがいではないタイプの新たな速読本が出たことは喜ぶべきことである。
速読










