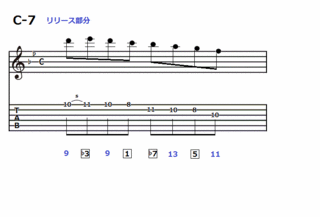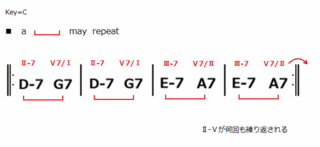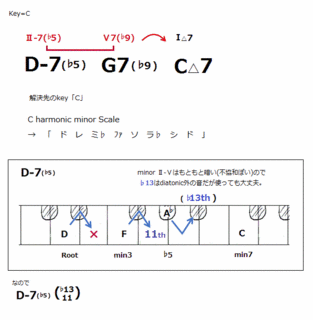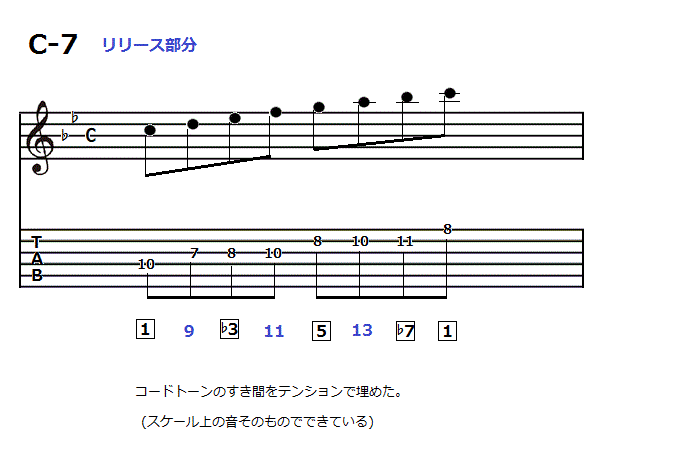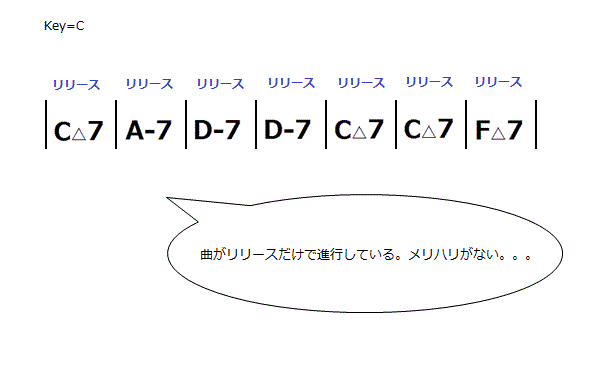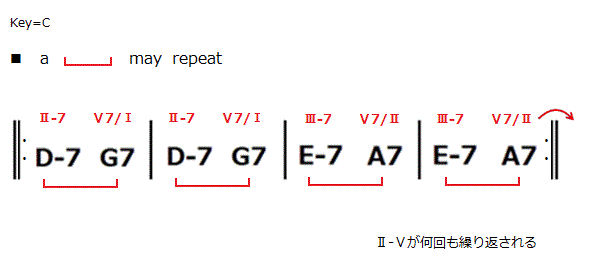2015年05月05日
0053. アナライズを利用してダイアトニックリハモニゼーションしてみる。Ⅴ7(sus4)の解釈がポイント。あと解決はディセプティブレソリューションできることも知っておくとアレンジの幅が広がります
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
♪♪今回はアナライズの方法です
diatonic reharmonizationのアナライズは
それぞれの役割をアルファベットで書きます
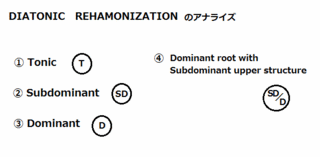
dominant root subdominant
upper structure(SD/D)とは
Ⅴ7(sus4)のことです。
このSD/Dは
その曲での使われ方で
その役割はSDともDとも解釈できます
くわしくはここで
→Ⅴ7(sus4)の説明①ドミナントモーションについて
→Ⅴ7(sus4)の説明②演奏上のヴォイシング例
【スポンサーリンク】
そこを踏まえながら、
diatonic reharmonizationをすると
次のようなやり方が考えられます
例)この曲をreharmonizationしていきます
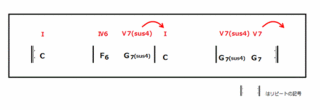
まず、各コードの
diatonic reharmonizationの
アナライズを書いていきます
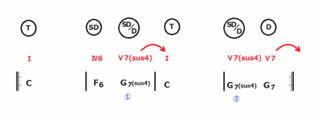
Ⅴ7(sus4)の①は、
ドミナントモーションしているので
→「D」と捉える
Ⅴ7(sus4)の②は、
Ⅴ7の前で猶予を持たせているだけで
ドミナントモーションは直接していない
→なので「SD」と捉えてみる
以上から
コードの役割をまもりつつ
Diatonic reharmonizationしてみます
reham.例)
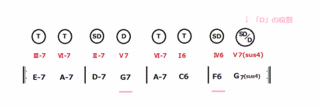
Diatonic reharmonizationは
フレーズの音価なども考慮して
同じ役割のコードから選択していきますが
今回は進行だけなので
前半は5度進行をベースに組み替えてます
よく使われる3625進行のパターンです
後半はそのままⅠⅣⅤ進行の流れのまま
一部をⅥ-にして組み立ててます
前後半とも、
元々のⅤ7(sus4)コードの位置にも
うまくD、SDのコードが入ってます
コード進行感はずいぶん変わりましたが
小節ごとの役割は
おなじものなのでこの変化を
楽しんでみてください
(●´艸`)フ゛ハッ
■deceptive resolutionに注意
reharmonization後の
2小節目Ⅴ7thコード①と
4小節目さいごのⅤ7(sus4)コード②は
どちらも「D」の役割なので
本来ならドミナントモーション
しているはずの進行なのですが、
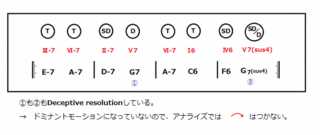
Point!!)
reharmonizationにより解決先が変わったため
解決先が「Ⅰ」でなくなった結果
→ドミナントモーションではなくなってます
このような
本来の解決先以外に向かう
コード進行のことを
→deceptive resolutionといいます
(ゴマカシカイケツとも呼ばれる)
Diatonic reharmonizationによって
進行を組み替えていくと
deceptive resolutionすることも増えますが
このdeceptive resolutionは
ディセプティブの効果を
意図的に狙って進行を組み立てるものなので
ここから先のコード進行は
より複雑な組み立てが可能になります
その結果
コード進行のアナライズは
判断がだんだん難しくなるので
ここからは注意して
曲全体を見るようにしましょう
(●´∀`)ノ+
ひとまず今回は以上です
次回は、何曲か実例をはさんで
reharmonizationの練習をしましょうか
連休明けたら更新遅れるとおもうから
がんばるよおおヾ(*・ω・)ノ゜
♪♪今回はアナライズの方法です
diatonic reharmonizationのアナライズは
それぞれの役割をアルファベットで書きます
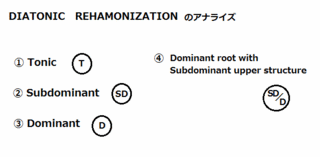
dominant root subdominant
upper structure(SD/D)とは
Ⅴ7(sus4)のことです。
このSD/Dは
その曲での使われ方で
その役割はSDともDとも解釈できます
復習) 以前にも触れましたが Dominant7th(sus4)コードは その構造は演奏上 SDコード/5 of key(←bass音)の形で Ⅴ7(sus4)コードとなり また その利用の方法は ①Ⅴ7の代わりとして用いられるもの →直接ドミナントモーションする ②Ⅴ7の前に一度猶予を持たせるもの →直接はドミナントモーションしない の2つがあります。 |
くわしくはここで
→Ⅴ7(sus4)の説明①ドミナントモーションについて
→Ⅴ7(sus4)の説明②演奏上のヴォイシング例
【スポンサーリンク】
そこを踏まえながら、
diatonic reharmonizationをすると
次のようなやり方が考えられます
例)この曲をreharmonizationしていきます
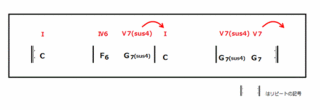
まず、各コードの
diatonic reharmonizationの
アナライズを書いていきます
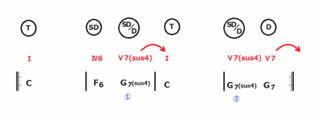
Ⅴ7(sus4)の①は、
ドミナントモーションしているので
→「D」と捉える
Ⅴ7(sus4)の②は、
Ⅴ7の前で猶予を持たせているだけで
ドミナントモーションは直接していない
→なので「SD」と捉えてみる
以上から
コードの役割をまもりつつ
Diatonic reharmonizationしてみます
reham.例)
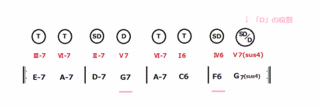
Diatonic reharmonizationは
フレーズの音価なども考慮して
同じ役割のコードから選択していきますが
今回は進行だけなので
前半は5度進行をベースに組み替えてます
よく使われる3625進行のパターンです
後半はそのままⅠⅣⅤ進行の流れのまま
一部をⅥ-にして組み立ててます
前後半とも、
元々のⅤ7(sus4)コードの位置にも
うまくD、SDのコードが入ってます
コード進行感はずいぶん変わりましたが
小節ごとの役割は
おなじものなのでこの変化を
楽しんでみてください
(●´艸`)フ゛ハッ
■deceptive resolutionに注意
reharmonization後の
2小節目Ⅴ7thコード①と
4小節目さいごのⅤ7(sus4)コード②は
どちらも「D」の役割なので
本来ならドミナントモーション
しているはずの進行なのですが、
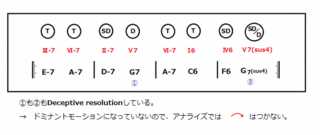
Point!!)
reharmonizationにより解決先が変わったため
解決先が「Ⅰ」でなくなった結果
→ドミナントモーションではなくなってます
このような
本来の解決先以外に向かう
コード進行のことを
→deceptive resolutionといいます
(ゴマカシカイケツとも呼ばれる)
Diatonic reharmonizationによって
進行を組み替えていくと
deceptive resolutionすることも増えますが
このdeceptive resolutionは
ディセプティブの効果を
意図的に狙って進行を組み立てるものなので
ここから先のコード進行は
より複雑な組み立てが可能になります
●deceptive resolutionの強さにも注意 Ⅴ7コードがⅠへ向かう代わりに Ⅲ-やⅥ-などの おなじTonicの仲間に進行する場合は ディセプティブ感はあまり強くなく ⅣやⅡ-などの ほかの役割に進行する場合は ディセプティブ感は強くなります |
その結果
コード進行のアナライズは
判断がだんだん難しくなるので
ここからは注意して
曲全体を見るようにしましょう
(●´∀`)ノ+
ひとまず今回は以上です
次回は、何曲か実例をはさんで
reharmonizationの練習をしましょうか
連休明けたら更新遅れるとおもうから
がんばるよおおヾ(*・ω・)ノ゜
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/3625077
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック