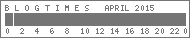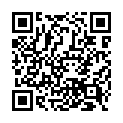2012年06月22日
これからのカフェの行く先
日本のカフェの新しいスタイルは今も確実に誕生している。
2001年4月にカフェ激戦地、大阪・堀江のはずれにオープンした「Logic」(ロジック)は、ブライダルも行う大型カフェである。経営は心斎橋を中心に「グラム」「ナイン コンテンツ」など、6店のカフェ、レストランを展開する急成長企業であり、それまでは若年層をターゲットにした業態を展開していたが、「店に来ていただいているお客様に、ブライダルもできる場所を提供したかった」という思いで、ブライダルカフェというコンセプトがつくられたという。店内は「大人を対象にした店づくり」で、余計な装飾はいっさいなく、インテリアも黒や茶、グレイなどシックな色で統一しており、実際に30〜40代のお客が多い。建物は4階建てで、1,2階はカフェレストランとして、3階は同社のオフィスと、セントラルキッチンが配置され、4階は披露宴やイベントなどをおこなうパーティスペースとし、屋上には挙式もできるガラス張りの空間をつくっている。
2001年9月にオープンした「MERCURY」(マーキュリー)は「しっかりと食べられる食事、おいしいデザート、ドリンクを出す店にニーズを感じ、客層も幅広くしたかったので、メニューの6〜7割は和食を中心にした定食に決めました」とオーナーの吉田大門さんが言うように、イワシや銀ムツに、福島産のコシヒカリのごはん、野菜の小鉢、味噌汁、漬物というような、まさに「定食」を提供するカフェである。店内にはレトロな日本製の家具をゆったりと配置し、落ち着ける雰囲気である。
ロサンゼルス在住のファッションデザイナーが展開する「空(KU)」ブランドの「café KU(カフェ・クウ)」は、おしゃれなブティックやレストランが点在する若者の街、代官山に2001年8月にオープンした。独特の箱型フォルムの建物の1階に同ブランドのブティックがあり、カフェは2階に位置している。空ブランドはアメリカ人デザイナーがイメージした“和”の世界を表現しているが、それは日本にとどまらず、中国やインドなどアジア各国のエッセンスが融合した不思議な雰囲気が漂ったものである。そのイメージに合わせて、カフェのメニューには、和食やエスニックをアレンジした個性あふれる料理や豊富なバラエティの日本茶メニューが並ぶ。「代官山にはカフェはたくさんありますが、日本茶や和食を気軽に味わえる場所は少ないんです。ここは外国の方がイメージした“和”がコンセプトですから、若い方にも受け入れやすいんじゃないでしょうか。」と店長の森健一さんは言う。店内のメイン席は現代的な食堂風(図18)、ロフト席はゆったりと落ち着いたラウンジ風(図19)とまったく異なる雰囲気の二つのスペースを設けたことで空間を選ぶ楽しさも提供している。
渋谷の喧騒から少しはずれたマンションの2階に2001年3月にオープンした「AINA」(アイナ)は南国の伝統文化を伝えるスピリチュアルなアロハファクトリーの一部というコンセプトである。カフェで南国の伝統文化を伝えようとするだけでなく、お店の奥の可動ドアの向こうには約40坪のフラスタジオがあり、定期的にフラダンスの講習が行われている。広々としたフロアには南国風の家具や植栽がゆったりと置かれ(図20)、やわらかな照明が、大人向けの落ち着いた空間をつくっている。メニューも野菜をたっぷりと使った手作りのオリジナル料理やフルーツたっぷりのデザートは、沖縄やハワイ、インドネシアなど、どこか南の島を感じるものが多い。しかし、その感じ方はけっしておしつけがましいものではなく、伝えたいことをあくまでも自然体で、伝えようとする店側の姿勢が、心地よい空間をつくっているようだ。


これらの他にも「本」をコンセプトにつくりだしたブックカフェ「café&books」「Dexee Diner」(デキシーダイナー) や、「リビング系」「部屋カフェ」と呼ばれる「Nid CAFÉ」(ニドカフェ)「eau café」(オウカフェ)など、さまざまなコンセプトのカフェが誕生している。これからのカフェはより細分化し、より独特で個性的なものが増えていくのかもしれない。そして、これらのカフェが提供してくれる居心地のよい空間を人々は選び、受け入れていく。人々が求めるカフェの形は時代にそって変化していくだろうが、「居心地のいいカフェ」というキーワードはこれからも残っていくのではないだろうかと思う。「Café Doji」(カフェドジ)のオーナーの宮野堂治郎さんは「カフェなんてある意味、時代にも社会にも逆らっている商売だ」と言う。「居心地のいいカフェ」が自然と誕生し、自然と受け入れられてきた背景には人々が感じる社会の居心地の悪さ、時代のめまぐるしさが関係しているのかもしれない。むかしからカフェの魅力を感じていたカフェ好きの人々、あるいはオーナーはカフェブームに対して、よく思わない人も多い。しかし、宮野さんは「この時代がくるまで本当にイライラしていた。“いつまでたっても認められない”、と。」と言う。確かに約20年前には、喫茶店は水商売の一種と思われていた時期もあったりした。その喫茶店やカフェの魅力や、大切な役割、必要性に気づいた人が多くなったのは本当に最近のことである。ブームと言われるのは、急激にカフェの魅力が広まり、認められたからなのかもしれないとも思う。
これからの行く先が楽しみなのはカフェばかりではない。同時にカフェに行く人々にも言えることではないかと思う。宮野さんは「Café Doji」にオープンカフェ的なスペースをつくったこともあるそうだ。しかし、「時間が経つと、その形態は日本の社会性に馴染まないっていうのが分かってきた。埃とか気候とかの問題があるし、何より表から通行人に見られて日本人がそれを楽しむっていうのは難しいと思う。」という理由でなくしてしまったらしい。しかし、それも変わるかもしれない、あるいは、もう変わりつつあるのではないかと思う。実際に、オープンテラスが馴染んでいるカフェも存在している。ただ、宮野さんが言うように「日本人はフランクにしていいと言うと、自由になりすぎる」というのは当たっているのではないだろうか。カフェはくつろぐ場所ではあるけれど、パブリックな場所であり、見られている場所である。カフェのマナーという面では日本人はまだ出来上がってないのかもしれない。時々、日本人が世代に関係なく持っている、“お金を出せば客=何でもありの絶対的存在”という観念は間違いだと思う。その場その場のルールを理解し、カフェで働く人に対しても少し気を使うことができる人が増えていけば、日本のカフェ文化はよりよいものなっていくのではないだろうか。宮野さんは「日本人のそういう意識は、いつか変わると信じているし、変わらざるを得ないとも思う。」と、言う。カフェが日本人の性質を変えることもあるかもしれないのだ。


ここ2〜3年続いているカフェブームも、ブームと呼ばれない日がやってくるだろう。その時、カフェはどのような形になっていくのだろうか。これまでにあげてきたカフェのなかに、もしかしたらなくなっているお店もあるかもしれない。しかし、カフェという空間はけっしてなくなってほしくないと私は思う。人と人が出会う場所、あるいは人と物が出会う場所、新たな感覚を生み出す場所、あるいは新たな文化を生み出す場所として、カフェは存在していってほしいと願うのである。カフェから生まれる文化はそんなに大きなものではないかもしれない。しかし、「人と人をつなぎ、会話が生まれ、そこから何かが生まれる」。それも、文化とは呼べないだろうか。日本にカフェ文化がはじまってから約90年たった今も、そしてこれから先もカフェの形は変化していったとしても、カフェの持つ、人々に提供される、さまざまな豊かさは変わらないでいて欲しいと願う。
2001年4月にカフェ激戦地、大阪・堀江のはずれにオープンした「Logic」(ロジック)は、ブライダルも行う大型カフェである。経営は心斎橋を中心に「グラム」「ナイン コンテンツ」など、6店のカフェ、レストランを展開する急成長企業であり、それまでは若年層をターゲットにした業態を展開していたが、「店に来ていただいているお客様に、ブライダルもできる場所を提供したかった」という思いで、ブライダルカフェというコンセプトがつくられたという。店内は「大人を対象にした店づくり」で、余計な装飾はいっさいなく、インテリアも黒や茶、グレイなどシックな色で統一しており、実際に30〜40代のお客が多い。建物は4階建てで、1,2階はカフェレストランとして、3階は同社のオフィスと、セントラルキッチンが配置され、4階は披露宴やイベントなどをおこなうパーティスペースとし、屋上には挙式もできるガラス張りの空間をつくっている。
2001年9月にオープンした「MERCURY」(マーキュリー)は「しっかりと食べられる食事、おいしいデザート、ドリンクを出す店にニーズを感じ、客層も幅広くしたかったので、メニューの6〜7割は和食を中心にした定食に決めました」とオーナーの吉田大門さんが言うように、イワシや銀ムツに、福島産のコシヒカリのごはん、野菜の小鉢、味噌汁、漬物というような、まさに「定食」を提供するカフェである。店内にはレトロな日本製の家具をゆったりと配置し、落ち着ける雰囲気である。
ロサンゼルス在住のファッションデザイナーが展開する「空(KU)」ブランドの「café KU(カフェ・クウ)」は、おしゃれなブティックやレストランが点在する若者の街、代官山に2001年8月にオープンした。独特の箱型フォルムの建物の1階に同ブランドのブティックがあり、カフェは2階に位置している。空ブランドはアメリカ人デザイナーがイメージした“和”の世界を表現しているが、それは日本にとどまらず、中国やインドなどアジア各国のエッセンスが融合した不思議な雰囲気が漂ったものである。そのイメージに合わせて、カフェのメニューには、和食やエスニックをアレンジした個性あふれる料理や豊富なバラエティの日本茶メニューが並ぶ。「代官山にはカフェはたくさんありますが、日本茶や和食を気軽に味わえる場所は少ないんです。ここは外国の方がイメージした“和”がコンセプトですから、若い方にも受け入れやすいんじゃないでしょうか。」と店長の森健一さんは言う。店内のメイン席は現代的な食堂風(図18)、ロフト席はゆったりと落ち着いたラウンジ風(図19)とまったく異なる雰囲気の二つのスペースを設けたことで空間を選ぶ楽しさも提供している。
渋谷の喧騒から少しはずれたマンションの2階に2001年3月にオープンした「AINA」(アイナ)は南国の伝統文化を伝えるスピリチュアルなアロハファクトリーの一部というコンセプトである。カフェで南国の伝統文化を伝えようとするだけでなく、お店の奥の可動ドアの向こうには約40坪のフラスタジオがあり、定期的にフラダンスの講習が行われている。広々としたフロアには南国風の家具や植栽がゆったりと置かれ(図20)、やわらかな照明が、大人向けの落ち着いた空間をつくっている。メニューも野菜をたっぷりと使った手作りのオリジナル料理やフルーツたっぷりのデザートは、沖縄やハワイ、インドネシアなど、どこか南の島を感じるものが多い。しかし、その感じ方はけっしておしつけがましいものではなく、伝えたいことをあくまでも自然体で、伝えようとする店側の姿勢が、心地よい空間をつくっているようだ。
これらの他にも「本」をコンセプトにつくりだしたブックカフェ「café&books」「Dexee Diner」(デキシーダイナー) や、「リビング系」「部屋カフェ」と呼ばれる「Nid CAFÉ」(ニドカフェ)「eau café」(オウカフェ)など、さまざまなコンセプトのカフェが誕生している。これからのカフェはより細分化し、より独特で個性的なものが増えていくのかもしれない。そして、これらのカフェが提供してくれる居心地のよい空間を人々は選び、受け入れていく。人々が求めるカフェの形は時代にそって変化していくだろうが、「居心地のいいカフェ」というキーワードはこれからも残っていくのではないだろうかと思う。「Café Doji」(カフェドジ)のオーナーの宮野堂治郎さんは「カフェなんてある意味、時代にも社会にも逆らっている商売だ」と言う。「居心地のいいカフェ」が自然と誕生し、自然と受け入れられてきた背景には人々が感じる社会の居心地の悪さ、時代のめまぐるしさが関係しているのかもしれない。むかしからカフェの魅力を感じていたカフェ好きの人々、あるいはオーナーはカフェブームに対して、よく思わない人も多い。しかし、宮野さんは「この時代がくるまで本当にイライラしていた。“いつまでたっても認められない”、と。」と言う。確かに約20年前には、喫茶店は水商売の一種と思われていた時期もあったりした。その喫茶店やカフェの魅力や、大切な役割、必要性に気づいた人が多くなったのは本当に最近のことである。ブームと言われるのは、急激にカフェの魅力が広まり、認められたからなのかもしれないとも思う。
これからの行く先が楽しみなのはカフェばかりではない。同時にカフェに行く人々にも言えることではないかと思う。宮野さんは「Café Doji」にオープンカフェ的なスペースをつくったこともあるそうだ。しかし、「時間が経つと、その形態は日本の社会性に馴染まないっていうのが分かってきた。埃とか気候とかの問題があるし、何より表から通行人に見られて日本人がそれを楽しむっていうのは難しいと思う。」という理由でなくしてしまったらしい。しかし、それも変わるかもしれない、あるいは、もう変わりつつあるのではないかと思う。実際に、オープンテラスが馴染んでいるカフェも存在している。ただ、宮野さんが言うように「日本人はフランクにしていいと言うと、自由になりすぎる」というのは当たっているのではないだろうか。カフェはくつろぐ場所ではあるけれど、パブリックな場所であり、見られている場所である。カフェのマナーという面では日本人はまだ出来上がってないのかもしれない。時々、日本人が世代に関係なく持っている、“お金を出せば客=何でもありの絶対的存在”という観念は間違いだと思う。その場その場のルールを理解し、カフェで働く人に対しても少し気を使うことができる人が増えていけば、日本のカフェ文化はよりよいものなっていくのではないだろうか。宮野さんは「日本人のそういう意識は、いつか変わると信じているし、変わらざるを得ないとも思う。」と、言う。カフェが日本人の性質を変えることもあるかもしれないのだ。
ここ2〜3年続いているカフェブームも、ブームと呼ばれない日がやってくるだろう。その時、カフェはどのような形になっていくのだろうか。これまでにあげてきたカフェのなかに、もしかしたらなくなっているお店もあるかもしれない。しかし、カフェという空間はけっしてなくなってほしくないと私は思う。人と人が出会う場所、あるいは人と物が出会う場所、新たな感覚を生み出す場所、あるいは新たな文化を生み出す場所として、カフェは存在していってほしいと願うのである。カフェから生まれる文化はそんなに大きなものではないかもしれない。しかし、「人と人をつなぎ、会話が生まれ、そこから何かが生まれる」。それも、文化とは呼べないだろうか。日本にカフェ文化がはじまってから約90年たった今も、そしてこれから先もカフェの形は変化していったとしても、カフェの持つ、人々に提供される、さまざまな豊かさは変わらないでいて欲しいと願う。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image