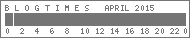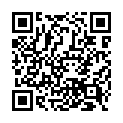2012�N08��10��
�q��^���Ɩf�ՃV�X�e��
1�A�q��^��
�@�q��@�́A�{���A�������A���S���A�K�����ɗD�ꂽ�A����i�ł��������A�ő�̌��_�́A�A���ʂ����A�������^���������Ƃ������Ƃł������B��^�ݕ��A���@�̓o��ɂ��A�q��ݕ��A���̌��_�͑傫���ɘa����邱�ƂɂȂ����B��Ƃ́A���t�����l���i�̕����q��@�ɂ���čs���悤�ɂȂ����B�D������r�I�����ȍq��^�����A�q��@�̍������A���S���A�K�����ɂ���č팸�ł��镨����p�ő��E�����悤�ɂȂ����̂ł���B���̂悤�Ȍ����ōq��A���̔��W�������炵���B
�@1945�N4���A�q���Ƃ̎�]�̓n�o�i�ɏW�܂�A���ۍq��^������܂�IATA�𐬗������BIATA�̋@�\�͂Q�ɏW���B�����@�\�Ɛ��Z�@�\�ł���BIATA�́A�ݗ���������A1919�N�ɐݗ��������E�풆�Ɏ��R���ł�����IATA�ɂȂ炢�A�㗝�X���x���[�������Ă������BIATA�㗝�X���x�Ƃ́AIATA�����F�����㗝�X���A����_��ł���IATA�㗝�X�_���������邱�Ƃɂ���āAIATA�����̊e�q���ЂƁA�ψ�̏����Ǝ萔���ő㗝�X�W�ɓ��邱�Ƃ��\�ɂ��鐧�x�ł���B1963�N��IATA�͉�p�R���e�i�Ƃ������x��݂����B���̐��x�́A�傪���炩���ߓo�^���Ă������R���e�i�𗘗p���čs���^���ɑ��ĉ^���������Ƃ������̂ł������B�������A�o�^���ꂽ�R���e�i�����푽�l�Ō����������������߁A1967�N��17��ނ̕W���R���e�i���w�肷�邱�ƂƂ����B���̐��x���q���A���ւ̃R���e�i�[�����𑣐i���邱�ƂɂȂ�B
�@�q���Ђ́A�{���A�ݕ��̏W�ׂ��K�������ȂǕ����\�͂Ɍ��肪���������A���̉ݕ��X���̃Z�[���X�\�̖͂R���������B�v�����Ƃ����q��A���̓������������ɂ́A�ݕ��A���̔̔��Ɖݕ��̏W�ׂ��A������t�H���[�_�[��ƂɈˑ�����K�v������A�q��ݕ��㗝�X���x�͂��̂��߂̗L���Ȏ�i�ł������B
�@����A���ډݕ����x�́A�L��������̍q��ݕ��^�����͏d�ʂ�������قǂ₷���Ȃ�Ƃ��������ƁA�q��ݕ��͂��Ƃ��Ə��ʉݕ������S�ł���Ƃ��������𗘗p���Đ����Ă������x�ł���B�܂�A���ʉݕ��̉�ɂƂ��ẮA�q���Ђɒ��ډ^�����˗�������A���ډݕ��Ƃ��ĉ^�����˗����������L���ȉ^�����𗘗p�ł��邵�A���ڋƍۂƂ��Ă����ڍ��v������ł���̂ł���B
�@���ڍ��v��ɂ́A�ł��邾����ʂ̉ݕ����W�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�A�W�ה\�͂ɍ��ڋƎ҂Ƃ��Ă̓K�ۂ��������Ă���̂ł���B�قƂ�ǂ̍q��ݕ��㗝�X�����ڋƎ҂��c�ނ悤�ɂȂ����͓̂��R�ł���B���t��ς���A�����ݕ��A���Z�[���X�\�͂ƕ����\�͂����q��ݕ��㗝�X�������A���ڋƎ҂Ƃ������Ƃ��ł���B�����āA�t�H���[�_�[�͑㗝�X�Ƃ����@�\�ɉ����āA���ڋƎ҂Ƃ����@�\�������ƂɂȂ�B�q��ݕ��㗝�X�⍬�ڋƎ҂ɂȂ�O�̃t�H�[���[�_�[�̑����́A���łɍ����^���ƎҁA�ʊƎҁA�ی��㗝�X�A�q�ɋƎ҂Ȃǂ̋@�\�������Ă����B
�@�q�ݕ��͒����ݕ��ƍ��ډݕ��ɕ�������B�����ݕ��͉ב��l�����ڍq���Ђ։^�����˗�������@�ł���A�ב��l�ƍq��ݕ��㗝�X���^���_����������B���ډݕ��́A�ב��l����^���˗����A�����̉^���Ō_�������������ڋƎ҂��A���x�͉ב��l�Ƃ��čq��ݕ��㗝�X�Ɖ^���_�������B
�@�����ݕ��̗��ʉߒ��͈ȉ��̐}�P�|�P�̒ʂ�ł���B
�@�ב��l����^���˗������q��ݕ��㗝�X�́A�ʏ펩�炠�邢�͑��̉^���Ǝ҂Ɉ˗����č����^�����s���B�ݕ����G�A�J�[�S�E�^�[�~�i�����o�R����ꍇ�ɂ́A�ʊ֎葱���̍ςݕ����ꊇ�^�����s���B
�G�A�J�[�S�E�^�[�~�i�����o�R����ݕ��������āA�q��ݕ��㗝�X���邢�͂��̉������^�����s���^���l�̎�ɂ���`�ɂ������܂ꂽ�ݕ��́A�q��ݕ��㗝�X�ɂ��A����A�o���N�E���j�^�C�[�[�V�����A�ʊւȂǍ��ۉ^�����ł����Ԃɂ���B�ݕ��ɂ���ẮA��`�����O�ɁA�e�㉮�Œʊւ����`�܂ŕېʼn^�����s�����Ƃ�����B�����āA�q��ݕ��㗝�X���^������쐬����B
�A���n�ɓ��������ݕ��́A�q���Ђ����l�Ɉ����n�����B��l�͒ʊƎ҂����˂�Ǝ҂�㗝�X�Ƃ��Ďw�肵�Ă���B���̑㗝�X�͍q��ݕ��㗝�X�ł��邱�Ƃ������B�A���ʊւ₻�̑��̕K�v�ȑ������I�����ݕ��́A���̑㗝�X�ɂ���Ă��邢�͂��̉������Ǝ҂̎�ɂ���āA�ב��l�₠�邢�͉�l�̎w�肷��q�ɂɔz�B�����B
�ב��l����̉^���˗��ɂ��A���ڋƎ҂͏W�ׁE�����^�����s�����Ƃ������B�ݕ��G�A�J�[�S�E�^�[�~�i���⍬�ڋƎҏ��L�̏㉮�ɔ�������A���ڎd���Ă�A�o�ʊւɕK�v�Ȏ葱�����s����B
�@�ב��l�ɑ��ĉ^���𐿂����������ڋƎ҂́A���x�͎������ב��l�ƂȂ��āA�q���Ђ̑㗝�X�ɉ^�����˗�����B�q��ݕ��㗝�X�͍q��^������쐬���A�ݕ����q���Џ��L�̏㉮�ɔ�������B�������ꂽ�ݕ��́A�q���Ў��炠�邢�͒n��戵���X�ɂ��q��@�ɐςݍ��܂��B
�@�d����`�ɓ��������ݕ��́A���ڋƎ҂ɂ���l�Ɏw�肳�ꂽ���ڎd���㗝�X���A���ڎd�������āA�K�v�ɉ����ʊւ�z�B���s���B���ڋƎ҂��A���n�ɉc�Ə��⌻�n�@�l�������Ă���A����炪�s���B
�@���ڋƎ҂͂قƂ��IATA�q��ݕ��㗝�X�����˂Ă���̂ŁA���ۂ́A�A�o�n�ł̏W�ׂ���q���Ђւ̈��n�����A1�Ђ����ꂼ��̎��i�ōs���Ă���B���̂��Ƃ��q��ݕ����ʂ̓����ł���B
2�A�f�ՃV�X�e��
�@�f�ՃV�X�e���Ƃ́A���鍑���炽�̍��ւ̕��i�Ƃ���ɑ���Ή��̍����I�ړ����\�ɂ��邽�߂̏W���̂ł���B�f�Վ�����l�o�ς܂莄��Ƃ���f�Չ�Ђ���݂�ƁB���i�̈��n���Ƒ���̎x�����Ƃ�����̍��𗚍s���邱�ƂɏW���B�����ł̒�`�́A���̂悤�ȍ��̗��s�������I�ɍs�����߂̃V�X�e���Ƃ������Ƃł���B
�@�u�}�P�|�R�S�̖f�ՃV�X�e���̍\�����f���v���݂Ȃ���A�S�̖f�ՃV�X�e���ɂ��Đ�������B�f�Վ���ɊԂ�鐭�{�A��s�A�ی���ЁA�t�H���[�_�[�A�^����Ђ̏W���̂��A�A�o�҂̏W���ƗA���҂̏W���𒆐S�Ƃ��Ĕz�Ă���B�����ł́A�A�o�҂��A�o�҂��A����ɂ͂��̑��̎���W�҂��A���ꂼ��S�̂̏W���̂Ƃ��Ĉ����Ă���̂ŁA�u�S�̖f�ՃV�X�e���v�ɂȂ�B���̖f�ՃV�X�e���͗A�o�҂̕��i���n���ƗA���҂̑Ή��̎x�������\�ɂ�����̂ł��邩��A�A�o�v�f�ƗA���v�f��f�ՃV�X�e���ɂ������̗v�f�ɂȂ�B
�f�ՃV�X�e���̊e�v�f�Ԃɂ́A���Ŏ��������݊W������B�����ɂ������݊W�Ƃ́A���x�����邢�͊��K�����ꂽ���ɂ�铭�������̂��Ƃł���B�f�ՃV�X�e���Ƃ����ϓ_���猩��A�f�Ղ̊e�v�f�̓T�u�V�X�e���Ƃ�Ԃ��Ƃ��ł���B
�@�f�ՃV�X�e���̊e�v�f�܂�T�u�V�X�e���ɂ́A�����A�f�ՊǗ��A�f�Ռ��ρA�ݕ��ی��A�_��̃T�u�V�X�e������Ȃ�B�e�T�u�V�X�e���́A�q��^���̔��W�ɉ����āA���̍\����ω������Ă����B
�@�����T�u�V�X�e���̂Ȃ��ŁA�܂������I�Ȃ̂́A�ݕ��̍q��@�ւ̐ςݍ��`�Ԃł���B
�q��^���ł́A�ב��l���ςݍ��݂��s�����Ƃł͂Ȃ��A�^���l���邢�͂��̑㗝�l���A�ςݍ��݂ɐ旧���āA�ב���l����ݕ����������B���̂悤�Ȑςݍ��`�Ԃ́A�R���e�i�A���ł́A�������炱�̂悤�Ȉ������`�Ԃ��̗p����Ă����B���̗��R�́A�q��A���ł͂��̐v�����䂦�ɁA�����悭�ςݍ��ޕK�v�����邱�ƁA�ݕ���p�@�o��̈ȑO�͗��q�@�̉����ݕ����𗘗p���ĉݕ���A�����Ă��āA���̂悤�ȗA���`�Ԃł͉^���l���ݕ���ςݍ���ł����B
�@�q��ݕ��A���̔��W�ɂƂ��Ȃ��A�ȉ��̉e���ł���
�@�f�ՊǗ��V�X�e���܂�ʊ��x���������́A�葱���̊ȑf����ȗ����ł������B
�A�f�Ռ��σT�u�V�X�e���ɉe����^�����B
�B�q��^�����M�p��K���ň������ނƂ������Ƃł������B
�C�ݕ��ی��ɑ��āA�V�ی����x�̊J���͕K�v�ɂȂ�B
�@�T�u�V�X�e���\���ω��̗v���Ƃ��̘A���́A�t�H���[�_�[�̑��l�i���ƍq��^���x�̐����ł���B����̃t�H���[�_�[�����ł́A���ꂼ��̒S���ҕ������قȂ�������ŋƖ����������Ă���̂ł��邪�A�O���̎҂ɂƂ��ẮA�����̐l�i���Ƃ��ɉ����Č���Ă͏����鑽�d�l�i�҂�����v���ł���B�t�H���[�_�[�̂����̂悤�ȕ��G�ȋ@�\�𑼐l�i���Ƃ�Ԃ��Ƃɂ���B���l�e�ۂƂ������t�ŕ\�����t�H���[�_�[�̑��@�\�����A�q��ݕ������\���̒��S�I�ȓ����ł���B
�@�q��^���̓����̈�́A�v���ȉ^����i�Ƃ������Ƃł���B���̂悤�ȓ�������A�q��A����͔ʐ��ł���B�ʐ��^�����ނ̔��s�Ƃ����q��A���̓����́A����ɁA�q��^����̉�l�����A�A���҂Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�M�p�s��s�ȂǗA���n��s�Ƃ���Ƃ����葱�����������B�^�����ނ��L���،��ł���ꍇ�ɂ́A���̏،������L���邱�Ƃɂ���ĉݕ��̏��L�����咣�ł���̂����A�ʐ��̉^�����ނł́A��l�������ݕ���������錠���������ƂɂȂ�B���̂��ߐM�p�������邢�͔����_���A��s����l�Ƃ��邱�ƂŁA�ݕ��ɑ���S�ی����m�ۂ��悤�Ƃ���̂ł���B
�@���̂ق��A���ڐ��x���f�Ռ��σT�u�V�X�e���։e����^���邱�ƂɂȂ�B�q��A���̐v�����A���^���A�������t�����l�i�Ƃ����������A���ډݕ����x���q��^���ɓ��������A��ʗA���̎n�܂肪�A���ڐ��x�������������W�������B
�@�f�ՃV�X�e���̒��̂���T�u�V�X�e�����\���\���ω����N�����Ă����B���̂Ƃ��ɁA���̃T�u�V�X�e�����A����ɓK�����č\���ω����N�����Ă����B���邢�́A���Ƃ��āA���̍\���ω��͂ǂ̂悤�ȓ��@�ɂ���čs����̂ł���B�\���ω��̓��@�́A�e�T�u�V�X�e���̒��ɑ��݂���e�v�f�ɂ��Ƃ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�A���Ղɂ����A���Ƃł���A���邢�͈�g�D�ł���B��Ƃɂ���āA����T�u�V�X�e�����\���ω����N�������ꍇ�́A���Ђ̑�����ɉh�̂��߂̌o�c���f�Ƃ��āA�\���ω��Ƃ����ӎ�������s���B
�@����T�u�V�X�e���̒��̂���T�u�V�X�e���̍\���ω��ɑ��āA�ʂ̃T�u�V�X�e���́A�\���ω������邱�ƂœK��������@�͎O�ł���B��́A����\���ω����邱�Ƃł���B�\���ω��́A�܂��A�]�����������x��@�\���A�V�����\���ɓK�����ׂ��ω������邱�Ƃɂ���ĂȂ����B�\���ω��ɂ��K����2�Ԗڂ̕��@�́A���x��@�\��V���ɒNj�������@�ł���B����́A�ގ��̕��@��x���C������̂ƈ���āA�C���̑ΏۂƂȂ���@��x���]�����݂����A�܂������V�������x��@�\��n�݂�����@�ł���B�\���ω��ɂ��K���̍Ō�̕��@�́A���x��@�\�����ł����邱�Ƃł���B����T�u�V�X�e���̍\���ω��ɑΉ����邽�߂ɁA�s�K�v�ƂȂ������x��@�\�����ł����邱�ƂŁA�V���x�ɓK�����悤�Ƃ���B
�y���̃J�e�S���[�̍ŐV�L���z
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image