2013年12月11日
「山霧-毛利元就の妻」 永井路子
戦国ものの時代小説において女性が男性と同等に活躍するものは少ない。活躍するとしても色香で城を傾けるものや、せいぜい「真田太平記」に出てくるくノ一のようなものぐらいだ。本書はその点においては「功名が辻」と並び、珍しく女が男と同等に知恵を振るい、戦国の世を生き抜く話である。
大河ドラマ「毛利元就」の原作となった本作は、22歳の弱小国人領主、少輔次郎の元に近隣の強豪・鬼吉川の娘、美伊が嫁ぐ所から始まる。元就・美伊二人の視点・心情が代わる代わる展開していく。
この作品で興味深いのが元就と美伊の関係は単純な夫妻ではないことだ。元就も美伊も互いを深く愛し合っており、そのことは物語終盤まで変わらない。ただ、各々の配下のスパイに話がいく時だけさっと夫婦の関係ではなくなるのだ。さながら冷戦下のスパイマスター同士がカフェで対峙するようなものか。毛利元就が弱小領主の身から奸詐謀略をもって中国の太守となったことはよく知られている。その妻である美伊の背景は絶妙なものだ。親が近隣の強豪・鬼吉川「国経」で、叔父には尼子経久がいたりと元就も気が抜けない。現に美伊の付添いの侍女はたびたび美伊に向かい情報戦のアドバイスをしてくる。最終的には、美伊は元就の城下から完全に実家からのスパイを去らせるに至るのだが、この作品は戦国時代の夫婦関係・諜報戦・弱小土豪のありさまを実によく描けている。
「たしかに戦国の花嫁は、ただの着飾った人形ではない。ある意味では複雑な性格の二重スパイでもある。婚家先は彼女を相手方との親善の窓口としながらも、一方では情報収集に利用しようとする。また花嫁も、頬には笑みを湛えながら、ぬかりなく実家に婚家の動きを伝えたりもする。」
「戦国の女たちはしたたかなのだ。後世『政略結婚』と名づけられたこうした嫁ぎ方を、女の権利を無視した人身御供的なありかたと思うのは、およそ見当違いである。」
と作者は書く。元就と美伊の「毛利家」が隣接する大内・尼子という大勢力の間で知略の限りを尽くして生き抜くさまがありありと浮かぶ本作。この他にも連歌師による情報活動などにも触れられており面白い。毛利元就は知名度の割には小説が少なく、この小説が出る以前の有名どころだと山岡荘八の「毛利元就」があるがこれは元就配下のスパイを中心とした記述が多く、元就自身の心情描写が少ないのが淋しい。毛利元就を扱った小説で代表作を挙げるならば間違いなく本作を推す。「政略結婚」や「国人領主」、「戦国の女」といったトピックでも同様だ。
小説冒頭にはこうある。
「これは乱世の梟雄、毛利元就の物語ではない。中国山脈の山裾の霧の中を這いずりまわりつつ、十六世紀を生きた若い男と女の話である。」
毛利元就 戦国の女
戦国の女
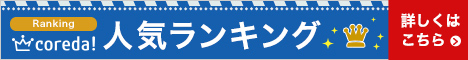

大河ドラマ「毛利元就」の原作となった本作は、22歳の弱小国人領主、少輔次郎の元に近隣の強豪・鬼吉川の娘、美伊が嫁ぐ所から始まる。元就・美伊二人の視点・心情が代わる代わる展開していく。
この作品で興味深いのが元就と美伊の関係は単純な夫妻ではないことだ。元就も美伊も互いを深く愛し合っており、そのことは物語終盤まで変わらない。ただ、各々の配下のスパイに話がいく時だけさっと夫婦の関係ではなくなるのだ。さながら冷戦下のスパイマスター同士がカフェで対峙するようなものか。毛利元就が弱小領主の身から奸詐謀略をもって中国の太守となったことはよく知られている。その妻である美伊の背景は絶妙なものだ。親が近隣の強豪・鬼吉川「国経」で、叔父には尼子経久がいたりと元就も気が抜けない。現に美伊の付添いの侍女はたびたび美伊に向かい情報戦のアドバイスをしてくる。最終的には、美伊は元就の城下から完全に実家からのスパイを去らせるに至るのだが、この作品は戦国時代の夫婦関係・諜報戦・弱小土豪のありさまを実によく描けている。
「たしかに戦国の花嫁は、ただの着飾った人形ではない。ある意味では複雑な性格の二重スパイでもある。婚家先は彼女を相手方との親善の窓口としながらも、一方では情報収集に利用しようとする。また花嫁も、頬には笑みを湛えながら、ぬかりなく実家に婚家の動きを伝えたりもする。」
「戦国の女たちはしたたかなのだ。後世『政略結婚』と名づけられたこうした嫁ぎ方を、女の権利を無視した人身御供的なありかたと思うのは、およそ見当違いである。」
と作者は書く。元就と美伊の「毛利家」が隣接する大内・尼子という大勢力の間で知略の限りを尽くして生き抜くさまがありありと浮かぶ本作。この他にも連歌師による情報活動などにも触れられており面白い。毛利元就は知名度の割には小説が少なく、この小説が出る以前の有名どころだと山岡荘八の「毛利元就」があるがこれは元就配下のスパイを中心とした記述が多く、元就自身の心情描写が少ないのが淋しい。毛利元就を扱った小説で代表作を挙げるならば間違いなく本作を推す。「政略結婚」や「国人領主」、「戦国の女」といったトピックでも同様だ。
小説冒頭にはこうある。
「これは乱世の梟雄、毛利元就の物語ではない。中国山脈の山裾の霧の中を這いずりまわりつつ、十六世紀を生きた若い男と女の話である。」
毛利元就










