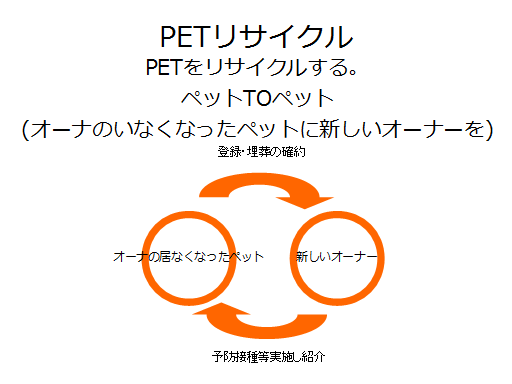何しろ、ロシアとの技術競争の時代ではないというのだ。
そして、月に拠点を作るのが目的。
拠点とは?
月に住まないにしても、資源や宇宙での開発、さらには、防衛の観点からの拠点だろう。
中国も既にそうした動きがあることもあり、敵はロシアだけではなくなった。
むしろ領土問題。月を後回しにして火星だけ目指している間に中国に月を支配されてしまう懸念が現実のものとなったということだろう。
なお、記事にもあるように、
地球の磁場の影響下から遠く離れた月周辺で、どれだけの宇宙放射線を浴びるのかを測定し、有人飛行での健康リスクを調べます
ということで、これまで宇宙放射量をどれだけ浴び、健康リスクがどれだけあるかということさえ、新たに調べなければならないということ。
宇宙飛行士は今でも命懸け、また、自ら人体実験の対象としての役割を担っているということなのだ。
Yahoo!より、
アポロ計画から50年…月面着陸の先へ“探査拠点”の作成も視野『アルテミス計画』
8/29(月) 23:30配信
テレビ朝日系(ANN)
https://news.yahoo.co.jp/articles/7d146e8844d763c000c9a9d43598c51d9f78c8c6
記事より、
アポロ計画以来の月面着陸を目指す『アルテミス計画』の第1弾、新型ロケットの打ち上げが日本時間29日午後9時半過ぎに予定されていましたが、エンジントラブルなどにより、延期となりました。
アルテミス計画のフェーズ1の目的は、4〜6週間かけて、月をぐるりと周ってから地球に帰還すること。成功すれば、再来年のフェーズ2で同じルートの有人飛行へ。そして最終フェーズで、50年ぶりとなる月面到達を目指すことになります。
見据える先にあるものは、50年前とは違います。月面へのタッチダウンが目的だったアポロ計画に対し、アルテミス計画のゴールは、探査のための拠点を月面に作ること。周回軌道上には中継基地も作る予定です。いわば“月の上空”に浮かぶ宇宙ステーションです。地下に氷が眠ると言われている南極近くには、着陸地点の候補も選定されています。
月に常駐という、遠大な計画。その大事な一歩となる今回、いくつも重要なミッションがあります。例えば、宇宙船に“搭乗”するマネキンは、地球の磁場の影響下から遠く離れた月周辺で、どれだけの宇宙放射線を浴びるのかを測定し、有人飛行での健康リスクを調べます。
春山純一助教:「月は地球に比べ、放射線などの影響も大きいが、普通の人でも滞在し、健康でいられるための課題を発見・解決し、さらにその先、火星に行くための技術を月で開発する」
月面探査には、中国がかなり力を入れています。2013年に『嫦娥3号』が月面着陸。2019年には『嫦娥4号』が世界初、月の裏側に軟着陸成功。2020年『嫦娥5号』が中国初のサンプルリターンに成功しています。
中国は、月の地下の空洞を利用して、放射線の影響を受けずに暮らす基地をつくる構想を持って進めているということです。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image