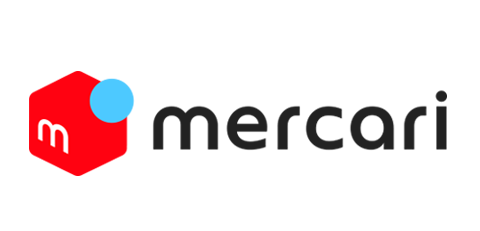新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2024年12月22日
引っ越し
2024年12月14日
日本昔話 旅人馬
昔々、ある村外れに心優しい夫婦が住んでおりました。夫婦は貧しかったものの、互いを思いやる心を持ち、慎ましく幸せに暮らしていました。しかし、夫婦の心配事は一つ。それは、年老いた馬のタロウでした。
タロウは若いころから夫婦の家で働き者として村中に知られていました。重い荷物を運び、田畑を耕し、どんな仕事も嫌がることなくこなしてきた馬です。しかし、今やタロウもすっかり歳をとり、脚は細く、背中も痩せてしまっています。夫はある夜、妻にぽつりと話しました。
「もうタロウを養う余裕がない。こんなことを言うのは心が痛むが、森に放してやるしかないのかもしれない。」
妻は涙を浮かべてうなずきました。「でも、せめて安全な場所まで送ってやりましょう。」
翌朝、夫はタロウを連れて森へ向かいました。途中、優しい声でタロウに語りかけます。
「タロウ、お前は本当に良く働いてくれた。申し訳ないが、これからは自由に生きておくれ。」
タロウは夫の言葉をじっと聞き、まるで人間のように目を細めると、静かにうなずいたように見えました。
森の出来事
夫がタロウを森に置いて帰ろうとすると、突然どこからともなく若い旅人が現れました。その旅人は立派な衣をまとい、優しい顔立ちをしていました。
「その馬、譲っていただけませんか?」と旅人は尋ねました。
夫は驚きました。「この馬は年老いてもう役に立ちませんよ。」
しかし旅人は微笑んで、「この馬には何か特別な力を感じます。大切にしますので、ぜひ譲ってください。」
夫は少し戸惑いながらも、旅人の誠実そうな態度に心を動かされ、タロウを引き渡しました。旅人はタロウのたてがみを優しくなでると、「ありがとう」と言い残して森の奥へと消えていきました。
不思議な噂
それからしばらくして、村には奇妙な噂が流れ始めました。遠い町から旅人が訪れ、その馬に乗っている姿が話題になったのです。その馬は年老いているにもかかわらず、まるで風のように速く走り、どんな険しい道も難なく越えるのだとか。
「それってタロウじゃないか?」夫婦は互いに顔を見合わせました。
数日後、旅人が再び村にやってきました。夫婦は驚きましたが、旅人は笑顔で言いました。
「この馬のおかげで多くの困難を乗り越えられました。この恩をお返ししたいと思い、やってきました。」
旅人は夫婦にたくさんの金貨と食料を差し出しました。「どうか、これで幸せに暮らしてください。」
夫婦は感激し、涙ながらに旅人に感謝しました。タロウは旅人のそばで穏やかに目を閉じ、まるで「これで良かっただろう」と言っているかのように見えました。
終わりに
その後、夫婦は村で誰よりも幸せに暮らしました。タロウも旅人とともに新しい人生を送り、年老いた体ながらも、その力を惜しみなく発揮しました。
そして村では、「年老いても誠実な心を忘れないものには、不思議な幸運が訪れる」という話が語り継がれるようになりました。
ギャグ編
旅人馬 〜笑って泣けるタロウの物語〜
昔々、とある村に夫婦と一匹の馬が暮らしていました。夫婦は貧しくも仲良く暮らしていましたが、一つだけ頭を悩ませる問題がありました。それは年老いた馬のタロウ。年を重ねるごとにタロウはどんどん頑固になり、最近では畑仕事をしながら演歌を口ずさむ始末。しかも音痴。
ある日、夫は深刻な顔で妻に話しかけました。
「おい、タロウも限界だ。最近なんて、クワを持たせたら『腰が痛い』ってため息つくだけだぞ。」
妻も大きくうなずきました。「この前なんて、私が『荷物運んで』って頼んだら、わざと転んでサボったのよ。しかも転び方が舞台俳優みたいだったわ。」
二人は相談の末、タロウを森に放してやることにしました。
森での出会い
翌朝、夫はタロウを連れて森へ向かいました。途中、タロウは何度も立ち止まってこちらを振り返り、「本当に捨てるのか?」と言わんばかりの目でじっと夫を見つめてきます。
「お前、そんな目で見てもだめだ。俺だってつらいんだぞ!」
夫は泣きそうな顔をして前を向きました。
やっとのことでタロウを森の奥まで連れて行き、別れの言葉を伝えました。
「タロウ、自由に生きてくれ。きっと森の中では新しい仲間が見つかるさ。野生の馬とか、森の妖精とか…うん、きっと楽しいぞ!」
タロウは首をかしげ、まるで「そんな話、信じると思ってるのか?」と言いたげです。夫が帰ろうとすると、突然、木陰から派手な服を着た旅人が現れました。まるで街中の大道芸人のような格好です。
「ちょっと待った!その馬、譲ってくれませんか?」
旅人は笑顔で近づいてきました。
夫は驚きました。「いや、この馬は年を取りすぎてもう役に立たないんですよ。最近じゃ、カラスに『お前の方が遅い』って笑われる始末です。」
旅人はにっこり笑って、「いやいや、この馬、ただものじゃないオーラを感じます!大丈夫、僕が鍛え直します!」と自信満々。
タロウ、大出世
数週間後、村に奇妙な噂が流れ始めました。
「おい、聞いたか?近くの町で年老いた馬が大活躍してるらしいぞ。しかも旅人を背中に乗せながら、坂道を全力疾走だと!」
「それ、うちのタロウじゃないか?最近森に放したんだけど…。」
夫婦は耳を疑いましたが、その噂は日増しに広がり、とうとう旅人とタロウが村に戻ってきました。旅人は笑顔で言いました。
「見てください、この馬の筋肉!毎朝ジョギングさせて、プロテインも飲ませました。今や野生馬も追いつけない速さですよ!」
タロウも得意げに「ヒヒーン!」と嘶きます。ただ、嘶いた拍子に咳き込んで、旅人に水をねだっていました。
旅人は夫婦に金貨と食料を渡し、「この馬のおかげで大成功を収めました!感謝の気持ちです」と言いました。
夫は感激しましたが、タロウを見て一言。
「おい、俺が頼んでも走らなかったくせに、なんで今さら全力出してるんだ?」
タロウはふてぶてしい表情で「ヒヒン」と鳴き、まるで「俺のやる気スイッチは旅人専用だ」とでも言いたげでした。
終わりに
それからタロウは旅人とともに大活躍を続け、夫婦も金貨のおかげで裕福な生活を送りました。村ではタロウの伝説が語り継がれるようになり、いつしかこんな言葉が生まれました。
「やる気スイッチは誰にでもある。ただし、押す人を選ぶ。」
2024年12月12日
日本昔話 二十三夜さま
二十三夜様の奇跡
昔、ある山里に、おばあさんが一人で暮らしていました。おばあさんはとても貧しく、自分の家もボロボロ。けれども、いつも笑顔を絶やさず、毎晩欠かさずに二十三夜様にお参りをしていました。
「二十三夜様、どうかこの世のすべてをお守りくださいな。私の願いは少しでも村のみんなが幸せになることだけです。」
そんなおばあさんの謙虚な祈りが天に届いたのか、ある晩、不思議な夢を見ました。夢の中で二十三夜様が現れ、おばあさんにこう告げたのです。
「お前の信仰は深く、心は清らかである。明日、山のふもとの古い井戸を掘るがよい。そこにお前の未来がある。」
古井戸の秘密
翌朝、おばあさんは近所の若者たちに事情を話し、助けを頼みました。村の若者たちは快く協力し、古井戸を掘り始めました。井戸の底が見え始めた頃、なんと黄金の光る石がゴロゴロと出てきたのです!
「これが二十三夜様のお導き…!」おばあさんは目を輝かせました。
黄金を使ってもともと貧しい村は立派な道や学校、井戸を作り、村人全員が恩恵を受けました。しかし、おばあさんは自分の家には一切手をつけず、あいかわらず慎ましい暮らしを続けました。
「これでみんなが幸せになれれば、私はそれで十分じゃ。」
妬みの炎
しかし、村外れに住む欲深い男がこの話を聞きつけ、鼻息を荒くして古井戸に向かいました。男は井戸をさらに深く掘り、もっと多くの黄金を見つけようとしました。
「ハッ、俺様にはこんなに黄金がふさわしい!もっと掘って掘って掘りまくるぞ!」
ところが、井戸は突然ゴォォッと恐ろしい音を立て、水が勢いよく噴き出しました。男は吹き飛ばされ、ずぶ濡れになりながら逃げ帰りました。それ以来、黄金は二度と現れることなく、井戸は再び静かになりました。
村の繁栄
おばあさんはその後も二十三夜様への祈りを続け、村は年々豊かになっていきました。村人たちは毎月の二十三夜になると月夜の下に集まり、感謝の祈りを捧げるようになりました。
そして今でも、その村では二十三夜様へのお参りが欠かされることはありません。
ギャグ編
二十三夜様と黄金の井戸
昔々、とある山里に、おばあさんが一人で暮らしていました。おばあさんは貧乏でしたが、毎晩のように二十三夜様にお参りをしていました。
「二十三夜様、どうか私が明日転ばずに済みますように。あとできれば、ご飯にちょっとだけ味をくださいな。」
そんな控えめな願いが毎晩続き、ある日、二十三夜様はたまらず夢に現れました。
「おばあさん、そろそろ本気で願いなさい。そんな小さいことばかり願って、神様のスケールが試されているような気分じゃ!」
驚いたおばあさん、翌日から願いをグレードアップ!
「二十三夜様、どうか、こう、村中がひっくり返るような奇跡を起こしてくださいませ!」
井戸の中のサプライズ
その晩、二十三夜様は再び夢に現れ、おばあさんに言いました。
「いいだろう。明日、村の古井戸を掘りなさい。そこにすごいものが眠っているぞ。」
次の日、おばあさんは村の若者たちに声をかけました。
「二十三夜様に井戸を掘れと言われたんじゃ! 掘ったら何かすごいものが出るらしいぞ!」
若者たちは半信半疑でしたが、暇だったので手伝うことにしました。途中、ひとりがポツリ。
「おばあさん、これでドブネズミでも出てきたらどうします?」
「そしたら鍋にするさ!」
みんなで笑いながら掘り進めると、なんと底から黄金がザックザク!若者たちは目を丸くしました。
「おばあさん、これ、えらいことですよ!黄金ですよ!」
「よっしゃ! まずは村に温泉でも作るか! いや、露天風呂のほうがいいな!」
欲深男の逆襲
この話を聞いた村外れの欲深い男が黙っているはずがありません。彼は夜中にこっそり井戸を掘りに行きました。
「黄金だと?そんなもん、全部俺様がいただくぜ!」
勢いよく掘り進める男。やがて井戸の奥から何かキラリと光るものが見えました。
「おお、黄金だ!二十三夜様、ありがとよ!」
男が掴み取ったその瞬間――ゴォォォ!と井戸が唸り声を上げ、突然水が吹き出しました。
水柱とともに飛び上がった男は村中を大回転しながら叫びます。
「二十三夜様〜!あんたマジで何してんだぁぁぁ!」
男は村中をグルグル回ったあと、井戸の隣に落っこちました。
「これが…黄金の代償ってやつか…」と呟きながら、彼は翌日から真面目に農業を始めるようになったとか。
村の大繁栄
一方、おばあさんは黄金を使って村のために井戸を作り直し、学校や橋も建設。村人たちは感謝の意を込めて、毎月二十三夜様にお参りするようになりました。
おばあさんも相変わらず、質素な暮らしを続けながら言います。
「二十三夜様、毎日感謝しとるよ。でも次は、できれば腰が痛くならない布団をくださいな。」
そんなおばあさんの声に、二十三夜様は夢の中でまた頭を抱えるのでした。
2024年12月08日
日本昔話 そこつそうべえ
昔々、山のふもとの村に、そこつ者のそう兵衛という男が住んでいました。とにかくこの男、何をやらせてもドジばかり。考えなしに行動するため、村中の人が彼の失敗談を知っているほどでした。
ある日、そう兵衛の妻が言いました。
「そう兵衛さん、今日は米を買いに町へ行ってきておくれ。それから、ちゃんと袋を持っていってね!」
妻の言うことなんて普段聞かないそう兵衛ですが、この日は珍しく「わかった、わかった」と素直に返事をしました。袋を肩に担いで、町へ向かいます。
しかし道中、袋を使うつもりで練習しようと思ったそう兵衛は、袋を頭にかぶり、踊りながら歩き始めました。「ほれ、どうだい! 袋使いの名人だろう!」と一人で大笑い。しかし、前が見えないので、川にドボン! 袋はびしょ濡れ、そう兵衛もぐしょぐしょ。
町に着いた頃には、袋は乾ききらず。米屋に行くと、店主が驚いて言いました。
「なんだ、その袋は? 米を入れるにはまだ湿ってるぞ!」
そう兵衛は「ははは、大丈夫、大丈夫! 湿ってたほうが米がツヤツヤするって聞いたんだ!」と強引に話を進め、米を入れてもらいました。袋の底が湿っていたせいで、家に帰るまでに米が少しずつこぼれ、村に着く頃にはほとんど空っぽに。
「ちょっと! 何してきたのよ!」と怒る妻に、そう兵衛は平然と答えます。
「おい、これでも運がいいほうさ! 残った米は新しい道しるべになるかもしれないだろう!」
妻は呆れて言葉も出ませんでした。
次の日、妻は心配になり、そう兵衛にもっと簡単な仕事を頼みました。
「この魚を村の鍛冶屋さんに届けてちょうだい。でも、絶対に寄り道しちゃダメよ!」
「わかってるさ!」と答えたそう兵衛は魚を持って出発しますが、途中で友達に会い、「いい魚だな、少し焼いて食べようぜ」と提案され、つい一緒に焼き魚を食べてしまいました。気がつけば魚は跡形もなし!
「困ったな」とそう兵衛は、鍛冶屋に向かう途中で道端の石を拾い、包み紙に包んで渡しました。
「奥さんからの贈り物だってさ!」
鍛冶屋は怪訝そうな顔をしながら包みを開け、中の石を見て大爆笑。「お前の奥さんが石を食わせるつもりか?!」と言われ、そう兵衛は大いに恥をかきました。
村人たちはそんなそう兵衛を見て言います。
「ああ、またか。またあのドジなやつがやらかしたよ!」
そう兵衛の失敗談はどんどん増えていき、村の笑い話の種になったのでした。
めでたし、めでたし
ギャグ編
昔々、どこかの村に、天下一のドジ男、そこつそう兵衛が住んでいました。何を頼んでも失敗するので、村人たちは「そう兵衛に頼むくらいなら自分でやる」と口を揃えて言うほど。けれども、そう兵衛本人は気にするどころか、「俺は天才だ」と本気で思い込んでいました。
ある日、妻が言いました。
「そう兵衛さん! 今日は米を買いに町へ行ってきてちょうだい。でも、ちゃんと袋を持っていくのよ!」
そう兵衛は胸を張りながら答えました。
「任せろ! 俺に米を買わせたら、日本一の米が手に入るぞ!」
妻が念押しして袋を渡すと、そう兵衛は袋を肩にかけて町へ出発。しかし、道中で袋を頭にかぶり、「袋マン!」と叫びながら踊り出しました。
「どうだ、この姿! この村で一番カッコいい男は誰だ? …俺だ!」
調子に乗って踊りながら歩いていると、もちろん前が見えません。次の瞬間、ドボーン! 川に落ちて袋はびしょ濡れ。道端にいたカラスまで爆笑しています。
「おい、笑うな! お前らだって濡れたら飛べないくせに!」とカラスに怒鳴りながら、びしょびしょの袋で町に到着しました。
米屋での大騒ぎ
米屋に着くと、店主が驚いた顔で言いました。
「そう兵衛さん、その袋どうしたんだい? 湿気がすごいじゃないか!」
そう兵衛は得意げに答えます。
「湿った袋で米を運ぶのが、通のやり方なんだ! ツヤツヤになるって噂だぜ!」
店主は半信半疑ながら米を詰めてくれました。しかし、帰り道で袋の底から米がポタポタこぼれます。それを見たスズメたちが大喜びで米を追いかけ、そう兵衛の周りは鳥だらけに。
「おいおい、俺は米屋じゃないんだぞ! …まあ、俺の人気っぷりには驚くよな!」と呟きながら帰宅。
家に着くと、袋の中はほぼ空っぽ。妻は呆れ果てて叫びます。
「何これ!? こんなに少ししかないじゃない!」
そう兵衛は肩をすくめて、満足げに言いました。
「いやぁ、道中の鳥たちが感謝してる顔が忘れられないんだよ。俺、村のヒーローになったかも!」
妻はその場でそう兵衛に炊飯しゃもじを投げつけました。
魚を届ける任務
次の日、妻はもっと簡単な仕事を頼むことにしました。
「この魚を村の鍛冶屋さんに届けてきて。絶対に寄り道しちゃダメよ!」
「任せろ! 魚を届けるプロフェッショナルって呼ばれてるからな!」と胸を叩いて出発。
しかし、途中で友達の熊五郎に出会います。熊五郎は魚を見て言いました。
「いい魚だな! これ、焼いたら絶対うまいぞ!」
「だろ? 俺のセンスだ!」と調子に乗ったそう兵衛は、つい友達と魚を焼いて食べてしまいます。魚は跡形もなし。
「さて、鍛冶屋に何を渡そうかな…」と考えたそう兵衛、道端にあった石を拾い、包み紙で包みます。そして鍛冶屋に到着すると、堂々と渡しました。
「奥さんからの贈り物だ! 大事にしてくれよ!」
鍛冶屋は不思議そうに包みを開け、中から出てきた石を見て大爆笑。
「お前の奥さん、俺に石焼きでもさせる気か?」
そう兵衛は首をかしげて言いました。
「いやいや、それは最新の料理法だぞ! 『石の風味』が今流行ってるらしい!」
村人たちはその話を聞いて大笑いし、そう兵衛の新たな伝説がまた一つ増えました。それでもそう兵衛本人は涼しい顔で言います。
「いやぁ、俺みたいな天才がこの村にいるのは幸運だな!」
村人たちは口を揃えて言いました。
「お前がいるだけで十分笑わせてもらってるよ!」
めでたし、めでたし
2024年12月02日
11月の結果
2024年11月18日
日本昔話 地獄穴の話
https://manngamukashi.seesaa.net/
こっちに引っ越しました。
終了のため。


むかしむかし、とある村に、欲深いけれど腕のいい職人が住んでいた。名前を権右衛門(ごんえもん)という。彼は鍛冶仕事で名を馳せ、その腕前は村中の人々から頼られていた。しかし、仕事の対価は厳しく、貧しい者にも容赦なく高い報酬を求めた。そのため村人たちは彼の仕事を頼みつつも、心の中では恐れと不満を抱いていた。
そんなある日、村の近くの山で奇妙な噂が広まった。山の中腹に「地獄穴」と呼ばれる深い穴が現れたというのだ。誰が覗いても底が見えず、不気味な風が吹き出してくるその穴は、村人たちの間で「罪人を地獄へ引きずり込む穴」だと言われ始めた。
村人たちは恐れてその穴に近づかなかったが、好奇心旺盛な権右衛門だけは違った。「地獄穴だって? そんな馬鹿げたもの、この俺が確かめてやるさ。」
権右衛門は翌日、穴へ向かった。噂通り、穴は底知れぬ深さで、吹き出す風は不気味だった。しかし彼は臆することなく大声で叫んだ。「おい、地獄の奴ら!俺の悪事を暴けるもんなら暴いてみろ!」
すると、穴から低い声が響いてきた。
「権右衛門よ、お前は数々の悪事を働いた。村人を困らせ、貧しい者からも金を巻き上げた。それゆえ、この地獄穴がお前を招き入れる。」
権右衛門は笑い飛ばした。「冗談じゃない!俺の腕がなけりゃ村は回らん。これくらいの罪、地獄送りにはならんだろう!」
しかし、地獄穴からはさらに恐ろしい声が響いた。「では、お前自身が裁きを見極めよ。」
すると権右衛門の足元の地面が崩れ、彼は地獄穴の中へと吸い込まれた。
気がつくと、権右衛門は真っ暗な世界にいた。目の前には地獄の裁きの場が広がっている。火の海や苦しむ者たちの声が響き渡る中、閻魔大王が玉座に座っていた。
「権右衛門、お前の罪を裁く。」
次々と彼の行いが暴かれた。弱い者から金を搾り取り、助けを求める者を冷たく突き放してきた数々の記憶が浮かび上がる。
権右衛門は言葉を失った。「俺は…こんなにも酷いことを…。」
閻魔大王は厳かに告げた。「お前の罪を償うには地獄での罰を受けるか、あるいは生き返って善行を積む道がある。」
権右衛門は即座に叫んだ。「善行を積ませてくれ!もう一度、俺にチャンスを!」
村に戻った権右衛門は人が変わったようだった。報酬を求めずに鍛冶仕事を引き受け、困っている者には惜しみなく手を差し伸べた。
最初は村人たちも怪しんだが、彼の行動は嘘ではなかった。やがて村人たちは彼を尊敬し、信頼するようになった。
数年後、権右衛門は静かに息を引き取った。その夜、村の人々は地獄穴から眩しい光が昇るのを見た。それは、権右衛門が善行を積んだ証として地獄から救われたことを示していたのだろう。
村人たちは彼の名を語り継ぎ、「地獄穴」の場所には小さな祠を建て、罪を悔い改める大切さを教える場としたという。
ギャグ編
むかーしむかし、とある村に「欲深ゴンちゃん」こと権右衛門(ごんえもん)という鍛冶職人がおった。まあ、腕は確かなんだけど、性格がちょっとアレだった。
「おい、この鍋直すのに銀貨10枚な!」
「ゴンちゃん、それ高すぎるよ!たった1枚しか持ってないよ!」
「じゃあ持ってるの全部置いてけ。ついでにお前んちの猫もな!」
こんな具合で、村人たちからもっぱら「欲深ゴンちゃん」と呼ばれていた。ゴンちゃん本人は、「いやいや、オレがいなきゃ村は終わりだろ?」と全く反省する気なし。
そんなある日、村の外れの山で奇妙な「地獄穴」なるものが見つかったという噂が広まった。
「なんでも罪人が吸い込まれる穴らしいぞ!」
「夜になると穴から『ゴオォォン…』って音が聞こえるんだって!」
村人たちは怖がって誰も近づかない。でもゴンちゃんは大笑い。
「ハハハ!そんなのただの風穴だろ。オレが確認してやるよ!」
次の日、ゴンちゃんは鼻歌交じりに地獄穴へ向かった。そして、穴を見下ろして叫ぶ。
「おーい!地獄の連中よ!オレ様のどこが悪いってんだ!文句あるなら出てこいやー!」
すると、穴から低くて怖〜い声が響いてきた。
「権右衛門よ…お前の悪行、すべて知っておるぞ…」
ゴンちゃんは一瞬ビクッとしたが、すぐに笑い飛ばす。
「ははっ!悪行?具体的に何だよ!」
穴の声がすかさず返す。
「村人から金をむしり取り、猫まで奪ったその行い…」
ゴンちゃん、思わず目を泳がせる。
「いやいや、猫は向こうが勝手に置いてったんだよ!あとで返そうと思ってたし!」
声はさらに怒りを増して続ける。
「地獄の掟により、お前を穴に引きずり込む!」
その瞬間、ゴンちゃんの足元の地面が崩れ、見事に穴に吸い込まれた。
気がつくと、ゴンちゃんは地獄の裁きの場に立たされていた。目の前には閻魔大王。でっかい舌をペロリと出しながらゴンちゃんを睨みつける。
「権右衛門よ、お前の罪を暴いてやる!この鏡を見よ!」
鏡にはこれまでの悪行が鮮明に映し出された。
「ほら見ろ、この映像!貧しい婆さんから銀貨を巻き上げた挙句、鍋を歪ませて返しておる!」
「えっ、いや、それは鍋の素材が悪かったんですって!」
「さらにこれだ!村の猫を奪って、勝手に『鍛冶屋のマスコット』と呼んでいる!」
「だって可愛かったんだもん…」
ゴンちゃん、どんどん言い訳が苦しくなる。閻魔大王はついに怒りの雷を落とした。
「黙れ!貴様は地獄行きだ!」
ゴンちゃん、慌てて土下座。
「待った!待った!生き返って善行を積むから、それで許してくれよ!頼むって!」
閻魔大王、腕組みをして少し考えた後、こう告げた。
「よかろう。その代わり、次に悪事を働けば即アウトだ。覚悟せよ!」
地上に戻ったゴンちゃんは人が変わった…というか、めちゃくちゃ小心者になっていた。
「ゴンちゃん、この鍋修理してくれない?」
「あ、ああ!タダでいいよ!えっと、猫も返すからね!」
「ゴンちゃん、これも修理して!」
「もちろんもちろん!お礼なんていらないよ!むしろお米分けようか?」
村人たちは最初、「どうしたゴンちゃん、頭打ったのか?」と怪しんだが、彼の善行が本物だとわかると感動して泣いた。
数年後、ゴンちゃんが息を引き取ると、地獄穴から突然、輝く光がブワーッと吹き出た。そして穴の中から閻魔大王の声が響いた。
「権右衛門、よくやった!お前は天国行きだ!」
村人たちは光を見ながら、「ゴンちゃん、あんた最高のオチをつけてくれたなぁ!」と涙ながらに笑ったという。


こっちに引っ越しました。
終了のため。
むかしむかし、とある村に、欲深いけれど腕のいい職人が住んでいた。名前を権右衛門(ごんえもん)という。彼は鍛冶仕事で名を馳せ、その腕前は村中の人々から頼られていた。しかし、仕事の対価は厳しく、貧しい者にも容赦なく高い報酬を求めた。そのため村人たちは彼の仕事を頼みつつも、心の中では恐れと不満を抱いていた。
そんなある日、村の近くの山で奇妙な噂が広まった。山の中腹に「地獄穴」と呼ばれる深い穴が現れたというのだ。誰が覗いても底が見えず、不気味な風が吹き出してくるその穴は、村人たちの間で「罪人を地獄へ引きずり込む穴」だと言われ始めた。
村人たちは恐れてその穴に近づかなかったが、好奇心旺盛な権右衛門だけは違った。「地獄穴だって? そんな馬鹿げたもの、この俺が確かめてやるさ。」
権右衛門は翌日、穴へ向かった。噂通り、穴は底知れぬ深さで、吹き出す風は不気味だった。しかし彼は臆することなく大声で叫んだ。「おい、地獄の奴ら!俺の悪事を暴けるもんなら暴いてみろ!」
すると、穴から低い声が響いてきた。
「権右衛門よ、お前は数々の悪事を働いた。村人を困らせ、貧しい者からも金を巻き上げた。それゆえ、この地獄穴がお前を招き入れる。」
権右衛門は笑い飛ばした。「冗談じゃない!俺の腕がなけりゃ村は回らん。これくらいの罪、地獄送りにはならんだろう!」
しかし、地獄穴からはさらに恐ろしい声が響いた。「では、お前自身が裁きを見極めよ。」
すると権右衛門の足元の地面が崩れ、彼は地獄穴の中へと吸い込まれた。
気がつくと、権右衛門は真っ暗な世界にいた。目の前には地獄の裁きの場が広がっている。火の海や苦しむ者たちの声が響き渡る中、閻魔大王が玉座に座っていた。
「権右衛門、お前の罪を裁く。」
次々と彼の行いが暴かれた。弱い者から金を搾り取り、助けを求める者を冷たく突き放してきた数々の記憶が浮かび上がる。
権右衛門は言葉を失った。「俺は…こんなにも酷いことを…。」
閻魔大王は厳かに告げた。「お前の罪を償うには地獄での罰を受けるか、あるいは生き返って善行を積む道がある。」
権右衛門は即座に叫んだ。「善行を積ませてくれ!もう一度、俺にチャンスを!」
村に戻った権右衛門は人が変わったようだった。報酬を求めずに鍛冶仕事を引き受け、困っている者には惜しみなく手を差し伸べた。
最初は村人たちも怪しんだが、彼の行動は嘘ではなかった。やがて村人たちは彼を尊敬し、信頼するようになった。
数年後、権右衛門は静かに息を引き取った。その夜、村の人々は地獄穴から眩しい光が昇るのを見た。それは、権右衛門が善行を積んだ証として地獄から救われたことを示していたのだろう。
村人たちは彼の名を語り継ぎ、「地獄穴」の場所には小さな祠を建て、罪を悔い改める大切さを教える場としたという。
ギャグ編
むかーしむかし、とある村に「欲深ゴンちゃん」こと権右衛門(ごんえもん)という鍛冶職人がおった。まあ、腕は確かなんだけど、性格がちょっとアレだった。
「おい、この鍋直すのに銀貨10枚な!」
「ゴンちゃん、それ高すぎるよ!たった1枚しか持ってないよ!」
「じゃあ持ってるの全部置いてけ。ついでにお前んちの猫もな!」
こんな具合で、村人たちからもっぱら「欲深ゴンちゃん」と呼ばれていた。ゴンちゃん本人は、「いやいや、オレがいなきゃ村は終わりだろ?」と全く反省する気なし。
そんなある日、村の外れの山で奇妙な「地獄穴」なるものが見つかったという噂が広まった。
「なんでも罪人が吸い込まれる穴らしいぞ!」
「夜になると穴から『ゴオォォン…』って音が聞こえるんだって!」
村人たちは怖がって誰も近づかない。でもゴンちゃんは大笑い。
「ハハハ!そんなのただの風穴だろ。オレが確認してやるよ!」
次の日、ゴンちゃんは鼻歌交じりに地獄穴へ向かった。そして、穴を見下ろして叫ぶ。
「おーい!地獄の連中よ!オレ様のどこが悪いってんだ!文句あるなら出てこいやー!」
すると、穴から低くて怖〜い声が響いてきた。
「権右衛門よ…お前の悪行、すべて知っておるぞ…」
ゴンちゃんは一瞬ビクッとしたが、すぐに笑い飛ばす。
「ははっ!悪行?具体的に何だよ!」
穴の声がすかさず返す。
「村人から金をむしり取り、猫まで奪ったその行い…」
ゴンちゃん、思わず目を泳がせる。
「いやいや、猫は向こうが勝手に置いてったんだよ!あとで返そうと思ってたし!」
声はさらに怒りを増して続ける。
「地獄の掟により、お前を穴に引きずり込む!」
その瞬間、ゴンちゃんの足元の地面が崩れ、見事に穴に吸い込まれた。
気がつくと、ゴンちゃんは地獄の裁きの場に立たされていた。目の前には閻魔大王。でっかい舌をペロリと出しながらゴンちゃんを睨みつける。
「権右衛門よ、お前の罪を暴いてやる!この鏡を見よ!」
鏡にはこれまでの悪行が鮮明に映し出された。
「ほら見ろ、この映像!貧しい婆さんから銀貨を巻き上げた挙句、鍋を歪ませて返しておる!」
「えっ、いや、それは鍋の素材が悪かったんですって!」
「さらにこれだ!村の猫を奪って、勝手に『鍛冶屋のマスコット』と呼んでいる!」
「だって可愛かったんだもん…」
ゴンちゃん、どんどん言い訳が苦しくなる。閻魔大王はついに怒りの雷を落とした。
「黙れ!貴様は地獄行きだ!」
ゴンちゃん、慌てて土下座。
「待った!待った!生き返って善行を積むから、それで許してくれよ!頼むって!」
閻魔大王、腕組みをして少し考えた後、こう告げた。
「よかろう。その代わり、次に悪事を働けば即アウトだ。覚悟せよ!」
地上に戻ったゴンちゃんは人が変わった…というか、めちゃくちゃ小心者になっていた。
「ゴンちゃん、この鍋修理してくれない?」
「あ、ああ!タダでいいよ!えっと、猫も返すからね!」
「ゴンちゃん、これも修理して!」
「もちろんもちろん!お礼なんていらないよ!むしろお米分けようか?」
村人たちは最初、「どうしたゴンちゃん、頭打ったのか?」と怪しんだが、彼の善行が本物だとわかると感動して泣いた。
数年後、ゴンちゃんが息を引き取ると、地獄穴から突然、輝く光がブワーッと吹き出た。そして穴の中から閻魔大王の声が響いた。
「権右衛門、よくやった!お前は天国行きだ!」
村人たちは光を見ながら、「ゴンちゃん、あんた最高のオチをつけてくれたなぁ!」と涙ながらに笑ったという。
2024年11月16日
日本昔話 かじやのババア
昔々、とある山奥の村に、腕の立つ鍛冶屋のおばあさんがいました。村の人々は彼女を「鍛冶屋のババア」と呼び、鉄鍋や農具が必要になると、こぞって彼女の家に押しかけてきました。しかし、このババア、とにかく口が悪い。
「お前の顔、見てるだけで鉄が曲がるわ!」
「このクワの刃が鈍い?お前の脳みそよりは切れるさ!」
などなど、いつも毒舌全開。にもかかわらず、彼女の作る道具はどれも一流。だから誰も文句を言えなかったのです。
ある日、奇妙な依頼が…
そんなある日のこと。山を越えた隣村から、ひとりの男がやってきました。服はボロボロ、足には泥がついており、いかにも苦労している様子。
「ババアさん、この鍋を修理してくれませんか?」
彼が差し出したのは、見るからに古くてボコボコの鉄鍋でした。
「こんなポンコツ鍋、叩いても直らんわ!新しいの買え!」と、いつものように追い返そうとするババア。しかし男は土下座をして懇願しました。
「どうかお願いします。この鍋は母の形見なんです…」
その言葉に、さすがのババアも心を動かされました。
「仕方ねぇな、やってみるか!」
奇跡の鉄鍋
ババアは鍛冶場にこもり、鍋を叩き始めました。すると、不思議なことが起こりました。
ゴンッ!ゴンッ!と叩くたびに、鍋がピカピカに光り始め、まるで新しい鍋に生まれ変わっていくではありませんか。
「おいおい、なんだこれ?鍋のくせに調子に乗りやがって!」と毒づきながらも、ババアは鍋を修理し続けました。完成した鍋は、なんと金色に輝き、触ると温かい。不思議な力を宿しているようでした。
鍋の秘密
修理を終えたババアが男に鍋を渡すと、男は涙を流して喜びました。
「これで母の魂も喜んでくれる…ありがとうございます!」
そのとき、鍋から声が聞こえました。
「ありがとう、ババアさん。この鍋には母の魂が宿っていたのです!」
ババアは目を丸くして叫びました。
「な、鍋がしゃべった!? おいおい、幽霊仕事まで引き受けるつもりはねぇぞ!」
しかし、鍋はこう続けました。
「あなたの腕前と心意気に感謝しています。この村とあなたを守る力を与えましょう。」
その日から、村には奇跡が起こりました。鍋で作った料理を食べると、不思議とどんな病気も治り、鍛冶屋の道具を使うと収穫が増えるようになったのです。村人たちは大喜びしました。
最後に
鍛冶屋のババアは、その後も変わらず毒舌を続けましたが、村では「ありがたいババア」と呼ばれるようになりました。
「鉄も人間も、叩けばなんとかなるもんさ!」と言いながら、ババアは今日も鍛冶場で鍋を叩いています。
めでたし、めでたし。
ギャグ編
鍛冶屋のババアとしゃべる鍋
昔々、山奥の村に「鍛冶屋のババア」と呼ばれる、口が悪いけど腕は超一流のおばあさんがいました。村人たちは彼女に道具を直してもらいに来るものの、みんな彼女の毒舌でボコボコにされるのが通過儀礼のようになっていました。
「このクワの刃、もうちょっと鋭くならんか?」と相談すれば、
「お前の頭よりは鋭いだろうが!」
「この鍋、焦げつきやすいんだけど…」と言えば、
「お前が料理下手なだけだ!」
それでも彼女の作る道具は頑丈で使いやすいので、誰も文句を言えませんでした。いや、文句を言ったところで、ババアの返しが強烈すぎて二度と言えなくなるのでした。
しょぼくれた男とボコボコの鍋
ある日、隣村から一人のしょぼくれた男がババアの鍛冶場にやってきました。服はボロボロ、顔は土色、歩き方はゾンビみたい。
「ババアさん、この鍋、修理してほしいんです!」
彼が差し出した鍋は、もはや鍋というより鉄クズの集合体みたいなものでした。穴だらけで、もはやカゴとしても使えない状態。
ババアはそれを見て鼻で笑いました。
「これを鍋だと思ってるのか?私にゴミ処理場やれってのか?」
男は必死に頭を下げました。
「どうかお願いします!この鍋は母の形見なんです!」
それを聞いたババアは一瞬だけ真顔になり、そして豪快に笑い飛ばしました。
「母ちゃん、なんでこんな鍋残していったんだよ!せめて蓋ぐらい残せ!」
それでも男が涙ながらに頼むので、ババアは仕方なく引き受けることにしました。
「まったく、しょうがねぇな!あんた、ラーメン1年分くらいの料金払えるんだろうな?」
「えっ、そんなに高いんですか!?」
「冗談だよ。1年分じゃ足りない。3年分な。」
奇跡の修理
ババアは鍛冶場にこもり、鍋を叩き始めました。しかし、この鍋、とにかくクセが強い!
叩けば「ボコッ!」という音とともに鍋が跳ね返り、ババアの額にヒット。
「痛ぇ!おい、鍋のくせに反抗すんな!」
再び叩けば、鍋が突然蒸気を吹き出し、ババアの髪が爆発したみたいにボサボサに。
「なんだ、爆弾鍋か!? これ作った奴、どういう神経してんだ!」
何度も苦戦しながら修理を続けると、鍋がピカピカに光り始めました。
「おい、どうなってんだ?お前、鍋のくせに進化してんのか?」
すると突然、鍋がしゃべり出しました。
「進化じゃない、私は生まれ変わったのだ!」
ババア、驚きすぎてハンマーを取り落としました。
「しゃ、しゃべる鍋!? おい、誰だ、こんな悪ふざけしたのは!」
鍋の恩返し
しゃべる鍋は、ババアに向かって頭を下げました(もちろん、鍋なので上下の概念はない)。
「鍛冶屋のババアさん、ありがとう。この鍋には亡き母の魂が宿っていました。あなたの腕で鍋を修理してもらい、魂も安らかになりました!」
ババアは鍋をつまんでひっくり返し、穴がふさがったのを確認しました。
「ふーん、魂が宿ってた?そんな大事な話、最初にしろよ!」
男は泣きながら喜びました。
「これで母が天国で安心して眠れます!」
鍋は続けてこう言いました。
「お礼に、この村を守る力を授けましょう。この鍋で作る料理を食べると、どんな病気も治ります!」
ババアは鍋をジロリと見て、ニヤリと笑いました。
「病気が治るだぁ?こりゃ商売上がったりだな。でもまぁ、いいか。この鍋で商売するか!」
その後の村
村では鍋で作られる料理が大評判となり、みんな健康で幸せになりました。ババアの毒舌も健在で、こう言い放つのでした。
「この鍋で飯を食うやつ、毒舌にも耐える免疫がつくんだよ!」
めでたし、めでたし。
2024年11月02日
日本昔話 ほそごし
むかしむかし、山あいの小さな村に、とても貧しいけれど心優しい夫婦が暮らしていました。彼らの家は古びて、風が吹くたびに壁の隙間から寒い風が吹き込むほどでした。それでも夫婦は手を取り合って毎日を生き抜いていました。
ある年の冬、雪は例年にも増して厳しく、村人たちは食べ物を探すのに苦労していました。夫婦も例外ではなく、食料の蓄えは尽きてしまい、夫は意を決して、山に狩りに出かけることにしました。
「気をつけてな、早く帰ってきておくれ」と妻は心配そうに声をかけます。夫はうなずき、弓矢を背負って深い雪の中に足を踏み入れました。
森の奥へと進むにつれ、夫は獲物の気配を探しましたが、雪の静寂はそのままに何の音もありません。やがて、彼は凍えそうになりながら小さな祠を見つけ、しばし休息をとることにしました。祠には「ほそごし」という名が彫られた古びた木板がありました。
「ほそごし…?妙な名前じゃな」と夫はつぶやきました。すると、不意に冷たい風が吹き、祠の中からかすかな声が響きました。
「わたしの名を呼んだか?」
驚いた夫は後ずさりましたが、そこには小さな、しかし不思議な姿をした老人が立っていました。細い体に大きな眼鏡をかけ、まるで風そのものが人の形をとったかのような姿です。
「もし、あなたが困っているのなら、わたしが助けてあげよう」と老人は言いました。「その代わりに、わたしの細さをもらってくれないか?」
夫は何のことかわからず困惑しましたが、助けを求める気持ちが勝ちました。「お願いします。何でもいたします。妻が飢えています。どうか、どうか助けてください」
すると、老人は細い指をひと振りすると、一陣の風と共に姿を消しました。代わりに夫の前には食べ物が山のように積まれた包みがありました。夫は驚きながらもその包みを抱え、急いで家に帰りました。
家で待っていた妻は夫を見て大喜びしました。「こんなにたくさんの食べ物、一体どうしたの?」
夫はその日の出来事を話し、二人は涙を流しながら感謝しました。しかし、夫の体は日ごとに痩せ細っていきました。老人の「細さ」を受け取った夫は、やがて村一番の「ほそごし」と呼ばれるようになったのです。
それでも夫婦は幸せでした。彼らは助け合い、生きる喜びを知り、村人たちと共にその後も長く幸せに暮らしたということです。
ギャグ編
ある寒い冬の日、山あいの村に暮らす貧乏夫婦がいました。家はあまりにボロボロで、風が吹くたびに「寒っ!やだもう!」と妻がつぶやき、夫が「いや、今日こそ大丈夫…たぶん」と無理やり楽観的な返事をしていました。しかしその日は違いました。食料は尽き、夫はついに言いました。
「今日こそオレ、狩りに行って伝説の獲物を手に入れるんだ!その名も『山の中で噂のホットケーキ』だ!」
妻は眉をひそめて言いました。「あなた、ホットケーキじゃなくて普通に獲物捕まえてきてくれる?あと、オレって誰?」
夫は深くうなずき、出発しました。山は寒く、彼の歯がガチガチ鳴る音が森全体に響きました。「さ、さ、さむい…この音で獲物が逃げたらどうしよう!」と思っていると、彼は小さな祠を見つけました。祠の扉には「ほそごし」と書かれた木板が貼られていました。
「ほそごし?細い腰でも守るおまじないか?」と夫がふざけて言ったその瞬間、冷たい風が吹き荒れ、祠の中から老人が飛び出してきました。老人は細くて眼鏡をかけ、風に揺れる髭がまるでネギのようです。
「わたしの名を呼んだかのぅ?」と老人が言いました。
夫は驚き、「いやいやいや、呼んだんじゃなくて読んだだけですよ!」と手を振りました。
しかし老人は聞いていませんでした。「わしの細さを授けてやろう。それと引き換えに、お前に食べ物を与えよう」と宣言しました。
「いや、ちょっと待って!細さって何?」と夫が焦りましたが、老人はニヤリと笑い、「細くて得すること、たくさんあるぞ。例えば…ええと、隙間から楽々脱出できるとか!」と訳のわからないことを言いました。
一瞬のうちに、夫の目の前に食べ物が山積みされました。夫は叫びました。「おお、これは夢か?いや、これは現実だ、リアルホットケーキだ!」
夫は急いで家に戻り、妻はその山積みの食べ物を見て目を丸くしました。「ちょっと!何この量!まさかあの『伝説のホットケーキ』?」
夫は笑って答えました。「いや、これ全部老人がくれたんだ。あと、ちょっとだけ痩せてくる副作用があるらしい」
その後、夫の体はみるみる細くなり、ついに妻から「ねぇ、ほそごしってあなたのことだったのね」と言われる始末。夫はにやりと笑い、「これで村一の細マッチョさ!」と言いながら腕を振り上げたが、風に飛ばされそうになりました。
それでも夫婦は笑い、食べ物に囲まれて幸せに暮らしました。村では、「細くなるといいことあるらしい」という妙な伝説が生まれ、みんながダイエットを始めたとか、始めなかったとか。
10月
2024年10月14日
日本昔話 ねずみの相撲
むかしむかし、山あいの小さな村に、おじいさんとおばあさんが住んでいました。二人はとても優しい心を持っていましたが、長いこと二人きりの生活を送っていました。家には、小さなネズミが一匹、チョロチョロと動き回っていて、時折姿を見せるそのネズミは、まるで二人の家族のような存在でした。
ある日、おじいさんが薪を拾いに山へ出かけたときのこと。途中で立ち寄った神社のそばで、何やら小さな声が聞こえてきました。耳を澄ますと、どうやらその声は地面の中から響いているようです。不思議に思ったおじいさんが、そっと草むらをかき分けてみると、小さなネズミたちが楽しそうに相撲を取っているではありませんか!小さな体でありながら、力強く押し合い、真剣な表情で勝負に挑む姿に、おじいさんは驚きました。
「ほう、これは面白いことだ」と、おじいさんはしばらくその様子を見守り、心が温かくなるのを感じました。
家に帰ると、おじいさんはおばあさんにこの不思議な出来事を話しました。「おばあさん、今日はとんでもないものを見たぞ。山のネズミたちが、なんと相撲を取っていたんだ!」と嬉しそうに話すと、おばあさんも驚き、「そんなことがあるのかい?不思議だねえ」と首を傾げました。
翌日、おじいさんとおばあさんは、ふと「あのネズミたちにご馳走をあげよう」と思い立ちました。二人はお餅を作り、それを持って再び山へ向かいました。神社の近くの草むらに餅を置いて、少し離れたところから見守ることにしました。
しばらくすると、ネズミたちがまた集まってきて、相撲を始めました。おじいさんとおばあさんが餅を置いたことに気づいたネズミたちは、大喜びで餅を抱え上げ、感謝の気持ちを込めてその餅を持ち帰りました。
その夜、家に戻ったおじいさんとおばあさんが眠りにつこうとしたとき、不思議な音が聞こえてきました。窓の外を見ると、なんとあの相撲を取っていたネズミたちが家の前に現れ、小さな小判を運んできたのです!ネズミたちは、お餅のお礼として、小判を二人に渡し、何度も頭を下げました。
それ以来、おじいさんとおばあさんの生活は豊かになり、二人は幸せに暮らしました。そして、いつまでもネズミたちとの温かい絆は続いていったのです。
めでたし、めでたし。
ギャグ編
昔々、山あいの小さな村に、おじいさんとおばあさんが住んでいました。二人は優しい心を持っていましたが、最近少し暇を持て余していました。暇すぎて、とうとう「今日はどの辺が痛いか」について語り合うのが唯一の楽しみとなっていました。
ある日、おじいさんが「今日は膝が痛むなぁ」とぼやきながら山へ薪拾いに出かけました。すると途中で、どこからともなく「はっけよーい、残った残った!」という小さな声が聞こえてきます。「え?相撲中継?」おじいさんは耳を疑いました。「いやいや、そんなはずはない。山の中にテレビなんてないじゃろ」と自分にツッコミを入れつつ、声の方へ近づいてみると――
なんと、そこにはネズミたちがちっちゃな土俵で相撲を取っているではありませんか!おじいさんは目をパチクリさせながら、その壮絶な(いや、むしろちんまりした)取り組みを眺めました。
「おお、すごいじゃないか!」と声を上げると、近くのネズミがびっくりして「な、なんだ、おっさん!」と言いながら、すっ転びました。「えっ、喋るんかい!」とおじいさんもびっくりして後ずさり。でもすぐに「これは面白いことになったぞ」とほくそ笑みます。
家に戻ると、おじいさんはおばあさんにそのことを興奮気味に話しました。「おばあさん、今日すごいもん見たぞ。山でネズミたちが相撲をしておった!」と。おばあさんは「はあ?おじいさん、それは薪拾いのしすぎでついに幻覚を見たんじゃないのかい?」と冷静に返しましたが、おじいさんは「いや、ほんまやって!明日一緒に行こう!」と強引におばあさんを誘います。
翌日、二人はネズミたちにご馳走をあげようと、お餅を持って山へ向かいました。神社のそばにお餅を置いてこっそり隠れていると、ネズミたちがまた集まってきました。「おお、餅じゃん!」「誰が置いたんだ?」「まぁ、いいか、いただきまーす!」とネズミたちは大喜びで餅をむさぼります。
ところが、一匹のネズミが大声で言いました。「ちょっと待て!これ、消費期限切れてないか?」みんな急に手を止め、「いや、まだセーフだろ」「いや、アウトだろ」なんて言い合いが始まりました。そこにおじいさんがこっそり現れ、「大丈夫、まだ3日くらい余裕があるぞ!」と突っ込むと、ネズミたちは「おっさん、どこから出てきたんだよ!」とびっくり。
その夜、おじいさんとおばあさんが家で眠っていると、窓の外からカサカサ音が聞こえてきます。「またネズミか?」と思って外を覗くと、ネズミたちが今度は小判を運んできたのです。「この前のお餅、ウマかったからお礼だよ!」と言い、さらに「消費期限のことは気にしないでくれ!」とにっこり。
それからというもの、おじいさんとおばあさんの家には定期的にネズミたちが訪れ、お餅と小判の物々交換が始まりました。おじいさんたちは「これって商売になるか?」と密かに考えながら、のんびりと幸せに暮らしましたとさ。
めでたしめでたし。