2018年10月15日
産後1か月はどんなことに注意が必要?水仕事は?
「産後、床上げするまでの1ヶ月間はゆっくりしたほうがいい」と耳にしたことがある人もいるかもしれませんね。そもそも「床上げ」にはどのような意味があるのでしょうか。今回は産後の床上げについて、産後1ヶ月の生活の注意点や水仕事はしてもいいのかどうかについてご説明します。
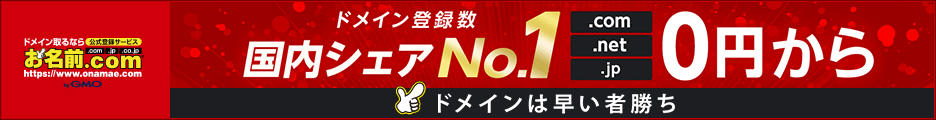

産後の床上げとは?期間はいつからいつまで?
産後の「床上げ(とこあげ)」とは、出産の疲れから体が回復して、日常の生活に徐々に復帰することをいいます。
そもそも、なぜ床上げと呼ばれているのでしょうか?
床上げとは、産後、ママがいつでも休めるようにと敷いたままにしていた布団を、体調の回復とともに片付ける様子からきた言葉です。出産だけでなく、大きな病気が完治したときのお祝いの言葉としても使われます。
産後は、自分が思っている以上に体が疲れています。医学的にも、出産の影響を受けた体が妊娠前の状態に戻るまで6~8週間かかるとしており、この期間を「産褥期」と呼びます(※1)。
床上げは、出産から3週間後を目安に考えましょう。3週間ほど経つと、悪露や会陰切開の傷口なども癒えてきます。
床上げまでの期間は短い人で産後3週間、長い人では2ヶ月ほど取るようです。人それぞれ回復のスピードは異なるので、自分の体調とよく相談して床上げのタイミングを決めてくださいね。


床上げ前の産後1ヶ月の生活で注意すべきことは?
床上げを迎える前の産後1ヶ月間は、どれくらい安静にして生活したらいいのかと気になりますよね。また、どんなことに注意すれば良いのでしょうか。
産後1ヶ月間の生活は、下記のような点に注意してください。
日常生活の注意点
産後1ヶ月の間は、授乳や赤ちゃんのお世話、自分の体のケアにできるだけ集中してください。
しかし、安静にしすぎてずっと横になっていると、逆に回復が遅くなることもあります。体調を見て、少しずつ活動範囲を広げていきましょう。適度に動くことで、血栓の予防にもなります。
また、産後すぐは子宮内の感染症などのリスクが高いため、湯船に浸かるのは控え、シャワーだけですませるようにしてください。一般的に、1ヶ月健診で体に問題がなければ、湯船に浸かることができるようになります。
家事の注意点
体のことを考えて、産後2週間ほどは料理や掃除、洗濯などの家事は極力控えましょう。産後3週目に入ったら、体調が良い日を見つけて軽めの家事から始めてみてください。
日中、家族の協力が得られないときは、一人で行う家事をできるだけ減らしましょう。自分が使った食器を洗う、赤ちゃんの周りをちょっと片付けるなど、軽いものだけにしてください。
体力を必要とする家事は、旦那さんや家族が休みの日などに一緒にできるといいですね。
ちなみに、昔は「産後1ヶ月がすぎるまでは、水仕事をしてはいけない」といわれていました。これは、「水仕事」が井戸での水汲みや湯沸かしなど、今よりはるかに重労働だったためです。
今では蛇口をひねればすぐ水やお湯が出るので、水仕事を控える必要はありませんよ。
外出の注意点
赤ちゃんもママも、基本的に1ヶ月健診を終えるまでは外出を控えたほうがよいでしょう。
産後は体調が安定していないことも多いため、病院に行くなどする場合は、電車やバスなどの公共の交通機関の利用は避けたほうが安心です。タクシーを利用したり、自家用車を家族に運転してもらったりしましょう。
外出できるようになっても、いきなり長時間外出したり、人ごみに行ったりするのは控えましょう。
食品や日用品の買い物は、自宅まで届けてくれるネットスーパーなどを活用するのがおすすめです。
また里帰り出産の場合は、1ヶ月健診で異常がなければ帰省先から自宅に戻ることができます。しかし、新幹線や飛行機などでの長距離移動は赤ちゃんやママに負担がかかりやすいので、無理のない計画を立ててくださいね。


運動の注意点
産後は妊娠前と体型が大きく変わっているので、妊娠前の状態に戻すために、産後ダイエットをすぐに始めたいと思う人もいるかもしれません。
しかし、産後1ヶ月の間に無理をしすぎると、体の回復が遅くなってしまいます。激しい運動は避け、体への負担がない「産褥体操」から始めてみましょう。
産後すぐから使える骨盤ベルトなどの矯正器具もあるので、体調の回復に合わせて使ってみるのもいいかもしれません。
性行為の注意点
産後の体は、すぐに性行為をできる状態ではないため、旦那さんに体の状態を理解してもらってください。
1ヶ月健診で異常がなく、悪露や会陰切開の痛みなどもなくなっているのが、性行為を再開する目安とされています。
また、「産後すぐなら避妊しなくてもいい」と考えがちですが、人によっては産後すぐに生理が再開することもあり、妊娠する可能性もあります。
子宮の回復には最低でも産後2ヶ月は必要で、帝王切開の場合は傷の回復に半年から1年ほどはかかります。
産後すぐの性行為は控え、ママの体のためにも、子宮が回復するまでは避妊するようにしましょう。

産後の床上げ後は情緒不安定になりやすい?
床上げ後も、すぐに無理をするのは厳禁です。徐々に体を慣らしていくことを心がけてください。
ママは、赤ちゃんのお世話に追われる生活で疲れがたまりがちです。旦那さんや家族に状況を説明し、自分のことは自分でやってもらうようにしたいですね。
力仕事も、できるだけ旦那さんや家族に任せましょう。
また、産後はホルモンバランスの乱れから、精神的に不安定になる時期です。
産後3~10日の間には、30~50%の妊婦さんが、一過性の軽い抑うつ状態である「マタニティーブルーズ」を発症します(※2)。
ここで無理をして症状が重症化すると、強い抑うつ状態が続く「産後うつ病」になる可能性もあります。
周囲への理解を求め、適度に肩の力を抜いて、育児や家事と向き合ってくださいね。
産後の床上げまでは無理をしない生活を
床上げを迎えるまでの約1ヶ月は、お産で疲れたママの体を回復させるために大切な期間です。
真面目で頑張り屋さんのママほど、つい無理をしてしまいがちですが、この時期は周囲の助けを借りて体を休ませることに集中してください。そして、少しずつ体を動かして日常生活に戻っていきましょう。
旦那さんや家族に協力をお願いできない場合は、「産後ケアセンター」を利用するのも一つの方法です。
最近では、家事支援やホームヘルパーなど、産後の日常生活をサポートしてくれる様々なサービスがあるので、積極的に利用してください。
また、産後ダイエットを始めたいと思う人も多いと思いますが、床上げの時期は体調回復を優先しましょう。

※1 日本産科婦人科学会『産科婦人科用語集・用語解説集 改訂第3版』p.196
※2 株式会社メディックメディア『病気がみえるvol.10 産科 第3版』p.369
産後の床上げとは?期間はいつからいつまで?
産後の「床上げ(とこあげ)」とは、出産の疲れから体が回復して、日常の生活に徐々に復帰することをいいます。
そもそも、なぜ床上げと呼ばれているのでしょうか?
床上げとは、産後、ママがいつでも休めるようにと敷いたままにしていた布団を、体調の回復とともに片付ける様子からきた言葉です。出産だけでなく、大きな病気が完治したときのお祝いの言葉としても使われます。
産後は、自分が思っている以上に体が疲れています。医学的にも、出産の影響を受けた体が妊娠前の状態に戻るまで6~8週間かかるとしており、この期間を「産褥期」と呼びます(※1)。
床上げは、出産から3週間後を目安に考えましょう。3週間ほど経つと、悪露や会陰切開の傷口なども癒えてきます。
床上げまでの期間は短い人で産後3週間、長い人では2ヶ月ほど取るようです。人それぞれ回復のスピードは異なるので、自分の体調とよく相談して床上げのタイミングを決めてくださいね。
床上げ前の産後1ヶ月の生活で注意すべきことは?
床上げを迎える前の産後1ヶ月間は、どれくらい安静にして生活したらいいのかと気になりますよね。また、どんなことに注意すれば良いのでしょうか。
産後1ヶ月間の生活は、下記のような点に注意してください。
日常生活の注意点
産後1ヶ月の間は、授乳や赤ちゃんのお世話、自分の体のケアにできるだけ集中してください。
しかし、安静にしすぎてずっと横になっていると、逆に回復が遅くなることもあります。体調を見て、少しずつ活動範囲を広げていきましょう。適度に動くことで、血栓の予防にもなります。
また、産後すぐは子宮内の感染症などのリスクが高いため、湯船に浸かるのは控え、シャワーだけですませるようにしてください。一般的に、1ヶ月健診で体に問題がなければ、湯船に浸かることができるようになります。
家事の注意点
体のことを考えて、産後2週間ほどは料理や掃除、洗濯などの家事は極力控えましょう。産後3週目に入ったら、体調が良い日を見つけて軽めの家事から始めてみてください。
日中、家族の協力が得られないときは、一人で行う家事をできるだけ減らしましょう。自分が使った食器を洗う、赤ちゃんの周りをちょっと片付けるなど、軽いものだけにしてください。
体力を必要とする家事は、旦那さんや家族が休みの日などに一緒にできるといいですね。
ちなみに、昔は「産後1ヶ月がすぎるまでは、水仕事をしてはいけない」といわれていました。これは、「水仕事」が井戸での水汲みや湯沸かしなど、今よりはるかに重労働だったためです。
今では蛇口をひねればすぐ水やお湯が出るので、水仕事を控える必要はありませんよ。
外出の注意点
赤ちゃんもママも、基本的に1ヶ月健診を終えるまでは外出を控えたほうがよいでしょう。
産後は体調が安定していないことも多いため、病院に行くなどする場合は、電車やバスなどの公共の交通機関の利用は避けたほうが安心です。タクシーを利用したり、自家用車を家族に運転してもらったりしましょう。
外出できるようになっても、いきなり長時間外出したり、人ごみに行ったりするのは控えましょう。
食品や日用品の買い物は、自宅まで届けてくれるネットスーパーなどを活用するのがおすすめです。
また里帰り出産の場合は、1ヶ月健診で異常がなければ帰省先から自宅に戻ることができます。しかし、新幹線や飛行機などでの長距離移動は赤ちゃんやママに負担がかかりやすいので、無理のない計画を立ててくださいね。
運動の注意点
産後は妊娠前と体型が大きく変わっているので、妊娠前の状態に戻すために、産後ダイエットをすぐに始めたいと思う人もいるかもしれません。
しかし、産後1ヶ月の間に無理をしすぎると、体の回復が遅くなってしまいます。激しい運動は避け、体への負担がない「産褥体操」から始めてみましょう。
産後すぐから使える骨盤ベルトなどの矯正器具もあるので、体調の回復に合わせて使ってみるのもいいかもしれません。
性行為の注意点
産後の体は、すぐに性行為をできる状態ではないため、旦那さんに体の状態を理解してもらってください。
1ヶ月健診で異常がなく、悪露や会陰切開の痛みなどもなくなっているのが、性行為を再開する目安とされています。
また、「産後すぐなら避妊しなくてもいい」と考えがちですが、人によっては産後すぐに生理が再開することもあり、妊娠する可能性もあります。
子宮の回復には最低でも産後2ヶ月は必要で、帝王切開の場合は傷の回復に半年から1年ほどはかかります。
産後すぐの性行為は控え、ママの体のためにも、子宮が回復するまでは避妊するようにしましょう。
 | 【送料無料】 ワコール Wacoal マタニティ マタニティー 産後シェイプマミーガードル ロング丈 MGR378 (ウエスト上丈9cm) 産後ガードル wcl-maaセール 価格:11,000円 |
産後の床上げ後は情緒不安定になりやすい?
床上げ後も、すぐに無理をするのは厳禁です。徐々に体を慣らしていくことを心がけてください。
ママは、赤ちゃんのお世話に追われる生活で疲れがたまりがちです。旦那さんや家族に状況を説明し、自分のことは自分でやってもらうようにしたいですね。
力仕事も、できるだけ旦那さんや家族に任せましょう。
また、産後はホルモンバランスの乱れから、精神的に不安定になる時期です。
産後3~10日の間には、30~50%の妊婦さんが、一過性の軽い抑うつ状態である「マタニティーブルーズ」を発症します(※2)。
ここで無理をして症状が重症化すると、強い抑うつ状態が続く「産後うつ病」になる可能性もあります。
周囲への理解を求め、適度に肩の力を抜いて、育児や家事と向き合ってくださいね。
産後の床上げまでは無理をしない生活を
床上げを迎えるまでの約1ヶ月は、お産で疲れたママの体を回復させるために大切な期間です。
真面目で頑張り屋さんのママほど、つい無理をしてしまいがちですが、この時期は周囲の助けを借りて体を休ませることに集中してください。そして、少しずつ体を動かして日常生活に戻っていきましょう。
旦那さんや家族に協力をお願いできない場合は、「産後ケアセンター」を利用するのも一つの方法です。
最近では、家事支援やホームヘルパーなど、産後の日常生活をサポートしてくれる様々なサービスがあるので、積極的に利用してください。
また、産後ダイエットを始めたいと思う人も多いと思いますが、床上げの時期は体調回復を優先しましょう。
 | 価格:1,999円 |
※1 日本産科婦人科学会『産科婦人科用語集・用語解説集 改訂第3版』p.196
※2 株式会社メディックメディア『病気がみえるvol.10 産科 第3版』p.369
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8198586
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック