2018年08月23日
妊婦健診は何回?費用や内容は?
妊娠が判明すると、産婦人科や助産院で定期的に妊婦健診(検診)を受けるようになります。初産婦さんだと、「どれくらいのペースで、どんなことをするのかな?」と知らないことも多いのではないでしょうか。そこで妊娠したときに知っておきたい妊婦健診(検診)の目的や頻度・回数、内容、費用についてご説明します。
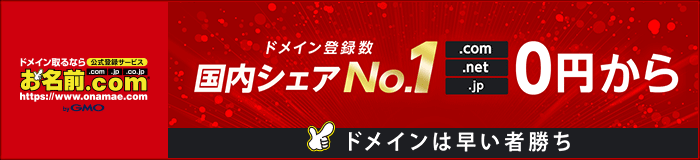

妊婦健診(検診)の目的とは?
妊婦健診とは、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に見るためのものです。妊婦健診には以下のような目的があり、きちんと受けることでより安全な出産へとつながります(※1)。
妊娠に伴う心身の変化に適応できているか、母体の健康状態を確認する
胎児が元気に成長しているか、異常がないか確認する
子宮収縮や子宮口の状態から分娩時期を予想する
妊娠中に発症しやすい合併症の予防
どのような方法で分娩するのか決める
リスクの高い妊娠を早期に発見する
妊婦さんが抱えている不安や悩みの相談にのる
妊娠中の過ごし方についてアドバイスする
妊婦健診(検診)の頻度や回数は?
厚生労働省は妊婦健診の標準的な回数を14回として、次のようなスケジュール例を示しています(※2)。
妊娠初期~23週 :合計4回(4週間に1回)
妊娠24~35週 :合計6回(2週間に1回)
妊娠36週~出産 :合計4回(1週間に1回)
これはあくまで一つの目安であり、病院によっては妊娠23週目まで2週間に1回の頻度だったり、初産かどうかや妊娠した年齢などによって妊婦健診の頻度が変わったりすることがあります。
回数を知りたいときは、かかりつけの病院に確認するようにしましょう。


妊婦健診(検診)の内容は?
妊婦健診ではいつも同じ検査をするというわけではなく、時期や健康状態によって検査内容は変わってきます。一般的な妊婦健診の内容は、次の通りです。
毎回行う検査
問診
体調や妊娠経過について医師から質問されます。妊娠中の体重管理について、アドバイスをもらうこともあります。
妊娠に関することで疑問や心配があるときは、問診時に相談してみましょう。
超音波ドップラー検査
超音波ドップラー装置を使って、赤ちゃんの心拍数や健康状態を調べます。元気な赤ちゃんの心拍数の目安は、妊娠末期で1分間に110~160です(※3)。
尿検査
尿中に尿たんぱくや尿糖が出ているかを検査して、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病のリスクがあるかどうかをみます(※3)。
体重測定
妊娠による体重の増加や、つわりによる体重の減少がリスクのない範囲かをみます。必要以上に体重が増えると、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病、難産になりやすくなってしまいます。
体重の増加は、1週間あたり300~500gが目安とされています。痩せ型の人は妊娠期を通じて9~12kg、標準体型の人は7~12kgの増加が理想です(※4)。


血圧測定
妊婦さんの血圧を測定して、正常な範囲内にあるかを調べます。妊娠20週以降に最高血圧が140mmHg以上、最低血圧が90mmHg以上だと、妊娠高血圧症候群の可能性があります(※3)。
外診
妊婦さんのお腹を触って、おなかの張り(子宮の固さ)や赤ちゃんの位置や向きなどを調べます。


妊娠4ヶ月以降に毎回行う検査
腹囲測定
妊婦さんの体重増加具合や、赤ちゃんの成長度をチェックするため、メジャーでお腹の周囲を測定します。
浮腫検査
妊婦さんの体にむくみ(浮腫)が出ているか検査するため、足のすねを押し、そのへこみ具合をみます。むくみがひどいときは妊娠高血圧症候群の可能性が考えられます(※4)。


妊娠中期以降に毎回行う検査
子宮底長測定
恥骨の上から子宮の一番上までの長さである子宮底長を測定し、赤ちゃんの発育が順調に進んでいるかや、羊水がどれくらいあるかをチェックします。
必要に応じて行う検査
内診
腟のなかに指を入れて、子宮の状態をみます。妊娠初期は子宮のサイズや位置、硬さを、出産予定日の近くになると子宮口がどのくらい開いているいるかなどを確認します。
血液検査
血液検査では血糖やB型肝炎抗原、HIV抗体、風疹ウイルス抗体などを調べて、妊婦さんや赤ちゃんが健康な状態なのかや、病気になっていないかをチェックします。
超音波検査
超音波断層撮影装置を使って、胎嚢や胎盤の位置、羊水の量、赤ちゃんの発育状態などさまざまなことをみます。
子宮頸がん検診
妊娠初期に行われる可能性がある子宮頸がん検診は、ヘラやブラシで子宮頸部の粘膜を軽くこすり細胞を採取して、がん細胞や異形成の有無をチェックします。
子宮頸がんにかかっていたとしても妊娠を継続できる可能性はありますが、放置しておくと母体の命が危険にさらされることもあるため、できるだけ早めに発見して対処することが肝心です(※4)。
クラミジア検査
クラミジアとは、性器クラミジア感染症を引き起こす細菌のことです。腟内に綿棒のようなものを入れて子宮頸管の表皮細胞を取り出すクラミジア検査は、必要に応じて妊娠30週までに行われ、クラミジア感染の有無を調べます(※3)。
クラミジアが進行すると、絨毛膜羊膜炎や子宮頸管炎が起こったり、最悪の場合流産や早産に至ったりするリスクが生じます。
また、出産時に新生児が産道感染して、結膜炎や肺炎を引き起こす恐れもあるので、早期に発見して治療してもらいましょう(※4)。
GBSチェック
GBSとは、B群溶血性レンサ球菌という細菌のことで、出産時に赤ちゃんが産道感染すると、新生児GBS感染症という疾患になる恐れがあります。
GBSチェックは綿棒でおりものを採取してGBSがいるかどうかを調べる検査で、妊娠33~37週の期間に必要に応じて行われます(※3)。
NST
NSTとは「ノンストレステスト」の略称で、子宮に緊縮を加えない状態で赤ちゃんの心拍数を確認し、赤ちゃんが元気かどうかを調べる検査です。
妊娠期間が満42週を超えた過期妊娠や、ハイリスク妊娠(高齢妊娠や多胎妊娠、妊娠高血圧症など)の妊婦さん向けに妊娠30週前後~出産までに行うことが一般的です(※4)。


妊婦健診(検診)の費用は?補助券が使える?
妊婦健診は健康保険が適用されないので、基本検査で約3,000~7,000円程度、血液検査などの特別な検査を行った場合は約1万~1万5000円の費用がかかります。
全部で14回あった場合は約10~15万円かかる計算になりますが、補助金で助成されるので自己負担額はこれより低くなります。
母子手帳と一緒に交付される「妊婦健康診査受診票」、いわゆる「補助券(助成券)」によって、妊婦健診の費用が助成されます。自治体によって助成内容や費用は異なるので、交付の際に助成内容を教えてもらうようにしましょう。
補助券を使えない検査もあり、約3~7万円程度は費用を自己負担した人が多いようです。


妊婦健診(検診)は妊婦さんと赤ちゃんを守る大事なもの
妊娠初期のつわりで体調が優れないときや、妊娠後期でお腹が大きくなって動くのがおっくうなときは、妊婦健診に行くのが面倒くさいと感じることもあるかもしれません。
しかし、妊婦健診は妊婦さんと赤ちゃんの健康状態をチェックし、トラブルを未然に防ぐ大切なものです。
妊婦健診は赤ちゃんの成長を感じられる機会だと前向きに捉え、きちんと定期的に受けるようにしましょう。
※1 日本産科婦人科学会 日産婦誌59巻11号『妊婦健診』
※2 厚生労働省 妊婦健診Q&A
※3 メジカルビュー社『プリンシプル 産科婦人科学2 産科編』pp.247,321,407-410
※4 株式会社メディックメディア『病気がみえるvol.10 産科 第3版』pp.47,66,76-78,98,186,218-219
妊婦健診(検診)の目的とは?
妊婦健診とは、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に見るためのものです。妊婦健診には以下のような目的があり、きちんと受けることでより安全な出産へとつながります(※1)。
妊娠に伴う心身の変化に適応できているか、母体の健康状態を確認する
胎児が元気に成長しているか、異常がないか確認する
子宮収縮や子宮口の状態から分娩時期を予想する
妊娠中に発症しやすい合併症の予防
どのような方法で分娩するのか決める
リスクの高い妊娠を早期に発見する
妊婦さんが抱えている不安や悩みの相談にのる
妊娠中の過ごし方についてアドバイスする
妊婦健診(検診)の頻度や回数は?
厚生労働省は妊婦健診の標準的な回数を14回として、次のようなスケジュール例を示しています(※2)。
妊娠初期~23週 :合計4回(4週間に1回)
妊娠24~35週 :合計6回(2週間に1回)
妊娠36週~出産 :合計4回(1週間に1回)
これはあくまで一つの目安であり、病院によっては妊娠23週目まで2週間に1回の頻度だったり、初産かどうかや妊娠した年齢などによって妊婦健診の頻度が変わったりすることがあります。
回数を知りたいときは、かかりつけの病院に確認するようにしましょう。
妊婦健診(検診)の内容は?
妊婦健診ではいつも同じ検査をするというわけではなく、時期や健康状態によって検査内容は変わってきます。一般的な妊婦健診の内容は、次の通りです。
毎回行う検査
問診
体調や妊娠経過について医師から質問されます。妊娠中の体重管理について、アドバイスをもらうこともあります。
妊娠に関することで疑問や心配があるときは、問診時に相談してみましょう。
超音波ドップラー検査
超音波ドップラー装置を使って、赤ちゃんの心拍数や健康状態を調べます。元気な赤ちゃんの心拍数の目安は、妊娠末期で1分間に110~160です(※3)。
尿検査
尿中に尿たんぱくや尿糖が出ているかを検査して、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病のリスクがあるかどうかをみます(※3)。
体重測定
妊娠による体重の増加や、つわりによる体重の減少がリスクのない範囲かをみます。必要以上に体重が増えると、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病、難産になりやすくなってしまいます。
体重の増加は、1週間あたり300~500gが目安とされています。痩せ型の人は妊娠期を通じて9~12kg、標準体型の人は7~12kgの増加が理想です(※4)。
血圧測定
妊婦さんの血圧を測定して、正常な範囲内にあるかを調べます。妊娠20週以降に最高血圧が140mmHg以上、最低血圧が90mmHg以上だと、妊娠高血圧症候群の可能性があります(※3)。
外診
妊婦さんのお腹を触って、おなかの張り(子宮の固さ)や赤ちゃんの位置や向きなどを調べます。
妊娠4ヶ月以降に毎回行う検査
腹囲測定
妊婦さんの体重増加具合や、赤ちゃんの成長度をチェックするため、メジャーでお腹の周囲を測定します。
浮腫検査
妊婦さんの体にむくみ(浮腫)が出ているか検査するため、足のすねを押し、そのへこみ具合をみます。むくみがひどいときは妊娠高血圧症候群の可能性が考えられます(※4)。
妊娠中期以降に毎回行う検査
子宮底長測定
恥骨の上から子宮の一番上までの長さである子宮底長を測定し、赤ちゃんの発育が順調に進んでいるかや、羊水がどれくらいあるかをチェックします。
必要に応じて行う検査
内診
腟のなかに指を入れて、子宮の状態をみます。妊娠初期は子宮のサイズや位置、硬さを、出産予定日の近くになると子宮口がどのくらい開いているいるかなどを確認します。
血液検査
血液検査では血糖やB型肝炎抗原、HIV抗体、風疹ウイルス抗体などを調べて、妊婦さんや赤ちゃんが健康な状態なのかや、病気になっていないかをチェックします。
超音波検査
超音波断層撮影装置を使って、胎嚢や胎盤の位置、羊水の量、赤ちゃんの発育状態などさまざまなことをみます。
子宮頸がん検診
妊娠初期に行われる可能性がある子宮頸がん検診は、ヘラやブラシで子宮頸部の粘膜を軽くこすり細胞を採取して、がん細胞や異形成の有無をチェックします。
子宮頸がんにかかっていたとしても妊娠を継続できる可能性はありますが、放置しておくと母体の命が危険にさらされることもあるため、できるだけ早めに発見して対処することが肝心です(※4)。
クラミジア検査
クラミジアとは、性器クラミジア感染症を引き起こす細菌のことです。腟内に綿棒のようなものを入れて子宮頸管の表皮細胞を取り出すクラミジア検査は、必要に応じて妊娠30週までに行われ、クラミジア感染の有無を調べます(※3)。
クラミジアが進行すると、絨毛膜羊膜炎や子宮頸管炎が起こったり、最悪の場合流産や早産に至ったりするリスクが生じます。
また、出産時に新生児が産道感染して、結膜炎や肺炎を引き起こす恐れもあるので、早期に発見して治療してもらいましょう(※4)。
GBSチェック
GBSとは、B群溶血性レンサ球菌という細菌のことで、出産時に赤ちゃんが産道感染すると、新生児GBS感染症という疾患になる恐れがあります。
GBSチェックは綿棒でおりものを採取してGBSがいるかどうかを調べる検査で、妊娠33~37週の期間に必要に応じて行われます(※3)。
NST
NSTとは「ノンストレステスト」の略称で、子宮に緊縮を加えない状態で赤ちゃんの心拍数を確認し、赤ちゃんが元気かどうかを調べる検査です。
妊娠期間が満42週を超えた過期妊娠や、ハイリスク妊娠(高齢妊娠や多胎妊娠、妊娠高血圧症など)の妊婦さん向けに妊娠30週前後~出産までに行うことが一般的です(※4)。
妊婦健診(検診)の費用は?補助券が使える?
妊婦健診は健康保険が適用されないので、基本検査で約3,000~7,000円程度、血液検査などの特別な検査を行った場合は約1万~1万5000円の費用がかかります。
全部で14回あった場合は約10~15万円かかる計算になりますが、補助金で助成されるので自己負担額はこれより低くなります。
母子手帳と一緒に交付される「妊婦健康診査受診票」、いわゆる「補助券(助成券)」によって、妊婦健診の費用が助成されます。自治体によって助成内容や費用は異なるので、交付の際に助成内容を教えてもらうようにしましょう。
補助券を使えない検査もあり、約3~7万円程度は費用を自己負担した人が多いようです。
妊婦健診(検診)は妊婦さんと赤ちゃんを守る大事なもの
妊娠初期のつわりで体調が優れないときや、妊娠後期でお腹が大きくなって動くのがおっくうなときは、妊婦健診に行くのが面倒くさいと感じることもあるかもしれません。
しかし、妊婦健診は妊婦さんと赤ちゃんの健康状態をチェックし、トラブルを未然に防ぐ大切なものです。
妊婦健診は赤ちゃんの成長を感じられる機会だと前向きに捉え、きちんと定期的に受けるようにしましょう。
※1 日本産科婦人科学会 日産婦誌59巻11号『妊婦健診』
※2 厚生労働省 妊婦健診Q&A
※3 メジカルビュー社『プリンシプル 産科婦人科学2 産科編』pp.247,321,407-410
※4 株式会社メディックメディア『病気がみえるvol.10 産科 第3版』pp.47,66,76-78,98,186,218-219
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/7980564
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック