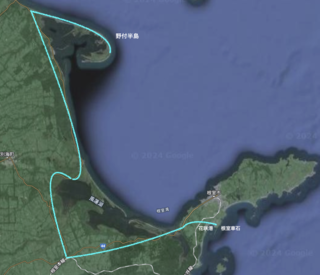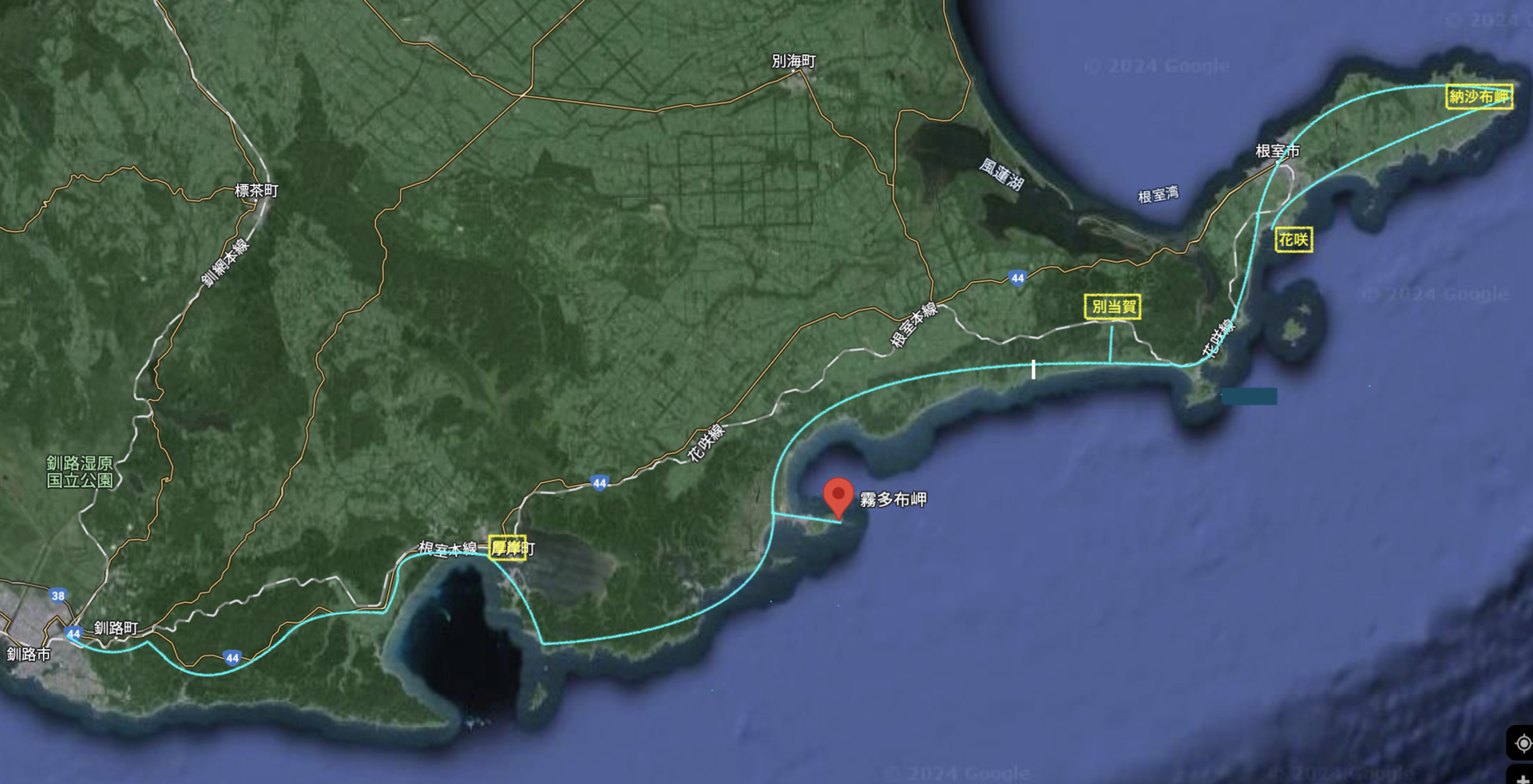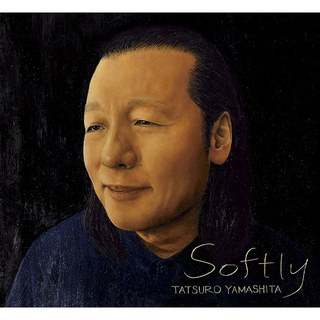いきなりですが、ボクはクィーンが好きではありません。
だから、これだけ話題になっているボヘミアンラプソディを観に行くこともしていません。
本来好きじゃないものあーだこーだ言っても、誰に対してもましてや自分にとっても何のプラスにはならないことは分かってます。
でも、毎日の様にマスコミやネットからは賞賛の嵐しか聞こえていないことにちょっとした違和感を覚えます。また普段からボクがポピュラー音楽好きだって認識が周囲の人に有って、その人達からもマキノさんボヘミアンラプソディ観ました?なんて聞かれます。なのでこの際自分のクイーンに対する持論を明らかにしておこう(大げさか!?)と思ったのであります。
しかしボヘミアンラプソディ観ないでは何も言えません。だからと言ってその為にわざわざ映画館行ってなんてプライドが許しません(これもっと大げさ)。
ところが、ちょうどこのタイミングで海外旅行で長時間フライト乗るのでボヘミアンきっとやってるよ、これだったら自発的じゃないから収まりつくよね、なんて元来ひねくれ者のボクならではのソリューション(笑)
今回訳あってロサンジェルスに9年ぶりに行くことになりました。ノースウエストの時代から集めていたデルタ航空のマイレージがかなり貯まっていたので、ビジネスクラスでのフリートリップ。
今まで何度かマイル使用のアップグレードや、安売りチケット、ラッキーアップグレードでビジネスクラス乗った事ありましたが、180°フルフラットシートのビジネスクラスはお初でした。でフライト中、食事しながら、その後は寝っ転がって観ましたよ、ボヘミアンラプソディ。

和食を事前予約してたけど、ちょっと期待はずれだったかな。


で、結論から言うと映画はほぼ予想通りの内容でした。というより賞賛を送っていた誰しもが言っていた『ラスト20分は涙を抑えきれない』は正直言って「感動」って程のもんじゃなかったかな?悪くは無かったけどね。
こう感じるのも、自分のクイーンに対する先入観がそうさせていると批判されることは否定はしません。でも正直もっとフレディマーキュリーの「死」に対する恐怖感、メンバーとの軋轢に打ち勝って、などがもっと劇的に強調されているのかな?なんて思ってたのでちょっと拍子抜けした感がありました。
今回、自分が読んだ論評でこの映画を賞賛している人はおしなべて自分より年下です。リアルタイムで聴いてた人ってお目にかかってないし、ましてやこの映画のハイライト『ライブエイド』の際はまだ生まれていなかった、なんて人かなりいます。
実は、クィーンに対する好き嫌いというのは、その人の年齢がとても重要なファクターになっているのです。
自分の話をするとクィーンがデビューして日本で初めて紹介されたのは1973年のアルバム『戦慄の王女』と記憶しています。
毎号欠かさず愛読していたMUSIC LIFE誌のアルバム評でいきなり最高評価の5つ星がつけられ、いったいどんな奴らなんだろう?と思ったのが最初でした。
この1973年って言うのは、レッドツェッペリン、ディープバープル、ユーライヤヒープ、マウンテンと言ったハードロック、そしてピンクフロイド、イエス、キングクリムゾン、ELPなのどのプログレッシブロック、更にはシカゴに代表されるブラスロック、サンタナのラテンロック、ドゥービーやイーグルスのウエストコーストロックなどなど、ロックは男の子が「肩肘」張りながら、また欲望のはけ口として、更には音楽論を戦わせながら聞く硬派ロックバンド全盛の時代まっただ中でありました。
そこに登場したクィーンでしたが、MISIC LIFE誌の当時の編集長東郷かおる子女史が彼等をアイドルスター的扱いで毎号特集を組み、表紙にも多く登場させたため、ロックファンの男の子から疎ましく思われたと言うか、反感買ったのが事実でありました。東郷編集長としては、クィーンを日本からスターにしたいという意気込みが強く、特に女の子を中心に実際世界に先駆けて日本でその人気がブレイクしたという実績が残ったのは事実であります。その一方で硬派のロックファンはクィーンをきっかけとして同誌を去っていったんじゃないかと想像します。

ところでこの時代以前からMUSIC LIFEの表4(裏表紙)の広告は、毎号必ずグレコというエレキギターの広告が掲載されていました。
クィーンが同誌の扱いで他のミュージシャン、グループを露出量的に圧倒していた頃、グレコギターは、ブライアン メイのレプリカギターを発売。(あの赤いギターですね)その広告が裏表紙に掲載されました。

その際のキャッチコピーはそれから45年近く経た今でもハッキリ記憶しています。「クィーンは嫌いでもこのギターのことは気になります」
これこそが正にこの時代のロック少年の気持ちを代弁していたのです。
じゃあ、この時代の多くの「ロック少年」は何故クィーンを嫌ったのでしょうか?
先に述べたアイドル的要素は別として、ロックミュージックとして表現が大仰すぎる(プログレはもっと大仰といえば大仰でしたがより様式美に拘っていた)、ロックミュージックの大きな根源であるブルース的要素があまり無い、ボーカルにしろギターにしろ音が前へ前へでてきて抑制が効いていない、歌い方がロックンロールじゃないなどなど。
それらを総称して10代のころのマキノ少年はこう表現しておりました。「クィーンの音楽は音の洪水である」今回映画を観てみて、あ、あの曲意外とシンプルなアレンジだったんだな?なんて思った曲もありましたが、ミキシングのせいか実際より多くの音が洪水がごとくこっちに押し寄せ、目の前で鳴っている事で その様に印象づけられたのだと思います。
ところが、クィーンから洋楽聞き始めた自分より5〜6才以上年齢下の男の子たちにとってすれば、クイーンの『劇的かつ前へ前へ突進する音作り』それが彼等にとってロックミュージックのデフォルトになっているんでしょう、きっと。
だからセンター手前にイアンギランが、右からブラックモアのギターが、左からジョンロードのハモンドが、後ろに定位があるイアンペイスのシンコペーションに乗って奏でられても、物足りなく感じちゃうのかな?なんて思ってます。
ちなみに山下達郎サンデーソングブックでは、その26年の歴史の中でいまだかつて一度もクィーンかかった事ありません。
【このカテゴリーの最新記事】