新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2021年07月13日
映画「ダイヤルMを廻せ!」− 予期せぬ誤算, 犯人の側からみた推理劇
「ダイヤルMを廻せ!」(Dial M for Murder)
1954年 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
原作・脚本フレデリック・ノット
撮影ロバート・バークス
音楽ディミトリ・ティオムキン
〈キャスト〉
レイ・ミランド グレース・ケリー
ジョン・ウィリアムズ ロバート・カミングス
ハリウッドへ渡ったヒッチコックの18本目の監督作品で、イギリス時代の監督デビューからを含めれば43本目となる作品。

かなり余裕を持って作られた印象が強く、殺人を扱ったミステリーというよりは、犯人の側に立って事件を追いかけてゆく倒叙形式を取っており、後年の傑作TVシリーズ「刑事コロンボ」と同じく、周到に組み立てられた犯行を暴き、どうやって犯人を追い詰めてゆくのかが見どころ。




元プロテニスのスター選手であるトニー・ウェンディス(レイ・ミランド)はテニス界を引退して地道に働き出したが、金銭的には思うようにいかない。
妻のマーゴ(グレース・ケリー)は、かつて夫がテニスのツアー中に留守になる寂しさから、推理作家のマーク・ハリディと不倫の関係になり、トニーとは義理にキスは交わしても冷めた気持ちは変わらず、離婚を持ち出そうと考えています。
トニーは妻とマークの関係を薄々知っており、離婚話が持ち出されて自分が妻と別れた場合、資産家の娘で、現在も妻の財産で生活をしているような自分は、マーゴと離婚した途端、生活の破綻は目にみえています。
もし、マーゴが誰かに殺されるようなことがあれば、妻の財産はすべて自分のものになる。
自動車を売りに出しているスワン(アンソニー・ドーソン)はある日、車を買いたいという電話を受けてトニーのアパートへ。
待っていたトニーは、スワンを部屋へ招き入れ、スワンがかつての大学の先輩だったことを初めて知るが、これはあらかじめトニーが書いた筋書きで、初めて気づいたように見せかけて実は、大学時代におけるスワンの悪癖や、その後の女性関係から起きた金銭トラブルについて、スワンの人となりをすべて調べ上げていた。
過去の事情を洗いざらい話し出すトニーの態度にいぶかしさを感じ始めたスワンに、トニーは穏やかに、報酬1000ポンドで妻の殺害に手を貸してほしいと持ちかける。
そんなことはできないと撥(は)ねつけるスワン。しかし用意周到なトニーは、室内に残ったスワンの指紋をたてに、マーゴ殺害の実行をスワンに請け負わせることに成功。
マーゴ殺害計画のその夜、マーゴをひとりで部屋に残すため、マークと連れ立ってパーティーに出かけたトニーは、スワンが部屋の鍵を使って忍び込み、机の奥のカーテンの陰に隠れて、トニーが電話を掛ける手はずになっている11時には少し間があることを腕時計で確認。
しかし、再び確認した時間は少しも動いておらず、時計が止まっていることを知って、慌ててロビーの公衆電話へ。

部屋の電話が鳴り、ベッドから起き上がったマーゴが机の上の受話器を手に取っている隙に、カーテンの陰に隠れたスワンはストッキングを手に、マーゴを絞殺する一瞬の隙をうかがい、首に巻き付けたストッキングでマーゴの首を締め上げるが、そこに思わぬ誤算が…。




とても面白く、よくできた映画なのだけど、どうしてこうなるのだろうという疑問を一つ。
マーゴ殺害計画の現場。
スワンがストッキングをマーゴの首に巻き付け、締め上げる。マーゴは机の上にのけ反り、苦しみながらも机の上のハサミをつかむと、スワンの背中へグサッと一突き。
驚きと激痛の表情を浮かべながら、そのまま仰向けに床に倒れたスワン。背中のハサミを突き立てているため、そのままズブズブとハサミはスワンの背中に突き通ってスワンは絶命。
首を絞められて喘いでいる女性が、コートを着ている男の背中へハサミを突き立てられるものなのだろうか。
しかもスワンは、コートの下は背広、もちろんその下にはシャツや下着を着けているわけで、夏の暑い盛りにTシャツ一枚の体へハサミを突き立てるというのならともかく、それが鋭利なハサミであったとしてもコートの上から、というのはどうなのかな。
しかもスワンは、ハサミが突き通りやすいように都合よく仰向けに倒れている。素直に考えれば、背中に異物が突き刺さっている場合、うつ伏せに倒れるのが普通ではなかろうか。
それに、スワンの死因はなんなのだろう。
出血は少しなので、出血による死亡でもない。背中から心臓までハサミが通ったとも思えないし、このあたりは適当に誤魔化されてしまった感じで、ヒッチコックともあろう人が、どうしてこんな不自然なシーンで落ち着いてしまったのだろう。




疑問は疑問として置いといて。
トニーとマーゴのキスシーンで始まるこの映画は、くちびるを話してからの二人の態度がヘンによそよそしく、夫婦の間があまりうまくいっていないことを思わせながらも、体裁上は、二人が円満な夫婦を演じていることを匂わせているうまい導入部。
やがて、マーゴの不倫の発覚と、それに気づいたトニーのマーゴへの脅迫の手紙などが明るみに出始め、マーゴ殺害計画へと話が移っていきます。
しかし最大の誤算は、マーゴが殺されずに、逆に実行犯のスワンがマーゴによって殺されてしまったことで、話の展開が読めなくなってしまう。
「ダイヤルMを廻せ!」の面白さはここからで、冷静に事態に対処しようとするトニーは、素早くマーゴに罪を着せようと考え、そのための工作を始めます。
スワンが使ったストッキングを暖炉で燃やし、代わりにマーゴのストッキングを机の上にそれとなく隠して置き、マーゴの不倫相手マークの手紙をスワンのポケットに忍ばせる。
トニーの一連の行動は、ゲームを楽しんでいるようにも見え、実際、事件に乗り出したハバード警部(ジョン・ウィリアムズ)によってトニーの計画が崩れ去ったのち、犯人のトニーは、マーク、マーゴ、ハバード警部たちに、お酒でもどうだい、と言っているのですから、チェスでも楽しんで、自分の敗北を認めた対局者の余裕すら見せています。




主演のトニーに、「失われた週末」(1945年)でアカデミー賞主演男優賞、カンヌ国際映画祭男優賞、ゴールデングローブ賞男優賞を受賞したレイ・ミランド。
妻マーゴに、「真昼の決闘」(1952年)で注目を集めたグレース・ケリー。
美貌と知性と気品をあわせ持った稀有な女優で、その後、ヒッチコック作品には「裏窓」「泥棒成金」(1955年)と立て続けに出演。
モナコ公国の大公レーニエ3世に見初められて1956年に結婚。モナコ公妃となりましたが、1982年に脳梗塞による自動車事故で亡くなっています。
「ダイヤルMを廻せ!」は、下手をすれば地味な映画になってしまうところで、それを救っているのがグレース・ケリーの華やかな魅力といってもいいと思います。

マーゴの不倫相手で推理作家のマーク・ハリディに、「逃走迷路」(1942年)以来、12年ぶりのヒッチコック作品となるロバート・カミングス。
マーゴを殺すはずが、逆に殺されてしまう不運な実行犯のスワンに、「007/ドクター・ノオ」(1962年)、「レッド・サン」(1971年)、「バラキ」(1972年)で悪役として活躍したアンソニー・ドーソン。




事件の鍵となるのが、文字通りの“鍵”で、犯人しか知るはずのない場所に鍵が置かれていたことからトニーの犯行が暴かれるラストは推理ドラマの真骨頂。
続けて撮った「裏窓」と同じく、ほとんどが部屋の中での展開で、それだけに、ストーリーのテンポの良さや、「見知らぬ乗客」以降ヒッチコック作品の常連となったロバート・バークスによる撮影、また、登場人物の性格設定なども見ていて楽しく、特に、英国紳士然としたハバード警部の登場などは、ディクスン・カーやF・W・クロフツの小説に出てくるスコットランドヤードの警部といった風情で、口ひげをひねりながら思索にふける、茫洋とした姿は味わい深いものがありました。





1954年 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
原作・脚本フレデリック・ノット
撮影ロバート・バークス
音楽ディミトリ・ティオムキン
〈キャスト〉
レイ・ミランド グレース・ケリー
ジョン・ウィリアムズ ロバート・カミングス
ハリウッドへ渡ったヒッチコックの18本目の監督作品で、イギリス時代の監督デビューからを含めれば43本目となる作品。

かなり余裕を持って作られた印象が強く、殺人を扱ったミステリーというよりは、犯人の側に立って事件を追いかけてゆく倒叙形式を取っており、後年の傑作TVシリーズ「刑事コロンボ」と同じく、周到に組み立てられた犯行を暴き、どうやって犯人を追い詰めてゆくのかが見どころ。
元プロテニスのスター選手であるトニー・ウェンディス(レイ・ミランド)はテニス界を引退して地道に働き出したが、金銭的には思うようにいかない。
妻のマーゴ(グレース・ケリー)は、かつて夫がテニスのツアー中に留守になる寂しさから、推理作家のマーク・ハリディと不倫の関係になり、トニーとは義理にキスは交わしても冷めた気持ちは変わらず、離婚を持ち出そうと考えています。
トニーは妻とマークの関係を薄々知っており、離婚話が持ち出されて自分が妻と別れた場合、資産家の娘で、現在も妻の財産で生活をしているような自分は、マーゴと離婚した途端、生活の破綻は目にみえています。
もし、マーゴが誰かに殺されるようなことがあれば、妻の財産はすべて自分のものになる。
自動車を売りに出しているスワン(アンソニー・ドーソン)はある日、車を買いたいという電話を受けてトニーのアパートへ。
待っていたトニーは、スワンを部屋へ招き入れ、スワンがかつての大学の先輩だったことを初めて知るが、これはあらかじめトニーが書いた筋書きで、初めて気づいたように見せかけて実は、大学時代におけるスワンの悪癖や、その後の女性関係から起きた金銭トラブルについて、スワンの人となりをすべて調べ上げていた。
過去の事情を洗いざらい話し出すトニーの態度にいぶかしさを感じ始めたスワンに、トニーは穏やかに、報酬1000ポンドで妻の殺害に手を貸してほしいと持ちかける。
そんなことはできないと撥(は)ねつけるスワン。しかし用意周到なトニーは、室内に残ったスワンの指紋をたてに、マーゴ殺害の実行をスワンに請け負わせることに成功。
マーゴ殺害計画のその夜、マーゴをひとりで部屋に残すため、マークと連れ立ってパーティーに出かけたトニーは、スワンが部屋の鍵を使って忍び込み、机の奥のカーテンの陰に隠れて、トニーが電話を掛ける手はずになっている11時には少し間があることを腕時計で確認。
しかし、再び確認した時間は少しも動いておらず、時計が止まっていることを知って、慌ててロビーの公衆電話へ。

部屋の電話が鳴り、ベッドから起き上がったマーゴが机の上の受話器を手に取っている隙に、カーテンの陰に隠れたスワンはストッキングを手に、マーゴを絞殺する一瞬の隙をうかがい、首に巻き付けたストッキングでマーゴの首を締め上げるが、そこに思わぬ誤算が…。
とても面白く、よくできた映画なのだけど、どうしてこうなるのだろうという疑問を一つ。
マーゴ殺害計画の現場。
スワンがストッキングをマーゴの首に巻き付け、締め上げる。マーゴは机の上にのけ反り、苦しみながらも机の上のハサミをつかむと、スワンの背中へグサッと一突き。
驚きと激痛の表情を浮かべながら、そのまま仰向けに床に倒れたスワン。背中のハサミを突き立てているため、そのままズブズブとハサミはスワンの背中に突き通ってスワンは絶命。
首を絞められて喘いでいる女性が、コートを着ている男の背中へハサミを突き立てられるものなのだろうか。
しかもスワンは、コートの下は背広、もちろんその下にはシャツや下着を着けているわけで、夏の暑い盛りにTシャツ一枚の体へハサミを突き立てるというのならともかく、それが鋭利なハサミであったとしてもコートの上から、というのはどうなのかな。
しかもスワンは、ハサミが突き通りやすいように都合よく仰向けに倒れている。素直に考えれば、背中に異物が突き刺さっている場合、うつ伏せに倒れるのが普通ではなかろうか。
それに、スワンの死因はなんなのだろう。
出血は少しなので、出血による死亡でもない。背中から心臓までハサミが通ったとも思えないし、このあたりは適当に誤魔化されてしまった感じで、ヒッチコックともあろう人が、どうしてこんな不自然なシーンで落ち着いてしまったのだろう。
疑問は疑問として置いといて。
トニーとマーゴのキスシーンで始まるこの映画は、くちびるを話してからの二人の態度がヘンによそよそしく、夫婦の間があまりうまくいっていないことを思わせながらも、体裁上は、二人が円満な夫婦を演じていることを匂わせているうまい導入部。
やがて、マーゴの不倫の発覚と、それに気づいたトニーのマーゴへの脅迫の手紙などが明るみに出始め、マーゴ殺害計画へと話が移っていきます。
しかし最大の誤算は、マーゴが殺されずに、逆に実行犯のスワンがマーゴによって殺されてしまったことで、話の展開が読めなくなってしまう。
「ダイヤルMを廻せ!」の面白さはここからで、冷静に事態に対処しようとするトニーは、素早くマーゴに罪を着せようと考え、そのための工作を始めます。
スワンが使ったストッキングを暖炉で燃やし、代わりにマーゴのストッキングを机の上にそれとなく隠して置き、マーゴの不倫相手マークの手紙をスワンのポケットに忍ばせる。
トニーの一連の行動は、ゲームを楽しんでいるようにも見え、実際、事件に乗り出したハバード警部(ジョン・ウィリアムズ)によってトニーの計画が崩れ去ったのち、犯人のトニーは、マーク、マーゴ、ハバード警部たちに、お酒でもどうだい、と言っているのですから、チェスでも楽しんで、自分の敗北を認めた対局者の余裕すら見せています。
主演のトニーに、「失われた週末」(1945年)でアカデミー賞主演男優賞、カンヌ国際映画祭男優賞、ゴールデングローブ賞男優賞を受賞したレイ・ミランド。
妻マーゴに、「真昼の決闘」(1952年)で注目を集めたグレース・ケリー。
美貌と知性と気品をあわせ持った稀有な女優で、その後、ヒッチコック作品には「裏窓」「泥棒成金」(1955年)と立て続けに出演。
モナコ公国の大公レーニエ3世に見初められて1956年に結婚。モナコ公妃となりましたが、1982年に脳梗塞による自動車事故で亡くなっています。
「ダイヤルMを廻せ!」は、下手をすれば地味な映画になってしまうところで、それを救っているのがグレース・ケリーの華やかな魅力といってもいいと思います。

マーゴの不倫相手で推理作家のマーク・ハリディに、「逃走迷路」(1942年)以来、12年ぶりのヒッチコック作品となるロバート・カミングス。
マーゴを殺すはずが、逆に殺されてしまう不運な実行犯のスワンに、「007/ドクター・ノオ」(1962年)、「レッド・サン」(1971年)、「バラキ」(1972年)で悪役として活躍したアンソニー・ドーソン。
事件の鍵となるのが、文字通りの“鍵”で、犯人しか知るはずのない場所に鍵が置かれていたことからトニーの犯行が暴かれるラストは推理ドラマの真骨頂。
続けて撮った「裏窓」と同じく、ほとんどが部屋の中での展開で、それだけに、ストーリーのテンポの良さや、「見知らぬ乗客」以降ヒッチコック作品の常連となったロバート・バークスによる撮影、また、登場人物の性格設定なども見ていて楽しく、特に、英国紳士然としたハバード警部の登場などは、ディクスン・カーやF・W・クロフツの小説に出てくるスコットランドヤードの警部といった風情で、口ひげをひねりながら思索にふける、茫洋とした姿は味わい深いものがありました。

2021年07月09日
映画「間違えられた男」ー 平凡な市民が巻き込まれる冤罪という深い闇
「間違えられた男」(The Wrong Man )
1956年 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
原作・脚本マクスウェル・アンダーソン
音楽バーナード・ハーマン
撮影ロバート・バークス
〈キャスト〉
ヘンリー・フォンダ ヴェラ・マイルズ
アンソニー・クエイル
実際に起きた冤罪事件をもとに、事件に巻き込まれた男と、その家族の苦悩を描いたアルフレッド・ヒッチコックの傑作スリラー。

クリストファー・バレストレロ、愛称マニー(ヘンリー・フォンダ)は38歳。ベーシストとしてナイトクラブでの演奏が終わり、明け方に自宅へ戻ったマニーは玄関脇に置かれた牛乳を手に寝室へ向かいます。
眠っているはずの妻のローズは目覚めていて、歯が痛くて眠れないと言います。
歯の治療をさせてあげたいが、金銭的な余裕の無いマニーは、妻の掛けている保険で金が借りられるんじゃないかと思いつきます。
翌日、保険会社の支店に出向いたマニーは窓口で女性事務員に声をかけます。
保険証券を見せて、金を借りられないか、と尋ねるマニーの顔を見た事務員の表情がこわばり、少しお待ちを、と言って上司のデスクへ向かい、先日、拳銃を突き付けて強盗に入った男によく似ていることを告げます。
保険会社を後に、金の工面ができそうだと喜んで自宅へ戻ろうとしたマニーは、張り込んでいた刑事に玄関先で身柄を拘束され、警察署へ連行されてしまいます。
何がなんだか訳の分からないマニーは、妻が心配するから電話を、と言っても刑事は、心配は要らない、の一点張りで取り合わず、取調室での尋問が始まります。
自分が無実であることはマニー自身がよく知っていますから、落ち着いた態度で刑事の質問に答えようとしますが、目撃者の証言や、筆跡鑑定の結果などからマニーは不利な状況に追い込まれ、裁判所の手続きを経て、留置所へ入れられてしまいます。
一方、事件を知った妻のローズは、夫が無実であることを疑わず、弟と相談の上、7500ドルの保釈金を出してマニーを保釈します。

自由の身になったマニーは無実の罪を晴らそうと、弁護士のフランク・オコナー(アンソニー・クエイル)に相談。
マニーはアリバイを立証しようと、強盗が行われた日に旅行先で宿泊客たちとカードをしていた事実があることから、当時の宿泊客を探し出しますが、二人がすでに死亡。
アリバイの立証が絶望的になったことを引き金に、ローズの精神状態に異変が現れ始めます。




サスペンスやミステリー、スリラーなどを扱っても、ユーモアや娯楽性を盛り込むことを忘れないアルフレッド・ヒッチコックがここでは一転。身に覚えのない犯罪者として扱われた男の苦悩と、その妻が陥る暗黒に満ちた日常をリアルに描き出しています。
強盗犯人に似ているというだけで、ごく平凡な市民が犯罪者に仕立て上げられてしまう怖さ。
中でも一番の決め手となるのが筆跡鑑定で、犯人の残したメモを手掛かりに、犯人の書いた同じ文句を刑事が読み上げ、それをマニーが書くのですが、一度目はどうもハッキリしない。ところが二度目になると、マニーがスペルを間違えた。その間違え方が犯人の書いたものと同じであったという、あり得ないことが起こってしまう。

強盗に入られた店主たちも口をそろえて彼が犯人らしいと言う。
筆跡鑑定でも、犯人しか間違えようのないことをマニーがやってしまう。
あとは本人の自白になるのですが、もちろん自分は無実なのだから、自白できるはずがない。
この映画がかなり深刻性を帯びてくるのが、後半からの、妻のローズの精神状態。
マニーのアリバイを立証してもらえるはずの証人の二人はすでに死亡していると判り、そこからローズの様子がおかしくなっていきます。
この映画の怖さは、犯人に間違えられたマニーひとりの悲劇ではなく、当然ながら、その家族にも影響が及ぶということです。しかも、真犯人が捕まり、冤罪と認められたマニーは救われるとしても、ローズの精神障害はその後も長く残ってしまいます。
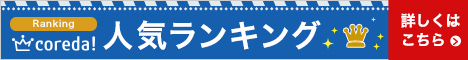

かつて江戸川乱歩も「D坂の殺人事件」だったかで、人間の記憶や視覚の頼りなさを書いていましたが、ここでは保険会社の事務員を含め、目撃者がマニーを犯人だと断定してしまっていることで、絶対的な思い込みがひとりの人間の運命を左右してしまう怖さ。
そしてそれは家族をも巻き込む悲劇につながってしまう。
このまま進めば、救いようのない映画になってしまうところでしたが、真犯人が強盗事件を起こしたことで、マニーの冤罪に結びつくことになります。




主人公マニーに「怒りの葡萄」(1940年)、「荒野の決闘」(1946年)、「ミスタア・ロバーツ」(1955年)など、巨匠ジョン・フォード作品でお馴染みの名優ヘンリー・フォンダ。
翌年の1957年に名作「十二人の怒れる男」での、他の陪審員全員が有罪とする中、物静かながら、粘り強く無罪判決へと導いてゆく陪審員を好演してアメリカの良心を表現しましたが、他方、その二年後の「ワーロック」(1959年)では貫禄十分の二丁拳銃の早撃ちガンマンに扮し、最後の決闘では保安官のリチャード・ウィドマークを圧倒しながら、拳銃を二丁とも捨てて静かに去ってゆくラストのカッコ良かったこと。
妻ローズに「捜索者」(1956年)のヴェラ・マイルズ。
後の「サイコ」(1960年)で再びヒッチコック作品に出演。
弁護士フランク・オコナーに「ナバロンの要塞」(1961年)、「アラビアのロレンス」(1962年)、「ローマ帝国の滅亡」(1964年)など、大作に顔をのぞかせるアンソニー・クエイル。




自作のほぼすべてにチラリと顔を見せる茶目っ気のあるアルフレッド・ヒッチコックは影を潜め(「間違えられた男」でもチラッと登場しますが)、冒頭、ヒッチコック自身が登場して、この映画が実話であることを語っているように、かなりシリアスなタッチで人間社会の不条理を描いています。
なぜ、こうまで目撃者は自信をもって、まるで関係のない人間を犯人だと決めつけてしまうのか。
早く犯人が捕まってほしいと願う心理が、そこに作用するのかもしれませんが、あまりにも無責任で、結果の重大性を考えれば目撃証言の信憑性(しんぴょうせい)をもっと疑ってもいいのではないかと思います。
不安におびえるヘンリー・フォンダの表情は印象的で、特に刑事に連行されて車に乗り込み、座席に座ってかたわらの刑事の顔を盗み見するシーンは、マニーの陥(おちい)りつつある不安な状況を表現した見事なシーン。
また、刑事二人も無闇にマニーを犯人と決めつけるのではなく、といって特別な温情を持って接するでもなく、容疑者とは余計な口をきかない、といった態度が、数々の事件を扱ってきた刑事らしく、親しみはもてないけれども、冷たい法の番人らしくてよかったなあ。
でもマニーが、妻が心配するから電話をさせてほしいと頼んでも、心配はいらない、の一点張りでまったく取り合おうとしなかったのには、やはり、容疑者を犯人として見る習性からなのかとは思うけど、容疑者に対しては寛大さがほしかった。




この映画を見て思うのは、犯人扱いをされて、この先どうなっていくのか不安を抱えながらもマニーが決して声を荒げることなく、静かに周囲の状況を見ながら行動していくところで、これは後の「十二人の怒れる男」の粘り強い陪審員を思わせ、苦難の経験を積んだマニーが精神的にも強くなって陪審員になったような、そんなことも連想させるヘンリー・フォンダの名演でした。





1956年 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
原作・脚本マクスウェル・アンダーソン
音楽バーナード・ハーマン
撮影ロバート・バークス
〈キャスト〉
ヘンリー・フォンダ ヴェラ・マイルズ
アンソニー・クエイル
実際に起きた冤罪事件をもとに、事件に巻き込まれた男と、その家族の苦悩を描いたアルフレッド・ヒッチコックの傑作スリラー。

クリストファー・バレストレロ、愛称マニー(ヘンリー・フォンダ)は38歳。ベーシストとしてナイトクラブでの演奏が終わり、明け方に自宅へ戻ったマニーは玄関脇に置かれた牛乳を手に寝室へ向かいます。
眠っているはずの妻のローズは目覚めていて、歯が痛くて眠れないと言います。
歯の治療をさせてあげたいが、金銭的な余裕の無いマニーは、妻の掛けている保険で金が借りられるんじゃないかと思いつきます。
翌日、保険会社の支店に出向いたマニーは窓口で女性事務員に声をかけます。
保険証券を見せて、金を借りられないか、と尋ねるマニーの顔を見た事務員の表情がこわばり、少しお待ちを、と言って上司のデスクへ向かい、先日、拳銃を突き付けて強盗に入った男によく似ていることを告げます。
保険会社を後に、金の工面ができそうだと喜んで自宅へ戻ろうとしたマニーは、張り込んでいた刑事に玄関先で身柄を拘束され、警察署へ連行されてしまいます。
何がなんだか訳の分からないマニーは、妻が心配するから電話を、と言っても刑事は、心配は要らない、の一点張りで取り合わず、取調室での尋問が始まります。
自分が無実であることはマニー自身がよく知っていますから、落ち着いた態度で刑事の質問に答えようとしますが、目撃者の証言や、筆跡鑑定の結果などからマニーは不利な状況に追い込まれ、裁判所の手続きを経て、留置所へ入れられてしまいます。
一方、事件を知った妻のローズは、夫が無実であることを疑わず、弟と相談の上、7500ドルの保釈金を出してマニーを保釈します。

自由の身になったマニーは無実の罪を晴らそうと、弁護士のフランク・オコナー(アンソニー・クエイル)に相談。
マニーはアリバイを立証しようと、強盗が行われた日に旅行先で宿泊客たちとカードをしていた事実があることから、当時の宿泊客を探し出しますが、二人がすでに死亡。
アリバイの立証が絶望的になったことを引き金に、ローズの精神状態に異変が現れ始めます。
サスペンスやミステリー、スリラーなどを扱っても、ユーモアや娯楽性を盛り込むことを忘れないアルフレッド・ヒッチコックがここでは一転。身に覚えのない犯罪者として扱われた男の苦悩と、その妻が陥る暗黒に満ちた日常をリアルに描き出しています。
強盗犯人に似ているというだけで、ごく平凡な市民が犯罪者に仕立て上げられてしまう怖さ。
中でも一番の決め手となるのが筆跡鑑定で、犯人の残したメモを手掛かりに、犯人の書いた同じ文句を刑事が読み上げ、それをマニーが書くのですが、一度目はどうもハッキリしない。ところが二度目になると、マニーがスペルを間違えた。その間違え方が犯人の書いたものと同じであったという、あり得ないことが起こってしまう。

強盗に入られた店主たちも口をそろえて彼が犯人らしいと言う。
筆跡鑑定でも、犯人しか間違えようのないことをマニーがやってしまう。
あとは本人の自白になるのですが、もちろん自分は無実なのだから、自白できるはずがない。
この映画がかなり深刻性を帯びてくるのが、後半からの、妻のローズの精神状態。
マニーのアリバイを立証してもらえるはずの証人の二人はすでに死亡していると判り、そこからローズの様子がおかしくなっていきます。
この映画の怖さは、犯人に間違えられたマニーひとりの悲劇ではなく、当然ながら、その家族にも影響が及ぶということです。しかも、真犯人が捕まり、冤罪と認められたマニーは救われるとしても、ローズの精神障害はその後も長く残ってしまいます。
かつて江戸川乱歩も「D坂の殺人事件」だったかで、人間の記憶や視覚の頼りなさを書いていましたが、ここでは保険会社の事務員を含め、目撃者がマニーを犯人だと断定してしまっていることで、絶対的な思い込みがひとりの人間の運命を左右してしまう怖さ。
そしてそれは家族をも巻き込む悲劇につながってしまう。
このまま進めば、救いようのない映画になってしまうところでしたが、真犯人が強盗事件を起こしたことで、マニーの冤罪に結びつくことになります。
主人公マニーに「怒りの葡萄」(1940年)、「荒野の決闘」(1946年)、「ミスタア・ロバーツ」(1955年)など、巨匠ジョン・フォード作品でお馴染みの名優ヘンリー・フォンダ。
翌年の1957年に名作「十二人の怒れる男」での、他の陪審員全員が有罪とする中、物静かながら、粘り強く無罪判決へと導いてゆく陪審員を好演してアメリカの良心を表現しましたが、他方、その二年後の「ワーロック」(1959年)では貫禄十分の二丁拳銃の早撃ちガンマンに扮し、最後の決闘では保安官のリチャード・ウィドマークを圧倒しながら、拳銃を二丁とも捨てて静かに去ってゆくラストのカッコ良かったこと。
妻ローズに「捜索者」(1956年)のヴェラ・マイルズ。
後の「サイコ」(1960年)で再びヒッチコック作品に出演。
弁護士フランク・オコナーに「ナバロンの要塞」(1961年)、「アラビアのロレンス」(1962年)、「ローマ帝国の滅亡」(1964年)など、大作に顔をのぞかせるアンソニー・クエイル。
自作のほぼすべてにチラリと顔を見せる茶目っ気のあるアルフレッド・ヒッチコックは影を潜め(「間違えられた男」でもチラッと登場しますが)、冒頭、ヒッチコック自身が登場して、この映画が実話であることを語っているように、かなりシリアスなタッチで人間社会の不条理を描いています。
なぜ、こうまで目撃者は自信をもって、まるで関係のない人間を犯人だと決めつけてしまうのか。
早く犯人が捕まってほしいと願う心理が、そこに作用するのかもしれませんが、あまりにも無責任で、結果の重大性を考えれば目撃証言の信憑性(しんぴょうせい)をもっと疑ってもいいのではないかと思います。
不安におびえるヘンリー・フォンダの表情は印象的で、特に刑事に連行されて車に乗り込み、座席に座ってかたわらの刑事の顔を盗み見するシーンは、マニーの陥(おちい)りつつある不安な状況を表現した見事なシーン。
また、刑事二人も無闇にマニーを犯人と決めつけるのではなく、といって特別な温情を持って接するでもなく、容疑者とは余計な口をきかない、といった態度が、数々の事件を扱ってきた刑事らしく、親しみはもてないけれども、冷たい法の番人らしくてよかったなあ。
でもマニーが、妻が心配するから電話をさせてほしいと頼んでも、心配はいらない、の一点張りでまったく取り合おうとしなかったのには、やはり、容疑者を犯人として見る習性からなのかとは思うけど、容疑者に対しては寛大さがほしかった。
この映画を見て思うのは、犯人扱いをされて、この先どうなっていくのか不安を抱えながらもマニーが決して声を荒げることなく、静かに周囲の状況を見ながら行動していくところで、これは後の「十二人の怒れる男」の粘り強い陪審員を思わせ、苦難の経験を積んだマニーが精神的にも強くなって陪審員になったような、そんなことも連想させるヘンリー・フォンダの名演でした。

2021年06月30日
映画「見知らぬ乗客」− 偶然乗り合わせた列車で持ちかけられた“交換殺人”
「見知らぬ乗客」(Strangers on a Train )
1951年 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
原作パトリシア・ハイスミス
脚本レイモンド・チャンドラー
音楽ディミトリ・ティオムキン
撮影ロバート・バークス
〈キャスト〉
ファーリー・グレンジャー ロバート・ウォーカー
ケイシー・ロジャース レオ・G・キャロル




偶然乗り合わせた列車の乗客から“交換殺人”を持ちかけられたテニス・プレイヤーが陥る恐怖を描いたアルフレッド・ヒッチコックの傑作。

ガイ・ハミルトン(ファーリー・グレンジャー)は、向かい合った乗客の足が触れたことから挨拶を交わし、会話が弾んで相手の男と親しくなります。
相手の男の名前はブルーノ・アントニー。
テニス選手として人気のあるガイのファンだというブルーノは、初対面ながらガイの身辺の事情をよく知っており、また、浮気な妻のミリアム(ケイシー・ロジャース)に嫌気がさし、モートン上院議員の娘であるアン・モートン(ルース・ローマン)との結婚を強く望んでいるガイは、そんな事情も急速に親しくなったブルーノに話します。
食堂車でグラスを傾け、お互いの事情を話す中で、ブルーノは殺人についての話を始めます。
君は妻のミリアムがいなくなれば、恋人のアン・モートンと結婚ができる。
僕は母とは仲がいいが、父とは折り合いが悪い。殺したいと思っている。
殺人が行われても、動機を持っていなければ疑われることはない。
“僕がミリアムを殺すから、君は僕の父を殺してくれないか”
そうすれば、お互いに動機が無いんだから疑われる心配はない。
半信半疑で笑顔を浮かべながら、冗談話にしてしまおうと思ったガイでしたが、後日ブルーノは、その言葉通り、夜の遊園地でガイの妻ミリアムを絞殺してしまいます。

ブルーノからミリアムのかけていたメガネを見せられたガイは、次は君が僕の父を殺す番だ、と“交換殺人”の強要を迫られます。
殺人など出来るはずのないガイは、恋人のアンにも事情を告げられないまま、ひとりブルーノの脅迫に苦しむことになります。
なぜ実行しないんだ、とガイの身辺に執拗に姿を現すブルーノ。
ブルーノの存在を不審に思ったアンは、“交換殺人”を持ちかけられたことをガイから聞き、衝撃を受けながらも、ガイを信じることを約束します。
一方、ガイの妻ミリアムが殺されたことで、アリバイの立証ができなかったことから、ガイには容疑者として刑事二人のゆるい監視の目がつくことになります。
交換殺人などできない、と言うガイに業を煮やしたブルーノは、一目でガイのものと判る特注品のライターを持っていたことから、これを殺人現場に落とせば君は有罪だと、ガイを脅します。
ブルーノよりも先に現場の遊園地へ向かいたいガイですが、折しもその日はテニスの試合日。
早く勝敗を決して遊園地へ駆けつけたいと焦るガイ。
しかし、相手の選手もしぶとく粘り、容易に決着がつきません。
ようやく勝負が決し、警察の尾行を逃れるように遊園地へと急ぐガイ。
先に駆けつけていたブルーノでしたが、誤って証拠品のライターを側溝へ落としてしまいます。懸命に手を伸ばして拾おうと焦るブルーノ。
やっとライターをつかみ、現場へ急ぐブルーノは、ガイと共に警察の追求が近づいていることを知ります。
そして二人はメリーゴーランドで対峙することになるのですが、多数の子どもたちを乗せたメリーゴーランドに入った二人を見て警察が発砲した銃弾は、誤って操作係りを撃ってしまい、メリーゴーランドは急回転を始めます。





原作は「太陽がいっぱい」のパトリシア・ハイスミス。
“交換殺人”というサスペンスミステリーを扱っていますが、脚色をしたのが「さらば愛しき女よ」「長いお別れ」などでハードボイルド小説を文学にまだ高めたレイモンド・チャンドラーなので、ハードボイルド的雰囲気も盛り込み、特にラストのメリーゴーランドの場面は息をのむ迫力とスリル。
それに、この映画は撮影が素晴らしい効果を上げていて、撮影に当たったロバート・バークスはアカデミー賞撮影賞にノミネート。受賞こそ逃しましたが(ちなみに撮影賞受賞は、白黒部門で「陽のあたる場所」のウィリアム・C・メラー、カラー部門で「巴里のアメリカ人」のアルフレッド・ジルクスとジョン・アルトン)、映画冒頭の、乗客が列車へ乗り込む場面を足の動きで追い、脚を組むために動かした足先が相手の足に当たって、そこからお互いの顔へ移動するシーンは、そこだけでドラマチックな展開。
物語の怖さ、不気味さを特徴づけるのがブルーノ・アントニーという男の異常性。
彼はガイ・ハミルトンに対して“交換殺人”を持ちかけます。理屈の上では動機なき殺人ですから、捜査の手が及ぶことはない。完全犯罪になり得そうに思われますが、見ず知らずの人間を簡単に殺せるものではない。
しかし、それをブルーノは淡々とやってのけます。
そしてブルーノが殺してほしいと願う相手が、こともあろうに自分の実の父親であるところに変質的な異常性が現れています。
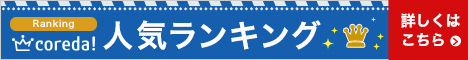

父親を殺したいと願う男の心理とはどのようなものなのか。
フロイトは「精神分析入門」の中で、こんなことを言っています。
“同性、つまり母と娘、父と息子は互いに離反させる傾向を示す。息子にとって父親は、イヤイヤながら我慢していなければならない、あらゆる社会的強制の権化なのです。父親は、息子の意欲的な活動や、早期における性的な歓びを妨げ、………父親の死を待ち構えている気持ちは………悲劇的なものを生み出しかねないほど激しく高まります”「高橋義孝・下坂幸三訳」
世の中のすべての父親と息子の関係がフロイトのいうようなものであるとは思いませんが、ブルーノ・アントニーは父親との折り合いが悪くはあっても、母親との情愛が深いというのは、フロイト流にいえばエディプスコンプレックスと呼ぶべきものなのでしょう。
この性格造形は後の「サイコ」(1960年)のノーマン・ベイツにつながるのではないかと思います。
この異常性を持ったブルーノが、早く殺人を実行しろと、執拗にガイの身辺に現れる怖さ。
特に、ガイのテニスの試合観戦に現れたブルーノが、観客のすべてがテニスボールを追って首を左右に動かす中で、ひとりブルーノだけがジーッとガイを見つめる怖さ。
様々に散りばめられた恐怖シーンの中でも、最大の見どころとなるのはラストのメリーゴーランドのシーンでしょう。
ブルーノを狙撃するはずの警察の銃弾がそれて、メリーゴーランドの操作係に当たってしまう。倒れた拍子に機械が誤作動を起こし、異常な速さでメリーゴーランドが回転を始める。
最初は歓声を上げていた子供たちも、やがてその表情は恐怖におびえ、悲鳴と絶叫に変わります。
猛スピードで回転するメリーゴーランドで、振り落とされそうになりながら格闘するガイとブルーノ。
そして、ここに一人、おそらく遊園地の係員か何かの男が、メリーゴーランドを止めるべく、猛スピードで回転を続けるメリーゴーランドの下へもぐって機械のスイッチを探りにいく場面の怖いこと。




ガイ・ハミルトンに「ロープ」(1948年)でもヒッチコック作品に登場しているファーリー・グレンジャー。
ブルーノ・アントニーに「大草原」「愛の調べ」(1947年)のロバート・ウォーカー。
サイコパス的犯人像を演じて絶賛されたロバート・ウォーカーでしたが、「見知らぬ乗客」公開直後に32歳の若さで急死しています。
また、ガイの恋人アン・モートンの妹バーバラに、アルフレッド・ヒッチコックの娘パトリシア・ヒッチコック。
しっかり者の姉とは対照的に、ちょっとおしゃべりな脇役ながら、かけているメガネがブルーノの潜在意識に働きかける重要な役どころを好演。




怖い映画ですが、晴れて結ばれたガイとアン・モートンが列車に乗り、向かいあった乗客から声をかけられ、そそくさと立ち去るラストは、ユーモアを忘れないヒッチコックらしくて微笑ましい締めくくりでした。





1951年 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
原作パトリシア・ハイスミス
脚本レイモンド・チャンドラー
音楽ディミトリ・ティオムキン
撮影ロバート・バークス
〈キャスト〉
ファーリー・グレンジャー ロバート・ウォーカー
ケイシー・ロジャース レオ・G・キャロル
偶然乗り合わせた列車の乗客から“交換殺人”を持ちかけられたテニス・プレイヤーが陥る恐怖を描いたアルフレッド・ヒッチコックの傑作。

ガイ・ハミルトン(ファーリー・グレンジャー)は、向かい合った乗客の足が触れたことから挨拶を交わし、会話が弾んで相手の男と親しくなります。
相手の男の名前はブルーノ・アントニー。
テニス選手として人気のあるガイのファンだというブルーノは、初対面ながらガイの身辺の事情をよく知っており、また、浮気な妻のミリアム(ケイシー・ロジャース)に嫌気がさし、モートン上院議員の娘であるアン・モートン(ルース・ローマン)との結婚を強く望んでいるガイは、そんな事情も急速に親しくなったブルーノに話します。
食堂車でグラスを傾け、お互いの事情を話す中で、ブルーノは殺人についての話を始めます。
君は妻のミリアムがいなくなれば、恋人のアン・モートンと結婚ができる。
僕は母とは仲がいいが、父とは折り合いが悪い。殺したいと思っている。
殺人が行われても、動機を持っていなければ疑われることはない。
“僕がミリアムを殺すから、君は僕の父を殺してくれないか”
そうすれば、お互いに動機が無いんだから疑われる心配はない。
半信半疑で笑顔を浮かべながら、冗談話にしてしまおうと思ったガイでしたが、後日ブルーノは、その言葉通り、夜の遊園地でガイの妻ミリアムを絞殺してしまいます。

ブルーノからミリアムのかけていたメガネを見せられたガイは、次は君が僕の父を殺す番だ、と“交換殺人”の強要を迫られます。
殺人など出来るはずのないガイは、恋人のアンにも事情を告げられないまま、ひとりブルーノの脅迫に苦しむことになります。
なぜ実行しないんだ、とガイの身辺に執拗に姿を現すブルーノ。
ブルーノの存在を不審に思ったアンは、“交換殺人”を持ちかけられたことをガイから聞き、衝撃を受けながらも、ガイを信じることを約束します。
一方、ガイの妻ミリアムが殺されたことで、アリバイの立証ができなかったことから、ガイには容疑者として刑事二人のゆるい監視の目がつくことになります。
交換殺人などできない、と言うガイに業を煮やしたブルーノは、一目でガイのものと判る特注品のライターを持っていたことから、これを殺人現場に落とせば君は有罪だと、ガイを脅します。
ブルーノよりも先に現場の遊園地へ向かいたいガイですが、折しもその日はテニスの試合日。
早く勝敗を決して遊園地へ駆けつけたいと焦るガイ。
しかし、相手の選手もしぶとく粘り、容易に決着がつきません。
ようやく勝負が決し、警察の尾行を逃れるように遊園地へと急ぐガイ。
先に駆けつけていたブルーノでしたが、誤って証拠品のライターを側溝へ落としてしまいます。懸命に手を伸ばして拾おうと焦るブルーノ。
やっとライターをつかみ、現場へ急ぐブルーノは、ガイと共に警察の追求が近づいていることを知ります。
そして二人はメリーゴーランドで対峙することになるのですが、多数の子どもたちを乗せたメリーゴーランドに入った二人を見て警察が発砲した銃弾は、誤って操作係りを撃ってしまい、メリーゴーランドは急回転を始めます。

原作は「太陽がいっぱい」のパトリシア・ハイスミス。
“交換殺人”というサスペンスミステリーを扱っていますが、脚色をしたのが「さらば愛しき女よ」「長いお別れ」などでハードボイルド小説を文学にまだ高めたレイモンド・チャンドラーなので、ハードボイルド的雰囲気も盛り込み、特にラストのメリーゴーランドの場面は息をのむ迫力とスリル。
それに、この映画は撮影が素晴らしい効果を上げていて、撮影に当たったロバート・バークスはアカデミー賞撮影賞にノミネート。受賞こそ逃しましたが(ちなみに撮影賞受賞は、白黒部門で「陽のあたる場所」のウィリアム・C・メラー、カラー部門で「巴里のアメリカ人」のアルフレッド・ジルクスとジョン・アルトン)、映画冒頭の、乗客が列車へ乗り込む場面を足の動きで追い、脚を組むために動かした足先が相手の足に当たって、そこからお互いの顔へ移動するシーンは、そこだけでドラマチックな展開。
物語の怖さ、不気味さを特徴づけるのがブルーノ・アントニーという男の異常性。
彼はガイ・ハミルトンに対して“交換殺人”を持ちかけます。理屈の上では動機なき殺人ですから、捜査の手が及ぶことはない。完全犯罪になり得そうに思われますが、見ず知らずの人間を簡単に殺せるものではない。
しかし、それをブルーノは淡々とやってのけます。
そしてブルーノが殺してほしいと願う相手が、こともあろうに自分の実の父親であるところに変質的な異常性が現れています。
父親を殺したいと願う男の心理とはどのようなものなのか。
フロイトは「精神分析入門」の中で、こんなことを言っています。
“同性、つまり母と娘、父と息子は互いに離反させる傾向を示す。息子にとって父親は、イヤイヤながら我慢していなければならない、あらゆる社会的強制の権化なのです。父親は、息子の意欲的な活動や、早期における性的な歓びを妨げ、………父親の死を待ち構えている気持ちは………悲劇的なものを生み出しかねないほど激しく高まります”「高橋義孝・下坂幸三訳」
世の中のすべての父親と息子の関係がフロイトのいうようなものであるとは思いませんが、ブルーノ・アントニーは父親との折り合いが悪くはあっても、母親との情愛が深いというのは、フロイト流にいえばエディプスコンプレックスと呼ぶべきものなのでしょう。
この性格造形は後の「サイコ」(1960年)のノーマン・ベイツにつながるのではないかと思います。
この異常性を持ったブルーノが、早く殺人を実行しろと、執拗にガイの身辺に現れる怖さ。
特に、ガイのテニスの試合観戦に現れたブルーノが、観客のすべてがテニスボールを追って首を左右に動かす中で、ひとりブルーノだけがジーッとガイを見つめる怖さ。
様々に散りばめられた恐怖シーンの中でも、最大の見どころとなるのはラストのメリーゴーランドのシーンでしょう。
ブルーノを狙撃するはずの警察の銃弾がそれて、メリーゴーランドの操作係に当たってしまう。倒れた拍子に機械が誤作動を起こし、異常な速さでメリーゴーランドが回転を始める。
最初は歓声を上げていた子供たちも、やがてその表情は恐怖におびえ、悲鳴と絶叫に変わります。
猛スピードで回転するメリーゴーランドで、振り落とされそうになりながら格闘するガイとブルーノ。
そして、ここに一人、おそらく遊園地の係員か何かの男が、メリーゴーランドを止めるべく、猛スピードで回転を続けるメリーゴーランドの下へもぐって機械のスイッチを探りにいく場面の怖いこと。
ガイ・ハミルトンに「ロープ」(1948年)でもヒッチコック作品に登場しているファーリー・グレンジャー。
ブルーノ・アントニーに「大草原」「愛の調べ」(1947年)のロバート・ウォーカー。
サイコパス的犯人像を演じて絶賛されたロバート・ウォーカーでしたが、「見知らぬ乗客」公開直後に32歳の若さで急死しています。
また、ガイの恋人アン・モートンの妹バーバラに、アルフレッド・ヒッチコックの娘パトリシア・ヒッチコック。
しっかり者の姉とは対照的に、ちょっとおしゃべりな脇役ながら、かけているメガネがブルーノの潜在意識に働きかける重要な役どころを好演。
怖い映画ですが、晴れて結ばれたガイとアン・モートンが列車に乗り、向かいあった乗客から声をかけられ、そそくさと立ち去るラストは、ユーモアを忘れないヒッチコックらしくて微笑ましい締めくくりでした。

2021年06月23日
映画「バルカン超特急」ー 列車という密室、消えた婦人を追って展開するサスペンス・ミステリー
「バルカン超特急」(The Lady Vanishes)
1938年 イギリス/アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
脚本アルマ・レヴィル
シドニー・ギリアット
フランク・ラウンダー
原作エセル・リナ・ホワイト
撮影ジャック・コックス
〈キャスト〉
マーガレット・ロックウッド メイ・ウィッティ
マイケル・レッドグレイヴ
列車内で姿を消した老婦人をめぐるサスペンスで、翌年の「岩窟の野獣」を最後にハリウッドへ渡ったヒッチコックのイギリス時代の、文字通りサスペンス映画の傑作。





第二次世界大戦を間近に控え、世界情勢が混沌とするヨーロッパ、バンドリカ(架空の国)の山中。
雪のために列車が立ち往生して、乗客たちは仕方なく駅の近くのホテルへ宿泊することになります。
乗客たちの中には、クリケットの試合を観戦することを最大の楽しみにいているイングランド人の二人組、カルディコット(ノウントン・ウェイン)とチャータース(ベイジル・ラドフォード)。
弁護士トッドハンター(セシル・パーカー)とその愛人(リンデン・トラヴァース)は不倫関係。
家庭教師のミス・フロイ(メイ・ウィッティ)。
結婚を控え、独身時代の最後の旅行を楽しもうとしているアイリス・ヘンダーソン(マーガレット・ロックウッド)たちがいて、ホテルへの不満を口にしながら夜を過ごすことになります。
しかし、上の階のクラリネットの音や、床を踏み鳴らす音がうるさくて、アイリスは眠ることができません。
我慢ができなくなったアイリスは、支配人に頼んで静かにしてもらうように言いますが、上の階のクラリネット奏者ギルバート(マイケル・レッドグレイヴ)は、民族舞踊を記録するための大事な仕事なんだと主張。
支配人とモメた揚げ句、ギルバートは部屋を追い出されてしまいます。
やっと静かになったと喜んだアイリスでしたが、そこへ、部屋を追い出されたギルバートが入り込み、君のためにこうなったと、今度はアイリスとひと悶着。
仕方なくアイリスはギルバートを元の部屋へ戻してもらうよう支配人に頼むハメに。
列車の運行が決まり、客室に乗り込んだアイリスは、ミス・フロイと名乗る老婦人と同室になり、一緒に食堂車へ出かけて食事を楽しみます。
客室へ戻ったアイリスはひと眠りしますが、目を覚ますとミス・フロイの姿は無く、ミス・フロイの座っていた席には見知らぬ女性、クマー夫人が座っています。
ミス・フロイはどこへ行ったのかと、アイリスは他の乗客に尋ねますが、そんな女性は知らないという言葉しか返ってきません。

同乗していたエゴン・ハーツ医師からは、あなたはホテルを出たとき、鉢植えで頭を打ったから、その後遺症で記憶障害を起こしているのだ、と言われる始末。
納得のいかないアイリスは、列車内の他の乗客にも訊いてみますが、誰もが自分たちの事情を抱えていて他の問題に関わりたくないために、そんな女性は知らないと答えます。
そんな中、昨夜のトラブルの相手、クラリネット奏者のギルバートとバッタリ出会います。
ちょっと風変わりなギルバートは、アイリスの言葉を信じ、アイリスと一緒にミス・フロイ捜索のために危険の中へ乗り出すことになります。
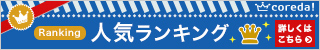





原題は「消えたレディ」。
誰もが、そんな女性は知らないという、自分でも、本当はミス・フロイという人間は存在していなかったんじゃないか、そんなことを思い始めた矢先、食堂車の窓ガラスにミス・フロイが自分を紹介するために書いた名前、“フロイ”の文字跡がクッキリと浮かび上がる場面は秀逸で、そのため、列車の乗客すべてが嘘をついていると気づいた瞬間に、サスペンスの緊張感が一気に高まります。
しかし、緊張感の中にもユーモアを織り交ぜ、シャーロック・ホームズを気取ったギルバートと、助手役のアイリスの素人探偵コンビの軽妙さは、まるで子どもの探偵ごっこのような雰囲気を生み出して、ユーモア好きなイギリス人気質を持ったヒッチコックならでは。
アイリスとギルバートの男女設定は、最初はお互いに悪感情を持ったものの、事件に巻き込まれながらも、お互いに協力して最後には結ばれるというパターンで、ロマンティック・コメディとしての要素を持っていて、見ていても微笑ましく気持ちよく楽しめます。
事件の鍵を握るミス・フロイとはいったい何者なのか。それはやがて映画の後半で明らかにされてゆくのですが、そもそも、走行している狭い列車の中で、人間一人をどこへ隠したのか。

列車の乗客には様々な主要な人物が登場します。
外科医のエゴン・ハーツ医師。
不倫関係のトッドハンターとその愛人。
クリケット愛好家の英国人カルディコットとチャータース。
奇術師のイタリア人ドッポ。
ハーツ医師の助手の尼僧。
アイリスとギルバートの探偵コンビは、奇術師ドッポが人を消すトリックを使うことを知り、ドッポの道具を調べようと貨物車両に潜入。床に落ちているミス・フロイの眼鏡を発見します。
そこへ現れたドッポと揉み合いの格闘。
事件は国際的スパイ団が暗躍する様相を呈してきます。




アイリスに「ミュンヘンの夜行列車」(1940年)、「灰色の男」(1943年)などの美人女優マーガレット・ロックウッド。
ギルバートに「扉の陰の秘密」(1947年)、「静かなアメリカ人」(1958年)のマイケル・レッドグレイヴ。
クリケット愛好家のノウントン・ウェインとベイジル・ラドフォードは、次回作「ミュンヘンの夜行列車」でもクリケット愛好家として登場。「バルカン超特急」と同様とぼけたユーモアを振りまいています。
エゴン・ハーツ医師に、1933年のジョージ・キューカー版「若草物語」でベア教授を演じ、「ラインの監視」(1943年)でアカデミー賞主演男優賞を受賞した演技派ポール・ルーカス。
事件の鍵を握るミス・フロイに「断崖」(1941年)、「ミニヴァー夫人」(1942年)、「ガス燈」(1944年)など、名作に顔をのぞかせるメイ・ウィッティ。




ミステリー、サスペンス、アクション、ユーモア、ラブ・ロマンス。
1時間40分ほどの時間にエンターテインメントの要素を存分に盛り込み、なお、不倫関係の二人、クリケット愛好家の二人など、脇役の存在も軽視することなく個性を持たせました。
特に、クリケットの試合に遅れることを心配するあまり、余計なことに関わろうとせず、アイリスに対しても嘘までついてクリケットの観戦に急いだカルディコットとチャータースの二人は、駅に到着して目についた広告によって、天候悪化のために試合が中止になったことを知る場面は笑わせてくれます。
次回作「岩窟の野獣」(1939年)を最後にイギリスを去り、ハリウッドへ渡って「レベッカ」(1940年)を皮切りに次々と傑作を世に送り出したアルフレッド・ヒッチコック。
渡米以降ミステリー性やサスペンスタッチはさらに深みのある充実したものになりましたが、イギリス時代の、切れ味鋭く畳み込むような展開など、何度見ても飽きさせません。




ただ、完全に褒められたわけでもないのが、アイリスの婚約者の立場の描き方。
アイリスは彼(婚約者)との結婚にあまり乗り気ではなく、ギルバートとの仲が急展開してギルバートに心が移ってしまう。
駅へ到着して、婚約者が迎えにきていないことを知ったアイリスは、イヤな男よね、とかなんとか言って彼を非難する。
そこでサッとギルバートとの抱擁とキスがあるのですが、その後アイリスの婚約者は、彼女の姿を探してホームでウロウロする後ろ姿が描かれる。
なんとも間抜けな男としてアイリスの婚約者は描かれていて、彼の立場になってみると、これほど惨めな結末はありません。
名作として名高いダスティン・ホフマン主演の「卒業」(1967年, マイク・ニコルズ監督)の、有名なラストシーンでもそうなのですが、教会での結婚式へ、エレーンの結婚を阻止しようとベンジャミンが現れる。そして二人は手に手を取って…。
しかし、相手の新郎の立場はどうなるんだろう。
彼は別に悪者でもなく、結婚を嫌がるエレーンに無理やり結婚を強要したわけでもない。
ハッピーエンドのベンジャミンとエレーンはいいとしても、挙式の最中に、見ず知らずの男に花嫁をさらわれた新郎ほど惨めで情けない立場はないでしょう。
「卒業」を手放しで称賛する気になれないのは、相手の婚約者への配慮がまったく欠けているためです。
同じことが「バルカン超特急」でもいえるようで、アイリスとギルバートのロマンスの展開を急ぎ過ぎたのか、ちょっと腑に落ちないシーンでした。
とはいえ、イギリス時代の傑作であるには変わりなく、ミステリーとスリルに満ちた、とても優れた映画です。





1938年 イギリス/アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
脚本アルマ・レヴィル
シドニー・ギリアット
フランク・ラウンダー
原作エセル・リナ・ホワイト
撮影ジャック・コックス
〈キャスト〉
マーガレット・ロックウッド メイ・ウィッティ
マイケル・レッドグレイヴ
列車内で姿を消した老婦人をめぐるサスペンスで、翌年の「岩窟の野獣」を最後にハリウッドへ渡ったヒッチコックのイギリス時代の、文字通りサスペンス映画の傑作。

第二次世界大戦を間近に控え、世界情勢が混沌とするヨーロッパ、バンドリカ(架空の国)の山中。
雪のために列車が立ち往生して、乗客たちは仕方なく駅の近くのホテルへ宿泊することになります。
乗客たちの中には、クリケットの試合を観戦することを最大の楽しみにいているイングランド人の二人組、カルディコット(ノウントン・ウェイン)とチャータース(ベイジル・ラドフォード)。
弁護士トッドハンター(セシル・パーカー)とその愛人(リンデン・トラヴァース)は不倫関係。
家庭教師のミス・フロイ(メイ・ウィッティ)。
結婚を控え、独身時代の最後の旅行を楽しもうとしているアイリス・ヘンダーソン(マーガレット・ロックウッド)たちがいて、ホテルへの不満を口にしながら夜を過ごすことになります。
しかし、上の階のクラリネットの音や、床を踏み鳴らす音がうるさくて、アイリスは眠ることができません。
我慢ができなくなったアイリスは、支配人に頼んで静かにしてもらうように言いますが、上の階のクラリネット奏者ギルバート(マイケル・レッドグレイヴ)は、民族舞踊を記録するための大事な仕事なんだと主張。
支配人とモメた揚げ句、ギルバートは部屋を追い出されてしまいます。
やっと静かになったと喜んだアイリスでしたが、そこへ、部屋を追い出されたギルバートが入り込み、君のためにこうなったと、今度はアイリスとひと悶着。
仕方なくアイリスはギルバートを元の部屋へ戻してもらうよう支配人に頼むハメに。
列車の運行が決まり、客室に乗り込んだアイリスは、ミス・フロイと名乗る老婦人と同室になり、一緒に食堂車へ出かけて食事を楽しみます。
客室へ戻ったアイリスはひと眠りしますが、目を覚ますとミス・フロイの姿は無く、ミス・フロイの座っていた席には見知らぬ女性、クマー夫人が座っています。
ミス・フロイはどこへ行ったのかと、アイリスは他の乗客に尋ねますが、そんな女性は知らないという言葉しか返ってきません。

同乗していたエゴン・ハーツ医師からは、あなたはホテルを出たとき、鉢植えで頭を打ったから、その後遺症で記憶障害を起こしているのだ、と言われる始末。
納得のいかないアイリスは、列車内の他の乗客にも訊いてみますが、誰もが自分たちの事情を抱えていて他の問題に関わりたくないために、そんな女性は知らないと答えます。
そんな中、昨夜のトラブルの相手、クラリネット奏者のギルバートとバッタリ出会います。
ちょっと風変わりなギルバートは、アイリスの言葉を信じ、アイリスと一緒にミス・フロイ捜索のために危険の中へ乗り出すことになります。
原題は「消えたレディ」。
誰もが、そんな女性は知らないという、自分でも、本当はミス・フロイという人間は存在していなかったんじゃないか、そんなことを思い始めた矢先、食堂車の窓ガラスにミス・フロイが自分を紹介するために書いた名前、“フロイ”の文字跡がクッキリと浮かび上がる場面は秀逸で、そのため、列車の乗客すべてが嘘をついていると気づいた瞬間に、サスペンスの緊張感が一気に高まります。
しかし、緊張感の中にもユーモアを織り交ぜ、シャーロック・ホームズを気取ったギルバートと、助手役のアイリスの素人探偵コンビの軽妙さは、まるで子どもの探偵ごっこのような雰囲気を生み出して、ユーモア好きなイギリス人気質を持ったヒッチコックならでは。
アイリスとギルバートの男女設定は、最初はお互いに悪感情を持ったものの、事件に巻き込まれながらも、お互いに協力して最後には結ばれるというパターンで、ロマンティック・コメディとしての要素を持っていて、見ていても微笑ましく気持ちよく楽しめます。
事件の鍵を握るミス・フロイとはいったい何者なのか。それはやがて映画の後半で明らかにされてゆくのですが、そもそも、走行している狭い列車の中で、人間一人をどこへ隠したのか。

列車の乗客には様々な主要な人物が登場します。
外科医のエゴン・ハーツ医師。
不倫関係のトッドハンターとその愛人。
クリケット愛好家の英国人カルディコットとチャータース。
奇術師のイタリア人ドッポ。
ハーツ医師の助手の尼僧。
アイリスとギルバートの探偵コンビは、奇術師ドッポが人を消すトリックを使うことを知り、ドッポの道具を調べようと貨物車両に潜入。床に落ちているミス・フロイの眼鏡を発見します。
そこへ現れたドッポと揉み合いの格闘。
事件は国際的スパイ団が暗躍する様相を呈してきます。
アイリスに「ミュンヘンの夜行列車」(1940年)、「灰色の男」(1943年)などの美人女優マーガレット・ロックウッド。
ギルバートに「扉の陰の秘密」(1947年)、「静かなアメリカ人」(1958年)のマイケル・レッドグレイヴ。
クリケット愛好家のノウントン・ウェインとベイジル・ラドフォードは、次回作「ミュンヘンの夜行列車」でもクリケット愛好家として登場。「バルカン超特急」と同様とぼけたユーモアを振りまいています。
エゴン・ハーツ医師に、1933年のジョージ・キューカー版「若草物語」でベア教授を演じ、「ラインの監視」(1943年)でアカデミー賞主演男優賞を受賞した演技派ポール・ルーカス。
事件の鍵を握るミス・フロイに「断崖」(1941年)、「ミニヴァー夫人」(1942年)、「ガス燈」(1944年)など、名作に顔をのぞかせるメイ・ウィッティ。
ミステリー、サスペンス、アクション、ユーモア、ラブ・ロマンス。
1時間40分ほどの時間にエンターテインメントの要素を存分に盛り込み、なお、不倫関係の二人、クリケット愛好家の二人など、脇役の存在も軽視することなく個性を持たせました。
特に、クリケットの試合に遅れることを心配するあまり、余計なことに関わろうとせず、アイリスに対しても嘘までついてクリケットの観戦に急いだカルディコットとチャータースの二人は、駅に到着して目についた広告によって、天候悪化のために試合が中止になったことを知る場面は笑わせてくれます。
次回作「岩窟の野獣」(1939年)を最後にイギリスを去り、ハリウッドへ渡って「レベッカ」(1940年)を皮切りに次々と傑作を世に送り出したアルフレッド・ヒッチコック。
渡米以降ミステリー性やサスペンスタッチはさらに深みのある充実したものになりましたが、イギリス時代の、切れ味鋭く畳み込むような展開など、何度見ても飽きさせません。
ただ、完全に褒められたわけでもないのが、アイリスの婚約者の立場の描き方。
アイリスは彼(婚約者)との結婚にあまり乗り気ではなく、ギルバートとの仲が急展開してギルバートに心が移ってしまう。
駅へ到着して、婚約者が迎えにきていないことを知ったアイリスは、イヤな男よね、とかなんとか言って彼を非難する。
そこでサッとギルバートとの抱擁とキスがあるのですが、その後アイリスの婚約者は、彼女の姿を探してホームでウロウロする後ろ姿が描かれる。
なんとも間抜けな男としてアイリスの婚約者は描かれていて、彼の立場になってみると、これほど惨めな結末はありません。
名作として名高いダスティン・ホフマン主演の「卒業」(1967年, マイク・ニコルズ監督)の、有名なラストシーンでもそうなのですが、教会での結婚式へ、エレーンの結婚を阻止しようとベンジャミンが現れる。そして二人は手に手を取って…。
しかし、相手の新郎の立場はどうなるんだろう。
彼は別に悪者でもなく、結婚を嫌がるエレーンに無理やり結婚を強要したわけでもない。
ハッピーエンドのベンジャミンとエレーンはいいとしても、挙式の最中に、見ず知らずの男に花嫁をさらわれた新郎ほど惨めで情けない立場はないでしょう。
「卒業」を手放しで称賛する気になれないのは、相手の婚約者への配慮がまったく欠けているためです。
同じことが「バルカン超特急」でもいえるようで、アイリスとギルバートのロマンスの展開を急ぎ過ぎたのか、ちょっと腑に落ちないシーンでした。
とはいえ、イギリス時代の傑作であるには変わりなく、ミステリーとスリルに満ちた、とても優れた映画です。

2021年01月14日
映画「死刑執行人もまた死す」‐ ナチス副総督ラインハルト・ハイドリヒ暗殺事件を背景にした傑作サスペンス
「死刑執行人もまた死す」(Hangmen Also Die!)
1943年 アメリカ
監督フリッツ・ラング
原案フリッツ・ラング
ベルトルト・ブレヒト
脚本ジョン・ウェクスリー
撮影ジェームズ・ウォン・ハウ
音楽ハンス・アイスラー
〈キャスト〉
ブライアン・ドンレヴィ ウォルター・ブレナン
アンナ・リー ジーン・ロックハート
ヴェネツィア国際映画祭特別賞
ナチス占領下のプラハで実際に起きたナチス副総督、ラインハルト・ハイドリヒ暗殺事件を背景に、ナチスに抑圧されたチェコの民衆、そして反ナチの活動家たちの暗躍と悲劇を、重厚でリアリティーあふれる中に娯楽性を織り交ぜた傑作。





第二次世界大戦下のヨーロッパ、ナチス・ドイツのベーメン・メーレン保護領(チェコ)で、統治者であるラインハルト・ハイドリヒが何者かに狙撃されます。
ゲシュタポ(国家秘密警察)は犯人捜索を開始。
そんな中、マーシャ・ノヴォトニー(アンナ・リー)は、立ち寄った八百屋の店先で不審な男を目撃しますが、ゲシュタポから男の行方を尋ねられたマーシャは、男の逃げた道とは反対の方角を教えます。
しかし、その男との偶然の出会いが、マーシャとその家族にとっては波乱の要因となるものでした。
夜の8時以降の外出が禁止されているその日、マーシャの家にひとりの男が現れます。
ヴァニヤックと名乗るその男(ブライアン・ドンレヴィ)は、ゲシュタポを欺いて自分を助けてくれたマーシャにお礼を言いに来たのですが、マーシャの父、ステファン・ノヴォトニー教授(ウォルター・ブレナン)とも親しくなる中、その夜は遅くなったので帰宅することのできなくなったヴァニヤックはマーシャの家で一夜を過ごすことになります。
犯人追求のゲシュタポの手は、嘘をつかれたマーシャの身辺に及び、怪しい男ヴァニヤックをかくまっていたマーシャ一家へと疑惑が移り、やがてノヴォトニー教授はゲシュタポに連れ去られ、プラハの市民たちも人質のために連行されることになります。

父が連れ去られ、処刑されることを恐れたマーシャは、ヴァニヤックのために事件に巻き込まれたことを憤り、ヴァニヤックの居所を突き止め、自首をすすめますが、ヴァニヤックに断られたマーシャはゲシュタポ本部へ通報しようとします。
しかし、プラハ市民やレジスタンスは巧妙にそれを察知し、マーシャの通報を阻みます。
一連の騒動を不審に思ったゲシュタポは、犯人が名乗り上げるまで、連行した市民たちを次々と処刑する方策へと非情性を表していきます。
レジスタンス内部でも動揺が広がる中、ヴァニヤックは自分が自首することもなく、市民たちの処刑を止められる一計を考えつきます。
それは、レジスタンスの中に紛れ込んでいるゲシュタポのスパイ、ビール工場の持ち主、チャカ(ジーン・ロックハート)を犯人に仕立て上げることでした。
レジスタンスの仕組んだ罠の中に入り込みそうになったチャカでしたが、彼には絶対ともいえるアリバイが切り札として残っており、それを証明してくれる警察主任クリューバーの存在が鍵となったのですが、そのクリューバーは行方不明となっていて、クリューバーは後に死体となって発見されます。






ヒロイン、マーシャや、その父で教授のステファン・ノヴォトニー、謎めいたヴァニヤックなど、個性的な人物たちが登場する中で、悪賢く立ち回ろうとするチャカの存在が映画に面白いドラマ性を添えています。
ビール工場主で秘密警察とも内通してレジスタンスの分裂を図ろうとするチャカ。
しかしチャカの悪だくみは自分自身へと跳ね返り、レジスタンスの仕掛けた罠にはまり込んで、ハイドリヒ暗殺事件の犯人として射殺されてしまいます。
このチャカの存在はイソップ物語の寓話を連想させて面白いし、自らの保身のために選んだ策略に自らがはまり込む人間的な哀れさが、なんとなく同情を起こさせてしまう滑稽さも含んでいて印象的でした。
製作が戦時中の1943年で、監督のフリッツ・ラングや原案を担当したベルトルト・ブレヒト、音楽のハンス・アイスラーなど、ドイツからの亡命者によって作られているので、映画としてはナチスに対するプロパガンダの要素を持っていることは確かなのですが、にも関わらず、スリリングな展開や巧妙なストーリーなど、一瞬も目を離せない面白さを持った娯楽要素をタップリと含んでいて、映画史に残る傑作といえます。
映画の背景となっているのは、チェコのイギリス亡命政府などが計画した“エンスポライド作戦”と呼ばれるラインハルト・ハイドリヒ暗殺計画で、当時、秘密警察をも束ねた国家保安本部の長官で、ユダヤ人や他の人種問題を扱っていたハイドリヒは、その冷酷さから“金髪の野獣”“絞首刑人”の異名をもって恐れられていた人物。
映画「死刑執行人もまた死す」は、ハイドリヒ暗殺事件そのものを扱うのではなく、ナチスによる抑圧から解放されたいと願うプラハの市民、そして地下に潜って活動を続けるレジスタンスたちの活動を、暗殺事件を背景に力強く描いたものです。

監督は、「メトロポリス」(1927年)、「月世界の女」(1928年)、「M」(1931年)などの巨匠フリッツ・ラング。
原案には、詩や戯曲などで世界的な影響を与えたベルトルト・ブレヒト。
ヒロイン、マーシャに「わが谷は緑なりき」(1941年)、「アパッチ砦」(1948年)、「馬上の二人」(1961年)など、巨匠ジョン・フォードとも縁の深い美人女優アンナ・リー。
マーシャの父親で大学教授のステファンに、「西部の男」(1940年)でアカデミー賞助演男優賞を受賞。その後「ヨーク軍曹」(1941年)、「荒野の決闘」(1946年)などで、善人や悪役など幅広い演技力を持つウォルター・ブレナン。
特に、「リオ・ブラボー」(1959年)では飄々とした味わいを残しました。
事件の犯人ヴァニヤック(フランツ・スヴォボダ医師)に「大平原」(1939年)、「砂塵」(1939年)、「死の接吻」(1947年)のブライアン・ドンレヴィ。
ゲシュタポに内通するビール工場主チャカに、「群衆」(1941年)、「壮烈第七騎兵隊」(1941年)、「三十四丁目の奇蹟」(1947年)のジーン・ロックハート。




アルフレッド・ヒッチコックばりのとても面白いサスペンス映画であるため、映画が製作された1943年という時代を忘れそうになるほどなのですが、ラストに使われた「NOT THE END」(終わりではない)は、現在もまだ続いているナチスの蛮行と、それと戦い、自由をつかもうとする民衆蜂起を訴えるようなラストの余韻は、映画の世界から一気に現実の狂気の時代へと引き戻され、その時代に苦難をなめた人々の悲痛な思いが伝わってきます。

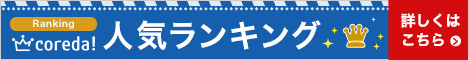



1943年 アメリカ
監督フリッツ・ラング
原案フリッツ・ラング
ベルトルト・ブレヒト
脚本ジョン・ウェクスリー
撮影ジェームズ・ウォン・ハウ
音楽ハンス・アイスラー
〈キャスト〉
ブライアン・ドンレヴィ ウォルター・ブレナン
アンナ・リー ジーン・ロックハート
ヴェネツィア国際映画祭特別賞
ナチス占領下のプラハで実際に起きたナチス副総督、ラインハルト・ハイドリヒ暗殺事件を背景に、ナチスに抑圧されたチェコの民衆、そして反ナチの活動家たちの暗躍と悲劇を、重厚でリアリティーあふれる中に娯楽性を織り交ぜた傑作。

第二次世界大戦下のヨーロッパ、ナチス・ドイツのベーメン・メーレン保護領(チェコ)で、統治者であるラインハルト・ハイドリヒが何者かに狙撃されます。
ゲシュタポ(国家秘密警察)は犯人捜索を開始。
そんな中、マーシャ・ノヴォトニー(アンナ・リー)は、立ち寄った八百屋の店先で不審な男を目撃しますが、ゲシュタポから男の行方を尋ねられたマーシャは、男の逃げた道とは反対の方角を教えます。
しかし、その男との偶然の出会いが、マーシャとその家族にとっては波乱の要因となるものでした。
夜の8時以降の外出が禁止されているその日、マーシャの家にひとりの男が現れます。
ヴァニヤックと名乗るその男(ブライアン・ドンレヴィ)は、ゲシュタポを欺いて自分を助けてくれたマーシャにお礼を言いに来たのですが、マーシャの父、ステファン・ノヴォトニー教授(ウォルター・ブレナン)とも親しくなる中、その夜は遅くなったので帰宅することのできなくなったヴァニヤックはマーシャの家で一夜を過ごすことになります。
犯人追求のゲシュタポの手は、嘘をつかれたマーシャの身辺に及び、怪しい男ヴァニヤックをかくまっていたマーシャ一家へと疑惑が移り、やがてノヴォトニー教授はゲシュタポに連れ去られ、プラハの市民たちも人質のために連行されることになります。

父が連れ去られ、処刑されることを恐れたマーシャは、ヴァニヤックのために事件に巻き込まれたことを憤り、ヴァニヤックの居所を突き止め、自首をすすめますが、ヴァニヤックに断られたマーシャはゲシュタポ本部へ通報しようとします。
しかし、プラハ市民やレジスタンスは巧妙にそれを察知し、マーシャの通報を阻みます。
一連の騒動を不審に思ったゲシュタポは、犯人が名乗り上げるまで、連行した市民たちを次々と処刑する方策へと非情性を表していきます。
レジスタンス内部でも動揺が広がる中、ヴァニヤックは自分が自首することもなく、市民たちの処刑を止められる一計を考えつきます。
それは、レジスタンスの中に紛れ込んでいるゲシュタポのスパイ、ビール工場の持ち主、チャカ(ジーン・ロックハート)を犯人に仕立て上げることでした。
レジスタンスの仕組んだ罠の中に入り込みそうになったチャカでしたが、彼には絶対ともいえるアリバイが切り札として残っており、それを証明してくれる警察主任クリューバーの存在が鍵となったのですが、そのクリューバーは行方不明となっていて、クリューバーは後に死体となって発見されます。
ヒロイン、マーシャや、その父で教授のステファン・ノヴォトニー、謎めいたヴァニヤックなど、個性的な人物たちが登場する中で、悪賢く立ち回ろうとするチャカの存在が映画に面白いドラマ性を添えています。
ビール工場主で秘密警察とも内通してレジスタンスの分裂を図ろうとするチャカ。
しかしチャカの悪だくみは自分自身へと跳ね返り、レジスタンスの仕掛けた罠にはまり込んで、ハイドリヒ暗殺事件の犯人として射殺されてしまいます。
このチャカの存在はイソップ物語の寓話を連想させて面白いし、自らの保身のために選んだ策略に自らがはまり込む人間的な哀れさが、なんとなく同情を起こさせてしまう滑稽さも含んでいて印象的でした。
製作が戦時中の1943年で、監督のフリッツ・ラングや原案を担当したベルトルト・ブレヒト、音楽のハンス・アイスラーなど、ドイツからの亡命者によって作られているので、映画としてはナチスに対するプロパガンダの要素を持っていることは確かなのですが、にも関わらず、スリリングな展開や巧妙なストーリーなど、一瞬も目を離せない面白さを持った娯楽要素をタップリと含んでいて、映画史に残る傑作といえます。
映画の背景となっているのは、チェコのイギリス亡命政府などが計画した“エンスポライド作戦”と呼ばれるラインハルト・ハイドリヒ暗殺計画で、当時、秘密警察をも束ねた国家保安本部の長官で、ユダヤ人や他の人種問題を扱っていたハイドリヒは、その冷酷さから“金髪の野獣”“絞首刑人”の異名をもって恐れられていた人物。
映画「死刑執行人もまた死す」は、ハイドリヒ暗殺事件そのものを扱うのではなく、ナチスによる抑圧から解放されたいと願うプラハの市民、そして地下に潜って活動を続けるレジスタンスたちの活動を、暗殺事件を背景に力強く描いたものです。

監督は、「メトロポリス」(1927年)、「月世界の女」(1928年)、「M」(1931年)などの巨匠フリッツ・ラング。
原案には、詩や戯曲などで世界的な影響を与えたベルトルト・ブレヒト。
ヒロイン、マーシャに「わが谷は緑なりき」(1941年)、「アパッチ砦」(1948年)、「馬上の二人」(1961年)など、巨匠ジョン・フォードとも縁の深い美人女優アンナ・リー。
マーシャの父親で大学教授のステファンに、「西部の男」(1940年)でアカデミー賞助演男優賞を受賞。その後「ヨーク軍曹」(1941年)、「荒野の決闘」(1946年)などで、善人や悪役など幅広い演技力を持つウォルター・ブレナン。
特に、「リオ・ブラボー」(1959年)では飄々とした味わいを残しました。
事件の犯人ヴァニヤック(フランツ・スヴォボダ医師)に「大平原」(1939年)、「砂塵」(1939年)、「死の接吻」(1947年)のブライアン・ドンレヴィ。
ゲシュタポに内通するビール工場主チャカに、「群衆」(1941年)、「壮烈第七騎兵隊」(1941年)、「三十四丁目の奇蹟」(1947年)のジーン・ロックハート。
アルフレッド・ヒッチコックばりのとても面白いサスペンス映画であるため、映画が製作された1943年という時代を忘れそうになるほどなのですが、ラストに使われた「NOT THE END」(終わりではない)は、現在もまだ続いているナチスの蛮行と、それと戦い、自由をつかもうとする民衆蜂起を訴えるようなラストの余韻は、映画の世界から一気に現実の狂気の時代へと引き戻され、その時代に苦難をなめた人々の悲痛な思いが伝わってきます。

2021年01月07日
映画「ブレイブ ワン」‐ ニューヨークの夜に浮かび上がるもう一人の自分, そして衝撃のラストへ
「ブレイブ ワン」(The Brave One ) 2007年
アメリカ / オーストラリア
監督ニール・ジョーダン
脚本ロドリック・テイラー
ブルース・A・テイラー
シンシア・モート
音楽ダリオ・マリアネッリ
撮影フィリップ・ルースロ
〈キャスト〉
ジョディ・フォスター テレンス・ハワード
メアリー・スティーンバージェン
結論から言ってしまえば、女性版「狼よさらば」。
1972年にマイケル・ウィナー監督、チャールズ・ブロンソン主演で作られた「狼よさらば」は、街のチンピラグループに妻を殺され、娘をレイプされた男が、かつてアメリカに根付いていた自警の精神に目覚め、銃を手に入れて犯罪者を処刑(射殺)していくという話でした。
あきらかに「狼よさらば」を下敷きにしたと思われる「ブレイブ ワン」なのですが、違うところは、主人公が男性ではなく若い女性(多少無理はありますが)であるということと、「狼よさらば」が妻子を凌辱した犯人に対する復讐劇ではなく、社会の悪そのものに目を向けられていたのに対し、「ブレイブ ワン」では犯人への復讐に主眼が置かれていること。





エリカ・ベイン(ジョディ・フォスター)はニューヨークでラジオパーソナリティーを務め、恋人デイビッド(ナヴィーン・アンドリュース)との結婚を目前に控えて幸せな日々を送っています。
そんな二人は夜、デイビッドの愛犬を連れて散歩の途中、三人の暴漢にからまれ、袋叩きにされてデイビッドは死亡、エリカは一命をとりとめますが、事件の衝撃から立ち直ることができず、心に傷を負ったまま外出もできない状態が続きます。
警察は事件の捜査をつづけますが、警察署の対応に嫌気がさしたエリカは護身のための銃を買おうと銃器店に入りますが、ライセンス取得のために日数を要すると言われ、銃の購入をあきらめかけた直後、アジア系の男に声をかけられ、闇でオートマチックの拳銃を手に入れます。

ある夜、買い物のために立ち寄ったコンビニエンスストアでエリカは強盗事件に遭遇。店主の女性を射殺した犯人に追い詰められながらも、エリカは強盗を射殺してしまいます。
コンビニ事件を担当したショーン・マーサー刑事(テレンス・ハワード)とも親しくなる中、エリカの中でもう一人の自分が目覚め、地下鉄の暴漢を平然と射殺する、歯止めのきかない自分に気づきます。
事件を捜査するマーサー刑事は、犯人が男性ではなく女性であることに気づき、親しくなったエリカの言動に不審を抱くようになります。
やがて、エリカを襲った暴漢グループの所在が明るみに出始め、破滅を覚悟したエリカはマーサーに別れのメッセージを残し、ひとり、復讐の死地へと向かいます。




「狼よさらば」でもそうでしたが、法の裁きを経ずに犯罪者を処刑してゆく人間に対して、世論からは賛否両論の声が上がります。そして、それはそのまま、映画を見ている私たち観客に対してへの問いかけでもあります。エリカ・ベインのやっていることは正しいのか?
私たちは無法地帯に暮らしているわけではなく、法治国家に住んでいる以上、どんな犯罪者であろうとも法の裁きを経て審判が下されなければいけない。
だから、エリカは間違っている。
しかし、そう単純に決められないところに人間社会の、モヤモヤとした複雑さがあります。


「ブレイブ ワン」でエリカ・ベインの犯す殺人の設定には同じパターンはなくて、コンビニ強盗であったり、地下鉄の暴漢であったり、セックスにからんだ娼婦への暴行、さらに、マーサー刑事たちが追いかけながらも捕まえることできなかった犯罪組織の極悪なボスなどが登場しますが、これは社会悪の暴力の象徴として考えることができます。
それらを抹殺する中でエリカは煩悶します。殺さなくても、銃で脅すだけでよかったのではないか。
しかしまた、人間には自分で気づかないもう一人の自分がいることに気づくことがあります。
「アラビアのロレンス」(1962年)の中で、重傷を負って、とても助かる見込みがないと分かったロレンスの従者の少年を、楽にしてあげようとロレンスが銃で撃ち殺してしまう場面があります。
しかしロレンスは一発で仕留めるのではなく、二発三発と少年の体に銃弾を撃ち込みます。
そのときの邪悪な自分を振り返ってロレンスはこう言います。
「私は彼を殺すことを楽しんでいた」




「ブレイブ ワン」のラストでは、エリカの復讐が遂げられようとしている場面を私たちは目撃するのですが、そこへ現れたマーサー刑事の視点に立って、自分ならどうするだろうという問いかけが突きつけられます。
エリカの殺人をやめさせ、法に従うようエリカを説得するのか、それとも…。
マーサー刑事は「合法的な銃を使え」とエリカに自分の銃を渡し、復讐を遂げさせます。
このラストを、間違っている、と感じるのが正常な感覚であるかとも思います。法の番人たる警察官が殺人に手を貸したのですから。
「目には目を 歯には歯を」は、やられたらやり返せという意味ではありませんが、人の命を奪った者に対しては、その人の命で償うのが本当だと思いますから(明確に犯人が特定された場合に限ります)、映画としての、このラストはいささか衝撃的でしたが、個人的には納得してしまいました。





監督は、「クライング・ゲーム」(1992年)、「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア」(1994年)のニール・ジョーダン。
ヒロイン、エリカ・ベインに、「ダウンタウン物語」、「タクシードライバー」(1976年)で天才子役と騒がれながらも映画界を離れ、後に「告発の行方」(1988年)、「羊たちの沈黙」(1991年)で二度オスカーを受賞したジョディ・フォスター。
エリカの心のよりどころとなるマーサー刑事に、「クラッシュ」、「Ray/レイ」(2004年)などのテレンス・ハワード。
ラジオ局のディレクター、キャロルに「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3」(1990年)、「ギルバート・ブレイク」(1993年)、「ニクソン」(1995年)などの実力派で、1980年の「メルビンとハワード」ではアカデミー賞、ゴールデングローブ賞の助演女優賞を受賞しているメアリー・スティーンバージェン。
暴力という社会的で普遍的なテーマとエンターテインメントをうまく一つにまとめ上げた見応えのある映画。
ただ、欲を言えば、ジョディ・フォスターもいいのですが、さすがに40代半ばに達していて、これから結婚しようという女性を演じるにはちょっと無理があったかなあ。
一度結婚に失敗して、新たな幸せをつかめると思った矢先に暴力事件に巻き込まれるとか、そんなほうが良かったような気もしました。
「羊たちの沈黙」のころだと良かったのですがね。





アメリカ / オーストラリア
監督ニール・ジョーダン
脚本ロドリック・テイラー
ブルース・A・テイラー
シンシア・モート
音楽ダリオ・マリアネッリ
撮影フィリップ・ルースロ
〈キャスト〉
ジョディ・フォスター テレンス・ハワード
メアリー・スティーンバージェン
結論から言ってしまえば、女性版「狼よさらば」。
1972年にマイケル・ウィナー監督、チャールズ・ブロンソン主演で作られた「狼よさらば」は、街のチンピラグループに妻を殺され、娘をレイプされた男が、かつてアメリカに根付いていた自警の精神に目覚め、銃を手に入れて犯罪者を処刑(射殺)していくという話でした。
あきらかに「狼よさらば」を下敷きにしたと思われる「ブレイブ ワン」なのですが、違うところは、主人公が男性ではなく若い女性(多少無理はありますが)であるということと、「狼よさらば」が妻子を凌辱した犯人に対する復讐劇ではなく、社会の悪そのものに目を向けられていたのに対し、「ブレイブ ワン」では犯人への復讐に主眼が置かれていること。

エリカ・ベイン(ジョディ・フォスター)はニューヨークでラジオパーソナリティーを務め、恋人デイビッド(ナヴィーン・アンドリュース)との結婚を目前に控えて幸せな日々を送っています。
そんな二人は夜、デイビッドの愛犬を連れて散歩の途中、三人の暴漢にからまれ、袋叩きにされてデイビッドは死亡、エリカは一命をとりとめますが、事件の衝撃から立ち直ることができず、心に傷を負ったまま外出もできない状態が続きます。
警察は事件の捜査をつづけますが、警察署の対応に嫌気がさしたエリカは護身のための銃を買おうと銃器店に入りますが、ライセンス取得のために日数を要すると言われ、銃の購入をあきらめかけた直後、アジア系の男に声をかけられ、闇でオートマチックの拳銃を手に入れます。

ある夜、買い物のために立ち寄ったコンビニエンスストアでエリカは強盗事件に遭遇。店主の女性を射殺した犯人に追い詰められながらも、エリカは強盗を射殺してしまいます。
コンビニ事件を担当したショーン・マーサー刑事(テレンス・ハワード)とも親しくなる中、エリカの中でもう一人の自分が目覚め、地下鉄の暴漢を平然と射殺する、歯止めのきかない自分に気づきます。
事件を捜査するマーサー刑事は、犯人が男性ではなく女性であることに気づき、親しくなったエリカの言動に不審を抱くようになります。
やがて、エリカを襲った暴漢グループの所在が明るみに出始め、破滅を覚悟したエリカはマーサーに別れのメッセージを残し、ひとり、復讐の死地へと向かいます。
「狼よさらば」でもそうでしたが、法の裁きを経ずに犯罪者を処刑してゆく人間に対して、世論からは賛否両論の声が上がります。そして、それはそのまま、映画を見ている私たち観客に対してへの問いかけでもあります。エリカ・ベインのやっていることは正しいのか?
私たちは無法地帯に暮らしているわけではなく、法治国家に住んでいる以上、どんな犯罪者であろうとも法の裁きを経て審判が下されなければいけない。
だから、エリカは間違っている。
しかし、そう単純に決められないところに人間社会の、モヤモヤとした複雑さがあります。
「ブレイブ ワン」でエリカ・ベインの犯す殺人の設定には同じパターンはなくて、コンビニ強盗であったり、地下鉄の暴漢であったり、セックスにからんだ娼婦への暴行、さらに、マーサー刑事たちが追いかけながらも捕まえることできなかった犯罪組織の極悪なボスなどが登場しますが、これは社会悪の暴力の象徴として考えることができます。
それらを抹殺する中でエリカは煩悶します。殺さなくても、銃で脅すだけでよかったのではないか。
しかしまた、人間には自分で気づかないもう一人の自分がいることに気づくことがあります。
「アラビアのロレンス」(1962年)の中で、重傷を負って、とても助かる見込みがないと分かったロレンスの従者の少年を、楽にしてあげようとロレンスが銃で撃ち殺してしまう場面があります。
しかしロレンスは一発で仕留めるのではなく、二発三発と少年の体に銃弾を撃ち込みます。
そのときの邪悪な自分を振り返ってロレンスはこう言います。
「私は彼を殺すことを楽しんでいた」
「ブレイブ ワン」のラストでは、エリカの復讐が遂げられようとしている場面を私たちは目撃するのですが、そこへ現れたマーサー刑事の視点に立って、自分ならどうするだろうという問いかけが突きつけられます。
エリカの殺人をやめさせ、法に従うようエリカを説得するのか、それとも…。
マーサー刑事は「合法的な銃を使え」とエリカに自分の銃を渡し、復讐を遂げさせます。
このラストを、間違っている、と感じるのが正常な感覚であるかとも思います。法の番人たる警察官が殺人に手を貸したのですから。
「目には目を 歯には歯を」は、やられたらやり返せという意味ではありませんが、人の命を奪った者に対しては、その人の命で償うのが本当だと思いますから(明確に犯人が特定された場合に限ります)、映画としての、このラストはいささか衝撃的でしたが、個人的には納得してしまいました。

監督は、「クライング・ゲーム」(1992年)、「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア」(1994年)のニール・ジョーダン。
ヒロイン、エリカ・ベインに、「ダウンタウン物語」、「タクシードライバー」(1976年)で天才子役と騒がれながらも映画界を離れ、後に「告発の行方」(1988年)、「羊たちの沈黙」(1991年)で二度オスカーを受賞したジョディ・フォスター。
エリカの心のよりどころとなるマーサー刑事に、「クラッシュ」、「Ray/レイ」(2004年)などのテレンス・ハワード。
ラジオ局のディレクター、キャロルに「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3」(1990年)、「ギルバート・ブレイク」(1993年)、「ニクソン」(1995年)などの実力派で、1980年の「メルビンとハワード」ではアカデミー賞、ゴールデングローブ賞の助演女優賞を受賞しているメアリー・スティーンバージェン。
暴力という社会的で普遍的なテーマとエンターテインメントをうまく一つにまとめ上げた見応えのある映画。
ただ、欲を言えば、ジョディ・フォスターもいいのですが、さすがに40代半ばに達していて、これから結婚しようという女性を演じるにはちょっと無理があったかなあ。
一度結婚に失敗して、新たな幸せをつかめると思った矢先に暴力事件に巻き込まれるとか、そんなほうが良かったような気もしました。
「羊たちの沈黙」のころだと良かったのですがね。

2020年11月21日
映画「恐怖の報酬」1977年版 吼えるトラック、命を懸けた男たちの報酬とは
「恐怖の報酬」(Sorcerer ) 1977年アメリカ
監督ウィリアム・フリードキン
脚本ウォロン・グリーン
音楽タンジェリン・ドリーム
キース・ジャレット
原作ジョルジュ・アルノー
撮影ジョン・M・スティーブンス
〈キャスト〉
ロイ・シャイダー ブリュノ・クレメール
フランシスコ・ラバル アミドウ

私の映画好きの原点になったのが、アンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督のフランス映画「恐怖の報酬」(1953年)で、これは当時小学校五年生くらいのころにテレビで放映されていたのを見た覚えがあります(しかも朝の番組)。
ニトロをトラックで運ぶ男たちの話で、その背景となったいきさつはよく分かりませんでしたが、全体を貫く緊張感と、時折り見せるユーモア(二人並んで立ちションをする場面は妙に印象的)、その中でも、油が溜まって沼のようになった道を必死に通り抜けようとする二人の男。
滑るタイヤの下で一人の足が下敷きになり、悲鳴の中でそれを乗り越えてトラックを前進させる鬼気迫る迫力は圧倒的で、映画ファンとなるキッカケを作ってくれた傑作でした。
クルーゾー監督版「恐怖の報酬」からおよそ24年後に撮られたウィリアム・フリードキン監督による「恐怖の報酬」は、クルーゾー監督版のリメイクです。
簡単にあらすじを追ってゆくと。
殺し屋ニーロ(フランシスコ・ラバル)と、莫大な負債を抱えてフランスから逃亡した銀行員セラーノ(ブリュノ・クレメール)、強盗の末に組織から追われる羽目になったドミンゲス(ロイ・シャイダー)、テロの実行犯で逮捕を逃れたカッセム(アミドウ)たちは、事情が異なりながらも祖国から離れ、吹き溜まりのような南米の村に身を潜めて暮らしています。
故国に帰って元の生活に戻りたいと切望しますが、金は無く、社会の目を逃れている立場としては思うように身動きがとれません。
とにかく金さえ手に入ればなんとかなる、そんな彼らの前に、遠く離れた油井での爆発事故が発生します。
大爆発とともに発生した火災を消すためには爆風によるしかないと専門家は判断。
ニトログリセリンの威力を借りて火災を消すことになりますが、遠く離れた油井まで、少しの振動でも爆発するような危険なニトロをどうやって運ぶのか。
空からの輸送も考えられましたが、乱気流に巻き込まれる恐れがあると、その意見は却下され、トラックで運ぶことに決定します。
しかし問題は人選で、まかり間違えば一瞬で自分たちが吹き飛んでしまうような恐怖の輸送です。
それでも、高額な報酬とあって何人かが募集に応じて運転の腕前を試された結果、残ったのは、ドミンゲス、ニーロ、カッセム、セラーノの4人。
4トンほどのボロボロのトラック2台に二人一組となって乗り込み、悪路と悪天候の待ち受ける長い道のりを進むことになります。

息を飲むスリルと悪臭も漂ってきそうな南米の村の情景、命を懸けた男たちが挑む、狂気すら孕(はら)んだ死に物狂いの戦い。
「フレンチ・コネクション」(1971年)、「エクソシスト」(1973年)で鬼才と評されたウィリアム・フリードキンが、オレはこういう映画を作りたいんだ! と全霊を込めて作り上げたような作品でしたが、封切り当時は見事に惨敗。
惨敗の理由はなんとなく分かるような気がします。
クルーゾー版「恐怖の報酬」のリメイクということで、どうしてもそちらと比較されてしまいます。これはリメイクの宿命なので仕方がないのですが、サスペンスと同時に当時の社会状況、そこに生きる人間たちのドラマを重厚に扱った53年版と比較して、サスペンス一辺倒で押しまくったフリードキン版「恐怖の報酬」の評価が下がるのはもっともなことです。
それに前半の、それぞれの背景を持った4人が南米へ落ち延びる過程が長過ぎて、ひとつひとつのエピソードは面白いのですが、セリフを極力排しているためか説明不足になっていて、現金強盗の失敗で追われる身となるロイ・シャイダー以外の3人の背景が分かりにくい。
オリジナル完全版は2時間を超えていますが、封切り当時の上映時間が90分ほどとなったのは前半をかなりカットしたためだと思われます。
「大脱走」(1963年)のダイジェスト版(テレビ放映)が、殿様の膳に供された“目黒のサンマ”のように脂っ気を抜かれて味わいのないものであったように、2時間を超える大作をズタズタに切ってしまったのでは惨敗するのが当たり前。
フリードキンの作品として最も好きな「L.A.大走査線/ 狼たちの街」を何度も繰り返して見ているフリードキンファンの私として感じることは、リメイク版「恐怖の報酬」はウィリアム・フリードキンの力量が存分に発揮された映画であるということです。

クルーゾー版「恐怖の報酬」と比較するのは意味のないことです。
前半が説明不足でやけに長い。これも置いておきましょう。
後に公開されたフランシス・F・コッポラの「地獄の黙示録」(1979年)の、むせかえるようなジャングル、アラン・パーカーの「エンゼル・ハート」(1987年)における猥雑なニューヨークやニュー・オーリンズの湿度感。そういった、映画の背景に塗り込められた、巨匠たちが生み出したリアリズムがフリードキン版「恐怖の報酬」には満ちています。
それだけではなく、映画のハイライトと呼んでもいいような、暴風雨の吹き荒れる朽ちた吊り橋をトラックで渡り切ろうとする緊張感と迫力は圧巻。トラックがまるで巨大な猛獣のごとく咆哮しながら、のたうつようにジリジリと進む場面は、まさに最大の見せ場といってもよく、数ある映画の中でも最高にスリリングなシーンのひとつといえます。




主演は「フレンチ・コネクション」(1971年)、「ジョーズ」(1975年)、「2010年」(1984年)などのロイ・シャイダー。
元銀行家のセラーノにフランス俳優ブリュノ・クレメール。
殺し屋ニーロに「太陽はひとりぼっち」(1962年)、「昼顔」(1967年)、そして1984年の「無垢なる聖者」でカンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞したフランシスコ・ラバル。




原題は「Sorcerer」(魔術師)。
映画の内容からすれば「魔術師」という題名はピンときませんが、数々の難関を切り抜けて成功する一連の行動が魔術師のようだということでしょうか。
それはさておき、映画の最後に「アンリ=ジョルジュ・クルーゾーに捧げる」と流れたように、クルーゾー版「恐怖の報酬」を念頭に置きながら、サスペンスを存分に盛り込んだフリードキン版「恐怖の報酬」は娯楽映画の醍醐味を十二分に味わえるものだといえます。





監督ウィリアム・フリードキン
脚本ウォロン・グリーン
音楽タンジェリン・ドリーム
キース・ジャレット
原作ジョルジュ・アルノー
撮影ジョン・M・スティーブンス
〈キャスト〉
ロイ・シャイダー ブリュノ・クレメール
フランシスコ・ラバル アミドウ

私の映画好きの原点になったのが、アンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督のフランス映画「恐怖の報酬」(1953年)で、これは当時小学校五年生くらいのころにテレビで放映されていたのを見た覚えがあります(しかも朝の番組)。
ニトロをトラックで運ぶ男たちの話で、その背景となったいきさつはよく分かりませんでしたが、全体を貫く緊張感と、時折り見せるユーモア(二人並んで立ちションをする場面は妙に印象的)、その中でも、油が溜まって沼のようになった道を必死に通り抜けようとする二人の男。
滑るタイヤの下で一人の足が下敷きになり、悲鳴の中でそれを乗り越えてトラックを前進させる鬼気迫る迫力は圧倒的で、映画ファンとなるキッカケを作ってくれた傑作でした。
クルーゾー監督版「恐怖の報酬」からおよそ24年後に撮られたウィリアム・フリードキン監督による「恐怖の報酬」は、クルーゾー監督版のリメイクです。
簡単にあらすじを追ってゆくと。
殺し屋ニーロ(フランシスコ・ラバル)と、莫大な負債を抱えてフランスから逃亡した銀行員セラーノ(ブリュノ・クレメール)、強盗の末に組織から追われる羽目になったドミンゲス(ロイ・シャイダー)、テロの実行犯で逮捕を逃れたカッセム(アミドウ)たちは、事情が異なりながらも祖国から離れ、吹き溜まりのような南米の村に身を潜めて暮らしています。
故国に帰って元の生活に戻りたいと切望しますが、金は無く、社会の目を逃れている立場としては思うように身動きがとれません。
とにかく金さえ手に入ればなんとかなる、そんな彼らの前に、遠く離れた油井での爆発事故が発生します。
大爆発とともに発生した火災を消すためには爆風によるしかないと専門家は判断。
ニトログリセリンの威力を借りて火災を消すことになりますが、遠く離れた油井まで、少しの振動でも爆発するような危険なニトロをどうやって運ぶのか。
空からの輸送も考えられましたが、乱気流に巻き込まれる恐れがあると、その意見は却下され、トラックで運ぶことに決定します。
しかし問題は人選で、まかり間違えば一瞬で自分たちが吹き飛んでしまうような恐怖の輸送です。
それでも、高額な報酬とあって何人かが募集に応じて運転の腕前を試された結果、残ったのは、ドミンゲス、ニーロ、カッセム、セラーノの4人。
4トンほどのボロボロのトラック2台に二人一組となって乗り込み、悪路と悪天候の待ち受ける長い道のりを進むことになります。

息を飲むスリルと悪臭も漂ってきそうな南米の村の情景、命を懸けた男たちが挑む、狂気すら孕(はら)んだ死に物狂いの戦い。
「フレンチ・コネクション」(1971年)、「エクソシスト」(1973年)で鬼才と評されたウィリアム・フリードキンが、オレはこういう映画を作りたいんだ! と全霊を込めて作り上げたような作品でしたが、封切り当時は見事に惨敗。
惨敗の理由はなんとなく分かるような気がします。
クルーゾー版「恐怖の報酬」のリメイクということで、どうしてもそちらと比較されてしまいます。これはリメイクの宿命なので仕方がないのですが、サスペンスと同時に当時の社会状況、そこに生きる人間たちのドラマを重厚に扱った53年版と比較して、サスペンス一辺倒で押しまくったフリードキン版「恐怖の報酬」の評価が下がるのはもっともなことです。
それに前半の、それぞれの背景を持った4人が南米へ落ち延びる過程が長過ぎて、ひとつひとつのエピソードは面白いのですが、セリフを極力排しているためか説明不足になっていて、現金強盗の失敗で追われる身となるロイ・シャイダー以外の3人の背景が分かりにくい。
オリジナル完全版は2時間を超えていますが、封切り当時の上映時間が90分ほどとなったのは前半をかなりカットしたためだと思われます。
「大脱走」(1963年)のダイジェスト版(テレビ放映)が、殿様の膳に供された“目黒のサンマ”のように脂っ気を抜かれて味わいのないものであったように、2時間を超える大作をズタズタに切ってしまったのでは惨敗するのが当たり前。
フリードキンの作品として最も好きな「L.A.大走査線/ 狼たちの街」を何度も繰り返して見ているフリードキンファンの私として感じることは、リメイク版「恐怖の報酬」はウィリアム・フリードキンの力量が存分に発揮された映画であるということです。

クルーゾー版「恐怖の報酬」と比較するのは意味のないことです。
前半が説明不足でやけに長い。これも置いておきましょう。
後に公開されたフランシス・F・コッポラの「地獄の黙示録」(1979年)の、むせかえるようなジャングル、アラン・パーカーの「エンゼル・ハート」(1987年)における猥雑なニューヨークやニュー・オーリンズの湿度感。そういった、映画の背景に塗り込められた、巨匠たちが生み出したリアリズムがフリードキン版「恐怖の報酬」には満ちています。
それだけではなく、映画のハイライトと呼んでもいいような、暴風雨の吹き荒れる朽ちた吊り橋をトラックで渡り切ろうとする緊張感と迫力は圧巻。トラックがまるで巨大な猛獣のごとく咆哮しながら、のたうつようにジリジリと進む場面は、まさに最大の見せ場といってもよく、数ある映画の中でも最高にスリリングなシーンのひとつといえます。
主演は「フレンチ・コネクション」(1971年)、「ジョーズ」(1975年)、「2010年」(1984年)などのロイ・シャイダー。
元銀行家のセラーノにフランス俳優ブリュノ・クレメール。
殺し屋ニーロに「太陽はひとりぼっち」(1962年)、「昼顔」(1967年)、そして1984年の「無垢なる聖者」でカンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞したフランシスコ・ラバル。
原題は「Sorcerer」(魔術師)。
映画の内容からすれば「魔術師」という題名はピンときませんが、数々の難関を切り抜けて成功する一連の行動が魔術師のようだということでしょうか。
それはさておき、映画の最後に「アンリ=ジョルジュ・クルーゾーに捧げる」と流れたように、クルーゾー版「恐怖の報酬」を念頭に置きながら、サスペンスを存分に盛り込んだフリードキン版「恐怖の報酬」は娯楽映画の醍醐味を十二分に味わえるものだといえます。

2019年12月14日
映画「死刑台のエレベーター」- 二組の男女が織り成す愛の結末
「死刑台のエレベーター」
(Ascenseur pour l'échafaud) 1957年 フランス
監督ルイ・マル
脚本ロジェ・ニミエ
ルイ・マル
原作ノエル・カレフ
撮影アンリ・ドカエ
音楽マイルス・デイヴィス
〈キャスト〉
モーリス・ロネ ジャンヌ・モロー
ジョルジュ・プージュリー ヨリ・ベルタン
1957年ルイ・デリュック賞受賞(ルイ・マル)
濡れたようにしっとりと潤んだ瞳、挑発的で退廃的な唇、フランスを代表する名女優ジャンヌ・モローのクローズアップで始まるこの映画は、甘く湿った緊張感と共に一気に映画の世界に引き込まれます。
世界映画界に衝撃を与えた若干25歳のルイ・マル監督のデビュー作として名高い本作ですが、同時に、本作以降ヌーベルバーグの立役者として存在感を発揮することになる名手アンリ・ドカエの冴えわたる撮影が素晴らしい効果を発揮しています。





「もう耐えられない、…愛してるわジュリアン」
社長夫人フロランス・カララ(ジャンヌ・モロー)は、電話の相手ジュリアン・タベルニエ(モーリス・ロネ)にささやきかけます。
愛人関係にあるフロランスとジュリアンは、フロランスの夫でジュリアンが勤める会社の社長であるサイモン・カララ(ジャン・ウォール)を殺そうと計画しています。
計画は実行に移され、自分のオフィスから社長室に忍び込んだジュリアンはサイモンを射殺。
拳銃を握らせて自殺に見せかけます。
計画は成功し、ジュリアンは会社を出ようとしますが、社長室に忍び込むために使ったロープがそのままになっていることに気づきます。
あわてて会社に引き返し、エレベーターに乗ったジュリアンでしたが、終業時間をとっくに過ぎていることもあり、保安係によってエレベーターの電源が落とされます。
真っ暗になったエレベーターの中に閉じ込められることになったジュリアン。

一方、会社の外では花屋の店員ベロニク(ヨリ・ベルタン)と恋人のルイ(ジョルジュ・プージュリー)が路上に放置されているジュリアンの車を見つけ、反抗心むき出しの不良のルイが車に乗り込み、二人はジュリアンの車を盗んでドライブに出かけてしまいます。
約束の時間を過ぎても現れないジュリアンに不審を抱き、彼を探そうと夜のパリをさまよい歩くフロランス。
そして事件は意外な方向へと発展してゆきます。
ベロニクとルイはモーテルでドイツ人夫婦と知り合いになり、シャンパンと葉巻で一夜を過ごすのですが、ドイツ人のスポーツカーを盗もうとしたルイが見つかり、ジュリアンの拳銃でドイツ人を射殺してしまいます。
一夜が明け、ようやくエレベーターから解放されたジュリアンでしたが、彼を待っていたのはドイツ人殺しの容疑でした。
社長の自殺死体も発見され、シェリエ警部(リノ・ヴァンチュラ)が捜査に乗り出します。
ジュリアンの車が盗まれ、助手席に乗る花屋のベロニクを目撃していたフロランスは、ドイツ人殺しは二人の仕業だと警察に通報。
ルイは逮捕されますが、フロランスとジュリアンの関係を怪しいとみたシェリエは、社長殺しは計画されたものではないかと疑念を持ちます。
ジュリアンとの関係を否定したフロランスでしたが…。





完全犯罪として計画された殺人は、なんなく成功するように思われたのですが…。
こんな場面があります。
社長を射殺したジュリアンがふと顔を上げると、窓の外を黒猫がゆっくりと歩いている。完全犯罪が失敗に終わるであろうことを暗示させる場面だと思われます。
世の中、そううまくいかないもの。どこかに落とし穴が潜んでいるものですが、ジュリアンの場合は社長室へ忍び込むために使ったロープが命取りになりました。
しかしこのロープ、先端に引っ掛けるためのかぎが付いているシロモノで、事を成したあと、ジュリアンはふたたびこのロープで下へ降りているのですから、殺人を計画したときにロープの回収をどうするかということは考えなかったのかな、という疑問が生じます。
下へ降りてしまえばロープは回収できませんし、ロープを外して下へ落とせば自分が戻れない。
しかも、ジュリアンがエレベーターに閉じ込められているあいだにロープはいつの間にか会社の外に落ちてしまっている。
一見、脚本のミスなのか、編集上の手違いなのかと思われるこのロープ、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」を裏返しにしたような、ひとりの人間の運命を左右する魔性の小道具のようにも思われます。






フロランス・カララに「雨のしのび逢い」(1960年)、「突然炎のごとく」(1962年)のジャンヌ・モロー。
ジュリアン・タベルニエに「太陽がいっぱい」(1960年)、「鬼火」(1963年)のモーリス・ロネ。
不良青年ルイに「禁じられた遊び」(1952年)の名子役ジョルジュ・プージュリー。
その恋人ベロニクに「修道女」(1996年)のヨリ・ベルタン。
事件を追うシェリエ警部に「モンパルナスの灯」(1958年)、「冒険者たち」(1967年)のリノ・ヴァンチュラ。
全編をおおう緊張感の中に退廃的でけだるいムードを醸し出すジャズの帝王マイルス・デイヴィスのトランペット。
とりわけ、夜のパリをさまようフロランスの心情を見事に表現したように流れる曲は映画音楽史上に残る名曲といえます。




完全犯罪がもろくも崩れ去るラストの暗室に浮かび上がるフロランスとジュリアンの幸福感あふれる現像写真。
見事な幕切れで、犯罪を証明したような証拠写真でありながら、それを見つめるフロランスの表情には愛しい時代を懐かしむような幸せそうな笑みがこぼれているのが、むしろ見ているほうが切なくなるようなラストでした。
原作はノエル・カレフの推理小説で、こちらは金目当ての殺人なのですが、ルイ・マルは男女の愛に置き換え、道ならぬ不倫関係のフロランスとジュリアン、無軌道な青春像のベロニクとルイという二組の恋人たちが織り成す破滅的な恋の結末を描いています。
1950年代、フランス映画が輝いていたころの傑作です。





(Ascenseur pour l'échafaud) 1957年 フランス
監督ルイ・マル
脚本ロジェ・ニミエ
ルイ・マル
原作ノエル・カレフ
撮影アンリ・ドカエ
音楽マイルス・デイヴィス
〈キャスト〉
モーリス・ロネ ジャンヌ・モロー
ジョルジュ・プージュリー ヨリ・ベルタン
1957年ルイ・デリュック賞受賞(ルイ・マル)
濡れたようにしっとりと潤んだ瞳、挑発的で退廃的な唇、フランスを代表する名女優ジャンヌ・モローのクローズアップで始まるこの映画は、甘く湿った緊張感と共に一気に映画の世界に引き込まれます。
世界映画界に衝撃を与えた若干25歳のルイ・マル監督のデビュー作として名高い本作ですが、同時に、本作以降ヌーベルバーグの立役者として存在感を発揮することになる名手アンリ・ドカエの冴えわたる撮影が素晴らしい効果を発揮しています。

「もう耐えられない、…愛してるわジュリアン」
社長夫人フロランス・カララ(ジャンヌ・モロー)は、電話の相手ジュリアン・タベルニエ(モーリス・ロネ)にささやきかけます。
愛人関係にあるフロランスとジュリアンは、フロランスの夫でジュリアンが勤める会社の社長であるサイモン・カララ(ジャン・ウォール)を殺そうと計画しています。
計画は実行に移され、自分のオフィスから社長室に忍び込んだジュリアンはサイモンを射殺。
拳銃を握らせて自殺に見せかけます。
計画は成功し、ジュリアンは会社を出ようとしますが、社長室に忍び込むために使ったロープがそのままになっていることに気づきます。
あわてて会社に引き返し、エレベーターに乗ったジュリアンでしたが、終業時間をとっくに過ぎていることもあり、保安係によってエレベーターの電源が落とされます。
真っ暗になったエレベーターの中に閉じ込められることになったジュリアン。

一方、会社の外では花屋の店員ベロニク(ヨリ・ベルタン)と恋人のルイ(ジョルジュ・プージュリー)が路上に放置されているジュリアンの車を見つけ、反抗心むき出しの不良のルイが車に乗り込み、二人はジュリアンの車を盗んでドライブに出かけてしまいます。
約束の時間を過ぎても現れないジュリアンに不審を抱き、彼を探そうと夜のパリをさまよい歩くフロランス。
そして事件は意外な方向へと発展してゆきます。
ベロニクとルイはモーテルでドイツ人夫婦と知り合いになり、シャンパンと葉巻で一夜を過ごすのですが、ドイツ人のスポーツカーを盗もうとしたルイが見つかり、ジュリアンの拳銃でドイツ人を射殺してしまいます。
一夜が明け、ようやくエレベーターから解放されたジュリアンでしたが、彼を待っていたのはドイツ人殺しの容疑でした。
社長の自殺死体も発見され、シェリエ警部(リノ・ヴァンチュラ)が捜査に乗り出します。
ジュリアンの車が盗まれ、助手席に乗る花屋のベロニクを目撃していたフロランスは、ドイツ人殺しは二人の仕業だと警察に通報。
ルイは逮捕されますが、フロランスとジュリアンの関係を怪しいとみたシェリエは、社長殺しは計画されたものではないかと疑念を持ちます。
ジュリアンとの関係を否定したフロランスでしたが…。

完全犯罪として計画された殺人は、なんなく成功するように思われたのですが…。
こんな場面があります。
社長を射殺したジュリアンがふと顔を上げると、窓の外を黒猫がゆっくりと歩いている。完全犯罪が失敗に終わるであろうことを暗示させる場面だと思われます。
世の中、そううまくいかないもの。どこかに落とし穴が潜んでいるものですが、ジュリアンの場合は社長室へ忍び込むために使ったロープが命取りになりました。
しかしこのロープ、先端に引っ掛けるためのかぎが付いているシロモノで、事を成したあと、ジュリアンはふたたびこのロープで下へ降りているのですから、殺人を計画したときにロープの回収をどうするかということは考えなかったのかな、という疑問が生じます。
下へ降りてしまえばロープは回収できませんし、ロープを外して下へ落とせば自分が戻れない。
しかも、ジュリアンがエレベーターに閉じ込められているあいだにロープはいつの間にか会社の外に落ちてしまっている。
一見、脚本のミスなのか、編集上の手違いなのかと思われるこのロープ、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」を裏返しにしたような、ひとりの人間の運命を左右する魔性の小道具のようにも思われます。
フロランス・カララに「雨のしのび逢い」(1960年)、「突然炎のごとく」(1962年)のジャンヌ・モロー。
ジュリアン・タベルニエに「太陽がいっぱい」(1960年)、「鬼火」(1963年)のモーリス・ロネ。
不良青年ルイに「禁じられた遊び」(1952年)の名子役ジョルジュ・プージュリー。
その恋人ベロニクに「修道女」(1996年)のヨリ・ベルタン。
事件を追うシェリエ警部に「モンパルナスの灯」(1958年)、「冒険者たち」(1967年)のリノ・ヴァンチュラ。
全編をおおう緊張感の中に退廃的でけだるいムードを醸し出すジャズの帝王マイルス・デイヴィスのトランペット。
とりわけ、夜のパリをさまようフロランスの心情を見事に表現したように流れる曲は映画音楽史上に残る名曲といえます。
完全犯罪がもろくも崩れ去るラストの暗室に浮かび上がるフロランスとジュリアンの幸福感あふれる現像写真。
見事な幕切れで、犯罪を証明したような証拠写真でありながら、それを見つめるフロランスの表情には愛しい時代を懐かしむような幸せそうな笑みがこぼれているのが、むしろ見ているほうが切なくなるようなラストでした。
原作はノエル・カレフの推理小説で、こちらは金目当ての殺人なのですが、ルイ・マルは男女の愛に置き換え、道ならぬ不倫関係のフロランスとジュリアン、無軌道な青春像のベロニクとルイという二組の恋人たちが織り成す破滅的な恋の結末を描いています。
1950年代、フランス映画が輝いていたころの傑作です。

2019年10月10日
映画「ジャッカルの日」- 標的はド・ゴール、周到な準備で計画を遂行する殺し屋ジャッカル
「ジャッカルの日」(The Day of the Jackal)
1973年 イギリス/フランス
監督フレッド・ジンネマン
原作フレデリック・フォーサイス
脚本ケネス・ロス
撮影ジャン・トゥルニエ
音楽ジョルジュ・ドルリュー
〈キャスト〉
エドワード・フォックス マイケル・ロンズデール
デルフィーヌ・セイリグ




フランス第18代大統領シャルル・ド・ゴールを狙った暗殺事件を、「真昼の決闘」(1952年)、「地上より永遠に」(1953年)、「わが命つきるとも」(1966年)の名匠フレッド・ジンネマンが、周到に積み上げた細部と史実に基づいて、ド・ゴール暗殺を目論む武装組織の暗躍を背景に、暗殺を依頼された一匹狼の殺し屋ジャッカルと、暗殺を阻止しようとジャッカルを追い詰めるフランス官憲のクロード・ルベル警視の活躍を描いたサスペンス映画の傑作。
1962年、OAS(フランス極右民族主義)によるド・ゴール暗殺未遂事件が起こり、首謀者は逮捕、さらに銃殺。
当局の締め付けが厳しくなったOASは壊滅状態に陥ります。
OASによるド・ゴール暗殺の最後の切り札として登場したのが、国籍不明の殺し屋、暗号名ジャッカル(エドワード・フォックス)です。

50万ドルの契約で仕事を引き受けたジャッカルは着々と準備を進めます。
身分証明書を偽造し、精巧な狙撃銃を作らせたジャッカルはフランスへと進入。
ド・ゴール暗殺の機会をうかがいます。
一方、50万ドルという破格の契約のために資金を確保しなければならなくなったOASは銀行強盗を決行。
現金強奪にはいくつか成功しますが、テロを警戒したフランス当局は厳重な包囲網を敷き、強盗の一人を狙撃して逮捕。
尋問からOASの計画の断片を察知した大統領官邸は、ド・ゴール大統領を狙う正体不明の暗殺者捜索のためにフランス警察の腕利き、クロード・ルベル警視(マイケル・ロンズデール)を招集することになります。
パッとしない風采でボソボソとした話し方のルベルは、体こそ大きいものの、茫洋とした感じで切れ者のイメージからはほど遠い男なのですが、粘り強く、少ない情報を元に殺し屋ジャッカルの足取りをつかんでゆきます。
治安組織の動きを察知するため、フランス治安当局の官僚に近づいたOASのジャクリーヌは、機密情報を盗み出してOASに流し、その情報を元にジャッカルは当局やルベル警視の目を潜(くぐ)り抜けてパリへ潜入してゆきます。

一向に手がかりのつかめないジャッカルの足取りに疑問を感じたルベルは、内部から情報が洩れていることを突き止め、やがて、ド・ゴール暗殺のためのジャッカルの計画がパリ解放記念式典にあることに気づきます。
ジャクリーヌが逮捕され、足取りが察知されていることを感じたジャッカルは、計画を思いとどまることなく、むしろ敢然と挑むように渦中に飛び込んでゆきます。
8月25日のその日、大勢のパリ市民でにぎわいを見せる中、厳重な警戒網の目をくぐって、松葉づえをついた片足の男がアパートへの帰宅のために歩いています。
傷痍軍人に変装したジャッカルです。
シャルル・ド・ゴールが記念式典に参列。
アパートに侵入したジャッカルは狙撃の機会を待ちます。
躍起になってジャッカルの姿を探すルベルは、一人の男が警戒の目を抜けていたことを察知。男が向かったアパートに駆け込みます。
ド・ゴールが勲章授与のために進み出た瞬間、ジャッカルは狙撃銃の引き金を引きます。






私は高校時代、この映画を映画館で観ましたが、正直に言って何が何だかよく分かりませんでした。
当時「ジャッカルの日」は大きな話題になっていて、シャルル・ド・ゴールを狙う殺し屋の話として映画ファンの間で盛り上がっていたこともあったので、単純にアクション映画としてしか考えなかった私は(なにしろ「ダーティハリー」や「フレンチ・コネクション」の時代でしたから)、心に大きな空白を抱いて帰宅することになりました。
今でもよく覚えているシーンは、狙撃銃を手に入れたジャッカルが山の中で、木の枝に吊るしたスイカを標的に銃の精度を調節するシーンと、サウナで知り合った友人を殺害するシーン。
この二つだけで、その他はほとんど覚えていません。
なぜよく分からなかったのかというのは、その背景となっている国際情勢の流れと、どうしてド・ゴールを暗殺しなければいけないのか、ということだったのでしょう。

●シャルル・ド・ゴール暗殺の理由は?
植民地政策を執る欧米列強の中で、フランスはインドシナや北アフリカへ侵攻。
1847年にはアルジェリアを支配します。
しかしアルジェリアでは各地で独立運動が起き、FLN(民族解放戦線)の武装蜂起によって1954年にはフランスの支配に対するアルジェリアの独立戦争が勃発。
一方、1890年にフランス北部のリールで生まれたド・ゴールは、陸軍軍人や首相を経験しながら1959年に大統領に就任。
第二次世界大戦のナチス・ドイツによる占領や、第一次インドシナ戦争で疲弊したフランスの国力なども考慮して、ド・ゴールはアルジェリアの独立を承認。
アルジェリアの独立戦争は1962年に終結をします。
しかし極右勢力はこれに反発。
シャルル・ド・ゴール暗殺計画が企てられます。




1962年8月22日。
パリ郊外のプティ・クラマールで、OASによるド・ゴール暗殺事件が起こります。
ド・ゴールを乗せた専用車DS19シトロエンが12発の銃弾を受けますが、ド・ゴール本人は無傷のままシトロエンは襲撃場所を突っ切って事なきを得ます。
映画「ジャッカルの日」は、プティ・クラマール襲撃事件の史実を踏まえ、襲撃に失敗して弱体化したOASの最後の手段としてプロの殺し屋を雇うところからストーリーが動きだします。
「第四の核」「戦争の犬たち」のフレデリック・フォーサイスの同名小説を原作に、名匠フレッド・ジンネマンが監督として取り組んだ作品で、用意周到に獲物を狙うプロの殺し屋ジャッカルの冷静で緻密な行動、まさにジャッカル(狼に似たイヌ科イヌ属の哺乳動物)を思わせる風貌を持った非情な殺し屋と、それを追うのが、妻に頭の上がらない凡庸(ぼんよう)とした風采のクロード・ルベル警視という、正反対の男たちの対決を軸に、ド・ゴール暗殺をクライマックスとしたスリリングな展開で迫ります。
殺し屋ジャッカルに「恋」(1971年)、「遠すぎた橋」(1977年)、「ガンジー」(1982年)の名優エドワード・フォックス。
ジャッカルを追うクロード・ルベル警視に「日曜日には鼠を殺せ」(1964年)、「パリは燃えているか」(1966年)、「薔薇の名前」(1986年)の、こちらも名優マイケル・ロンズデール。
ド・ゴール本人は31回という暗殺未遂事件を受けながらも生き延び、大動脈瘤破裂によって1970年に79歳で世を去っていますから、ジャッカルの暗殺は失敗に終わるのが判っているのですが、それでも最後の最後まで見る者を惹きつけて離さない超一級のサスペンス映画です。
ただ、難点をひとつあげるとすれば、舞台はほとんどフランスだし、登場人物のほとんどもフランス人なのに、セリフがすべて英語というのは違和感がありますが、そこは少し大目に見て、難点を差し引いても十分過ぎるほど見ごたえのある傑作です。





1973年 イギリス/フランス
監督フレッド・ジンネマン
原作フレデリック・フォーサイス
脚本ケネス・ロス
撮影ジャン・トゥルニエ
音楽ジョルジュ・ドルリュー
〈キャスト〉
エドワード・フォックス マイケル・ロンズデール
デルフィーヌ・セイリグ
フランス第18代大統領シャルル・ド・ゴールを狙った暗殺事件を、「真昼の決闘」(1952年)、「地上より永遠に」(1953年)、「わが命つきるとも」(1966年)の名匠フレッド・ジンネマンが、周到に積み上げた細部と史実に基づいて、ド・ゴール暗殺を目論む武装組織の暗躍を背景に、暗殺を依頼された一匹狼の殺し屋ジャッカルと、暗殺を阻止しようとジャッカルを追い詰めるフランス官憲のクロード・ルベル警視の活躍を描いたサスペンス映画の傑作。
1962年、OAS(フランス極右民族主義)によるド・ゴール暗殺未遂事件が起こり、首謀者は逮捕、さらに銃殺。
当局の締め付けが厳しくなったOASは壊滅状態に陥ります。
OASによるド・ゴール暗殺の最後の切り札として登場したのが、国籍不明の殺し屋、暗号名ジャッカル(エドワード・フォックス)です。

50万ドルの契約で仕事を引き受けたジャッカルは着々と準備を進めます。
身分証明書を偽造し、精巧な狙撃銃を作らせたジャッカルはフランスへと進入。
ド・ゴール暗殺の機会をうかがいます。
一方、50万ドルという破格の契約のために資金を確保しなければならなくなったOASは銀行強盗を決行。
現金強奪にはいくつか成功しますが、テロを警戒したフランス当局は厳重な包囲網を敷き、強盗の一人を狙撃して逮捕。
尋問からOASの計画の断片を察知した大統領官邸は、ド・ゴール大統領を狙う正体不明の暗殺者捜索のためにフランス警察の腕利き、クロード・ルベル警視(マイケル・ロンズデール)を招集することになります。
パッとしない風采でボソボソとした話し方のルベルは、体こそ大きいものの、茫洋とした感じで切れ者のイメージからはほど遠い男なのですが、粘り強く、少ない情報を元に殺し屋ジャッカルの足取りをつかんでゆきます。
治安組織の動きを察知するため、フランス治安当局の官僚に近づいたOASのジャクリーヌは、機密情報を盗み出してOASに流し、その情報を元にジャッカルは当局やルベル警視の目を潜(くぐ)り抜けてパリへ潜入してゆきます。

一向に手がかりのつかめないジャッカルの足取りに疑問を感じたルベルは、内部から情報が洩れていることを突き止め、やがて、ド・ゴール暗殺のためのジャッカルの計画がパリ解放記念式典にあることに気づきます。
ジャクリーヌが逮捕され、足取りが察知されていることを感じたジャッカルは、計画を思いとどまることなく、むしろ敢然と挑むように渦中に飛び込んでゆきます。
8月25日のその日、大勢のパリ市民でにぎわいを見せる中、厳重な警戒網の目をくぐって、松葉づえをついた片足の男がアパートへの帰宅のために歩いています。
傷痍軍人に変装したジャッカルです。
シャルル・ド・ゴールが記念式典に参列。
アパートに侵入したジャッカルは狙撃の機会を待ちます。
躍起になってジャッカルの姿を探すルベルは、一人の男が警戒の目を抜けていたことを察知。男が向かったアパートに駆け込みます。
ド・ゴールが勲章授与のために進み出た瞬間、ジャッカルは狙撃銃の引き金を引きます。
私は高校時代、この映画を映画館で観ましたが、正直に言って何が何だかよく分かりませんでした。
当時「ジャッカルの日」は大きな話題になっていて、シャルル・ド・ゴールを狙う殺し屋の話として映画ファンの間で盛り上がっていたこともあったので、単純にアクション映画としてしか考えなかった私は(なにしろ「ダーティハリー」や「フレンチ・コネクション」の時代でしたから)、心に大きな空白を抱いて帰宅することになりました。
今でもよく覚えているシーンは、狙撃銃を手に入れたジャッカルが山の中で、木の枝に吊るしたスイカを標的に銃の精度を調節するシーンと、サウナで知り合った友人を殺害するシーン。
この二つだけで、その他はほとんど覚えていません。
なぜよく分からなかったのかというのは、その背景となっている国際情勢の流れと、どうしてド・ゴールを暗殺しなければいけないのか、ということだったのでしょう。

●シャルル・ド・ゴール暗殺の理由は?
植民地政策を執る欧米列強の中で、フランスはインドシナや北アフリカへ侵攻。
1847年にはアルジェリアを支配します。
しかしアルジェリアでは各地で独立運動が起き、FLN(民族解放戦線)の武装蜂起によって1954年にはフランスの支配に対するアルジェリアの独立戦争が勃発。
一方、1890年にフランス北部のリールで生まれたド・ゴールは、陸軍軍人や首相を経験しながら1959年に大統領に就任。
第二次世界大戦のナチス・ドイツによる占領や、第一次インドシナ戦争で疲弊したフランスの国力なども考慮して、ド・ゴールはアルジェリアの独立を承認。
アルジェリアの独立戦争は1962年に終結をします。
しかし極右勢力はこれに反発。
シャルル・ド・ゴール暗殺計画が企てられます。
1962年8月22日。
パリ郊外のプティ・クラマールで、OASによるド・ゴール暗殺事件が起こります。
ド・ゴールを乗せた専用車DS19シトロエンが12発の銃弾を受けますが、ド・ゴール本人は無傷のままシトロエンは襲撃場所を突っ切って事なきを得ます。
映画「ジャッカルの日」は、プティ・クラマール襲撃事件の史実を踏まえ、襲撃に失敗して弱体化したOASの最後の手段としてプロの殺し屋を雇うところからストーリーが動きだします。
「第四の核」「戦争の犬たち」のフレデリック・フォーサイスの同名小説を原作に、名匠フレッド・ジンネマンが監督として取り組んだ作品で、用意周到に獲物を狙うプロの殺し屋ジャッカルの冷静で緻密な行動、まさにジャッカル(狼に似たイヌ科イヌ属の哺乳動物)を思わせる風貌を持った非情な殺し屋と、それを追うのが、妻に頭の上がらない凡庸(ぼんよう)とした風采のクロード・ルベル警視という、正反対の男たちの対決を軸に、ド・ゴール暗殺をクライマックスとしたスリリングな展開で迫ります。
殺し屋ジャッカルに「恋」(1971年)、「遠すぎた橋」(1977年)、「ガンジー」(1982年)の名優エドワード・フォックス。
ジャッカルを追うクロード・ルベル警視に「日曜日には鼠を殺せ」(1964年)、「パリは燃えているか」(1966年)、「薔薇の名前」(1986年)の、こちらも名優マイケル・ロンズデール。
ド・ゴール本人は31回という暗殺未遂事件を受けながらも生き延び、大動脈瘤破裂によって1970年に79歳で世を去っていますから、ジャッカルの暗殺は失敗に終わるのが判っているのですが、それでも最後の最後まで見る者を惹きつけて離さない超一級のサスペンス映画です。
ただ、難点をひとつあげるとすれば、舞台はほとんどフランスだし、登場人物のほとんどもフランス人なのに、セリフがすべて英語というのは違和感がありますが、そこは少し大目に見て、難点を差し引いても十分過ぎるほど見ごたえのある傑作です。

2019年09月05日
映画「何がジェーンに起こったか?」嫉妬と憎悪,サイコミステリーの傑作
「何がジェーンに起こったか?」
(What Ever Happened to Baby Jane?)
1962年 アメリカ
製作・監督ロバート・アルドリッチ
原作ヘンリー・ファレル
脚本ルーカス・ヘラー
撮影アーネスト・ホーラー
〈キャスト〉
ベティ・デイヴィス ジョーン・クロフォード
ヴィクター・ブオノ
第35回アカデミー賞衣装デザイン賞(白黒)
「ベラクルス」(1954年)、「特攻大作戦」(1967年)、「北国の帝王」(1973年)など、男性的で骨太い作品を得意とするロバート・アルドリッチが、愛憎に満ちた姉妹の確執をテーマに、そこから生じたミステリーに挑んだ傑作。
アカデミー賞を始めとして、カンヌ国際映画祭やゴールデングローブ賞など数々の賞にノミネートをされるなど、作品の質の高さは評価されましたが、何しろ1962年は「アラビアのロレンス」が作品賞を始めとして7部門を受賞するなど圧倒的な存在感を見せつけ、「奇跡の人」「アラバマ物語」「戦艦バウンティ」「史上最大の作戦」といったそうそうたる作品の並んだ時期だっただけに、衣装デザイン賞のみの受賞に沈みましたが、主演のベティ・デイヴィス、ジョーン・クロフォードの火花を散らす演技と、ヒッチコックばりのサスペンスとスリラーの展開は、とにかく見応えがあります。





1917年、世界的には第一次世界大戦が終結に向かい始め、ロシア革命が勃発し、映画の世界ではチャーリー・チャップリンがその才能を発揮していたころ、ショービジネスの世界では一人の少女が愛らしい歌と踊りを披露して観客の喝采を浴びていました。
その名は“ベイビー・ジェーン・ハドソン”。
観客の熱烈なリクエストに応えて彼女が歌う曲は「パパに手紙を」。
しかし、華やかな舞台の陰でジェーンに冷たい視線を送る少女がいました。
ジェーン・ハドソンの姉、ブランチです。
舞台での愛らしい仕草とは反対に、傲慢な態度の目立つジェーンでしたが、ドル箱の少女スターは周囲からはチヤホヤされています。
そんなジェーンへの嫉妬が憎しみともいえる心境へブランチを追いやっているのです。


時は流れ、大人の女性へと成長したジェーン(ベティ・デイヴィス)とブランチ(ジョーン・クロフォード)は映画の世界で活躍を始めます。
しかし、少女時代とは対照的に、抜群の美貌と演技力でスターの地位を築いた姉のブランチでしたが、大した演技力を持たない妹のジェーンは映画界から爪弾(つまはじ)きにされていきます。
そしてある夜、自宅の前で自動車事故が起こり、酒に酔ったジェーンが姉のブランチを轢き殺そうとしたものだと新聞は報じます。
ここが、この映画のミステリーの発端となるところで、車を運転していたのが誰で、衝突されたのが誰なのか、両方ともに女性であるということの他には一切明らかにされていません。
話は変わって、ハリウッドにあるジェーンとブランチの家。
自動車事故から長い年月が過ぎ去り、華やかな映画スターの面影の消えかけたブランチは事故による脊髄損傷から車イスの生活を送り、白い厚化粧のジェーンが姉の世話をしています。
二人の間にわだかまるのは、自動車事故の加害者としてのジェーンの負い目による姉への奉仕と、妹のジェーンの助けを借りなければ食事も満足にとれない、妹に対する弱みを持つ車イスのブランチ。
少女時代の華やかさを取り戻そうと夢見るジェーンは、当時の人気曲「パパに手紙を」でカムバックを果たすべく専属のピアニスト、エドウィン・フラッグ(ヴィクター・ブオノ)を雇い、レッスンに励みます。
しかし、酒に溺れ、老いて自分の醜さを鏡の中に見出すようになったジェーンは、少なからず病み始めていた精神が加速度を増し、ブランチに対する支配力を強めて陰湿な虐待へとエスカレートしてゆきます。

通いの家政婦エルヴァイラ(メイディ・ノーマン)はジェーンの態度に不審を抱き、ブランチの窮状を救おうとしますが、それに気づいたジェーンに殺害されてしまいます。
手首をロープで縛られて自由を失ったブランチは衰弱し、死が目前に迫ってゆきます。





少女時代の嫉妬と羨望は大人になってから完全に逆転し、骨肉であるがゆえに、出来のいい姉への憎悪と老醜に対する怯えに支配され、徐々に正気を失ってゆくジェーンを演じたベティ・デイヴィスは、「化石の森」(1936年)、「黒蘭の女」(1938年)などの美貌からは想像できない、何かに取り憑かれたかのような狂気の演技でアカデミー賞主演女優賞にノミネート。

対するジョーン・クロフォードはサイレントの時代から活躍していた女優ですが、やはり「大砂塵」(1954年)が最も印象が強いです。
ベティ・デイヴィスの鬼気迫る演技の陰に隠れがちになってしまいましたが、暴君と化してゆく妹に怯えるジョーン・クロフォードの演技は、見ている側にもその怖さが直(じか)に伝わる迫真性があり、特に、主治医に助けを求めるために不自由な足を引きずって階段を降り、電話にすがりつく場面はサスペンス映画の極致です。
姉妹の確執を描いた映画ですが、実生活でもベティ・デイヴィスとクロフォードはかなり仲が悪かったらしく、それが映画にも反映されているのでしょうか。
でも、「お熱いのがお好き」(1959年)でのマリリン・モンローとトニー・カーティスも実生活では不仲だったようですから、お熱い恋人同士を演じた彼らの演技力も大したものです。




「何がジェーンに起こったか?」はミステリーとサイコスリラーの要素を併せ持った映画で、最後の最後まで自動車事故の真実が明らかにされることはなく、この二人の身の上に何が起こったのか、ミステリーはミステリーのままでドラマは進行し、そしてついに、ラストの浜辺で死に瀕したブランチの口から事故の真実が語られてゆきます。
しかし、ブランチの告白を聞いているジェーンはすでに正気を失っていて、明るい太陽と輝く夏の海辺、そこに、6歳当時の自分に戻って踊るジェーン、やせ衰えた体を砂浜に横たえて死を待つブランチという、狂気と死の構図は、真夏の海水浴客との対比の中で、姉妹の確執の醜悪さがひときわ浮き彫りにされています。





最後に、ジェーンの専属ピアニストとして雇われることになるエドウィン。
ジェーンに気があるような、ないような、売れないピアニストなのでジェーンに気に入られようと気のある素振りをしているのか、そんな態度を母親のデリラにたしなめられる気の弱い太ったピアニスト。
この親子のやり取りはときにユーモラスで、このあたりもヒッチコックをお手本にしているのかな、と思わせるものがあります。
ジェーンの異常さに気づき、部屋に監禁されて死にかけているブランチを発見しながら、慌てふためいて逃げてしまうダメ男を演じたヴィクター・ブオノは助演男優賞にノミネート。
受賞は「渇いた太陽」のエド・ベグリーにさらわれましたが、「何がジェーンに起こったか?」の緊張した展開の中で、母親のデリラと行きずりの男との間に生まれた出自を持ち、母親に反抗をしながらも、なんとなく人生に妥協してしまっているエドウィンには不思議で奇妙な存在感がありました。







(What Ever Happened to Baby Jane?)
1962年 アメリカ
製作・監督ロバート・アルドリッチ
原作ヘンリー・ファレル
脚本ルーカス・ヘラー
撮影アーネスト・ホーラー
〈キャスト〉
ベティ・デイヴィス ジョーン・クロフォード
ヴィクター・ブオノ
第35回アカデミー賞衣装デザイン賞(白黒)
「ベラクルス」(1954年)、「特攻大作戦」(1967年)、「北国の帝王」(1973年)など、男性的で骨太い作品を得意とするロバート・アルドリッチが、愛憎に満ちた姉妹の確執をテーマに、そこから生じたミステリーに挑んだ傑作。
アカデミー賞を始めとして、カンヌ国際映画祭やゴールデングローブ賞など数々の賞にノミネートをされるなど、作品の質の高さは評価されましたが、何しろ1962年は「アラビアのロレンス」が作品賞を始めとして7部門を受賞するなど圧倒的な存在感を見せつけ、「奇跡の人」「アラバマ物語」「戦艦バウンティ」「史上最大の作戦」といったそうそうたる作品の並んだ時期だっただけに、衣装デザイン賞のみの受賞に沈みましたが、主演のベティ・デイヴィス、ジョーン・クロフォードの火花を散らす演技と、ヒッチコックばりのサスペンスとスリラーの展開は、とにかく見応えがあります。

1917年、世界的には第一次世界大戦が終結に向かい始め、ロシア革命が勃発し、映画の世界ではチャーリー・チャップリンがその才能を発揮していたころ、ショービジネスの世界では一人の少女が愛らしい歌と踊りを披露して観客の喝采を浴びていました。
その名は“ベイビー・ジェーン・ハドソン”。
観客の熱烈なリクエストに応えて彼女が歌う曲は「パパに手紙を」。
しかし、華やかな舞台の陰でジェーンに冷たい視線を送る少女がいました。
ジェーン・ハドソンの姉、ブランチです。
舞台での愛らしい仕草とは反対に、傲慢な態度の目立つジェーンでしたが、ドル箱の少女スターは周囲からはチヤホヤされています。
そんなジェーンへの嫉妬が憎しみともいえる心境へブランチを追いやっているのです。
時は流れ、大人の女性へと成長したジェーン(ベティ・デイヴィス)とブランチ(ジョーン・クロフォード)は映画の世界で活躍を始めます。
しかし、少女時代とは対照的に、抜群の美貌と演技力でスターの地位を築いた姉のブランチでしたが、大した演技力を持たない妹のジェーンは映画界から爪弾(つまはじ)きにされていきます。
そしてある夜、自宅の前で自動車事故が起こり、酒に酔ったジェーンが姉のブランチを轢き殺そうとしたものだと新聞は報じます。
ここが、この映画のミステリーの発端となるところで、車を運転していたのが誰で、衝突されたのが誰なのか、両方ともに女性であるということの他には一切明らかにされていません。
話は変わって、ハリウッドにあるジェーンとブランチの家。
自動車事故から長い年月が過ぎ去り、華やかな映画スターの面影の消えかけたブランチは事故による脊髄損傷から車イスの生活を送り、白い厚化粧のジェーンが姉の世話をしています。
二人の間にわだかまるのは、自動車事故の加害者としてのジェーンの負い目による姉への奉仕と、妹のジェーンの助けを借りなければ食事も満足にとれない、妹に対する弱みを持つ車イスのブランチ。
少女時代の華やかさを取り戻そうと夢見るジェーンは、当時の人気曲「パパに手紙を」でカムバックを果たすべく専属のピアニスト、エドウィン・フラッグ(ヴィクター・ブオノ)を雇い、レッスンに励みます。
しかし、酒に溺れ、老いて自分の醜さを鏡の中に見出すようになったジェーンは、少なからず病み始めていた精神が加速度を増し、ブランチに対する支配力を強めて陰湿な虐待へとエスカレートしてゆきます。

通いの家政婦エルヴァイラ(メイディ・ノーマン)はジェーンの態度に不審を抱き、ブランチの窮状を救おうとしますが、それに気づいたジェーンに殺害されてしまいます。
手首をロープで縛られて自由を失ったブランチは衰弱し、死が目前に迫ってゆきます。
少女時代の嫉妬と羨望は大人になってから完全に逆転し、骨肉であるがゆえに、出来のいい姉への憎悪と老醜に対する怯えに支配され、徐々に正気を失ってゆくジェーンを演じたベティ・デイヴィスは、「化石の森」(1936年)、「黒蘭の女」(1938年)などの美貌からは想像できない、何かに取り憑かれたかのような狂気の演技でアカデミー賞主演女優賞にノミネート。

対するジョーン・クロフォードはサイレントの時代から活躍していた女優ですが、やはり「大砂塵」(1954年)が最も印象が強いです。
ベティ・デイヴィスの鬼気迫る演技の陰に隠れがちになってしまいましたが、暴君と化してゆく妹に怯えるジョーン・クロフォードの演技は、見ている側にもその怖さが直(じか)に伝わる迫真性があり、特に、主治医に助けを求めるために不自由な足を引きずって階段を降り、電話にすがりつく場面はサスペンス映画の極致です。
姉妹の確執を描いた映画ですが、実生活でもベティ・デイヴィスとクロフォードはかなり仲が悪かったらしく、それが映画にも反映されているのでしょうか。
でも、「お熱いのがお好き」(1959年)でのマリリン・モンローとトニー・カーティスも実生活では不仲だったようですから、お熱い恋人同士を演じた彼らの演技力も大したものです。
「何がジェーンに起こったか?」はミステリーとサイコスリラーの要素を併せ持った映画で、最後の最後まで自動車事故の真実が明らかにされることはなく、この二人の身の上に何が起こったのか、ミステリーはミステリーのままでドラマは進行し、そしてついに、ラストの浜辺で死に瀕したブランチの口から事故の真実が語られてゆきます。
しかし、ブランチの告白を聞いているジェーンはすでに正気を失っていて、明るい太陽と輝く夏の海辺、そこに、6歳当時の自分に戻って踊るジェーン、やせ衰えた体を砂浜に横たえて死を待つブランチという、狂気と死の構図は、真夏の海水浴客との対比の中で、姉妹の確執の醜悪さがひときわ浮き彫りにされています。

最後に、ジェーンの専属ピアニストとして雇われることになるエドウィン。
ジェーンに気があるような、ないような、売れないピアニストなのでジェーンに気に入られようと気のある素振りをしているのか、そんな態度を母親のデリラにたしなめられる気の弱い太ったピアニスト。
この親子のやり取りはときにユーモラスで、このあたりもヒッチコックをお手本にしているのかな、と思わせるものがあります。
ジェーンの異常さに気づき、部屋に監禁されて死にかけているブランチを発見しながら、慌てふためいて逃げてしまうダメ男を演じたヴィクター・ブオノは助演男優賞にノミネート。
受賞は「渇いた太陽」のエド・ベグリーにさらわれましたが、「何がジェーンに起こったか?」の緊張した展開の中で、母親のデリラと行きずりの男との間に生まれた出自を持ち、母親に反抗をしながらも、なんとなく人生に妥協してしまっているエドウィンには不思議で奇妙な存在感がありました。







