2014”N02Œژ19“ْ
پu‘إ‚؟‚ج‚ك‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ب‚·‚²‚¢–{پvپ@•ؤŒ´–œ—¢
پ@گ¶‘O‚ي‚ھچ‘چإچ‚•ô‚جƒچƒVƒAŒê’ت–َژز‚إ‚ ‚ء‚½•ؤŒ´–œ—¢‚جٹeژ†‚ةŒfچع‚µ‚ؤ‚¢‚½ڈ‘•]‚ًˆêچû‚ة‚ـ‚ئ‚كڈم‚°‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBڈ‘•]‘خڈغ‚ئ‚ب‚é–{‚ح‚©‚ب‚è•‚ھچL‚پA•ؤŒ´ژ©گg‚ج’m“IچDٹïگS‚à‘ٹ“–چL‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚éپB‘خڈغ‚ئ‚ب‚é–{‚ح1995”Nپ`2005”N‚ج‚à‚ج‚ھƒپƒCƒ“‚¾پB
پ@ƒ^ƒCƒgƒ‹‚ح‚ ‚é“ْŒfچع‚³‚ꂽڈ‘•]‚جƒ^ƒCƒgƒ‹‚ب‚ج‚¾‚ھپA“ا—¹Œم‚ةژv‚¦‚خ‚±‚ج–{ژ©‘ج‚ھپu‘إ‚؟‚ج‚ك‚·پv‚¾‚¯‚ج—ح‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚éپBچىژز‚جƒRƒپƒ“ƒg‚حژ‚ةگhç…پAژ‚ة‚ׂ½–J‚ك‚إ‚ ‚èپA‚ع‚ë‚‚»‚ة‚¯‚ب‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½–{‚إ‚·‚ç“ا‚ف‚½‚‚ب‚é‚©‚ç•sژv‹c‚¾پB‚ـ‚½ٹ´ڈîک_‚ةڈIژn‚µ‚ب‚¢پAک_—“I‚©‚آ‹ï‘ج“I‚ب”ل•]گ¸گ_‚إ•]‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ‘fگ°‚炵‚¢پB
پ@‚ـ‚½پA–{ڈ‘‚ًچ\گ¬‚·‚é”قڈ—‚جŒ¾—tˆê‚آˆê‚آ‚ھ⼌¾‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚à–{ڈ‘‚ج‘ه‚«‚ب“ء’¥‚إ‚ ‚éپB
پuچى‰ئ‚حپAژ©گg‚جŒ©‰ً‚ً—¦’¼‚ة‹U‚è‚ب‚Œê‚é‚ׂ«‚إپAŒ —حژز‚ة‚¨‚à‚ث‚ء‚½‚艓—¶‚µ‚½‚ج‚إ‚حپAŒ¾—t‚ھ—ح‚ًژ¸‚¤پBپv
پuگ¶ژ€‚ج‹«‚ً‰½“x‚àœfœr‚¢پA‹°•|‚ئ— گط‚è‚ةکM‚خ‚ê‚ؤگlٹi‚ً•ِ‰َ‚³‚¹‚ؤ‚¢‚گlپX‚à‚ ‚ê‚خپA‚»‚ٌ‚ب’†‚إ‚à‰·‚©‚¢گlٹشٹضŒW‚ً’z‚«پA‘¸Œµ‚ًˆغژ‚µ‚ؤ‚¢‚گlپX‚جژp‚ھ‚ ‚éپBپv
پu•¶ژڑ‚إ‹L‚³‚ꂽ‚à‚ج‚ة‚ح‹•چ\‚ھ•´‚êچ‚ف‚â‚·‚¢پBپv
پ@‚ـ‚½پA–{ڈ‘‚ح’P‚ب‚éڈ‘•]ˆبٹO‚ةچىژز‚جƒKƒ““¬•a“ْ‹L‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‘¤–ت‚à•¹‚¹ژ‚آپBڈ‘•]‘خڈغ‚جٹô•ھ‚©‚حƒKƒ“ژ،—أ‚ةٹض‚·‚é–{‚ھگè‚ك‚ؤ‚¨‚èپA”قڈ—‚ح“ا‚ٌ‚¾ژ،—أ–@‚ًژہ‘H‚·‚é‚ئ‚±‚ë‚ـ‚إڈ‘‚«•\‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚ ‚ـ‚è‚ة‚à’mژ¯‚ًژd“ü‚ê‚·‚¬‚ؤ‚¢‚邽‚ك‚ةپAˆمژز‚ة‰Œ‚½‚ھ‚ç‚ꂽ‚èپA’ا‚¢ڈo‚³‚ê‚é•`ژت‚ھٹô“x‚à‚ ‚éپB”قڈ—ƒŒƒxƒ‹‚إƒCƒ“ƒtƒHپ[ƒ€ƒhƒRƒ“ƒZƒ“ƒgپAƒZƒJƒ“ƒhƒIƒsƒjƒIƒ“‚ً”ٹِ‚·‚éٹ³ژز‚à‚»‚¤‚»‚¤‚¢‚ـ‚¢پBˆم—أڈ]ژ–ژز‚©‚炵‚ؤ‚ف‚ê‚خپA‚ ‚éˆس–،‚»‚±‚ç•س‚ج–â‘è‚ًٹ³ژز‘¤‚©‚ç•`‚¢‚½چى•i‚ئ“ا‚ق‚±‚ئ‚à‚إ‚«‚éپB‚ـ‚½پA‘م‘ضˆم—أ‚جژہ‘H‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚à‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚ھپAڈ‚µ‚إ‚àچ¼‹\ڈL‚³پE‚ـ‚ھ‚¢•¨ڈL‚³‚ھ‚·‚é‚ئ‚·‚®‚ة•ش•i‚µ‚½‚èپAژ~‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئ‚±‚ë‚à”قڈ—‚炵‚¢پB
پ@پu’mژ¯گl99گl‚جژ€‚ة•ûپiچr–“چGٹؤڈCپjپv‚ئ‚¢‚¤–{‚إ‚حژO“‡—R‹I•vپA‹g“c–خ‚ç’mژ¯گl’B‚جژ€‚ة‚´‚ـپEژ€‚ة—ص‚ٌ‚إ‚جگSڈî‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚¨‚èژ€‚ً‘O‚ة‚µ‚ؤ’mژ¯گl‚ج’mژ¯پEژvچl‚ح‚ا‚ج‚و‚¤‚ةگU‚é•‘‚ء‚½‚©‚ً’m‚é‚ةگâچD‚جڈ‘‚إ‚ ‚é‚ج‚¾‚ھپA–{گlژ‹“_‚ج“¬•a‹LپA‚»‚ê‚à‚ئ‚è‚ي‚¯—’m“I‚بچىژز‚جژè‚ة‚و‚é“_‚إ–{ڈ‘‚ح‚»‚êˆبڈم‚ة“ا‚قژز‚ً‚®‚¢‚®‚¢ژ†–ت‚ضˆّ‚«چ‚ٌ‚إ‚ن‚پBڈ‚µ‚àژ€‚ً‘O‚ة‚µ‚½’ْ‚كپAژم‰¹‚ئ‚¢‚ء‚½‚à‚ج‚ھٹ´‚¶‚ç‚ꂸپAچإŒم‚ـ‚إگ¶‚«‚و‚¤پA–{‚ً“ا‚à‚¤پAگ¢ٹE‚ً’m‚낤پA‚ئ‚µ‚ؤ‘«‘~‚¢‚½‚ج‚ھ•ھ‚©‚éپB
پ@‰ًگà‚ًˆنڈم‚ذ‚³‚µ‚ئٹغ’Jچثˆê‚ھڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚±‚ج“ٌگl‚ج•¶ڈح‚à‚ـ‚½گ^‚ة“ا‚ق‚ة’l‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBڈ‘•]‚ئ‚¢‚¤’کچى‚ة‚µ‚ؤ‚ح‚ ‚ـ‚èƒIƒٹƒWƒiƒٹƒeƒBپ[‚ً‘S–ت‚ة‰ں‚µڈo‚¹‚ب‚¢•ھ–ى‚ة‚¨‚¢‚ؤپA‚±‚±‚ـ‚إ“ا‚فژè‚ً–£—¹‚إ‚«‚éڈ‘‚«ژè‚ح‚»‚¤‚»‚¤‚¢‚ب‚¢‚¾‚낤پB‚»‚ج•ھپA’£‚è‚آ‚ك‚½‚à‚ج‚ھگط‚ê‚ؤ“ا—¹ŒمپA‚ا‚ء‚ئ”و‚ê‚ھڈo‚½پB
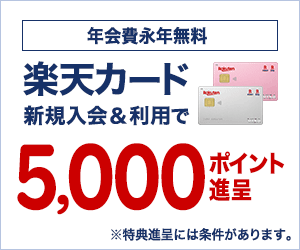

پ@ƒ^ƒCƒgƒ‹‚ح‚ ‚é“ْŒfچع‚³‚ꂽڈ‘•]‚جƒ^ƒCƒgƒ‹‚ب‚ج‚¾‚ھپA“ا—¹Œم‚ةژv‚¦‚خ‚±‚ج–{ژ©‘ج‚ھپu‘إ‚؟‚ج‚ك‚·پv‚¾‚¯‚ج—ح‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚éپBچىژز‚جƒRƒپƒ“ƒg‚حژ‚ةگhç…پAژ‚ة‚ׂ½–J‚ك‚إ‚ ‚èپA‚ع‚ë‚‚»‚ة‚¯‚ب‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½–{‚إ‚·‚ç“ا‚ف‚½‚‚ب‚é‚©‚ç•sژv‹c‚¾پB‚ـ‚½ٹ´ڈîک_‚ةڈIژn‚µ‚ب‚¢پAک_—“I‚©‚آ‹ï‘ج“I‚ب”ل•]گ¸گ_‚إ•]‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ‘fگ°‚炵‚¢پB
پ@‚ـ‚½پA–{ڈ‘‚ًچ\گ¬‚·‚é”قڈ—‚جŒ¾—tˆê‚آˆê‚آ‚ھ⼌¾‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚à–{ڈ‘‚ج‘ه‚«‚ب“ء’¥‚إ‚ ‚éپB
پuچى‰ئ‚حپAژ©گg‚جŒ©‰ً‚ً—¦’¼‚ة‹U‚è‚ب‚Œê‚é‚ׂ«‚إپAŒ —حژز‚ة‚¨‚à‚ث‚ء‚½‚艓—¶‚µ‚½‚ج‚إ‚حپAŒ¾—t‚ھ—ح‚ًژ¸‚¤پBپv
پuگ¶ژ€‚ج‹«‚ً‰½“x‚àœfœr‚¢پA‹°•|‚ئ— گط‚è‚ةکM‚خ‚ê‚ؤگlٹi‚ً•ِ‰َ‚³‚¹‚ؤ‚¢‚گlپX‚à‚ ‚ê‚خپA‚»‚ٌ‚ب’†‚إ‚à‰·‚©‚¢گlٹشٹضŒW‚ً’z‚«پA‘¸Œµ‚ًˆغژ‚µ‚ؤ‚¢‚گlپX‚جژp‚ھ‚ ‚éپBپv
پu•¶ژڑ‚إ‹L‚³‚ꂽ‚à‚ج‚ة‚ح‹•چ\‚ھ•´‚êچ‚ف‚â‚·‚¢پBپv
پ@‚ـ‚½پA–{ڈ‘‚ح’P‚ب‚éڈ‘•]ˆبٹO‚ةچىژز‚جƒKƒ““¬•a“ْ‹L‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‘¤–ت‚à•¹‚¹ژ‚آپBڈ‘•]‘خڈغ‚جٹô•ھ‚©‚حƒKƒ“ژ،—أ‚ةٹض‚·‚é–{‚ھگè‚ك‚ؤ‚¨‚èپA”قڈ—‚ح“ا‚ٌ‚¾ژ،—أ–@‚ًژہ‘H‚·‚é‚ئ‚±‚ë‚ـ‚إڈ‘‚«•\‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚ ‚ـ‚è‚ة‚à’mژ¯‚ًژd“ü‚ê‚·‚¬‚ؤ‚¢‚邽‚ك‚ةپAˆمژز‚ة‰Œ‚½‚ھ‚ç‚ꂽ‚èپA’ا‚¢ڈo‚³‚ê‚é•`ژت‚ھٹô“x‚à‚ ‚éپB”قڈ—ƒŒƒxƒ‹‚إƒCƒ“ƒtƒHپ[ƒ€ƒhƒRƒ“ƒZƒ“ƒgپAƒZƒJƒ“ƒhƒIƒsƒjƒIƒ“‚ً”ٹِ‚·‚éٹ³ژز‚à‚»‚¤‚»‚¤‚¢‚ـ‚¢پBˆم—أڈ]ژ–ژز‚©‚炵‚ؤ‚ف‚ê‚خپA‚ ‚éˆس–،‚»‚±‚ç•س‚ج–â‘è‚ًٹ³ژز‘¤‚©‚ç•`‚¢‚½چى•i‚ئ“ا‚ق‚±‚ئ‚à‚إ‚«‚éپB‚ـ‚½پA‘م‘ضˆم—أ‚جژہ‘H‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚à‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚ھپAڈ‚µ‚إ‚àچ¼‹\ڈL‚³پE‚ـ‚ھ‚¢•¨ڈL‚³‚ھ‚·‚é‚ئ‚·‚®‚ة•ش•i‚µ‚½‚èپAژ~‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئ‚±‚ë‚à”قڈ—‚炵‚¢پB
پ@پu’mژ¯گl99گl‚جژ€‚ة•ûپiچr–“چGٹؤڈCپjپv‚ئ‚¢‚¤–{‚إ‚حژO“‡—R‹I•vپA‹g“c–خ‚ç’mژ¯گl’B‚جژ€‚ة‚´‚ـپEژ€‚ة—ص‚ٌ‚إ‚جگSڈî‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚¨‚èژ€‚ً‘O‚ة‚µ‚ؤ’mژ¯گl‚ج’mژ¯پEژvچl‚ح‚ا‚ج‚و‚¤‚ةگU‚é•‘‚ء‚½‚©‚ً’m‚é‚ةگâچD‚جڈ‘‚إ‚ ‚é‚ج‚¾‚ھپA–{گlژ‹“_‚ج“¬•a‹LپA‚»‚ê‚à‚ئ‚è‚ي‚¯—’m“I‚بچىژز‚جژè‚ة‚و‚é“_‚إ–{ڈ‘‚ح‚»‚êˆبڈم‚ة“ا‚قژز‚ً‚®‚¢‚®‚¢ژ†–ت‚ضˆّ‚«چ‚ٌ‚إ‚ن‚پBڈ‚µ‚àژ€‚ً‘O‚ة‚µ‚½’ْ‚كپAژم‰¹‚ئ‚¢‚ء‚½‚à‚ج‚ھٹ´‚¶‚ç‚ꂸپAچإŒم‚ـ‚إگ¶‚«‚و‚¤پA–{‚ً“ا‚à‚¤پAگ¢ٹE‚ً’m‚낤پA‚ئ‚µ‚ؤ‘«‘~‚¢‚½‚ج‚ھ•ھ‚©‚éپB
پ@‰ًگà‚ًˆنڈم‚ذ‚³‚µ‚ئٹغ’Jچثˆê‚ھڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚±‚ج“ٌگl‚ج•¶ڈح‚à‚ـ‚½گ^‚ة“ا‚ق‚ة’l‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBڈ‘•]‚ئ‚¢‚¤’کچى‚ة‚µ‚ؤ‚ح‚ ‚ـ‚èƒIƒٹƒWƒiƒٹƒeƒBپ[‚ً‘S–ت‚ة‰ں‚µڈo‚¹‚ب‚¢•ھ–ى‚ة‚¨‚¢‚ؤپA‚±‚±‚ـ‚إ“ا‚فژè‚ً–£—¹‚إ‚«‚éڈ‘‚«ژè‚ح‚»‚¤‚»‚¤‚¢‚ب‚¢‚¾‚낤پB‚»‚ج•ھپA’£‚è‚آ‚ك‚½‚à‚ج‚ھگط‚ê‚ؤ“ا—¹ŒمپA‚ا‚ء‚ئ”و‚ê‚ھڈo‚½پB








![‚ة‚ظ‚ٌƒuƒچƒO‘؛ –{ƒuƒچƒO ڈ‘•]پEƒŒƒrƒ…پ[‚ض](http://book.blogmura.com/bookreview/img/originalimg/0000345592.jpg)

