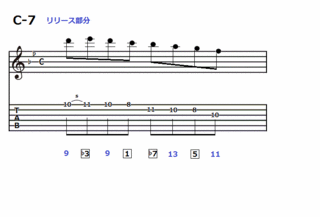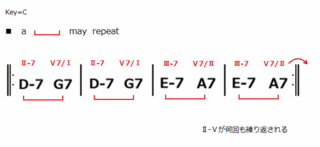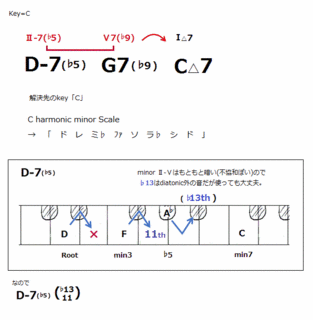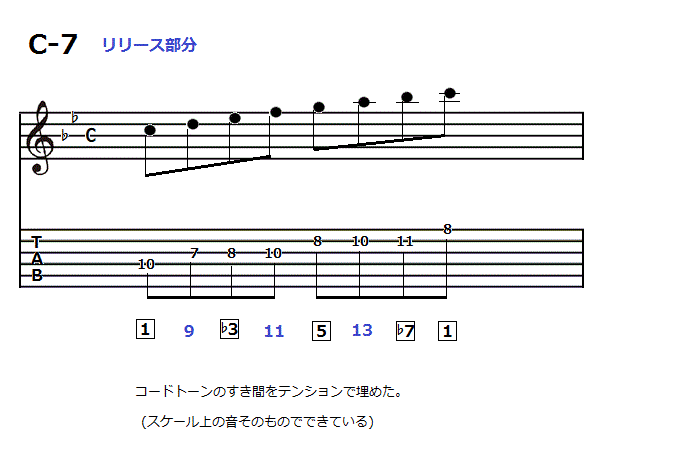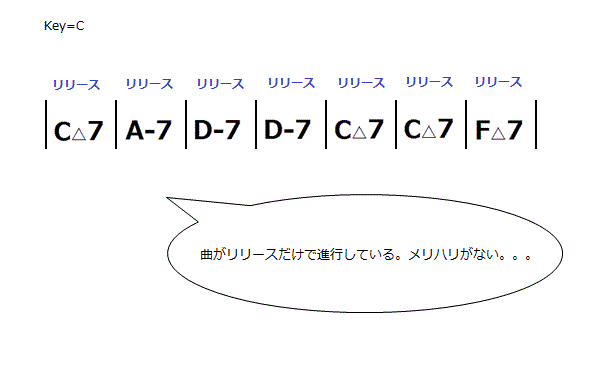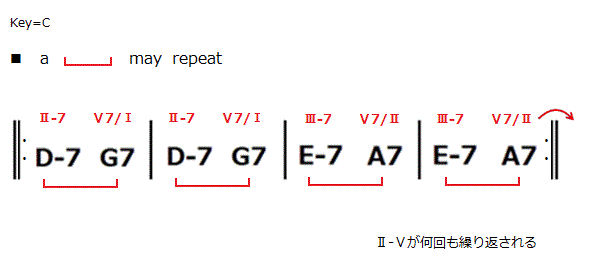2015年06月04日
0064.related Ⅱ-7のavailable tensionのつけかたについての説明します。ポイントはその場限りのkeyのとらえ方。あと、おまけでコード進行感がみえるフレーズのつくり方にちょっとだけ。
おんがくりろんでごはんたべたい(灬╹ω╹灬)です
♪♪今回はRelated Ⅱ-7のavailable tensionです
Related Ⅱ-7コードのavailable tensionは
keyに対するtensionを考える前に
その解決先を
→『その場限りのkey』としてtensionをつけます
■その場限りのkey
(from the key of the moment)
セカンダリーⅤ7は、「Ⅰ」以外の
diatonic chordに解決させるためのⅤ7コードですが
本来のドミナント7thコードが持つ
Primary Ⅴ7としての機能で、
瞬間的には、元の調性からOutして、
他のkeyの「Ⅰ」に向かう進行感を感じさせます
この解決先を
その場限りのkeyと捉えます
たとえば)
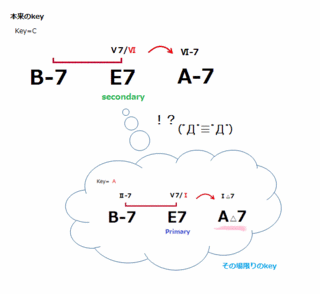
Key=C で、
セカンダリーⅤ7/ⅥのE7が向かうのは
diatonic Ⅵ-7のA-7ですが、
その場限りのkeyとしてみるなら
E7はプライマリーⅤ7として
key=A の「Ⅰ」に向かうので
その場限りのkeyは「A」となります
そして、
Related Ⅱ-7は、
セカンダリー Ⅴ7をⅡ-Ⅴ進行に
分割したものともいえるので
セカンダリーⅤ7の解決先のkeyに対する
Related Ⅱ-7 の役割を常にもっています
つまり、
その場限りのkeyの
2番目のdiatonic chordと同じものなので
Point!)
Related Ⅱ-7のavailable tensionは
ダイアトニックコードのⅡ-7と同じになります
diatonic chordのavailable tensionはこちら
→diatonic chord(セブンス)
→diatonic chord(トライアド)
■RelatedⅡ-7のavailable tensionを確認する
以下にkey=Cの
それぞれのセカンダリーⅤ7に対する
RelatedⅡ-7のavailable tensionを載せました
どのRelated Ⅱ-7コードも
その場限りのkeyに対して
同じテンションのつき方をしているので
確認してみてください。
●Ⅴ7/Ⅱに対するRelated Ⅱ-7

●Ⅴ7/Ⅲに対するRelated Ⅱ-7
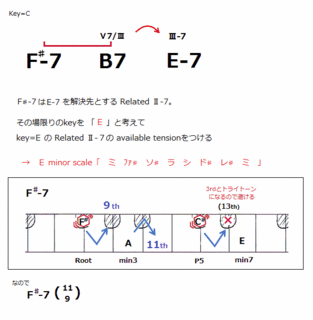
●Ⅴ7/Ⅳに対するRelated Ⅱ-7

●Ⅴ7/Ⅴに対するRelated Ⅱ-7
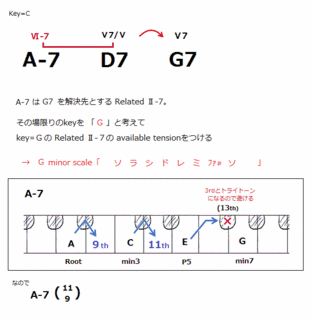
●Ⅴ7/Ⅵに対するRelated Ⅱ-7

それぞれの解決先に対するⅡ-7コードなので
その場限りのkeyが違っても、
available tensionはおなじです。
つまりは
これだけ覚えたら
かんたん。
→ related Ⅱ-7(9,11)
■おまけ
コード進行の例)

あえて本来のkeyからはRootがOutしている
related Ⅱ-7を利用したコード進行にしてみました
(Dual functionのないものだけ)
でも進行は自然です
使われているコードだけを見ていると
すごくOutしているように見えるけど
セカンダリー自体がちゃんと本来のkeyに
インサイドするための働きを持っているので
それに対するRelated Ⅱ-7が
diatonic chordじゃなくても
それはちゃんと
本来のkeyの調性の範囲内におさまります
こうした考えが
きっちり理解できていると
曲中にいろんなコードを加えて
複雑にしていっても
ちゃんと狙い通りの音楽がつくれるので
作曲の際のコード選びが、また自由になります
自由っていいよね。
さいごに)
もう1つおまけ
●フレーズの音選びについて
作曲であれば、フレーズに対して
狙い通りの進行感やコード感がでるように
つくっていきます。
コードなどの表記は、演奏者側が
そのニュアンスを読み取ってくれるように
テンションなどの情報を加えて
書き入れます
同様に
アドリブであれば、
スコアを見た時の情報から
そうした作曲者側の、曲の狙いを読み取って
使える音やスケールを判断していきます
たとえば、今回の例のように
Dual functionをあえて持たない進行であったり
Dual functionを持っていても、あえて
Related Ⅱ-7のtensionがついているような進行は
作曲者のⅡ-Ⅴぽさを出したいって
意図がニヤニヤ感じ取れるので
Ⅱ-Ⅴのニュアンスがはっきりでるような
フレーズを入れます。
ここでPoint)
Ⅱ-Ⅴのニュアンスが出るフレーズとは
かんたんにいうと
コード進行感がわかるフレーズにするという意味です
で、そのコード進行感を出すための
フレージングの方法は
大きく分けて2種類
①コードトーンによるフレージング
②コードスケールによるフレージング
となります。
フレーズの例)

B-7にテンション9、11がついているので
あえて音価の強いところに
9や11などがくるように
テンションの音を入れてみました。
E7のところでは、上昇のフレーズに
コードトーンがみえるフレーズを入れました。
また、B-7のフレーズの終点を
E7のRootになるように下降させてつなげてます
今回はここまで。
ちょっとおまけを入れ過ぎて
メインより長くなってしまった。
内容ぐちゃぐちゃになってすいません
テンションを含んだフレーズに慣れると
コードにテンション入れるのにも慣れるので
いろんなフレーズ、
作って試してみてくださいね
それではまた次回。
♪♪今回はRelated Ⅱ-7のavailable tensionです
Related Ⅱ-7コードのavailable tensionは
keyに対するtensionを考える前に
その解決先を
→『その場限りのkey』としてtensionをつけます
■その場限りのkey
(from the key of the moment)
セカンダリーⅤ7は、「Ⅰ」以外の
diatonic chordに解決させるためのⅤ7コードですが
本来のドミナント7thコードが持つ
Primary Ⅴ7としての機能で、
瞬間的には、元の調性からOutして、
他のkeyの「Ⅰ」に向かう進行感を感じさせます
この解決先を
その場限りのkeyと捉えます
たとえば)
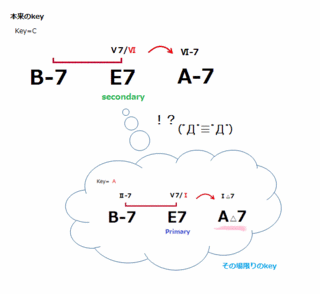
Key=C で、
セカンダリーⅤ7/ⅥのE7が向かうのは
diatonic Ⅵ-7のA-7ですが、
その場限りのkeyとしてみるなら
E7はプライマリーⅤ7として
key=A の「Ⅰ」に向かうので
その場限りのkeyは「A」となります
そして、
Related Ⅱ-7は、
セカンダリー Ⅴ7をⅡ-Ⅴ進行に
分割したものともいえるので
セカンダリーⅤ7の解決先のkeyに対する
Related Ⅱ-7 の役割を常にもっています
つまり、
その場限りのkeyの
2番目のdiatonic chordと同じものなので
Point!)
Related Ⅱ-7のavailable tensionは
ダイアトニックコードのⅡ-7と同じになります
注意) このテンションのつけかたは Ⅱ-Ⅴの進行感としての Related しているⅡ-7に対する テンションのつけ方です Dual function的な解釈で 本来のkeyの diatonic mainor 7thとして捉えた場合は 今までどおりのダイアトニックコードの available tensionのつけ方になります |
diatonic chordのavailable tensionはこちら
→diatonic chord(セブンス)
→diatonic chord(トライアド)
■RelatedⅡ-7のavailable tensionを確認する
以下にkey=Cの
それぞれのセカンダリーⅤ7に対する
RelatedⅡ-7のavailable tensionを載せました
どのRelated Ⅱ-7コードも
その場限りのkeyに対して
同じテンションのつき方をしているので
確認してみてください。
●Ⅴ7/Ⅱに対するRelated Ⅱ-7

●Ⅴ7/Ⅲに対するRelated Ⅱ-7
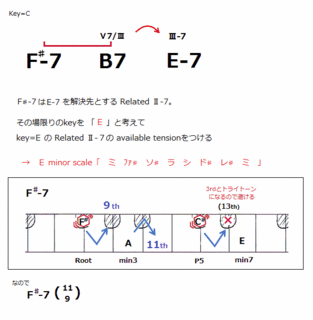
●Ⅴ7/Ⅳに対するRelated Ⅱ-7

●Ⅴ7/Ⅴに対するRelated Ⅱ-7
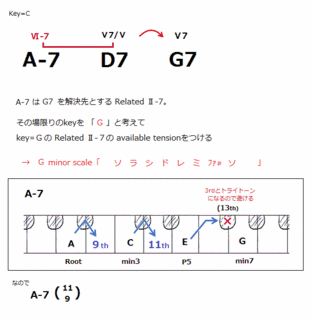
●Ⅴ7/Ⅵに対するRelated Ⅱ-7

それぞれの解決先に対するⅡ-7コードなので
その場限りのkeyが違っても、
available tensionはおなじです。
つまりは
これだけ覚えたら
かんたん。
→ related Ⅱ-7(9,11)
■おまけ
コード進行の例)

あえて本来のkeyからはRootがOutしている
related Ⅱ-7を利用したコード進行にしてみました
(Dual functionのないものだけ)
でも進行は自然です
使われているコードだけを見ていると
すごくOutしているように見えるけど
セカンダリー自体がちゃんと本来のkeyに
インサイドするための働きを持っているので
それに対するRelated Ⅱ-7が
diatonic chordじゃなくても
それはちゃんと
本来のkeyの調性の範囲内におさまります
こうした考えが
きっちり理解できていると
曲中にいろんなコードを加えて
複雑にしていっても
ちゃんと狙い通りの音楽がつくれるので
作曲の際のコード選びが、また自由になります
自由っていいよね。
さいごに)
もう1つおまけ
●フレーズの音選びについて
作曲であれば、フレーズに対して
狙い通りの進行感やコード感がでるように
つくっていきます。
コードなどの表記は、演奏者側が
そのニュアンスを読み取ってくれるように
テンションなどの情報を加えて
書き入れます
同様に
アドリブであれば、
スコアを見た時の情報から
そうした作曲者側の、曲の狙いを読み取って
使える音やスケールを判断していきます
たとえば、今回の例のように
Dual functionをあえて持たない進行であったり
Dual functionを持っていても、あえて
Related Ⅱ-7のtensionがついているような進行は
作曲者のⅡ-Ⅴぽさを出したいって
意図がニヤニヤ感じ取れるので
Ⅱ-Ⅴのニュアンスがはっきりでるような
フレーズを入れます。
ここでPoint)
Ⅱ-Ⅴのニュアンスが出るフレーズとは
かんたんにいうと
コード進行感がわかるフレーズにするという意味です
で、そのコード進行感を出すための
フレージングの方法は
大きく分けて2種類
①コードトーンによるフレージング
②コードスケールによるフレージング
となります。
フレーズの例)

B-7にテンション9、11がついているので
あえて音価の強いところに
9や11などがくるように
テンションの音を入れてみました。
E7のところでは、上昇のフレーズに
コードトーンがみえるフレーズを入れました。
また、B-7のフレーズの終点を
E7のRootになるように下降させてつなげてます
フレーズの話は今回の話とずれるので 後日フレーズの話で詳しくふれていきますが コード感やスケール感を フレーズでみせるコツを少しだけ触れると 音価の強いところから感じる 2音の使い方(インターバル)が大事です ●コードぽくしようとしても 2音が順次的に動いていると 何のコードかわかりづらいし ●スケールぽくしようとしても 音が飛び飛びに跳躍していると そこからは何のスケールかが伝わりにくい ●あと各コードのつながりを どのようにつなげるかで、 進行感を見せる上では重要です |
今回はここまで。
ちょっとおまけを入れ過ぎて
メインより長くなってしまった。
内容ぐちゃぐちゃになってすいません
テンションを含んだフレーズに慣れると
コードにテンション入れるのにも慣れるので
いろんなフレーズ、
作って試してみてくださいね
それではまた次回。
タグ:ポピュラーミュージック 音楽理論 音楽教室 related Ⅱ-7 その場限りのkey コードスケール フレーズのつくり方 プライマリードミナント セカンダリードミナント ダイアトニックコード available tension アウトサイド インサイド
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/3754431
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック