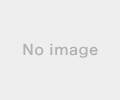2021年11月、エリック・バニヤン氏は、かつて「フォーエバー21」の店舗があったショッピングモール「ダンベリーフェア」の空きスペースに日本人ビジネスマンのグループを案内した。フォーエバー21は19年の運営会社の経営破綻後、2つのフロアから成る6万平方フィートのスペースを明け渡した。米コネティカット州にある同モールからは百貨店のシアーズとロード・アンド・テイラーも撤退し、厳しい状況にあった。
同モールを所有するメイスリッチでリースを担当していたバニヤン氏は、百貨店が栄光を取り戻すわけではないことを認識していた。下着やTシャツを買うにはインターネットのほうが「より良い、より速い、より安い選択肢がある」と言う同氏は、屋内型複合レジャー施設を運営するラウンドワン(大阪市)の担当者らが、巨大なスペースを人々が訪れようとするものに変える方法を提供してくれるかもしれないと考えた。
ラウンドワンの従業員らがダンベリーフェアの見学に訪れた当時、同社は経営難のモールのオーナーとの取引で既に10年超の実績があった。LED照明に照らされた日本のビデオゲームやサッポロビールを備えた同社の店舗は、米国内で既に数十ものモールに入居していた。ラウンドワンは、高齢化でゲームセンターの利用層が縮小する日本への依存を減らす方法として、米国で事業を拡大する取り組みを加速させている。ゲームセンターの誘致は、米国のショッピングモールにとって不可逆的な死のスパイラルと長い間考えられていた衰退から抜け出す方法のように見える。
ラウンドワンは3月にダンベリーフェアに店舗をオープンした。米国で54番目となる店舗で、他の53店舗と同様、異文化間のエンターテインメントに賭けている。このゲームセンターでは、ボーリングやチキンフィンガーといった米国人の楽しみに加え、たこ焼き、カラオケ、クレーンゲーム、そしておそらく最も特筆すべきは、大ヒットの音楽ゲーム「ダンスダンスレボリューション」といった日本の娯楽も提供されている。日本のアーケードゲーム機の輸出は著作権の関係で驚くほど複雑だが、これを設置することでラウンドワンは何時間も離れた遠方から貪欲なゲーマーを引き寄せることができ、ニューカマーの関心も集めるお祭りムードをつくり出せる。
「日本に行けない人たちに見てもらうのが狙いだ」。同社のシニアディレクター、ピーター・ユー氏が開店直前にずらりと並んだクレーンゲームの間を縫うように歩きながら話した。各クレーンゲームには、ぬいぐるみの種類ごとにラベルが貼られている。
ローラースケート場からスタート
ラウンドワンは1980年、まだ大学生だった杉野公彦社長が父親から引き継いだ大阪のローラースケート場からスタートした。そのスケート場は赤字続きで、杉野氏の父親が閉鎖を望んだのに対し、同氏は他の形のエンターテインメントに進出することを提案した。この基本的なアイデアが、LED照明の空間がうなるゲーマーやベビーボイスのアニメゲームで埋め尽くされた現代日本のゲームセンターへと発展し、ラウンドワンを10億ドル規模の企業へと成長させた。最も有名なのは大阪にある11階建ての複合施設で、ゲーム機やボーリング、バッティングケージ、バスケットボールコート、カラオケ、ゴーカートなどがあり、日本のゲーマーだけでなく米国の観光客も大勢訪れる。
2010年頃、ラウンドワンの幹部らは停滞への懸念が高まる中で行動を起こすことを決断。国内には105の拠点があったが、日本の少子化は深刻な脅威だと考えたのだ。次の約20年間について考える必要があると話すラウンドワンの米国社長兼最高経営責任者(CEO)、高橋博利氏は、日本で事業を拡大し続けるだけではだめだと指摘する。
その年、ラウンドワンは初の米国店舗をオープンした。同社が選んだ場所は、ロサンゼルス郊外の「プエンテヒルズ・モール」。このショッピングセンターは、1985年の映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のロケ地として知られるが、不振に陥っていた。それ以来、同社は米国で着実に事業を拡大し、24年3月期には米国の店舗が全体の売上高の37%を占め、5年前の16%から拡大した。
2024年05月31日
2024年05月30日
超長期金利の上昇止まらず、日銀オペ不透明
超長期国債利回りの上昇が止まらず、スワップとの金利差は30年物でアベノミクス前となる12年ぶりの水準に拡大した。日本銀行の国債買い入れオペを巡る不透明感という需給要因が歴史的な金利差を生み出している。
ブルームバーグのデータによると30年国債利回りとスワップの差は29日時点で42ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と2012年11月以来の水準に広がった。スワップ金利を払って国債を買うと、2年国債利回りを上回る42bpの収益を確保できる計算だ。スワップは変動金利と固定金利を交換する取引で、金利上昇時の保有債券の損失を補うヘッジ効果がある。
この差の拡大は投資家が金利上昇に備える一方、割安な超長期国債購入に消極的であることを示唆する。日銀が6月の金融政策決定会合で国債買い入れを現在の月6兆円程度から減らす方針を示すとの観測が、通常の金利裁定を妨げている。減額余地が大きい中長期金利が上がると価格変動の大きい超長期債がより上昇する。金利の高さだけでは外債運用中心の国内投資家の円債回帰につながらない。
「30年2%超」と「後出しじゃんけん」、生保の超長期債戦略
三井住友トラスト・アセットマネジメントの稲留克俊シニアストラテジストは、金利差拡大について「追加利上げよりも需給悪化の影響が国債利回りの上昇に表れている」と指摘した。パインブリッジ・インベストメンツ債券運用部の松川忠部長も「日銀があす政策変更するわけではなく、債券相場の下落は需給バランスの崩れによる要因が大きい」として「買いが入りづらくなっている」と述べた。
日銀は13日の国債買い入れオペで、残存期間「5年超10年以下」の購入額を500億円減らした。これを受けて市場では日銀が早期に国債買い入れ減額に動くとの観測が広がり、10年債をはじめ全年限にわたって金利上昇に弾みがついた。
日銀の安達誠司審議委員は29日の記者会見で、国債買い入れについて、将来のどこかの時点で減額させるとしながらも、債券市場の需給や機能度、流動性の状況を総合的に勘案しつつ「段階的に減額していくことが望ましい」とし、本格的な減額計画をあらかじめ示すことには慎重な認識を示した。
ブルームバーグのデータによると30年国債利回りとスワップの差は29日時点で42ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と2012年11月以来の水準に広がった。スワップ金利を払って国債を買うと、2年国債利回りを上回る42bpの収益を確保できる計算だ。スワップは変動金利と固定金利を交換する取引で、金利上昇時の保有債券の損失を補うヘッジ効果がある。
この差の拡大は投資家が金利上昇に備える一方、割安な超長期国債購入に消極的であることを示唆する。日銀が6月の金融政策決定会合で国債買い入れを現在の月6兆円程度から減らす方針を示すとの観測が、通常の金利裁定を妨げている。減額余地が大きい中長期金利が上がると価格変動の大きい超長期債がより上昇する。金利の高さだけでは外債運用中心の国内投資家の円債回帰につながらない。
「30年2%超」と「後出しじゃんけん」、生保の超長期債戦略
三井住友トラスト・アセットマネジメントの稲留克俊シニアストラテジストは、金利差拡大について「追加利上げよりも需給悪化の影響が国債利回りの上昇に表れている」と指摘した。パインブリッジ・インベストメンツ債券運用部の松川忠部長も「日銀があす政策変更するわけではなく、債券相場の下落は需給バランスの崩れによる要因が大きい」として「買いが入りづらくなっている」と述べた。
日銀は13日の国債買い入れオペで、残存期間「5年超10年以下」の購入額を500億円減らした。これを受けて市場では日銀が早期に国債買い入れ減額に動くとの観測が広がり、10年債をはじめ全年限にわたって金利上昇に弾みがついた。
日銀の安達誠司審議委員は29日の記者会見で、国債買い入れについて、将来のどこかの時点で減額させるとしながらも、債券市場の需給や機能度、流動性の状況を総合的に勘案しつつ「段階的に減額していくことが望ましい」とし、本格的な減額計画をあらかじめ示すことには慎重な認識を示した。
2024年05月29日
債券は下落か、米長期金利が大幅上昇−円安進行で日銀政策修正観測
29日の債券相場は下落が予想されている。米国の長期金利が5年と2年債の入札低調や強い米消費者信頼感指数を受けて大幅に上昇した流れを引き継ぐ。外国為替市場で1ドル=157円台へ円安が進行しており、日本銀行による早期の政策修正への警戒感も重しになりそうだ。
三井住友トラスト・アセットマネジメントの稲留克俊シニアストラテジストは、米長期金利が4.5%を超えて先物夜間取引は下げているとして、「朝方は売り先行で始まりそうだ。円安進行で日銀に政策修正のプレッシャーがかかるとみられることも重しになりそうだ」と述べた。
同氏の新発10年物国債利回りの予想レンジは1.035〜1.05%(28日は1.035%で終了)、先物中心限月6月物は143円20銭〜143円45銭(同143円50銭)。
米消費者信頼感、4カ月ぶりに上昇−インフレへの懸念は強まる
先物夜間取引で6月物は28日の日中取引終値比17銭安の143円33銭で終えた。
日銀の安達誠司審議委員は29日午前に熊本県金融経済懇談会で講演し、午後に記者会見する。早期の追加利上げや国債買い入れオペの減額に前向きな姿勢を示すかどうかが注目される。
三井住友トラストAMの稲留氏は、今週の債券相場の地合いは売り材料に反応しやすくなっており、「タカ派的な発言に反応して売られる可能性がある」との見方を示した。
三井住友トラスト・アセットマネジメントの稲留克俊シニアストラテジストは、米長期金利が4.5%を超えて先物夜間取引は下げているとして、「朝方は売り先行で始まりそうだ。円安進行で日銀に政策修正のプレッシャーがかかるとみられることも重しになりそうだ」と述べた。
同氏の新発10年物国債利回りの予想レンジは1.035〜1.05%(28日は1.035%で終了)、先物中心限月6月物は143円20銭〜143円45銭(同143円50銭)。
米消費者信頼感、4カ月ぶりに上昇−インフレへの懸念は強まる
先物夜間取引で6月物は28日の日中取引終値比17銭安の143円33銭で終えた。
日銀の安達誠司審議委員は29日午前に熊本県金融経済懇談会で講演し、午後に記者会見する。早期の追加利上げや国債買い入れオペの減額に前向きな姿勢を示すかどうかが注目される。
三井住友トラストAMの稲留氏は、今週の債券相場の地合いは売り材料に反応しやすくなっており、「タカ派的な発言に反応して売られる可能性がある」との見方を示した。
2024年05月28日
岸田首相が「日銀総裁を叱った」
官邸に呼び出し「くぎを刺した」
写真提供: 現代ビジネス
日銀の植田和男総裁が円安対応に苦心させられている。
4月26日の金融政策決定会合後の記者会見で足元の円安について「基調的な物価上昇率に今のところ大きな影響はない」と発言したことが仇となり、一時、1ドル=160円台と約34年ぶりの安値まで円安が進むきっかけを作った。
【写真】ヤバい円安に「財務省の宇宙人」もお手上げ
円相場を巡り、市場と激しい駆け引きを続けている官邸や財務省内では、相場の恐ろしさを熟知していない「植田総裁リスク」を警戒する声が拡大。連休明けの5月7日に岸田文雄首相から官邸に呼び出された植田氏は「市場の受け止め方には十分注意してください」などとくぎを刺されたという。
その後、植田氏は一転、過度な円安には利上げで対応する可能性を示唆するなど軌道修正に躍起の様子だ。
だが、4月の植田発言から景気や物価の先行きに自信を持ち切れない日銀の姿も見透かした市場では「前倒し利上げは難しい」との見方が根強く、円安牽制にはつながっていないのが実情だ。
「初心(うぶ)な総裁の発言は、円売りを仕掛ける投機筋から格好のカモにされた」
神田真人財務官(1987年旧大蔵省)の指揮の下、連休中も休日出勤態勢で円安に歯止めをかけるための大規模な円買い・ドル売りの「覆面介入」に奔走した財務省国際局幹部はこう嘆いた。
財務省でも非難轟々
植田氏の4月の記者会見での発言は、経済学者による物価情勢分析の観点からは正しいかもしれないが、国際金融マフィアからすれば「言わずもがなの不用意な発言」にほかならなかった。円安進行による物価高への懸念が内閣支持率を一層下落させるリスクに神経を尖らせている岸田政権を逆撫でし、政治的なハレーションも大きかった。
発言の軌道修正だけでは市場へのアピールが不十分と見たのか、日銀は5月13日、定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で長期国債の買い入れ額を500億円減らす行動に打って出た。
しかし、円相場の押し上げ効果が乏しかった半面、長期金利は一時1%台と約11年ぶりの高水準を付けるなど、政府にとって都合の悪い結果となった。財務省内では「植田失言の尻拭いで、無用な長期金利上昇を招いた」との不満の声も漏れる。個人的に親しい日銀幹部に「総裁の言動をもっとコントロールできないのか」と苦言を呈した財務官僚もいた。
昨春の総裁就任以来、学者らしい丁寧な説明をモットーにしてきた植田氏。記者会見では企画局が書いた想定問答を読まず、自分の言葉で語る場面もしばしばで、その姿勢こそが世論から評価されてきた。
周辺筋によると、黒田東彦前総裁が自分の主張を述べ立てるばかりで記者の質問をはぐらかす「官僚答弁」に終始し、不興を買ったことを反面教師にした面もあるという。
写真提供: 現代ビジネス
日銀の植田和男総裁が円安対応に苦心させられている。
4月26日の金融政策決定会合後の記者会見で足元の円安について「基調的な物価上昇率に今のところ大きな影響はない」と発言したことが仇となり、一時、1ドル=160円台と約34年ぶりの安値まで円安が進むきっかけを作った。
【写真】ヤバい円安に「財務省の宇宙人」もお手上げ
円相場を巡り、市場と激しい駆け引きを続けている官邸や財務省内では、相場の恐ろしさを熟知していない「植田総裁リスク」を警戒する声が拡大。連休明けの5月7日に岸田文雄首相から官邸に呼び出された植田氏は「市場の受け止め方には十分注意してください」などとくぎを刺されたという。
その後、植田氏は一転、過度な円安には利上げで対応する可能性を示唆するなど軌道修正に躍起の様子だ。
だが、4月の植田発言から景気や物価の先行きに自信を持ち切れない日銀の姿も見透かした市場では「前倒し利上げは難しい」との見方が根強く、円安牽制にはつながっていないのが実情だ。
「初心(うぶ)な総裁の発言は、円売りを仕掛ける投機筋から格好のカモにされた」
神田真人財務官(1987年旧大蔵省)の指揮の下、連休中も休日出勤態勢で円安に歯止めをかけるための大規模な円買い・ドル売りの「覆面介入」に奔走した財務省国際局幹部はこう嘆いた。
財務省でも非難轟々
植田氏の4月の記者会見での発言は、経済学者による物価情勢分析の観点からは正しいかもしれないが、国際金融マフィアからすれば「言わずもがなの不用意な発言」にほかならなかった。円安進行による物価高への懸念が内閣支持率を一層下落させるリスクに神経を尖らせている岸田政権を逆撫でし、政治的なハレーションも大きかった。
発言の軌道修正だけでは市場へのアピールが不十分と見たのか、日銀は5月13日、定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で長期国債の買い入れ額を500億円減らす行動に打って出た。
しかし、円相場の押し上げ効果が乏しかった半面、長期金利は一時1%台と約11年ぶりの高水準を付けるなど、政府にとって都合の悪い結果となった。財務省内では「植田失言の尻拭いで、無用な長期金利上昇を招いた」との不満の声も漏れる。個人的に親しい日銀幹部に「総裁の言動をもっとコントロールできないのか」と苦言を呈した財務官僚もいた。
昨春の総裁就任以来、学者らしい丁寧な説明をモットーにしてきた植田氏。記者会見では企画局が書いた想定問答を読まず、自分の言葉で語る場面もしばしばで、その姿勢こそが世論から評価されてきた。
周辺筋によると、黒田東彦前総裁が自分の主張を述べ立てるばかりで記者の質問をはぐらかす「官僚答弁」に終始し、不興を買ったことを反面教師にした面もあるという。
2024年05月27日
日銀、政策金利を年内に0.5%まで引き上げる余地
日銀は万全期したいだろうが、円安の副作用にも対処する必要
SBI金融経済研究所の政井貴子理事長がBTVに語る
日本銀行は、経済情勢がほぼこのまま推移すれば、年内に政策金利を0.5%まで引き上げる余地がある。元日銀審議委員でSBI金融経済研究所の政井貴子理事長がこうした見方を示した。
政井氏は27日午前、ブルームバーグテレビジョンのインタビューで、「実体経済次第だが、現状のような経済予想が続くのであれば、あと1回か2回の利上げで、0.5%ぐらいまで引き上げてもいいと思う」と語った。
同氏は企業や家計のインフレ期待が過去2年間の物価上昇で変化していると指摘。「日銀は万全を期したいだろうが、同時に円安といった副作用にも対処しなければならない。明るい面としては、企業業績は良好で、将来のための投資をする十分な能力がある」と述べた。
政井氏はさらに、日銀が円に関する情報発信を強化し、消費への影響を警戒する必要があると指摘した。同氏は2021年6月まで5年間、審議委員を務めた。
先週24日に発表された4月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)の前年比上昇率は2カ月連続で縮小した。コアCPIは前年同月比2.2%上昇と、日銀の目標の2%を2年1カ月連続で上回った。
消費者物価は2カ月連続伸び縮小、市場で追加利上げ時期探る展開続く
政井氏は、金融政策決定会合の「主な意見」や幹部発言を含む最近の日銀のコミュニケーションに基づくと、当局は国債イールドカーブのさらなるスティープ化を追求することに集中しているようだと指摘した。
同氏は、円安が経済に与える影響について日銀の具体的な評価を見定めるのはまだ難しいと説明。日銀は「この点について、何らかのコミュニケーションを取る必要がある」と述べた。
SBI金融経済研究所の政井貴子理事長がBTVに語る
日本銀行は、経済情勢がほぼこのまま推移すれば、年内に政策金利を0.5%まで引き上げる余地がある。元日銀審議委員でSBI金融経済研究所の政井貴子理事長がこうした見方を示した。
政井氏は27日午前、ブルームバーグテレビジョンのインタビューで、「実体経済次第だが、現状のような経済予想が続くのであれば、あと1回か2回の利上げで、0.5%ぐらいまで引き上げてもいいと思う」と語った。
同氏は企業や家計のインフレ期待が過去2年間の物価上昇で変化していると指摘。「日銀は万全を期したいだろうが、同時に円安といった副作用にも対処しなければならない。明るい面としては、企業業績は良好で、将来のための投資をする十分な能力がある」と述べた。
政井氏はさらに、日銀が円に関する情報発信を強化し、消費への影響を警戒する必要があると指摘した。同氏は2021年6月まで5年間、審議委員を務めた。
先週24日に発表された4月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)の前年比上昇率は2カ月連続で縮小した。コアCPIは前年同月比2.2%上昇と、日銀の目標の2%を2年1カ月連続で上回った。
消費者物価は2カ月連続伸び縮小、市場で追加利上げ時期探る展開続く
政井氏は、金融政策決定会合の「主な意見」や幹部発言を含む最近の日銀のコミュニケーションに基づくと、当局は国債イールドカーブのさらなるスティープ化を追求することに集中しているようだと指摘した。
同氏は、円安が経済に与える影響について日銀の具体的な評価を見定めるのはまだ難しいと説明。日銀は「この点について、何らかのコミュニケーションを取る必要がある」と述べた。
2024年05月26日
長期金利は市場で形成されることが基本
動向を今後も丁寧にモニタリング、日々の動きや水準にコメントせず
金利上昇は財政圧迫、気を引き締めて健全化に取り組む−鈴木財務相
日本銀行の植田和男総裁は25日、長期金利が12年ぶりの1%台に上昇していることに関し、長期金利は金融市場で形成されることが基本になると語った。イタリア・ストレーザで開催された主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議の終了後、記者会見した。
植田総裁は、大規模緩和の修正に踏み切った3月の金融政策決定会合で、国債買い入れは「これまでとおおむね同程度の金額で継続する」ことを決定したと説明し、「長期金利は金融市場で形成されることが基本になると考えている」と指摘。日々の短期的な金利の動向や水準にはコメントを控えるとしつつ、「市場の動向を今後とも丁寧にモニタリングをしていく」と述べた。
新発10年債利回りは22日に11年ぶりの1%に上昇し、24日には1.005%と12年ぶりの高水準を付けた。日銀が早期に国債買い入れの減額や追加利上げに踏み切るとの思惑が背景にあり、市場では植田総裁の見解に注目が集まっていた。
【日本市況】株式反落、長期金利は12年ぶり高水準−円は157円台軟調
会見に同席した鈴木俊一財務相は、「金利の上昇は利払い費の増加を招き、財政を圧迫する恐れがある」とし、これまで以上に気を引き締めて財政健全化の取り組みを進めていくと強調。低金利で国債が発行できた従来とは環境が異なるとし、「金利のある世界が到来したことを強く認識する必要がある」と主張した。
G7会議では、為替レートの過度の変動や無秩序の動きは経済および金融の安定に悪影響を与え得るとしたコミットメントが再確認されたと説明。G7期間中にイエレン米財務長官との会談は行われなかったとも述べた。
金利上昇は財政圧迫、気を引き締めて健全化に取り組む−鈴木財務相
日本銀行の植田和男総裁は25日、長期金利が12年ぶりの1%台に上昇していることに関し、長期金利は金融市場で形成されることが基本になると語った。イタリア・ストレーザで開催された主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議の終了後、記者会見した。
植田総裁は、大規模緩和の修正に踏み切った3月の金融政策決定会合で、国債買い入れは「これまでとおおむね同程度の金額で継続する」ことを決定したと説明し、「長期金利は金融市場で形成されることが基本になると考えている」と指摘。日々の短期的な金利の動向や水準にはコメントを控えるとしつつ、「市場の動向を今後とも丁寧にモニタリングをしていく」と述べた。
新発10年債利回りは22日に11年ぶりの1%に上昇し、24日には1.005%と12年ぶりの高水準を付けた。日銀が早期に国債買い入れの減額や追加利上げに踏み切るとの思惑が背景にあり、市場では植田総裁の見解に注目が集まっていた。
【日本市況】株式反落、長期金利は12年ぶり高水準−円は157円台軟調
会見に同席した鈴木俊一財務相は、「金利の上昇は利払い費の増加を招き、財政を圧迫する恐れがある」とし、これまで以上に気を引き締めて財政健全化の取り組みを進めていくと強調。低金利で国債が発行できた従来とは環境が異なるとし、「金利のある世界が到来したことを強く認識する必要がある」と主張した。
G7会議では、為替レートの過度の変動や無秩序の動きは経済および金融の安定に悪影響を与え得るとしたコミットメントが再確認されたと説明。G7期間中にイエレン米財務長官との会談は行われなかったとも述べた。
2024年05月25日
出資金を返還したバフェット
1967年、バフェットは出資者に対して「出資金の返還」を申し出る手紙を送った。「理解可能で価格も魅力的な投資先を見つけるのがどんどん難しくなっている」というのが理由だ。
1960年代後半はかなりの強気相場であったため、バフェットが望むような「(優良)投資案件」が市場からほとんど消え去っていたといえよう。簡単に言えば、企業の「本質的価値」(後述)を大幅に上回る株価で市場取引される「バブル」であったということだ。
その後、バフェットの積極的な動きは途絶えたのだが、1973年から株価が大幅に下落し、再び投資のチャンスが巡ってきた。そのチャンスに、(投資から遠ざかってため込んでいた)潤沢な現金が大活躍したのだ。ただし、その間バフェットは約6年間も静観を決め込んでいたということになる。
また、ドットコムバブル全盛であった1990年代後半も、バフェットはドットコム企業などに一切投資をせずに、やはり静観を決め込んだ。
バフェットがドットコム企業に投資しなかったのは、4月3日公開「バフェットの警鐘『ヘビの油売りに気をつけよ』の意味〜投資で成功するためには『自分の範囲』を見極めることだ」で述べたように(当時は)「IT・インターネットビジネスは『自分の範囲』ではない」と考えたことが大きな原因である。
だが、その頃のメディアは「バフェットはITやインターネットが分からない時代遅れのポンコツだ」と散々揶揄した。
それに対してバフェットは、ドットコム企業の経営者・幹部も多数参加するある講演会で、一冊の分厚い資料を聴衆に見せながらこう語った。
「皆さん、私の手元にあるのは米国自動車産業黎明期に存在した自動車メーカーの一覧表です。この無数の『新興』自動車メーカーの数が現在いくつになっているかご存じですよね?そう、たったの三つです(ビッグスリーのことを意味する)」と言い放ったのだ。
つまり、バフェットの前に居並ぶ聴衆たちが経営する「ドットコム企業」のほとんどは「いずれ消えてなくなりますよ……」と言ったのと同じことである。
1960年代後半はかなりの強気相場であったため、バフェットが望むような「(優良)投資案件」が市場からほとんど消え去っていたといえよう。簡単に言えば、企業の「本質的価値」(後述)を大幅に上回る株価で市場取引される「バブル」であったということだ。
その後、バフェットの積極的な動きは途絶えたのだが、1973年から株価が大幅に下落し、再び投資のチャンスが巡ってきた。そのチャンスに、(投資から遠ざかってため込んでいた)潤沢な現金が大活躍したのだ。ただし、その間バフェットは約6年間も静観を決め込んでいたということになる。
また、ドットコムバブル全盛であった1990年代後半も、バフェットはドットコム企業などに一切投資をせずに、やはり静観を決め込んだ。
バフェットがドットコム企業に投資しなかったのは、4月3日公開「バフェットの警鐘『ヘビの油売りに気をつけよ』の意味〜投資で成功するためには『自分の範囲』を見極めることだ」で述べたように(当時は)「IT・インターネットビジネスは『自分の範囲』ではない」と考えたことが大きな原因である。
だが、その頃のメディアは「バフェットはITやインターネットが分からない時代遅れのポンコツだ」と散々揶揄した。
それに対してバフェットは、ドットコム企業の経営者・幹部も多数参加するある講演会で、一冊の分厚い資料を聴衆に見せながらこう語った。
「皆さん、私の手元にあるのは米国自動車産業黎明期に存在した自動車メーカーの一覧表です。この無数の『新興』自動車メーカーの数が現在いくつになっているかご存じですよね?そう、たったの三つです(ビッグスリーのことを意味する)」と言い放ったのだ。
つまり、バフェットの前に居並ぶ聴衆たちが経営する「ドットコム企業」のほとんどは「いずれ消えてなくなりますよ……」と言ったのと同じことである。
2024年05月24日
これから「人件費の安い日本」に工場は戻ってくる
iPhoneの製造場所が中国からインドに移転するなど、サプライチェーンの世界的な再編が起きつつある。エコノミストのエミン・ユルマズさんとフリーアナウンサーの大橋ひろこさんの書籍『無敵の日本経済! 株とゴールドの「先読み」投資術』(ビジネス社)より、一部をお届けする――。
■サプライチェーンが日本に戻ってきている理由
【エミン・ユルマズ(以下、エミン)】中国の変化により、結果的には西側諸国は中国と距離を置いていくことになり、ものづくりのサプライチェーンが日本をはじめとした先進諸国に戻ってきています。
もう一つは、ウクライナ戦争による影響で、先進諸国に重要な動きが見られることです。
経済制裁されたロシアがその報復として、ドイツをはじめとした先進諸国に天然ガスを売らなくなりました。結果的にドイツは何とかして乗り越えたけれども、ガス価格が上がり、インフレに見舞われています。
そんな現実を踏まえて、先進諸国は完全に方針を“転換”したのです。エネルギーの調達を権威主義国家に依存しないようにしようと。
【大橋ひろこ(以下、大橋)】自分たちの影響力圏内で何とかできるようにしようと。
【エミン】そうです。資源供給を含めて、従来とは異なる自由主義陣営内でのサプライチェーンをつくるべきだと、考えを改めたのです。
【大橋】サプライチェーンを再構築する動きですね。
「インドのiPhone」は品質に疑問
【エミン】要は、グローバル化から“ブロック化”に移行するということなのです。でも、それは結果的に“コスト増”を招きます。
【大橋】それはそうですよね。全般的にコストの高い、自由主義陣営内でサプライチェーンを築くわけですから。
【エミン】これに対して、少しでもコストを抑えようとして、多くの人は「コストが安い国に、先進国用の供給メーカーを連れて行けばいい」と主張するわけです。中国の代わりに、例えばベトナムとかマレーシアとか、あるいはインドネシアとか。
しかしながら、ハイテクな部品のなかでも、最上位にある部品の製造については、申し訳ないけれど、そのような国に技術的な蓄積があるとは思えない。製造を任せられるほど、信用することはできないでしょう。
【大橋】インドでiPhoneをつくり始めていますが、専門家の話では、品質が芳しくないらしい。製造した工場によって品質にバラつきが見られると聞いています。
■サプライチェーンが日本に戻ってきている理由
【エミン・ユルマズ(以下、エミン)】中国の変化により、結果的には西側諸国は中国と距離を置いていくことになり、ものづくりのサプライチェーンが日本をはじめとした先進諸国に戻ってきています。
もう一つは、ウクライナ戦争による影響で、先進諸国に重要な動きが見られることです。
経済制裁されたロシアがその報復として、ドイツをはじめとした先進諸国に天然ガスを売らなくなりました。結果的にドイツは何とかして乗り越えたけれども、ガス価格が上がり、インフレに見舞われています。
そんな現実を踏まえて、先進諸国は完全に方針を“転換”したのです。エネルギーの調達を権威主義国家に依存しないようにしようと。
【大橋ひろこ(以下、大橋)】自分たちの影響力圏内で何とかできるようにしようと。
【エミン】そうです。資源供給を含めて、従来とは異なる自由主義陣営内でのサプライチェーンをつくるべきだと、考えを改めたのです。
【大橋】サプライチェーンを再構築する動きですね。
「インドのiPhone」は品質に疑問
【エミン】要は、グローバル化から“ブロック化”に移行するということなのです。でも、それは結果的に“コスト増”を招きます。
【大橋】それはそうですよね。全般的にコストの高い、自由主義陣営内でサプライチェーンを築くわけですから。
【エミン】これに対して、少しでもコストを抑えようとして、多くの人は「コストが安い国に、先進国用の供給メーカーを連れて行けばいい」と主張するわけです。中国の代わりに、例えばベトナムとかマレーシアとか、あるいはインドネシアとか。
しかしながら、ハイテクな部品のなかでも、最上位にある部品の製造については、申し訳ないけれど、そのような国に技術的な蓄積があるとは思えない。製造を任せられるほど、信用することはできないでしょう。
【大橋】インドでiPhoneをつくり始めていますが、専門家の話では、品質が芳しくないらしい。製造した工場によって品質にバラつきが見られると聞いています。
2024年05月23日
エヌビディア、5─7月売上高見通しが予想超え
米半導体大手エヌビディア(NVDA.O), opens new tabが22日発表した第2・四半期(5─7月)の売上高見通しは市場予想を上回った。人工知能(AI)向け半導体の需要拡大を見込む投資家の期待に応える結果となった。1株を10株に分割する計画も明らかにした。
第2・四半期の売上高見通しは280億ドルプラスマイナス2%。LSEGがまとめたアナリスト予想は266億6000万ドルだった。
株価は引け後の時間外取引で2.7%上昇。同社の株価は年初来で90%以上上昇している。
第1・四半期(2─4月)の売上高は前年比262%増の260億4000万ドルと、市場予想の246億5000万ドルを上回った。純利益は628%増の148億8000万ドル。
エドワード・ジョーンズのアナリスト、ローガン・パーク氏は「エヌビディアの画像処理半導体(GPU)に対する需要は引き続き非常に強い」と指摘。「今回の決算はおそらく投資家の期待に応えるのに十分で、AI関連投資がまだ減速していないという安心感を市場に与えるだろう」と述べた。
稼ぎ頭のデータセンター部門は第1・四半期売上高が427%増の226億ドルと、ファクトセットがまとめた予想の213億2000万ドルを上回った。
カーソン・グループのチーフ市場ストラテジスト、ライアン・デトリック氏は「エヌビディアは大きな期待の中でも再び結果を出した」とし、重要なデータセンターの売上高が好調だったほか、今後の売上高見通しも非常に良い内容だったと評価した。
第2・四半期の調整後粗利益率見通しは75.5%プラスマイナス0.5%。市場予想は75.8%だった。
第1・四半期の調整後粗利益率は78.9%、予想は77%だった。諸項目を除いた1株利益は6.12ドルと、予想の5.59ドルを上回った。
株式分割は6月7日を効力発生日として実施する。分割後の四半期配当を150%引き上げ、1株当たり1セントとすることも発表した。
第2・四半期の売上高見通しは280億ドルプラスマイナス2%。LSEGがまとめたアナリスト予想は266億6000万ドルだった。
株価は引け後の時間外取引で2.7%上昇。同社の株価は年初来で90%以上上昇している。
第1・四半期(2─4月)の売上高は前年比262%増の260億4000万ドルと、市場予想の246億5000万ドルを上回った。純利益は628%増の148億8000万ドル。
エドワード・ジョーンズのアナリスト、ローガン・パーク氏は「エヌビディアの画像処理半導体(GPU)に対する需要は引き続き非常に強い」と指摘。「今回の決算はおそらく投資家の期待に応えるのに十分で、AI関連投資がまだ減速していないという安心感を市場に与えるだろう」と述べた。
稼ぎ頭のデータセンター部門は第1・四半期売上高が427%増の226億ドルと、ファクトセットがまとめた予想の213億2000万ドルを上回った。
カーソン・グループのチーフ市場ストラテジスト、ライアン・デトリック氏は「エヌビディアは大きな期待の中でも再び結果を出した」とし、重要なデータセンターの売上高が好調だったほか、今後の売上高見通しも非常に良い内容だったと評価した。
第2・四半期の調整後粗利益率見通しは75.5%プラスマイナス0.5%。市場予想は75.8%だった。
第1・四半期の調整後粗利益率は78.9%、予想は77%だった。諸項目を除いた1株利益は6.12ドルと、予想の5.59ドルを上回った。
株式分割は6月7日を効力発生日として実施する。分割後の四半期配当を150%引き上げ、1株当たり1セントとすることも発表した。
2024年05月22日
ウォラーFRB理事、インフレ良好に推移なら年末の利下げ検討可能
物価データの成績は「Cプラス」、落第ではないが優秀とも言えず
アトランタ連銀総裁、10−12月に利下げ開始できる可能性高い
米連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事は21日、物価データの軟化が今後3−5カ月間続けば、金融当局は年末の利下げ実施も検討できるだろうと述べた。
同理事は米経済専門局CNBCとのインタビューで、「データが今後3−5カ月間にわたり軟化し続けた場合は、年末の実施さえも考えられる」と発言。「正しい方向に向かうデータが十分得られたなら、われわれは年内ないし来年初めの利下げを考えることができる」と語った。
ウォラー理事はこの日、ピーターソン国際経済研究所で講演し、利下げを開始するには良好なインフレ数値を「あと数カ月」確認する必要があると述べていた。
同理事は講演で4月の消費者物価指数(CPI)について、物価圧力が加速していない兆候だと指摘。4月のCPIは変動の大きい食品とエネルギーを除くコアベースで、前月比の伸びが6カ月ぶりに鈍化した。同理事はまた4月の小売売上高についても、労働市場の減速を示唆する兆候だとした。
「最新のCPIデータはインフレが加速していないという良い兆候であり、消費と労働市場に関するデータはインフレを押し下げる圧力を加えるという意味で、金融政策が適切に設定されていることを示唆していると私には見受けられる」と述べた。
また同理事は質疑応答で、「3、4カ月の据え置きで経済が崖から急転落するようなことにはならないだろう」と話した。
ウォラー理事以外にも複数の当局者がここ最近、政策金利を従来想定していたよりも長期間据え置く必要性があるかもしれないとの見解を示している。政策金利は昨年7月から23年ぶりの高水準に据え置かれている。
同理事は講演で、2%目標に向かうという意味で物価データは小幅な進展を見せたに過ぎないとし、「私がまだ教授で、このインフレ統計に成績を付けるとすれば、Cプラスを与えるだろう。落第から程遠いが優秀とも言えない」と発言した。
さらに、「労働市場に著しい軟化が見られないため、金融政策のスタンス緩和を快く支持するには、もう数カ月良好なインフレデータを確認する必要がある」と述べた。追加利上げは「恐らく不要だろう」とも話した。講演後のディスカッションでは、金利の次の動きは引き下げだろうとの予想を示した。
アトランタ連銀総裁
これより先、アトランタ連銀のボスティック総裁は景気を刺激することも減速させることもない中立金利の水準を巡って、金融当局者は活発な議論を行っていると述べた。
ボスティック氏は長期的な中立金利について「誰もがそのダイナミクスを再考している」とした上で、「まだ結論は出ていない。年内に一段と深く掘り下げていくことになるだろう」と話した。アトランタ連銀がフロリダ州アメリア島で開催した会議の合間に記者団に語った。
さらにインフレが今後も緩やかに鈍化するとの見方を改めて表明。米金融当局は10−12月(第4四半期)に利下げを開始できる可能性が高いと述べた。
アトランタ連銀総裁、10−12月に利下げ開始できる可能性高い
米連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事は21日、物価データの軟化が今後3−5カ月間続けば、金融当局は年末の利下げ実施も検討できるだろうと述べた。
同理事は米経済専門局CNBCとのインタビューで、「データが今後3−5カ月間にわたり軟化し続けた場合は、年末の実施さえも考えられる」と発言。「正しい方向に向かうデータが十分得られたなら、われわれは年内ないし来年初めの利下げを考えることができる」と語った。
ウォラー理事はこの日、ピーターソン国際経済研究所で講演し、利下げを開始するには良好なインフレ数値を「あと数カ月」確認する必要があると述べていた。
同理事は講演で4月の消費者物価指数(CPI)について、物価圧力が加速していない兆候だと指摘。4月のCPIは変動の大きい食品とエネルギーを除くコアベースで、前月比の伸びが6カ月ぶりに鈍化した。同理事はまた4月の小売売上高についても、労働市場の減速を示唆する兆候だとした。
「最新のCPIデータはインフレが加速していないという良い兆候であり、消費と労働市場に関するデータはインフレを押し下げる圧力を加えるという意味で、金融政策が適切に設定されていることを示唆していると私には見受けられる」と述べた。
また同理事は質疑応答で、「3、4カ月の据え置きで経済が崖から急転落するようなことにはならないだろう」と話した。
ウォラー理事以外にも複数の当局者がここ最近、政策金利を従来想定していたよりも長期間据え置く必要性があるかもしれないとの見解を示している。政策金利は昨年7月から23年ぶりの高水準に据え置かれている。
同理事は講演で、2%目標に向かうという意味で物価データは小幅な進展を見せたに過ぎないとし、「私がまだ教授で、このインフレ統計に成績を付けるとすれば、Cプラスを与えるだろう。落第から程遠いが優秀とも言えない」と発言した。
さらに、「労働市場に著しい軟化が見られないため、金融政策のスタンス緩和を快く支持するには、もう数カ月良好なインフレデータを確認する必要がある」と述べた。追加利上げは「恐らく不要だろう」とも話した。講演後のディスカッションでは、金利の次の動きは引き下げだろうとの予想を示した。
アトランタ連銀総裁
これより先、アトランタ連銀のボスティック総裁は景気を刺激することも減速させることもない中立金利の水準を巡って、金融当局者は活発な議論を行っていると述べた。
ボスティック氏は長期的な中立金利について「誰もがそのダイナミクスを再考している」とした上で、「まだ結論は出ていない。年内に一段と深く掘り下げていくことになるだろう」と話した。アトランタ連銀がフロリダ州アメリア島で開催した会議の合間に記者団に語った。
さらにインフレが今後も緩やかに鈍化するとの見方を改めて表明。米金融当局は10−12月(第4四半期)に利下げを開始できる可能性が高いと述べた。