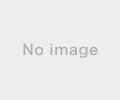2017年02月15日
書評『生物多様性とは何か』
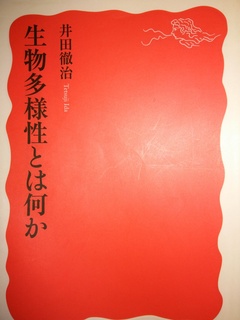
こんにちわ、小谷中広之です
「小谷中広之」が読んだ本の書評をします。「小谷中広之」なりに感じたこと(感情)を書き、少しでも皆様の何かのきっかけになれればこのうえない喜びです(定期的に書評は更新していきます)
「小谷中広之」が感じ、思った事を書きたいと思っております
今回のご紹介する本は、井田徹治様の「生物多様性とは何か」です
このような方にお勧めです
「自然に興味のある人 自然にかかわる仕事をしている人」
著者の方のプロフィール
「1959年生まれ 著者 環境、エネルギー、開発問題を25年以上、取材し続けている また自然保護の取り組みなどを取材しています。」
まとめ
人間は、人間だけの勝手な考えだけでは決して生きてはいけない
ハゲワシがいなくなれば、その周辺では、農地などに多くの生物の死骸が処理されずに残される。そしてこれらを今まではハゲワシがスカベンジャーであったが、そのハゲワシがいなくなってしまったばかりに、代わって野犬やネズミが急激に増え狂犬病などの病気で年間の死者が3万人にも及んだインドとその周辺
中年米の先住民は、古くからバニラを伝統的な医薬品として使ってきた。19世紀にヨーロッパ人がそのバニラの株を持ち帰って移植したが、大きく育ち花も咲いたのだが実がならない。その理由は長いあいだ不明だったが、やがてハリナシミツバチがいなければ受粉が起こらないことが判明。現在アフリカのマダガスカルで栽培されているが、ハチがいないためすべて人間の手作業で行っているという
狼が絶滅してしまったために、鹿などが増殖し植物や農家に対する食害が深刻化しています
また、農業が衰退している日本では田んぼが減ってきていますが、田んぼが減れば必ず同じように減っていく生物が存在するでしょう。例えばトンボやヤゴやカエルなどです。そしてこれらの生物が減れば、これらの生物を食べて生きていた生物も減ることになり、その結果土壌やその地域の空気などが変化して、もしかしたら人体への悪影響へとなってしまう原因になるかもしれません
そして、植物には必ずと言っていいほど媒介するものが必要となる。もし虫媒に依存している植物が虫媒してくれるムシが絶滅してしまえば、同じように依存していたその植物も絶滅してしまう危険がある
これと同じように人間も必ずそれぞれに依存している何かがある、その依存している何かが何かの拍子に絶滅してしまえば、また亡くなってしまえば、同じように死を選択してしまう行動をとらざるをえなくなってしまうのではないでしょうか
地球上の生物が与えてくれる恩恵の大きさと、それが失われた時の影響の大きさをしっかりと考えてみましょう
生態系の維持にとくに重要な種は「キ―ストーン種」と呼ばれています。このキ―ストーン種をしっかりと見極め、それに対してどのような行動をとっていくか、言ってしまえばどのように共存共栄していくのかを考えてみましょう
ここまで読んでいただきありがとうございます。読んでいただいた方の人生での何かのお役に立てればとても嬉しいです
この本の他の文章が気になった方下記のサイトで購入可能です。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144a17ac.c8562bfa.144a17ad.e20d474b/?me_id=1213310&item_id=13700479&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2574%2F9784004312574.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2574%2F9784004312574.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext) 生物多様性とは何か [ 井田徹治 ] |
⇓私の会社のホームページです。コラムも書いていますので覗いてみてください⇓
http://cycleair.jp/
タグ:井田徹治 様
【このカテゴリーの最新記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/5742555
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック