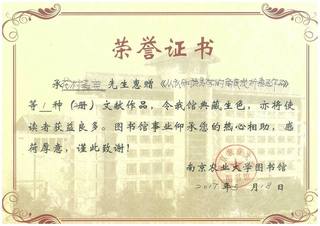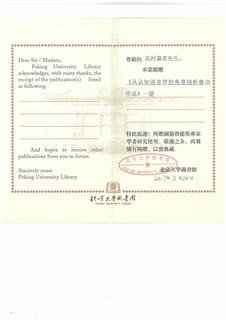データベースの作成法について説明する。エクセルのデータについては、列の前半(文法1から意味5)が構文や意味の解析データ、後半(医学情報から人工知能)が理系に寄せる生成のデータである。一応、L(受容と共生)を反映している。データベースの数字は、登場人物を動かしながら考えている。
こうしたデータベースを作る場合、共生のカラムの設定が難しい。受容はそれぞれの言語ごとに構文と意味を解析し、何かの組を作ればよい。しかし、共生は作家の知的財産に基づいた脳の活動が問題になるため、作家ごとにカラムが変わる。
【データベースの作成】表1「Wunschloses Unglück」のデータベースのカラム
項目名 内容 説明
文法1 態 能動、受動、使役。
文法2 時制、相 現在、過去、未来、進行形、完了形。
文法3 様相 可能、推量、義務、必然。
意味1 喜怒哀楽 喜怒哀楽と記事なし。
意味2 五感 視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚。
意味3 振舞い ジェスチャー、身振り。直示と隠喩を考える。
意味4 感情の縺れ あり、なし。
医学情報 病跡学との接点 受容と共生の共有点。構文や意味の解析から得た組「母の半生と精神疾患」と病跡学でリンクを張るためにメディカル情報を入れる。
記憶 短期、作業記憶、長期(陳述と非陳述) 作品から読み取れる記憶を拾う。長期記憶は陳述と非陳述に分類される。
情報の認知1 感覚情報の捉え方 感覚器官からの情報に注目するため、対象の捉え方が問題になる。例えば、ベースとプロファイルやグループ化または条件反射。
情報の認知2 記憶と学習 外部からの情報を既存の知識構造に組み込む。その際、未知の情報は、学習につながるためカテゴリー化する。記憶の型として、短期、作業記憶、長期を考える。
情報の認知3 計画、問題解決、推論 受け取った情報は、計画を立てるときにも役に立つ。目的に応じて問題を分析し、解決策を探っていく。獲得した情報が完全でない場合、推論が必要になる。
人工知能 記憶と感情 エキスパートシステム 記憶は、情報を脳に書き込み、保持し、意識にのせる三段階の機能かならなる。感情は、驚き、怒り、喜び、恐怖、悲しみ、嫌悪など状況に反応して進行する複雑な感覚のこと。
花村嘉英(2020)「ペーター・ハントケの『幸せではないが、もういい』の執筆脳について」より
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image