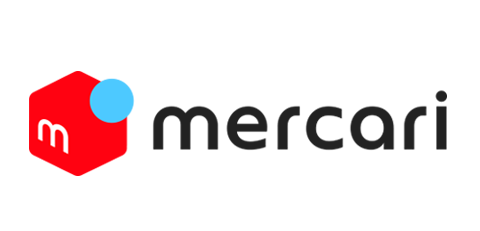むかしむかし、山深い村に、奇妙な噂が流れていた。村人たちは「大鹿」と呼んでいたが、それはただの鹿ではなかった。その姿は他の鹿と違い、まるで虹が地上に降り立ったかのような、不思議な色に輝いていた。
ある日、その村に住む若者の太郎が山へ狩りに出かけた。太郎は村でも腕利きの猟師で、誰よりも山を知り尽くしていた。しかし、今日はいつもと違って、山の奥深くへと足を進めていた。理由は一つ。最近、村で「奇しき色の大鹿」を見たという噂が絶えなかったからだ。太郎もその鹿を目にし、捕らえたいと心に決めていた。
木々が風に揺れ、鳥たちが鳴く音の中、太郎は静かに山を歩いていた。そして、ふと前方に目を向けたその瞬間――信じられない光景が広がっていた。目の前に、噂の「奇しき色の大鹿」が立っていたのだ。その毛並みは青や緑、黄金のように光り、目を奪われる美しさだった。まるで自然そのものがこの鹿を祝福しているかのようだった。
太郎は静かに弓を構えた。心臓の鼓動が耳元に響く。射止めることができれば、村の英雄になれる――そう思い、矢を引いた。しかし、放とうとしたその瞬間、大鹿が太郎をじっと見つめた。その瞳は驚くほど静かで、深い知恵を秘めているかのようだった。
太郎は動けなくなった。まるで、その瞳に何か言葉にならない力で引き寄せられたかのようだった。矢を放つことができず、ただじっと大鹿を見つめ返していた。
しばらくの間、二人は無言で対峙していた。しかし突然、大鹿はゆっくりと森の奥へと歩き出した。太郎は、その後を追うべきか迷ったが、体は動かなかった。まるで、大鹿が「追ってはいけない」と言っているような気がしたのだ。
そして、森の中にその不思議な姿が消えたとき、太郎は深い安堵とともに弓を下ろした。彼はその場に立ち尽くし、何も言えなかった。あの大鹿は一体何者だったのか。捕まえることができたのに、なぜ手を出さなかったのか。
村に戻った太郎は、誰にも大鹿の話をしなかった。ただ、あの不思議な瞳が今でも心に焼き付いて離れなかった。そして、太郎はそれ以降、二度とその大鹿に遭遇することはなかった。
その後も、村には「奇しき色の大鹿」の噂は絶えなかったが、誰一人としてその鹿を捕まえることはできなかったという。大鹿はまるで、山そのものの精霊のように、静かに山中を歩き続けているのかもしれない。
それは、自然と人間の間に存在する、目には見えない境界を守り続けるものだったのだろう。
ギャグ編
むかしむかし、山深い村に住む太郎という若者がいた。太郎は村一番の自信家で、「俺の狩りの腕前にかかれば、山のすべての動物はビビって震えるぜ!」なんて、毎晩のように酒を飲みながら自慢していた。そんな太郎に、ある日ふと噂が耳に入った。
「おい、聞いたか?奇しき色の大鹿がこの山に出るらしいぞ!」
「奇しき…何だって?」太郎は酒をこぼしながら聞き返した。
「奇しき色の大鹿だよ!何やら青やら緑やら、虹みたいな色してるってさ。」
太郎は思わず笑い転げた。「ははは!そんな馬鹿な話があるか!鹿が虹色なんて、俺の夢の中でしか見たことねぇぞ!」
だが、酔いが冷めると、太郎の中の狩り魂が燃え上がった。「よし、明日その大鹿を捕まえて、村一番の英雄になるか!」
翌朝、太郎は弓と矢を持って、さっそうと山へ向かった。いつもの道ではなく、噂の大鹿がいるという山の奥深くへと足を進めた。木々の間を歩きながら、太郎は心の中でひとり言をつぶやいていた。「虹色の鹿?まさか。次は星が落ちてくる話でもするんじゃねぇか。」
そうしてしばらく進んでいると、突然、太郎の目に信じられない光景が飛び込んできた。なんと、そこには噂の通り、青や緑、黄金色に輝く鹿が立っていたのだ!
「う、嘘だろ…!本当にいたのか!?」太郎は驚きのあまり、声が裏返った。
大鹿は、そんな太郎をまるで「また一人来たな」って感じで、冷めた目で見つめ返した。
太郎は慌てて弓を構え、心臓がドキドキしながらも矢を引いた。しかし、大鹿の瞳が妙に落ち着いていて、まるで「お前、本当に矢を放つつもりか?」とでも言いたげだった。
「う…うるさい!俺は村一番の猟師だ!この矢で仕留めてやる!」太郎は自分に言い聞かせ、力いっぱい矢を引いた。
だが、その瞬間、大鹿がふいに頭を傾けて太郎にこう問いかけるかのような表情をした。「お前、その矢で当てられる自信、本当にあるのか?」
太郎はその一瞬、体が固まった。そう言われてみれば、最近あんまり練習してないし、前回も狙った的を外して村人に笑われたし…。
「はっ、いやいや、関係ねぇ!この俺が外すわけが…」と言いかけたその瞬間、大鹿は鼻でフンッと笑ったように見えた。
「えっ?今笑った?鹿って笑うのか?」太郎は混乱しながら、矢を放とうとしたが、どうにも手が震えて放てない。
そのとき、大鹿は悠然と森の奥へ歩き出した。まるで、「この勝負、お前の負けだな」とでも言いたげに。
太郎は茫然と立ち尽くしながら、大鹿の背中を見送った。「な、なんで俺、矢を放てなかったんだ…?」
村に帰った太郎は誰にもその出来事を話さなかった。なぜなら、鹿に鼻で笑われたなんて話したら、村中の笑い者になること間違いなしだからだ。
それからというもの、太郎は村の居酒屋で「俺は大鹿と対峙したけど、あえて見逃してやったんだ。英雄は、必ずしも矢を放たないものさ」と、得意げに話すようになった。
だが、村人たちはみんな内心こう思っていた。「おいおい、太郎よ、あの虹色の大鹿に笑われたって話、誰かが知ってるぞ。」
そして村では、いつの間にか「太郎、鹿に笑われる」という新たな噂が広まっていたのだった。