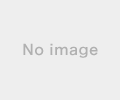古墳時代、ヤマト王権との関係が深かった一つの証しだ。
古墳群は標高60~80m の西都原台地が中心。
「一ツ瀬川の中流右岸の勢力が首長を埋葬古墳群でしょう。」
県立西都原考古博物館の東憲章副館長が解説する。
天照大神の命令で地上に降り立った孫のニニギノミコトと、その妻コノハナサクヤヒメの墓との伝承も残る。
<何故ここに?>
神話では現在の宮崎、鹿児島県境にある高千穂峰、或いは宮崎県高千穂町が「天孫降臨」の地とされます。
その子孫、神武天皇は船軍を率いて日向を出て、大和を平定し初代の天皇の位に就いたとなっています。
8世紀に成立した日本書紀や古事記にある神話を、作り話として否定する時期もありましたが、近年は弥生や古墳の時代に起きた事を示唆するとの見方もあります。
天皇の祖先が大和に降臨しても良かったはずです。
態々南九州に降り立った話となったのは、何らかの影響力のある豪族、勢力がいたと考える事も出来ます。
<どんな勢力?>
種子島の貝も使う様になると、現在の鹿児島県の志布志、内陸の宮崎県の都城を経て日向灘、豊後水道、瀬戸内海を通って運ばれました。
こう言う海運に携わる人々が南九州にいたと考えられます。
勿論中国、朝鮮半島とも繋がるルートもあったはずです。
ヤマトは南九州と結ぶ事で北部を牽制する意図もあったのでしょう。
馬は古墳時代に半島から導入され日向で育てられた様です。
殉葬は大陸の風習なので馬を飼う技術者も半島から来たのでしょう。
前方後円墳を何処にどの大きさで造るかは、ヤマト王権が地方の豪族との関係、支配の視点から差配していたはずです。
<古墳群が多くある>
年代毎に違うのです。
これは広域の首長連合があって盟主の座を定期的に交代していたとも言えますし、ヤマト王権内の権力争いとその結果が反映されたとも想像できます。
古墳群がある関東などの地域でも同様の傾向にあります。
宮崎県立西都原考古博物館 東 憲章副館長
愛媛新聞 歴史を旅するから
この地域では盗掘が増えているらしい。
持田古墳群(高鍋町)から盗掘された銅鏡は高い値段で取引されたらしい。
宇和にも古墳がある。
歴史は勝者が作る。
だから都合の良い様に作り替える。
自民党と同じだ。
負けた者の見方も知る必要がある。
でないと本当の事は分からない。