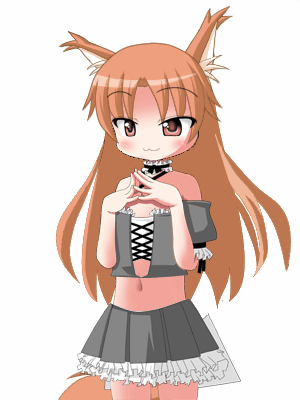2009年02月03日
『学園侵略計画! 個別面談にご用心!?』 part5
その翌日、登校途中に達也の姿を見つけた菫は、一緒に帰るという昨日の約束を破っ
て何をしていたのかと彼を問い詰めた。連絡しても全く電話がつながらないので、
何かあったんじゃないかと心配する彼女に対し、少年は心からすまなそうに、先生か
ら頼まれた用事でどうしても外せなかったと謝罪し、後で埋め合わせは必ずするから
許してくれと頭を下げた。
その様子には嘘をついている風もなかった。菫としても恋人とそんな些細なことでけ
んかをしたくなかったため、彼女はかすかに心に引っかかるものは感じたものの、こ
の件についてはそれでおしまいにすることにした。
「でも、今度からはちゃんと連絡入れてよね?」
「わかった、もう約束をすっぽかすようなことは二度としないよ」
最後にもう一度だけ念を押すと、そのまま二人は並んで学園への道を歩き始めた。
テーレッテー
放課後、帰り支度をしていると彼女の携帯電話が着信ありのメロディーを奏でた。
ポケットから小さな機械を探り当てると取り出し、二つ折りのそれを開いて画面を見
る。四角い液晶にはメール受信の旨と、送信者の名前が表示されていた。
「……あれ? 達也君からじゃない。珍しいわね。なんだろ、わざわざ……」
別に、彼氏である達也から彼女にメールが来ること自体はよくあることで不思議でも
なんでもない。しかし、彼とはクラスが同じであることから、それほど重要な用件で
ない限り大抵の場合は直接会って話してくるのが普通だ。メールを送ってくるにして
も意外と几帳面な彼は、題名にも中身が分かるようなことを書いてくるはずだった。
「今大丈夫?」とだけ書かれた簡潔な題名に疑問を浮かべながらも、菫はボタンを操
作し彼氏から送られてきたメールの本文をディスプレイに表示させる。
だが、それはますます彼女の混乱を深めるばかりだった。
『話したいことがある。学園特別棟3階、一番端の教室で待ってる』
メールはそれだけで終わっていた。いつもの彼らしくないそっけない一方的な呼び出
しに一抹の不安を感じる。思い返せば今日の彼は一日中、なんだかそわそわしていた
ような気がした。授業が終わった後も、わき目も振らず教室を飛び出していった姿を
彼女も目にしている。
「う〜ん、気になるけど……ここで考えていても仕方ないわよね。当人が呼び出して
きているんだし,会って直接聞いた方が早いわ」
彼女はそう自分を納得させると、勉強道具を詰め込んだ鞄を手に教室を後にした。
夕日が窓から射し込み、茜色に染まる廊下はどこか不安を掻き立てる。逢魔が時とは
よく言ったものだわ、と彼女は内心呟きながら自分以外の生徒の姿のない特別棟の階
段を上る。まるで一歩一歩異界へ近づいているような不気味な感覚を、無理に笑って
吹き飛ばす。
「……はぁ、学校の怪談を信じる小学生じゃあるまいし。この前といい最近ちょっと
神経質になりすぎてるのかなあ」
ぼやきながらも廊下を進む足は止めない。歩く彼女の横には空き教室の曇りガラスに
室内に乱雑に積まれたガラクタの影が映り、出来の悪いお化け屋敷の背景のような印
象を与えてくる。生徒や教師からも忘れ去られたような特別棟の薄気味悪さに、知ら
ず菫の歩みは早足となっていた。
やがて、達也がメールで指定して来た教室が見えてくる。廊下の行き止まりに作られ
たそこは今まで通り過ぎた教室と同じく、ここ最近の間に使われたような形跡はない。
本当にここに彼がいるのだろうか、という疑いもかすかに生まれてはいたが、ここま
で来た以上帰るにしてもせめて中を一目見て確かめてからにしようと思い、菫は勇気
を震わせて塗装の色あせた引き戸に手を掛けた。
「失礼します……。達也君、いるの?」
こわごわと教室の中を覗き込み、一歩踏み出す。室内の明かりはついておらず、夕日
が壁や床をオレンジ色に染めていた。倉庫特有のつんとした埃っぽい空気に、菫は思
わず顔をしかめる。

菫が求める姿はすぐに見つかった。部屋の中央、机やイスをどけて作られた空間に、
よく見知った少年がこちらに顔を向けて立っている。夕日を背にした逆行の中でも見
間違えるはずもない彼の姿を認めた菫の顔に、無意識に安堵の表情が浮かんだ。
「早かったね、待ってたよ」
にこにこと笑顔を浮かべ話しかける達也の姿にほっとした彼女は、中央に立つ彼に2、
3歩近寄りながら声を掛けた。
「それで、メールでは何か話したいってことだったけど。急にどうしたの?
それもわざわざこんなところに呼び出して。教室では出来ない話?」
わざわざ人気の少ないこんな場所まで呼び出され、気味の悪い思いまでした不満が見
知った人物に逢えた安堵からつい口をつく。だが当の彼氏は先ほどからなにがおかし
いのかずっと笑みを浮かべたまま、彼女の姿を見つめていた。
「……ちょっと? 達也君?」
その様子にいつもの彼と違った何かを直感的に感じ取った菫は、こわばった声を出し、
無意識に一歩後ずさった。それでもまだ、達也は笑みを浮かべたまま彼女から視線を
外そうとしない。いつもの彼とはどこか違うその態度に、菫は言いようのない違和感
と恐怖を感じる。
「ねえ、ちょっと何か言ってよ……。あんまりたちの悪いいたずらが過ぎると、
流石に私も怒るわよ……」
いつの間にか震えだした腕を押さえながら、出来る限り強い調子で言おうと口を開い
た菫から発せられたのは、しかし恐怖にかすれた小さな声だった。
その声を受けて、彼が菫の方に一歩踏み出す。思わず彼女は身をすくめ、一瞬目をつ
ぶった。
「ごめんごめん、怖がらせるつもりはなかったんだ。ただちょっと……あまりにも
「おいしそう」だったんでつい、ね」
「え……? 何言って……」
いまいち彼の言葉を上手く理解できなかった菫は、戸惑いも露に聞き返す。だが頭の
どこか別の部分は冷静に今彼女が置かれている状況を分析していた。
そしてさっきの言葉は、聞き間違いでなければ……彼は、私を「おいしそう」って言
ったのではなかったか? 何をバカな、人間が人間を美味しそうなどと思うはずがな
いじゃない。きっと何かのいたずらかドッキリなんだわ。
人間としての常識はそうさっきからひっきりなしに声を上げているものの、彼女の生
存本能、動物的な直感は先ほどからずっと警告音を鳴らしていた。目の前のモノは危
険だ、今すぐ逃げろと。
だが彼女の前に立つ人物がよく見知った、大好きな少年であったことが彼女の判断を
鈍らせた。そして全ては遅すぎた。戸惑い混乱する間に菫はもう敵の罠……狩場に完
全に踏み込んでしまっていた。そして目の前の相手には彼女を見逃す気などこれっぽ
っちも無かった。
近づいてくる達也の体から奇妙な気配が立ち上る。彼女はそれが以前に唯子との面談
のときに感じたものと同じであると気付いた。彼の笑みが深まるのに比例するように、
どんどんその気配は濃くなっていく。不意に菫は彼から感じる違和感の正体に気付い
た。その瞳だ、夕日を背に、影になっているはずなのにどこかぎらついて見える。
そのくせ、妙なことだが……全く光が無かった。
「ひっ……」
意図せず漏れたか細い悲鳴に、達也は困ったように頭を掻く。
「参ったな……。そんなにこわがらないで貰いたいんだけど。まあいいか、
どうせやることは一緒なんだしね」
その言葉と共に制服の上着を脱ぎ捨てた少年の姿が、しだいに変わっていく。
黒髪の間から、髪の毛とは違う真っ黒な毛に覆われた三角の耳が伸びだし、ピンと立
つ。同時にズボンの後ろ、尾てい骨のやや上あたりからは黒くふさふさした毛に覆わ
れた見事な尻尾が飛びだした。口元からは鋭く尖った牙が覗き、手の爪もまるで刃物
のように鋭く長く伸びる。両足がふくらみ上履きを破るとまるで獣のような形になっ
た。
て何をしていたのかと彼を問い詰めた。連絡しても全く電話がつながらないので、
何かあったんじゃないかと心配する彼女に対し、少年は心からすまなそうに、先生か
ら頼まれた用事でどうしても外せなかったと謝罪し、後で埋め合わせは必ずするから
許してくれと頭を下げた。
その様子には嘘をついている風もなかった。菫としても恋人とそんな些細なことでけ
んかをしたくなかったため、彼女はかすかに心に引っかかるものは感じたものの、こ
の件についてはそれでおしまいにすることにした。
「でも、今度からはちゃんと連絡入れてよね?」
「わかった、もう約束をすっぽかすようなことは二度としないよ」
最後にもう一度だけ念を押すと、そのまま二人は並んで学園への道を歩き始めた。
テーレッテー
放課後、帰り支度をしていると彼女の携帯電話が着信ありのメロディーを奏でた。
ポケットから小さな機械を探り当てると取り出し、二つ折りのそれを開いて画面を見
る。四角い液晶にはメール受信の旨と、送信者の名前が表示されていた。
「……あれ? 達也君からじゃない。珍しいわね。なんだろ、わざわざ……」
別に、彼氏である達也から彼女にメールが来ること自体はよくあることで不思議でも
なんでもない。しかし、彼とはクラスが同じであることから、それほど重要な用件で
ない限り大抵の場合は直接会って話してくるのが普通だ。メールを送ってくるにして
も意外と几帳面な彼は、題名にも中身が分かるようなことを書いてくるはずだった。
「今大丈夫?」とだけ書かれた簡潔な題名に疑問を浮かべながらも、菫はボタンを操
作し彼氏から送られてきたメールの本文をディスプレイに表示させる。
だが、それはますます彼女の混乱を深めるばかりだった。
『話したいことがある。学園特別棟3階、一番端の教室で待ってる』
メールはそれだけで終わっていた。いつもの彼らしくないそっけない一方的な呼び出
しに一抹の不安を感じる。思い返せば今日の彼は一日中、なんだかそわそわしていた
ような気がした。授業が終わった後も、わき目も振らず教室を飛び出していった姿を
彼女も目にしている。
「う〜ん、気になるけど……ここで考えていても仕方ないわよね。当人が呼び出して
きているんだし,会って直接聞いた方が早いわ」
彼女はそう自分を納得させると、勉強道具を詰め込んだ鞄を手に教室を後にした。
夕日が窓から射し込み、茜色に染まる廊下はどこか不安を掻き立てる。逢魔が時とは
よく言ったものだわ、と彼女は内心呟きながら自分以外の生徒の姿のない特別棟の階
段を上る。まるで一歩一歩異界へ近づいているような不気味な感覚を、無理に笑って
吹き飛ばす。
「……はぁ、学校の怪談を信じる小学生じゃあるまいし。この前といい最近ちょっと
神経質になりすぎてるのかなあ」
ぼやきながらも廊下を進む足は止めない。歩く彼女の横には空き教室の曇りガラスに
室内に乱雑に積まれたガラクタの影が映り、出来の悪いお化け屋敷の背景のような印
象を与えてくる。生徒や教師からも忘れ去られたような特別棟の薄気味悪さに、知ら
ず菫の歩みは早足となっていた。
やがて、達也がメールで指定して来た教室が見えてくる。廊下の行き止まりに作られ
たそこは今まで通り過ぎた教室と同じく、ここ最近の間に使われたような形跡はない。
本当にここに彼がいるのだろうか、という疑いもかすかに生まれてはいたが、ここま
で来た以上帰るにしてもせめて中を一目見て確かめてからにしようと思い、菫は勇気
を震わせて塗装の色あせた引き戸に手を掛けた。
「失礼します……。達也君、いるの?」
こわごわと教室の中を覗き込み、一歩踏み出す。室内の明かりはついておらず、夕日
が壁や床をオレンジ色に染めていた。倉庫特有のつんとした埃っぽい空気に、菫は思
わず顔をしかめる。
菫が求める姿はすぐに見つかった。部屋の中央、机やイスをどけて作られた空間に、
よく見知った少年がこちらに顔を向けて立っている。夕日を背にした逆行の中でも見
間違えるはずもない彼の姿を認めた菫の顔に、無意識に安堵の表情が浮かんだ。
「早かったね、待ってたよ」
にこにこと笑顔を浮かべ話しかける達也の姿にほっとした彼女は、中央に立つ彼に2、
3歩近寄りながら声を掛けた。
「それで、メールでは何か話したいってことだったけど。急にどうしたの?
それもわざわざこんなところに呼び出して。教室では出来ない話?」
わざわざ人気の少ないこんな場所まで呼び出され、気味の悪い思いまでした不満が見
知った人物に逢えた安堵からつい口をつく。だが当の彼氏は先ほどからなにがおかし
いのかずっと笑みを浮かべたまま、彼女の姿を見つめていた。
「……ちょっと? 達也君?」
その様子にいつもの彼と違った何かを直感的に感じ取った菫は、こわばった声を出し、
無意識に一歩後ずさった。それでもまだ、達也は笑みを浮かべたまま彼女から視線を
外そうとしない。いつもの彼とはどこか違うその態度に、菫は言いようのない違和感
と恐怖を感じる。
「ねえ、ちょっと何か言ってよ……。あんまりたちの悪いいたずらが過ぎると、
流石に私も怒るわよ……」
いつの間にか震えだした腕を押さえながら、出来る限り強い調子で言おうと口を開い
た菫から発せられたのは、しかし恐怖にかすれた小さな声だった。
その声を受けて、彼が菫の方に一歩踏み出す。思わず彼女は身をすくめ、一瞬目をつ
ぶった。
「ごめんごめん、怖がらせるつもりはなかったんだ。ただちょっと……あまりにも
「おいしそう」だったんでつい、ね」
「え……? 何言って……」
いまいち彼の言葉を上手く理解できなかった菫は、戸惑いも露に聞き返す。だが頭の
どこか別の部分は冷静に今彼女が置かれている状況を分析していた。
そしてさっきの言葉は、聞き間違いでなければ……彼は、私を「おいしそう」って言
ったのではなかったか? 何をバカな、人間が人間を美味しそうなどと思うはずがな
いじゃない。きっと何かのいたずらかドッキリなんだわ。
人間としての常識はそうさっきからひっきりなしに声を上げているものの、彼女の生
存本能、動物的な直感は先ほどからずっと警告音を鳴らしていた。目の前のモノは危
険だ、今すぐ逃げろと。
だが彼女の前に立つ人物がよく見知った、大好きな少年であったことが彼女の判断を
鈍らせた。そして全ては遅すぎた。戸惑い混乱する間に菫はもう敵の罠……狩場に完
全に踏み込んでしまっていた。そして目の前の相手には彼女を見逃す気などこれっぽ
っちも無かった。
近づいてくる達也の体から奇妙な気配が立ち上る。彼女はそれが以前に唯子との面談
のときに感じたものと同じであると気付いた。彼の笑みが深まるのに比例するように、
どんどんその気配は濃くなっていく。不意に菫は彼から感じる違和感の正体に気付い
た。その瞳だ、夕日を背に、影になっているはずなのにどこかぎらついて見える。
そのくせ、妙なことだが……全く光が無かった。
「ひっ……」
意図せず漏れたか細い悲鳴に、達也は困ったように頭を掻く。
「参ったな……。そんなにこわがらないで貰いたいんだけど。まあいいか、
どうせやることは一緒なんだしね」
その言葉と共に制服の上着を脱ぎ捨てた少年の姿が、しだいに変わっていく。
黒髪の間から、髪の毛とは違う真っ黒な毛に覆われた三角の耳が伸びだし、ピンと立
つ。同時にズボンの後ろ、尾てい骨のやや上あたりからは黒くふさふさした毛に覆わ
れた見事な尻尾が飛びだした。口元からは鋭く尖った牙が覗き、手の爪もまるで刃物
のように鋭く長く伸びる。両足がふくらみ上履きを破るとまるで獣のような形になっ
た。
【このカテゴリーの最新記事】