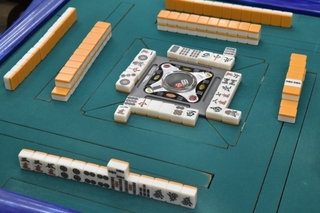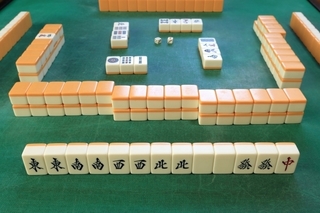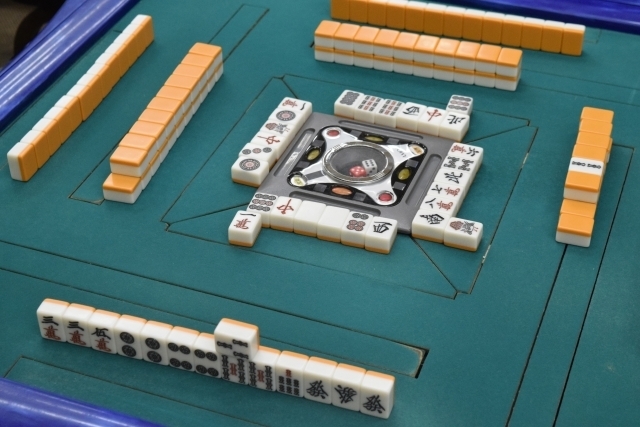2021年11月13日
色の意識

麻雀を打っていると「ここ何局、マンズ待ちだけ引けない」とか「ピンズターツだけ何局も埋まらない」といった経験がおありになるかと思います。
最初に言っておきますと、四人それぞれにその半荘内で得意な色、苦手な色が存在します。
得意な色は言い換えれば引きやすい色のことで、苦手な色は引きづらい色のことです。
この得意な色、苦手な色はずっと同じ色が苦手というわけでもなく、急に変わったりもします。
Aさんはピンズなら得意で引ける、マンズは苦手とか、Bさんはマンズが得意でピンズが苦手とか。
そんなAさんが苦手なマンズ待ちでリーチして、Bさんも得意なマンズ待ちでリーチするとどうなるでしょうか?
答えはおのずとおわかりの通り、得意なBさんの勝ちになります。
このケースでBさんが追っかけリーチをかけるとAさんが一発放銃したり、何度もBさんに放銃してしまうような現象が起こり得るわけです。
個人がそれぞれ得意な色、不得意な色を意識していれば、うっかり放銃や一発放銃する機会も減ってくるんじゃないでしょうか?
テンパイした人同士でじゃんけんをするようなイメージで見てみるといいかもしれません。
Aさんがグーを出し、Bさんがパーを出し、Cさんがチョキを出すと、誰が誰に勝てるか明白ですよね。
じゃんけんのような三すくみの関係になったりするのが麻雀における四家の関係です。
これがグーとグーなら引き分けで流局にもなるわけです。
ここで一つの疑問が湧いてくる方もいらっしゃることでしょう。
「三色のどの色も得意じゃない人も出てくるんじゃないの?」と。
そういう時は三色以外の牌が存在しますよね。
そう、そんな時は字牌が得意だということです。
あと、「そんな苦手な色がある時はどうすればいいの?」と考える方もいらっしゃるでしょう。
方法は2つあります。
1つ目は苦手な色を全部切っていく方法です。
一つの色の牌を全部切っていく「絶一門(ツェーイーメン)」は昔からある打法の一つです。
三色のうち一色を何度も切っていくと、残る二色のブロックが強くなっていきます。
これを利用して混一色や清一色を後で作るために、絶一門して他の色を引きやすくするように手組することもあります。
もう1つは苦手な色を鳴く方法です。
これはできるだけ他の色は鳴かず、苦手な色だけ鳴いて、その色を得意な方向へと持っていこうとするものです。
ただこの方法だと苦手が一局で解消されるわけではなく、何局もかかるため、南場からこれをしようとすると終了してしまうため、東場からこれをする必要があります。
この考え方は自分だけでなく他家に対しても使えるわけで、他家のアガリ時にもアガリ牌や待ち色、形をチェックしておくと、今後注意する相手やツキに乗っている人を判断する材料の一つにもなります。
今回のまとめ
・四人それぞれに得意な色、苦手な色が存在し、その関係によって勝ち負けが決まりやすい(それぞれが三色の色でじゃんけんをするイメージ)
・苦手な色がある時の対応策は2つある(1、苦手な色を全部切る 2、苦手な色を鳴く)
・苦手な色を鳴く時は何局もかかるため東場から仕掛ける
・得意・不得意は自分のアガリだけでなく相手のアガリ、アガリ牌の色や待ちの色、形などを見て今後注意する相手やツキに乗っている相手を判断する材料の一つになる
麻雀ランキング
【このカテゴリーの最新記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11091637
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック