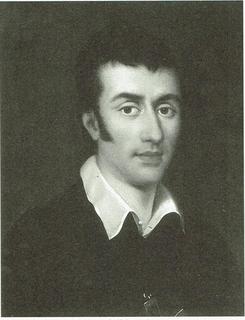第3部 司牧者
導入
激情的な生涯が終わりに近づくにつれて、ウジェーンの精神は柔らかさを見せ始める。やがてその妥協しない性格、一歩も譲らない性格は弱められて、新しい社会の現実に順応する開かれた心を見せる。しかしそれでもド・マズノ司教は、それまでと同じように思いがけない激しさを見せる時もある。特に「寝起き」が悪い。人々は日によって変わるド・マズノの極端な対照的な激しい性格を見て驚く。「母親的な優しい愛情」を持つ日もあれば、「ダイヤモンドの固さと冷たさ」を見せる日もある。初対面の時、魅力的な優しい目が輝く日もあれば、人を狼狽させ人の反感を買う日もある。いく人かは驚きと痛みを覚える。そして初めの印象を忘れられない。
ウジェーン・ド・マズノ司教は五十五歳になった。数か月後マルセイユ司教区の責任者になる。これから司教区民全体の司牧者になる。「この司教区民に対して子に対する父親の愛情を持たなければならない。一言でいえば、彼らのために全てを尽くし自分の暇や好みや休みや命さえ犠牲にしなければならない」とある日書いた。
その責任者になる前日、この新しい司牧者は何を考えていただろう。自分の霊的長所と短所を振り返って言った。「少年時代いろいろ私の信仰上のさまたげになったもの、それは心の散漫、性格の弱さ、世俗的な雑事、矛盾している生活、嫌悪感、人間に対する軽視である」。司教は人間として短所の多い自分の過去を振り返って次のように神に向かって願った。「主よ助けてください。あなたご自身で私を救いに来てください」
この謙虚さによって、司教は司牧者として司教区民の近づきやすく親しみやすい者になった。同じ視線で同じ立場から物事を見始め感じ始めた。心の振動は人々の心の振動と同じになり彼らをよく理解できた。
「彼らを通して私の救いがあり、彼らと共に救いを得なければならない」と。見事な決意だが果たせられるだろうか。
変えるべき事はたくさんあるがもう慌てることはなかった。これまで苦い経験をいっぱいしてきた彼は注意深くなっていた。「一気にすべてを変える訳ではない。厳しさも時には重要であるが常に温和さも伴うべきだ」。けれども「弱さ」はいけない。「司教は第一に導く役目があるのだと皆に分からせるべきだ」
ウジェーン・ド・マズノ司教の過去の行動から考えてみるならば、やはり厳しさを和らげることに努力しつつ、しっかりとした気骨を示して司教区や修道会を導くだろう。教会のために戦ってきた司教は根本的なものでは断固として譲らないだろう。
強さと寛大さ
新司教を理解するためには先ず状況を振り返って見た方が良いだろう。マルセイユ司教区に来た叔父フォルツネ・ド・マズノ司教は元気に活動していた。そして二人の代理、甥のウジェーンとタンピエ神父も同じように活動していた。妥協やあいまいな態度を退け、司教の権威を取り戻そうと努めていた。従って命令や掟や決定や規定、懲罰や宣告や賞罰、停止制裁や聖務制裁が多かった。ウジェーンは一日で六つの聖務制裁を下したことがある。
司教区のいわゆる聖職者はどんな人たちだったのか不思議に思う。あるいはその当時司牧的な方法を知らなかったのだろうか。
明確に言えることは司教区は頭を欠いていた。聖職者たちは長い間そういう頭がいなかったために少しずつ個人主義に陥っていた。しかも港のマルセイユは、世界のあらゆる革命的な地域から来た外国の多くの司祭の避難所になっていた。その中に非常に好き勝手に振る舞っていた司祭もいた。だから一つにまとめて正しくしていくことが必要だった。
一方、地元の司祭は真面目にやっていたが全体的な団結に欠けていた。何人かの熱狂的な司祭は浮かれ騒いで突飛なこともやらかしたりした。確かにそのなかには冗談みたいなこともあった。例えばある主任司祭は説教台で話す時にイエスの弟子たちがよく魚を釣った奇跡を描こうとして、古いマルセイユ港の桟橋で市場をやっているかのように魚の種類までも述べたてた。
当然こういう司祭団を寛大さを持ちながら強く正しい道へ導かねばならない。ウジェーンとフォルツネの両方の司教は状態を挽回するために熱心に努力はした。しかし常に良い方法を選んだだろうか。
今日司教になる元司教代理のウジェーン・ド・マズノは正直に反対し、そう思っていたであろう。とにかく司教代理として務めていく上で昔から常に非の打ちどころのない司祭が欲しかった。疑いもなく彼は「短気で激し易く厳しい面もあった」ことから司祭団の多くの司祭の目から見ると自分が嫌われ者であることを知っていた。でも常に司牧のやり方は断固としていて、規律に負けてしまうことなどは絶対になかった。全ての司祭を兄弟のように愛していた。しかも彼らの苦しみや試練は自分のものとして受け止めていた。
ウジェーンの夢は各々の小教区で主任司祭や助任司祭が一つの共同体を作り共同生活のうちにパンや心配を分かち合うということだった。これによって司祭としての活力を一致させ得るという今までにない光景のはずだった。しかしこの計画はフランス南部地方にあっては余りにも革命的だった。そしてこれは抗議の叫びを引き起こし広がっていった。それで司教はこの計画を司教区の司祭の養成によって熟させるために後回しにした。
司祭たちに対する配慮を示しているもう一つのものは1832年のマルタン神父宛の手紙である。司教館は率先してより良い道を選んだ。即ち司教区内の主任司祭や助任司祭に典礼上の謝礼金全部を平等に分配した。革命的なことであり、これによって豊かな教会も貧しい教会も収入に関しては平等になる。でもいつまでもいろいろな問題にぶつかる運命があるようだ。セマフォールという新聞は司教を叱った。ある人は、司教代理が年寄りの司祭よりも若い司祭の立場を取っていると訴えた。若い世代の側につけば皆を支配できるだろうと考えているように見えたのだ。不誠実なマルタン神父がその新聞の記事を書いていたのだった。しかし、彼はすぐに自省して、ウジェーン・ド・マズノ司教代理にそのことを謙虚に手紙で打ち明けた。
その時ウジェーンは急いで次のように書いた。「親愛なる友よ、あなたの手紙を受けて読んだが今一番したいことはあなたの処に飛んで行きあなたを安心させ、慰め、あなたに平和の接吻を与えることだ。・・・あなたの悔悛だけに注目している」。引用すべき寛大さのこもった手紙だ。マルセイユの司教館でも他の町の司教館と同じように当時聖務禁止や聖職停止がよく行われていたがそれも司牧的な方法によるものつまり愛の心を持ったものであった。
独裁制と優しさ
司教代理として務めながら修道会の総長もこなしていたド・マズノ司教は修道会という小さな群れをしっかりと指導していた。暗い日もあり、崩壊もあり、激しく落ち込むこともあったが父親のように全てを導いていた。修道会は二十一年の歴史があり、二百五名の修練者がいたが誓願を立てて入会したのはたった四十二名だ。施設は十棟で止まっている。そして創立者の大胆な見解や再三の働きかけにも関わらず修道会はまだ海外への宣教には行っていない。
もちろん人数は足りない。会員の質も欠けている。特に最初の頃はそうだ。つまり最初に入会した司祭たちは、ある程度全てにおいて特に小教区の活動において、自分独自の考えを持っている。ほとんど準備なしで入ってきているので修道生活の厳しい面に嫌々ながらぶつかり、要求される細かい規律を守ることは難しい。頭に付いて行けない。同じリズムで歩めない会士たちの多くは疲れ果てた。
しかし何人かは成功した。創立者が大好きだったスザンヌ神父、コルシカの使徒であり奇跡を行うアルビニ神父、交渉上手だったギベール神父がその例である。一方、自分では気がつかないながら頭としての目的を果たすために着々と準備に励む将来の海外宣教師たちはその種である。疲れ果てた者も、熱心な者も、やっと歩み始めた者も皆、師の厳しさと優しさを味わったに違いないのだ。その中でスザンヌ神父は特別に大いに味わったと言える。
ウジェーン・ド・マズノ司教が可愛がっているこの神父は比較的若い時に入会した。先入観のない柔らかい素材で修道生活の養成には従順に従った。当然ながら創立者は、オブレート会士の理想を示しているこの会士に対して、とても誇りを持っていた。
ド・マズノ司教は二十七歳になったばかりの彼をマルセイユの修道院の院長に任命した。同時にノートルダム・ド・ボン・セクール教会を建築することや、司祭になるために勉強中の6〜7名の若い神学生を指導するという責任を彼に与えた。驚くべき努力によって建築は終わり、町のあらゆる処から多くの信徒が集まった。底抜けに陽気で熱心な若い院長の魅力によってである。
ある日の事、オブレート会の創立者は突然スザンヌ神父と他の会士を集めて、皆の前で厳しい言葉で若い院長を非難しその任を解いた。
修道院の中の修道生活として望まれる修行よりも外の聖務に励み過ぎたからだ。自分で制御することのできない情熱的な熱意の「被害者」であり、そして指導すべきだった神学生の修道上の熱心さの「被害者」である。神学生たちは創立者にこの院長の暴走と規則正しくない状態を嘆き悲しみながら訴えていた。
院長の解任と軌道修正というこの例を見た若い神学生たちは更に熱心になり修道生活のリズムを取り戻した。
それから間もなくスザンヌ神父は説教者として働き、過労から血を吐き始めたのである。
創立者は強い衝撃を受けた。この若い神父に対して大きな期待を持っていたのだ。昼でも夜でも仕事から解放された時には必ず彼のベッドの傍で過ごした。創立者は次のように書いた。「今感じている内面的な激しい苦痛を耐えるためには鉄の体が必要だ」。この特別な若者を主に委ねるために彼には信じられないほどの自制心が必要だった。「もし今、私の心の中の苦悶を外に出して見せたら人々は皆私のことを気が狂ったと思うだろう」
三十歳の若さでスザンヌ神父は死に瀕し、そしてついに亡くなった。
三週間経っても創立者はまだ疲れ果てた状態にいて自分の務めに集中することはできなかった。「わが子同然のこの神父の臨終の顔はいつでも私の目の前にある」と言って嘆く日が続いた。
これらの過去を今、一通り振り返って見たのでド・マズノ司教がマルセイユの司教として出発するに当たってどんな精神状態であったかを理解できるのではないだろうか。
これから三つの点で司牧者としての創立者を見る事にしよう。
羊飼いとその羊の群れ
「わたしの羊はわたしをしっている・・・」
そう、それはその通りだ。しかし口の悪い羊飼いは、その日の気分によって窓から首だけ出して、
「誰?」と言うこともある。
「司教様、私です」
「私がここにいることをあなたに教えたのは誰だ?司教になっても休息を取ることはできないということだ
ろうか?」
「司教様、すみません、帰ります」
「いやいや、もうここまで来ているんじゃないか、玄関で待ってくれ」
今日、司教の邪魔をする人、訪ねてきた迷惑な客は悩みごとを一杯抱えた人だ。誰か友だちを求めて来ている。間違った門を叩いたのだろうか。いや、そうではない。司教館の塀の後ろに住んでいる司教はこの町中で最も慈悲深い心の持ち主だとこの物乞いは知っている。
「いらっしゃいませ」とあらゆる門とあらゆる塀をはじき飛ばすような声で司教は叫ぶ。
シャルル・オグストゥ・ティモン・ダヴィッド神父は部屋に入った。司教に話したいことは山ほどあるのだが吃りながら話すことしかできない。彼は今、若き労働者との活動を重荷として感じている。とてもやっていけないと思い悩み、うつ病になるほど落ち込んでいるので司教の力を借りたい、司教の力強い言葉、活気を与える言葉を聞きたいと思ってやって来たのだった。
ティモン・ダヴィッド神父がぽつぽつと話し始めるにつれて、司教の心は開き、声は静かになり、不機嫌は消えはじめる。「親愛なる子よ、こういうような悩みがある時になぜ私の方に相談に来てくれないのか?あなたの父ではないか?」と司教の言葉は暖かい。
後になって、ティモン・ダヴィドは言う。「話してくれた後、私を抱き、司教の涙が私のほおに伝わって落ちるのを感じた。こういう魅力を発揮する人には会ったことがない」と。
思い掛けない時にこうしてやって来る客に対しても示される羊飼いの姿である。友人は勿論、敵たる人でも司教の心を疑う人はいない。
マルセイユの司教館。誰でも近付くことができる所だ。港湾労働者でも、弁護士でも同じように歓迎される。肩書は関係ない、前もっての約束も要らない。
ド・マズノ司教は普段、朝十時から午後二時までを客を迎える時間としていた。司教館の門を通って入るともう客は自分の家に居るのと同じだ。先ずその敷居を越さなければならないが、そこには番犬のように口うるさい門番がいる。しかし実はこの人も優雅な人だ。質素な部屋に迎え入れられ、気紛れな召使によって整頓の行き届いた待合室で順番を待つ。時々司教は部屋の整理を怠けた召使を凄く叱りつけていた。召使は忍耐を持ってその叱責を受けたが、それでもこりることなくそれ以後も再び司教の優しさを裏切る機会を持っていた。
当時、請願する人々は次々とやってきた。世界の交差点であるマルセイユでは、請願に来る人はあまりにも多いのだ。時折は人々を選別しなければならない。そうしなければ多くの詐欺師にだまされてしまうこともあり得る。時々司教はそんな詐欺師を探し出した。
ある紳士は、服装もよく、とても礼儀正しく、しかも自分の叔父も司教だと言ってその司教の名前を持ち出す。久しぶりに会いたいと言うのだが、しかしその旅の費用は持っていない。
ド・マズノ司教は微笑みながら、「それは簡単だ。叔父さんは今マルセイユに来ているので連絡します。」
と言った。
そのとたん直ちにその親戚云々の話はないことになり、紳士は逃げてしまう。
応対の時に司教はとても素朴で単純な態度で接し、客の方にも同じような振る舞いを求めていた。けれど厚かましい態度だけは決して許さなかった。
ある日、「お客さま、どうしても座りたいならばこちらの椅子を使いなさい!」と命令的な声で言った。相手はセールスマンとしてやって来ただけで招待されていなかったのにひじ掛け椅子に深々と座り込んでいた!
そして多弁を弄していたが、司教の命令にはもちろんすぐに従って立ち上がった。
でも司教は本当に不幸な事柄に対しては深い配慮をもって努力に努力を重ねた。憤慨させられることもなく、うんざりさせられることもなく、疲れさせられることもなかった。役に立つなら何でもしようと努力した。
疲れる仕事である!司教はある日、日記に書いた。「人に金銭を渡すのは簡単だ。しかし悲惨な人々に直面し、あらゆることを成し遂げても彼らの必要を満たすことは不可能であると気付くと疲れる。私の力は追いつかない・・・。これ以上何もできない・・・。こういう場面を経験した後で食卓についてみなさい。食べることができるだろうか。できないだろう!」
でもこういう長い間を過ごしてからもし司教が豊富な食卓の前に座ったのであれば食欲は復活したかもしれないが、しかし司教館の献立はあまりにも粗食であった。頑健な体格に恵まれてはいたが、司教は「スープとパンに八つ当たりにする」と言っていた。例外的に、お客が通り過ぎていってしまった時だけ自分の食欲を満たすことができた。夕食はいつでも惨めな食事だったが、特に、四旬節と毎週の金曜日には何もなかった。そういう日に司教は、度々書斎を離れなかった。召使はお盆に載せたコップ一杯の水とパンの一切れを運んでくるだけだ。「神は私に丈夫な体と健康を下さったのだから、私は私に任された司教区民のために苦行を行わなければならない」と厚かましく訪ねてくる人たちに答えていた。
夜になると、自分の書斎を整理するために司教は寝室に戻る。そして寝る前に必ず日記帳を開いた。ある時こう書いた。「毎日の面会は私の時間を全部取ってしまう。しかしとても大切で必要なものだ。司教の義務の一つは司教区民の一人ひとりが司教の側に行きやすくすることだ。私の慰めは、誰でもが私の応対に満足して帰ることだ」
羊飼いは、もう休まなくてはならない。薄い水色の古い壁紙をはった本当に質素な寝室でマルセイユの司教は藁布団に横になる。
私の羊を知っている
歓迎する面ではこの羊飼いは他の人に秀でていることは確かだが、特に司牧的な訪問を行う時、その対象となる人たちに近付き、溶け込むことについては他の司教たちよりもとても勝っていた。すぐに雰囲気は盛り上がり、話しはじめた瞬間から皆の注意を引き付けた。ある時、典礼を終えて行列している時に、ちょっとしたうわさ話が耳に入った。それはある人が司教は聖アンブロジオみたいな大雄弁家だと友人に言っていた言葉だ。司教は、微笑むだけで、部屋に戻ってから日記に書いた。「聖アンブロジオ!とんでもない。私は惨めな罪人だ。神は罪人である私に司牧的な義務を果たすための感覚、聖務の貴さに対する感覚を下さっただけだ」。司教は、こういうような司牧的な儀式を「常に新しい慰めとして」行ったのだ。そして「そういう儀式は単調なものどころか、余りにも短い時間で済んでしまう」と思っていた。
聴衆の方から見るとどうだろう。彼らは儀式が短い時間で終わったと言って悔やんでいただろうか。
司教は決して一時間以内に終わるような説教をしなかった。「課題によって必要な熱情を示していた」と彼らは言う。田舎のプロヴァンスでは必ずその地方の方言を使っていた。説教師や主任司祭たちが精密に時間を測定し、十分以上喋ったら皆から文句を受けるのでめったにそれを超さないように気を使っている現代、もしマルセイユの司教が現代の人々に説教したならば、恐らく次々と教会はからっぽになるだろう。恐らくと言っているが、そうでもないかも知れない。何故なら、「月並みなことを喋り散らし説教するのではなく、そして言葉は完璧であっても聴衆に分かりにくい説教ではなく」、ウィットに富んだ即興的な話をし、その時その時に精彩のある華麗な描写、ぴったり合う言葉の使い方、常に分かりやすい話し方、常に完全に環境に適合した話し方だったからである。したがって、ある日一人は指摘した、「子供でも頭を動かすことなくジッと聞いていた」。司教はそれに気付いて「聴衆の目は、私の方に注がれていた、聴衆の耳は注意深かった」と語った。
でもこういうことも毎度というわけにはいかない。どんな優れた雄弁者でも凡庸な時もある。しかしここでド・マズノ司教が自分自身を奨励している次の言葉を聞こう。「私が言える唯一の言葉は、私のやり方はきっと良いのだろう。何故なら、大人も子供も、何時でも何処でも、常に注意深く私の声を聞くからだ。・・・恐らく彼らの必要に答えていなければ、こういう結果はないだろう」
司教は、自分の言葉によって急に目覚め堅信の秘跡を受けたいと申し出る若者に、どんなふさわしい糧を与えていただろうか。雄弁者自身が言う。「若者たちは、私が教え込んだ真理をよく覚えていたようだ。その真理は、堅信の秘跡の際、私が、彼らの額に聖油を以て十字架のしるしをきった時に、一人ひとりが大きな奇跡の主体にも対象にもなるのだ」。彼らに次のことも告げた。「堅信の秘跡を授ける時に、私は毎朝のミサを捧げる時と同じ注意深さで行い、ミサと同じように尊重している」と。司教の信仰は深かったので自分自身について次のように書いた。「私は、奇跡を行う人と同じような者だ。子供に堅信の秘跡を授ける度に、神の聖なる力によって多くの奇跡を行っている」。この思想はとても強かったので、どんな長い儀式でも、絶えず自分自身の「注意」と「熱意」を呼び起こし、その儀式は常にうっとりするようなものであった。
堅信の秘跡の儀式が終わった後は、司教は喜んで信者たちと交わっていた。イコジアの名誉司教としてではあるが、プロヴァンスでは有名な親しみ深さや、くったくのない純真な付き合いに慣れてきた。このような機会について、自分自身も驚いていたが、マルセイユの東にある造船と鋳造の街ラシオタで人々と関わっている時のことを次のように書いた。「昼の食事の後に、いつものようにとても退屈で、町中顔を出したかった。何処を通っても敬意の念しか受けなかった。桟橋の方へ行っても、暇人と軽薄な男ばかり集まっている喫茶店の前を通っても、誰もが挨拶してくれた。何人かと会話を交わした。多くの人々は私の後ろに付いてきた。何人かの話が漏れ聞こえてきたがそれは『高慢な人だと聞いていたが、こうやってみるととても優しい人だね』という声だった」
このように、自分の性格をよく知っていた司教には反省の機会となった。「高慢な」人は「優しい」人に変身した。しかしラシオタの人々たちは自分たちの問題を司教に打ち開けなかった。産業化の時代だったので、労働者の働く環境はよくなかったが、当時彼らが直面しているそういう問題を教会の者に話しても分かりっこないだろうと彼らは思ったからである。
編成された羊小屋
もちろん、司教がラシオタの労働者を脅かしていた新しい産業の危機を全部把握することは不可能だった。しかしある程度のものは掴んでいた。それらを深刻なものとして感じていたので、夜司教館に戻った時にがっくり肩を落としていることも多かった。
司教は、産業上急速に発展していたその地方の地図やマルセイユの市街図を度々眺めた。こちらには教会の数が多すぎる、あちらには教会がない。しかしながら産業の発達によってあちらの方で人口が増えている。他の所では小教区の区域はめちゃくちゃである。いずれの所でも巨大な使徒的仕事が待っていた。
かつてフォルツネ司教の総代理として、緊密な協力で、苦労して製作した司牧的な施設の企画を実行し始めた。しかし、フォルツネが辞職してから、特に1840年2月に死亡してからは、いたずらっぽく光る目の老人、常に苦痛・貧困に対して心を開いていた賢い老人の助言はもうなかった。フォルツネは九十一才で死亡したが甥のウジェーンに奇妙な遺産を残した。つまり、四百人の貧しい人々であり、そして彼らに食べ物をとらせるためのたった八十五フランである。そのフラン一個一個は綺麗に小さな紙に包んであり、幸運にもそれを受けることになった人たちの名前付きなのだった!こうして完全に見事なほどの赤貧な状態でド・マズノ家の一人の司教、しかも紳士は亡くなったのだった。
司牧的な企画を実行に移すために、ウジェーン・ド・マズノ司教は非常な能力を発揮してこれに一生を賭けた。実体を掴むためには非常に想像力が必要だった。

マルセイユ司教座聖堂(カテドラル)
司教区では新しく二十二の小教区を設立した。多くの教会の建物を新しく建てるか、あるいは増築し、または修復した。特に指摘したいのは二つの施設である。バジリカのノートルダム・ド・ラ・ガルドと司教座のカテドラルである。実はこの二つの施設の完成は司教の死後だが両方とも彼の絶え間ない努力の実りである。
特にカテドラルは司教の大きな計画の一つだった。しかしながら、この建設に当たって賛成を得るまでの過程は大変だった。人々の無気力を払い除け、反対を突き飛ばし、敵愾心を打破することによって司教は打ち勝った。時節によって、そして様々な政治的な大混乱によって、カテドラルのことで選挙がひっくり返る時もあった。選挙の時にカテドラルに賛成しているか反対しているかだった。運を天に任せて、司教は会う誰にでも自分の計画について会話に引き込んだ。王にも、王子たちにも、大臣にも、マルセイユの議員にも、フランスの大貴族にも、知事にも、市長とその評議会にも、小教区の主任司祭にも話していた。皆が分かるように、マルセイユにはカテドラルが必要だと説いた!パリでさえそれは課題になっていた。プロヴァンス出身の国会議員にルイ・フィリップ王は尋ねた。「マルセイユの司教に会いましたか。カテドラルについてお話したに違いない」と。

マルセイユのノートルダム・ド・ラ・ガルド教会(バジリカ)
マルセイユの一番高い丘にあって宣教師たちが船で遠ざかっていっても最後まで見えるのはこのマリア像
不幸にも最終的に決まった場所は司教は気に入ってない。彼は街のもっと中央に建てたかったのである。
司教区を再建するためには、もちろん小教区の設立だけでは足りない。教会の建設は良いことだがそれに必要なのは修道院の祈りの声、説教師の活気ある話、要理の明解さ、芸術作品を作成する勇気のある人、司教区内、小教区の信仰生活に関わる人の使徒的な熱意だ。
今までにない勢い、それはまぎれもなく使徒たちの侵略のような勢いであり、疾駆する軍隊のような勢いだった。新しく七つの男子修道会がマルセイユに設立された。イエズス会、カプチン・フランシスコ修道会などができた。そして新しく二十四の女子修道会も現れた。他の所から来たのもあり、その時点で創設されたものもあった。それらの修道会は様々で、教育に携わるものもあれば、慈善のためのあらゆる施設もあった。
全ての集団の塊は司教自身だった。積極的すぎる人を制御し、機能しない人がいればその人を奨励することによって確実に皆を引っ張って前進していた。あらゆる事業を激励し、あらゆる熱意から生じる意思を考慮していた。何故なら、世事に対して商売人が現実主義者であると同じように、司教は宣伝活動においても現実主義者であった。
修道会を創設するという恐るべき召命を感じて司教の助言を懇願するために訪れた人たちには、司教は、取り乱さないで、困った顔を見せないで、興奮しないで、その人をバカにしないで、かえって今生じようとするその出来事の中で神の霊の息吹を獲得しようとした。司教自身が自分の修道会を始めようとした時に、嘲笑や反対や敵意を受けて傷つけられたので、自分の保護を求める人の立場をよく理解していた。しかしながら、たまには、新しい営みの不安定な状況を感じることもあった。その時、「かまわない!自分の力を試してみるのは悪いことではない。そして創設したものは何世紀も残らなくても良い。たった一人だけの救いのためになるものであっても助けなければならない」と言った。
ある時、自分の修道会に入会していた一人、ダッシ神父は同じような危険を招く営みを始めようとした。司教は、彼を導きそして若き盲目の人の教育に携わる汚れなきマリアの女子修道会を祝福した。後に、その修道会は開花した。
しかし一番大事な仕事、マルセイユ司教区の司牧的な設備の「骨組み」は、司祭たちの養成だった。マルセイユとい言う街は大きな港街だった。そこでは一人ひとりの商売人は残忍なほどの気持ちで自分の財産を広げようと戦っていたので、金もうけばかりの社会になっていた。そういう社会に対抗するには、自分の命を捨てても良いという覚悟の司祭が必要だった。商売や生活にただ熱狂しているこの街の福音化、そして都市の生活の慌ただしい麻痺状態の影響を受けていた周辺の田舎の福音化は、司祭の聖務の課題だった。
そのために司教はその司教区の聖職者を激しく振るい動かした。年寄りの司祭にも若き司祭にも今までのリズムを変えさせた。同時に、いつも休むことなく小神学生や大神学生の養成に目を注いだ。
一人ひとりの神学生は、神学校に入る時から司祭のなるまでずっと司教の手元、目の届くところで養成を受けていた。そして司教は、自らその神学生に叙階の秘跡を授ける権利を保留した。自らの司祭になって、その新司祭の親、その新司祭の兄弟になっていた。「主イエスの言葉を借りると叙階式毎に、大きな力が私から出る」と司教は説明した。そして自らの叙階の秘跡を授けた司祭が死亡した時には、精神的な痛みと悲しみは大きく「血縁の繋がりを持っているような気がする」と語った。
責任を引き受けていた司祭に対しては殆ど絶え間なく働かせた。勉学するように励まし、今までの説教のやり方をひっくり返し、これまでに溜まっている不適切な説教の原稿は風に投げ付けて吹き飛ばしてしまえば良いとさえ思っていた。「信者の信仰と道徳に関わる殆どのふしだらな生活の大きな原因は、間違いなく私たちが彼らに十分な正しい育成を与えていないからだ」と堂々司祭たちに向かって言っていた。
司教は何度も要求を繰り返し、説教師である司祭たちのだらしなさを手厳しく指摘した。「告白して自ら認めよう!私たち司祭にはそれをするのが必要だ!信者たちは、わけのわからない日曜日の説教を聞いていやになっている・・・。何人かの説教師は・・・説教台で、信者である会衆に向かって彼らをおもちゃみたいに扱う。どうせ聴衆は物わかりが悪いのだから、自分の説教を理解できないだろうと判断する。しかしながら、聴衆は、説教師が自らの直面している問題を理解していないことをよく分かっている。他の司祭は、説教台に上る前に、はっきり恥さえも感じないで説教の準備をしていないと平気で言う・・・。信者たちは退屈で、こういう説教師を耐え忍ぶことに耐えられずに教会から離れていくのだということを聞いて驚く人がいるだろうか」
司牧者ド・マズノ司教からのこの侮辱は飲みがたいものかも知れないが司教にはそういう侮辱を口にする資格があった。そしてその侮辱以外に次のような言葉がつけ加えられてもおかしくない。「私の説教を聞いて下さい。聞いてみれば説教のやり方を覚えるだろう」
現実主義者である司教は、興味のないもの、内容のないもの、効果のない討論に陥るものを自分たちの説教から追放するように司祭たちに懇願していた。どうしても必要なもの、それは信仰宣言の内容の一つひとつ、ミサの典礼、旧約聖書と新約聖書だけを信者たちに説明したら良い。しかもその説明は分かりやすいように言葉の使い方に気をつけなければならない。
少しの間、説教の課題はそのままにしておいて、ド・マズノ司教は、もう少し冷静に、しかし同じ厳しい堅固な意志を見せて、毎年、司祭たちに、主任司祭と助任司祭の共同生活の必要性について語り、一定の方法に従ってそういう同居を導入した。
司教総代理の時代に、もうすでにこの企画をし始めていた。司牧者になった今、それを実行に移そうと堅く決心していた。何故なら、彼の目から見ると、多くの場合、単独で住む司祭が、色々な危機に陥るのは共同体の支えがないからだ。共同生活は、そういう危機を乗り越える支え、その危機を乗り越える支え、その危機を防ぐ方法になるだろうと思った。司祭たちの反応は、歯ぎしり、叫び、雷雨、嵐である。司教に一番反対していたのは、時には一番真面目で最も良い司祭だった。
司教は一歩も後ろに下がれない。しかし、忍耐を持って、荒っぽい行動や言葉で対抗することはしないで身体的、精神的な困難が消え失せるのを待った。もちろんそういう困難が、新しい共同体が生まれてから生じるならば、絶対に妥協はしなかった。
歴史を見ても、有名な司牧者の特徴は、彼らは常に無関心よりも、あるいは熱情、あるいは反感や憎悪を生み出す源となっている。ド・マズノ司教もその原則から遠くはない。あらゆる時に、司祭たちの中に頑固な反対者もいれば熱狂的で忠実な者もいた。そして、困難ではあったが、強情な者もそして熱狂者もともに心は通じ合って死んでいたような司教区を蘇らせたのである。そして同時に今日に至るまで残っているような安定した活動の本拠を設立した。
各々の司祭は、全員一致、同じ波に乗って、ある者はとても喜んで働き、ある者はぶつぶつ不平を言いながらも働いた。司教は司牧的な義務から生じる目標を決して失わないで最後まで成し遂げた。
妥協しない羊飼い
義務をよく自覚している羊飼い、つまり「内側」では群れを導き、その群れのために「外側」と戦う羊飼いである。
マルセイユ司教区内部でのド・マズノ司教の活躍は有名であった。対外的には、その時代の宗教史の上で圧倒的な支配者というわけではないが、司教の「闘士」としての権威と偉大さはやはり顕著である。マルセイユ座には、利点と弱点が同時に存在する。利点としては、地中海に沿っているということだ。その時代は永遠の都ローマへ行くには船しかない。巡礼者としてローマへ往復する人たちはマルセイユ港を出入りする。こういう多くの旅行者、とりわけ聖職者ならば、彼らを通してローマ聖座との密接な関係や繋がりを持つ司教は、素早く聖座と相談し導きを受けることができる。弱点としては、パリから遠いことだ。「フランスの端にある私のへんぴな場所からは、物事を遠くから見ることになるので、恐らくはっきりと正確に見ることは出来ないだろうと思う」とパリの大司教宛の手紙で言う。他の仲間には次のように呟いた。「パリの都の近くにいる司教たちは、宗教に反対している人々の動きを知りそして理解できるのに、私たちに何が起こっているかを伝えてくれないとはどう言うことだ。全く理解できない」
このようにマルセイユには利点も弱点もあったが、マルセイユの司教は常に全てに耳を傾けてちょっとした警報に対しても、戦う姿勢を持った。その時の司教の声は、敵対者のためには恐ろしいもの、仲間のためには安堵させるようなもので、ミストラルのように突然沸き起こり、吹きわたった。その攻撃は、常に率直で、激しく挑発的であった。大臣であっても、王もしくは皇帝であっても、バカにされたくないならば、その挑戦に応じなければならない。
早くも政府はマルセイユの司教をひどく恐れていて、逆らわないようにしていた。でも司教はそれを正統派の支援と受け取ってはいない。司教は、政治的な問題に関しては関わらないようにしていた。しかしながら、教会や教皇の聖なる権利に対してちょっとでもそれを侵害するような事態が生じた場合には絶対にそれを黙認しなかった。
数年後、フランス司教団の方から相談を受け、同時に司教団の中で何かにつけて一番話題にのぼった司教の一人になった。
他の司教たちは必ずド・マズノ司教の意見に従うと言うわけではないのだが、どうしても彼の意見を知りたくて常に彼に尋ねていた。ド・マズノ司教の教書は、いつも問題の今日的な意義を強調していた。そういう教書はマルセイユ司教区のために書かれたものだが、必ずそれらの影響は司教区外にまで及んだ。しかも時としてフランス全体にまで広がっていた。最も進んでいるカトリック信徒の多い地方では興味をもって周期的に発行されるマルセイユの司教の新しい教書を待っていた。発行者たちや新聞記者はその教書の出版を待ちかねていた。そして、司教の小冊子や記事は多くの人に手渡された。
突然の攻撃と言う点で、その早さではド・マズノ司教はめったに他の司教に負けていない。他の司教が彼よりも早く攻撃に出る時もあったが、そういう時は直ちにその司教の支援に出た。
その勇敢さを褒められた時には、その機会を使ってすぐ相手のことも褒め返した。あるとき、ラングルの司教は次のように言った。「意見がよく通る司教で、とても権力のある司教の一人だ」。ド・マズノ司教は上手に答えた。「褒めていただいてありがとう。しかしお願いがある。敵対する人がある限りあなたも筆を取って戦いなさい」。それで相手の司教を励ますと共に自分と同じようにできると主張し、相手の認識を高めた。
1837年に司教になってから、1861年に死亡するまでド・マズノ司教は教会に関する殆どの事件に関わっていた。多くの場合がその事件に完全に巻き込まれていたと言える。
教育の自由を主張する擁護者
その時代に熱烈な論戦を招いた大きな問題は、中等教育の自由という問題だった。フランスのカトリック信者はその自由のために戦っていたし、マルセイユの司教はそれに大いに参加した。その論争は、1841年に始まりファルー法によって解決されたのは1850年だった。ナポレオン皇帝はカトリック信者からその権利を奪っていた。そしてこのことはフランスのブルボン家による王政復古時代まで続いた。ルイ・フィリップの政権は、宗教新聞の攻撃と国民の意見を受けて次々と二つの法律的な企画を練り上げた。そういう法律はある程度理解のあるものだったが、最終的には虫喰いだらけの法律だった。何故かと言うと国立大学がその専制的な独占性をそのまま維持したからだ。
ド・マズノ司教は、その侮辱について訴えた最初の司教の一人だった。大法官宛の手紙の中で激烈に訴えた。当時の宗教新聞の二つ、アミ・ド・ラ・レリジオン(宗教の友)とウニヴェール(宇宙)にもその主張を伝えた。
殆どの司教たちも同じように訴えることにした。しかし何人かは、事件の深刻さを恐れて、妥協するよう薦めた。最後まで戦うと全てを失ってしまうかも知れないからである。派手で挑発的な新聞などに意見を述べるのには反対していた。政府の怒りを恐れたのである。司教の主張をあまり表ざたにしないで、この問題についての独立した所見をコツコツと直接当局に届け出るべきだと思った。
マルセイユの司教の体には、ド・マズノ家の血が流れているので爆発しやすいものを持っている。一先ず大臣たちを置いておいて妥協しようとする司教たちを是が非でも攻めた。妥協は不可能だと主張した。「大声で叫び、教会に対する正義が行われ得るまで叫び続けるのだ。」「今さらごちゃごちゃとした議論は要らない。」「全てを明確に公にせよ。」「全司教団が団結して大声で叫べば当局は耳を傾け、最終決定を下すだろう。以前と比べて新聞は、我々の主張に耳を傾けさせる現代の唯一の手段である」と断言した。こういう非難は、政府に頭を下げて嘆願の形でするものではない。「司教と言うものは王権に対して卑屈に訴えをするような下位のものではない。司教とはあらゆるものに対して教会の権利や徳性の擁護者であり管理人である」と堂々言い切った。
全てを尽くしたが、ド・マズノ司教は、司教団を完全に団結させることは出来なかった。とても落胆し、そして困惑した。彼が思っていたのは皆が本当に完全な団結をして初めて、一つの声で戦えるということだった。司教職を勤めた長い期間の間、そして最も激しい戦いの時、それぞれの努力の調整に絶え間なく励んだ。何故なら意義のある立派な戦いではあっても、なかなか一致団結した抵抗とはならず、また広く影響を与えるような力にもなり難かったからである。
政府は、国立大学の独占についての司教の絶え間ない攻撃に対してやはり怒ってしまった。そのために大学を経営していたイエズス会を追放しようと脅かした。政府の抜け目のないやり方だ。カトリック信者たちは教育の自由のために熱烈に戦ってきたが、これによって世論は一歩退いて戦いを止めるだろうと思われた。しかし実際は、皆は政府の作戦を見抜いていた。フランスの国立大学と競争できるのは、イエズス会の大学しかないと誰でもが分かっていた。政府は、どうしてもこの力のある競争相手を退けようとしている。直ちに、マルセイユの司教は、仲裁をした。自分の司教区に招いていたイエズス会を保護しなければならないと思った。次のように大法官に手紙で伝えた。「私はイエズス会をこの司教区に招待した。その会の会士は私から宣教使命を受け、そしてその聖務を果たすための能力を私から受けている。彼らは私の司教区で聖務を果たしていることを誇りとし、そしてとても満足している・・・」と。
政府の虚勢は、効果がなかった。しかし司教は前よりも用心していた。その時、王は、残念な行動をしてしまった。議会の両院への開会式の演説の中で「教育に関して政府の行動と権威の必要性」を強く主張し過ぎたのだ。直ちに反応があった。事実、殆どの司教は途方にくれて新しい作戦を求めてマルセイユの司教に相談した。ド・マズノ司教は、依然として司教団の団結や「法律の企画の攻撃と破壊」や「本当の宗教的な運動」や「評議会の成員として行為する王に直接の誓願」の必要性を主張した。同時に、有名になったメモを作成し、ルイ・フィリップ王に送った。パリの政府当局は、そのニュースに激しく興奮した! 閣僚の新聞、特にジュルナル・デ・デバ(論議の新聞)は、ド・マズノ司教を強く攻めた。それに対してあらゆるカトリック新聞は直ちに答えた。ウニヴェールと言う新聞は先頭に立った。その間、司教が書いた長いメモは小冊子になって何千冊もが多くの人に配られた。
あらゆる地方からマルセイユの司教座に祝賀の手紙が寄せられた。ド・マズノ司教は教育の自由の擁護者として認められた。何故かというと勇気を持って王に次のことを伝えたからである。「教育の自由は、宗教の急を要する権利であると共に国民としての権利である」と。大成功したからと言ってそれに陶酔していないで、司教は、更に攻撃に移る姿勢を保った。ローマでは妥協案も出てきた。司教は、直ちに、ローマ教皇庁尚書局の書記に手紙を書いた。注意を与えて、フランス政府の本当の狙いを解明した。政府は絶対に教育の自由を欲してはいないのだ。いつものように、ド・マズノ司教は尚書局の書記に切り込むような口調で書いた。「良いと思われる人の言い分に対しても注意して自衛しなければならない・・・。彼らはいわゆる「平和」の仲介者になり、自覚しないままに偽りの約束の使者であると主張しているが、これまでの15年間の経験から見るとその偽善を見抜くことができる。もう彼らの言い分を信用できない。」そして司教は続ける。「もし聖座が、彼らの約束によって騙されて、フランス政府といかなる事柄においても妥協してしまうなら、フランスのカトリック信者は悲しみに沈むだろう。その行為によって今まで戦ってきた意味は無くなるし、決定的な勝負に負けてしまうに違いない・・・」
1845年に、新たに敵は、承認されていない宗教法人に対して革命的な法律を適応するように命じる。特に政府にとって敵となっているはイエズス会だ。イエズス会と言う名前だけで政府は冷静さを失ってしまう。これから政府は一層迫害を強めてくるだろうか。心配だ。
ローマでの陰謀の噂が再び広がる。噂によると、教皇でさえイエズス会の会士だけではなく、教育の自由を応援してきた全ての人が降伏するようにと命令するかもしれない。何故なら、フランス政府は、依然としてさまざまな困難に遭遇しているにも関わらず、そして外見では全く正反対に見えるにも関わらず、聖座と暖かい関係を持っていると言い張っているからだ。
ド・マズノ司教は、一瞬でも迷うことはない。「ローマと当局は、フランスにいるローマ大使だけによって情報を集めているのであれば、本当のことを知らないはずだ。第三者である他の人にも知らせるべきだ」と確信していたので直接に教皇宛の手紙を書いた。率直に、教皇にイエズス会と教育の自由についての憂慮される問題についての自分の意見を伝えた。そして、思いきって結びの言葉を付け加えた。「猊下、私の願いを退けないで下さい。他からくるあらゆる懇願を退けて下さい。彼らは、猊下の許可がなければできないと思って、あらゆる方面から特別な懇願をしています。そういう懇願をする人たちは不公平きわまる意図を持ち、猊下を彼らの計画に巻き込むことができたら好都合だと思っています」
1848年2月に起こった革命はルイ・フィリップ王の失墜を招いた。マルセイユでは、少なくとも最初の頃、市民たちの混乱はなかった。当時ド・マズノ司教は日記で次のように書いた。「病人訪問をするために街のあらゆる所を回ってきた。全てにおいて完全な静けさが保たれている。市民は、壁や塀に掲示された声明書を読んでいたが無関心なようすだった」
事件が起こるにつれて
1852年11月の国民投票の時に、ド・マズノ司教は、「皇帝制度の尊い位の復興のためにルイ・ナポレオンという人物ならば」と賛成投票を入れた。無条件に賛同した。確かに今まではブルボン王家をずっと応援してきたが、国家のためには不幸を招くばかりの政治的な不安な状態を止めなければはならない。もちろん、ルイ・フィリップの息子に当たる王子を応援することも出来た。彼は味方にもなった。教育の自由のために大いに役立ったファルー法の方に票を入れた。そしてフランス軍隊を使ってピオ9世を助けてローマ教皇領の復興のために貢献した。1848年に暴動の扇動者によって教皇領から追い出されていたのだ。年ごとに、司教の心の中で大きな変動が起こった。前は王家だけを応援していたが、今はどの政府でも良かろうと考えるようになっていた。但し、国家の首脳陣が、少しでも不正なことをしたら、司教は、直ちに彼らの義務を明確に指摘し、そしてそれを正した。
その間、ピオ9世は、革命の圧力を受けて、1848年11月にローマから逃げ出し、ナポリの王国のガエタという要塞になっている街に亡命した。
この噂を受けてから間もなく次の噂も飛んできた。ガエタにいる教皇はフランスに亡命したいということだ。そして間もなくマルセイユに着くそうだ。ド・マズノ司教は急いで緊急に手紙をガエタに送った。教皇にマルセイユの司教館を自由にお使い下さいという内容の手紙だ。司教館は広いし便利だと司教は伝えた。しかも、「偉大な教皇が、ここに来てくださって臨在してくださるならば、もし不自由なことや足りないものがあった時には私は親に対する息子のような心でそれを補いましょう」と書いた。
この計画は満たされなかった。しかし、「子」としての盛大かつ心のこもった歓迎のかわりに、まもなく全てを失っていた教皇の生活費としてぺトロ献金という多額の寄付を送った。しかも、マルセイユの司教は、用心深くそれを行った。何故なら、司教が慈善をするつもりで送金したものが、かえって教皇の自尊心を傷つけるという心配がありうるからである。赤貧の状態に陥った人に対してもある程度の礼儀作法があるはずだ。司教は密かに調べてみたが確かに教皇は赤貧の状態にあった。もう躊躇は許されない。直ちに、マルセイユの司教は司教区民に声を掛けた。この説得には大きな反応があった。マルセイユ司教区の信者の寛大さはフランスの何処の司教区の信者のものよりも大きかった。
ド・マズノ司教は、教皇ピオ9世と皇帝ルイ・ナポレオンとの友好関係を死ぬまで保ち続けた。数多くの機会においてそれぞれに適切な行動をするように助言し促した。しかし、いつも忠誠を持ちながら敬意を示して介入した。決してバカ丁寧な調子ではなく率直に彼らに語った。
ナポレオン3世は、ド・マズノ司教を上院議員に任命した。昔、皇帝制度の激しい反対者であり、周知の王政主義者である人をその位に上げるというのは珍しいことだ。一方では、皇帝のド・マズノ司教に対する敬意を表している。他方では、皇帝はマルセイユを自分の味方にしたかったので、これは賢い作戦でもあったに違いない。しかし新議員は遠慮なく自分を任命した皇帝を攻めた。ナポレオンが教皇の地上の権利を支えているというふりをしながらも、教皇の持ち物が奪われても公然とそれを許していたことに対してである。
ピオ9世は、ド・マズノ司教が「聖座と宗教の権利を保護するために」行った行為を認めて司教を枢機卿に昇進させたかった。枢機卿に昇進されたら、この十九世紀の偉大な闘士は最高の栄冠を受けただろうが、しかしながら、その昇進は正式に公表されなかった。何故かと言うと、皇帝と聖座の間にある緊張は司教が死亡するまで持ち続けられたからだ。でも、この中断された昇進は、今日でも、おそらく意味のあることなのではないだろうか。

パリの上院議員だった時代のド・マズノ司教 74才(写真)
全世界を視野に入れて宣教する羊飼い
羊飼いだが、地平線のかなたまでも見通すほどの鋭い視力を持った羊飼いである。マルセイユの教会を超えて、フランスの教会を超えて、北極地方から熱帯地方まで、いたるところにキリストの福音を聞くために待っている羊たちがいるということをこの羊飼いはよく知っている。
ド・マズノ司教は、神の国の現存を認めない人の心の中にも神の国が働いていることを確信していた。神を告げるためには決して遅れてはならない。だからド・マズノ司教は19世紀における大胆不敵で行動的な宣教師の一人になった。
派遣される宣教師と一緒に出港はしないけれども宣教師の出発の準備をし、遠い所からも彼らが企画した計画を導き、絶え間なく彼らに勇気を与え、元気づける役割を果たした。
この神の国の建設という大きな仕事に対して、働き手は少なく、最初は修道会の少人数の「息子たち」だけであった。
25年が過ぎても修道会の会士はまだフランスの南部地方にしかいなかった。助け手となる会士はなかなか入会してこない。人数は増えない。最初に入会した会士たちは明らかに疲れきっている。オブレート会の会士たちは、どうにか細々とその活動を続けていた。他の修道会のように痕跡を残さず消えていってしまうのだろうか。全体を見ると、そう思わざるをえないような状況だった。
最初の隊商
1841年のある日のこと。カナダ人でモントリオール司教区のブルジェ司教はローマへ行く途中、マルセイユを通り、そして途中でド・マズノ司教の所を訪れていろいろなことを相談した。この旅人は、ここで、客を迎える司教の熱意溢れる心と同じ心を持っていた。今までも色々な人々が度々訪れてきているが、今回は熱意溢れる者同士である。二人の司教は直ちに友だちになった。カナダの司教は、自分の司教区では聖職者は少ないし司教区自体がとても広いということを心配していた。モントリオールの郊外や田舎地方や樵の森林伐採場やインディアンの野営地には助力が必要だ。しかも今すぐ必要だ。
二人が話しているうちに思いがけず、ド・マズノ司教が宣教会の創立者だということを彼は知った。幸せな驚きである。ブルジェ司教は求めていたものを見つけたのだ。今はさしあたって四人の司祭で十分だ。司祭たちを貰い受けたくてたまらない。ド・マズノ司教の方は断りたいのだがブルジェ司教はそれを許さない。「ローマに予定より早く出発し、カナダに戻る途中マルセイユに寄って連れて帰る」と喜びに溢れて言う。
ブルジェ司教の熱情に対してド・マズノ司教はやさしく寛大であったが一方大きな当惑もあった。何故かと言うと宣教会の成員は少ない。これより少なくするということは宣教会の絶滅になるかも知れないからだ。また修道会の会士は移民するために入会しているのではない。そして、当時、こんな遠い所に出発するなどということは強い意志と勇気が必要だった。そのために会士たちと相談した。すると単に肯定的な答えというだけではなく、熱狂的な反応が返ってきた。今までに見たことのない全員一致が現れた。ド・マズノ司教はこの成り行きを見て慰められた。そして熱意に応えて、信仰に支えられて直ちにカナダに手を貸すことを決意した。この寛大な行為によって宣教会自体の生命は救われた。
会士の最初の隊商が出発する用意は出来た。
「父」は「息子たち」に最後の忠告として次のように言った。「到着した時に人々の目はあなた方の方に向いてしまうだろう。最初の印象は永遠に続くものだからあなた方は振る舞いに気をつけなさい」。司教は恐らく自分自身の経験から話していたに違いない。司教自身の性格のために多くの人が司教の心まで浸透することができなかった例が過去に一杯あった。
そして未来を予言するかのように「モントリオールはこの宣教家族が福音宣教するための他の国々への門になるに違いない」と付け加えた。
最初の隊商は出発した。
半年が過ぎてからカナダからの最初の便りがあった。司教は笑ったり泣いたりしながらそれを読んだ。仕事や要請が多く、重圧ではあったが隊商はしっかり足を踏み締めていた。何処も会士たちを求めていた。そして希望の光がもう既に見えてきた。何人かのカナダ人が本宣教会に向けて目を注いでいた。
頭である司教は「アメリカ大陸における本宣教会の将来はあなた方の手にある⋅⋅⋅。自分自身の体力を超える仕事なら断りなさい。・・・勉学と聖性のための時間を十分に取って下さい。...これは欠かせないものだ」と言っていた。
北極地帯の勇壮な冒険
ド・マズノ司教が予言したようにモントリオールはカナダ全体への門になった。もう既に会士たちは四方に行って仕事をしていた。そして幾つかのインディアン部族に接触していた。
1844年から1845年の間、モントリオールから大分離れたリヴィエール・ルージュの堤にあるサン・ボニファス知牧区でフランス系のカナダ人の司教である知牧区長が活躍している。このサン・ボニファスからカナダ北西部の幅広い森林地帯(三百十二万五千平方キロ)にある多くのインディアンと混血人の野営地に行って宣教師としての熱意を燃やした。何回も縫い直した粗末なスータンを着、重い鹿皮の靴を履き、自給自足のための畑を作った。牛車を使って移動する。この知牧区を導くのはプロヴァンシェ司教である。
少数の司祭たちと一緒に草原や森林にいる人々に信仰の灯火をもたらした。その小さな灯火を燃えるような炎にまでしたい。しかし援助者はどこにあるのだろうか。オブレート会の会士に依頼したらどうだろうかと考えた。
マルセイユの司教はプロヴァンシュ司教の要請を受けた。直ちにもう既にカナダに根を下ろしている「息子たち」に命令をし、リヴィエール・ルージュまで進むようにと指示する。「神は我々の道を示している」と彼らに呼び掛けた。
しかしカナダでの創立者の代理者であるギーグ神父は同意してくれない。殆んど探検の進んでいない未開の地リヴィエール・ルージュに宣教拠点を設立するのはとんでもないことだ。「かえって神の御旨に反するバカな行為だ」という意見である。
「息子」のためらいを聞いて悲しむド・マズノ司教は、「一刻も遅れないように」と返事を書き、指示通りに行うようにと伝えた。

1844年にカナダの方へ福音宣教に行く宣教師たち
1845年6月24日、6人の漕手と共に2人の会士は樹皮で作ったカヌーに乗った。旅は62日間かかった。ようやく宣教師たちはサン・ボニファスに着く。牛車の側に立って、鹿皮の靴を履いた司教が迎えに来た。北極地帯の雄壮な冒険が始まろうとしている。
本宣教会では、これまで使ったことのない単語が馴染み深いものになった。例えば「カヌー」、「激流」、「連水陸路」、「テント」、「野営地」、「鹿皮の靴」、「かんじき」、「野牛狩り」、「干し肉」、などだ。一つひとつは興味をそそる単語だ。しかしこれらの単語は彼らの生活の真意を伝えるものではない。何故かというと、現場にいる会士たちの生活の冒険性を語るのではなく、彼らの使徒的生活の耐えがたい過酷さを語る単語だからである。それでも結局「雄壮な冒険」という面が強調されるのだ。宣教師たちは常にインディアンの広大な草原を縦横に走り、大きな河を上り下りし、湖を渡って行った。狼や狐の皮が腐らないようにと森を走る人たちと同じように速く前進し、熱意に燃えて全ての人々の救いのために北極地帯に近付こうとした。年々に彼らは徒刑囚のように斧の使い方を覚え、丸い仮小屋や小聖堂を建て、学校や病院を造り、インディアンの方言を覚えた。遊牧民と共に遊牧民になった。
年々に新しい単語のリストは、長くなった。「雪煙」、「猟犬の群れ」、「橇」そして最も恐るべき単語、「エスキモー」、「不毛の土地」、「カヤック」、「氷の家(イグルー)」、「なま肉」、「銛」などが登場する。サン・ボニファスから北氷洋まで、太平洋からハドソン湾まで、北極の島々までオブレート会の会士によってイエス・キリストの教会は臨在していった。
1846年。ためらっていたギーグ神父は立ち直った。カナダの司教団は全員一致で彼を聖座に推薦し、彼はバイタウン(現オタワ)の新しい司教区の司教として任命された。カナダにおけるオブレート会から生まれた最初の司教である。
1847年、また新しい苦悩の叫びが創立者の耳まで届く。アメリカ合衆国のロッキー山脈の向こうにあるオレゴン州の司教からだ。オブレート会に声を掛けてきた。ド・マズノ司教は会士の数を計算する。派遣する適当な人は誰もいない。病人の神父を復帰させることにする。四十二才でまだまだ早すぎるのだが疲れきったリカール神父がプロヴァンスのノートルダム・ド・ルミエールの巡礼地で細々と暮らしていた。彼の人生の日々はもう残り少ない。でもかまわない。オレゴンの宣教のための拠点を設立するために必要な人物だ! 旅の間だけでも生き残ることができるだろうかと不安だったが生き残った!
世界に向かって開かれた広い心
そういう寛大さに対して、主はさらに寛大に応えた。今までは、イゼール地方にあるノートルダム・ド・ロジェは、オブレート会の唯一の修練院であった。入会志願者は多すぎたので場所が足りなかった。1847年10月20日にナンシという場所に二番目の修練院を開いた。
翌日、新たな隊商は出発した。しかし今回はカナダ行きではない。今度はアジアのセイロン(スリランカ)で新しい宣教の拠点が設立された。
ド・マズノ司教はもう断ることができない。心を開くための合い言葉が見つかってしまえば司教の心はすぐに開いてしまうのだった。
「マルセイユに行きなさい」と誰かがベタチーニ司教に教えた。その司教はセイロンのために宣教師を探していたが見つからず困っていた。「マルセイユの司教は・・・聖パウロと同じような広い心を持つ。世界を視野に入れた広い心の持ち主だ・・・。貧しい人々、とても貧しい人々を救う仕事なのだとよく説明しなさい・・・。それは彼が抵抗できない合い言葉になるはずだ」とベタチーニ司教に教えたのだ。
ベタチーニ司教はそれで直ちに物乞いのようにマルセイユまで足を運んだ。
「ああ、どうやってあなたの希望に応えようか?」とド・マズノ司教は言った。
さあ決定的な瞬間だ。セイロンの司教はためらいなく答えた。
「司教よ、ここの人たちは貧しい人々なのです。最も貧しい人々だと保証いたします・・・。ああ、この世の最も惨めな人々です・・・。お願いだから彼らに宣教師を派遣して下さい」

1847年にスリランカへ福音宣教に。
やはりこれが合い言葉になった。ド・マズノ司教の心は激しく動かされた。腕を広く開いて、泣きながらセイロンの司教を抱いた。「直ちに派遣する」と力強く約束した。
新しい宣教地の設立のリズムは加速した。ここで全てを述べることは不可能だ。
カナダへ行った年に同じくイギリスにも会士は派遣された。そこでの宣教も毎日広がって行った。
フランスでも、海外への派遣に影響がない程度まで修道院は益々増えていた。
1849年。オブレート会はアメリカ合衆国のテキサス州まで足を運んだが、この地では悲しい災いがもたらされた。黄熱病によって会士の数が減っていった。「テキサスの残酷な宣教地よ ! 私の心は傷ついている」とド・マズノ司教は悲しく書いた。「五人目も惨めな病気にむさぼり食われてしまった!・・・六人目はまた何時になるのか。私の神よ、私の苦悩の叫びをお許しください」

1852年3月15日から南アフリカでの福音宣教が始まる。
1850年。ド・マズノ司教はアフリカの端まで「息子たち」を派遣することにした。オブレート会が経営している大学からその大学長、元修練長のアラール神父を取り上げてしまうことになるが彼をアフリカのナタール地方に派遣したいと強制的とも言える手紙を書いた。しかし厳しい苦業者であるアラール神父は、自分の心を掘り下げて見つめた結果、多くの欠点を見い出した。そして新しい宣教の拠点を設立する頭として自分はふさわしくない、また黒人たちの司教となる資格はないと判断した。
ド・マズノ司教は信じられなかった。この元修練長を動かすためには、教皇からの決定さえ必要だった。
遂にこれが神の御旨だと認め、受け入れたこの誠意ある厳しい修道者は一生懸命になった。1851年7月にマルセイユで司教の叙階を受け、そして間もなく南アフリカ行きの船で出発した。
この出発によって、献身宣教会の創立者はブラックアフリカのことを常に心にかけるようになった。「180万人のカフィール族の人を改心させるなんて何と素晴らしいことだろう」と叫んで、カフィールのアラール司教に絶えず手紙を送ってはげました。その手紙は殆んど叩き付けるような厳しいものだった。鞭打ちのように激しかった。
その手紙を少し読んでみよう。
「カフィール人へのあなたの宣教が成功しなかったことについて私は悩んでいる。・・・この様な空しい例はあまり見たことがない。信徒でない人々の所へあなたは派遣されたが、彼らの中の誰一人も、あなたが彼らにもたらした真実へと目を開かなかったとは何ということか。私はその事について自分を慰めることに難儀している。・・・あなたが送られたのはカフィール人の所であり、教会があなたに委ねた聖なる奉仕から期待するのは、彼らの改心である。だから、あなたのすべての考えと努力をさし向けなければならないのはカフィール人に対してである。あなたが外に出て、あなたの司教区を少しでも調査するなら、私はとてもうれしい。宣教地の司教たちは、決して司教館で座り込んでいてはいけない」
黒人のまっただ中にいるアラール司教は日によって何もできない。その時再び創立者は叱咤激励する。
「親愛なる司教よ、あなたの手紙がまだ私を非常に悩ませていることを認めなければならない。今日までのあなたの宣教は失敗した宣教であると言える。率直に言えば、使徒座代理区長やかなり多数の宣教師を派遣したのは、単に、数少ない四方に散らばっている古いカトリック信徒の世話をするためではないはずだ。これらキリスト者には一人の宣教師で充分だろう。私が宣教師を派遣した理由はそれではない。この地方において、ただただカフィール人に福音を宣べ伝えるという目的で設立されたということは明白なはずだ。もしそれをする見込みがなければそこから退くべきだ。」
こうして、頭は、マルセイユから特別な決意をもって指揮を取っていた。足ふみ状態は許さない。常に前進しなければならないのだ。旅人の杖を持って、右へ行くのに障害があれば左へ行く。山があろうと河があろうと、人の反対を受けようと、黒人の種族を主に導くために常に前進しようとした。
しかしながら、広いアフリカにいるカフィールの司教のアラール司教の口からは一度も文句は聞かれなかった。院長ド・マズノ司教から一杯侮辱を受けてもアラール司教は黙っていた。
今日、熱帯地方にあるこのオブレート会の宣教拠点はアフリカ全体で一番栄えている宣教地だ。
この新しい宣教的活動を祝福し、完成させるために、1857年にはボルドーの聖家族のシスターの創立者である良き司祭ノアイユ神父が、ド・マズノ司教の修道会にそのシスターの修道会を加入させたいと申し出た。こういうことは特に宣教地では欠かせない歓迎されるべきことだ。もちろん司教はそれを受け入れた。
従って、それ以来、オブレート会はシスターたちと一緒に歩むという新しい道を開いたのである。「シスターたちは皆の姉妹となり、皆の母となっている。女性、この言葉は意味深い。彼女らは優しい場面をもたらしてくれている」
ド・マズノ司教の死
1861年5月。ウジェーン・ド・マズノ司教の一生は晩秋という時期にさしかかっている。最後までマルセイユ司教区と本宣教会を確かな手で指導した。時には司教区を、時には宣教会を指導し、きっちりとその勤めを成し遂げた。小競り合いがあったり大きな戦いもあったりしたが全てに力を抜くことなくやり遂げ、そして退いた。
性格上も、身体上も鉄人だ。
ついに、終わりが来たと感じた時に、「もし居眠りしてしまっていたら、そして容態が悪化していたら、お願いだから、起こして下さい。意識しながら死亡したいのです」と言い出した。

マルセイユ大聖堂内にある小聖堂のド・マズノ司教のお墓
主は十分彼を満足させて下さった。司教は自分が死へと赴く姿を見たのである。一生は戦いだったが、最後の苦しみは永遠の安らぎの前兆だった。会士たちが、泣きながら、サルヴェ・レジナを歌っていた時にオー・ドゥルチス・ヴィルゴ・マリア(ああ甘美なる処女マリア)の言葉を聞きながら、このキリストの「闘技者」、この「汚れなきマリアの献身宣教師会士」は、完全な意識を持ったまま、最後の安らぎに今、まさに移っていくのだということを深く味わっていた。
この心静かで平和な休息が得られたのは深い悟りの結果である。その悟りは晩年になってから、少しずつ確実につかんできたものだ。度々の抵抗や闘争は彼を傷つけ疲れさせたが、一方それが彼を完全に円熟に導いた。この、苦しいがしかし有益な体験によって、偉大な頭は一番大切な美徳とは激情や怒りではないことを学んだ。美徳の中の厳しさは、時には人間に節度を保たせるために必要であるが、冷静な分別や温和で甘美な情が必要であるということを学んだのである。
一筆で、この力強い人物像を描こうとすることは無謀な計画だ。彼の生涯の展開、つまり若い頃の放蕩生活から司牧者としての充実までについて、幾つかの主な描写を提供しただけだ。読者の一人ひとりが、この人物の最も顕著な特徴を選んだ方が良い。フランスのツッルの司教ベルトラン司教は、この偉大な「汚れなきマリアの献身宣教会士」について自らの評価としてこう言った。「マルセイユへ行きなさい。そこにまだ小さい修道会を持つ司教がいる。その修道会は小さいけれども本人は聖パウロの広い心と同じような心の持ち主だ。世界を視野に入れた広い心だ」と。
【このカテゴリーの最新記事】