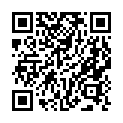2018�N03��08��
��ł����͂��̋���U���u���K���h���v�ɐ��E���k�����I
�f��W���[�Y�ł�����݂̃z�z�W���U����5m��1�g���Ƃ��Ȃ���Ȃ�傫�����ŁA���̃T�C�Y�̃z�z�W���U�����ߊl�����ƃj���[�X�ɂȂ�قǂ������K���h���͂��̑�����2�`3�{�ȏ�̏d�Ɏ����Ă�30�{�O����������Ƃ����B
150���N�O�̊C�ɐ������Ă������Â̋���ȃT���Ō��݂ł͐�ł��Ă���ƍl�����Ă��邪�A���X�̖ڌ��k�؋��ʐ^�Ȃǂ��琶�������������B
����ȋ���U���������c���Ă���Ȃ猩�Ă݂����C�����邪�A�ۈ��݂��ꂽ�炽�܂������ł͂Ȃ��̂ł����炪�������Ă��邤���ɂ��̐��Ԃ�������ƌ��Ă݂悤�B
���H����L
���K���h���̐����Ȋw���̓J���J���h���E���K���h���Ƃ����A�a���̓��J�V�z�z�W���U���Ƃ����B
�w����a��������킩��ʂ�z�z�W���U�����̃t�`�Ƀm�R�M����̓ˋN�̕t�����O�p�`�̎��͑傫���������Ό����̃z�z�W���U���̂���ƍ������Ă���B
�L�͂��̎�ނɂ���Ď��̌`�������قȂ胁�K���h���̎����z�z�W���U���Ǝ��Ă���Ƃ������̓��K���h���̎p���܂��z�z�W���U���Ǝ��Ă���Ƃ����\���������������������R���烁�K���h���̓z�z�W���U�������̂܂܋��剻�������p�ŕ�������Ă���B
�N�W���̉����烁�K���h���Ɋ��݂��ꂽ�Ǝv���鎕�^�Ȃǂ�����Ñ�̌��n�I�ȃN�W���ޓ���ߐH���Ă����ƌ����Ă���B
�N�W��2�����炢�͂䂤�Ɉ��ݍ��߂鐨�����֖҂ȕߐH�҂ł���B
�Ȃ���ł����̂��H
���K���h���͊C����r�I�g������������ɐ������Ă������N�V��(��600���N�`200���N�O)�����ɐ�ł����ƍl�����Ă���B
�����̊C�͌��݂����g�����N�W���Ȃǂ̑�^�C�m�M���ނ��ɉh���Ă��胁�K���h���͂��̃N�W���Ȃǂ��l���Ƃ��Đ����̊C�m���Ԍn�̒��_�ɌN�Ղ���ߐH�҂ł������B
����ȓ����̊C���x�z���Ă����}�K���h���͂Ȃ���ł��Ă��܂����̂��H
���̌����͑傫��������2����ƌ����Ă���B
�E1��
�C�̊��≻
���ɉ��g��������O�I�̊C������ɓ���Ɗ��≻���i�ݕX�͂��`�������悤�ɂȂ��������K���h�����܂ގL�̒��Ԃ͕ω������ł��邽�ߋC���ω��̉e�����₷���ƌ����Ă���B
�܂��P�������ł���N�W��������ȊC��ɓ��������ߐg�̂̑傫�ȃ��K���h���͐[���ȐH�ƕs���Ɋׂ邱�ƂɂȂ����̂��B
�E2��
�V���`�̏o��
�P�������ł��苭�����i�����V���`�̔����͓����̊C�̐��Ԍn��傫���ς�����̂������B
��ʓI�̃T���͕��܂������Ȃ����ߋ��剻����قljj���X�s�[�h���x���Ȃ�ƌ����Ă��邪�A�V���`�͋���Ȑg�̂������Ă��Ă����ɍ����ʼnj�����Ƃ��\�ł������B
���̃V���`�̏o���ɂ�胁�K���h���͐��Ԍn�n�ʂ�D����ł��Ă��܂����̂��ƌ����Ă���B
�ڌ��k�E�؋��ʐ^�ɂ�鐶����
1942�N11��18���A��A�t���J�̃P�[�v�^�E�����Ń��K���h���̐������ؖ�����؋��ʐ^�Ƃ��ėL���ȂP�����Ƃ��Ă���B
�h�C�c�R��U�{�[�g�̌��������ɋ���U���̎p���f���Ă���̂��B
�C�ʂɏo�Ă���w�т�Ɣ��т�̊Ԃ�19.5m������Ɛ�������Ă���B
��O��U�{�[�g�Ɣ�r���������Ǝv����̂łقڐ��m�Ȑ����ł͂Ȃ����낤���H
�����{���Ȃ烁�K���h���̒��ł�20m�����̓���T�C�Y���B
�܂��A�ߔN�ł��n���C���Ŕ��Ђ��H��������ꂽ�~���N�N�W���̎��̂��������ꂽ���A�t���J�ŃN�W�����P���Ă��郁�K���h���Ǝv���鋐�吶���̔��Ђꂪ�B�e���ꂽ�蓙�ڌ��k�����₽�Ȃ��B
�C�m�����͗��㐶���ɔ�ׂĊ��̉e�����ɂ����A���K���h���������c���Ă���\���������ƌ����Ă���B
���ہA�������������Ɛ̂ɒa�������V�[���J���X�͐[�C�ɓK�����邱�ƂŌ���܂Ő����c�邱�Ƃ��ł����B
���K���h�����[�C�ɐ������Ă���\���������ĒႭ�͂Ȃ����낤�B
����Ñォ�琶���鋐��U���ɂ��ڂɂ����肽�����̂��B
�����܂ł��A�l���Ƃ��Ăł͂Ȃ��T�ώ҂Ƃ��Ă̘b�����B�B�B
���̋L���ւ̃R�����g
�R�����g������
���̋L���ւ̃g���b�N�o�b�NURL
https://fanblogs.jp/tb/7400797
���̋L���ւ̃g���b�N�o�b�N