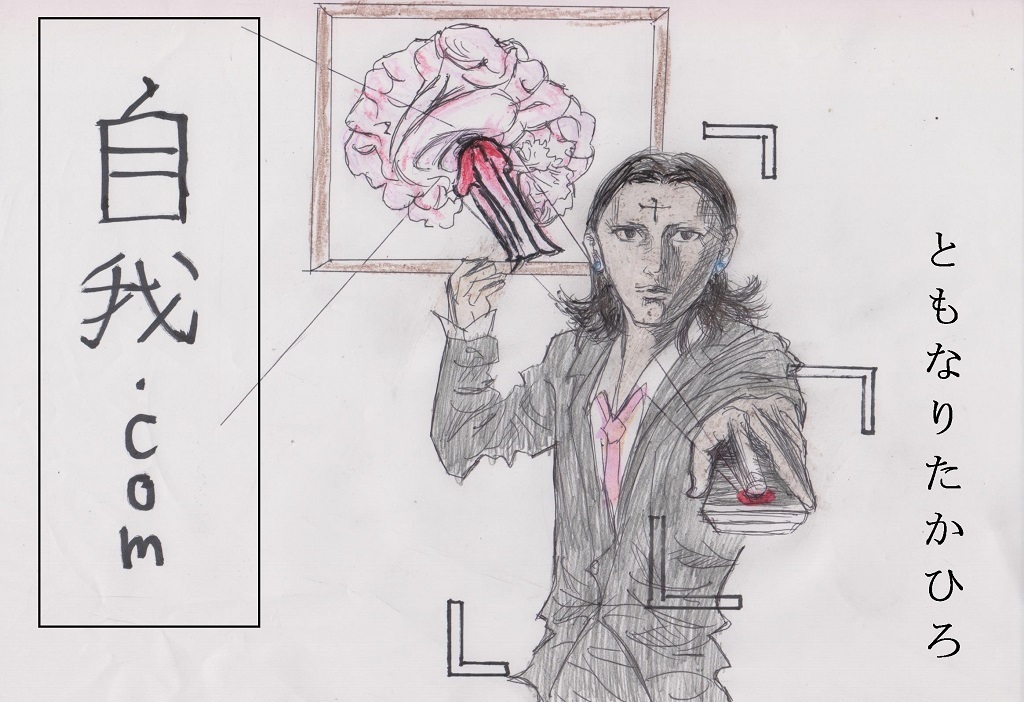2016年01月23日
こんな寒い日には・・・・・・独り、短編小説を読むのが一番でしょう。
こんな雪の降るような寒い日には、――小説を読むのが一番でしょう。
以下に、初期の僕が書いた「雪」をテーマにした短編小説を。
読者である貴方の心に、ちょっとした「灯り」がともればいいな、と思ってます。
では。
タイトル『野暮ったいやつ』
例えば、福岡などの九州でさえ降る雪が、なぜか関東だけは降らない、ということがよくある。
そのたびに僕は、
「関東っていうのは、ほんと、気の利かない、野暮ったい奴だな。」
と思ってきた。
その呟きは、関東の野暮ったさについての感慨であると同時に、僕自身の中にある野暮ったさに対する感慨でもあったのである。
本当に、雪ぐらい気軽に降ってくれさえいれば、こんな「別れ」にはならなかっただろうに、と口惜しく思われる、小さな小さな物語がある。それを物語ろう。
当時、26歳の僕は、神奈川県の海老名市という片田舎に住んでいた。
小説家を目指していた僕は、昼は地元の食料関係を取り扱う物流倉庫で働き、夜空いた時間に小説を執筆する、という生活を続けていた。一日の大半を倉庫内で過ごし、それも仕事が終わるのは大抵夜7時過ぎ、となると、当然、仕事終りに事務所の玄関から外に出ると、もうすでに辺りは真っ暗になっている。ゆえに、必然的にもう長いこと日中の日差しを浴びたことがなかったし、ましてや、西日の美しさを見る機会など皆無と言っていいほどなかった。
うす汚れた喫煙室にて、あらくれ者たちとタバコを吹かしながら、とりとめもない雑談を交していると、何度となく「僕は一生、こんな世界の片隅で終わるのだろうか?」という考えに囚われたものだ。雑談に溶け込み、「顔」は笑っていたとしても、僕の「影」は泣いているに違いなかった。
そんな倉庫内の仕事の中にも、一つの救いがあった。
それは事務の中谷さんという女のひとの存在であった。僕は彼女のことが好きだったのだ。
中谷さんは、事務所内でもなかなかの古株らしく、歳も36、7ぐらいと噂されていたが、未だに独身のようであった。どころか恋の気配すらなく、仕事一徹の堅物といった感じであった。面長の顔立ちで、顎が突き出ており、目も一重で光なく、かわいそうなほど顔中の至るところに赤いにきび痕が残っていて、少しも垢抜けていなかった。からだも小柄すぎるほど小柄で、足などは紺のハイソックスのせいか、小学生のようにさえ見えるほどで、要するに、女性としての色気はまったくと言っていいほどなかった。
しかし、小さなくちびるを真一文字に締め、小さな背筋をぴんと伸ばし、書類をトントンと揃え、てきぱきと仕事をこなす姿は、僕にはとても理知的に見えた。中谷さんと僕の担当業務は違ったので、僕はそんな中谷さんの仕事姿を、ただ遠くから見つめるばかりであったのだが、僕が見た限りでは、中谷さんはそんな理知的に振る舞いによって、自身の女性としての深い苦悩を隠蔽しているように思えてならなかった。むしろ彼女が女性としての魅力のなさを、気にしていないかのように振舞えば振舞うほど、それが「影」として浮き彫りになるのだから、不思議なものだ。
中谷さんの「影」は泣いている。僕はそこに好意を抱いてしまったのである。前述のとおり、僕も「影」が泣いていたのだから、この人とはきっと理解しあえる、と思い込んでしまったわけだ。
しかし、担当業務が違うので、そもそも話す機会がなかった。万に一、あるとすれば、それは帰り際、雨の降っている日に限っていた。
ある雨の日の仕事終わり、偶然にも、僕は中谷さんと事務所の玄関先で一緒になったことがある。
その際僕は、
「雨、ですね。」
と言った。
中谷さんも平気な顔で、
「ですね。」
とだけ言った。
たったそれだけのやりとりであった。
彼女はしっかり者であるから、小柄な体型にしては大きすぎるピンクの傘を携帯しており、それをぱっと開いて、「それじゃ、お先に失礼します。」と小声で僕に言い残し、しのつく雨の中へと消えていった。僕は僕で、安物の傘を持っていたのだから、お話にならない。そう。雨では駄目なのだ。お互いに傘を持っていれば、雨などなんの「きっかけ」ももたらしてはくれない。
時間が過ぎるのは早いものである。季節はすでに12月になっていた。気温が一桁台の寒い日々が続いた。未だ雪は降っていないが、この調子ならこの冬は関東にも雪が降るだろう、と思われた。
もし雪が降ったとしたら、中谷さんと急接近できるかもしれない。なぜならば、雪の場合、「雪が降ったこと」自体がすでに話のネタになるからだ。そうなれば、もはや傘の有無で一喜一憂する必要がなくなるわけだ。
しかし、待てど暮らせど、関東だけは決して雪が降らなかった。
12月という季節は、物流系、なかでもうちのような食料を取り扱う仕事にとっては、一番の書き入れ時らしく、多忙をきわめる。僕の担当する業務もそのご多分にもれず、12月から年末にかけて、過労死するほどの仕事量を押しつけられ、僕もめくらめっぽう八面六臂に立ち働かされた。その間はさすがに中谷さんのことを思い慕う余裕などなかった。
年末が去り、1月に入った。しばらくしてから、ふと、事務所内に中谷さんの姿がないことに気がついた。
これは後で聞いたことなのだが、彼女は12月中にはもうこの仕事を辞めることを決めていたという。
中谷さんは、暇を見つけては度々、同期の大木さん(同期といっても、一回り上のおばさんなのだが)に、身の上相談をしていたらしい。大木さんは勿論、なぜその歳で仕事を辞めるのか、その理由を詰問したそうだ。すると中谷さんは、静かな口調で、「これからの人生を、一度、真剣に考え直してみたいんです。」とだけ答えたそうだ。
そんな後日談を聞いて僕は、「やはり恋愛や結婚のことで悩んでいたのだな」としみじみ思った。と同時に、そんな彼女の裏の「人生問題」に僕という存在は含まれていなかったのだ、と思うと、真っ向から眉間を割られた思いだった。
それを知らされた日の仕事帰り、呆然とした思いで外に出てみると、――馬鹿な話、雪が降っていたのだ。塵を散らしたようなボタン雪であった。泣けなかった。ただ、間の悪さに、胸が一杯になっただけだった。
いくらこの雪が今日深夜から明日の朝にかけて断続的に降ったとしても、この関東地方においては、翌日には暖かい日差しを受け、跡形もなく消え失せるだけなのだ。おそらく、僕の彼女に対する思いも、この関東地方における雪のように、明日になってしまえば、仕事の忙しさの中へと埋没してしまうに違いない。やがて、彼女の存在自体もまた、次第次第に忘れ去られていってしまうに違いない。
僕は長い間じっと、そのボタン雪を見るともなく見ながら、もし、彼女が辞める前に、雪が降っていたとしたらどうなっていただろう? と考えた。
僕は、雪を見て、
「あ。雪、ですね。」
と言う。
中谷さんは、
「ほんとだ。雪ですね。」
とやはり理知的に答えたに違いない。
そして、白い息を弾ませて、ふたり、自然と同じ方向へと歩き出していたかもしれない。
そんな甘い空想を思い浮かべていると、どうにも目が滲んできて、困った。僕はボタン雪を眺めたまま、やがて諦めたように白い息を吐き、苦笑しながら次のように呟く他なかった。
「おまえは、ほんと、気の利かない、野暮ったい奴だよ。」
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4654725
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック