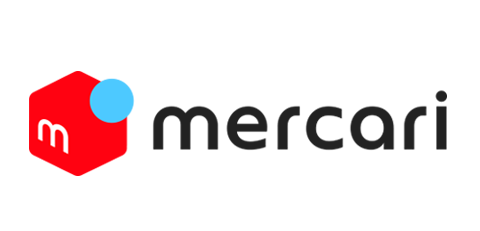小さな村の外れに、深い森の入り口があった。そこには透明な小川が流れ、葉の影に隠れるように、静かな池が横たわっていた。その池の中では、見慣れた緑色のカエルたちが住んでいた。池の中央には、年老いたカエルの長老が住む大きな蓮の葉が浮かんでいた。
長老はいつも村中のカエルたちを見守りながら、彼らの知恵を引き継いでいた。その長老に、最近、待望の孫が生まれた。その名はトビオ。小さなトビオは、誰よりも大きな夢を持っていた。「僕はこの池を出て、大きな湖で暮らすんだ」と、毎晩星空を見上げながらそう思いを馳せていた。
ある日、トビオは父親のトビスケにその夢を話した。「父さん、僕はいつかこの池を飛び出して、もっと広い世界を見るんだ。大きな湖や、さらに向こうの世界に行きたいんだよ!」トビスケはにっこりと笑い、トビオの頭をそっと撫でた。
「トビオ、それは素晴らしい夢だ。でもな、覚えておくんだ。カエルの子はカエルだ。俺たちは池の中で生まれ、ここで生きる。だから、お前もいつかはこの池に戻ってくるんだよ。」そう言うと、トビスケはトビオに向かって目を細めた。「お前がどんなに遠くに行こうとも、ここがいつでもお前の帰る場所だということを忘れないでくれ。」
それから数年が過ぎ、トビオは大きく成長し、ついに池を飛び出す時がやってきた。風に乗り、広い大地を越えて旅を続けたトビオは、ついに夢にまで見た大きな湖にたどり着いた。湖は広大で、池とは比べものにならないほどの美しさだった。
トビオは湖の美しさに感動し、その岸辺に住むことを決意した。日々、自由を謳歌し、湖の新しい仲間たちと共に冒険を重ねたが、時が経つにつれて、心の中にはかすかな寂しさが募っていった。どれだけ美しい湖でも、どれだけ多くの仲間がいても、心の底から落ち着くことはなかった。
ある夕暮れ、トビオはふと、故郷の池を思い出した。小さな池だったが、家族や仲間たちがいて、自分が育った場所だった。「帰りたい」と心の中でつぶやいた瞬間、トビオは翼を広げ、再び風に乗って故郷へと飛び立った。
故郷の池に戻ったトビオは、久しぶりに見た懐かしい風景に胸が熱くなった。池の縁には、年老いたトビスケが静かに座っていた。トビスケはトビオの姿を見て、にっこりと微笑んだ。
「おかえり、トビオ。やはりカエルの子はカエルだな。」
トビオは父の言葉を思い出しながら、池の中に静かに飛び込んだ。その水の中は、思い出の香りで満たされていた。そして、トビオはようやく、ここが自分の本当の居場所であることを深く感じたのだった。
物語の終わりに、トビオは池の中で、父や仲間たちと共に平穏な日々を過ごした。広い世界を知り、夢を叶えたトビオは、その経験を村の若いカエルたちに語りながら、「どんなに遠くに行こうとも、いつでも戻る場所があることが、何よりの幸せなのだ」と教えるのだった。
カエルの子はカエル。それは、運命を受け入れることではなく、どこにいても自分の根を忘れないということ。そして、その根があるからこそ、どんな冒険にも出られるのだ。
ギャグ編
小さな村の外れに、カエルの池があった。その池は平和そのもので、カエルたちは毎日ピョンピョンと飛び跳ねながらのんびり暮らしていた。池の主、カエルの長老ガマさんは、村中で一番長く生きており、誰よりもお説教が長いことで有名だった。
ガマさんには孫がいた。その名はトビオ。トビオは村一番の跳ねっぷりで有名だったが、夢見がちなカエルでもあった。毎晩、星空を見上げては「もっとデカい池で、ビッグに生きてやる!」と息巻いていた。
ある日のこと、トビオは父カエルのトビスケにこう言った。「父ちゃん、俺、この池を飛び出すぜ!なんつったって、俺はトビオだ。名に恥じぬ飛びっぷりで、湖くらいまで飛んでやるぜ!」
トビスケは深いため息をつきながら、言った。「おい、トビオ。そりゃ無理だ。カエルの子はカエルだ。お前のジャンプ力、見たことあるけど、せいぜい3メートルだぞ。湖なんて夢のまた夢だ。お前の目的地は、となりのどぶ川くらいだな。」
トビオはむっとした。「父ちゃん、それ、かなり失礼だぞ!見てろよ、俺は絶対にビッグになるんだ!池の長老?そんなの古臭い。俺は世界一のカエル、"スーパージャンプカエル"になるんだから!」
トビスケは肩をすくめて笑った。「いいか、トビオ。世界が広いのはわかるけど、結局カエルはカエルなんだよ。どんなにジャンプしても、俺たちは湿ったところが大好きなんだ。あと、虫だって食わなきゃならないしな。豪華ディナーとか期待するなよ?」
トビオは耳を貸さず、「じゃあ見てろよ!」と、その場から思いっきり飛び上がった。しかし、勢い余って木の枝にぶつかり、ドサッと地面に落ちた。
「いててて...まぁ、最初のジャンプはこんなもんだ。準備運動さ!」
トビオはなんとか池を飛び出し、旅に出た。最初の目的地は近くのどぶ川。しかしそこに到着すると、トビオは絶望の声を上げた。「うわ、臭い!やっぱりこんなところで終わる俺じゃねえ!」
なんとか勇気を振り絞って次の目的地、憧れの大きな湖を目指して飛び続けた。ついに、トビオはその湖にたどり着いた。湖はキラキラと輝き、広大な水面が広がっていた。
「すげえ!これだよ、これが俺の求めてた場所だ!」トビオは喜び勇んで湖に飛び込もうとした――が、湖の岸辺に待っていたのは、大きな魚だった。
「おい、小さなカエル。ここは俺たちの縄張りだ。そんな小さなジャンプじゃ、お前なんか一口だぜ。」魚がニヤリと笑った。
トビオは慌てて「え、えーと、いや、俺はただ観光に来ただけだから!観光名所をちょっと見るだけで、あとはもうすぐ帰る予定だし!」と、後ずさりながら叫んだ。
そしてトビオは、渋々故郷の池に戻ることになった。池に帰りついたトビオは、父のトビスケや村のカエルたちが待ち構えているのを見て、苦笑いを浮かべた。「やっぱりさ、家が一番だよな。あの湖、あんまり居心地良くなかったし…いや、正直に言うと怖かった。」
トビスケは大笑いしながら「だから言ったろ!カエルの子はカエルだ。結局、俺たちはこの池が一番さ!」と背中を叩いた。
トビオは池の中に飛び込みながら、心の中で小さく呟いた。「まぁ、ビッグにはなれなかったけど、この池でみんなと一緒にピョンピョンしてるのも、悪くないかもな…ただ、次は魚には絶対会いたくねえ!」
村のカエルたちはその日も、トビオの冒険談に大笑いしながら、平和な日常を取り戻したのだった。
「カエルの子はカエルだ!」という教訓が、笑いの中で深く浸透する一日だった。