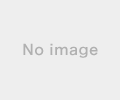2014年07月10日
うまや
うまや
馬を飼っておく独立した建物や家屋内の馬(ときには牛)を飼う部屋で,〈まや〉とも呼ぶ。農耕馬を飼う農家の馬屋と乗馬用の馬を飼う武家屋敷や神社・寺院の馬屋とでは構造が異なる。農家の馬屋は,主屋内にある内馬屋と独立して建つ外馬屋に分かれるが,南部の曲屋は外馬屋を主屋に接続させて成立した形式である。また日本海側の多雪地方に多い中門造はもともとは主屋内にあった馬屋を中門に移すことによって成立しており,両者の中間的な存在である。南関東地方などでは内馬屋は少ないが,全国的には内馬屋が広くおこなわれ,主屋内の作業空間である土間の一隅をあてる。農家では刈草やわらを踏み込ませて堆肥とするので,地面を掘りさげる。深いものは1mにも及ぶ。東北地方などの上層の家では数房の馬屋をもち,また子馬を別馬屋に入れる例もある。馬屋の入口には〈ません棒〉と呼ばれる取外し可能な木の桟を取りつけ,他は板壁とする。ただ堆肥を取り出す戸口を別に設ける例もある。馬屋には多くの場合,天井を張り,この上を下男部屋や物置にあてる。冬が長い東北地方などでは,馬屋は広く,近畿地方などのものは狭く,約3m四方ほどである。外馬屋は馬屋ばかりでなく,便所,納屋を併設するのが普通である。内馬屋の場合,馬屋の柱は他より腐朽しやすいので,主屋とは構造を切りはなし,柱を容易に取りかえられるようにした例が長野県などにみられる。
武家の馬屋,すなわち書院造の邸宅に設けられた馬屋は,馬をつないでおく立て場,遠侍と呼ばれる座敷と土間の草の間をもつ。《洛中洛外図[zAC25]風》や幕府大棟梁平内(へいのうち)家の伝書《匠明(しようめい)》には,妻入りで桁行3間の馬屋が描かれ,当時もっとも正式のものとされている。立て場は土間でなく板張りで,農家の馬屋のようにません棒を用いず,くつわつなぎ,腹掛けなどをもつ。中世の絵巻などに描かれた武家の馬屋では,猿が飼われているが,これは猿が馬の病気をなおすと信じられたためである。日光東照宮の神厩は,武家の馬屋の形式で造られ,三猿(見ざる,いわざる,聞かざる)その他の猿の彫刻が飾られている。また彦根城の馬屋はL字形の平面をもち,21の小間,端部に馬丁の休息所をもつ大規模なものである。⇒畜舎
馬を飼っておく独立した建物や家屋内の馬(ときには牛)を飼う部屋で,〈まや〉とも呼ぶ。農耕馬を飼う農家の馬屋と乗馬用の馬を飼う武家屋敷や神社・寺院の馬屋とでは構造が異なる。農家の馬屋は,主屋内にある内馬屋と独立して建つ外馬屋に分かれるが,南部の曲屋は外馬屋を主屋に接続させて成立した形式である。また日本海側の多雪地方に多い中門造はもともとは主屋内にあった馬屋を中門に移すことによって成立しており,両者の中間的な存在である。南関東地方などでは内馬屋は少ないが,全国的には内馬屋が広くおこなわれ,主屋内の作業空間である土間の一隅をあてる。農家では刈草やわらを踏み込ませて堆肥とするので,地面を掘りさげる。深いものは1mにも及ぶ。東北地方などの上層の家では数房の馬屋をもち,また子馬を別馬屋に入れる例もある。馬屋の入口には〈ません棒〉と呼ばれる取外し可能な木の桟を取りつけ,他は板壁とする。ただ堆肥を取り出す戸口を別に設ける例もある。馬屋には多くの場合,天井を張り,この上を下男部屋や物置にあてる。冬が長い東北地方などでは,馬屋は広く,近畿地方などのものは狭く,約3m四方ほどである。外馬屋は馬屋ばかりでなく,便所,納屋を併設するのが普通である。内馬屋の場合,馬屋の柱は他より腐朽しやすいので,主屋とは構造を切りはなし,柱を容易に取りかえられるようにした例が長野県などにみられる。
武家の馬屋,すなわち書院造の邸宅に設けられた馬屋は,馬をつないでおく立て場,遠侍と呼ばれる座敷と土間の草の間をもつ。《洛中洛外図[zAC25]風》や幕府大棟梁平内(へいのうち)家の伝書《匠明(しようめい)》には,妻入りで桁行3間の馬屋が描かれ,当時もっとも正式のものとされている。立て場は土間でなく板張りで,農家の馬屋のようにません棒を用いず,くつわつなぎ,腹掛けなどをもつ。中世の絵巻などに描かれた武家の馬屋では,猿が飼われているが,これは猿が馬の病気をなおすと信じられたためである。日光東照宮の神厩は,武家の馬屋の形式で造られ,三猿(見ざる,いわざる,聞かざる)その他の猿の彫刻が飾られている。また彦根城の馬屋はL字形の平面をもち,21の小間,端部に馬丁の休息所をもつ大規模なものである。⇒畜舎
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/2571959
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック