木曜日。2001年・2003年製作アニメ、「天使のしっぽ」の二次創作掲載の日です。(当作品の事を良く知りたい方はリンクのWikiへ)。
ヤンデレ、厨二病、メアリー・スー注意
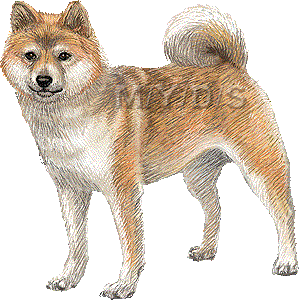
イラスト提供=M/Y/D/S動物のイラスト集。転載不可。
 |
新品価格 |
-茶会-
コポコポコポ・・・
白い磁器のカップを、澄んだ琥珀色の液体が満たしてゆく。
立ち昇る白い湯気に乗って、優しい香りが緩々とたゆらった。
「・・・まさか、お茶にお呼ばれするとは思わなかった・・・。」
目の前に置かれたカップ。
その中で揺れる、自分の瞳と同じ色をした液体。
それを見つめながら、少女は珍しくあっけに取られた声でそう言った。
「お茶をご一緒すれば、初対面の方でもその人柄がよく分かりますから・・・。」
少女の前の席に座したアユミが、自分のカップにも紅茶を注ぎながらそう言う。
「・・・そういうもん?」
「そういうものです。」
いまいち腑に落ちないといった顔の少女に、アユミはキッパリと言い切った。
「・・・天使の考える事って、よくわかんない・・・。」
少女はそう言って、頭を捻る。
白透色のリボンが、羽ばたく様にフルッと揺れた。
「・・・まぁ、こんなこと考えるのって、アユミくらいのもんよね。ねぇ、アカネ?」
部屋の隅に座したミカが、お茶をすすりながら隣のアカネに声をかける。
しかし、返事はない。
「・・・アカネ?」
いぶかしんだミカが、その視線をアカネに向けた。
目の前で湯気を立てるお茶に手もつけず、身じろぎ一つせず、アカネはその瞳をじっと眼前のテーブルへと向けていた。その瞳にらしくもない暗い輝きを乗せて、テーブルに座する黒衣の少女を、ただ一心に――
「アカネ!」
「え?あ、な、何?」
少々語気を強めた呼びかけに、やっと反応を示したアカネ。
彼女に、ミカが顔を寄せてくる。
「あんた、なんかおかしいわよ?大丈夫なの?」
「あ・・う、うん。な、何でもないよ・・・。ちょっと、ボウッとしちゃっただけ・・・。」
「・・・そう?」
「うん。」
なおも心配気な視線を向けてくるミカに、アカネはそう言ってニコリと形ばかりの笑みを向けて見せた。
少女の白い両手が、カップを包む様にしてそっと持ち上げる。
薄い唇の間からぺロッと出た舌が、揺れる琥珀の液体を味見する様にチロリと舐めた。
「・・・渋っ!!」
途端、顔をしかめてそう呟く。しかし、アユミが見つめているのに気づくと、慌ててその顔を引っ込める。そして、何事もなかった様に紅茶を口に含んで―
「~~~~~!!!」
含んだまま、固まってしまう。
どうやら、飲み込めないらしい。
口を真一文字に引き結んだまま、目を白黒させている。
その顔が、何だか苦い薬を飲まされてる子供の様で、なんとも情けない。
「・・・ストレートは、苦手ですか?」
様子を見ていたアユミにそう尋ねられると、ブンブンと首を振る。
どうも、自分の味覚が子供っぽいと思われるのが嫌らしい。
しかし、いくら意地をはった所でその顔が文字通り「苦虫を噛み潰して」いるものだから、説得力なぞまるでない。
「・・・・・・。」
アユミは無言で、角砂糖の入った小ビンを少女の方に押しやる。
必死の形相でようやく口の中の紅茶を飲み下した(かなり力んで飲み込んだらしく、飲み込む時の「ゴクン」という音がミカやアカネの所まで聞こえた。)少女は、それを見ると慌てた様子で手を伸ばした。
もどかしげにビンの蓋を開け、つかみ出した角砂糖を二、三個まとめて口に放り込む。
ガリガリ、シャリシャリと噛み砕く音。
やがて、細い喉が今度はコクンと控え目に鳴った。
それでやっと人心地がついたのか、少女はほっとしたように溜息をついた。
それを見届けたアユミが、改めて言う。
「・・・無理せずに、砂糖お入れになったらいかがです?」
「・・・べ、別にわたしは、渋いのなんか・・・」
「一口飲む度にそんな事をやっていては、ちっとも話が進みませんが?」
「う・・・。」
少女はしばし、涼しげな顔で自分の茶をすするアユミと、諸悪の根源である紅茶にそれぞれ忌々しげな視線を送る。
しかし、やがて手元の小ビンに手を伸ばすと、角砂糖を一つ二つと紅茶の中に入れ始めた。
「・・・で、ご主人様は何処にいるの?」
紅茶に砂糖を投じながら、おもむろに少女が口を開く。
成り行きを見守っていたアカネとミカが、ハッとその視線をアユミに向ける。
一方、当のアユミは黙ってお茶をすすっていたが、やがてカップを受け皿に置くと、ゆっくりと口を開いた。
「・・・先程も言いましたが、御主人様は今、この町にはいません。」
アユミの言葉に、少女がピクリと眉根を寄せる。
「・・・だから、何処にいるのって訊いてるんだよ・・・。」
少女の言葉に剣呑な響きがこもり、その瞳が薄っすらと朱に染まり始める。
「答える気がないなら・・・」
少女の右袖がユラリと揺れ、その奥でチラリと何かが光る。
それを見たアカネが思わず立ち上がりかけるが、それを目で制し、アユミは言葉を続ける。
「短気は損気と言いますわ。話は最後までお聞きなさい。」
その言葉に、少女はその瞳に剣呑な光を残したまま、とりあえず袖を下ろす。
「御主人様は今、御一人で帰郷されております。誰かさんが出した、宿題の答えを探しに。」
そう言って、アユミは皮肉気な視線を少女に向ける。
「あなたが言い出したことです。よもや、邪魔はしないでしょうね?」
「・・・帰ってる?田舎に?宿題の答えを、探しに・・・?」
それを聞いた少女は一瞬キョトンとした顔をしていたが、やがてその顔が一気に破顔する。
「・・・く・・く・・くふふふふ・・・そっか、そっかぁ!!ご主人様、わたしとの約束、守ってくれるんだぁ!!」
ほんの一瞬前とはまるで別人の様な、喜気と稚気の溢れる笑みが満面に浮ぶ。
それは、湧き起こる幸福感に耐えきれないと言わんばかりの至福の笑顔。
そのあまりの変わり様に、さしものアユミもギョッとする。
「そっかぁ。ご主人様、田舎にいるんだぁ。あそこには、まだ「あれ」がいるからなぁ、ちょっとだけ、つながんなくなっちゃっても、仕方ないかぁ・・・。」
笑い混じりでよく分からない独り言を呟きながら、指を踊る様に動かす。
角砂糖が紅茶に沈む音が、ポチョン、ポチョンとリズミカルに響く。
「ふふ、ふふふ・・・。ご主人様が、わたしの名前、思い出してくれる・・・。ご主人様が、わたしの名前、呼んでくれる・・・。」
ポチョン、ポチョン。弾む音。まるでその心を、代弁する様に。
「・・・一体、幾つ入れる気ですか・・・!?」
しばらく黙って見ていたアユミが、そう言って顔を引きつらせる。
この時点で、小ビンの中の角砂糖の残量は元の三分の一程。
見れば、少女のカップの底には飽和状態になった砂糖がまるで雪の様に厚く積もっている。
「だってこれ、渋いんだもん。」
少女は上機嫌にそう言って、トドメとばかり二,三個分くっついた大きな砂糖の塊をカップの中にチャポンと入れた。
スプーンで軽く掻き混ぜて、口へと運ぶ。カップを傾けると、積もった砂糖がサララと鳴った。
「・・・うん、美味しくなった。」
溶けかけの砂糖をサリサリと噛みながら、少女は幸せそうに微笑んだ。
「・・・納得したのなら、今度はこちらの質問に答えていただきますわ。」
「いいよぉ。わたし、今とってもハッピーな気分だから、何でも答えてあげる。」
激甘の紅茶(というか、もはや「砂糖の紅茶漬け」とでも言った方がより正しい表現と思われる。)をすすりながら、少女はアユミの言葉にあっさりと頷く。
「・・・結構なことです。では、率直にお聞きしますが・・・」
アユミの瞳が、いつになく鋭い光を燈して目の前の少女を見据える。
「・・・あなたの目的は、何です?」
「ご主人様。」
即答して、「何を今更」とでも言いた気な視線を上目づかいにチラリと向ける。
「わたしが欲しいのは、ご主人様だけ。ご主人様と、一緒になるの。だから、ご主人様を貰いに来た。それ意外の事に、興味ない。」
「・・・・・・!!」
サラリと吐き出されたその言葉に、胸の奥底で暗い炎が灯る。
それを感じて、アカネは思わず不快気に顔をしかめる。
その隣では、やはりミカがその頭に青筋を幾つも浮かべ、何やらぶつぶつと物騒な言葉を呪詛の様に呟いていた。
心なしか、立ち昇るオーラで周囲の空気が歪んで見える。
今は場合が場合なので、とりあえずアユミに全権を譲ってはいる。
しかし、本当なら今すぐにでも目の前の小娘の襟首を摘み上げ、そのまま玄関から蹴り出したそうな気配である。
けれど、件の少女はそんな殺気に動じる気配もなく、涼しい顔で紅茶をすすっている。
そして対峙するアユミもまた、ほんの一瞬、その眉をしかめはしたものの、すぐにそれを変らぬ平静の色へとに塗り変えていた。
「・・・あなた、御自分が「悪魔」だということを、自覚してらっしゃいますか?」
それでも、少々険の入った口調でそんな言葉を紡ぐと、少女が少し訝しげな顔をした。
「何なのさ?さっきから、分かりきってることばかり聞いてきて・・・。」
「・・・あなたが御主人様に初めて接した日、御主人様は熱を御出しになられました。」
少女の問いに答えず、アユミは言葉を続けた。
少女の顔が、ピクリとほんの少しだけ強張る。
「ユキさん・・メガミ様から聞きました。あなた達「悪魔」は純然たる「陰」のエネルギーの結晶体。そんなあなた達が生身の人間に直接接すれば、体内に巡る「気」の調和が乱れ、結果、その人間の身体を害し、命を著しく縮めると・・・。」
「・・・・・・。」
少女は黙ったまま、ただじっとアユミを見つめている。
「・・・ほんの十分かそこら、御主人様の近くに「居ただけ」であの有り様です。仮に御望みの通り、あなたが御主人様と一緒になったら、御主人様は一体、どうなってしまわれるのでしょうね・・・?」
「・・・・・・!!」
答えを想像したのか、ミカとアカネが総毛立つ気配が伝わる。
少女は答えず、沈黙したまま。
そして、アユミは厳かに言い放つ。
「・・・お帰りなさい。あなたの居るべき場所へ。どんなに頑張った所で、御主人様はあなたの届かない所に在るのですから。」
「・・・・・・。」
覆ざる、告刑の言葉。
それに、少女は双眸を針の様に細め、手にしたカップの中身をズズッとすする。
唇についた砂糖を、薄朱い舌がぺロリと舐める。
そして、その唇が、ゆっくりゆっくり、三日月に歪んだ。
「・・・何が可笑しいんですの?」
怪訝そうな顔のアユミに薄笑いを向けながら、少女はカチャリとカップを受け皿に置いた。
「御高説どうも。御礼に、今度はわたしが語ってあげる。」
そう言って右手を上げると、教鞭で拍子でも取る様にクルクルと人差し指を回し始めた。
「確かに、わたし達悪魔の身体は、極めて純度の高い「陰」の気の結晶で出来ています。そして、そこから発せられる純度100%の「陰」の気が人間の様な陰陽両方の気を持つ現世の生き物に当たると、体内の気のバランスを崩して、肉体や魂魄を著しく損壊させちゃうのも、事実です。つまり、あなたの言った事は全部正解。ここまで100点。メガミから貰った知識を、ちゃんと理解していらっしゃる。あったまイー!!パチパチパチ。」
そう言って、わざとらしく手を叩く。
あからさまに小馬鹿にした口調に、さしものアユミも不快気に眉根を寄せる。
「・・・でもね、そっから先がいけないねぇ。せっかくそこまで知識として得たのに、何でそこで止めちゃうの?得た知識は、そこからさらに自分で展開させなくちゃ。余所から得た知識をただ脳味噌に張りつけるだけじゃ、本当の「智」の獲得とは言えないよ?はい、減点。」
言いながら、赤ペンでバツでもつける様にピッと人差し指で宙を弾く。
「わたし達「悪魔」が人間に接すると、放つ「陰」の気が体内の気の調和を乱しちゃうことは、さっき言った通り。でもね、それなら、何で「天使」だと人間は平気なんでしょう?」
「え・・・?」
その言葉にアユミのみならず、端で聞いていたアカネやミカも一瞬呆気にとられる。
考えた事すらないことである。何しろ、彼女達が悟郎の元に来てからすでに一年と半年近くが経つが、そんな異変が悟郎の身に起きたことなど、一度もなかったのだから。何気に過ぎていく日常に、抱く疑問などある筈もない。
「・・・考えたこともない?」
案の定と言わんばかりに、面白げに目を細める。
「考えてもごらんよ?体内の「陰陽」の調和が崩れて身体や魂魄の崩壊を起こすっていうのなら、それは「陰」に傾いても、「陽」に傾いても同じだと思わない?冬の木枯らしは花を枯らすけど、夏の日照りもやっぱり、花を枯らすんだから。なのに何で、人間の身体は純粋な「陰」の存在である悪魔にだけ過敏に反応して、純粋な「陽」の存在である天使には「寛大」なんだと思う?」
理を語り、それに連なる真理を紐解き、そして悪魔は天使に向かってクックッと笑う。それは、智を知る者が、知らぬ者に向ける嘲笑。酷く、癇に障る響き。
「簡単だよ。人間は元々、「陽」の側に重きを置いて生活を営む生き物なんだから。陰陽両得の生き物は、とても不安定だけど、その分広くて柔軟な適応性も持ち合わせるの。「陽」と「陰」、それぞれの生活の場に重きを得る側に合わせて、その身体はそれにより馴染む様に「調整」される。例えば同じ「魚」という種でも、海の魚が海水に、川の魚が淡水に、それぞれ適合した生理を持てるのと同じ。だから、人間みたいに「陽」の側に調整された生き物は「そっち」側の変化に対しては強い耐性を持てる。その反面、そういう風に「調整済み」な分、今度は逆方向への急激な変化には、酷く脆くなっちゃうわけ。ね、簡単な理屈でしょ?」
一句一句を噛み締める様に、それでいてこちらの無知を嘲る様な調子で語る。
その様子を、アユミはただ黙って見つめる。
(・・・なるほど、そういうことですか・・・)
ここにきて、アユミは気づいた。
少女がこんなにも丁寧に、けれどここで話すべき事柄とは少々焦点のずれた高説を述べるのは、自分の智をひけらかして悦に浸るためではない。
これは、自分自身の「計画」を推敲するための行為。それを成す為の理論をもう一度反芻し、さらに絶対の確信を得んが為のもの。
それをわざわざ慇懃無礼な講義の形を借りて行うことで、こちらに対して精神的にも優位に立とうとしているのだと、アユミは判断する。
何しろ、敵対する相手に知恵で上回られるということは、何気に結構なプレッシャーになるものだから。
(―危うく、「飲まれる」ところでしたわ・・・。ただ感情にまかせて振舞うだけの子供かと思っていましたが、結構、いえ、かなり賢しいですのね・・・。)
想定以上に、「怖い」相手。アユミはそう、評価を下す。
(そう言えば、話術や心理戦は悪魔の得意分野っていうのは、昔話での定番でしたっけ・・・。)
そう考えながら、改めて自分の心に喝を入れる。これ以上、相手の話術に飲まれない様に。
「・・・・・・。」
そんなアユミの様子を見止めた少女の顔から、ふと例の小馬鹿にした表情が消えた。そして、ガラリと変った口調で一言。
「飲まれてくれないね?あなたには、この手は効かないか。」
「あら、ビンゴでしたか?」
少女の言葉に、アユミはさらりと答える。
「途中までは引っかかりそうでしたが、まぁ、見下す表情なんかが少々わざとらしかったですから・・・。話術はともかく、表象の演技はまだ、「修行の余地有り」ですわね?はい、減点。」
そう言って、人差し指でバツをつける様に宙を弾く。
ムッとする少女を見て、「先ほどのお返しですわ。」とアユミは軽く笑って見せる。
傍らで、話について行き損ねたアカネとミカが、ポカンとして顔を見合わせた。
少しの間の後、回し過ぎた舌を湿らす様に、残っていた紅茶を一息に空けると、少女は再び話し始めた。
「・・・まぁ、裏の策謀うんぬんは別として、今話したこと自体はホントの事だよ。そういう理由があるから、悪魔は現世で人間と添い遂げることは出来ない・・・。確かにそれは、揺るがし様のない、この世の理(ことわり)・・・。でもね・・・」
カップの底に残った砂糖を一さじスプーンですくい、ぺロリと舐める。
「・・・知ってる?理を乱し、壊すのって悪魔の十八番だって事・・・。」
カップの中から、上目づかいに見上げた瞳がボウッとほの朱い光を放つ。
その様に、アユミはかすかに背筋が泡立つのを感じた。
続く
タグ:天使のしっぽ
【このカテゴリーの最新記事】

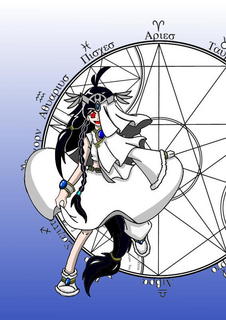





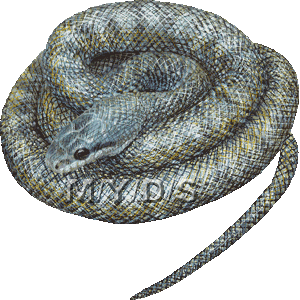

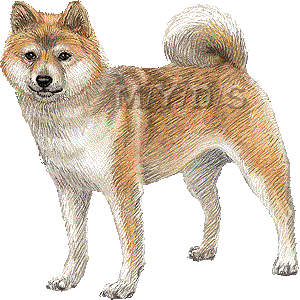
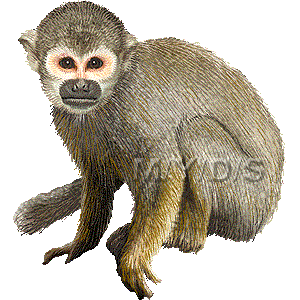



.jpg?2023-01-2212:27:19)
