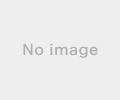| 70�Ń{�P��l�A110�܂Ō��C�Ȑl �y�f�̗͂Ŕ]���g�̂�����Ȃɕς��I [ �ߌ����j ] ���i:1,650�~ |
�E�������l�̂ɓłł����B
�E�����َq���l�̂ɓłł����ƃA�����J�l�����������
�i�A�����J�ł́u�����ƍ�������v���i��ł���v(P28)
���Ȃ����b���]�̓����ɏd�v�Ȃ̂�(P140)
1.���b�͐_�o�זE�₻�̈ꕔ���L�т�����Ƃ�������̎听���ł��邱��
2.���b�̓~���G����i����j�̎听���i80%�j�ł��邱��
�@�]���ɂ͂P�O�O�O�����̐_�o�זE�����݂��܂��B�]�Ŕ����������͓d�C�V�O�i���ƂȂ��Ď����Ƃ����P�[�u����ʂ��āA�]�̕ʂ̉ӏ��ɑ����܂��B���̃P�[�u�����Ă���̂��~�G������Ƃ����قƂ�ǎ��b�łł�����Ȃ̂ł��B
�@�����ǎ��Ȏ��b���s������~�G������͔����Ȃ�A�d�C�V�O�i���͘R�d���܂��B���̂��ߐ_�o�`�B�����̏��̓`���X�s�[�h�͗����A����ɏ��͓`���Ȃ��Ȃ�܂��B
�@�d�C�V�O�i���́A�_�o�זE�����_�炩���Ɠ`���₭���Ȃ�܂��B�_�o�זE���̂V�O���͎��b�i�c��̂Q�O���͂���ς����A�T���̓R���X�g���[���A�T���̓r�^�~���d�j�łł��Ă��܂��̂ŁA�_�炩���͎��b�̎��ō��E����܂��B
�@�܂�A�悢���b�͏_��Ȕ]�_�o�זE�����A�������b�͍d������̂œd�C�V�O�i���́A�`���ɂ����Ȃ�A�]�͂ǂ�ǂ����̂ł��B
�@�]�̒��ɂ͐��������Ǝ��b���U�O��������ƌ����Ă��܂��B���̂قƂ�ǂ�_�o�זE������߂Ă���̂ŁA���̍זE�����`�����鎉�b�̎��̗ǂ��������d�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�����b�͖O�a���b�_�A�ꉿ�s�O�a���b�_�A�����s�O�a���b�i�I���K�R�ƃI���K�U�j������܂����A�̓��ɓ����������̎��b�͑̓��œ]������邱�Ƃ͂Ȃ��A�̓��ɓ����������זE����זE�ɂȂ�̂ł��B
�@���̂��߁A�H���Őۂ����b�̓��e�̗ǂ������������N�̕�����ڂł���A�F�m�ǂ̕�����ڂƂȂ�܂��B
���F�m�ǂɂȂ�R�̈������b�iP141�j
�u�_���������b�v�u�g�����X���b�_�v�u���m�[���_���b�v
���K�{���b�_�ɂ̓I���K�R�i��-���m�����n��j�ƃI���K�U�i���m�[���_�n��j�̂Q������܂��B
���ꂪ�P�P�Ƒ̓��Ƀo�����X�悭�����Ă���Ζ��͂���܂���B���Ƃ��I���K�R�ƃI���K�U�̔䂪�P�X�Ƃ����悤�Ȑۂ���̏ꍇ�A�̒��͈����ȂĂ����܂��B
�I���K�U�ŋC��t���������̂́A�T���_���A�哤���A�S�}���A�R�[�����A�q�}�������A�x�j�o�i���Ȃǂł��B�����̐ۂ肷���ɋC��t���܂��傤�B
������h�����߂ɂȂɂ���Ȃ̂́A�y�f�ƃI���K�R�̂���DHA���O����ۂ邱�Ƃł��B
���a�C�A�V���A�����A�����̌���(P59)
�@�_��
�A����
�B���ǖƉu�̒ቺ
�C�y�f�s��
�D�������b�̐ێ�
�@�H�ו��̏�����ċz�̎��ɔ������銈���_�f���זE���_��������B�������A���̕��s�ł��_������B
�@�ʏ�A�����͈��S�ŋɏ��ȉh�{�f������ʂ��A�傫�ȕ��q�⓾�̂̂���Ȃ����͎̂Ւf����̂����A���ǂ�����ƌ����J�����悤�ȏ�ԂɂȂ�A�ӂ��Ȃ�Ւf�����ׂ����̂��ʂ蔲����B�i���[�L�[�K�b�g�j
�@�ٕ������t�ɐN������ƁA�̂̂��������Ŗh��Ԑ����Ƃ��A�U�����͂��܂�B���ꂪ�A�����M�[�����ł��B�S�g�ɂ���݂┭�]�A�M���ł�̂́A���̉e���ł��B������ԕ��ǁA�A�g�s�[���畆�������̕��s���������Ǝ��͍l���Ă��܂��B
�@���̕��s�́A�̑��̍זE���_�������A�̑��̉�ŋ@�\��ቺ�����A���t�ɓőf�����ʂ������Ă����B
�@���̓őf�̑�\���u����ς����̂�����v�ƌ����钂�f�c�����ł��B���t�ɓ���̂͂������ʂŁA�����Ɏ��ɂȂ���킯�łȂ����A�ғłł��B
�����̕��s�͔]�ɂ��_���[�W��^����(P73)
�@�]�̐_�o�זE�ƒ��̐_�o�זE�͔������ʂ������ŁA����̐_�o�ǂł��B���̂��߁u���̔]�v�ƌ����܂��B�������A�C�\�M���`���N�Ȃǂ̐����͔]���Ȃ��A���ōl���Đ����Ă��邩��A���́u���̔]�v���Ǝv���Ă��܂��B
�����s�����錴��(P75)
�@�H�ׂ���
�A����������ς����̐H�߂�
�B����������P���Y�������̐H�߂�
�E����ς����̓A�~�m�_�ɕ�������邪�A�A�~�m�_�߂�ꏊ�̗e�ʂ��������A�����ɂ��ӂ�Ă��܂��B���̂��߁A����ς����𑽂��ۂ�ƒ������s�̌����ɂȂ�B�����ȑ�w�̒����ɂ��u�����P���Q�ȏ�H�ׂ�l�͎��S�����Q�{�ɂ͂ˏオ��v
�E�|�e�g�`�b�v�X�ɂ́A��ʂ̃A�N�����A�~�h�i���������j���܂܂��B
�E�Ă��A�u�߂�A�g����A�����Ĉ��͓���g���������œ������N����B
�E�����̋��낵���̂́A�P�O�����炢�͕������ꂸ�ɋz������A�O.�V���͍זE�ɒ~�ς����B��x�~�ς����Ɣr�o����ɂ����B
���P���Y�������i�P���j�̊Q(P85)
�@�P���Ƃ̓u�h�E���A�ʓ��A�V�����Ȃǂ̓��ނ̂��Ƃł��B
�@�V�����̓������H�ו��́A�ݒ����ň��ʋۂ�^�ہi�J�r�j�̃G�T�ɂȂ�A�����̈����ۂ̔ɐB�𑣐i�����܂��B
�@�܂��A�V�����͕��q�����������߁A�݂ŕ������ꂸ�ɂ��̂܂܌��t���ɐN�����܂��B
�@�����đS�g�𗬂�A�^�ۂ̃G�T�ƂȂ�����A���ʋۂ̃G�T�ƂȂ����肵�܂��B
�@���ꂪ�������ƂȂ�A�S�g�̉��ǂ������N�����܂��B
�@���Ƃ��A�G���B����Ђ��̎��A�b����̎��Ȃǂ̉��ǏǏ�́A�V�����𑽂��H�������Ƃ���N����ꍇ���悭����܂��B
�@�������A�u�h�E����ʓ���P�Ƃł��ׂĂ��A���l�̏Ǐ�������N�����܂��B
���y�f�Ƃ͂Ȃɂ�(P120)
�@�傫���킯�āu�����y�f�v�Ɓu��Ӎy�f�v�ł��B
�@�����y�f�́A�H�ו��̏����E�z���Ɏg����y�f�ł��B
�@���Ƃ��A���̂Ȃ��̑��t�ɂ̓A�~���[�[�Ƃ����y�f���܂܂�Ă���A�Y�����������A�X���ł̓��p�[�[�����b�����A�����ł̓X�N���[�[���V���������܂��B
�@���̑��ɂ��A���v�łQ�S��ނ̏����y�f������A���̍y�f�̗͂���ĐH�ו������X�ƕ������A�z�����Ă����킯�ł��B
�@�����ۂ��A��Ӎy�f�́A�l�̂�����A�������̂Ɏg����y�f�ł��B
�@�����E�z�����ꂽ�������G�l���M�[�Ɋ�������A�������זE���C��������A�L�Q�ȓŕ���V�p����r�������肵�܂��B
�@�l�Ԃ������邽�߁A�l�̂𐳏�ɓ��������߂ɍs���Ă���n���Ȋ����́A���ׂčy�f�̗͂ɂ���Đ��藧���Ă���̂ł��B
���V���Ƌ��ɍy�f�̐��Y�ʂ͌����Ă���(P121)
�@�����y�f�Ƒ�Ӎy�f���A�̂̒��ɏ\���ɂ����Ԃ��ƁA�זE�͂������蓭�����߁A�V���̃X�s�[�h�͒x���Ȃ�܂��B
�@�t�ɁA���̂Q�̍y�f�������Ă���ƁA�זE�͗��A���܂��܂ȕa�C�ɂȂ�₷���A�V�����������܂��B
���y�f����������O������������(P123)
�E�y�f�������܂܂�Ă���H�ނ�ۂ�
�@���̖��ʕ��A���̋��A�[����Е��A�L���`�A���݂��Ȃǂ̔��y�H�i��
�i���̓��A�`�[�Y��[�O���g�ɂ��y�f���܂܂�邪�A�̂ɑ��Ă̊Q�������j
�E�����̑P�ʋۂ́A�H�����E�������Ĕ��y�����Ȃ��瑝�B���Ă����܂��B
�@���̎��ɂ������ʂ̍y�f�݂����Ă���̂ł��B
�@���̖��ʕ���H�ׂ邱�Ƃ͍y�f�𑝂₷���ƂɂȂ�܂��B
�@�y�f�͔M�Ɏア�̂ŁA���M���Ă͂��߁i���M���Ă��H���@�ۂ⑼�̉h�{�f�͎c��܂��B
���ߐH�ɂ���čy�f�͂ǂ�ǂ���(P125)
���̂R���y�f�̃��_����
�E�H�ׂ���
�E����������ς����̐H�ׂ���
�E����������P���Y�������̐H�ׂ���
���]�̂Ȃ��ł́A���X�A����ς����̃S�~���łĂ��܂��B�����|���i��Ӂj����̂��y�f�̖�ڂ̂ЂƂł��B�iP128�j
�����������邽�߂̐H�̂S�僋�[��(P162)
�ȉ������Ȃ��Ƃ��R�A���邢�͂T����Ă݂܂��傤
�@ �A�����̂��̂�H���̒��S�ɂ���
�A�u���H�v�𒆐S�ɂ���i���H�܊��E���M�H�܊����炢�j
�B�u���H�v����{�Ƃ���
�C���H�͐H�ׂȂ��i���l�ȍ~�j
�P�P�僋�[��
�D���H����{�����A�H�ׂ�Ȃ琶�̖���ʕ��ɂ���
�E�_���_���H��ԐH�����Ȃ�
�F��H��H�ׂĂ����ɐQ��̂͌���
�G�f�H������
�H���Ɩ�̎�H�͕����Y�������ɂ���
�I�H�����̔��y�H�i��H�ׂ�
�J�悭����ŐH�ׂ�
�y���̃J�e�S���[�̍ŐV�L���z
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image