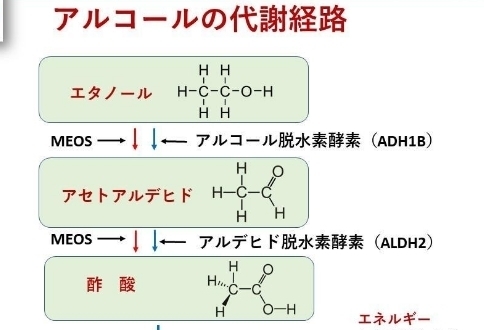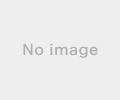| 老いる意味 うつ、勇気、夢 (中公新書ラクレ 718) [ 森村 誠一 ] 価格:924円 |
私の友人で、入院期間が長引くにつれ、病気は快方に向かっているにもかかわらず、次第に無気力になっていったケースがあった。
そこで私はその彼にスケジュール表をつくることをすすめた。
「入院しているのだから、予定などは何もない」というので、「何時になったら売店を覗くとか、何時になったら病院の周辺を散歩するとか、そういうことでもいいんだ」と言って聞かせた。それでも乗り気でないようだったので、私のほうでスケジュール表を作って渡しておいた。
そてに従って行動するようになった彼は少しずつ気力を取り戻していったのである。
一日の自分のリズムができ、やるべきことがあれば、それだけで張り合いが生まれる。
老後に自由な時間が持てるようになると、縛りがない分、いい加減な生活になりやすい。
易に流されるのが人間である。
ダラダラとした生活を続けていると、やる気も持てず、朝起きる気力もなくなっていく。無気力、自墜落にならないためにもスケジュールによって自分を律するのがいいわけである。(P146)
スケジュールに縛られすぎたくない人は、ある程度アバウトな時間配分にしておくのがいい。あまり細かく組んでしまうと、それにあわせなければならないという焦りから気持ちに余裕がなくなり、スケジュールの奴隷になってしまうからだ。かえってストレスになる。(P151)
■曲がり角になる70代(P129)
70代になると、失っていくものの多さが実感されてくる。体力、気力、記憶力、人脈などといったものがそうだ。
そうした事実を受け止め、克服するのが70代のテーマである。
思うように動けなくなってきたと感じたなら、少しでも運動機会を増やすようにする。内臓疾患などが見つかったなら、しっかりと治療するか、それ以上悪くなっていかないようにケアする。記憶力があやしくなってきたなら、認知症が他人事ではないのを自覚して、ボケ防止になることを考える。友人知人の死が増えてきた時には、悲しみを乗り越えるだけでなく、新たな交流関係をつくっていく。
つらいことが増えていっても、仕方がないとあきらめてしまわず、先細りになっていかないように手を打つことでが大切になる。
■緑内障と最高のコーヒー(P178)
60代の頃、緑内障を発症する可能性があると医師に指摘された。予防法を聞くと、「目を酷使しないこと」眼圧を高めないように刺激性の強い飲食物を摂らないこと」だといわれた。「カフィンを控えろ」といわれたのも問題だった。大のコーヒー好きで、当時は一日に何倍もコーヒーを飲んでいた。しかし、視力と引き替えにできない。仕方なく一日一杯を目安にすることにした。
一日一杯となると、豆も厳選するようになり、よりおいしさを追及するようになる。すると、香りや味をより深く楽しめるようになってきたのである。
■老いるに従い「現状維持」を考える(P154)
いまより体力をつけるとか、より健康になろうと目指すのではなく、老いるに従い「現状維持」を考えて、そのためのメンテナンスをしていく。
筋肉などは年齢とともに退化していくので、ある程度食い止めるために最低限の運動を心がけておく。
ある程度の距離は歩ける、階段を上がれるというなら、それでいい。
バリアフリーに頼りすぎないほうがいい。筋肉を退化させないためにも、ケガなどに注意しながら無理のない範囲で階段を使うようにするのも大切である。そういう心がけが筋力維持につながる。
■楽しみながらボケを予防する(P156)
自転車に乗るのはボケ防止に効果があるというのは脳の専門医から聞いたことだ。自転車に乗っていれば、自然に周りに注意をはらうことになるので、それがいいわけである。前後左右に目をくばり、車や歩行者の動きを確かめながら瞬時の判断をしていく。
視覚、聴覚、反射神経。それに加えてバランスを取るためにも脳は働く。それぞれの機能を同時に働かせるため、脳が活性化するのである。
見知らぬ町を一人で歩いていると不審の目で見られることもあるが、自転車だと不思議にそれがない。
自転車事故は増えているので、その点での注意は必要だ。自分が車にはねられたりしないようにするだけでなく、歩行者にも迷惑をかけないようにしなければならない。