新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2019年03月29日
映画「ブリッジ・オブ・スパイ」東西冷戦の捕虜交換劇
「ブリッジ・オブ・スパイ」(Bridge of Spies)
2015年 アメリカ
監督スティーヴン・スピルバーグ
脚本マット・チャーマン
イーサン・コーエン
ジョエル・コーエン
撮影ヤヌス・カミンスキー
〈キャスト〉
トム・ハンクス マーク・ライランス
エイミー・ライアン
第88回アカデミー賞/ニューヨーク映画批評家協会賞助演男優賞(マーク・ライランス)

東西両陣営
1945年に第二次世界大戦が終結し、戦勝国の首脳が集まったヤルタ会談から、戦後の世界は分割協定へと動き始めます。
その主要な対立軸となったのが、超大国となったアメリカを代表とする自由主義諸国と、ソビエト連邦を盟主とする社会主義国でした。
アジアでは朝鮮半島。ヨーロッパは主にドイツが対象となって、北と南、あるいは西と東に分断。アメリカ的自由主義とソビエトの社会主義的イデオロギーは全ヨーロッパを巻き込み、政治的・経済的にも異なった価値観を持った東西ヨーロッパへと変容してゆきます。
アメリカとソ連の対立は政治のみならず、軍事的にも激しく対立。
西側の北大西洋条約機構(NATO)に対して東側のワルシャワ条約機構が生まれ、米ソの核ミサイルの開発と配備は一触即発の緊張状態へと突き進んでゆきます。
こうした現状をイギリス人の作家でジャーナリストのジョージ・オーウェルは1947年に、冷たい戦争「冷戦」と呼びました。





ジェームズ・ドノヴァン(トム・ハンクス)は法律事務所で保険裁判などを担当する弁護士。
彼はある日、ソ連の諜報員として逮捕されたルドルフ・アベル(マーク・ライランス)の国選弁護人を依頼されます。
時は1957年、東西冷戦の真っ只中。
ドノヴァンは刑事事件から遠ざかっていることや、敵国人の弁護を引き受けた場合の社会的非難、勝つ見込みのない裁判であることを考えると不安を覚えますが、弁護士としての職務に順じ、引き受けることにします。
拘置所を訪れ、アベルと面会したドノヴァンは、諜報員でありながら芸術家としての顔を持つアベルの落ち着いた物腰や、死を恐れず、国家に忠誠を尽くそうとする態度に友情にも似た感銘を受け、裁判での無罪判決に奔走しますが、陪審員の評決は有罪。
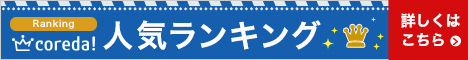

死刑だけは免(まぬが)れさせようとするドノヴァンは判事にかけあい、近い将来、スパイの交換があった場合の人質としてアベルの減刑を要求。
ドノヴァンの粘り強い交渉は功を奏し、アベルの死刑判決は退けられて懲役刑が確定します。
一方、パキスタンのアメリカ軍空軍基地ではU-2偵察機によるソ連への偵察飛行が行われようとしており、基地から飛び立ったパイロットのひとりフランシス・ゲーリー・パワーズ中尉はソ連のS-75地対空ミサイルの攻撃を受けて撃墜され、ソ連の捕虜となってしまいます。
さらに、ベルリンでは東西ドイツを二分する壁の建設が進められ、アメリカ人学生で経済学を専攻するフレデリック・プライヤー(ウィル・ロジャース)は、恋人と一緒に東ドイツから西ドイツへ逃れるべく、壁建設の混乱に乗じて脱出を試みますが、ドイツ軍兵士に止められ、捕らわれてしまいます。

ドノヴァンの捕虜交換の予想は期せずして的中した形になり、ソ連側のアベルと、アメリカ側のパワーズとプライヤーの交換交渉をするべくドノヴァンは東ベルリンへ向かいますが、CIAとKGBが入り乱れて暗躍する中で交渉は難航。
CIAの要求はアベル対パワーズの一対一の交換だという主張に対し、ドノヴァンはあくまでパワーズとプライヤーも含めた一対二の交渉を主張。
持ち前の粘り強さでドノヴァンは捕虜交換の交渉を続け、アベル対パワーズ、そしてプライヤーも含めた一対二の交渉が実現します。
交換場所はドイツ・メクレンブルクからブランデンブルク、ベルリンへと流れるハーフェル川に架かるグリーニッケ橋。
東西両陣営が対峙する橋の上で西側からはアベル、東側からパワーズの姿が現れますが、もう一人現れるはずのプライヤーの姿が見えないまま、捕虜交換が進められようとしますが、ソ連側の意図を察したドノヴァンはギリギリまで交渉を制止、交渉は決裂かと思われましたが………。


見応え十分の捕虜交換ドラマ
題名からは、暗躍するスパイアクション映画という印象を受けますが、アメリカとソ連の諜報員の交換が行われた史実をもとに、冷戦という重い空気感の漂う時代の中で、国家やイデオロギーを超えた人間同士の信頼や友情を描いた重厚なヒューマンドラマであるといえます。
特に、アカデミー賞を始めとして数々の賞を総なめにした助演男優賞受賞のマーク・ライランスの演技は素晴らしく、諜報活動をする傍(かたわ)ら、画家としての卓越した才能を持っているルドルフ・アベルを物静かな芸術家として表現。
拘置所の中で、ドノヴァンが差し入れたと思われるラジオから流れるショスタコーヴィチの音楽を、乾いた心の中に染み込んでいくように聴き入る姿、少年時代の体験をドノヴァンの置かれた立場と重ね合わせて語る場面からは、物静かな芸術家であると同時に強い信念の持ち主であり、ドノヴァンに対する信頼が芽生え始める印象的なシーンでした。
冷戦時代は破壊的な戦争が起きることもなく、1991年のソ連崩壊により冷戦は終結しましたが、スパイの交換が行われたグリーニッケ橋が東西冷戦の象徴として観光地化されているように、冷戦時代を懐かしむ声があるのは、失われてしまった、あるいは失われつつある古き時代の家族としての在り方、友情、人間同士のつながりが強く残っていた時代であり、「ブリッジ・オブ・スパイ」はそういったものをも含めて描いた傑作です。





2015年 アメリカ
監督スティーヴン・スピルバーグ
脚本マット・チャーマン
イーサン・コーエン
ジョエル・コーエン
撮影ヤヌス・カミンスキー
〈キャスト〉
トム・ハンクス マーク・ライランス
エイミー・ライアン
第88回アカデミー賞/ニューヨーク映画批評家協会賞助演男優賞(マーク・ライランス)

東西両陣営
1945年に第二次世界大戦が終結し、戦勝国の首脳が集まったヤルタ会談から、戦後の世界は分割協定へと動き始めます。
その主要な対立軸となったのが、超大国となったアメリカを代表とする自由主義諸国と、ソビエト連邦を盟主とする社会主義国でした。
アジアでは朝鮮半島。ヨーロッパは主にドイツが対象となって、北と南、あるいは西と東に分断。アメリカ的自由主義とソビエトの社会主義的イデオロギーは全ヨーロッパを巻き込み、政治的・経済的にも異なった価値観を持った東西ヨーロッパへと変容してゆきます。
アメリカとソ連の対立は政治のみならず、軍事的にも激しく対立。
西側の北大西洋条約機構(NATO)に対して東側のワルシャワ条約機構が生まれ、米ソの核ミサイルの開発と配備は一触即発の緊張状態へと突き進んでゆきます。
こうした現状をイギリス人の作家でジャーナリストのジョージ・オーウェルは1947年に、冷たい戦争「冷戦」と呼びました。

ジェームズ・ドノヴァン(トム・ハンクス)は法律事務所で保険裁判などを担当する弁護士。
彼はある日、ソ連の諜報員として逮捕されたルドルフ・アベル(マーク・ライランス)の国選弁護人を依頼されます。
時は1957年、東西冷戦の真っ只中。
ドノヴァンは刑事事件から遠ざかっていることや、敵国人の弁護を引き受けた場合の社会的非難、勝つ見込みのない裁判であることを考えると不安を覚えますが、弁護士としての職務に順じ、引き受けることにします。
拘置所を訪れ、アベルと面会したドノヴァンは、諜報員でありながら芸術家としての顔を持つアベルの落ち着いた物腰や、死を恐れず、国家に忠誠を尽くそうとする態度に友情にも似た感銘を受け、裁判での無罪判決に奔走しますが、陪審員の評決は有罪。
死刑だけは免(まぬが)れさせようとするドノヴァンは判事にかけあい、近い将来、スパイの交換があった場合の人質としてアベルの減刑を要求。
ドノヴァンの粘り強い交渉は功を奏し、アベルの死刑判決は退けられて懲役刑が確定します。
一方、パキスタンのアメリカ軍空軍基地ではU-2偵察機によるソ連への偵察飛行が行われようとしており、基地から飛び立ったパイロットのひとりフランシス・ゲーリー・パワーズ中尉はソ連のS-75地対空ミサイルの攻撃を受けて撃墜され、ソ連の捕虜となってしまいます。
さらに、ベルリンでは東西ドイツを二分する壁の建設が進められ、アメリカ人学生で経済学を専攻するフレデリック・プライヤー(ウィル・ロジャース)は、恋人と一緒に東ドイツから西ドイツへ逃れるべく、壁建設の混乱に乗じて脱出を試みますが、ドイツ軍兵士に止められ、捕らわれてしまいます。

ドノヴァンの捕虜交換の予想は期せずして的中した形になり、ソ連側のアベルと、アメリカ側のパワーズとプライヤーの交換交渉をするべくドノヴァンは東ベルリンへ向かいますが、CIAとKGBが入り乱れて暗躍する中で交渉は難航。
CIAの要求はアベル対パワーズの一対一の交換だという主張に対し、ドノヴァンはあくまでパワーズとプライヤーも含めた一対二の交渉を主張。
持ち前の粘り強さでドノヴァンは捕虜交換の交渉を続け、アベル対パワーズ、そしてプライヤーも含めた一対二の交渉が実現します。
交換場所はドイツ・メクレンブルクからブランデンブルク、ベルリンへと流れるハーフェル川に架かるグリーニッケ橋。
東西両陣営が対峙する橋の上で西側からはアベル、東側からパワーズの姿が現れますが、もう一人現れるはずのプライヤーの姿が見えないまま、捕虜交換が進められようとしますが、ソ連側の意図を察したドノヴァンはギリギリまで交渉を制止、交渉は決裂かと思われましたが………。
見応え十分の捕虜交換ドラマ
題名からは、暗躍するスパイアクション映画という印象を受けますが、アメリカとソ連の諜報員の交換が行われた史実をもとに、冷戦という重い空気感の漂う時代の中で、国家やイデオロギーを超えた人間同士の信頼や友情を描いた重厚なヒューマンドラマであるといえます。
特に、アカデミー賞を始めとして数々の賞を総なめにした助演男優賞受賞のマーク・ライランスの演技は素晴らしく、諜報活動をする傍(かたわ)ら、画家としての卓越した才能を持っているルドルフ・アベルを物静かな芸術家として表現。
拘置所の中で、ドノヴァンが差し入れたと思われるラジオから流れるショスタコーヴィチの音楽を、乾いた心の中に染み込んでいくように聴き入る姿、少年時代の体験をドノヴァンの置かれた立場と重ね合わせて語る場面からは、物静かな芸術家であると同時に強い信念の持ち主であり、ドノヴァンに対する信頼が芽生え始める印象的なシーンでした。
冷戦時代は破壊的な戦争が起きることもなく、1991年のソ連崩壊により冷戦は終結しましたが、スパイの交換が行われたグリーニッケ橋が東西冷戦の象徴として観光地化されているように、冷戦時代を懐かしむ声があるのは、失われてしまった、あるいは失われつつある古き時代の家族としての在り方、友情、人間同士のつながりが強く残っていた時代であり、「ブリッジ・オブ・スパイ」はそういったものをも含めて描いた傑作です。

2019年03月21日
映画「ホロコースト-アドルフ・ヒトラーの洗礼-」法王庁の沈黙
「ホロコースト-アドルフ・ヒトラーの洗礼-」(Amen.) 2002年
フランス/ドイツ/ルーマニア/アメリカ
監督コスタ=ガブラス
脚本コスタ=ガブラス
原作ロルフ・ホーホフート「神の代理人」
撮影パトリック・ブロシェ
〈キャスト〉
ウルリッヒ・トゥクル マチュー・カソヴィッツ
ウルリッヒ・ミューエ
![LOrdre-et-la-Morale-Mathieu-Kassovitz-et-Ulrich-Tukur-dans-Amen[1].jpg](/2810/file/LOrdre-et-la-Morale-Mathieu-Kassovitz-et-Ulrich-Tukur-dans-Amen5B15D-thumbnail2.jpg)
原題は「Amen」。
キリスト教世界における祈りの言葉の後に唱える言葉が原題となっています。
大体において祈りの言葉は「あなた(神)の王国が来ますように」、または、主(神)に対する感謝の言葉で締めくくられることが多いのですが、その後に、是認の言葉として「アーメン」が唱えられ、そうありますように、そうです、といった意味を持ちます。
原題から判るように、「ホロコースト-アドルフ・ヒトラーの洗礼-」は宗教をテーマとして、バチカンがナチス・ドイツのユダヤ人迫害に対して非難の声明を出さなかったという史実をもとに、社会派の巨匠コスタ=ガブラスが取り組んだ意欲作です。


ナチス親衛隊中尉で、化学者として飲料水を殺菌する研究などをおこなっていたクルト・ゲルシュタイン(ウルリッヒ・トゥクル)は、知的障害を持つ姪が多数の精神障害者と共に“病死”という口実で安楽死させられたことを知ります。
ナチスによる“望ましからざる者たち”の事実上の抹殺、「障害者絶滅計画」でした。

さらにある日、ゲルシュタインは、医師で上官の将校(ウルリッヒ・ミューエ)らに連れられ、強制収容所でユダヤ人の大量虐殺を目撃します。
ナチスの蛮行を目の当たりにし、数万単位のユダヤ人が次々とガス室送りになることを知ったゲルシュタインは虐殺をやめさせるべく、“神の代理人”である宗教界に頼ろうとします。
プロテスタントの信者であるゲルシュタインは、仲間たちと話し合いの場を設けますが、誰もが彼の意見に耳を貸さず一蹴されてしまいます。
カトリックの総本山であるバチカンに訴えるしかないと考えたゲルシュタインはローマ法王庁の外交官に接触しますが、ここでも相手にされず、一時は落胆しますが、偶然にもその場にいた若い修道士リカルド(マチュー・カソヴィッツ)は、ゲルシュタインと共にナチスの蛮行を食い止める戦いを開始します。
自らもナチスの親衛隊員であるゲルシュタインは自己矛盾を抱えながらもバチカンへの接触を続け、法王への説得を試みますが、法王ピウス12世はナチスと敵対関係になることを恐れ、ゲルシュタインの訴えを退けてしまいます。

暗黒の時代における光の消滅
16世紀にマルティン・ルターが始めた宗教改革は、当時のローマ・カトリック教会に対する抗議の声でもありました。
マリア崇拝、クリスマスのミサ(クリスマスはキリストの誕生日ではなく、古代ローマの太陽崇拝に基づいています)、豪華な教会装飾など、神の言葉よりも教会の権威を高めることに執着し、堕落していたカトリック教会に対して非難の声をあげたのです。
プロテスタント(抗議する者)と呼ばれたマルティン・ルターはカトリック教会から離れ、プロテスタントとして神の言葉“聖書”を軸に宗教改革を推し進めてゆきます。
映画「ホロコースト-アドルフ・ヒトラーの洗礼-」は、ナチスによるユダヤ人の大量虐殺において、何の抵抗も示さなかった宗教界(特にローマ・カトリック教会)そのものを指弾した映画であるといえます。


素晴らしく重厚な映像で、俳優の演技も素晴らしいものでしたが、やはり、何らかの形で虐殺のシーンは欲しかったと思います。強制収容所でゲルシュタインが壁の穴から虐殺の様子を見る場面では、ゲルシュタインの表情ですべてが語られてゆくのですが、親衛隊員である自らの立場と、命を懸けてまで虐殺をやめさせようとする心情をクッキリと浮かび上がらせるためには、「シンドラーのリスト」(1993年)における赤い服の少女のようなシンボリックな映像か、目を背(そむ)けたくなるような、心に突き刺さるシーンが必要だと思いました。
しかし俳優たちの演技は完璧なもので、中でも若き修道士リカルドのマチュー・カソヴィッツの情熱と宗教の絶望感に打ちのめされる姿は強く印象に残りました。
宗教界の最高権威といえども人間社会のひとつの組織体にすぎず、ヨーロッパを席巻したアドルフ・ヒトラー率いるナチス・ドイツに対して保身と無力をさらけ出してしまったのは、ある意味、仕方のないことだったのかもしれませんが、神の名に値しない汚点を残してしまったといえます。
刺激的な映像が少ない分、俳優の演技がかなりの見どころを占めます。それだけに余計な刺激に惑わされずに宗教というテーマを追求することができるという利点があり、コスタ=ガブラスもそのあたりを考慮していたのかもしれません。
でも「ホロコースト-アドルフ・ヒトラーの洗礼-」という邦題には首をひねりたくなります。
“ホロコースト(大量虐殺)”の場面は出てきませんし、ヒトラーそのものも登場しないからです。といって原題そのままに「アーメン」では何だかよく分かりませんしね。題名を考えるのも難しいものです。





フランス/ドイツ/ルーマニア/アメリカ
監督コスタ=ガブラス
脚本コスタ=ガブラス
原作ロルフ・ホーホフート「神の代理人」
撮影パトリック・ブロシェ
〈キャスト〉
ウルリッヒ・トゥクル マチュー・カソヴィッツ
ウルリッヒ・ミューエ
![LOrdre-et-la-Morale-Mathieu-Kassovitz-et-Ulrich-Tukur-dans-Amen[1].jpg](/2810/file/LOrdre-et-la-Morale-Mathieu-Kassovitz-et-Ulrich-Tukur-dans-Amen5B15D-thumbnail2.jpg)
原題は「Amen」。
キリスト教世界における祈りの言葉の後に唱える言葉が原題となっています。
大体において祈りの言葉は「あなた(神)の王国が来ますように」、または、主(神)に対する感謝の言葉で締めくくられることが多いのですが、その後に、是認の言葉として「アーメン」が唱えられ、そうありますように、そうです、といった意味を持ちます。
原題から判るように、「ホロコースト-アドルフ・ヒトラーの洗礼-」は宗教をテーマとして、バチカンがナチス・ドイツのユダヤ人迫害に対して非難の声明を出さなかったという史実をもとに、社会派の巨匠コスタ=ガブラスが取り組んだ意欲作です。
ナチス親衛隊中尉で、化学者として飲料水を殺菌する研究などをおこなっていたクルト・ゲルシュタイン(ウルリッヒ・トゥクル)は、知的障害を持つ姪が多数の精神障害者と共に“病死”という口実で安楽死させられたことを知ります。
ナチスによる“望ましからざる者たち”の事実上の抹殺、「障害者絶滅計画」でした。

さらにある日、ゲルシュタインは、医師で上官の将校(ウルリッヒ・ミューエ)らに連れられ、強制収容所でユダヤ人の大量虐殺を目撃します。
ナチスの蛮行を目の当たりにし、数万単位のユダヤ人が次々とガス室送りになることを知ったゲルシュタインは虐殺をやめさせるべく、“神の代理人”である宗教界に頼ろうとします。
プロテスタントの信者であるゲルシュタインは、仲間たちと話し合いの場を設けますが、誰もが彼の意見に耳を貸さず一蹴されてしまいます。
カトリックの総本山であるバチカンに訴えるしかないと考えたゲルシュタインはローマ法王庁の外交官に接触しますが、ここでも相手にされず、一時は落胆しますが、偶然にもその場にいた若い修道士リカルド(マチュー・カソヴィッツ)は、ゲルシュタインと共にナチスの蛮行を食い止める戦いを開始します。
自らもナチスの親衛隊員であるゲルシュタインは自己矛盾を抱えながらもバチカンへの接触を続け、法王への説得を試みますが、法王ピウス12世はナチスと敵対関係になることを恐れ、ゲルシュタインの訴えを退けてしまいます。

暗黒の時代における光の消滅
16世紀にマルティン・ルターが始めた宗教改革は、当時のローマ・カトリック教会に対する抗議の声でもありました。
マリア崇拝、クリスマスのミサ(クリスマスはキリストの誕生日ではなく、古代ローマの太陽崇拝に基づいています)、豪華な教会装飾など、神の言葉よりも教会の権威を高めることに執着し、堕落していたカトリック教会に対して非難の声をあげたのです。
プロテスタント(抗議する者)と呼ばれたマルティン・ルターはカトリック教会から離れ、プロテスタントとして神の言葉“聖書”を軸に宗教改革を推し進めてゆきます。
映画「ホロコースト-アドルフ・ヒトラーの洗礼-」は、ナチスによるユダヤ人の大量虐殺において、何の抵抗も示さなかった宗教界(特にローマ・カトリック教会)そのものを指弾した映画であるといえます。
素晴らしく重厚な映像で、俳優の演技も素晴らしいものでしたが、やはり、何らかの形で虐殺のシーンは欲しかったと思います。強制収容所でゲルシュタインが壁の穴から虐殺の様子を見る場面では、ゲルシュタインの表情ですべてが語られてゆくのですが、親衛隊員である自らの立場と、命を懸けてまで虐殺をやめさせようとする心情をクッキリと浮かび上がらせるためには、「シンドラーのリスト」(1993年)における赤い服の少女のようなシンボリックな映像か、目を背(そむ)けたくなるような、心に突き刺さるシーンが必要だと思いました。
しかし俳優たちの演技は完璧なもので、中でも若き修道士リカルドのマチュー・カソヴィッツの情熱と宗教の絶望感に打ちのめされる姿は強く印象に残りました。
宗教界の最高権威といえども人間社会のひとつの組織体にすぎず、ヨーロッパを席巻したアドルフ・ヒトラー率いるナチス・ドイツに対して保身と無力をさらけ出してしまったのは、ある意味、仕方のないことだったのかもしれませんが、神の名に値しない汚点を残してしまったといえます。
刺激的な映像が少ない分、俳優の演技がかなりの見どころを占めます。それだけに余計な刺激に惑わされずに宗教というテーマを追求することができるという利点があり、コスタ=ガブラスもそのあたりを考慮していたのかもしれません。
でも「ホロコースト-アドルフ・ヒトラーの洗礼-」という邦題には首をひねりたくなります。
“ホロコースト(大量虐殺)”の場面は出てきませんし、ヒトラーそのものも登場しないからです。といって原題そのままに「アーメン」では何だかよく分かりませんしね。題名を考えるのも難しいものです。

2019年03月19日
映画「キートンの探偵学入門」娯楽映画の原点
「キートンの探偵学入門」(SHERLOCK JR.)
1924年 アメリカ
監督・主演バスター・キートン
撮影エルジン・レスリー バイロン・フーク
脚本クライド・ブラックマン
ジーン・C・ハヴェッツ
ジョセフ・ミッチェル
〈キャスト〉
キャスリン・マクガイア ジョー・キートン

チャップリンが人生の哀歓や政治的・社会的風刺を笑いの中に表現したのに対し、バスター・キートンはあくまで観客を楽しませるためにのみ映画を作っているといえます。
しかし、その表現方法は100年近く経った現在でも決して色褪せることなく、娯楽映画の原点として、見る者を楽しませてくれます。


原題は「シャーロック・ジュニア」。
主人公(バスター・キートン)は映画館の映写技師兼雑用係。シャーロック・ホームズのような名探偵になることを目指しています。
そんな彼は恋のライバルが仕組んだ企みによって指輪泥棒の嫌疑を受け、恋人(キャスリン・マクガイア)の父親から自宅への立ち入りを禁止されます。
意気消沈の主人公。
滅入った気分のまま仕事中の映画の映写中に居眠りをしてしまいます。
それは夢なのか、魂の分離なのか、眠った主人公の体からもう一人の主人公が現れ、摩訶不思議な物語が展開されてゆきます。

映画冒頭は、ごくありがちな喜劇で始まりますが、主人公の体が分離された瞬間から、アイデアに次ぐアイデア、アクションに次ぐアクションが詰め込まれたキートンの世界へと突入していきます。
いろいろなアイデアが満載ですが、まず驚かされるのが、主人公が映画の中へ入ってしまう場面。映画と現実の境界をアッサリと飛び越えてしまう奇想天外な着想で、これは後にウディ・アレンが「カイロの紫のバラ」に取り入れ、冴えないヒロイン(ミア・ファロー)が体験する異次元の恋物語であり、映画賛歌でもありました。
様々なトリックも見もので、編集の技術力とか、まさに一瞬の早わざが登場するかと思えば、ジャッキー・チェンも真っ青のアクションに次ぐアクション。これを無表情にこなしてしまうところがバスター・キートンのすごいところ。
50分に満たない上映時間の中に、ギャグありアクションあり、30年代のファッション・センスを先取りしたような、名探偵に扮したキートンのおしゃれ感覚ありで、何度見ても飽きさせません。
娯楽精神満載の理屈抜きに楽しめる映画です。





1924年 アメリカ
監督・主演バスター・キートン
撮影エルジン・レスリー バイロン・フーク
脚本クライド・ブラックマン
ジーン・C・ハヴェッツ
ジョセフ・ミッチェル
〈キャスト〉
キャスリン・マクガイア ジョー・キートン

チャップリンが人生の哀歓や政治的・社会的風刺を笑いの中に表現したのに対し、バスター・キートンはあくまで観客を楽しませるためにのみ映画を作っているといえます。
しかし、その表現方法は100年近く経った現在でも決して色褪せることなく、娯楽映画の原点として、見る者を楽しませてくれます。
原題は「シャーロック・ジュニア」。
主人公(バスター・キートン)は映画館の映写技師兼雑用係。シャーロック・ホームズのような名探偵になることを目指しています。
そんな彼は恋のライバルが仕組んだ企みによって指輪泥棒の嫌疑を受け、恋人(キャスリン・マクガイア)の父親から自宅への立ち入りを禁止されます。
意気消沈の主人公。
滅入った気分のまま仕事中の映画の映写中に居眠りをしてしまいます。
それは夢なのか、魂の分離なのか、眠った主人公の体からもう一人の主人公が現れ、摩訶不思議な物語が展開されてゆきます。

映画冒頭は、ごくありがちな喜劇で始まりますが、主人公の体が分離された瞬間から、アイデアに次ぐアイデア、アクションに次ぐアクションが詰め込まれたキートンの世界へと突入していきます。
いろいろなアイデアが満載ですが、まず驚かされるのが、主人公が映画の中へ入ってしまう場面。映画と現実の境界をアッサリと飛び越えてしまう奇想天外な着想で、これは後にウディ・アレンが「カイロの紫のバラ」に取り入れ、冴えないヒロイン(ミア・ファロー)が体験する異次元の恋物語であり、映画賛歌でもありました。
様々なトリックも見もので、編集の技術力とか、まさに一瞬の早わざが登場するかと思えば、ジャッキー・チェンも真っ青のアクションに次ぐアクション。これを無表情にこなしてしまうところがバスター・キートンのすごいところ。
50分に満たない上映時間の中に、ギャグありアクションあり、30年代のファッション・センスを先取りしたような、名探偵に扮したキートンのおしゃれ感覚ありで、何度見ても飽きさせません。
娯楽精神満載の理屈抜きに楽しめる映画です。

2019年03月15日
映画「戦艦ポチョムキン」サイレント映画の傑作
「戦艦ポチョムキン」(Броненосец ≪Потёмкин≫) 1925年 ソビエト連邦
監督・脚本・編集セルゲイ・エイゼンシュテイン
撮影エドゥアルド・ティッセ
〈キャスト〉
アレクサンドル・アントノフ ウラジミール・バルスキー

ロマノフ朝による君主政治が陰りを見せ始めた1905年、第一次ロシア革命が起こります。
国内ではストライキが頻発し、草原に燃え広がる野火のように革命の炎は全土に広がろうとしていました。
満州(現・中国東北部)の支配権をめぐり、ロシアは日本との戦争に突入しており、国内では不穏な社会情勢、対外的には日露戦争という混沌とした状況の中、日清戦争で勝利を得た日本は軍事力を強化。まとまりを欠いたロシアは日本との戦況において敗色が決定的なものになっていました。
1905年、日本海海戦で日本はロシアのバルチック艦隊を完全粉砕。ロシアの敗北が決定的になる中、遠く離れた黒海では一隻の戦艦が竣工されようとしていました。正式名称「ポチョムキン=タブリーチェスキー公」、略称「ポチョムキン号」です。

映画「戦艦ポチョムキン」は不穏なロシアの国内情勢を背景に、民衆による革命のうねりを鋭くとらえたサイレント映画の傑作です。
映画は史実としての「ポチョムキン号の反乱」から幕を開けます。
ウジの湧いた肉を食べさせられることへの反感から、水兵たちの間にストライキが起こります。上官たちは、命令に背いたとして数名の水兵たちを銃殺にしようとしますが、やがて指導的な立場になるワクリンチュク(アレクサンドル・アントノフ)によって上官たちへの反乱の火ぶたが切って落とされます。
水兵たちに乗っ取られた「ポチョムキン号」は港湾都市オデッサに寄港し、反乱の銃撃戦で死んだワクリンチュクの遺体を港に安置します。
ワクリンチュクの遺体は民衆に革命の気運を燃え立たせ、それが後にオデッサの階段の虐殺へとつながってゆくことになります。


世界映画史上最も有名な6分間「オデッサの階段」
ポチョムキン号は革命の象徴としてオデッサの民衆の大歓迎を受けます。
港に安置されたワクリンチュクの遺体の周りには人々が押し寄せ、どこからともなく続々と民衆が集まってきます。
このオデッサの港の場面は素晴らしく、自然主義の絵画を見るような美術感覚であると同時にオデッサの町そのものが美しいということもあるのでしょう。
現在はウクライナの一部ですが、ロシア帝国の時代には経済や文化の交流都市であり、多くの民族が共存する他民族都市でもあったことから、活気と混沌の入り混じる独特の魅力を持った町として、プーシキンやゴーゴリ、ゴーリキーといったロシアの文豪たちの創作の舞台となったようです。
そんなオデッサの港にポチョムキン号は寄港し、革命を叫ぶ民衆が続々と押し寄せたことで、革命を恐れる政府はコサックからなる軍隊をオデッサに派遣して民衆の鎮圧にあたることになります。

映画史上最も有名な「オデッサの虐殺」の場面は、狂乱と流血、階段の上から無表情に発砲し、市民を殺戮する軍隊、逃げ惑う群衆、倒れて踏みつけにされる子ども、息の絶えた子どもを抱え、抗議に向かう母親。
サイレントなので群衆の悲鳴は聞こえてはきませんが、ドキュメンタリー映画を観るような恐怖と混乱の映像は、阿鼻叫喚の殺戮の現場を目撃するかのような生々しい迫力に満ちています。
中でも赤ん坊を乗せた乳母車が階段を転がっていく場面は、後にブライアン・デ・パルマ監督、ケヴィン・コスナー主演の「アンタッチャブル」で、ユニオン駅の銃撃戦の中でそのまま引用されており、「オデッサの階段」の中でひときわ抜きんでた場面となっています。
技術的な面が盛んに評価されている「オデッサの階段」ですが、革命のうねりの中で避けることのできない流血と狂乱を見事にえぐり出した映像だと思います。





監督・脚本・編集セルゲイ・エイゼンシュテイン
撮影エドゥアルド・ティッセ
〈キャスト〉
アレクサンドル・アントノフ ウラジミール・バルスキー

ロマノフ朝による君主政治が陰りを見せ始めた1905年、第一次ロシア革命が起こります。
国内ではストライキが頻発し、草原に燃え広がる野火のように革命の炎は全土に広がろうとしていました。
満州(現・中国東北部)の支配権をめぐり、ロシアは日本との戦争に突入しており、国内では不穏な社会情勢、対外的には日露戦争という混沌とした状況の中、日清戦争で勝利を得た日本は軍事力を強化。まとまりを欠いたロシアは日本との戦況において敗色が決定的なものになっていました。
1905年、日本海海戦で日本はロシアのバルチック艦隊を完全粉砕。ロシアの敗北が決定的になる中、遠く離れた黒海では一隻の戦艦が竣工されようとしていました。正式名称「ポチョムキン=タブリーチェスキー公」、略称「ポチョムキン号」です。

映画「戦艦ポチョムキン」は不穏なロシアの国内情勢を背景に、民衆による革命のうねりを鋭くとらえたサイレント映画の傑作です。
映画は史実としての「ポチョムキン号の反乱」から幕を開けます。
ウジの湧いた肉を食べさせられることへの反感から、水兵たちの間にストライキが起こります。上官たちは、命令に背いたとして数名の水兵たちを銃殺にしようとしますが、やがて指導的な立場になるワクリンチュク(アレクサンドル・アントノフ)によって上官たちへの反乱の火ぶたが切って落とされます。
水兵たちに乗っ取られた「ポチョムキン号」は港湾都市オデッサに寄港し、反乱の銃撃戦で死んだワクリンチュクの遺体を港に安置します。
ワクリンチュクの遺体は民衆に革命の気運を燃え立たせ、それが後にオデッサの階段の虐殺へとつながってゆくことになります。
世界映画史上最も有名な6分間「オデッサの階段」
ポチョムキン号は革命の象徴としてオデッサの民衆の大歓迎を受けます。
港に安置されたワクリンチュクの遺体の周りには人々が押し寄せ、どこからともなく続々と民衆が集まってきます。
このオデッサの港の場面は素晴らしく、自然主義の絵画を見るような美術感覚であると同時にオデッサの町そのものが美しいということもあるのでしょう。
現在はウクライナの一部ですが、ロシア帝国の時代には経済や文化の交流都市であり、多くの民族が共存する他民族都市でもあったことから、活気と混沌の入り混じる独特の魅力を持った町として、プーシキンやゴーゴリ、ゴーリキーといったロシアの文豪たちの創作の舞台となったようです。
そんなオデッサの港にポチョムキン号は寄港し、革命を叫ぶ民衆が続々と押し寄せたことで、革命を恐れる政府はコサックからなる軍隊をオデッサに派遣して民衆の鎮圧にあたることになります。

映画史上最も有名な「オデッサの虐殺」の場面は、狂乱と流血、階段の上から無表情に発砲し、市民を殺戮する軍隊、逃げ惑う群衆、倒れて踏みつけにされる子ども、息の絶えた子どもを抱え、抗議に向かう母親。
サイレントなので群衆の悲鳴は聞こえてはきませんが、ドキュメンタリー映画を観るような恐怖と混乱の映像は、阿鼻叫喚の殺戮の現場を目撃するかのような生々しい迫力に満ちています。
中でも赤ん坊を乗せた乳母車が階段を転がっていく場面は、後にブライアン・デ・パルマ監督、ケヴィン・コスナー主演の「アンタッチャブル」で、ユニオン駅の銃撃戦の中でそのまま引用されており、「オデッサの階段」の中でひときわ抜きんでた場面となっています。
技術的な面が盛んに評価されている「オデッサの階段」ですが、革命のうねりの中で避けることのできない流血と狂乱を見事にえぐり出した映像だと思います。

2019年03月11日
映画「海外特派員」ヒッチコックの快作
「海外特派員」(Foreign Correspondent)
1940年 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
脚本チャールズ・ベネット
ジョーン・ハリソン
撮影ルドルフ・マテ
音楽アルフレッド・ニューマン
〈キャスト〉
ジョエル・マクリー レライン・デイ
ハーバート・マーシャル

ニューヨーク・モーニング・グローブ紙の社長室。
開戦間近の不穏なヨーロッパ情勢を探るため、イギリスへ特派員を送り込むことを社長は決めますが、ヤワな記者では勤(つと)まりそうにもない仕事。社内にはこれといった人物が見当たりません。
ジョニー・ジョーンズ(ジョエル・マクリー)は記者をクビになりかけていましたが、警官とモメて武勇伝を発揮したことから社長に気に入られ、クビは取り消し、海外特派員としてヨーロッパへ渡ることになります。
「海外特派員」の導入部分ですが、なんだか稚拙(ちせつ)な脚本で、風雲急を告げるヨーロッパへ向かう新聞記者にしては緊張感のカケラもなく、ユーモア好きなヒッチコックの悪い面が出ている感じで、その後の展開も、イギリスへ渡り、大物政治家のパーティーの席上で若く美しいキャロル(レライン・デイ)と感情の行き違いがあるのですが、結局この二人はそれなりの関係になるのだろう、と先の読めてしまう展開。


ところが、脚本の稚拙さはそこまでで、開戦のカギを握るオランダの政治家ヴァン・メアとパーティーで知り合ったはずのジョーンズでしたが、雨のアムステルダムの取材で再びヴァン・メアと顔を合わせると、メアはジョーンズをまったく知らない様子。
この雨のアムステルダムのシーンは素晴らしく、ジョーンズは盛んに話しかけるのですが、ヴァン・メアは、君はいったい何を言っているのだ、と見ず知らずの人間に対する表情。

ヴァン・メアに近寄った男が大型のカメラを構え、メアの写真を撮ろうとしますが、カメラの横に隠したピストルでメアは射殺されてしまいます。
ここで一気にヒッチコックの世界に引き込まれます。
男を追うジョーンズ。
雨のアムステルダムでの追跡劇も見ごたえ十分で、やがて車での追跡に変わり、雨は上がり、風車が立ち並ぶ草原で男の乗った車を見失うのですが、この風車のシーンも見事です。
ヒッチコック映画はどの映画でもそうなのですが、撮影が見事で、この風車の場面は美術感覚が素晴らしい。


★★★★★
でも、ここで一点。
風車の近くで男の車を見失って、どこへ行ったんだろう、とジョーンズと友人の記者フォリオット(ジョージ・サンダース)、キャロルの三人は風車の前で佇(たたず)んでいるのですが、普通に考えれば、風車の中を疑ってもよさそうなものです。
「海外特派員」はところどころ脚本の不備のようなシーンがあるのですが、それを補って余りあるのが才気あふれるヒッチコックの力量です。
風車の場面でいえば、やはり風車が怪しいとにらんだジョーンズが風車の中へ忍び込み、そこに囚(とら)われていたヴァン・メアと再会(射殺されたヴァン・メアは替え玉)、敵の会話を盗み聞きしながらも、巨大な歯車にコートが挟まってしまう怖さは、ヒッチコックの本領発揮。

「海外特派員」が公開されたのは1940年ですが、その前年には「風と共に去りぬ」が公開され、ハリウッドの黄金時代が築かれていくのですが、ヒッチコックにしてみれば、そのアメリカで「レベッカ」に次ぐ第二作ということもあったのでしょう、「海外特派員」はかなり力の入った作品になっています。
特にドイツの軍用艦からの艦砲射撃を受け、ジョーンズたちの乗った飛行機の海上への墜落と、沈みゆく飛行機からの脱出、飛行機の残骸にしがみ付きながら荒波との必死の格闘は、この場面だけで並の映画以上の重量感があり、後の傑作「救命艇」にもつながっているようです。
現実にはアメリカは後に世界大戦に参戦。
ジョーンズとキャロルが空襲を受けるラジオ局のマイクに向かって開戦の様子を伝えるラストに見られるように、「海外特派員」はプロパガンダの要素を持った映画ですが、当時41歳の若きヒッチコックがその力を十分に発揮した映画でもあるといえます。





1940年 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
脚本チャールズ・ベネット
ジョーン・ハリソン
撮影ルドルフ・マテ
音楽アルフレッド・ニューマン
〈キャスト〉
ジョエル・マクリー レライン・デイ
ハーバート・マーシャル

ニューヨーク・モーニング・グローブ紙の社長室。
開戦間近の不穏なヨーロッパ情勢を探るため、イギリスへ特派員を送り込むことを社長は決めますが、ヤワな記者では勤(つと)まりそうにもない仕事。社内にはこれといった人物が見当たりません。
ジョニー・ジョーンズ(ジョエル・マクリー)は記者をクビになりかけていましたが、警官とモメて武勇伝を発揮したことから社長に気に入られ、クビは取り消し、海外特派員としてヨーロッパへ渡ることになります。
「海外特派員」の導入部分ですが、なんだか稚拙(ちせつ)な脚本で、風雲急を告げるヨーロッパへ向かう新聞記者にしては緊張感のカケラもなく、ユーモア好きなヒッチコックの悪い面が出ている感じで、その後の展開も、イギリスへ渡り、大物政治家のパーティーの席上で若く美しいキャロル(レライン・デイ)と感情の行き違いがあるのですが、結局この二人はそれなりの関係になるのだろう、と先の読めてしまう展開。
ところが、脚本の稚拙さはそこまでで、開戦のカギを握るオランダの政治家ヴァン・メアとパーティーで知り合ったはずのジョーンズでしたが、雨のアムステルダムの取材で再びヴァン・メアと顔を合わせると、メアはジョーンズをまったく知らない様子。
この雨のアムステルダムのシーンは素晴らしく、ジョーンズは盛んに話しかけるのですが、ヴァン・メアは、君はいったい何を言っているのだ、と見ず知らずの人間に対する表情。
ヴァン・メアに近寄った男が大型のカメラを構え、メアの写真を撮ろうとしますが、カメラの横に隠したピストルでメアは射殺されてしまいます。
ここで一気にヒッチコックの世界に引き込まれます。
男を追うジョーンズ。
雨のアムステルダムでの追跡劇も見ごたえ十分で、やがて車での追跡に変わり、雨は上がり、風車が立ち並ぶ草原で男の乗った車を見失うのですが、この風車のシーンも見事です。
ヒッチコック映画はどの映画でもそうなのですが、撮影が見事で、この風車の場面は美術感覚が素晴らしい。
★★★★★
でも、ここで一点。
風車の近くで男の車を見失って、どこへ行ったんだろう、とジョーンズと友人の記者フォリオット(ジョージ・サンダース)、キャロルの三人は風車の前で佇(たたず)んでいるのですが、普通に考えれば、風車の中を疑ってもよさそうなものです。
「海外特派員」はところどころ脚本の不備のようなシーンがあるのですが、それを補って余りあるのが才気あふれるヒッチコックの力量です。
風車の場面でいえば、やはり風車が怪しいとにらんだジョーンズが風車の中へ忍び込み、そこに囚(とら)われていたヴァン・メアと再会(射殺されたヴァン・メアは替え玉)、敵の会話を盗み聞きしながらも、巨大な歯車にコートが挟まってしまう怖さは、ヒッチコックの本領発揮。

「海外特派員」が公開されたのは1940年ですが、その前年には「風と共に去りぬ」が公開され、ハリウッドの黄金時代が築かれていくのですが、ヒッチコックにしてみれば、そのアメリカで「レベッカ」に次ぐ第二作ということもあったのでしょう、「海外特派員」はかなり力の入った作品になっています。
特にドイツの軍用艦からの艦砲射撃を受け、ジョーンズたちの乗った飛行機の海上への墜落と、沈みゆく飛行機からの脱出、飛行機の残骸にしがみ付きながら荒波との必死の格闘は、この場面だけで並の映画以上の重量感があり、後の傑作「救命艇」にもつながっているようです。
現実にはアメリカは後に世界大戦に参戦。
ジョーンズとキャロルが空襲を受けるラジオ局のマイクに向かって開戦の様子を伝えるラストに見られるように、「海外特派員」はプロパガンダの要素を持った映画ですが、当時41歳の若きヒッチコックがその力を十分に発揮した映画でもあるといえます。

2019年03月07日
映画「救命艇」男女8人の海洋サスペンス
「救命艇」(Lifeboat) 1944年 アメリカ
監督アルフレッド・ヒッチコック
原作ジョン・スタインベック
脚本ジョー・スワーリング
撮影グレン・マックウィリアムズ
〈キャスト〉
タルーラ・バンクヘッド ヒューム・クローニン
ヘザー・エンジェル

ノーベル賞作家ジョン・スタインベックの原作を巨匠アルフレッド・ヒッチコックが手がけた海洋サスペンス。
第二次大戦下、大西洋上で一隻の貨物船(客船とも)がドイツ軍のUボートによって撃沈されます。同時にUボートも連合軍の攻撃によって沈没。海上には船の残骸や死体が漂い、生き残った人たちの声が呼び交わされます。
濃霧と残骸の間を一隻の救命艇が漂っています。
乗っているのは一人の女性。
ミンクのコートを着こなし、タバコをくゆらす彼女は、高級ホテルのバーから現れたかのような、およそ遭難者とは程遠い、場違いな雰囲気を醸(かも)しています。

そこへ次々と遭難者が乗り込み、やがて若い黒人が乳飲み子を抱いた母親を助けて乗り込み、8人の男女が一隻の救命艇に乗り合わせることになります。
そして、そこにもう一人、船のへりに手をかけた男が、みんなの手を借りて船の中へ助け上げられ、倒れ込むように乗り込みます。
「大丈夫か?」と声をかけるみんなに応えて彼は言います。
「danke schön」
最後に乗り込んだドイツ人のウィリー(ウォルター・スレザック)は、やがて、撃沈されたUボートの艦長であることが判明し、広大な大西洋に浮かぶ小さな救命艇の中に、8人の連合国側の民間人と、敵国であるドイツの軍人が乗り合わせるという緊張した関係が生まれます。
ほどなく乳飲み子は死に、母親も後を追って自殺を図り、残った8人はハリケーンに襲われ、水や食料も尽きていく中で、緊張した人間関係は一気に暴発してゆくことになります。





救命艇という狭く限られた空間、登場人物が8人(最初は9人)という中で繰り広げられる人間ドラマで、ヒッチコック映画らしく、観る者をグイグイと引っ張っていきます。
登場人物は個性的で、最初に救命艇に乗っていたミンクの女性は、世界を股にかける著名なジャーナリスト、コニー・ポーター(タルーラ・バンクヘッド)。
さらに、シカゴの屠畜場で働いていたコバック(ジョン・ホディアク)。
実業家リットンハウス(ヘンリー・ハル)。
水夫スタンリー(ヒューム・クローニン)。
片足を切断することになるガス(ウィリアム・ベンディックス)。
看護婦マッケンジー(ヘザー・エンジェル)。
元スリの名手で、黒人のジョー(カナダ・リー)。
そして最後に乗り込んだUボートの艦長ウィリー(ウォルター・スレザック)。


粗野な性格のコバックは、ウィリーに対し「海に沈めろ!」と頑強に主張しますが、「国際法に従って捕虜は当局に引き渡すべきだ」と反論するリットンハウスとスタンリー。
7人の間で激論が戦わされますが、救命艇でバミューダを目指そうとしながらも針路が分からず、自信たっぷりなウィリーの指図に従ってしまうことになります。
やがてガスの足が壊疽(えそ)になり、医者でもあったウィリーは、ガスの足を切断。以降、ウィリーの存在が大きくなっていきます。
水や食料がなくなり、飢えと渇きが救命艇を支配する中、渇きに我慢できず、海水を飲んでしまうガス。
ひとりウィリーだけが疲れを見せず、洋々たる態度でボートを漕いでいきます。
後半からのウィリーの存在は不気味さと威圧感を増し、残りの7人には無力感が漂っているのですが、ガスが見殺しにされたことによって、看護婦のマッケンジーがウィリーに襲いかかり、狂気のフタがはじけたように、黒人のジョーを除く全員がウィリーを襲い、海に沈めてしまいます。





救命艇に乗り込んだ男女8人という状況設定は、敵国同士であっても、映画「太平洋の地獄」(1968年)のように最後には力を合わせて難局を乗り切ろう、といった友情物語で幕を閉じることが多いと思うのですが、「救命艇」はスタインベック色の濃い、人間の内面に深く踏み込んでゆく展開になっています。
中でも不可解なのはウィリーで、壊疽になったガスの命を救った彼は、最後にはガスを平然と海へ突き落してしまいます。
「なぜ殺したんだ!」とみんなに詰め寄られても、
「おれの気持ちも察してくれ。苦しむガスを解放してやったんだ」と言い放ちます。
渇きに苦しみ、海水を飲んだガスは正気を失いかけていましたから、ウィリーの反論はもっともらしく聞こえますが、少しでも邪魔な人間を減らしてしまおうという冷酷な傲慢さがうかがえます。


「救命艇」は1944年公開なので、ドイツ軍に対するプロパガンダ的な要素を含んでいるようにもみえますが、重厚な人間ドラマとしての性格がとても強いように思います。
7人対1人でありながら、サバイバルの知恵にすぐれ、医者でもあり、三ヵ国語を話す頑丈な体格の持ち主のドイツ軍人ウィリー一人に翻弄されてしまう民間人の7人。
この救命艇での支配関係は、国家の中における軍部の影響力の縮図とも考えられ、また、暴徒と化したコバックたちには加わらず、ひとり理性を保っていたのが人種差別の対象とされていた黒人のジョーだけだったというのもスタインベックらしい配慮かなと思います。
俳優たちの熱演も見もので、何度見ても見ごたえのあるヒッチコックの傑作です。





監督アルフレッド・ヒッチコック
原作ジョン・スタインベック
脚本ジョー・スワーリング
撮影グレン・マックウィリアムズ
〈キャスト〉
タルーラ・バンクヘッド ヒューム・クローニン
ヘザー・エンジェル

ノーベル賞作家ジョン・スタインベックの原作を巨匠アルフレッド・ヒッチコックが手がけた海洋サスペンス。
第二次大戦下、大西洋上で一隻の貨物船(客船とも)がドイツ軍のUボートによって撃沈されます。同時にUボートも連合軍の攻撃によって沈没。海上には船の残骸や死体が漂い、生き残った人たちの声が呼び交わされます。
濃霧と残骸の間を一隻の救命艇が漂っています。
乗っているのは一人の女性。
ミンクのコートを着こなし、タバコをくゆらす彼女は、高級ホテルのバーから現れたかのような、およそ遭難者とは程遠い、場違いな雰囲気を醸(かも)しています。

そこへ次々と遭難者が乗り込み、やがて若い黒人が乳飲み子を抱いた母親を助けて乗り込み、8人の男女が一隻の救命艇に乗り合わせることになります。
そして、そこにもう一人、船のへりに手をかけた男が、みんなの手を借りて船の中へ助け上げられ、倒れ込むように乗り込みます。
「大丈夫か?」と声をかけるみんなに応えて彼は言います。
「danke schön」
最後に乗り込んだドイツ人のウィリー(ウォルター・スレザック)は、やがて、撃沈されたUボートの艦長であることが判明し、広大な大西洋に浮かぶ小さな救命艇の中に、8人の連合国側の民間人と、敵国であるドイツの軍人が乗り合わせるという緊張した関係が生まれます。
ほどなく乳飲み子は死に、母親も後を追って自殺を図り、残った8人はハリケーンに襲われ、水や食料も尽きていく中で、緊張した人間関係は一気に暴発してゆくことになります。

救命艇という狭く限られた空間、登場人物が8人(最初は9人)という中で繰り広げられる人間ドラマで、ヒッチコック映画らしく、観る者をグイグイと引っ張っていきます。
登場人物は個性的で、最初に救命艇に乗っていたミンクの女性は、世界を股にかける著名なジャーナリスト、コニー・ポーター(タルーラ・バンクヘッド)。
さらに、シカゴの屠畜場で働いていたコバック(ジョン・ホディアク)。
実業家リットンハウス(ヘンリー・ハル)。
水夫スタンリー(ヒューム・クローニン)。
片足を切断することになるガス(ウィリアム・ベンディックス)。
看護婦マッケンジー(ヘザー・エンジェル)。
元スリの名手で、黒人のジョー(カナダ・リー)。
そして最後に乗り込んだUボートの艦長ウィリー(ウォルター・スレザック)。
粗野な性格のコバックは、ウィリーに対し「海に沈めろ!」と頑強に主張しますが、「国際法に従って捕虜は当局に引き渡すべきだ」と反論するリットンハウスとスタンリー。
7人の間で激論が戦わされますが、救命艇でバミューダを目指そうとしながらも針路が分からず、自信たっぷりなウィリーの指図に従ってしまうことになります。
やがてガスの足が壊疽(えそ)になり、医者でもあったウィリーは、ガスの足を切断。以降、ウィリーの存在が大きくなっていきます。
水や食料がなくなり、飢えと渇きが救命艇を支配する中、渇きに我慢できず、海水を飲んでしまうガス。
ひとりウィリーだけが疲れを見せず、洋々たる態度でボートを漕いでいきます。
後半からのウィリーの存在は不気味さと威圧感を増し、残りの7人には無力感が漂っているのですが、ガスが見殺しにされたことによって、看護婦のマッケンジーがウィリーに襲いかかり、狂気のフタがはじけたように、黒人のジョーを除く全員がウィリーを襲い、海に沈めてしまいます。

救命艇に乗り込んだ男女8人という状況設定は、敵国同士であっても、映画「太平洋の地獄」(1968年)のように最後には力を合わせて難局を乗り切ろう、といった友情物語で幕を閉じることが多いと思うのですが、「救命艇」はスタインベック色の濃い、人間の内面に深く踏み込んでゆく展開になっています。
中でも不可解なのはウィリーで、壊疽になったガスの命を救った彼は、最後にはガスを平然と海へ突き落してしまいます。
「なぜ殺したんだ!」とみんなに詰め寄られても、
「おれの気持ちも察してくれ。苦しむガスを解放してやったんだ」と言い放ちます。
渇きに苦しみ、海水を飲んだガスは正気を失いかけていましたから、ウィリーの反論はもっともらしく聞こえますが、少しでも邪魔な人間を減らしてしまおうという冷酷な傲慢さがうかがえます。
「救命艇」は1944年公開なので、ドイツ軍に対するプロパガンダ的な要素を含んでいるようにもみえますが、重厚な人間ドラマとしての性格がとても強いように思います。
7人対1人でありながら、サバイバルの知恵にすぐれ、医者でもあり、三ヵ国語を話す頑丈な体格の持ち主のドイツ軍人ウィリー一人に翻弄されてしまう民間人の7人。
この救命艇での支配関係は、国家の中における軍部の影響力の縮図とも考えられ、また、暴徒と化したコバックたちには加わらず、ひとり理性を保っていたのが人種差別の対象とされていた黒人のジョーだけだったというのもスタインベックらしい配慮かなと思います。
俳優たちの熱演も見もので、何度見ても見ごたえのあるヒッチコックの傑作です。

2019年03月04日
映画「銃殺」戦場の不条理
「銃殺」(King and Country) 1964年 イギリス
監督ジョセフ・ロージー
脚本エヴァン・ジョーンス
ジョセフ・ロージー
撮影デニス・クープ
〈キャスト〉
ダーク・ボガード トム・コートネイ
レオ・マッカーン
1964年ヴェネチア国際映画祭男優賞(トム・コートネイ)
原題は「King and Country」。
「国王と国土」「王と王国」といったような意味合いでしょうか。ヨーロッパでは絶対王政は19世紀にほぼ消滅していますから、ここでは支配する者と、そこに住む者、あるいは国王が支配する土地といったような、絶対的支配者と隷属する国民の関係を指しているかとも思います。

舞台は第一次世界大戦のベルギー、パッシェンデール駐屯地。
パッシェンデールはイギリス・カナダなどの連合軍とドイツ軍が戦った第一次世界大戦の激戦地であり、軟弱な沼沢地(しょうたくち)でもあったために連合軍によるおびただしい戦死者を出した場所でもあります。
そのパッシェンデール駐屯地では、一人の脱走兵に対する軍事裁判が開かれようとしています。
被告は陸軍兵士アーサー・ハンプ(トム・コートネイ)。
ハンプを弁護するのはハーグリーブス大尉(ダーク・ボガード)。
しかしハーグリーブスは、「死刑は自業自得だ。皆が戦っているときに逃げた者が悪い」という持論を公言する男。その彼は最初、上官と部下の立場でハンプの話を聞いています。
元々靴職人の23歳のハンプは、妻に裏切られ、義母と妻にそそのかされて戦場にやって来たいきさつをハーグリーブスに語ります。


大砲の音におびえ、大砲から遠ざかって歩いているうちに、足は家に向かっていたと話すハンプ。
朴訥(ぼくとつ)ながら、戦場の実態を知らずに志願してやって来た若者の心情を聞いているうち、ハーグリーブスの態度には変化が現れます。
ハンプを無罪にするべくハーグリーブスは対策を立て、裁判の席上、熱弁をふるいますが、ハンプにもたらされた判決は銃殺でした。
雨上がりのぬかるんだ空き地で目隠しをされて椅子に座り、駐屯地の全員が見守る中、銃殺隊の射撃を受けてハンプは小川の中に倒れますが、いくつかの銃弾はそれて絶命には至らず、近寄ったハーグリーブスはピストルの銃口をハンプの口に入れ、引き金を引きます。

★★★★★
映画は駐屯地を舞台として展開されていきます。
激戦地であったパッシェンデールですが特に戦闘シーンなどはなく、延々と降り続く雨、泥と水たまりの宿舎、兵舎のベッドを這いまわり、馬の死肉に群がるドブネズミ。
不衛生で不快な駐屯地の様子と、遠くで轟(とどろ)く砲声、画面がモノクロのため、ドキュメンタリー的な寒々とした映像が戦場の一端を伝えています。


ハンプの判決は銃殺でしたが、「ひとりの人間の命がかかっているんです」と訴えるハーグリーブスの熱弁とアーサー・ハンプの実直な態度は、裁判の趨勢(すうせい)を無罪へと傾かせていました。
しかし、前線への移動を控えた部隊の士気を高めるため、ハンプの命は犠牲にされてしまいます。
軍隊の中でひとりの若者の命が弄(もてあそ)ばれてしまう、暗く重い映画ですが、演技陣の熱演によるものでしょう、見応えのある裁判劇になっています。
トム・コートネイはヴェネチア国際映画祭で男優賞を受賞しましたが、同時に、深みのある落ち着きと裁判での熱弁。処刑に失敗したハンプに近寄り、ためらわずにハンプに止(とど)めを刺す冷徹な一面を持った軍人を演じたダーク・ボガードはお見事で、主演男優賞でもよかったんじゃないかと思いました。
でも、「銃殺」という邦題はよくないですね、有罪か無罪かを決める裁判劇でもあるわけなのに、判決の結果をそのままバラしてしまってますからね。





監督ジョセフ・ロージー
脚本エヴァン・ジョーンス
ジョセフ・ロージー
撮影デニス・クープ
〈キャスト〉
ダーク・ボガード トム・コートネイ
レオ・マッカーン
1964年ヴェネチア国際映画祭男優賞(トム・コートネイ)
原題は「King and Country」。
「国王と国土」「王と王国」といったような意味合いでしょうか。ヨーロッパでは絶対王政は19世紀にほぼ消滅していますから、ここでは支配する者と、そこに住む者、あるいは国王が支配する土地といったような、絶対的支配者と隷属する国民の関係を指しているかとも思います。

舞台は第一次世界大戦のベルギー、パッシェンデール駐屯地。
パッシェンデールはイギリス・カナダなどの連合軍とドイツ軍が戦った第一次世界大戦の激戦地であり、軟弱な沼沢地(しょうたくち)でもあったために連合軍によるおびただしい戦死者を出した場所でもあります。
そのパッシェンデール駐屯地では、一人の脱走兵に対する軍事裁判が開かれようとしています。
被告は陸軍兵士アーサー・ハンプ(トム・コートネイ)。
ハンプを弁護するのはハーグリーブス大尉(ダーク・ボガード)。
しかしハーグリーブスは、「死刑は自業自得だ。皆が戦っているときに逃げた者が悪い」という持論を公言する男。その彼は最初、上官と部下の立場でハンプの話を聞いています。
元々靴職人の23歳のハンプは、妻に裏切られ、義母と妻にそそのかされて戦場にやって来たいきさつをハーグリーブスに語ります。
大砲の音におびえ、大砲から遠ざかって歩いているうちに、足は家に向かっていたと話すハンプ。
朴訥(ぼくとつ)ながら、戦場の実態を知らずに志願してやって来た若者の心情を聞いているうち、ハーグリーブスの態度には変化が現れます。
ハンプを無罪にするべくハーグリーブスは対策を立て、裁判の席上、熱弁をふるいますが、ハンプにもたらされた判決は銃殺でした。
雨上がりのぬかるんだ空き地で目隠しをされて椅子に座り、駐屯地の全員が見守る中、銃殺隊の射撃を受けてハンプは小川の中に倒れますが、いくつかの銃弾はそれて絶命には至らず、近寄ったハーグリーブスはピストルの銃口をハンプの口に入れ、引き金を引きます。

★★★★★
映画は駐屯地を舞台として展開されていきます。
激戦地であったパッシェンデールですが特に戦闘シーンなどはなく、延々と降り続く雨、泥と水たまりの宿舎、兵舎のベッドを這いまわり、馬の死肉に群がるドブネズミ。
不衛生で不快な駐屯地の様子と、遠くで轟(とどろ)く砲声、画面がモノクロのため、ドキュメンタリー的な寒々とした映像が戦場の一端を伝えています。
ハンプの判決は銃殺でしたが、「ひとりの人間の命がかかっているんです」と訴えるハーグリーブスの熱弁とアーサー・ハンプの実直な態度は、裁判の趨勢(すうせい)を無罪へと傾かせていました。
しかし、前線への移動を控えた部隊の士気を高めるため、ハンプの命は犠牲にされてしまいます。
軍隊の中でひとりの若者の命が弄(もてあそ)ばれてしまう、暗く重い映画ですが、演技陣の熱演によるものでしょう、見応えのある裁判劇になっています。
トム・コートネイはヴェネチア国際映画祭で男優賞を受賞しましたが、同時に、深みのある落ち着きと裁判での熱弁。処刑に失敗したハンプに近寄り、ためらわずにハンプに止(とど)めを刺す冷徹な一面を持った軍人を演じたダーク・ボガードはお見事で、主演男優賞でもよかったんじゃないかと思いました。
でも、「銃殺」という邦題はよくないですね、有罪か無罪かを決める裁判劇でもあるわけなのに、判決の結果をそのままバラしてしまってますからね。







