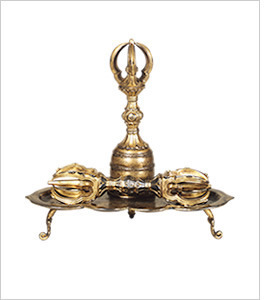2019年08月02日
文化の両義性について
文化の両義性
市民としての「つとめ」の一環で、或る神社の講社祭なるものに参列してきました。
待合場所で、今世間を騒がせているH議員にお会いしました。初めて目の当たりにしての印象はと言えば、想像していたようなアウラ(オーラ)は感じられませんでした。唯、アウラは「特別でない人」がまん延することで「特別な人」に付くもので、ネットやスマホが行き渡り、誰もが「有名人化」した現代では、「特別な人」が普通の人に見えてしまうことで、アウラは感じられないのは当然ですね(ウオルター・ベンヤミンは、複製時代には、芸術作品のアウラが消えるといったが、何か元々芸術なるものが在るとの前提でものを言っているから、真実を言っているように錯覚してしまいますが、実は逆で、複製の誕生でそれまで日の目を見なかった職人のアノニマスに日が当たるようになった=アウラが付いたのだと考えるべきでしょう)。
話がそれますが、彼の行動は、「世間」から見れば、あっちにふらふら、こっちにふらふら風見鶏の様に選挙民やマスコミにとって感じられるのが不快なのでしょう、あまり彼に対する好評は聞かれません。私の推測する処、今彼は、皮を脱ごうとしている蛇なのではないでしょうか。脱皮しないと死んでしまうあの蛇です。昔の全共闘のお遊びでは「連帯を求めて孤立を恐れず」がキャッチフレーズでしたが、彼は反対に「孤立を求めて、連帯を恐れず」の構えです。
それはいいのではないでしょうか。自分の覚悟に自信が無いから仲間を増やして、巻き込もうとするのです。信者を増やそうと布教するのも同じです。自信があればそんな必要はない。孤独を守らなければ(覚悟を決めなければ)政治などできません。そしてその孤独者同士が、個別案件で意見が一致すれば、党派など関係なく連帯を恐れず共闘するのです。互いの個を殺すことなく、和音を響かせるのです。これが、孔子の言う「龢して同せず」の意味でしょう。皆が孤独の覚悟を持てば、多数決などという暴力は必要ありません。皆の意見がポリフォニーを奏でるのですから。
今彼は、自分の持っていた信念というものは一体何だったのだろうか。振り出しに戻って考え直しているのではないでしょうか。自分の思っていることを実行しようとすればするほど、違った方向に行ってしまうという両義性を。
《政治について》
ご存知の通り今の、というより世界の政治は「代議制」をとっています。これが曲者なんですね。有権者が投票に行くのは結構なんですが、後は任せっきりで、監視もしない。人類における20世紀の最大の汚点は「専門家(科学者)」の波です。皆が専門家になりたがる。つまり責任回避したがるという事です。政治家も、行政も事あるごとに「専門家の意見を聞け」が合言葉です。そして責任を薄めたがる。本来、専門家は、結果なんですね。ところがいつの間にか学校の先生が、おまえこんなに偏差値が高いなら、医学部へ行けと無責任なことをおっしゃる。その結果医療者に適した人材の席を奪ってしまう。医療行為が好きだから、この道に進みたいのに、合格できない。そして横柄で、一人で大人になったかのようなクレバーだがワイズでない不適格医者が量産される。不幸なのは患者だけでなく、金持ちになるために医者になった本人も同じなのです。それは教師の道も、介護の道も同じです。こうして「この道しかなし、この道を行く」の「この性」の追求から、「結果」として生まれるべき専門家の道(「満足追求行動」)が、偏差値の壁で「目的」と化す(金銭豊富による「安全保障感追求行動(中井久夫)」の)。もっと悪い事には、これによってなりたい自分でないにも関わらず、「先生」と呼ばれ、あの人なら理想の行動をとってくれるだろうという「暗示」にまみれた誤解社会が膨らんでいく。あの人は東大出だから、あの人は何々の権威だからと、教育も宗教も医療も「暗示」に染まりきっている。フロイトも暗示効果には限界があり、うまくいってもやがてペンキがはがれ地肌がむき出しになるように再発することを回想している、そこから自由連想法を考え、無意識の変装した何気ない言葉から、隠蔽された抑圧を引き出した。
当選者の方も一度当選してしまえばこっちのもので、好き勝手なことを始める。このすれ違いと政党制の党議拘束が、悪魔の様な魅力を持ったファシズム(攻撃欲動)の誘惑を忍び込ませる原因なんで、どっちもどっちなんです。世界のほとんどの国が資本主義体制の基に国家を名乗り、排除の論理で探り合いをしています。その中で共産主義とか自由主義とか、国民国家のどちらを優先するかの順位の違うだけの国々が、どちらが正義かとしのぎを削っているわけです。そして国民を優先すると主張する国は、実際は国家を優先し、個人の自由を優先すると主張する国も、実際には国家を優先しているわけです。仮に世界に1国しか無ければこんな議論は無用です。2つ以上、つまり外部が発生すると国家概念が必要になり、排除の論理が出てくるわけです。
ここで、代議制の話をすると、終わらなくなるので別の機会にしたいのですが、最低限言っておかなければならないのは、国民の側には「選ぶだけが政治ではない、《政治の様に生活をする》。本来両者の区別など無いのだから。」代議士側には「票稼ぎが政治じゃない。《生活の様に政治をする》。本来両者の区別など無いのだから。」ぶっちゃけ、「俺は国家の為に政治をしているのだから、家庭など構っていられない。」も、「仕事・家庭が忙しくて政治のことなどかまってられない。」もどちらも、両者を区別しているから生まれた勘違いで、アウトなんですね。だからソクラテスは民会(議会)に行かず、広場に行って若者と議論した。彼は政治の様に生活し、生活の様に政治に向かった。奴隷と女性に選挙権が無く、仕事を奴隷がすることと侮辱して、政治だけをしていた、欺瞞に満ちた「デモクラシー」なるものの正体を嫌っていたから。彼がいつも悩まされたという「ダイモン」なる神々のお告げとは、常に意思決定をするたびに、反対をする声が聞こえるというものですが、「宜なるかな」ですね。どんな決定も必ず反対側に犠牲者があって善悪が成り立っている。一番いいのは決定しないこと(いじくり回さないこと)だ。その次にいいのはできるだけ犠牲者を保護することだ。だから彼は、何も書を残さなかったし、思想体系というものを持たなかった(プラトンは彼を利用しただけで、後の弁証法と言われる詭弁を使って、生活の中にこそある「かけがえのなさ」「取り換えのきかなさ」即ち「この私」の「この姓」を消し去り、イデアという夢想世界を支点にした体系を作りあげた。個をイデアの基に埋没させてしまうものです。それはカントの「物自体」とは似て非なるものです)。ソクラテスの信念を知りたかったら、柄谷さんの言うように、ディオゲネスの方を見た方がいいと思います。ソクラテスは何の積極的な事も言わなかったが、広場で話しかけたことは、若者の主張に対し、その主張に対するアンチノミーを提示し、自明と思っていたことの牙城を再点検させることのみです。
産婆術ともいわれますが、これによって自己の考えのディコンストラクションを促しただけです。これにより、当時のアテネのデモクラシーの自明性の欺瞞がくずされることになり、危険思想家として処刑されたのは当然ですね。
崩されたのは、公人と私人の両義性を持つ(分ける)ことの自己欺瞞で、それによって隠蔽されていた公人でも私人でもない「自己(かけがえのない、この性)」に目覚めさせることです。
《言語世界(象徴世界)に産み落とされて》
実は人間がこの世に産み落とされて、本能というオートマチック行動能力(本能)なしで生き延びる為に、言語の世界を強制されて以来、(言語で出来た=初めに言葉ありきの)文化という装置を祖先から与えられて以来、自己という統合性(ホメオスタシス)をもらった代わりに、大きな疎外も同時に受け取ったんです。つまり自己とは、本来無いもので、唯どうしても内から溢れ出てくる欲動をどう表現したらいいか判らず、人間は、その表現の支点(支えとしての場所)として「自己」なる虚構を創った(デカルトのコギトエルゴスム)。つまり対概念としての「自己(自我)」を発明してようやく、この内なる燃えるもの(「主体」)を、世界との「差異」を、外部へ向けて発信できたのですが、それが出来たつまり「自己」と「主体」が二重化された事で、永久に母の胎内にあったころの、もっと言えば、宇宙に無機質としてあった時の一体性は失われました。秀吉の辞世の句と言われる「露と落ち、露と消えにし我が身かな、難波のことも夢の又夢」の夢こそ、文化であり、言語界を表しているんですね。それは自身の主体(単独性=この俺というものは何なんだという疑問)を囲いとしての自己という表現(虚構=嘘)で表した瞬間に生まれた、疑問であり、淋しさです。結論だけ言っておくと、「物は事」であり、精神も、文化も機械と言っていい。我々の認識は、ゲシュタルトなんです。中島敦に「文字禍」という短編がありました。ある文字をずーっと見ていると、それが今まで機械的に読めて意味も感じていた、その感覚が飛び、その文字が唯の模様に見えてきてしまうお話でした。ゲシュタルト崩壊の瞬間ですね。唯の模様が、意味あるものに見える。それはネアンデルタール人に無く、新人類にあった象徴能力ですね。
象徴と言えば、文楽「菅原伝授手習鑑」での寺子屋の段、道真の書の弟子・式部源蔵が、師の息子(秀才)を守る為、寺子屋の男の子を偽って差し出し、時平の使者松王丸が連れ去り亡き者にすることになるのですが、実はその松王丸は、道真に恩があり、打ち首にしなければならない秀才の身代わりにさせる為、前日に寺子屋に実の息子を送り込んだ張本人でした。松王丸夫妻が犠牲とした実の息子に対する野辺の送りの、母の踊りは涙を誘わずに入られません。「ういのおくやまけふこえて・・・」寺子屋は「いろは」を教える道場であり、この連想の中に、無き子・小太郎の死が目に見えぬ重みをもって作用する。白衣の母はこの重力の周りで踊っている。或いはこの重力を静かに踏んで踊っている。「意味」と意味を越えているものとを、「踊り」が繋ぎ、「踊り」が象徴する(片山敏彦「象徴主義」)。夏の盆踊りもそのような祖先の死霊を踏み抑えて(祖先の霊と触れ合って)踊るものでしょう。
フェチシズムの能力もこの象徴力です。フェチというと、すぐに異常性愛を思われる方も多いでしょうが、とんでもない。異常も正常も、都合でどちらかを正常と決めた瞬間に発生した対概念に過ぎません。この議論も深入りするつもりはありませんが、フェチは、正常中の正常と思われていることにごろごろしています。「貨幣」「言語」はその代表的なものです。貨幣フェチでない人なんか、殆どいませんね。貨幣は、「それを持っていれば、物と交換できる権利の券」ですから、本来私の作ったものや得たものが、他のものと交換できるかどうかなんて、相手次第で全く判らない賭けの世界なのに、その不安に耐えられないから、強制的に、交換できると決めてしまった・権利を与えてしまった券なんですね。この券を持っていれば、交換できるかどうかわからないという不安から解放され、優先的に実現する。金を見ていれば勝利が見えてくるのです(約束事に過ぎませんが・虚構ですが)。あたかも、透ける下着や網タイツの目の向こうに、在りもしない「ファルス」があり、縫い目をくぐってその先に行けると夢想する下着フェチの様に。
だからこそ、60年サイクルぐらいで、「ここらで一旦、貨幣の虚構性を戻して、清算しときたい」と信用先送りの不安が頂点に達するものなんですね。これが恐慌ですね。コンドラチェフの60年周期説。
《言葉の両義性》
さて、横道に逸れるのもたいがいにして、或る観念を獲得してその世界にどっぷりつかっていても(言葉フェチ)、真面目にそれを追求すればするほど、主体が本来望んでいた方向と逸れていってしまうものなんですね。何故かというと、それと対概念の片方しか見ていないからですね。本当は両方とも同じもの、或いは両方を合わせて。どちらにも偏りすぎないようにバランスをとっていかないと意図しない悲劇(ギリシャ悲劇はエディプス期の、シェークスピア悲劇は壮年期(去勢後の悲劇)を招いてしまうんです。本来方便なのですから。これを調整する方法を人は、「中庸」とか、「たかが人生、されど人生」とか言います。一休禅師は「年々に咲くや吉野の花桜。木を割りてみよ花のありかを」と詠んで、美と言ってもそのありかがある訳じゃない。いくら桜の木を割ってみても判らない。といいました。
フロイトは晩年になり、無意識に抑圧されている欲動を、言語化すれば(意識の表舞台に引っ張り出せば)神経症は治癒されるという信念(快感原則)が、戦争経験の悪夢に反復脅迫的に襲われる患者の治癒に役立たないことから、とうとう、「死の欲動」という新たな概念を引っ張り出さざるを得なくなりました。「死の欲動」は、「生の欲動=快感原則」の彼岸に当たる対概念です。対概念を無視していたことで限界に来たのです。どちらも相手が無ければ成立しない虚構です。しかしそれが無ければ、文化の世界では片方を嘘にしてしまうような、必要な概念です。空の青、焚火の炎、いつまでも続く海岸線、見ていればいるほどストレス値は下がります。これこそ攻撃欲動が見ている破壊のその先の死への、無機質への欲動なんです。そして攻撃欲動の追求の先にあるのが、罪悪感としての攻撃欲動の抑制、つまり「超自我」です。この自然の仕組みを、人類の歴史に垣間見たのがカントです。彼の世界共和国は、国際連盟や国連のポリシーとなっていますが、今一つ評判が悪いのです。それはカント批判の常套句「現実的でない」です。私に言わせれば、冗談じゃない。そんな簡単に平和のような努力を要する(攻撃欲動を放し飼いにするような簡単な怠けた根性と比べて)理想が実現できて溜まるかです。理想と現実も対概念で、両方とも同じもので本来区別などありません。それを、相手を下げることで自分を比較優位に見せるのと同じで、互いに非難し合うのです。何の中身もありません。現実現実という者は、結局、努力をしたくないのです。早く決着をつけてしまいたいのです。本当はどちらでもいいのです。それも無理もありません。死の欲動の狡知に嵌まっているからです。しかしそのような勢力が攻撃欲動を強め、再び大きな犠牲を強いることになります。このような流れは人間にはどうしようもありません。唯その先に「超自我」が強まり、より強固な「良心」となって攻撃欲動を抑制するのを頼むしかないのです。それをカントは「自然の狡知(計画)」と呼びました。犠牲を出すのですから、「悪巧み」とも言っています。
突然ですが、H議員はそろそろこの、理想や現実といった信念の両義性に気付き始めたのではないでしょうか。中身のない議論に飽きたのではないでしょうか。そうはいっても、脱皮した後に待っているのは、攻撃欲動に満ちた対概念の世界です。どう乗り切って、石橋湛山のような覚悟を持った政治家になれるのか、見守ります。
送る言葉は、「孤立を求めて、連帯を恐れず」です。
烏合の衆に埋没せず、孤独であれ。仲間を作るな。個の判断を貫け(孤立を求める)。党議拘束に縛られず、その問題に限って対立政党であろうと、意見が一致すれば共闘する(連帯を恐れず)です。
市民としての「つとめ」の一環で、或る神社の講社祭なるものに参列してきました。
待合場所で、今世間を騒がせているH議員にお会いしました。初めて目の当たりにしての印象はと言えば、想像していたようなアウラ(オーラ)は感じられませんでした。唯、アウラは「特別でない人」がまん延することで「特別な人」に付くもので、ネットやスマホが行き渡り、誰もが「有名人化」した現代では、「特別な人」が普通の人に見えてしまうことで、アウラは感じられないのは当然ですね(ウオルター・ベンヤミンは、複製時代には、芸術作品のアウラが消えるといったが、何か元々芸術なるものが在るとの前提でものを言っているから、真実を言っているように錯覚してしまいますが、実は逆で、複製の誕生でそれまで日の目を見なかった職人のアノニマスに日が当たるようになった=アウラが付いたのだと考えるべきでしょう)。
話がそれますが、彼の行動は、「世間」から見れば、あっちにふらふら、こっちにふらふら風見鶏の様に選挙民やマスコミにとって感じられるのが不快なのでしょう、あまり彼に対する好評は聞かれません。私の推測する処、今彼は、皮を脱ごうとしている蛇なのではないでしょうか。脱皮しないと死んでしまうあの蛇です。昔の全共闘のお遊びでは「連帯を求めて孤立を恐れず」がキャッチフレーズでしたが、彼は反対に「孤立を求めて、連帯を恐れず」の構えです。
それはいいのではないでしょうか。自分の覚悟に自信が無いから仲間を増やして、巻き込もうとするのです。信者を増やそうと布教するのも同じです。自信があればそんな必要はない。孤独を守らなければ(覚悟を決めなければ)政治などできません。そしてその孤独者同士が、個別案件で意見が一致すれば、党派など関係なく連帯を恐れず共闘するのです。互いの個を殺すことなく、和音を響かせるのです。これが、孔子の言う「龢して同せず」の意味でしょう。皆が孤独の覚悟を持てば、多数決などという暴力は必要ありません。皆の意見がポリフォニーを奏でるのですから。
今彼は、自分の持っていた信念というものは一体何だったのだろうか。振り出しに戻って考え直しているのではないでしょうか。自分の思っていることを実行しようとすればするほど、違った方向に行ってしまうという両義性を。
《政治について》
ご存知の通り今の、というより世界の政治は「代議制」をとっています。これが曲者なんですね。有権者が投票に行くのは結構なんですが、後は任せっきりで、監視もしない。人類における20世紀の最大の汚点は「専門家(科学者)」の波です。皆が専門家になりたがる。つまり責任回避したがるという事です。政治家も、行政も事あるごとに「専門家の意見を聞け」が合言葉です。そして責任を薄めたがる。本来、専門家は、結果なんですね。ところがいつの間にか学校の先生が、おまえこんなに偏差値が高いなら、医学部へ行けと無責任なことをおっしゃる。その結果医療者に適した人材の席を奪ってしまう。医療行為が好きだから、この道に進みたいのに、合格できない。そして横柄で、一人で大人になったかのようなクレバーだがワイズでない不適格医者が量産される。不幸なのは患者だけでなく、金持ちになるために医者になった本人も同じなのです。それは教師の道も、介護の道も同じです。こうして「この道しかなし、この道を行く」の「この性」の追求から、「結果」として生まれるべき専門家の道(「満足追求行動」)が、偏差値の壁で「目的」と化す(金銭豊富による「安全保障感追求行動(中井久夫)」の)。もっと悪い事には、これによってなりたい自分でないにも関わらず、「先生」と呼ばれ、あの人なら理想の行動をとってくれるだろうという「暗示」にまみれた誤解社会が膨らんでいく。あの人は東大出だから、あの人は何々の権威だからと、教育も宗教も医療も「暗示」に染まりきっている。フロイトも暗示効果には限界があり、うまくいってもやがてペンキがはがれ地肌がむき出しになるように再発することを回想している、そこから自由連想法を考え、無意識の変装した何気ない言葉から、隠蔽された抑圧を引き出した。
当選者の方も一度当選してしまえばこっちのもので、好き勝手なことを始める。このすれ違いと政党制の党議拘束が、悪魔の様な魅力を持ったファシズム(攻撃欲動)の誘惑を忍び込ませる原因なんで、どっちもどっちなんです。世界のほとんどの国が資本主義体制の基に国家を名乗り、排除の論理で探り合いをしています。その中で共産主義とか自由主義とか、国民国家のどちらを優先するかの順位の違うだけの国々が、どちらが正義かとしのぎを削っているわけです。そして国民を優先すると主張する国は、実際は国家を優先し、個人の自由を優先すると主張する国も、実際には国家を優先しているわけです。仮に世界に1国しか無ければこんな議論は無用です。2つ以上、つまり外部が発生すると国家概念が必要になり、排除の論理が出てくるわけです。
ここで、代議制の話をすると、終わらなくなるので別の機会にしたいのですが、最低限言っておかなければならないのは、国民の側には「選ぶだけが政治ではない、《政治の様に生活をする》。本来両者の区別など無いのだから。」代議士側には「票稼ぎが政治じゃない。《生活の様に政治をする》。本来両者の区別など無いのだから。」ぶっちゃけ、「俺は国家の為に政治をしているのだから、家庭など構っていられない。」も、「仕事・家庭が忙しくて政治のことなどかまってられない。」もどちらも、両者を区別しているから生まれた勘違いで、アウトなんですね。だからソクラテスは民会(議会)に行かず、広場に行って若者と議論した。彼は政治の様に生活し、生活の様に政治に向かった。奴隷と女性に選挙権が無く、仕事を奴隷がすることと侮辱して、政治だけをしていた、欺瞞に満ちた「デモクラシー」なるものの正体を嫌っていたから。彼がいつも悩まされたという「ダイモン」なる神々のお告げとは、常に意思決定をするたびに、反対をする声が聞こえるというものですが、「宜なるかな」ですね。どんな決定も必ず反対側に犠牲者があって善悪が成り立っている。一番いいのは決定しないこと(いじくり回さないこと)だ。その次にいいのはできるだけ犠牲者を保護することだ。だから彼は、何も書を残さなかったし、思想体系というものを持たなかった(プラトンは彼を利用しただけで、後の弁証法と言われる詭弁を使って、生活の中にこそある「かけがえのなさ」「取り換えのきかなさ」即ち「この私」の「この姓」を消し去り、イデアという夢想世界を支点にした体系を作りあげた。個をイデアの基に埋没させてしまうものです。それはカントの「物自体」とは似て非なるものです)。ソクラテスの信念を知りたかったら、柄谷さんの言うように、ディオゲネスの方を見た方がいいと思います。ソクラテスは何の積極的な事も言わなかったが、広場で話しかけたことは、若者の主張に対し、その主張に対するアンチノミーを提示し、自明と思っていたことの牙城を再点検させることのみです。
産婆術ともいわれますが、これによって自己の考えのディコンストラクションを促しただけです。これにより、当時のアテネのデモクラシーの自明性の欺瞞がくずされることになり、危険思想家として処刑されたのは当然ですね。
崩されたのは、公人と私人の両義性を持つ(分ける)ことの自己欺瞞で、それによって隠蔽されていた公人でも私人でもない「自己(かけがえのない、この性)」に目覚めさせることです。
《言語世界(象徴世界)に産み落とされて》
実は人間がこの世に産み落とされて、本能というオートマチック行動能力(本能)なしで生き延びる為に、言語の世界を強制されて以来、(言語で出来た=初めに言葉ありきの)文化という装置を祖先から与えられて以来、自己という統合性(ホメオスタシス)をもらった代わりに、大きな疎外も同時に受け取ったんです。つまり自己とは、本来無いもので、唯どうしても内から溢れ出てくる欲動をどう表現したらいいか判らず、人間は、その表現の支点(支えとしての場所)として「自己」なる虚構を創った(デカルトのコギトエルゴスム)。つまり対概念としての「自己(自我)」を発明してようやく、この内なる燃えるもの(「主体」)を、世界との「差異」を、外部へ向けて発信できたのですが、それが出来たつまり「自己」と「主体」が二重化された事で、永久に母の胎内にあったころの、もっと言えば、宇宙に無機質としてあった時の一体性は失われました。秀吉の辞世の句と言われる「露と落ち、露と消えにし我が身かな、難波のことも夢の又夢」の夢こそ、文化であり、言語界を表しているんですね。それは自身の主体(単独性=この俺というものは何なんだという疑問)を囲いとしての自己という表現(虚構=嘘)で表した瞬間に生まれた、疑問であり、淋しさです。結論だけ言っておくと、「物は事」であり、精神も、文化も機械と言っていい。我々の認識は、ゲシュタルトなんです。中島敦に「文字禍」という短編がありました。ある文字をずーっと見ていると、それが今まで機械的に読めて意味も感じていた、その感覚が飛び、その文字が唯の模様に見えてきてしまうお話でした。ゲシュタルト崩壊の瞬間ですね。唯の模様が、意味あるものに見える。それはネアンデルタール人に無く、新人類にあった象徴能力ですね。
象徴と言えば、文楽「菅原伝授手習鑑」での寺子屋の段、道真の書の弟子・式部源蔵が、師の息子(秀才)を守る為、寺子屋の男の子を偽って差し出し、時平の使者松王丸が連れ去り亡き者にすることになるのですが、実はその松王丸は、道真に恩があり、打ち首にしなければならない秀才の身代わりにさせる為、前日に寺子屋に実の息子を送り込んだ張本人でした。松王丸夫妻が犠牲とした実の息子に対する野辺の送りの、母の踊りは涙を誘わずに入られません。「ういのおくやまけふこえて・・・」寺子屋は「いろは」を教える道場であり、この連想の中に、無き子・小太郎の死が目に見えぬ重みをもって作用する。白衣の母はこの重力の周りで踊っている。或いはこの重力を静かに踏んで踊っている。「意味」と意味を越えているものとを、「踊り」が繋ぎ、「踊り」が象徴する(片山敏彦「象徴主義」)。夏の盆踊りもそのような祖先の死霊を踏み抑えて(祖先の霊と触れ合って)踊るものでしょう。
フェチシズムの能力もこの象徴力です。フェチというと、すぐに異常性愛を思われる方も多いでしょうが、とんでもない。異常も正常も、都合でどちらかを正常と決めた瞬間に発生した対概念に過ぎません。この議論も深入りするつもりはありませんが、フェチは、正常中の正常と思われていることにごろごろしています。「貨幣」「言語」はその代表的なものです。貨幣フェチでない人なんか、殆どいませんね。貨幣は、「それを持っていれば、物と交換できる権利の券」ですから、本来私の作ったものや得たものが、他のものと交換できるかどうかなんて、相手次第で全く判らない賭けの世界なのに、その不安に耐えられないから、強制的に、交換できると決めてしまった・権利を与えてしまった券なんですね。この券を持っていれば、交換できるかどうかわからないという不安から解放され、優先的に実現する。金を見ていれば勝利が見えてくるのです(約束事に過ぎませんが・虚構ですが)。あたかも、透ける下着や網タイツの目の向こうに、在りもしない「ファルス」があり、縫い目をくぐってその先に行けると夢想する下着フェチの様に。
だからこそ、60年サイクルぐらいで、「ここらで一旦、貨幣の虚構性を戻して、清算しときたい」と信用先送りの不安が頂点に達するものなんですね。これが恐慌ですね。コンドラチェフの60年周期説。
《言葉の両義性》
さて、横道に逸れるのもたいがいにして、或る観念を獲得してその世界にどっぷりつかっていても(言葉フェチ)、真面目にそれを追求すればするほど、主体が本来望んでいた方向と逸れていってしまうものなんですね。何故かというと、それと対概念の片方しか見ていないからですね。本当は両方とも同じもの、或いは両方を合わせて。どちらにも偏りすぎないようにバランスをとっていかないと意図しない悲劇(ギリシャ悲劇はエディプス期の、シェークスピア悲劇は壮年期(去勢後の悲劇)を招いてしまうんです。本来方便なのですから。これを調整する方法を人は、「中庸」とか、「たかが人生、されど人生」とか言います。一休禅師は「年々に咲くや吉野の花桜。木を割りてみよ花のありかを」と詠んで、美と言ってもそのありかがある訳じゃない。いくら桜の木を割ってみても判らない。といいました。
フロイトは晩年になり、無意識に抑圧されている欲動を、言語化すれば(意識の表舞台に引っ張り出せば)神経症は治癒されるという信念(快感原則)が、戦争経験の悪夢に反復脅迫的に襲われる患者の治癒に役立たないことから、とうとう、「死の欲動」という新たな概念を引っ張り出さざるを得なくなりました。「死の欲動」は、「生の欲動=快感原則」の彼岸に当たる対概念です。対概念を無視していたことで限界に来たのです。どちらも相手が無ければ成立しない虚構です。しかしそれが無ければ、文化の世界では片方を嘘にしてしまうような、必要な概念です。空の青、焚火の炎、いつまでも続く海岸線、見ていればいるほどストレス値は下がります。これこそ攻撃欲動が見ている破壊のその先の死への、無機質への欲動なんです。そして攻撃欲動の追求の先にあるのが、罪悪感としての攻撃欲動の抑制、つまり「超自我」です。この自然の仕組みを、人類の歴史に垣間見たのがカントです。彼の世界共和国は、国際連盟や国連のポリシーとなっていますが、今一つ評判が悪いのです。それはカント批判の常套句「現実的でない」です。私に言わせれば、冗談じゃない。そんな簡単に平和のような努力を要する(攻撃欲動を放し飼いにするような簡単な怠けた根性と比べて)理想が実現できて溜まるかです。理想と現実も対概念で、両方とも同じもので本来区別などありません。それを、相手を下げることで自分を比較優位に見せるのと同じで、互いに非難し合うのです。何の中身もありません。現実現実という者は、結局、努力をしたくないのです。早く決着をつけてしまいたいのです。本当はどちらでもいいのです。それも無理もありません。死の欲動の狡知に嵌まっているからです。しかしそのような勢力が攻撃欲動を強め、再び大きな犠牲を強いることになります。このような流れは人間にはどうしようもありません。唯その先に「超自我」が強まり、より強固な「良心」となって攻撃欲動を抑制するのを頼むしかないのです。それをカントは「自然の狡知(計画)」と呼びました。犠牲を出すのですから、「悪巧み」とも言っています。
突然ですが、H議員はそろそろこの、理想や現実といった信念の両義性に気付き始めたのではないでしょうか。中身のない議論に飽きたのではないでしょうか。そうはいっても、脱皮した後に待っているのは、攻撃欲動に満ちた対概念の世界です。どう乗り切って、石橋湛山のような覚悟を持った政治家になれるのか、見守ります。
送る言葉は、「孤立を求めて、連帯を恐れず」です。
烏合の衆に埋没せず、孤独であれ。仲間を作るな。個の判断を貫け(孤立を求める)。党議拘束に縛られず、その問題に限って対立政党であろうと、意見が一致すれば共闘する(連帯を恐れず)です。