新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2016年05月16日
扉シリーズ 第三章 『呪詛』 第一話 「武市」著者:冨田武市
八龍での出来事から、一週間が過ぎた…
夏休みも終わりに近づいた今日、オレは昨晩から発熱し、床についていた。
熱を測ってみたら、三十九度…
なかなかの高熱である。
今日は昼からバイトがあるのだが、この体調では休まざるを得ない。
オレは携帯でバイト先に電話した。
長いコール音の後、電話が繋がった。
「はい、岩下ですが?」
バイト先である『イワシタ模型店』の店主が伝に出た。
このイワシタ模型店の息子は幼馴染で、そのツテで雇ってもらっている。
地元でも有数の資産家である岩下の家はいくつかの商売をしているが、この模型店は店主であるおじさんの道楽で始めたもので、おじさんは他の商売が忙しい為、ほとんど店に出ない。
よって、唯一のバイトであるオレは実質店長のようなものなのだが、昨今はあまり模型、つまりプラモデルが売れないので、仕事といえば掃除や棚卸し…一日中欠伸をして過ごしたこともある。
岩下家は、幼馴染の優二が優秀で東京の大学に進学したので、今は銀行員の優二の兄とおじさんとおばさんの三人家族である。
優二には悪いが、こんな楽な仕事はあるまいと、やりがいは感じないが、ここを辞める気は全くない。
「あ、冨田ですけど…おじさん、すみません…昨日から三十九度も熱出て体調悪いので、今日は休ませてもらっていいですか?」
「ああ、そうかぁ…ほな、ゆっくり休みや〜」
いつもの展開ならそうなるのだが、今日は違った。
「そうかぁ、困ったなあ…いや、なんかな、近々ギャンダムのプラモが品薄になるみたいでな、その前にと思って大量に発注しててよ、それが今日入荷するんや…何とかならんか武いっちゃん?荷物は業者に運ばせるよってに。」
ここで発熱を理由に断固欠勤する事は実に容易かろう。
しかし、日頃は気持ちよく休ませてくれる優しい店主の頼みごとを断れる程、オレは高潔な魂を捨ててはいない。
更に、断れば絶対に心象を損なうのは明白である。
それは失職に繋がる。
「わかりました。仕事はできないかも知れませんけど、何とか店には入ってますわ。」
オレはできるだけ動かなくていいような前置きを入れて、店主に了解の意思を伝えた。
「悪いなあ!レジ打ちと接客以外はせんでええ、店にいてるだけでええからよ、頼んどくわ〜!」
悪いのはこっちである。
発熱の原因が、友達と心霊スポットに行って、呪詛をお土産にもらってきたなどとは口が裂けても言えない。
しかし、叔母の言いつけどおり、禊の塩風呂を欠かさぬ毎日を送っているにもかかわらず、呪詛が進行しているような気がする…
嘔吐感は収まりつつあるのだが、塩風呂からあがった後の湯船を見ると、湯が薄黒く変色し、見たこともない形の小さい蟲の死骸が浮いていたりもする。
これは親には見せられぬと湯を抜いて風呂を綺麗にしてから出なくてはならず、しかも水道代が勿体無いと母親から本気で怒られる始末…
更に、今日の発熱…
叔母は仕事が忙しく、なかなか来阪できないという。
呪詛に侵されているということは、一般的には生命の危機と捉えられて然るべきであると思うが、おそらく叔母は
『死ぬごと苦しいばってん、死ぬごたなか』
更に、
『バカチンが!いい薬ばい!』
くらいに思っているであろうから、叔母が来るまでは、何とか耐え抜かねばならぬ!
さて、バイトに行く準備をせねば…
オレは鉛のように重い身体を起こすと、まずシャワーを浴びようと風呂場へ向かった…
風呂場で服を脱ぎつつ、鏡が気になり目をやるとオレの右肩から人間の目から上の部分が顔を出している。
う〜む、とそれと鏡越しに目を合わせていると、瞬きする間にそれは掻き消えていた。
やれやれと思い風呂場に入ると、今度は風呂場に黒い人影が立っている。
オレと同じくらいの身長であるから、おそらく男性であろうと思われるが、正直邪魔である。
オレは心の中で、
『あの、誠に申し訳ないのですが…シャワー浴びたいので退出願えますか?』
と黒い人影にお願いしてみた。
しかし、人影は少しの揺らぎも見せず、ただそこに立っている。
今一度お願いしてみたが、やはり人影は微動だにしない。
腹が立ってきたので塩風呂用に風呂場の外に置いてある粗塩を手に掴むと、思いきりぶちまけてやった。
すると人影は塩にとけるナメクジのように小さくなって、消えた。
さて、ようやくと蛇口をひねりシャワーを浴び始めた。
あれ以来、霊との遭遇率が飛躍的に増している…
これも呪詛の影響なのだろうか…
いい機会である。
一度、この呪詛というものを本格化的に調べてみる必要がある…
シャワーを浴び終え、少しサッパリした気分でTシャツとジーンズに身を包む。
一応、風邪薬を服用し、少し横になってから外に出ると原チャリにまたがりバイト先へ向かう。
バイト先へは歩いていける距離なのだが、これだけ身体が重いと歩く気は失せる。
原チャリなら信号に捕まらなければ三分程でバイト先へ到着だ。
しかし、運悪く信号に捕まってしまった…
やはり、身体が重い。
は〜とため息をつきながら数秒目を閉じる…
よし!と熱に負けそうな自分を振るい立たせると、カッと目を見開いた。
すると、景色が変わっている。
目の前の信号は木製で、赤、黄、青のライトが血走った眼球に変わっている。
眼球の目の色はご丁寧に向かって左から赤、黄、青である。
見慣れた町並みはどこか知らない時代遅れの田園風景…
アスファルトの道路は砂利道になっていた。
信号は今、左の赤い瞳が光っている。
その光が消えると真ん中の黄の瞳が数回点滅して消える。
すると、右の青い瞳が光った。
『行って、いいのだろうか?』
一瞬考えこんだが、思い切って発進した。
どうやらオレは、わけのわからない世界に迷いこんだようである。
原チャリを走らせていると、田園風景の中に懐かしい案山子を見つけたが、よく見ると、それは生身の人間であり、感情のないような表情で、ただ立っている…
それが、まばらだが、結構な人数立っているのである。
全員、男性である。
のどかな田園風景の中に異彩を放つ生身の案山子達…
そのシュールを極めたような風景は、不思議とオレの心を和ませた…
オレはその一人一人の顔を確認しながら、ゆるゆると原チャリを走らていた…
「ん?」
思わず声を出て、原チャリを止めた。
生身の案山子達の中に見覚えのある顔が見える。
「北尾?」
その案山子は、明らかに友人の北尾であった。
オレは原チャリにまたがりながらき北尾に声をかけた。
「お〜い北尾!お前そんなとこで何やってんや?」
北尾はトレードマークである銀縁眼鏡を日光に光らせながら、
「やあ武市、見て分かると思うが、今オレはワーキングナウさ。悪いが邪魔しないでくれでっさ〜」
案山子の仕事をしているらしい。
似合うと言えば似合うが、バイトか?
しかし、何故こんなバイトを選んだのか理解に苦しむ。
時給はいくらなのか、無性に知りたくなった。
「北尾〜!その仕事、時給いくらよ〜?」
オレは北尾に尋ねた。
「ん〜?今は820円さ〜武市〜!お前の模型店のバイトの時給はハウマッチでっさ〜!」
北尾が答えてくれたのだから、こちらも時給を明かさざるをえまい。
「940円〜!」
すると北尾は、
「…」
黙り込んでしまった。
それから何度か声をかけたが、北尾は無視を続けた。
オレの時給が何か彼のプライドを傷つけたのかもしれぬ。
謝ろうとした瞬間、隣の案山子が、
「兄やん仕事の邪魔せんといたってくれるか〜!!こいつはこの仕事に人生かけてんねん!おちょくってたらシバキ回すぞワレ!」
と完全にキレている。
オレは原チャリを急発進させた。
原チャリを走らせながら、思った。
やはり、オレはわけのわからない世界に迷いこんでいる…
早く抜け出さねば、バイトに遅れてしまう…
今日は名作ロボットアニメ『希望戦士ギャンダム』のプラモが大量に入荷されるのだから…
第二話に続く
★回答者全員に5000円★新築マンション・新築一戸建て購入者アンケート★
2014年1月以降、首都圏・関西にて新築マンションを購入された方!
■■■■回答者全員に5000円!!■■■■

夏休みも終わりに近づいた今日、オレは昨晩から発熱し、床についていた。
熱を測ってみたら、三十九度…
なかなかの高熱である。
今日は昼からバイトがあるのだが、この体調では休まざるを得ない。
オレは携帯でバイト先に電話した。
長いコール音の後、電話が繋がった。
「はい、岩下ですが?」
バイト先である『イワシタ模型店』の店主が伝に出た。
このイワシタ模型店の息子は幼馴染で、そのツテで雇ってもらっている。
地元でも有数の資産家である岩下の家はいくつかの商売をしているが、この模型店は店主であるおじさんの道楽で始めたもので、おじさんは他の商売が忙しい為、ほとんど店に出ない。
よって、唯一のバイトであるオレは実質店長のようなものなのだが、昨今はあまり模型、つまりプラモデルが売れないので、仕事といえば掃除や棚卸し…一日中欠伸をして過ごしたこともある。
岩下家は、幼馴染の優二が優秀で東京の大学に進学したので、今は銀行員の優二の兄とおじさんとおばさんの三人家族である。
優二には悪いが、こんな楽な仕事はあるまいと、やりがいは感じないが、ここを辞める気は全くない。
「あ、冨田ですけど…おじさん、すみません…昨日から三十九度も熱出て体調悪いので、今日は休ませてもらっていいですか?」
「ああ、そうかぁ…ほな、ゆっくり休みや〜」
いつもの展開ならそうなるのだが、今日は違った。
「そうかぁ、困ったなあ…いや、なんかな、近々ギャンダムのプラモが品薄になるみたいでな、その前にと思って大量に発注しててよ、それが今日入荷するんや…何とかならんか武いっちゃん?荷物は業者に運ばせるよってに。」
ここで発熱を理由に断固欠勤する事は実に容易かろう。
しかし、日頃は気持ちよく休ませてくれる優しい店主の頼みごとを断れる程、オレは高潔な魂を捨ててはいない。
更に、断れば絶対に心象を損なうのは明白である。
それは失職に繋がる。
「わかりました。仕事はできないかも知れませんけど、何とか店には入ってますわ。」
オレはできるだけ動かなくていいような前置きを入れて、店主に了解の意思を伝えた。
「悪いなあ!レジ打ちと接客以外はせんでええ、店にいてるだけでええからよ、頼んどくわ〜!」
悪いのはこっちである。
発熱の原因が、友達と心霊スポットに行って、呪詛をお土産にもらってきたなどとは口が裂けても言えない。
しかし、叔母の言いつけどおり、禊の塩風呂を欠かさぬ毎日を送っているにもかかわらず、呪詛が進行しているような気がする…
嘔吐感は収まりつつあるのだが、塩風呂からあがった後の湯船を見ると、湯が薄黒く変色し、見たこともない形の小さい蟲の死骸が浮いていたりもする。
これは親には見せられぬと湯を抜いて風呂を綺麗にしてから出なくてはならず、しかも水道代が勿体無いと母親から本気で怒られる始末…
更に、今日の発熱…
叔母は仕事が忙しく、なかなか来阪できないという。
呪詛に侵されているということは、一般的には生命の危機と捉えられて然るべきであると思うが、おそらく叔母は
『死ぬごと苦しいばってん、死ぬごたなか』
更に、
『バカチンが!いい薬ばい!』
くらいに思っているであろうから、叔母が来るまでは、何とか耐え抜かねばならぬ!
さて、バイトに行く準備をせねば…
オレは鉛のように重い身体を起こすと、まずシャワーを浴びようと風呂場へ向かった…
風呂場で服を脱ぎつつ、鏡が気になり目をやるとオレの右肩から人間の目から上の部分が顔を出している。
う〜む、とそれと鏡越しに目を合わせていると、瞬きする間にそれは掻き消えていた。
やれやれと思い風呂場に入ると、今度は風呂場に黒い人影が立っている。
オレと同じくらいの身長であるから、おそらく男性であろうと思われるが、正直邪魔である。
オレは心の中で、
『あの、誠に申し訳ないのですが…シャワー浴びたいので退出願えますか?』
と黒い人影にお願いしてみた。
しかし、人影は少しの揺らぎも見せず、ただそこに立っている。
今一度お願いしてみたが、やはり人影は微動だにしない。
腹が立ってきたので塩風呂用に風呂場の外に置いてある粗塩を手に掴むと、思いきりぶちまけてやった。
すると人影は塩にとけるナメクジのように小さくなって、消えた。
さて、ようやくと蛇口をひねりシャワーを浴び始めた。
あれ以来、霊との遭遇率が飛躍的に増している…
これも呪詛の影響なのだろうか…
いい機会である。
一度、この呪詛というものを本格化的に調べてみる必要がある…
シャワーを浴び終え、少しサッパリした気分でTシャツとジーンズに身を包む。
一応、風邪薬を服用し、少し横になってから外に出ると原チャリにまたがりバイト先へ向かう。
バイト先へは歩いていける距離なのだが、これだけ身体が重いと歩く気は失せる。
原チャリなら信号に捕まらなければ三分程でバイト先へ到着だ。
しかし、運悪く信号に捕まってしまった…
やはり、身体が重い。
は〜とため息をつきながら数秒目を閉じる…
よし!と熱に負けそうな自分を振るい立たせると、カッと目を見開いた。
すると、景色が変わっている。
目の前の信号は木製で、赤、黄、青のライトが血走った眼球に変わっている。
眼球の目の色はご丁寧に向かって左から赤、黄、青である。
見慣れた町並みはどこか知らない時代遅れの田園風景…
アスファルトの道路は砂利道になっていた。
信号は今、左の赤い瞳が光っている。
その光が消えると真ん中の黄の瞳が数回点滅して消える。
すると、右の青い瞳が光った。
『行って、いいのだろうか?』
一瞬考えこんだが、思い切って発進した。
どうやらオレは、わけのわからない世界に迷いこんだようである。
原チャリを走らせていると、田園風景の中に懐かしい案山子を見つけたが、よく見ると、それは生身の人間であり、感情のないような表情で、ただ立っている…
それが、まばらだが、結構な人数立っているのである。
全員、男性である。
のどかな田園風景の中に異彩を放つ生身の案山子達…
そのシュールを極めたような風景は、不思議とオレの心を和ませた…
オレはその一人一人の顔を確認しながら、ゆるゆると原チャリを走らていた…
「ん?」
思わず声を出て、原チャリを止めた。
生身の案山子達の中に見覚えのある顔が見える。
「北尾?」
その案山子は、明らかに友人の北尾であった。
オレは原チャリにまたがりながらき北尾に声をかけた。
「お〜い北尾!お前そんなとこで何やってんや?」
北尾はトレードマークである銀縁眼鏡を日光に光らせながら、
「やあ武市、見て分かると思うが、今オレはワーキングナウさ。悪いが邪魔しないでくれでっさ〜」
案山子の仕事をしているらしい。
似合うと言えば似合うが、バイトか?
しかし、何故こんなバイトを選んだのか理解に苦しむ。
時給はいくらなのか、無性に知りたくなった。
「北尾〜!その仕事、時給いくらよ〜?」
オレは北尾に尋ねた。
「ん〜?今は820円さ〜武市〜!お前の模型店のバイトの時給はハウマッチでっさ〜!」
北尾が答えてくれたのだから、こちらも時給を明かさざるをえまい。
「940円〜!」
すると北尾は、
「…」
黙り込んでしまった。
それから何度か声をかけたが、北尾は無視を続けた。
オレの時給が何か彼のプライドを傷つけたのかもしれぬ。
謝ろうとした瞬間、隣の案山子が、
「兄やん仕事の邪魔せんといたってくれるか〜!!こいつはこの仕事に人生かけてんねん!おちょくってたらシバキ回すぞワレ!」
と完全にキレている。
オレは原チャリを急発進させた。
原チャリを走らせながら、思った。
やはり、オレはわけのわからない世界に迷いこんでいる…
早く抜け出さねば、バイトに遅れてしまう…
今日は名作ロボットアニメ『希望戦士ギャンダム』のプラモが大量に入荷されるのだから…
第二話に続く
★回答者全員に5000円★新築マンション・新築一戸建て購入者アンケート★
2014年1月以降、首都圏・関西にて新築マンションを購入された方!
■■■■回答者全員に5000円!!■■■■
2016年05月19日
扉シリーズ 第三章 『呪詛』 第二話 「武市2」著者:冨田武市
しかし、オレは今どういう状態にあるのか…
信号待ちをしていたら北尾が案山子のバイトをしているという奇妙な世界に迷い込んだ事は確かだが、これがもし、熱による幻覚でなく、オレが受けた呪詛の影響であるのなら、あまりに長閑過ぎる光景である。
田園の中に地平線が見える程長い直線のあぜ道…
青く晴れ渡った空には時折小鳥が通りかかり、気候もちょうどよく、風も爽やかだ…
オレはふと気づいた。
ここにきて、オレは一度も振り返っていない。
今まで走ってきた道は、今ちゃんとオレの背後に広がっているのか…
そう気になり、ふとミラーを見た。
ある。
道はちゃんとある。
やれやれと思って、再び前に目をやると、目の前に人が立っていた。
忘れもしない…八龍で遭遇した、あの老人だ…
老人は、口角を上げて、オレをみていた…
気がつくと、オレは空を見上げていた。
背中にはアスファルトの固い感触がある。
空には今にも雨が降り出しそうに、灰色の厚い雲が風に流されている…
「兄ちゃん、大丈夫か!?」
オレはどうやら、バイクで事故ったらしい…
道路に大の字で倒れ、空を見上げているのだ。
どうやら、帰ってきたらしい。
「おい兄ちゃん!兄ちゃん!大丈夫か!?」
隣で見知らぬオッサンが心配そうに大声でオレに呼びかけている。
背中に痛みはあるが、身体を起こせそうだ。
オレはゆっくりと上半身を起こし、後頭部を撫でながら、
「だ、大丈夫みたいです…」
オレは何とか声を絞り出してオッサンに答えた。
「そうか、よかったなあ兄ちゃん!ワシ、兄ちゃんの後ろにおったんやけど、信号青になったら兄ちゃん急発進して一人でこけるからよぉ、ワシ、ホンマにビックリしたで!」
そうか、そういう事か…
まんまとしてやられた。
やはり、オレは呪詛を受けているのだ。
今までは嘔吐程度で済んでいたが、ついに本格的に始まったのだと、オレは確信した。
しかし、身体が無事ならバイトに行かねば…
「あ、す、すみません…ホンマにご迷惑おかけしました。ありがとうございます…」
オレは立ち上がりながら御礼を述べると、原チャリを起こして動くかどうか確認してみた。
どうやら、動くようだ。
「ちょっ!兄ちゃん、ホンマに大丈夫なんか!?」
オッサンが信じられぬという顔でそう言った。
背中が痛いだけで身体は動く。
擦り傷等も見当たらない。
「あ、ホンマにありがとうございます…僕、バイト行かなアカンので行きますわ…」
オッサンはまだ何か言っていたが、行かねばならぬのだから、行くしかあるまい。
オレは原チャリを走らせてバイト先へ向かった。
バイト先へ到着すると、おじさんは外で待っていた。
オレが来るまでは、おじさんが店に入っている。
「おう武市っちゃん!ホンマにすまんなあ…ん?えらいボロボロやんか?何かあったんか?」
そう言われて身体を見ると、服が少し破れたり、汚れたりしていたが、エプロンをすれば目立たないだろう。
「いや、ちょっと鈍臭い事してしもて…大丈夫ですよ?」
オレは作り笑顔でそう答えた。
おじさんは大丈夫なら後は頼むと、忙しそうに車に乗って走り去った。
おそらくメインの仕事である不動産屋に向かったと思われる。
オレはカウンターに入り、エプロンをつけると椅子に腰掛けた。
ふと見ると、コンビニ袋が置いてあり、中には栄養ドリンクが入ってある。
これは千円くらいする高いやつだ。
おじさんが気を使ってくれたのだろうと、オレは栄養ドリンクを取り出すと、遠慮なくそれを頂いた。
客が来る様子も見えないので、オレはカウンターに突っ伏した。
熱のせいか、うつらうつらとしてしまう。
三十分ほどそうしていたであろうか…
ゾォン!
それは突然襲いかかってきた。
全身を貫く強烈な悪寒。
内臓にガツンとくるプレッシャー…
オレは突っ伏したまま、顔を上げる事もできずに、店内に感じる禍々しい気配に神経を集中した。
あの老人か、それに近しい存在が今、店内にいる…
それから発っせられる気配がゆるゆるとオレに近づいてきている…
全身から脂汗が滲み、嘔吐感がこみ上げてくる。
気配が近づいてくるにつれて、プレッシャーが大きくなる…
今、気配はカウンターに突っ伏すオレを見下ろしている…
あくまで感覚でしないが、店の屋根に頭が触れそうな程、かなりの大男であると感じた。
大男が、その大きな手をオレの頭に伸ばしてくるのを感じたその時、
「毎度!十河急便です!」
という声が聞こえて、オレはプレッシャーから解放された。
顔を上げると、十河急便の井園さんがいつもの爽やかな笑顔を向けてくれていた。
井園さんは一つ年上で、よくこのイワシタ模型店に荷物を持ってきてくれる。
「どうしたんよ冨田君?何か調子悪そうやなあ?」
井園さんはオレに送り状と伝票を手渡しながら心配してくれた。
「いやあ、昨日から熱っぽいな〜と思ってたら、三十九度も熱出やがってね…」
オレの答えに井園さんは口を開けてビックリしている。
「三十九度て!大丈夫なん?」
確かにしんどい…
しかし、今までは色んな霊障を受けてきたオレだ。
このくらいの熱なら、しんどくても耐えられる。
しかし、先ほどのドリンクが効いたのか、少し熱が下がってきたようにも感じていた。
井園さんはオレを心配しながらも荷物を運んでくれて、帰りに外の自販機でスポーツドリンクを買ってくれた。
バイトは五時までである。
それ以降ははまた、おじさんが店に入る。
おじさんの模型仲間が仕事帰りに来店したりするからだ。
やはり客が来る気配がないので、オレはまたカウンターに突っ伏した。
しかし、さっきの大男の気配…
初めてのタイプだ…
模型店は箱を積み上げたりしなくてはならないので、天井が高めに作られている…
おそらく、3メートル近くはあったのではなかろうか…
それは、人類の範疇を超えたデカさだ…
叔母から聞いた事がある。
サイズが狂っている霊や、外見が人間離れしてしまっている霊は、特に危険である。
それは、人間性を失っている証拠であるという事を…
もし、オレが受けている呪詛があんな怪物みたいなモノを引きつけているなら、今後、どんなヤバイやつが現れてくるかわかったものではない…
そんな事を考えていると、またうつらうつらとしてきた…
オレはいつの間にか寝てしまっていた。
どれくらい寝ていたのだろう…
人の気配がして顔を上げた。
黒い光沢のあるワイシャツ、黒いスラックス、そしてサングラスをした五十代くらいの男性客が来店した。
その出で立ちから一瞬木林かと思ったたが、首にかけた金のネックレスと、その身体から発っせられるオーラは明らかに素人ではない。
オレは少し緊張した。
男性客は店内を物色し、軍艦や戦闘機のコーナーで長く脚を止めた後、カウンターに近づいてくる。
オレの緊張はさらに高まった。
男性客はカウンターにもたれかかり、
「岩下さんはいないのかい?」
と尋ねてきた。
渋みのある太い声に、明らかに地元出身ではない標準語…
「あ、店長は五時過ぎには店にいますが…」
と言いながら、男性客の興味がその質問の答えではなく、オレ自身に向いていると感じた。
サングラスの奥の目に見られている。
しかもそれは、ただ単純にオレを見ているのではなかった…
「あのさ、言いにくいんだけど…君、このままじゃ危ないぜ?」
オレは瞬時にその意味を理解した。
この人は、今のオレの状態を見抜いている。
「わ、わかりますか?」
オレは尋ね返した。
男性客はサングラスを下にずらす。
かなりの修羅場をくぐり抜けてきたような鋭く強い視線が、オレを視た。
「…出会っちまったらほっとけないな…ここじゃどうにもできないからさ、今晩ここに来なよ。」
男性客はそう言いながら名刺を差し出した。
名刺には
『GEN'S BAR 伊田源二』
と書かれていた。
BARを経営しているらしい。
裏には店の地図が書いてある。
隣の蜘蛛取町にあり、オレの自宅から近かった。
オレはその名刺に目をやりながら、
「あ、あの、あなたは霊能者なんですか?」
素人ではないと感じたのは、そういう事なのだと思って直球で尋ねた。
伊田さんは少し黙り込むと、
「…少し違うが、似たようなもんさ…きみ、無理にとは言わないけどさ、来たほうがいいぜ?じゃあ、岩下さんにまた来るよって、よろしく伝えといてくれるかい?それじゃあ…」
伊田さんは颯爽と店を出て行った。
店内には大人な香水と、叔母に似た匂いの残り香が漂っていた…
二話終わり
三話へ続く
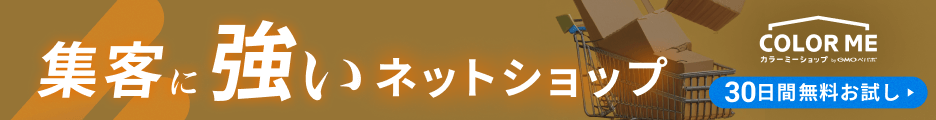

信号待ちをしていたら北尾が案山子のバイトをしているという奇妙な世界に迷い込んだ事は確かだが、これがもし、熱による幻覚でなく、オレが受けた呪詛の影響であるのなら、あまりに長閑過ぎる光景である。
田園の中に地平線が見える程長い直線のあぜ道…
青く晴れ渡った空には時折小鳥が通りかかり、気候もちょうどよく、風も爽やかだ…
オレはふと気づいた。
ここにきて、オレは一度も振り返っていない。
今まで走ってきた道は、今ちゃんとオレの背後に広がっているのか…
そう気になり、ふとミラーを見た。
ある。
道はちゃんとある。
やれやれと思って、再び前に目をやると、目の前に人が立っていた。
忘れもしない…八龍で遭遇した、あの老人だ…
老人は、口角を上げて、オレをみていた…
気がつくと、オレは空を見上げていた。
背中にはアスファルトの固い感触がある。
空には今にも雨が降り出しそうに、灰色の厚い雲が風に流されている…
「兄ちゃん、大丈夫か!?」
オレはどうやら、バイクで事故ったらしい…
道路に大の字で倒れ、空を見上げているのだ。
どうやら、帰ってきたらしい。
「おい兄ちゃん!兄ちゃん!大丈夫か!?」
隣で見知らぬオッサンが心配そうに大声でオレに呼びかけている。
背中に痛みはあるが、身体を起こせそうだ。
オレはゆっくりと上半身を起こし、後頭部を撫でながら、
「だ、大丈夫みたいです…」
オレは何とか声を絞り出してオッサンに答えた。
「そうか、よかったなあ兄ちゃん!ワシ、兄ちゃんの後ろにおったんやけど、信号青になったら兄ちゃん急発進して一人でこけるからよぉ、ワシ、ホンマにビックリしたで!」
そうか、そういう事か…
まんまとしてやられた。
やはり、オレは呪詛を受けているのだ。
今までは嘔吐程度で済んでいたが、ついに本格的に始まったのだと、オレは確信した。
しかし、身体が無事ならバイトに行かねば…
「あ、す、すみません…ホンマにご迷惑おかけしました。ありがとうございます…」
オレは立ち上がりながら御礼を述べると、原チャリを起こして動くかどうか確認してみた。
どうやら、動くようだ。
「ちょっ!兄ちゃん、ホンマに大丈夫なんか!?」
オッサンが信じられぬという顔でそう言った。
背中が痛いだけで身体は動く。
擦り傷等も見当たらない。
「あ、ホンマにありがとうございます…僕、バイト行かなアカンので行きますわ…」
オッサンはまだ何か言っていたが、行かねばならぬのだから、行くしかあるまい。
オレは原チャリを走らせてバイト先へ向かった。
バイト先へ到着すると、おじさんは外で待っていた。
オレが来るまでは、おじさんが店に入っている。
「おう武市っちゃん!ホンマにすまんなあ…ん?えらいボロボロやんか?何かあったんか?」
そう言われて身体を見ると、服が少し破れたり、汚れたりしていたが、エプロンをすれば目立たないだろう。
「いや、ちょっと鈍臭い事してしもて…大丈夫ですよ?」
オレは作り笑顔でそう答えた。
おじさんは大丈夫なら後は頼むと、忙しそうに車に乗って走り去った。
おそらくメインの仕事である不動産屋に向かったと思われる。
オレはカウンターに入り、エプロンをつけると椅子に腰掛けた。
ふと見ると、コンビニ袋が置いてあり、中には栄養ドリンクが入ってある。
これは千円くらいする高いやつだ。
おじさんが気を使ってくれたのだろうと、オレは栄養ドリンクを取り出すと、遠慮なくそれを頂いた。
客が来る様子も見えないので、オレはカウンターに突っ伏した。
熱のせいか、うつらうつらとしてしまう。
三十分ほどそうしていたであろうか…
ゾォン!
それは突然襲いかかってきた。
全身を貫く強烈な悪寒。
内臓にガツンとくるプレッシャー…
オレは突っ伏したまま、顔を上げる事もできずに、店内に感じる禍々しい気配に神経を集中した。
あの老人か、それに近しい存在が今、店内にいる…
それから発っせられる気配がゆるゆるとオレに近づいてきている…
全身から脂汗が滲み、嘔吐感がこみ上げてくる。
気配が近づいてくるにつれて、プレッシャーが大きくなる…
今、気配はカウンターに突っ伏すオレを見下ろしている…
あくまで感覚でしないが、店の屋根に頭が触れそうな程、かなりの大男であると感じた。
大男が、その大きな手をオレの頭に伸ばしてくるのを感じたその時、
「毎度!十河急便です!」
という声が聞こえて、オレはプレッシャーから解放された。
顔を上げると、十河急便の井園さんがいつもの爽やかな笑顔を向けてくれていた。
井園さんは一つ年上で、よくこのイワシタ模型店に荷物を持ってきてくれる。
「どうしたんよ冨田君?何か調子悪そうやなあ?」
井園さんはオレに送り状と伝票を手渡しながら心配してくれた。
「いやあ、昨日から熱っぽいな〜と思ってたら、三十九度も熱出やがってね…」
オレの答えに井園さんは口を開けてビックリしている。
「三十九度て!大丈夫なん?」
確かにしんどい…
しかし、今までは色んな霊障を受けてきたオレだ。
このくらいの熱なら、しんどくても耐えられる。
しかし、先ほどのドリンクが効いたのか、少し熱が下がってきたようにも感じていた。
井園さんはオレを心配しながらも荷物を運んでくれて、帰りに外の自販機でスポーツドリンクを買ってくれた。
バイトは五時までである。
それ以降ははまた、おじさんが店に入る。
おじさんの模型仲間が仕事帰りに来店したりするからだ。
やはり客が来る気配がないので、オレはまたカウンターに突っ伏した。
しかし、さっきの大男の気配…
初めてのタイプだ…
模型店は箱を積み上げたりしなくてはならないので、天井が高めに作られている…
おそらく、3メートル近くはあったのではなかろうか…
それは、人類の範疇を超えたデカさだ…
叔母から聞いた事がある。
サイズが狂っている霊や、外見が人間離れしてしまっている霊は、特に危険である。
それは、人間性を失っている証拠であるという事を…
もし、オレが受けている呪詛があんな怪物みたいなモノを引きつけているなら、今後、どんなヤバイやつが現れてくるかわかったものではない…
そんな事を考えていると、またうつらうつらとしてきた…
オレはいつの間にか寝てしまっていた。
どれくらい寝ていたのだろう…
人の気配がして顔を上げた。
黒い光沢のあるワイシャツ、黒いスラックス、そしてサングラスをした五十代くらいの男性客が来店した。
その出で立ちから一瞬木林かと思ったたが、首にかけた金のネックレスと、その身体から発っせられるオーラは明らかに素人ではない。
オレは少し緊張した。
男性客は店内を物色し、軍艦や戦闘機のコーナーで長く脚を止めた後、カウンターに近づいてくる。
オレの緊張はさらに高まった。
男性客はカウンターにもたれかかり、
「岩下さんはいないのかい?」
と尋ねてきた。
渋みのある太い声に、明らかに地元出身ではない標準語…
「あ、店長は五時過ぎには店にいますが…」
と言いながら、男性客の興味がその質問の答えではなく、オレ自身に向いていると感じた。
サングラスの奥の目に見られている。
しかもそれは、ただ単純にオレを見ているのではなかった…
「あのさ、言いにくいんだけど…君、このままじゃ危ないぜ?」
オレは瞬時にその意味を理解した。
この人は、今のオレの状態を見抜いている。
「わ、わかりますか?」
オレは尋ね返した。
男性客はサングラスを下にずらす。
かなりの修羅場をくぐり抜けてきたような鋭く強い視線が、オレを視た。
「…出会っちまったらほっとけないな…ここじゃどうにもできないからさ、今晩ここに来なよ。」
男性客はそう言いながら名刺を差し出した。
名刺には
『GEN'S BAR 伊田源二』
と書かれていた。
BARを経営しているらしい。
裏には店の地図が書いてある。
隣の蜘蛛取町にあり、オレの自宅から近かった。
オレはその名刺に目をやりながら、
「あ、あの、あなたは霊能者なんですか?」
素人ではないと感じたのは、そういう事なのだと思って直球で尋ねた。
伊田さんは少し黙り込むと、
「…少し違うが、似たようなもんさ…きみ、無理にとは言わないけどさ、来たほうがいいぜ?じゃあ、岩下さんにまた来るよって、よろしく伝えといてくれるかい?それじゃあ…」
伊田さんは颯爽と店を出て行った。
店内には大人な香水と、叔母に似た匂いの残り香が漂っていた…
二話終わり
三話へ続く
扉シリーズ 第三章 『呪詛』 第三話 「霊具」著者:冨田武市
伊田という男性客のつけていた香水の残り香が鼻をくすぐる…
呪詛を受けている今のオレの状況を見抜いたその目は、明らかに霊能関係者であり、相当な手練れであると思われる。
オレはまたカウンターに突っ伏して、今晩、伊田が経営しているBARに行くべきか、行かざるべきかを考えていた…
オレは生来、BARみたいなオシャレな場所とは縁遠く、正直苦手である…
しかし、これからも悪化していくであろう呪詛をどうにかしてもらえるなら、ためらっている場合ではない。
そういえば、何もオレ一人で店に行く必要などない。
近くにその道のエキスパートがいるではないか…
オレは携帯を手にとり、木林に電話をかけた。
「もしもし?おうおう武市、どないした?」
いつもの明るい木林の声に、オレは安堵感をおぼえた。
「アカンわ木林…だいぶ進行してきてるみたいやわ、クソ呪詛がよ…」
そういうオレに、木林は笑いながら、
「まだ風呂上がったら湯船のお湯黒いんけ?」
と尋ねてきたので、
「黒い黒い、真っ黒よ〜!北尾の腹の中くらい真っ黒やからな〜」
といって軽口で返した後、今日、俺の身に起こった事を報告した。
木林は笑気を口から漏らしつつオレの話を聞いている。
流石に北尾が案山子のバイトをしていたというくだりでは我慢ならずに吹き出して、
「あ〜ん、もしオレやったら笑死の可能性大よ〜!笑死も呪詛の結末の一つと思ってけつかってんやろなあ、あのジジイよ〜!」
あのジジイとは、八龍で遭遇した、あの老人の事である。
あの時、嘔吐するオレを介抱してくれた木林は事情を知っている為、木林には全てを話していた。
そして、バイト先で出会った伊田さんについて木林に話をし、今晩ついて来て欲しい旨を伝えた。
「そげなもん行くに決まってるやろ!武市〜、何時集合や〜?」
木林は乗り気で、集合時間は八時になった。
オレはやれやれと思い、そのまままたカウンターに突っ伏した。
結局、伊田さんの後の来客は三人。
三十代くらいの神経質そうな男性客が、今日入荷したばかりの『希望戦士ギャンダム』の人気ロボ、シュウ専用ザコを購入してくれたのが、唯一の売り上げだった。
夜…
オレはかなり体調が回復し、夕飯わ食べた後に塩風呂に浸かった。
体内に蓄積された悪いものが滲み出ていくように、体が軽くなってきた。
風呂から上がると、熱は完全に下がったようだ。
クーラーの効いた居間でしばらく寝転がってから服を着て外にでた。
オレはまた原チャリに跨ろうとしたが、そういえばBARに行くのなら飲まねばならぬと、徒歩で行く事にした。
地図によると、徒歩でも十分程で到着する距離である。
待ち合わせ場所は店の前。
ゆっくりと、夜風を楽しみながら、見慣れた景色のなかを歩く。
しかし…
大学に上がってから…特にこの夏休みに入ってからは、本当に色んな事が起こる。
まあ、よくない事が大半だが…
学生生活とは、こんなものなのだろうか…
実は、BARというものにはまだ行った事がない。
少しの緊張感は、見慣れた景色の色を少しだけ変えて見せていた。
店の前には既に木林がいた。
しかし、その隣には北尾がいる。
「やあ武市、お前からBARに誘うなんて、珍しい事もあるもんだなぁ…」
誘って、いないのだが…
おそらく木林が誘ったのだろう。
朝に会った時は時給820円で働く案山子だった北尾は、今、笑顔で銀縁眼鏡を光らせている。
店は飲食店やゲーセンなどが集まった、いわゆるプレイタウンの中にあった。
まあ、あくまで田舎のプレイタウンだが…
伊田さんの店はプレイタウンの角地にあった。
こじんまりとしているが、外壁とドアがブラックで、ドアにGEN'S BARという緑色のネオンが輝いている。
木林に促されて、オレは店のドアを開けた。
ドアを開けると、薄暗い店内には十人掛けくらいのカウンターがあり、六人掛けのボックス席にが二席ある。
カウンターの奥にはオシャレな写真やポスターが貼られてあり、見た事もない高そうな酒がズラっと並んでいる。
カウンターには、オレ達より少し年上くらいで、髪の長い色白の人と、ショートヘアで胸の大きい女性の二人が立っている。
「いらっしゃいませ〜」
と、カウンター席に座るよう促されたので、三人共素直に席に座る。
おしぼりを出されて、
「はじめまして、ですよね?ヒトミです〜」
髪の長い女性はヒトミさん。
「はじめまして、マミです。」
ショートの女性はマミさん。
「何にする?」
と言いながらヒトミさんが皿に盛りつけたお菓子を差し出す。
やはり慣れた木林が
「あ、とりあえずビールで。」
と落ち着いた対応を見せる。
やはり一緒にきてもらって良かった。
オレは今、女性達から漂う香水のいい香りにドキドキしていた。
マミさんが冷蔵庫からビールを3本出した。
BARでビールを注文すると、三本出てくるのだと、その時に学んだ。
ヒトミさんがグラスを取り出した。
グラスにビールが注がれるコポコポという音が、大人な音だと感じた。
そこからしばしお喋りをたのしんだが、肝心の伊田さんがいない…
「あの、伊田さんは?」
オレはこの店に来た本題を忘れてはいけないと、二人に尋ねてみた。
二人は顔を見合わせて、少しケラケラと笑うと、ヒトミさんが
「ああ、マスターやったら、そこにおるよ?」
とオレ達の背後にあるボックス席を指差した。
振り返ると、ボックス席にマスター…いや、伊田さんが座っていた。
いや待て!
さっき店に入ってきた時にはいなかったはずだ!
店内のどこにもいなかった。
いつ、どこから、どうやって現れたんだ!?
「やあ君、来てくれたんだね…こっちに来なよ。」
伊田さんはオレに手招きした。
木林が一声、
「渋〜」
と声を漏らした。
ヒトミさんとマミさんによると、伊田さんはほとんど気配がしないのだという。
だから、この店がオープンして働き始めた二人も、最初はよくビックリさせられたらしい。
木林と北尾は楽しく飲んでいるので、オレ一人、伊田さんのいるボックス席に移動した。
「あ、あの、こんばんは…昼には名前も言わなくてすみません…冨田武市と言います…」
オレはグラスを持ち、立ったままアタマを下げた。
伊田さんは少し笑うと、
「オレの方こそビックリさせたろう?緊張してるみたいだね?こういう所は初めてかい?まあ、いいから座りなよ…」
伊田さんはそう言って自分と対面の席を手でさした。
オレは頭をさげながらそこに座る。
すると伊田さんが、
「ヒトミ、あれを持ってきてくれるかい?」
とヒトミさんに指示した。
ヒトミさんはアッという表情でカウンターの下から何かを取り出してボックス席に持ってくる。
それはお盆の上に置かれた一本の高そうな毛筆と、墨石と硯、小さな瓶に入った水?それと数枚の和紙だった。
「冨ちゃん…」
伊田さんは見た目よりフレンドリーな人のようだ。
「その硯で墨を擦ってくれるかい?」
伊田さんはどこから取り出したのか新聞紙をテーブルに敷き、その上に和紙を載せながらそう言う。
オレは素直に墨石と硯を取り出す。
「水はその瓶の中身を使って」
指示通りに、オレは硯に水を垂らして、墨をすり始めた。
「できるだけ、集中して」
木林達の笑い声が気になるが、できるだけ気持ちを落ち着けて、墨をする。
数分間硯をすると、硯は並々と真っ黒な墨に満たされた。
「もういいよ。ありがとう。」
伊田さんはそういうと、毛筆を硯に浸けて墨を染み込ませる。
すると、伊田さんはその筆を和紙に塗りつけた。
和紙は、その繊維に沿ってオレが擦った墨を染み込ませていく。
伊田さんは筆を置くと、
「いいかい冨ちゃん、今からこの和紙に君を引っ張ろうとしてる奴の何らかの手がかりが浮かび上がる…」
オレを、引っ張る?
それは、オレが受けている呪詛の事を言っているのか?
オレはその和紙に何かが浮かび上がるのを待つ。
和紙に染み込んだ墨は不思議だが、しかし自然に何か文字の形を成していく…
鶴…
澤…
村…
和紙には、『鶴澤村』と浮かび上がった。
それは文字というより、水墨画のように、オレの目には映った。
鶴澤村…
鶴澤とは、オレや木林が住んでいる町の名前だが、鶴澤村?
今の鶴澤には村はつかない。
昔は鶴澤村だったのだろうか?
しかし、今気になるのは、今オレの目の前で起こった不思議な現象だ。
「あの、伊田さん、これは?」
オレは惚けたような顔で、そう尋ねた。
「これ等はオレがこさえた霊具でね…墨を擦った人間の中に潜む外的な霊障の手がかりを浮かび上がらせるのさ…」
霊具…
今からオレは今まで知らなかった霊能の世界を知る事になる…
第三話終わり
第四話へ続く
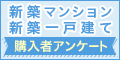

呪詛を受けている今のオレの状況を見抜いたその目は、明らかに霊能関係者であり、相当な手練れであると思われる。
オレはまたカウンターに突っ伏して、今晩、伊田が経営しているBARに行くべきか、行かざるべきかを考えていた…
オレは生来、BARみたいなオシャレな場所とは縁遠く、正直苦手である…
しかし、これからも悪化していくであろう呪詛をどうにかしてもらえるなら、ためらっている場合ではない。
そういえば、何もオレ一人で店に行く必要などない。
近くにその道のエキスパートがいるではないか…
オレは携帯を手にとり、木林に電話をかけた。
「もしもし?おうおう武市、どないした?」
いつもの明るい木林の声に、オレは安堵感をおぼえた。
「アカンわ木林…だいぶ進行してきてるみたいやわ、クソ呪詛がよ…」
そういうオレに、木林は笑いながら、
「まだ風呂上がったら湯船のお湯黒いんけ?」
と尋ねてきたので、
「黒い黒い、真っ黒よ〜!北尾の腹の中くらい真っ黒やからな〜」
といって軽口で返した後、今日、俺の身に起こった事を報告した。
木林は笑気を口から漏らしつつオレの話を聞いている。
流石に北尾が案山子のバイトをしていたというくだりでは我慢ならずに吹き出して、
「あ〜ん、もしオレやったら笑死の可能性大よ〜!笑死も呪詛の結末の一つと思ってけつかってんやろなあ、あのジジイよ〜!」
あのジジイとは、八龍で遭遇した、あの老人の事である。
あの時、嘔吐するオレを介抱してくれた木林は事情を知っている為、木林には全てを話していた。
そして、バイト先で出会った伊田さんについて木林に話をし、今晩ついて来て欲しい旨を伝えた。
「そげなもん行くに決まってるやろ!武市〜、何時集合や〜?」
木林は乗り気で、集合時間は八時になった。
オレはやれやれと思い、そのまままたカウンターに突っ伏した。
結局、伊田さんの後の来客は三人。
三十代くらいの神経質そうな男性客が、今日入荷したばかりの『希望戦士ギャンダム』の人気ロボ、シュウ専用ザコを購入してくれたのが、唯一の売り上げだった。
夜…
オレはかなり体調が回復し、夕飯わ食べた後に塩風呂に浸かった。
体内に蓄積された悪いものが滲み出ていくように、体が軽くなってきた。
風呂から上がると、熱は完全に下がったようだ。
クーラーの効いた居間でしばらく寝転がってから服を着て外にでた。
オレはまた原チャリに跨ろうとしたが、そういえばBARに行くのなら飲まねばならぬと、徒歩で行く事にした。
地図によると、徒歩でも十分程で到着する距離である。
待ち合わせ場所は店の前。
ゆっくりと、夜風を楽しみながら、見慣れた景色のなかを歩く。
しかし…
大学に上がってから…特にこの夏休みに入ってからは、本当に色んな事が起こる。
まあ、よくない事が大半だが…
学生生活とは、こんなものなのだろうか…
実は、BARというものにはまだ行った事がない。
少しの緊張感は、見慣れた景色の色を少しだけ変えて見せていた。
店の前には既に木林がいた。
しかし、その隣には北尾がいる。
「やあ武市、お前からBARに誘うなんて、珍しい事もあるもんだなぁ…」
誘って、いないのだが…
おそらく木林が誘ったのだろう。
朝に会った時は時給820円で働く案山子だった北尾は、今、笑顔で銀縁眼鏡を光らせている。
店は飲食店やゲーセンなどが集まった、いわゆるプレイタウンの中にあった。
まあ、あくまで田舎のプレイタウンだが…
伊田さんの店はプレイタウンの角地にあった。
こじんまりとしているが、外壁とドアがブラックで、ドアにGEN'S BARという緑色のネオンが輝いている。
木林に促されて、オレは店のドアを開けた。
ドアを開けると、薄暗い店内には十人掛けくらいのカウンターがあり、六人掛けのボックス席にが二席ある。
カウンターの奥にはオシャレな写真やポスターが貼られてあり、見た事もない高そうな酒がズラっと並んでいる。
カウンターには、オレ達より少し年上くらいで、髪の長い色白の人と、ショートヘアで胸の大きい女性の二人が立っている。
「いらっしゃいませ〜」
と、カウンター席に座るよう促されたので、三人共素直に席に座る。
おしぼりを出されて、
「はじめまして、ですよね?ヒトミです〜」
髪の長い女性はヒトミさん。
「はじめまして、マミです。」
ショートの女性はマミさん。
「何にする?」
と言いながらヒトミさんが皿に盛りつけたお菓子を差し出す。
やはり慣れた木林が
「あ、とりあえずビールで。」
と落ち着いた対応を見せる。
やはり一緒にきてもらって良かった。
オレは今、女性達から漂う香水のいい香りにドキドキしていた。
マミさんが冷蔵庫からビールを3本出した。
BARでビールを注文すると、三本出てくるのだと、その時に学んだ。
ヒトミさんがグラスを取り出した。
グラスにビールが注がれるコポコポという音が、大人な音だと感じた。
そこからしばしお喋りをたのしんだが、肝心の伊田さんがいない…
「あの、伊田さんは?」
オレはこの店に来た本題を忘れてはいけないと、二人に尋ねてみた。
二人は顔を見合わせて、少しケラケラと笑うと、ヒトミさんが
「ああ、マスターやったら、そこにおるよ?」
とオレ達の背後にあるボックス席を指差した。
振り返ると、ボックス席にマスター…いや、伊田さんが座っていた。
いや待て!
さっき店に入ってきた時にはいなかったはずだ!
店内のどこにもいなかった。
いつ、どこから、どうやって現れたんだ!?
「やあ君、来てくれたんだね…こっちに来なよ。」
伊田さんはオレに手招きした。
木林が一声、
「渋〜」
と声を漏らした。
ヒトミさんとマミさんによると、伊田さんはほとんど気配がしないのだという。
だから、この店がオープンして働き始めた二人も、最初はよくビックリさせられたらしい。
木林と北尾は楽しく飲んでいるので、オレ一人、伊田さんのいるボックス席に移動した。
「あ、あの、こんばんは…昼には名前も言わなくてすみません…冨田武市と言います…」
オレはグラスを持ち、立ったままアタマを下げた。
伊田さんは少し笑うと、
「オレの方こそビックリさせたろう?緊張してるみたいだね?こういう所は初めてかい?まあ、いいから座りなよ…」
伊田さんはそう言って自分と対面の席を手でさした。
オレは頭をさげながらそこに座る。
すると伊田さんが、
「ヒトミ、あれを持ってきてくれるかい?」
とヒトミさんに指示した。
ヒトミさんはアッという表情でカウンターの下から何かを取り出してボックス席に持ってくる。
それはお盆の上に置かれた一本の高そうな毛筆と、墨石と硯、小さな瓶に入った水?それと数枚の和紙だった。
「冨ちゃん…」
伊田さんは見た目よりフレンドリーな人のようだ。
「その硯で墨を擦ってくれるかい?」
伊田さんはどこから取り出したのか新聞紙をテーブルに敷き、その上に和紙を載せながらそう言う。
オレは素直に墨石と硯を取り出す。
「水はその瓶の中身を使って」
指示通りに、オレは硯に水を垂らして、墨をすり始めた。
「できるだけ、集中して」
木林達の笑い声が気になるが、できるだけ気持ちを落ち着けて、墨をする。
数分間硯をすると、硯は並々と真っ黒な墨に満たされた。
「もういいよ。ありがとう。」
伊田さんはそういうと、毛筆を硯に浸けて墨を染み込ませる。
すると、伊田さんはその筆を和紙に塗りつけた。
和紙は、その繊維に沿ってオレが擦った墨を染み込ませていく。
伊田さんは筆を置くと、
「いいかい冨ちゃん、今からこの和紙に君を引っ張ろうとしてる奴の何らかの手がかりが浮かび上がる…」
オレを、引っ張る?
それは、オレが受けている呪詛の事を言っているのか?
オレはその和紙に何かが浮かび上がるのを待つ。
和紙に染み込んだ墨は不思議だが、しかし自然に何か文字の形を成していく…
鶴…
澤…
村…
和紙には、『鶴澤村』と浮かび上がった。
それは文字というより、水墨画のように、オレの目には映った。
鶴澤村…
鶴澤とは、オレや木林が住んでいる町の名前だが、鶴澤村?
今の鶴澤には村はつかない。
昔は鶴澤村だったのだろうか?
しかし、今気になるのは、今オレの目の前で起こった不思議な現象だ。
「あの、伊田さん、これは?」
オレは惚けたような顔で、そう尋ねた。
「これ等はオレがこさえた霊具でね…墨を擦った人間の中に潜む外的な霊障の手がかりを浮かび上がらせるのさ…」
霊具…
今からオレは今まで知らなかった霊能の世界を知る事になる…
第三話終わり
第四話へ続く
2016年05月22日
扉シリーズ 第三章 『呪詛』 第四話 「職人」著者:冨田武市
霊具…
叔母から聞いた事がある。
この世には、人の祈りや恨みが込められた物体が存在する。
その中でも、何らかの目的の為に使用する事を前提として作られたものを『霊具』と呼ぶのだ。
しかし、それは偶然の産物であるものがほとんどらしい。
所有者に幸運をもたらしたり、不幸にしたりする宝石や、刀や壺などの骨董品、広義に捉えれば住むだけで不幸になる家も霊具にあてはまるかもしれない。
それらは元々は単純な使用目的で作られたものに祈りや恨みがしみついて誕生したものであろう。
しかし、伊田さんは今、『こさえた』と言った。
という事は、この硯や墨石等は意図的に作られたものだということになる。
そんな事が可能なのだろうか?
「冨ちゃん、この鶴澤村って何か心当たりはあるかい?」
伊田さんが和紙に染み出したその言葉について尋ねてきた。
「僕と、一緒に来た木林が住んでるとこが鶴澤っていうんですけど…村ではないですね…昔は村やったんかな…?」
オレは素直に答えた。
伊田さんは顎を撫でながら少し考えこむ。
何を考えているのだろう…?
「冨ちゃん…最近、どこかヤバイ場所に行ったよね?」
伊田さんがオレを見ながらそう尋ねる。
その目はバイト先でオレを見た、全てを見透かすような、あの目と同じ目であるように感じた。
「八龍っていう、心霊スポットに行きました。そこで…老人の霊を見ました…その老人に何かを言われて…その直前に嘔吐したんですが、嘔吐物体のなかに人間の爪みたいなのが混じってて…それ以来よく嘔吐するようになって…嘔吐物の中に色々な人間の破片みたいな物が混じるようになりました…」
オレはうつむきながら、淡々と答えた。
伊田さんはオレの言葉に耳を傾けながらも、何かを考えている…
すこしの沈黙の後、伊田さんはまた和紙に目をやりながら口を開く。
「その老人に何かを言われたと言ったね?その言葉、聞き取れたかい?」
その問いに、オレは胃のあたりに微かなプレッシャーを感じた。
「いえ…聞き取れませんでした…でも…あれは人間の声じゃないというか…発声じゃなかったように感じます…たぶん…普通の人間には知覚できない領域の音なんやないかと…」
伊田さんは何度かうなづきながらオレの答えを聞いた後、
「冨ちゃん…」
と、今までとは違ったトーンの声を発した。
いや、声は発していない。
これは、ダイレクトボイス?
伊田さんの意思が、オレの脳に直接伝わってくる。
『君はかなり鋭い方だから聞こえてるよね?』
オレはその答えを、頭の中で思い浮かべた。
そして、試しにその言葉を伊田さんの脳に投げるイメージで返してみた。
伊田さんがニヤリと口角を上げる。
伝わったのか?
『はい、聞こえます…朧げだが、確かに聞こえたよ、冨ちゃん。』
伊田さんの言葉が脳に響いた。
伊田さんの言った言葉は、オレが投げた言葉と一致している。
伝わったのだ…
これはテレパシーというやつなのでは?
伊田さんがクスリと笑う。
「テレパシーか…しかし、こいつは超能力でもなんでもない…誰にでもできる事なんだ…ただ、多少はセンスが必要なんだがね…で、君が遭遇した老人…その老人が発した言葉は、これを応用したもので、伝える言葉に呪詛をのせる…古来からそれは「邪声」や「邪思」と呼ばれる…」
「邪視」というものは聞いた事がある…
眼力によって相手の精神に作用し、その行動を操ったり、感情を支配したり、甚だしい場合には死に至らしめる恐ろしい呪いが込められた視線…
それと似た能力…いや、呪法なのか?
「しかしそれはね…この国に太古から伝わるという、今では名前もわからない一族にのみ伝わる呪法なんだ…」
名前もわからない一族…
太古から伝わる呪法…
その言葉に、オレは戦慄をおぼえた。
オレは今、想像以上にヤバイ状況におかれているのではないのか?
「冨ちゃん…俺にも確証は持てないが、もしそれだとすれば、こいつは相当難儀な事だぜ?」
嫌な事を、今最も信頼したい人から言われた事に、オレの不安は更に募る。
「しかし…よく今まで無事でいられたね…誰かに何かアドバイスを受けたりしたのかな?」
オレは気をとりなおして答えた。
「はい…実は、叔母が霊能者をやってまして…その叔母から毎日塩風呂に浸かるようにと…」
オレのその答えに、伊田さんの表情が変わった。
浮世離れした印象だった伊田さんの表情に、明らかに人間味がさした。
「その叔母さん、何て名前だい?」
伊田さんの口調が少し早口になった。
「あ、甲田福子と言います…」
伊田さんは一瞬動きを止めた後、
何故か肩を落として口を開く。
「そうか…そうだったのか…実はね、君の叔母さんとオレは、若い頃に同じ師匠の元で修業した仲間だったんだよ…」
予期していなかったわけではない…初めて会った時から、伊田さんには叔母に通じる何かを感じていた。
そういう事だったのか…
「君も何かを感じていたかもしれないが、実はオレも君に彼女に似た何かを感じていたんだ…そうか、そういう事だったか…塩風呂でピンときたんだが…あ、その塩風呂に使ってる塩ね、それ、福岡にいるオレの弟弟子がこさえたもんだと思うよ、たぶん…」
伊田さんのリアクションを見て、叔母とは懐かしいながらも、何か複雑な関係であるような印象を受けた。
しかし、やはりあの塩は何か特別なものなのだろう…
「それで君の霊感の鋭さにも納得したよ…霊感の鋭さは血筋にもよるからね…まあ、彼女は忙しい身だからね…アドバイスくらいしかできなかったんだろう…彼女なら君が受けている呪詛を何とかする事ができるかもしれない。しかし、それまでは、オレが面倒みるよ。呪詛の進行を食い止める事くらいはオレにもできるからね…」
伊田さん、そう言いながらまた和紙に目を向けた。
「鶴澤村か…冨ちゃん、オレの方でも調べてみるけど、君も調べてみてくれるかい?おそらく、根っこから断たないと、この呪詛は君の人生に一生ついてまわる事になる…」
無論、それについては調べてみるつもりだった。
オレは北尾の絵画の件以来、何かを大きな良くない渦の中に引き込まれつつあるイメージが脳裏にこびりついているのだ。
その渦の中心にある存在に近づく為の手がかりが、その鶴澤村にあるのだろうか?
カウンターでは木林と北尾が上機嫌で飲んでいる。
カウンターとボックス席は同じ空間にありながら、違う次元にあるのだと感じた。
あの老人に遭遇したのはオレだけではない…
そこにいる木林も遭遇しているのだ。
呪詛を受けたのがオレで良かったと思いながら、何故オレだけなのかという疑問もある。
霊感の鋭鈍が関係しているのか?
わからない事を考えても仕方ないのだが…
しかし、気になるのは伊田さんだ…
オレは伊田さんに疑問をぶつけてみた。
「あの、伊田さん…伊田さんは叔母と同じ霊能者ではないんですか?それに、何でオレを助けようとしてくれるんですか?」
伊田さんは今更何をという表情で答えた。
「オレは…霊能者にはなれなかった男さ…一番大事な所が少しだけ足りなかった…でもオレには別の才能があった…だからオレは霊具職人になった…これでも手先が器用でね…結構なんでも作れるんだぜ?装飾品から塩風呂の塩までね…冨ちゃん、コレを持ってるといい…」
伊田さんはそういうと、首からかけていたネックレスを外してオレに差し出した。
「こいつもオレの作品でね…常につけていれば、かなり効果を実感できると思うぜ?」
しかし、それはかなり高価なものであるように見える。
「でも伊田さん、これ、かなり高価なんじゃ?」
そう言いかけたオレを手で制した伊田さんは、
「野暮な事いうもんじゃないよ冨ちゃん…さっき、何で助けるのかって聞いたね?人間の行動全部に理由があるわけじゃない…そいつも野暮だぜ冨ちゃん?」
そう言って口角を上げる伊田さんがオレにはカッコ良く見えた。
オレには、この人から学ぶべき事がたくさんありそうだ。
その時、カウンター席にから物音が聞こえ、誰かがトイレに駆け込んだ。
振り返ると、木林がいない。
トイレから激しく嘔吐する声が聞こえ聞こえる。
木林がアルコールに負けた所を見た事はない。
嫌な予感に、オレは席から立ち上がった…
第四話 終わり
第五話へ続く


叔母から聞いた事がある。
この世には、人の祈りや恨みが込められた物体が存在する。
その中でも、何らかの目的の為に使用する事を前提として作られたものを『霊具』と呼ぶのだ。
しかし、それは偶然の産物であるものがほとんどらしい。
所有者に幸運をもたらしたり、不幸にしたりする宝石や、刀や壺などの骨董品、広義に捉えれば住むだけで不幸になる家も霊具にあてはまるかもしれない。
それらは元々は単純な使用目的で作られたものに祈りや恨みがしみついて誕生したものであろう。
しかし、伊田さんは今、『こさえた』と言った。
という事は、この硯や墨石等は意図的に作られたものだということになる。
そんな事が可能なのだろうか?
「冨ちゃん、この鶴澤村って何か心当たりはあるかい?」
伊田さんが和紙に染み出したその言葉について尋ねてきた。
「僕と、一緒に来た木林が住んでるとこが鶴澤っていうんですけど…村ではないですね…昔は村やったんかな…?」
オレは素直に答えた。
伊田さんは顎を撫でながら少し考えこむ。
何を考えているのだろう…?
「冨ちゃん…最近、どこかヤバイ場所に行ったよね?」
伊田さんがオレを見ながらそう尋ねる。
その目はバイト先でオレを見た、全てを見透かすような、あの目と同じ目であるように感じた。
「八龍っていう、心霊スポットに行きました。そこで…老人の霊を見ました…その老人に何かを言われて…その直前に嘔吐したんですが、嘔吐物体のなかに人間の爪みたいなのが混じってて…それ以来よく嘔吐するようになって…嘔吐物の中に色々な人間の破片みたいな物が混じるようになりました…」
オレはうつむきながら、淡々と答えた。
伊田さんはオレの言葉に耳を傾けながらも、何かを考えている…
すこしの沈黙の後、伊田さんはまた和紙に目をやりながら口を開く。
「その老人に何かを言われたと言ったね?その言葉、聞き取れたかい?」
その問いに、オレは胃のあたりに微かなプレッシャーを感じた。
「いえ…聞き取れませんでした…でも…あれは人間の声じゃないというか…発声じゃなかったように感じます…たぶん…普通の人間には知覚できない領域の音なんやないかと…」
伊田さんは何度かうなづきながらオレの答えを聞いた後、
「冨ちゃん…」
と、今までとは違ったトーンの声を発した。
いや、声は発していない。
これは、ダイレクトボイス?
伊田さんの意思が、オレの脳に直接伝わってくる。
『君はかなり鋭い方だから聞こえてるよね?』
オレはその答えを、頭の中で思い浮かべた。
そして、試しにその言葉を伊田さんの脳に投げるイメージで返してみた。
伊田さんがニヤリと口角を上げる。
伝わったのか?
『はい、聞こえます…朧げだが、確かに聞こえたよ、冨ちゃん。』
伊田さんの言葉が脳に響いた。
伊田さんの言った言葉は、オレが投げた言葉と一致している。
伝わったのだ…
これはテレパシーというやつなのでは?
伊田さんがクスリと笑う。
「テレパシーか…しかし、こいつは超能力でもなんでもない…誰にでもできる事なんだ…ただ、多少はセンスが必要なんだがね…で、君が遭遇した老人…その老人が発した言葉は、これを応用したもので、伝える言葉に呪詛をのせる…古来からそれは「邪声」や「邪思」と呼ばれる…」
「邪視」というものは聞いた事がある…
眼力によって相手の精神に作用し、その行動を操ったり、感情を支配したり、甚だしい場合には死に至らしめる恐ろしい呪いが込められた視線…
それと似た能力…いや、呪法なのか?
「しかしそれはね…この国に太古から伝わるという、今では名前もわからない一族にのみ伝わる呪法なんだ…」
名前もわからない一族…
太古から伝わる呪法…
その言葉に、オレは戦慄をおぼえた。
オレは今、想像以上にヤバイ状況におかれているのではないのか?
「冨ちゃん…俺にも確証は持てないが、もしそれだとすれば、こいつは相当難儀な事だぜ?」
嫌な事を、今最も信頼したい人から言われた事に、オレの不安は更に募る。
「しかし…よく今まで無事でいられたね…誰かに何かアドバイスを受けたりしたのかな?」
オレは気をとりなおして答えた。
「はい…実は、叔母が霊能者をやってまして…その叔母から毎日塩風呂に浸かるようにと…」
オレのその答えに、伊田さんの表情が変わった。
浮世離れした印象だった伊田さんの表情に、明らかに人間味がさした。
「その叔母さん、何て名前だい?」
伊田さんの口調が少し早口になった。
「あ、甲田福子と言います…」
伊田さんは一瞬動きを止めた後、
何故か肩を落として口を開く。
「そうか…そうだったのか…実はね、君の叔母さんとオレは、若い頃に同じ師匠の元で修業した仲間だったんだよ…」
予期していなかったわけではない…初めて会った時から、伊田さんには叔母に通じる何かを感じていた。
そういう事だったのか…
「君も何かを感じていたかもしれないが、実はオレも君に彼女に似た何かを感じていたんだ…そうか、そういう事だったか…塩風呂でピンときたんだが…あ、その塩風呂に使ってる塩ね、それ、福岡にいるオレの弟弟子がこさえたもんだと思うよ、たぶん…」
伊田さんのリアクションを見て、叔母とは懐かしいながらも、何か複雑な関係であるような印象を受けた。
しかし、やはりあの塩は何か特別なものなのだろう…
「それで君の霊感の鋭さにも納得したよ…霊感の鋭さは血筋にもよるからね…まあ、彼女は忙しい身だからね…アドバイスくらいしかできなかったんだろう…彼女なら君が受けている呪詛を何とかする事ができるかもしれない。しかし、それまでは、オレが面倒みるよ。呪詛の進行を食い止める事くらいはオレにもできるからね…」
伊田さん、そう言いながらまた和紙に目を向けた。
「鶴澤村か…冨ちゃん、オレの方でも調べてみるけど、君も調べてみてくれるかい?おそらく、根っこから断たないと、この呪詛は君の人生に一生ついてまわる事になる…」
無論、それについては調べてみるつもりだった。
オレは北尾の絵画の件以来、何かを大きな良くない渦の中に引き込まれつつあるイメージが脳裏にこびりついているのだ。
その渦の中心にある存在に近づく為の手がかりが、その鶴澤村にあるのだろうか?
カウンターでは木林と北尾が上機嫌で飲んでいる。
カウンターとボックス席は同じ空間にありながら、違う次元にあるのだと感じた。
あの老人に遭遇したのはオレだけではない…
そこにいる木林も遭遇しているのだ。
呪詛を受けたのがオレで良かったと思いながら、何故オレだけなのかという疑問もある。
霊感の鋭鈍が関係しているのか?
わからない事を考えても仕方ないのだが…
しかし、気になるのは伊田さんだ…
オレは伊田さんに疑問をぶつけてみた。
「あの、伊田さん…伊田さんは叔母と同じ霊能者ではないんですか?それに、何でオレを助けようとしてくれるんですか?」
伊田さんは今更何をという表情で答えた。
「オレは…霊能者にはなれなかった男さ…一番大事な所が少しだけ足りなかった…でもオレには別の才能があった…だからオレは霊具職人になった…これでも手先が器用でね…結構なんでも作れるんだぜ?装飾品から塩風呂の塩までね…冨ちゃん、コレを持ってるといい…」
伊田さんはそういうと、首からかけていたネックレスを外してオレに差し出した。
「こいつもオレの作品でね…常につけていれば、かなり効果を実感できると思うぜ?」
しかし、それはかなり高価なものであるように見える。
「でも伊田さん、これ、かなり高価なんじゃ?」
そう言いかけたオレを手で制した伊田さんは、
「野暮な事いうもんじゃないよ冨ちゃん…さっき、何で助けるのかって聞いたね?人間の行動全部に理由があるわけじゃない…そいつも野暮だぜ冨ちゃん?」
そう言って口角を上げる伊田さんがオレにはカッコ良く見えた。
オレには、この人から学ぶべき事がたくさんありそうだ。
その時、カウンター席にから物音が聞こえ、誰かがトイレに駆け込んだ。
振り返ると、木林がいない。
トイレから激しく嘔吐する声が聞こえ聞こえる。
木林がアルコールに負けた所を見た事はない。
嫌な予感に、オレは席から立ち上がった…
第四話 終わり
第五話へ続く
2016年05月24日
扉シリーズ 第三章 『呪詛』 第五話 「木林」著者:冨田武市
トイレから聞こえる木林が激しく嘔吐する声。
オレは立ち上がり、トイレのドア前に駆けた。
北尾も目を丸くしながら近づいてきて、
「さっきまで笑っていたのに…急に酒がまわったのか?しかし、木林が酒に負けるなんて、今まで見た事がないでっさ…」
と、オロオロしている。
後ろに気配がして振り返ると、伊田さんが立っていた。
「木林君…キバちゃんだったよね?彼も、行ったんだね?」
何かを感じとったのだろう、伊田さんが確信に満ちた声でそう尋ねてきた。
言葉は無用であろうと、オレは一つうなづいた。
しかし伊田さんは怪訝そうな声で
「彼にはかなり力のある守護霊が憑いてるんだけどな…それほど強力な呪詛だってことか…」
と言って腕組みした。
そういえばAYAさんもそんな事を言っていた…
そんなに強力ならオレでも何かを感じるはずだが…
「伊田さん、木林にはどんな守護霊が憑いてるんですか?」
オレは思いきって伊田さんに尋ねてみた。
親友であるオレには、奴に憑いているものを知る権利があるはずだ。
伊田さんは、
「あれ?冨ちゃんは、わからないのかい?」
と意外そうな表情を見せた。
意外だと言う事は、オレくらいのレベルでも、その存在を知覚できるはずなのだろう。
しかし、木林とは長い付き合いでありながら、オレはそれを一切感じとれない。
それには何か意味があるのだろうか?
伊田さんは少し眉間にシワをよせた後、何か閃いたように一度目を大きく見開いた後にトイレのドアを見つめたまま口を開く。
「彼には、銀色の長い髪を持った若い女性が憑いている…神官の様な服を着ているね…かなり強い力を持っている。彼女はおそらく神に近い存在か、下級の神かも知れない…だから冨ちゃんにはわからなかったのかも知れない…」
か、神?
木林に神が憑いてるって言うのか?
「か、神ですか?」
オレはあまりの事にうわずった声になってしまった。
伊田さんは一つうなづくと話を続ける。
「八百万の神って言うだろ?オレ達の国は世界一神が多い国と言えるのさ…元々極めて強い霊力を持っていた人間が無くなるとね、その人格はなかなか失われないのさ…それが現世にとどまり、長い時間を経ると、それは霊的に成長し続け、オレ達が神と呼ぶレベルの強い力を持つ様になる…彼に憑いてるのは、そういう存在さ…冨ちゃんはさ、霊感はかなり鋭い方だけど、正直、そういうのは信じてないだろ?」
オレはアッと口が開いた。
オレは霊感が鋭い方だ。
今まで色んなものを見て、色んな体験をしてきた。
しかし、それとこれとは話は別で、オレは無神論者なのだ。
神というものは、人間が発明した心の拠り所であり、自然災害の理由付けか、スケープゴートのようなものに過ぎないと思っていた。
しかし、神と聞いて思い出した。
木林は幼児の頃に猛スピードで走ってきた車と接触し、数十メートル跳ね飛ばされたが全くの無傷、すり傷一つなかったという経験をしている。
それは、通常考えてられない事だ。
しかし、それが木林に憑いているものの加護であるなら、それは神と呼んでもいいのかも知れない。
「信じていなければ、それは存在しない事になる。冨ちゃんは、ずっとそういう世界で生きてきたのさ…それが冨ちゃんの現実…しかし、神は存在する…それが真実さ…現実は色んな事で変わるものだけど、真実はどうやっても変わらない…」
所詮、現実は真実の一側面であるという意味か…
トイレから水が流れりる音がして、中からゴトゴトと物音がする。
ドアが開いて、ゲッソリとした表情の木林が出てきた。
木林はヨロヨロとしながらカウンターの一番端の席に腰掛ける。
ヒトミさんがすかさず氷の入った水を差し出した。
木林は無言で頭を下げなら、それを一気に飲み干す。
人心地ついたのか、木林がオレに手招きする。
オレは木林に顔を寄せた。
木林は小声で囁く。
「急に喉の奥でなんか違和感あって吐いたらよ…明らかに人毛よ〜人毛混ざってんよ〜、この気持ちよ〜」
木林はうなだれ、カウンターに突っ伏した。
やはり、木林にも呪詛の影響が出始めているようだ。
叔母なら一応、なんとかはしてくれるだろうが、叔母は来週まではこちらに来れない。
こちらから出向くこともできるが、叔母が忙しいという事は、それだけ霊障に苦しんでいる人が多いという事かも知れない。
そう考えると、たとえ甥と言えども、叔母の性格なら順番を無視する事はできないだろう。
その様子を見ていた伊田さんが、指にはめていた指輪を外して木林の肩に手を置く。
「キバちゃんって呼ばせてもらうよ。キバちゃん、これをつけておくといいよ。少しはマシになるはずだからさ…」
伊田さんはそう言うと、木林に指輪を手渡した。
銀色に輝くその指輪には、梵字のような装飾が施されている。
これも霊具なのだろう。
「キバちゃん、君に憑いてる守護霊は強力だけど、今は冨ちゃんと同じその呪詛に押されてしまっているみたいだ…それだけ、その呪詛が強力って事さ…」
オレはその時ハッと閃いた。
神か、それに近い存在をも抑える強い呪詛の力を持つもの…
それももしかしたら、神と呼べる存在なのかも知れない…
伊田さんは少し考え込んでから、また口を開いた。
「君達、今日は時間は大丈夫かい?」
まだそんなに遅い時間ではない。
木林にアイコンタクトすると、木林はうなづいた。
「大丈夫です。」
オレがそう答えると、
「ヒトミ、マミ、店を任せても構わないか?」
と伊田さんは二人の女性にそう尋ねた。
二人の女性はサムズアップで答えると、ヒトミさんが
「マスター、なんかよくわからんけども、いつもの感じのやつやよね?」
と尋ね返す。
「いつものってレベルじゃねえけどな…じゃ、店は任せたぜ?」
そういう伊田さんに、二人の女性はまたサムズアップで答えた。
「よし、じゃあ行こうか…」
い、行く?
一体どこへ行こうというんだ?
「あ、あの、伊田さん?一体どこへ?」
オレはまたうわずったような声で尋ねた。
「オレの家さ。今日できる事はやっておいた方がいいだろ?」
伊田さんはそう言いながら店の玄関に向かう。
オレ達もそれに続こうとしたが、その時、
「オレはどうしたらいいのでっさ?」
と、北尾がオロオロとそう尋ねてきた。
すると伊田さんは、
「君、名前は?」
と北尾に声をかけた。
「き、北尾公貴といいます…」
北尾は少し緊張した様子で名乗った。
「じゃあキミちゃんか…君は…そこで飲んでなよ?美人二人が相手なら退屈しないだろ?」
おそらく、北尾が全くの素人であると察した伊田さんの判断なのだろう。
すると北尾は、
「そうしたいのは山々なのですが、あいにく一人となると先立つものが…」
と、軍資金不足を心配する。
伊田さんはその答えにハハハと笑うと北尾に近づき、
「男なら野暮なこと言うじゃないよキミちゃん…サービスしとくからさ…」
と、北尾の肩に手をおいた。
北尾の鼻の下が伸びるのを、オレは見逃さなかった。
「さて、二人共、行こうか?」
伊田さんは颯爽と店を出る。
オレ達もそれに続く。
ドアを閉める前に聞こえた北尾の嬉しそうな笑い声が強く耳に残った…
第五話 終わり
第六話に続く


オレは立ち上がり、トイレのドア前に駆けた。
北尾も目を丸くしながら近づいてきて、
「さっきまで笑っていたのに…急に酒がまわったのか?しかし、木林が酒に負けるなんて、今まで見た事がないでっさ…」
と、オロオロしている。
後ろに気配がして振り返ると、伊田さんが立っていた。
「木林君…キバちゃんだったよね?彼も、行ったんだね?」
何かを感じとったのだろう、伊田さんが確信に満ちた声でそう尋ねてきた。
言葉は無用であろうと、オレは一つうなづいた。
しかし伊田さんは怪訝そうな声で
「彼にはかなり力のある守護霊が憑いてるんだけどな…それほど強力な呪詛だってことか…」
と言って腕組みした。
そういえばAYAさんもそんな事を言っていた…
そんなに強力ならオレでも何かを感じるはずだが…
「伊田さん、木林にはどんな守護霊が憑いてるんですか?」
オレは思いきって伊田さんに尋ねてみた。
親友であるオレには、奴に憑いているものを知る権利があるはずだ。
伊田さんは、
「あれ?冨ちゃんは、わからないのかい?」
と意外そうな表情を見せた。
意外だと言う事は、オレくらいのレベルでも、その存在を知覚できるはずなのだろう。
しかし、木林とは長い付き合いでありながら、オレはそれを一切感じとれない。
それには何か意味があるのだろうか?
伊田さんは少し眉間にシワをよせた後、何か閃いたように一度目を大きく見開いた後にトイレのドアを見つめたまま口を開く。
「彼には、銀色の長い髪を持った若い女性が憑いている…神官の様な服を着ているね…かなり強い力を持っている。彼女はおそらく神に近い存在か、下級の神かも知れない…だから冨ちゃんにはわからなかったのかも知れない…」
か、神?
木林に神が憑いてるって言うのか?
「か、神ですか?」
オレはあまりの事にうわずった声になってしまった。
伊田さんは一つうなづくと話を続ける。
「八百万の神って言うだろ?オレ達の国は世界一神が多い国と言えるのさ…元々極めて強い霊力を持っていた人間が無くなるとね、その人格はなかなか失われないのさ…それが現世にとどまり、長い時間を経ると、それは霊的に成長し続け、オレ達が神と呼ぶレベルの強い力を持つ様になる…彼に憑いてるのは、そういう存在さ…冨ちゃんはさ、霊感はかなり鋭い方だけど、正直、そういうのは信じてないだろ?」
オレはアッと口が開いた。
オレは霊感が鋭い方だ。
今まで色んなものを見て、色んな体験をしてきた。
しかし、それとこれとは話は別で、オレは無神論者なのだ。
神というものは、人間が発明した心の拠り所であり、自然災害の理由付けか、スケープゴートのようなものに過ぎないと思っていた。
しかし、神と聞いて思い出した。
木林は幼児の頃に猛スピードで走ってきた車と接触し、数十メートル跳ね飛ばされたが全くの無傷、すり傷一つなかったという経験をしている。
それは、通常考えてられない事だ。
しかし、それが木林に憑いているものの加護であるなら、それは神と呼んでもいいのかも知れない。
「信じていなければ、それは存在しない事になる。冨ちゃんは、ずっとそういう世界で生きてきたのさ…それが冨ちゃんの現実…しかし、神は存在する…それが真実さ…現実は色んな事で変わるものだけど、真実はどうやっても変わらない…」
所詮、現実は真実の一側面であるという意味か…
トイレから水が流れりる音がして、中からゴトゴトと物音がする。
ドアが開いて、ゲッソリとした表情の木林が出てきた。
木林はヨロヨロとしながらカウンターの一番端の席に腰掛ける。
ヒトミさんがすかさず氷の入った水を差し出した。
木林は無言で頭を下げなら、それを一気に飲み干す。
人心地ついたのか、木林がオレに手招きする。
オレは木林に顔を寄せた。
木林は小声で囁く。
「急に喉の奥でなんか違和感あって吐いたらよ…明らかに人毛よ〜人毛混ざってんよ〜、この気持ちよ〜」
木林はうなだれ、カウンターに突っ伏した。
やはり、木林にも呪詛の影響が出始めているようだ。
叔母なら一応、なんとかはしてくれるだろうが、叔母は来週まではこちらに来れない。
こちらから出向くこともできるが、叔母が忙しいという事は、それだけ霊障に苦しんでいる人が多いという事かも知れない。
そう考えると、たとえ甥と言えども、叔母の性格なら順番を無視する事はできないだろう。
その様子を見ていた伊田さんが、指にはめていた指輪を外して木林の肩に手を置く。
「キバちゃんって呼ばせてもらうよ。キバちゃん、これをつけておくといいよ。少しはマシになるはずだからさ…」
伊田さんはそう言うと、木林に指輪を手渡した。
銀色に輝くその指輪には、梵字のような装飾が施されている。
これも霊具なのだろう。
「キバちゃん、君に憑いてる守護霊は強力だけど、今は冨ちゃんと同じその呪詛に押されてしまっているみたいだ…それだけ、その呪詛が強力って事さ…」
オレはその時ハッと閃いた。
神か、それに近い存在をも抑える強い呪詛の力を持つもの…
それももしかしたら、神と呼べる存在なのかも知れない…
伊田さんは少し考え込んでから、また口を開いた。
「君達、今日は時間は大丈夫かい?」
まだそんなに遅い時間ではない。
木林にアイコンタクトすると、木林はうなづいた。
「大丈夫です。」
オレがそう答えると、
「ヒトミ、マミ、店を任せても構わないか?」
と伊田さんは二人の女性にそう尋ねた。
二人の女性はサムズアップで答えると、ヒトミさんが
「マスター、なんかよくわからんけども、いつもの感じのやつやよね?」
と尋ね返す。
「いつものってレベルじゃねえけどな…じゃ、店は任せたぜ?」
そういう伊田さんに、二人の女性はまたサムズアップで答えた。
「よし、じゃあ行こうか…」
い、行く?
一体どこへ行こうというんだ?
「あ、あの、伊田さん?一体どこへ?」
オレはまたうわずったような声で尋ねた。
「オレの家さ。今日できる事はやっておいた方がいいだろ?」
伊田さんはそう言いながら店の玄関に向かう。
オレ達もそれに続こうとしたが、その時、
「オレはどうしたらいいのでっさ?」
と、北尾がオロオロとそう尋ねてきた。
すると伊田さんは、
「君、名前は?」
と北尾に声をかけた。
「き、北尾公貴といいます…」
北尾は少し緊張した様子で名乗った。
「じゃあキミちゃんか…君は…そこで飲んでなよ?美人二人が相手なら退屈しないだろ?」
おそらく、北尾が全くの素人であると察した伊田さんの判断なのだろう。
すると北尾は、
「そうしたいのは山々なのですが、あいにく一人となると先立つものが…」
と、軍資金不足を心配する。
伊田さんはその答えにハハハと笑うと北尾に近づき、
「男なら野暮なこと言うじゃないよキミちゃん…サービスしとくからさ…」
と、北尾の肩に手をおいた。
北尾の鼻の下が伸びるのを、オレは見逃さなかった。
「さて、二人共、行こうか?」
伊田さんは颯爽と店を出る。
オレ達もそれに続く。
ドアを閉める前に聞こえた北尾の嬉しそうな笑い声が強く耳に残った…
第五話 終わり
第六話に続く
2016年05月26日
扉シリーズ 第三章 『呪詛』 第六話 「美弓」著者:冨田武市
「はぁぁ…」
思わず溜め息が出る。
明日の最終オーディション、絶対に失敗したくない。
高校を卒業して、この世界に入って三年目…
私は、今年のクリスマスに上演される舞台『忘れな草』の主人公オーディションの最終選考まで残れたのだ。
脚本・演出を、『世界の宮川』と呼ばれる宮川秀雄先生が務める大舞台だ。
もし、主人公役を射止める事ができれば、映画やドラマ出演への道が開けるかも知れない…
しかも、相手役はあのイケメン俳優『藤川敦也』…
あんなイケメンの恋人役が、手に届く所まで来ているのである。
しかし、脚本を読み込んでいるうちに、どうしても溜め息が出てしまう。
脚本1ページ分もある、この長ゼリフに対してだ…
おそらく、先生はこの長ゼリフを最重要視している事だろう…
正直、完璧に頭に叩き込んではいる…
問題は表現力である。
この重要な長ゼリフに込められた主人公の思いの全てをいかにお客さんに伝えるか…
それを考えていると、溜め息が止まらないのだ…
…
…
…
こういう時はお風呂に入って早く寝る方がいい。
答えを出せない事に悩んで煮詰まっているより、明日、自分の全てを発揮できるように体調を整える方が、遥かに生産的だ!
私は温度を低めに設定して、お風呂にお湯を張ると、しょっちゅうネット通販で購入しているお気に入りのバラの香りがする入浴剤をサラサラとお湯に落とした。
バラの香りが浴場に広がり、癒された気分になる。
私は入浴が長めで一時間くらい、たっぷりと湯に浸かる。
長湯のお供は常日頃から愛読している最上光夫という詩人の作品集だ。
優しく哀しい彼の世界観を、私は気にいっている。
衣服を脱ぎ、洗面所の鏡に映る生まれたままの自分の姿を見ると、まだまだ改善の余地があると思う。
特に、胸の辺りが…
まだ二十一歳である私には、それは伸びしろである。
私はまだまだ完成していないのだ!
再度バラの香りに包まれた浴室に入る。
軽くシャワーを浴びてから、湯船に身を預ける。
「ふ〜」
口元まで湯に浸かり、一つ溜め息をついた後、私は最上光夫の作品集を手にとる。
彼の作品で一番好きなのは『にんげん』というタイトルの長編詩だ。
『にんげん それは光とゐふ 神の造り賜うた芸術の極みが化身したる尊極の命』
から始まる人間愛の塊のようなこの長編詩には、いつ読んでも心を揺さぶられる。
…
…
…
ドアが開いた音がする。
…
…
…
あれ?お父さん、帰ってきたのかな?
まだ10時前だよ?
やけに早いなぁ…
もしかして、何かあったのかな…?
私は湯船から上がると、適当に身体を拭いてバスタオルを巻くとリビングに向かった。
「お父さ〜ん、やけに早いね〜」
バスタオル一枚だが、相手が父親なんだから問題ない。
私はリビングのドアを開けた。
中には、父親…と…
私は急いでドアを閉めた!
父親と、ゴリラ?
ゴリラと、何か黒いのがいた!
ていうか、ゴリラ!?
何でリビングにゴリラがいるの!?
思考がまとまらない。
私はとりあえず、
「お父さん!どういう事!?」
とドア越しに大きな声で父親に尋ねた。
父親はその声に
「美弓、お前いたのか?」
と間が抜けたような声で尋ね返してきた。
「いたよ!ていうか、誰か連れてくるなら電話の一本もよこしてよ!」
私はそう言いながら風呂場に戻った。
お父さんひどいよ!
若い娘がバスタオル一枚のあられもない姿を晒す事がどれほどの恥辱なのか、微塵も感じてないよ!
後で一言文句言わないと気がすまない!
私は長湯を取りやめ、洗髪して身体を洗い、さっと入浴を済ませると下着をつけて、お気に入りのピンクのパジャマに身を包んだ。
そのまま再度リビングまで移動する時、自分の足音がドシンドシンと、怒りに満ちているのを自覚した。
コンコン
私はノックした後、ドアを越しに
「お父さん!ちょっとこっちに来て!」
と父親を呼び出した。
父親はリビングのドアを少し開けて顔を出した。
「美弓、今さ、大事な話してるから、後にしてくれないか?」
その父親の言葉をに、私は怒りを込めて囁いた。
「娘がバスタオル一枚の姿を見られて何とも思わないの!?それに、あの人達、誰よ?」
父親はやれやれという、私の怒りをさらに刺激するような表情で、
「いいじゃないか、別に減るもんじゃないしさ…あ、それに、済まないけどさ、彼ら、今日はうちに泊めるから。」
というあり得ないことをサラリと返してきた。
もう許せないと思った時は、父親の口から意外な言葉が飛び出した。
「あの、ガッチリした彼さ、甲田の甥っ子さんなんだよ…」
甲田…?
もしかして、福子さんの?
甲田福子さんは、私が幼い頃から慕っている父親の友人だ。
それを聞いて、私の怒りは一気にトーンダウンした。
「福子さんの?」
私は自分の声が、グズっていた子供が他の事に興味が移った時の声に似ているような気がした。
しかし、あのゴリラみたいな男が優しくてキレイな福子さんの甥?
私の中で福子さんと彼のビジュアルを比較して、そこに血のつながりがあるというイメージが全く湧かなかった。
「美弓も、こっちに来るかい?」
その父親の誘いに、私は気がそそられた。
福子さんの甥…
どんな人間なのか、知りたい思いに駆られた。
福子さんの甥なら、『こちら側』の人間である可能性が高いからだ。
「うん…じゃあ飲み物とってくる…」
私はそう言ってキッチンに向かった。
後ろで父親が自分達の分はあるから、と言っていたので、私はキッチンで冷蔵庫から美容院にいいアセロラドリンクのペットボトルを取り出した。
冷蔵庫のドアを閉め、背中を向けた瞬間、冷蔵庫の中から
ドン!
という鈍い衝撃音がした。
背中に重苦しいプレッシャーと冷気を感じる。
はっと振り向くと、冷蔵庫はただブーンという起動音をたてているだけだった。
何かよくないモノを連れてきた、と私は思った。
コンコン
私は軽くノックして、リビングのドアを開けた。
リビングのソファーに福子さんの甥だというゴリラと黒ずくめの男が座っている。
テーブルを挟んで向かいに父親。
私はソファーに近づいて、
「こんばんわ、伊田美弓といいます。」
と引きつった笑顔で挨拶した。
こういう時に芝居ができない自分の性格に、女優としてはまだまだだと感じた。
ゴリラと黒いのは立ち上がり、
「はじめまして、冨田といいます。」
「木林です。遅い時間に突然申し訳ない。」
とそれぞれ名乗り、揃って二人で頭を下げた。
見た目とは違い、礼儀はわきまえているようだ。
私はまた、引きつった笑顔で会釈して、父親の隣に座った。
しかし、この黒ずくめの男は、黒が好きな隣にいる父親に影響されたのか、黒いワイシャツに黒いパンツ、髪は明るい茶髪で室内にも関わらずサングラスを着用している。
大きく開けた胸から覗く金のネックレスが胡散臭い印象を与えるが、まあ、なかなか可愛い顔をしている。
問題はその隣のゴリラだ。
白いTシャツの胸には青い文字で『FORCES』とプリントされており、ジーパンは膝が破れている。
この肩幅の広さは異常だ。
手も、分厚く大きい。
しかし、ギョロリとした目は、何となく福子さんを感じさせるものはある。
それだけでなく、やはり思った通り、訓練された様子は微塵も感じないが、霊感は相当鋭そうだ。
「父親から聞いたんですが、冨田さんは甲田福子さんの甥っ子さんなんですよね?」
私はいきなり直球を投げてみた。
すると冨田は
「あ、はい。甲田福子は僕の母親の末の妹にあたります。」
と、恥ずかしそうに目を合わせずに答えた。
見た目通り、女性に弱そうだ。
「いやあ、偶然って凄いですよね〜僕も話聞いてビックリしましたわ〜まさか伊田さんと福子先生が同門やったなんてね〜」
冨田に対して木林という男は社交的で、冨田に比べると大人に見える。
話を聞くと、木林も一度だけ福子さんに会った事があるらしい。
しかし、この二人の背中に漂っている黒く揺らめく人型のオーラ…
相当ヤバイ存在に見込まれてしまっているようだ…
明日は大事なオーディション…
こんな事に首を突っ込んでいる場合じゃないんだけど…
彼等の背中に漂う黒いオーラの正体を確かめたいという欲求が、少なからず私の足をここに留めているのだと、私は思った…
第六話 終わり
第七話に続く


思わず溜め息が出る。
明日の最終オーディション、絶対に失敗したくない。
高校を卒業して、この世界に入って三年目…
私は、今年のクリスマスに上演される舞台『忘れな草』の主人公オーディションの最終選考まで残れたのだ。
脚本・演出を、『世界の宮川』と呼ばれる宮川秀雄先生が務める大舞台だ。
もし、主人公役を射止める事ができれば、映画やドラマ出演への道が開けるかも知れない…
しかも、相手役はあのイケメン俳優『藤川敦也』…
あんなイケメンの恋人役が、手に届く所まで来ているのである。
しかし、脚本を読み込んでいるうちに、どうしても溜め息が出てしまう。
脚本1ページ分もある、この長ゼリフに対してだ…
おそらく、先生はこの長ゼリフを最重要視している事だろう…
正直、完璧に頭に叩き込んではいる…
問題は表現力である。
この重要な長ゼリフに込められた主人公の思いの全てをいかにお客さんに伝えるか…
それを考えていると、溜め息が止まらないのだ…
…
…
…
こういう時はお風呂に入って早く寝る方がいい。
答えを出せない事に悩んで煮詰まっているより、明日、自分の全てを発揮できるように体調を整える方が、遥かに生産的だ!
私は温度を低めに設定して、お風呂にお湯を張ると、しょっちゅうネット通販で購入しているお気に入りのバラの香りがする入浴剤をサラサラとお湯に落とした。
バラの香りが浴場に広がり、癒された気分になる。
私は入浴が長めで一時間くらい、たっぷりと湯に浸かる。
長湯のお供は常日頃から愛読している最上光夫という詩人の作品集だ。
優しく哀しい彼の世界観を、私は気にいっている。
衣服を脱ぎ、洗面所の鏡に映る生まれたままの自分の姿を見ると、まだまだ改善の余地があると思う。
特に、胸の辺りが…
まだ二十一歳である私には、それは伸びしろである。
私はまだまだ完成していないのだ!
再度バラの香りに包まれた浴室に入る。
軽くシャワーを浴びてから、湯船に身を預ける。
「ふ〜」
口元まで湯に浸かり、一つ溜め息をついた後、私は最上光夫の作品集を手にとる。
彼の作品で一番好きなのは『にんげん』というタイトルの長編詩だ。
『にんげん それは光とゐふ 神の造り賜うた芸術の極みが化身したる尊極の命』
から始まる人間愛の塊のようなこの長編詩には、いつ読んでも心を揺さぶられる。
…
…
…
ドアが開いた音がする。
…
…
…
あれ?お父さん、帰ってきたのかな?
まだ10時前だよ?
やけに早いなぁ…
もしかして、何かあったのかな…?
私は湯船から上がると、適当に身体を拭いてバスタオルを巻くとリビングに向かった。
「お父さ〜ん、やけに早いね〜」
バスタオル一枚だが、相手が父親なんだから問題ない。
私はリビングのドアを開けた。
中には、父親…と…
私は急いでドアを閉めた!
父親と、ゴリラ?
ゴリラと、何か黒いのがいた!
ていうか、ゴリラ!?
何でリビングにゴリラがいるの!?
思考がまとまらない。
私はとりあえず、
「お父さん!どういう事!?」
とドア越しに大きな声で父親に尋ねた。
父親はその声に
「美弓、お前いたのか?」
と間が抜けたような声で尋ね返してきた。
「いたよ!ていうか、誰か連れてくるなら電話の一本もよこしてよ!」
私はそう言いながら風呂場に戻った。
お父さんひどいよ!
若い娘がバスタオル一枚のあられもない姿を晒す事がどれほどの恥辱なのか、微塵も感じてないよ!
後で一言文句言わないと気がすまない!
私は長湯を取りやめ、洗髪して身体を洗い、さっと入浴を済ませると下着をつけて、お気に入りのピンクのパジャマに身を包んだ。
そのまま再度リビングまで移動する時、自分の足音がドシンドシンと、怒りに満ちているのを自覚した。
コンコン
私はノックした後、ドアを越しに
「お父さん!ちょっとこっちに来て!」
と父親を呼び出した。
父親はリビングのドアを少し開けて顔を出した。
「美弓、今さ、大事な話してるから、後にしてくれないか?」
その父親の言葉をに、私は怒りを込めて囁いた。
「娘がバスタオル一枚の姿を見られて何とも思わないの!?それに、あの人達、誰よ?」
父親はやれやれという、私の怒りをさらに刺激するような表情で、
「いいじゃないか、別に減るもんじゃないしさ…あ、それに、済まないけどさ、彼ら、今日はうちに泊めるから。」
というあり得ないことをサラリと返してきた。
もう許せないと思った時は、父親の口から意外な言葉が飛び出した。
「あの、ガッチリした彼さ、甲田の甥っ子さんなんだよ…」
甲田…?
もしかして、福子さんの?
甲田福子さんは、私が幼い頃から慕っている父親の友人だ。
それを聞いて、私の怒りは一気にトーンダウンした。
「福子さんの?」
私は自分の声が、グズっていた子供が他の事に興味が移った時の声に似ているような気がした。
しかし、あのゴリラみたいな男が優しくてキレイな福子さんの甥?
私の中で福子さんと彼のビジュアルを比較して、そこに血のつながりがあるというイメージが全く湧かなかった。
「美弓も、こっちに来るかい?」
その父親の誘いに、私は気がそそられた。
福子さんの甥…
どんな人間なのか、知りたい思いに駆られた。
福子さんの甥なら、『こちら側』の人間である可能性が高いからだ。
「うん…じゃあ飲み物とってくる…」
私はそう言ってキッチンに向かった。
後ろで父親が自分達の分はあるから、と言っていたので、私はキッチンで冷蔵庫から美容院にいいアセロラドリンクのペットボトルを取り出した。
冷蔵庫のドアを閉め、背中を向けた瞬間、冷蔵庫の中から
ドン!
という鈍い衝撃音がした。
背中に重苦しいプレッシャーと冷気を感じる。
はっと振り向くと、冷蔵庫はただブーンという起動音をたてているだけだった。
何かよくないモノを連れてきた、と私は思った。
コンコン
私は軽くノックして、リビングのドアを開けた。
リビングのソファーに福子さんの甥だというゴリラと黒ずくめの男が座っている。
テーブルを挟んで向かいに父親。
私はソファーに近づいて、
「こんばんわ、伊田美弓といいます。」
と引きつった笑顔で挨拶した。
こういう時に芝居ができない自分の性格に、女優としてはまだまだだと感じた。
ゴリラと黒いのは立ち上がり、
「はじめまして、冨田といいます。」
「木林です。遅い時間に突然申し訳ない。」
とそれぞれ名乗り、揃って二人で頭を下げた。
見た目とは違い、礼儀はわきまえているようだ。
私はまた、引きつった笑顔で会釈して、父親の隣に座った。
しかし、この黒ずくめの男は、黒が好きな隣にいる父親に影響されたのか、黒いワイシャツに黒いパンツ、髪は明るい茶髪で室内にも関わらずサングラスを着用している。
大きく開けた胸から覗く金のネックレスが胡散臭い印象を与えるが、まあ、なかなか可愛い顔をしている。
問題はその隣のゴリラだ。
白いTシャツの胸には青い文字で『FORCES』とプリントされており、ジーパンは膝が破れている。
この肩幅の広さは異常だ。
手も、分厚く大きい。
しかし、ギョロリとした目は、何となく福子さんを感じさせるものはある。
それだけでなく、やはり思った通り、訓練された様子は微塵も感じないが、霊感は相当鋭そうだ。
「父親から聞いたんですが、冨田さんは甲田福子さんの甥っ子さんなんですよね?」
私はいきなり直球を投げてみた。
すると冨田は
「あ、はい。甲田福子は僕の母親の末の妹にあたります。」
と、恥ずかしそうに目を合わせずに答えた。
見た目通り、女性に弱そうだ。
「いやあ、偶然って凄いですよね〜僕も話聞いてビックリしましたわ〜まさか伊田さんと福子先生が同門やったなんてね〜」
冨田に対して木林という男は社交的で、冨田に比べると大人に見える。
話を聞くと、木林も一度だけ福子さんに会った事があるらしい。
しかし、この二人の背中に漂っている黒く揺らめく人型のオーラ…
相当ヤバイ存在に見込まれてしまっているようだ…
明日は大事なオーディション…
こんな事に首を突っ込んでいる場合じゃないんだけど…
彼等の背中に漂う黒いオーラの正体を確かめたいという欲求が、少なからず私の足をここに留めているのだと、私は思った…
第六話 終わり
第七話に続く
2016年05月29日
扉シリーズ 第三章 『呪詛』 第七話 「儀式」著者:冨田武市
美弓さん…
伊田さんの一人娘である美弓さんは、かなりの美人だ。
少し明るめのブラウンで肩までありそうな髪を後ろで束ねており、かなりの細面で、顎のラインはかなりシャープだ。
目元がかなり伊田さんに似ていて目が大きく瞳が小さい。
色白で、肩幅が狭く女性らしいか弱さを感じさせる。
風呂上がりのいい香りが、彼女を一層魅力的に見せた。
伊田さんによれば、テレビで活躍しているタレントや俳優を輩出している老舗の劇団に所属し、映画女優を目指しているというが、このルックスなら納得である。
オレ達は改めて自己紹介も含めて、最近体験した北尾の絵画事件や八龍での出来事、さらに、今オレ達が抱えている問題、呪詛の事も話した。
腕組みをし、足も組んでソファに深く身を預ける美弓さんは少し機嫌が悪そうに見えるが、オレ達の話には真剣に耳を傾けてくれたようだったが、時折彼女がこちらに視線を送った時に、オレの背後を気にしているのに気づいた。
おそらく彼女の目には、オレ達が抱えている呪詛が何らかの形をなして見えているのだろう。
かなり霊感の鋭い女性であるように感じる。
それも、何らかの訓練を受けていて、知識も豊富であるように感じた。
会話が途切れた時、美弓さんが口を開いた。
「冨田さんは…訓練受けてないの?」
おそらく、話を聞きながらずっと気になっていたのではないか…
そんな口調だった。
美弓さんの疑問は当然である。
ある程度以上の鋭い霊感は、その持ち主である人間を決して幸福にはしない。
尋常な精神の持ち主なら、日常的にこの世のものでない者と接する事が日常生活に支障をきたさないわけがない。
それゆえ、その霊感の鋭さを、ある程度制御する術と、霊という者に対しての知識が必要になる。
霊感の鋭い人間の多くは、そういう術や知識がある事も知らず、ただじっと耐えるか、無関心を装い、生きていく。
しかし、この世には更に不幸な体質が存在する。
「集霊体質」
と
「霊媒体質」
である。
前者は浮遊霊を寄せつけてしまう体質であり、後者はその霊に憑依されやすい体質を指す。
オレは集霊体質の気がある。
叔母も幼い頃そうであったようだし、母親にもかすかにそれが伺える。
そういう者は、いつか必ず日常生活を全うできない日がやってくる為に、必ず訓練されるべきである。
しかも、オレは国内一とも言われる甲田福子の甥。
訓練されていて然るべきなのであるが、オレは訓練を受けていない。
しかし、叔母からは色々な話を聞かされているので、知識はそこそこのレベルにあるのではないかと思っている。
なぜ訓練を受けていないかと言うと、
「はい…何かオレが小さい頃、叔母のところで修業する事になってたらしいんですが…何か問題があったみたいで…まあ、中学に上がったくらいから修業に来いとは言われてたんですが、やっぱり中学生になったら色々ありますしね…正直、逃げてました…」
という事を美弓さんに答えた。
すると美弓さんは頭を掻きむしりながら、
「逃げてる場合じゃねえだろ…」
と、小声で呟いた。
木林にも聞こえたのか、オレの顔をみて目を丸くしている。
美弓さんのキツ目の突っ込みにオレのリアクションが気になったのだろう…
何も言い返せないオレに、伊田さんが助け舟を出してくれた。
「冨ちゃんの気持ちは最もな事さ…いざ修業を始めるとなると、一度は俗世間から完全に断絶されて、それこそ修行僧よりも厳しい修業をする事になるからね…」
その通りである。
叔母から説明は受けているが、修業の手始めとして、半年から一年くらいは俗世間から離れ、道場のような所で禁欲的な生活をしなければならない。
それにより、霊的に清廉な状態でないと、何も身にはつかないらしいのだ。
そんな事を考えて黙っていると、それに気づいたのか美弓さんがまた口を開いた。
「でも、もう逃げてる場合じゃない事くらいはわかってるよね…木林さんだったかな?君も、かなり強い守護霊が憑いてるみたいだけど、今、かなりヤバイよ?」
美弓さんの口調は冷たいが、心配してくれてるようには感じた。
「で、お父さん?今からやるの?」
美弓さんが伊田さんを見る。
「ああ、簡易的だけど甲田がこっちに来るまでは少しでも進行を遅らせないね…美弓、すまないけど、二人に浴衣を出して上げてくれるかい?」
伊田さんにそう頼まれた美弓さんは、ため息をついて
「はい、じゃあ浴衣出しとくし、お風呂も沸かし直すから、少し待って…」
と言って立ち上がるとリビングを出ていった。
伊田さんはリビングにある高そうな酒瓶が並ぶ棚から何かを取り出すと、それをテーブルに置いた。
見た事のある包みだ。
中身はおそらく粗塩。
いつもオレが塩風呂で使っている
のと同じものであるらしい。
という事は、これからオレ達は風呂に入る事になるのだろうか?
「冨ちゃんは知ってるよね?しかし、こいつはオレがこさえたやつだ。いつものやつよりキツイから心の準備はしといてくれよ?」
いつもよりキツイとはどういう意味だ?
心の準備とはどういう意味だ?
それよりも気になる事が…
「じゃあ二人とも風呂に入ってきてくれ…悪いが、一緒にお願いできるかい?男同士だからいいだろ?」
キタ!
悪い予感が現実になってキタ!
銭湯とかなら気にはならないが、家庭用の風呂で男二人はキツイ!
まさに拷問である。
隣を見ると、木林が目を見開き、口を開けている。
その瞳からは光が消えているように見えた。
しかし、それを拒否する権利がオレ達にはない事は、重々承知している。
しばらく無言の時が流れる。
30分程経った後、美弓さんが再びリビングに顔を出した。
「お風呂湧いたから…浴衣は風呂場においてあるから…」
美弓さんはそういうと、自室に行ったようだった。
オレは心を決め、すっと立ち上がると、
「伊田さんすみません…お風呂、頂きます…木林、しゃあないて、ちょっと我慢してくれ…」
なかなか立ち上がらない木林。
オレは木林の手を掴むと伊田さんに風呂場の位置を聞いて、塩を持って木林を引きずって風呂場へと向かった。
風呂場に着いて、オレは木林に服を脱ぐように命じた。
綺麗にたたまれた白い浴衣が二組、並んで置かれていた。
「気持ちよ〜ゴリラと混浴せなアカン、この気持ちよ〜」
木林の声が少し涙声に聞こえた。
風呂場を開けると、バラのいい香りがした。
さっき美弓さんからしたのと同じ香りだ。
オレは小さなお菓子の袋くらいの紙袋に入った塩をサラサラと湯船のお湯に入れた。
木林に先に入るように言うと、木林はもう観念したのか素直に風呂場に入り、シャワーを浴びてから湯船に入った。
オレもシャワーを浴びて風呂に入る。
木林の目に、涙が滲んでいる。
ザバーとお湯が溢れる。
溢れるお湯が収まり、オレ達は男二人には小さすぎる湯船の中、並んで湯船ね縁をつかみながら無言で時間を過ごした。
何かが身体の中から滲み出ていくように感じる…
木林がふと声を上げた。
「色、悪っ!」
その声に反応してお湯を見ると、墨汁のように黒くなっていく。
こんな黒さは初めてだ。
「武市よ?これ入ってて大丈夫なんか?」
木林がそう尋ねてくるが、オレもよくわからない。
しかし、これがキツイと言う事なのかと、
「たぶんな…」
と答えておいた。
しかし、またしばらくするとお湯がまた変色し始めた。
徐々に紫色になり、次第に赤みがかっていく。
「なんか、血みたいな色なってきたぞ?」
木林が少し青ざめたような声でそういった。
塩風呂は耐えることが大切である。
まだまだ我慢である。
お湯は、血の色に変わった。
それと呼応するかのように、何かが湯船の底から浮いてくる。
まず、爪のようなものが浮いてきた。
ドン退きする木林をなだめながら、じっと我慢していると、次には毛髪や皮膚の破片のようなものが浮いてきて、見た事のない小さな虫が浮いてきた。
さすがにオレも退いたが、まだまだ我慢する。
しかし、次に浮いてきたものには背筋が凍った。
眼球である。
二つの眼球がお湯に浮いてきたのだ。
上がろうとする木林の肩を押さえて、ひたすら我慢する。
心の準備とは、こういう事だったのか?
しばらくすると、お湯の色がまた黒く変色していく。
先ほどまで浮かんでいたものも、ほぼまた湯船の底へと沈んでいった。
ゲッソリしている木林をみて、また、いつもの身体が少し軽くなったような感じ…いや、いつもより軽く感じる…やはり伊田さんの塩は強力なのだろう…それも踏まえてそろそろ上がり時だろうと思った時、
「冨ちゃん、キバちゃん、もう上がっていいよ!」
という伊田さんの声が聞こえた。
その瞬間、木林が恐るべき早さで湯船から上がると、シャワーで身体を洗い流し始めた。
しかし、不思議な事に身体は汚れていないのである。
木林は首をかしげながら、
「武市、いつもこんな感じなんか?」
と尋ねてきた。
まあ、身体が汚れていないのは同じだが、いつもよりは凄まじい状況であったと木林に説明した。
風呂場から出たオレ達は浴衣に身を包む。
着方がわからないので適当だが、白い浴衣を着ると、何故か霊的に高まったような気分がした。
第七話 終わり
第八話に続く


伊田さんの一人娘である美弓さんは、かなりの美人だ。
少し明るめのブラウンで肩までありそうな髪を後ろで束ねており、かなりの細面で、顎のラインはかなりシャープだ。
目元がかなり伊田さんに似ていて目が大きく瞳が小さい。
色白で、肩幅が狭く女性らしいか弱さを感じさせる。
風呂上がりのいい香りが、彼女を一層魅力的に見せた。
伊田さんによれば、テレビで活躍しているタレントや俳優を輩出している老舗の劇団に所属し、映画女優を目指しているというが、このルックスなら納得である。
オレ達は改めて自己紹介も含めて、最近体験した北尾の絵画事件や八龍での出来事、さらに、今オレ達が抱えている問題、呪詛の事も話した。
腕組みをし、足も組んでソファに深く身を預ける美弓さんは少し機嫌が悪そうに見えるが、オレ達の話には真剣に耳を傾けてくれたようだったが、時折彼女がこちらに視線を送った時に、オレの背後を気にしているのに気づいた。
おそらく彼女の目には、オレ達が抱えている呪詛が何らかの形をなして見えているのだろう。
かなり霊感の鋭い女性であるように感じる。
それも、何らかの訓練を受けていて、知識も豊富であるように感じた。
会話が途切れた時、美弓さんが口を開いた。
「冨田さんは…訓練受けてないの?」
おそらく、話を聞きながらずっと気になっていたのではないか…
そんな口調だった。
美弓さんの疑問は当然である。
ある程度以上の鋭い霊感は、その持ち主である人間を決して幸福にはしない。
尋常な精神の持ち主なら、日常的にこの世のものでない者と接する事が日常生活に支障をきたさないわけがない。
それゆえ、その霊感の鋭さを、ある程度制御する術と、霊という者に対しての知識が必要になる。
霊感の鋭い人間の多くは、そういう術や知識がある事も知らず、ただじっと耐えるか、無関心を装い、生きていく。
しかし、この世には更に不幸な体質が存在する。
「集霊体質」
と
「霊媒体質」
である。
前者は浮遊霊を寄せつけてしまう体質であり、後者はその霊に憑依されやすい体質を指す。
オレは集霊体質の気がある。
叔母も幼い頃そうであったようだし、母親にもかすかにそれが伺える。
そういう者は、いつか必ず日常生活を全うできない日がやってくる為に、必ず訓練されるべきである。
しかも、オレは国内一とも言われる甲田福子の甥。
訓練されていて然るべきなのであるが、オレは訓練を受けていない。
しかし、叔母からは色々な話を聞かされているので、知識はそこそこのレベルにあるのではないかと思っている。
なぜ訓練を受けていないかと言うと、
「はい…何かオレが小さい頃、叔母のところで修業する事になってたらしいんですが…何か問題があったみたいで…まあ、中学に上がったくらいから修業に来いとは言われてたんですが、やっぱり中学生になったら色々ありますしね…正直、逃げてました…」
という事を美弓さんに答えた。
すると美弓さんは頭を掻きむしりながら、
「逃げてる場合じゃねえだろ…」
と、小声で呟いた。
木林にも聞こえたのか、オレの顔をみて目を丸くしている。
美弓さんのキツ目の突っ込みにオレのリアクションが気になったのだろう…
何も言い返せないオレに、伊田さんが助け舟を出してくれた。
「冨ちゃんの気持ちは最もな事さ…いざ修業を始めるとなると、一度は俗世間から完全に断絶されて、それこそ修行僧よりも厳しい修業をする事になるからね…」
その通りである。
叔母から説明は受けているが、修業の手始めとして、半年から一年くらいは俗世間から離れ、道場のような所で禁欲的な生活をしなければならない。
それにより、霊的に清廉な状態でないと、何も身にはつかないらしいのだ。
そんな事を考えて黙っていると、それに気づいたのか美弓さんがまた口を開いた。
「でも、もう逃げてる場合じゃない事くらいはわかってるよね…木林さんだったかな?君も、かなり強い守護霊が憑いてるみたいだけど、今、かなりヤバイよ?」
美弓さんの口調は冷たいが、心配してくれてるようには感じた。
「で、お父さん?今からやるの?」
美弓さんが伊田さんを見る。
「ああ、簡易的だけど甲田がこっちに来るまでは少しでも進行を遅らせないね…美弓、すまないけど、二人に浴衣を出して上げてくれるかい?」
伊田さんにそう頼まれた美弓さんは、ため息をついて
「はい、じゃあ浴衣出しとくし、お風呂も沸かし直すから、少し待って…」
と言って立ち上がるとリビングを出ていった。
伊田さんはリビングにある高そうな酒瓶が並ぶ棚から何かを取り出すと、それをテーブルに置いた。
見た事のある包みだ。
中身はおそらく粗塩。
いつもオレが塩風呂で使っている
のと同じものであるらしい。
という事は、これからオレ達は風呂に入る事になるのだろうか?
「冨ちゃんは知ってるよね?しかし、こいつはオレがこさえたやつだ。いつものやつよりキツイから心の準備はしといてくれよ?」
いつもよりキツイとはどういう意味だ?
心の準備とはどういう意味だ?
それよりも気になる事が…
「じゃあ二人とも風呂に入ってきてくれ…悪いが、一緒にお願いできるかい?男同士だからいいだろ?」
キタ!
悪い予感が現実になってキタ!
銭湯とかなら気にはならないが、家庭用の風呂で男二人はキツイ!
まさに拷問である。
隣を見ると、木林が目を見開き、口を開けている。
その瞳からは光が消えているように見えた。
しかし、それを拒否する権利がオレ達にはない事は、重々承知している。
しばらく無言の時が流れる。
30分程経った後、美弓さんが再びリビングに顔を出した。
「お風呂湧いたから…浴衣は風呂場においてあるから…」
美弓さんはそういうと、自室に行ったようだった。
オレは心を決め、すっと立ち上がると、
「伊田さんすみません…お風呂、頂きます…木林、しゃあないて、ちょっと我慢してくれ…」
なかなか立ち上がらない木林。
オレは木林の手を掴むと伊田さんに風呂場の位置を聞いて、塩を持って木林を引きずって風呂場へと向かった。
風呂場に着いて、オレは木林に服を脱ぐように命じた。
綺麗にたたまれた白い浴衣が二組、並んで置かれていた。
「気持ちよ〜ゴリラと混浴せなアカン、この気持ちよ〜」
木林の声が少し涙声に聞こえた。
風呂場を開けると、バラのいい香りがした。
さっき美弓さんからしたのと同じ香りだ。
オレは小さなお菓子の袋くらいの紙袋に入った塩をサラサラと湯船のお湯に入れた。
木林に先に入るように言うと、木林はもう観念したのか素直に風呂場に入り、シャワーを浴びてから湯船に入った。
オレもシャワーを浴びて風呂に入る。
木林の目に、涙が滲んでいる。
ザバーとお湯が溢れる。
溢れるお湯が収まり、オレ達は男二人には小さすぎる湯船の中、並んで湯船ね縁をつかみながら無言で時間を過ごした。
何かが身体の中から滲み出ていくように感じる…
木林がふと声を上げた。
「色、悪っ!」
その声に反応してお湯を見ると、墨汁のように黒くなっていく。
こんな黒さは初めてだ。
「武市よ?これ入ってて大丈夫なんか?」
木林がそう尋ねてくるが、オレもよくわからない。
しかし、これがキツイと言う事なのかと、
「たぶんな…」
と答えておいた。
しかし、またしばらくするとお湯がまた変色し始めた。
徐々に紫色になり、次第に赤みがかっていく。
「なんか、血みたいな色なってきたぞ?」
木林が少し青ざめたような声でそういった。
塩風呂は耐えることが大切である。
まだまだ我慢である。
お湯は、血の色に変わった。
それと呼応するかのように、何かが湯船の底から浮いてくる。
まず、爪のようなものが浮いてきた。
ドン退きする木林をなだめながら、じっと我慢していると、次には毛髪や皮膚の破片のようなものが浮いてきて、見た事のない小さな虫が浮いてきた。
さすがにオレも退いたが、まだまだ我慢する。
しかし、次に浮いてきたものには背筋が凍った。
眼球である。
二つの眼球がお湯に浮いてきたのだ。
上がろうとする木林の肩を押さえて、ひたすら我慢する。
心の準備とは、こういう事だったのか?
しばらくすると、お湯の色がまた黒く変色していく。
先ほどまで浮かんでいたものも、ほぼまた湯船の底へと沈んでいった。
ゲッソリしている木林をみて、また、いつもの身体が少し軽くなったような感じ…いや、いつもより軽く感じる…やはり伊田さんの塩は強力なのだろう…それも踏まえてそろそろ上がり時だろうと思った時、
「冨ちゃん、キバちゃん、もう上がっていいよ!」
という伊田さんの声が聞こえた。
その瞬間、木林が恐るべき早さで湯船から上がると、シャワーで身体を洗い流し始めた。
しかし、不思議な事に身体は汚れていないのである。
木林は首をかしげながら、
「武市、いつもこんな感じなんか?」
と尋ねてきた。
まあ、身体が汚れていないのは同じだが、いつもよりは凄まじい状況であったと木林に説明した。
風呂場から出たオレ達は浴衣に身を包む。
着方がわからないので適当だが、白い浴衣を着ると、何故か霊的に高まったような気分がした。
第七話 終わり
第八話に続く
2016年07月03日
扉シリーズ 第三章『呪詛』 第八話 「儀式2」
白い浴衣に着替えたオレと木林は、このような状態になければ、およそ見る事がなかったであろうお互いの白い浴衣姿に、唇から笑気を漏らした。
しかし、白い浴衣姿になろうとも、まだサングラスをかける事をやめない木林のこだわりは見上げたものだ。
もはや木林にとってサングラスは身体の一部分なのだろう。
サングラスが木林であり、木林がサングラスなのだ。
湯船な残る穢れたお湯は栓を抜いて流した。
その際、先ほどお湯に浮いてきた様々なモノを見かける事にはなかった。
あれは霊的なモノで、視覚にのみ影響を与える類いのモノで、物質として存在するものではないからだ。
一応、湯船もシャワーと残った粗塩で清めておいた。
オレ達は、今まで来ていた服を丁寧にたたんで小脇に抱えると、伊田さんが待つリビングへと戻った。
「二人共お疲れ」
リビングのソファに座り、そう言って笑顔を向ける伊田さんだったが、その目は笑っていなかった。
「どうだい?かなりキツかったろう?」
続けてそう尋ねる伊田さんに、オレ達は苦笑いで答えながら、伊田さんと対面する形でソファに腰掛けた。
伊田さんは唇から少し笑気を漏らしながら立ち上がると、酒瓶が並ぶ棚から一升瓶を一本取り出し、伊田さんとオレ達を隔てるテーブルにその一升瓶を置いた。
その一升瓶にはラベルがなく、中には液体がなみなみと詰まっている。
日本酒か?焼酎か?
酒瓶に入っているのだから、酒には違いなかろう。
「コイツはね、なかなかいい酒なんだぜ?」
オレの疑問を察したのか、伊田さんはそう言うと一升瓶の栓を抜き、瓶に直接口をつけて一口、中の液体を口に含んだ。
紳士的な伊田さんに似合わぬワイルドな飲み方にオレと木林は呆気にとられた。
しかし、伊田さんは口に含んだそれを飲み込まず、目を閉じ、口の中で転がし始めた。
オレ達はそれに目を奪われていた。
およそ10秒くらいそれを続けた後、伊田さんはかっと目を開き、口の中の液体をオレ達に吹きかけた。
突然の事にオレは目を閉じた。
「悪い悪い…しかし、やっぱりこうなるんだな…」
伊田さんの声に目を開ける。
そこには神妙な顔をした伊田さんがいる。
あれ?
そういえば、濡れていない…
隣で木林もそれに気づいて目を白黒させながらオレを見てくる。
「濡れてないだろ?コイツはね、とある神社で作ってる日本酒なんだけど…さっき禊をしたにも関わらず君らの身体はそれを受け付けない…コイツには場を清める力があるんだけど、そいつを掻き消しちまうんだからな…いいかい二人共、今から呪詛の進行を遅らせる為にかなりの荒療治をしなけりゃならない…オレの事、恨まないでくれよ?」
まっすぐな目でそういう伊田さんに、オレ達は首を縦に振る事しかできなかった…
オレ達はリビングの隣にある客間に案内された。
そこは殺風景な和室だった。
押入れ、箪笥、小さな机…
ここが客間?
しかし、そこには心地よい冷たさの神聖な空気が立ち込めている感じがした。
微かに香りのよい線香のような香りがする。
「客間にしては殺風景と思ったね?まあ、オレくらいの力でも除霊の真似事はできるからね…だから、ここは客間なのさ…」
そういう事かと納得した。
しかし、荒療治というのが気になる…
「あ、あの伊田さん?僕らはここで具体的にどんな目に遭わされるんですか?」
木林が突然そんな問いを切り出した。
伊田さんは少しだけ間を開けると、静かに答えた。
「オレは君らに対して特に何もしないよ…でも、今からかなりキツイ香を焚く…そいつは君らと呪詛の主を繋ぐ糸をあぶり出す…それがあぶり出たら、オレがそれを切る。でも、それをあぶり出す過程で、君らは相当苦しい思いをする事になる…でも耐えろ。糸があぶり出るまでは絶対にこの部屋を出ずに耐え抜いてくれ。そして、これだけは覚えていてくれ、どんなに苦しくても死ぬ事はない…いいかな?」
伊田さんの真剣な声に、自分の顔が青ざめていくのを感じた。
しかし、ここで退く事はできない。
今はこの伊田さんに頼る他、道はないのだ。
「わかりました…伊田さん、よろしくお願いします…」
オレがそう言って頭をさげると、木林も隣で頭を下げた。
伊田さんはそれを確認すると、小さな机の上に置いてあった、何やら複雑な、見た記憶のない文字や文様が刻まれた円形の香炉の蓋を開ける。
続いて、机の引き出しから瓶に入った植物を乾燥させた茶葉のようなものを取り出し、それを香炉に入れた。
「今から火をつけるけど、二人共準備はいいかな?」
伊田さんはオレ達の目をまっすぐに見つめながら尋ねてきた。
オレと木林は互いに見やり、うなづきあうと、
「よろしくお願いします」
とほぼ同時に答えた。
「わかった。最後にもう一度言うよ?どんなに苦しくても死ぬ事はない、頑張って耐えてくれ…」
伊田さんはそう言うと、右手の人差し指で香炉の円い縁をなぞり始めた。
リィーン
という金属の清い音が響く。
伊田さんが縁をなぞるスピードを速めていく。
その度に金属の清い音が徐々に大きくなっていく。
伊田さんは火をつける道具を一切手にしていない。
オレ達は伊田さんの縁をなぞる姿をただ見つめていた。
しばらくすると、香炉から煙が上がり始めた。
どんな原理かはわからないが、とにかく香に火がついたようだ。
煙を確認した伊田さんは、小さく唇を動かし、何かを呟き始めたが、声を聞き取る事ができない。
次第に煙の量が増していく。
高級で上品ないい香りが漂い始めた。
いい香りだな、と思った瞬間、オレの目の前の光景をがグニャリと歪み始めた…
第八話 終わり
第九話続く




しかし、白い浴衣姿になろうとも、まだサングラスをかける事をやめない木林のこだわりは見上げたものだ。
もはや木林にとってサングラスは身体の一部分なのだろう。
サングラスが木林であり、木林がサングラスなのだ。
湯船な残る穢れたお湯は栓を抜いて流した。
その際、先ほどお湯に浮いてきた様々なモノを見かける事にはなかった。
あれは霊的なモノで、視覚にのみ影響を与える類いのモノで、物質として存在するものではないからだ。
一応、湯船もシャワーと残った粗塩で清めておいた。
オレ達は、今まで来ていた服を丁寧にたたんで小脇に抱えると、伊田さんが待つリビングへと戻った。
「二人共お疲れ」
リビングのソファに座り、そう言って笑顔を向ける伊田さんだったが、その目は笑っていなかった。
「どうだい?かなりキツかったろう?」
続けてそう尋ねる伊田さんに、オレ達は苦笑いで答えながら、伊田さんと対面する形でソファに腰掛けた。
伊田さんは唇から少し笑気を漏らしながら立ち上がると、酒瓶が並ぶ棚から一升瓶を一本取り出し、伊田さんとオレ達を隔てるテーブルにその一升瓶を置いた。
その一升瓶にはラベルがなく、中には液体がなみなみと詰まっている。
日本酒か?焼酎か?
酒瓶に入っているのだから、酒には違いなかろう。
「コイツはね、なかなかいい酒なんだぜ?」
オレの疑問を察したのか、伊田さんはそう言うと一升瓶の栓を抜き、瓶に直接口をつけて一口、中の液体を口に含んだ。
紳士的な伊田さんに似合わぬワイルドな飲み方にオレと木林は呆気にとられた。
しかし、伊田さんは口に含んだそれを飲み込まず、目を閉じ、口の中で転がし始めた。
オレ達はそれに目を奪われていた。
およそ10秒くらいそれを続けた後、伊田さんはかっと目を開き、口の中の液体をオレ達に吹きかけた。
突然の事にオレは目を閉じた。
「悪い悪い…しかし、やっぱりこうなるんだな…」
伊田さんの声に目を開ける。
そこには神妙な顔をした伊田さんがいる。
あれ?
そういえば、濡れていない…
隣で木林もそれに気づいて目を白黒させながらオレを見てくる。
「濡れてないだろ?コイツはね、とある神社で作ってる日本酒なんだけど…さっき禊をしたにも関わらず君らの身体はそれを受け付けない…コイツには場を清める力があるんだけど、そいつを掻き消しちまうんだからな…いいかい二人共、今から呪詛の進行を遅らせる為にかなりの荒療治をしなけりゃならない…オレの事、恨まないでくれよ?」
まっすぐな目でそういう伊田さんに、オレ達は首を縦に振る事しかできなかった…
オレ達はリビングの隣にある客間に案内された。
そこは殺風景な和室だった。
押入れ、箪笥、小さな机…
ここが客間?
しかし、そこには心地よい冷たさの神聖な空気が立ち込めている感じがした。
微かに香りのよい線香のような香りがする。
「客間にしては殺風景と思ったね?まあ、オレくらいの力でも除霊の真似事はできるからね…だから、ここは客間なのさ…」
そういう事かと納得した。
しかし、荒療治というのが気になる…
「あ、あの伊田さん?僕らはここで具体的にどんな目に遭わされるんですか?」
木林が突然そんな問いを切り出した。
伊田さんは少しだけ間を開けると、静かに答えた。
「オレは君らに対して特に何もしないよ…でも、今からかなりキツイ香を焚く…そいつは君らと呪詛の主を繋ぐ糸をあぶり出す…それがあぶり出たら、オレがそれを切る。でも、それをあぶり出す過程で、君らは相当苦しい思いをする事になる…でも耐えろ。糸があぶり出るまでは絶対にこの部屋を出ずに耐え抜いてくれ。そして、これだけは覚えていてくれ、どんなに苦しくても死ぬ事はない…いいかな?」
伊田さんの真剣な声に、自分の顔が青ざめていくのを感じた。
しかし、ここで退く事はできない。
今はこの伊田さんに頼る他、道はないのだ。
「わかりました…伊田さん、よろしくお願いします…」
オレがそう言って頭をさげると、木林も隣で頭を下げた。
伊田さんはそれを確認すると、小さな机の上に置いてあった、何やら複雑な、見た記憶のない文字や文様が刻まれた円形の香炉の蓋を開ける。
続いて、机の引き出しから瓶に入った植物を乾燥させた茶葉のようなものを取り出し、それを香炉に入れた。
「今から火をつけるけど、二人共準備はいいかな?」
伊田さんはオレ達の目をまっすぐに見つめながら尋ねてきた。
オレと木林は互いに見やり、うなづきあうと、
「よろしくお願いします」
とほぼ同時に答えた。
「わかった。最後にもう一度言うよ?どんなに苦しくても死ぬ事はない、頑張って耐えてくれ…」
伊田さんはそう言うと、右手の人差し指で香炉の円い縁をなぞり始めた。
リィーン
という金属の清い音が響く。
伊田さんが縁をなぞるスピードを速めていく。
その度に金属の清い音が徐々に大きくなっていく。
伊田さんは火をつける道具を一切手にしていない。
オレ達は伊田さんの縁をなぞる姿をただ見つめていた。
しばらくすると、香炉から煙が上がり始めた。
どんな原理かはわからないが、とにかく香に火がついたようだ。
煙を確認した伊田さんは、小さく唇を動かし、何かを呟き始めたが、声を聞き取る事ができない。
次第に煙の量が増していく。
高級で上品ないい香りが漂い始めた。
いい香りだな、と思った瞬間、オレの目の前の光景をがグニャリと歪み始めた…
第八話 終わり
第九話続く
2016年07月05日
扉シリーズ 第三章 第九話 「儀式3」
グニャリと歪む景色が、螺旋を描きながら渦を巻き始めた。
隣で交直している木林の身にも同じ事がおこっているようだ。
渦の中心、即ち視界の中心に向かって、景色が吸い込まれていく。
伊田さんの姿も、その渦に吸い込まれていく。
すべての景色が吸い込まれた後、そこには闇があった。
闇そのものが渦を巻いている。
眼を凝らすと、渦の中心には暗黒の穴が開いていた。
今、己が置かれている状況への恐怖、また、未知の事象に対する少しの高揚感に包まれたオレの意識すら、その渦の中心にある穴に吸い込まれていく…
己の意識が目の前に広がる螺旋状の真っ黒い海に溶けていくような感覚の中、オレはオレである境界線を越えたような気がした…
頬っぺたに冷たい感覚を覚えて、オレは自我を取り戻した。
パッと眼を開くと、そこには見知らぬ天井があった。
ヌメッした湿っぽい光沢のあるゴツゴツとした岩から、時折、水の粒が滴っている。
それを眺めながら、今オレは…いや、オレの意識は洞窟のような場所にあるのだという事を悟った。
背中にも天井と同じようなヌメッとした冷たさと、岩の尖った部分が当たる感覚もある。
オレはどうやら、洞窟のような場所で寝ていた?いや、倒れていたのか?
明かりはないが、そこかしこに群生している苔が光を発しているように見える。
ヒカリゴケという物か?
オレは上半身を起こしてみた。
周りを見渡すと、やはり洞窟のようだ…
オレの正面、そして背後にも洞窟は続いているようだ…
…
…
…
木林は?
木林はどこだ?
…
…
…
どうやら、オレ一人であるようだ。
これはオレの意識内の場所なのだろうか?
しかし、こんな場所にまるで覚えもないし、心当たりもない。
さらに、オレがオレであるという自覚すら、霞みがかったようにおぼろげに感じる。
オレは自分の手のひらを顔の前にかざしてみた。
オレの手のひらは、輪郭のみそれらしいのだが、まるでボカシ加工された映像のよいにぼやけて見える。
自分の下半身に視線を移してみても、同じようにボヤけて見える。
自分の存在自体が不確かで、ロウソクの火のように強く吹けば消えてしまいそうな気がする。
オレは恐る恐るその場で立ち上がってみた。
どうやら立てるが、立ち上がってみても、やはり自分の存在が不確かであるという感覚は消えない。
オレは何故ここに在るのか?
また、ここで何をすればいいのか?
それさえわからぬ状況は、オレに不安以外を与えてくれない。
眼は見える。
音は聞こえる。
触覚もある。
考える事、思う事もできる。
しかし、それらをどう使えばよいのかが全くわからない。
しばし立ち尽くした後、オレはここにこうしていても、状況は変わらないと判断し、とりあえず、今自分が向いている方向に歩いてみる事にした。
歩き始めて、初めて意識したのだが、かなり広い洞窟のようだ。
天井もかなり高く、10メートル近くあるのではなかろうか…?
やはりそこかしこにヒカリゴケのような物が生えており、行く道を照らしてくれている。
しかし、先は途方もなく長い…
オレは不安に支配されながらも、延々と続く同じ景色の中、不確かな一歩一歩を道に刻んでいった…
どれだけ歩いたのだろうか…?
今までの人生でおよそ歩いた事のない距離をオレは歩いた。
不思議と全く疲れを感じない。
今、オレの意識は夢の中と同じような、物理法則に縛られない状態にあるのだろうと感じる。
試しに、走ってみた。
いくらでも走れる。
全く呼吸が乱れる事もない。
しかも、凄い速さで走れる。
中高と陸上部で短距離をやってきたオレの感覚で測れば、少なくとも五輪のトラック種目すべてで金メダルを獲得できるであろうくらいのスピードと持久力である。
まあ、物理法則に縛られないのなら当たり前の事なのだろうが…
しかし、景色は延々と変わらない。
ずっとループしているように、オレは同じ景色の中を駆けた。
駆けた距離だけ不安が募る。
このまま走り続けて何か変わる保障があるのか?
別の事をすべきではないのか?
そう考えて、オレは走る事をやめた。
立ち止まって、ふと思った。
物理法則に縛られないのなら、ここから出る事もまた、簡単な事なのではないか?
そう思った瞬間、背後から気配を感じた。
自分以外の何者かの気配である。
不安の中に光明が差す。
その気配がオレに何をもたらす者なのかはさておき、自分以外の他者が背後にあるのなら、それを求めるのが人間の性である。
オレは振り返った。
…
…
…
振り返るべきではなかったのかも知れない。
オレは今、見てはいけないものを目の当たりにしてしまった。
オレが今まで駆けてきた途方もない距離…
それを追いかけてきたかのようにはるかに続く鎖…
無数の人間の姿をした肉の鎖が、遥か向こうから続いていて、オレの脚にまで繋がっている。
「うあああああ!!」
オレは悲鳴を上げたが、洞窟はそれを響かせること無く、それを吸収した。
その声に反応したのか、連なる肉の鎖たちのおびただしい目が一斉にオレを見た。
その視線の一つ一つが、まるで矢のようにオレの心臓に突き刺さるような感覚を覚えた。
そして、その肉の鎖の最先端、オレの両脚をつかむ腕の持ち主を確認した時、オレの思考は停止した。
その肉の鎖の最先端は、見覚えのある…いや、忘れるはずもない親友、木林の姿をしていた…
隣で交直している木林の身にも同じ事がおこっているようだ。
渦の中心、即ち視界の中心に向かって、景色が吸い込まれていく。
伊田さんの姿も、その渦に吸い込まれていく。
すべての景色が吸い込まれた後、そこには闇があった。
闇そのものが渦を巻いている。
眼を凝らすと、渦の中心には暗黒の穴が開いていた。
今、己が置かれている状況への恐怖、また、未知の事象に対する少しの高揚感に包まれたオレの意識すら、その渦の中心にある穴に吸い込まれていく…
己の意識が目の前に広がる螺旋状の真っ黒い海に溶けていくような感覚の中、オレはオレである境界線を越えたような気がした…
頬っぺたに冷たい感覚を覚えて、オレは自我を取り戻した。
パッと眼を開くと、そこには見知らぬ天井があった。
ヌメッした湿っぽい光沢のあるゴツゴツとした岩から、時折、水の粒が滴っている。
それを眺めながら、今オレは…いや、オレの意識は洞窟のような場所にあるのだという事を悟った。
背中にも天井と同じようなヌメッとした冷たさと、岩の尖った部分が当たる感覚もある。
オレはどうやら、洞窟のような場所で寝ていた?いや、倒れていたのか?
明かりはないが、そこかしこに群生している苔が光を発しているように見える。
ヒカリゴケという物か?
オレは上半身を起こしてみた。
周りを見渡すと、やはり洞窟のようだ…
オレの正面、そして背後にも洞窟は続いているようだ…
…
…
…
木林は?
木林はどこだ?
…
…
…
どうやら、オレ一人であるようだ。
これはオレの意識内の場所なのだろうか?
しかし、こんな場所にまるで覚えもないし、心当たりもない。
さらに、オレがオレであるという自覚すら、霞みがかったようにおぼろげに感じる。
オレは自分の手のひらを顔の前にかざしてみた。
オレの手のひらは、輪郭のみそれらしいのだが、まるでボカシ加工された映像のよいにぼやけて見える。
自分の下半身に視線を移してみても、同じようにボヤけて見える。
自分の存在自体が不確かで、ロウソクの火のように強く吹けば消えてしまいそうな気がする。
オレは恐る恐るその場で立ち上がってみた。
どうやら立てるが、立ち上がってみても、やはり自分の存在が不確かであるという感覚は消えない。
オレは何故ここに在るのか?
また、ここで何をすればいいのか?
それさえわからぬ状況は、オレに不安以外を与えてくれない。
眼は見える。
音は聞こえる。
触覚もある。
考える事、思う事もできる。
しかし、それらをどう使えばよいのかが全くわからない。
しばし立ち尽くした後、オレはここにこうしていても、状況は変わらないと判断し、とりあえず、今自分が向いている方向に歩いてみる事にした。
歩き始めて、初めて意識したのだが、かなり広い洞窟のようだ。
天井もかなり高く、10メートル近くあるのではなかろうか…?
やはりそこかしこにヒカリゴケのような物が生えており、行く道を照らしてくれている。
しかし、先は途方もなく長い…
オレは不安に支配されながらも、延々と続く同じ景色の中、不確かな一歩一歩を道に刻んでいった…
どれだけ歩いたのだろうか…?
今までの人生でおよそ歩いた事のない距離をオレは歩いた。
不思議と全く疲れを感じない。
今、オレの意識は夢の中と同じような、物理法則に縛られない状態にあるのだろうと感じる。
試しに、走ってみた。
いくらでも走れる。
全く呼吸が乱れる事もない。
しかも、凄い速さで走れる。
中高と陸上部で短距離をやってきたオレの感覚で測れば、少なくとも五輪のトラック種目すべてで金メダルを獲得できるであろうくらいのスピードと持久力である。
まあ、物理法則に縛られないのなら当たり前の事なのだろうが…
しかし、景色は延々と変わらない。
ずっとループしているように、オレは同じ景色の中を駆けた。
駆けた距離だけ不安が募る。
このまま走り続けて何か変わる保障があるのか?
別の事をすべきではないのか?
そう考えて、オレは走る事をやめた。
立ち止まって、ふと思った。
物理法則に縛られないのなら、ここから出る事もまた、簡単な事なのではないか?
そう思った瞬間、背後から気配を感じた。
自分以外の何者かの気配である。
不安の中に光明が差す。
その気配がオレに何をもたらす者なのかはさておき、自分以外の他者が背後にあるのなら、それを求めるのが人間の性である。
オレは振り返った。
…
…
…
振り返るべきではなかったのかも知れない。
オレは今、見てはいけないものを目の当たりにしてしまった。
オレが今まで駆けてきた途方もない距離…
それを追いかけてきたかのようにはるかに続く鎖…
無数の人間の姿をした肉の鎖が、遥か向こうから続いていて、オレの脚にまで繋がっている。
「うあああああ!!」
オレは悲鳴を上げたが、洞窟はそれを響かせること無く、それを吸収した。
その声に反応したのか、連なる肉の鎖たちのおびただしい目が一斉にオレを見た。
その視線の一つ一つが、まるで矢のようにオレの心臓に突き刺さるような感覚を覚えた。
そして、その肉の鎖の最先端、オレの両脚をつかむ腕の持ち主を確認した時、オレの思考は停止した。
その肉の鎖の最先端は、見覚えのある…いや、忘れるはずもない親友、木林の姿をしていた…
2016年07月07日
扉シリーズ 第三章 第十話 「儀式4」
延々と果てしなく続く肉の鎖…
その最先端になっている親友木林がオレの脚を掴む…いや、巻きついている。
木林の腕が、まるで獲物に巻きつく蛇のように、しなやかに力強く、オレの脚に巻きついてくる。
よく見たら、木林も後ろにいる者に同じように巻きつかれている。
その後ろ者も同じように…
そうやって、肉の鎖は果てしなく先の見えぬ向こうへと繋がっている。
その肉の鎖が蛇のようにのたうつ度に
ジャラジャラ
と肉ではない、鎖そのものが地面に擦れる音がする。
もしや、これが伊田さんの言っていた呪詛の主とオレを繋ぐ「糸」というやつか?
それならば、何故その最先端に木林がいるのか?
もしや、木林は…
いや、そんなことはない!
伊田さんはこの儀式で絶対死ぬ事はないと言っていた。
木林がオレの想像通りになっているわけがない!
ならば、今オレに巻きついているこの木林は木林ではない!
そう思った瞬間、オレの心のずっと奥深い領域で何かが爆発したような気がした。
その爆発のエネルギーが不確かな存在に感じていたオレの全身に駆け巡った。
しばらく忘れていた感情が文字になって心を支配する。
「怒り」だ!
今までの人生でおよそ感じた事のない圧倒的な「怒り」が、オレの心を完全に支配した。
全身に力がみなぎり、オレの拳は鋼鉄のそれに変わったような感覚がした。
この鋼鉄の拳を、この木林…いやキバヤシモドキにぶち込んでやらねば収まりがつかない。
オレは手のひらが潰れんばかりの勢いで拳を握り締めると、それに全身全霊を込め、キバヤシモドキの頭頂部に向けてそれを振り下ろした!
一瞬、オレの拳がキバヤシモドキの頭頂部に炸裂した手応えを感じた後、キバヤシモドキの頭部が弾けるように消失した。
しかし、頭頂部を失いながらも、その腕はまだオレに巻きついて離れない。
やはり木林ではない!
そう確信すると共に、オレの心の中で再度爆発が起こった。
親友の姿を弄ぶ者に対し、また感じた事のない怒りが溢れる!
オレはまた拳を握り締めると、今度はキバヤシモドキの背中にそれを振り下ろした。
またさっきと同じような手応えの後、キバヤシモドキの上半身が消失した。
自由になったオレに、キバヤシモドキの後に続く者達がオレに遅いかかってきたが、今度はオレの脚が鋼鉄の棒に変わった。
オレを捉えようとする肉の鎖を、オレは超人的な動きで、ことごとく撃退していく。
オレはキレていた。
しかし、今自分の置かれている状況だけは直観していた。
この洞窟自体が、呪詛の主とオレを繋ぐ「糸」であり、肉の鎖はその繊維の一本に過ぎない。
今ここにいるオレは、オレの意識体である。
故に物理法則の制限下にはないのだ。
あの香には、インナートリップ、つまり己の意識界に精神を移行させる効果があったのだろう。
それゆえ、全身が爆発しそうな程にピュアに「怒り」という感情が表に現れてきたのだ。
オレは、そんな事を思いながらも肉の鎖を粉砕していく!
しかしそうだ!
この洞窟自体が「糸」であるなら、この洞窟自体を破壊してしまえば、「糸」を断ち切る事ができるのではないか!?
そう思ったオレは、即座にそれを行動に移した。
まとわりつく肉の鎖を無視し、オレは鋼鉄…いや金剛の右拳を洞窟の岩肌に向かって炸裂させた。
激しい手応えを感じた後、オレは目を疑った。
オレの右手が消失している。
痛みはない。
そのかわりに更に激しい怒りが湧き上がってきた!
「うおああああっ!」
言葉にならない声と共に、オレは左拳を岩肌に炸裂させた。
しかし、結果は同じ、オレの左から手が消失した。
そこでオレは冷静さを取り戻した。
「歯が立たない」
左右の手を消失したオレは、いかに物理法則に縛られない意識界においても、この洞窟は破壊できないのだと悟った。
正気に戻った時、肉の鎖は消え失せていた。
しかし、そのかわりに見覚えのある人影がこちらに近づいてくる。
奴だ!
直感した、その人影が八龍で遭遇した、あの老人であると…
手を後ろ手に組み、こちらを凝視しながらゆっくり、ゆっくりとこちらに近づいてくる…
一歩近づくたびに、オレの周囲の空気が重くなるような感覚…
ズシリ
ズシリ
か細い老人とは思えない威圧感が、オレを金縛りにする。
この老人の前には、オレの意識界など宙を舞う綿埃のような、吹けば飛ぶような脆弱なものなのだ。
老人は一歩一歩、オレに近づいてくる。
しかし
バシッ!と何かが割れるような音が聞こえたような気がした。
その瞬間、老人とオレの間に境界線ができた。
洞窟の岩肌に、たった数センチほどではあるが、まるでそこだけ輪切りに切りとられたように、老人とオレの間に境界が生まれたのだ。
老人は歩みを止めた。
「………」
老人は何かを呟いているように見えたが、声が聞こえる事はない。
しかし、老人からオレに向けられた視線が外れる事はない。
パーン
突然、手を打ったような音が洞窟中に響いた。
「ひぅっ!」
オレは突然、息が詰まった時のような、びっくりした時のようななんとも情けなない声を出して、畳に顔を擦り付けている自分に気づいた。
「大丈夫かい、冨ちゃん?」
伊田さんの声だ。
オレは起き上がり、伊田さんを見た。
隣で、木林も何か独り言を言いながら頭を上げてきた。
やはりあのキバヤシモドキは木林の姿を弄んだだけの存在だったのだ。
犯人はどう考えても、あの老人であろう。
しかし、目の前にいる伊田さんの様子が激変している。
50代半ばくらいに見える伊田さんだが、髪に白髪が目立つ。
明らかに黒い部分より白い部分が多い。
更に、目の下が落ち窪み、何日も寝ていないようなクマができている。
声にも張りがないように思う。
「だいぶ持っていかれたけど、なんとか時間稼ぎにはなったかと思うよ?」
伊田さんは、絞り出すような声で、儀式が成功した事をオレ達に告げた。


その最先端になっている親友木林がオレの脚を掴む…いや、巻きついている。
木林の腕が、まるで獲物に巻きつく蛇のように、しなやかに力強く、オレの脚に巻きついてくる。
よく見たら、木林も後ろにいる者に同じように巻きつかれている。
その後ろ者も同じように…
そうやって、肉の鎖は果てしなく先の見えぬ向こうへと繋がっている。
その肉の鎖が蛇のようにのたうつ度に
ジャラジャラ
と肉ではない、鎖そのものが地面に擦れる音がする。
もしや、これが伊田さんの言っていた呪詛の主とオレを繋ぐ「糸」というやつか?
それならば、何故その最先端に木林がいるのか?
もしや、木林は…
いや、そんなことはない!
伊田さんはこの儀式で絶対死ぬ事はないと言っていた。
木林がオレの想像通りになっているわけがない!
ならば、今オレに巻きついているこの木林は木林ではない!
そう思った瞬間、オレの心のずっと奥深い領域で何かが爆発したような気がした。
その爆発のエネルギーが不確かな存在に感じていたオレの全身に駆け巡った。
しばらく忘れていた感情が文字になって心を支配する。
「怒り」だ!
今までの人生でおよそ感じた事のない圧倒的な「怒り」が、オレの心を完全に支配した。
全身に力がみなぎり、オレの拳は鋼鉄のそれに変わったような感覚がした。
この鋼鉄の拳を、この木林…いやキバヤシモドキにぶち込んでやらねば収まりがつかない。
オレは手のひらが潰れんばかりの勢いで拳を握り締めると、それに全身全霊を込め、キバヤシモドキの頭頂部に向けてそれを振り下ろした!
一瞬、オレの拳がキバヤシモドキの頭頂部に炸裂した手応えを感じた後、キバヤシモドキの頭部が弾けるように消失した。
しかし、頭頂部を失いながらも、その腕はまだオレに巻きついて離れない。
やはり木林ではない!
そう確信すると共に、オレの心の中で再度爆発が起こった。
親友の姿を弄ぶ者に対し、また感じた事のない怒りが溢れる!
オレはまた拳を握り締めると、今度はキバヤシモドキの背中にそれを振り下ろした。
またさっきと同じような手応えの後、キバヤシモドキの上半身が消失した。
自由になったオレに、キバヤシモドキの後に続く者達がオレに遅いかかってきたが、今度はオレの脚が鋼鉄の棒に変わった。
オレを捉えようとする肉の鎖を、オレは超人的な動きで、ことごとく撃退していく。
オレはキレていた。
しかし、今自分の置かれている状況だけは直観していた。
この洞窟自体が、呪詛の主とオレを繋ぐ「糸」であり、肉の鎖はその繊維の一本に過ぎない。
今ここにいるオレは、オレの意識体である。
故に物理法則の制限下にはないのだ。
あの香には、インナートリップ、つまり己の意識界に精神を移行させる効果があったのだろう。
それゆえ、全身が爆発しそうな程にピュアに「怒り」という感情が表に現れてきたのだ。
オレは、そんな事を思いながらも肉の鎖を粉砕していく!
しかしそうだ!
この洞窟自体が「糸」であるなら、この洞窟自体を破壊してしまえば、「糸」を断ち切る事ができるのではないか!?
そう思ったオレは、即座にそれを行動に移した。
まとわりつく肉の鎖を無視し、オレは鋼鉄…いや金剛の右拳を洞窟の岩肌に向かって炸裂させた。
激しい手応えを感じた後、オレは目を疑った。
オレの右手が消失している。
痛みはない。
そのかわりに更に激しい怒りが湧き上がってきた!
「うおああああっ!」
言葉にならない声と共に、オレは左拳を岩肌に炸裂させた。
しかし、結果は同じ、オレの左から手が消失した。
そこでオレは冷静さを取り戻した。
「歯が立たない」
左右の手を消失したオレは、いかに物理法則に縛られない意識界においても、この洞窟は破壊できないのだと悟った。
正気に戻った時、肉の鎖は消え失せていた。
しかし、そのかわりに見覚えのある人影がこちらに近づいてくる。
奴だ!
直感した、その人影が八龍で遭遇した、あの老人であると…
手を後ろ手に組み、こちらを凝視しながらゆっくり、ゆっくりとこちらに近づいてくる…
一歩近づくたびに、オレの周囲の空気が重くなるような感覚…
ズシリ
ズシリ
か細い老人とは思えない威圧感が、オレを金縛りにする。
この老人の前には、オレの意識界など宙を舞う綿埃のような、吹けば飛ぶような脆弱なものなのだ。
老人は一歩一歩、オレに近づいてくる。
しかし
バシッ!と何かが割れるような音が聞こえたような気がした。
その瞬間、老人とオレの間に境界線ができた。
洞窟の岩肌に、たった数センチほどではあるが、まるでそこだけ輪切りに切りとられたように、老人とオレの間に境界が生まれたのだ。
老人は歩みを止めた。
「………」
老人は何かを呟いているように見えたが、声が聞こえる事はない。
しかし、老人からオレに向けられた視線が外れる事はない。
パーン
突然、手を打ったような音が洞窟中に響いた。
「ひぅっ!」
オレは突然、息が詰まった時のような、びっくりした時のようななんとも情けなない声を出して、畳に顔を擦り付けている自分に気づいた。
「大丈夫かい、冨ちゃん?」
伊田さんの声だ。
オレは起き上がり、伊田さんを見た。
隣で、木林も何か独り言を言いながら頭を上げてきた。
やはりあのキバヤシモドキは木林の姿を弄んだだけの存在だったのだ。
犯人はどう考えても、あの老人であろう。
しかし、目の前にいる伊田さんの様子が激変している。
50代半ばくらいに見える伊田さんだが、髪に白髪が目立つ。
明らかに黒い部分より白い部分が多い。
更に、目の下が落ち窪み、何日も寝ていないようなクマができている。
声にも張りがないように思う。
「だいぶ持っていかれたけど、なんとか時間稼ぎにはなったかと思うよ?」
伊田さんは、絞り出すような声で、儀式が成功した事をオレ達に告げた。