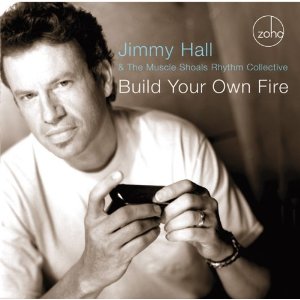2011年04月30日
リック・トレヴィーノ
この人はどういう位置にいる人なんでしょう。
英語で歌う、テハーノ・カントリーなんだと思いますが、とても歌がうまい人だと思います。
そして、コンテンポラリーといいますか、聴きやすいスタイルだとも感じました。
このCDは、リック・トレヴィーノの2枚のアルバムをカップリングしたお得盤になっています。

1. Overnight Success (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
2. In My Dreams (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
3. She'll Never Know (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
4. Downside of Love (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
5. Beautiful Day (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
6. Olivia (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
7. Are We Almost There (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
8. Heartaches (Rick Trevino, Raul Malo, Wally Wilson)
9. So Over (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
10. Have You Ever Really Loved a Woman (Bryan Adams, R.J.Lange, Michael Kamen)
11. Better in Texas (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
12. Separate Ways (Bill Anderson, Jimmy Yeary, Wally Wilson)
13. Whole Town Blue (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
14. Fool for Lesser Things (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
15. Cousin Paul (Rick Trevino, Alan Miller)
16. Loving You Makes Me a Better Man (Rodney Crowell)
17. Because of You (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
18. Autumn Rose (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
19. Remember the Alimony (Rick Trevino, Alan Miller)
20. Matter Much (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
サウンドの印象としては、難しいところですが、あえてアーティストで例えますと、ジョージ・ストレートよりも、ガース・ブルックス寄りかも知れません。
フィドルが目立たないことから、トラディショナル度があまり強く感じられないせいでしょう。
かといって、ポピュラー一辺倒という感じでもなく、バランスのとれた音だとも感じました。
ラップ・スチールのトロピカルなフレーズと、トワンギーなギターが耳に残る、なかなか好感が持てる音づくりです。
ただ、この傾向は、この時期のアルバムだけの可能性もあります。
声の感じはドワイト・ヨーカムに似た印象を受けます。
曲は、自作中心ですが、ラウル・マロとの共作が多いです。
アルバム・プロデュースは、両作ともにマロが行っています。
曲調は、全体的には、カントリー・ロックに接近した音だと思いますが、これは現代のカントリーではもはや特徴とは言い難いと思います。
そんな中で、コースト・カントリーといいますか、ずばりベイカーズ・フィールド風の曲も出てきて、うまくはまっていると思いました。
"Heartaches"なんかが、もろにそんなタイプの曲ですね。
ここでは、ドワイト・ヨーカムを通り越して、その先にバック・オーウェンスの姿が見えるかのような、明るく元気で乾いたサウンドが魅力的です。
やはりチカーノ・ルーツが出た曲がこの人のアイデンティティなのだと思いますが、うれしいことに、パブ・ロック風のフックを持った曲もあって、耳を惹きます。
冒頭の"Overnight Success"は、ニック・ロウを連想させるサビを持った曲で、好感度アップです。
そして、"Better in Texas"では、メキシカン・トランペットの高らかなトーンからスタートして、チカーノ・ルーツを明らかにしています。
"Because of You"は、珍しくフィドルが活躍する伝統的なホンキー・トンク・スタイルの曲で、この流れの中ではむしろ新鮮に感じます。
クラりネットのような、あるいはミュートしたトランペットのようなサウンドを配した仕上げも曲にマッチしています。
"Remember the Alimony"もそれに近いホンキー・トンク・スタイルの曲です。
安酒場の喧騒が思い浮かぶような、ウキウキ感が好きです。
そして、ラストの"Matter Much"は、エヴァリー・フラザーズの名作、"Walk Right Back"を思わせるメロデイを持った曲で、感傷的な雰囲気がたまりません。
この感じは、プロデューサーのラウル・マロの好みが出ているような気がします。
前半よりも後半のアルバムのほうが、若干トラディショナルな印象があるかも知れません。
とはいえ、全体的にはとても聴きやすいサウンドだと感じました。
あえて、欲をいいますと、はちゃめちゃさがもっとあっても面白いかと思います。
このへんは、単に私がバー・バンド好きだからでしょう。
追記
ここまでタイプして、以下のことを思い出しました。
"Matter Much"は、ラウル・マロが最新作、"Sinners & Saints"に収録していた曲です。
そのアルバムでは、"Matter Much To You"というタイトルになっていました。
よければ、関連記事をご覧ください。
関連記事はこちら
罪人と聖者のはざ間で
英語で歌う、テハーノ・カントリーなんだと思いますが、とても歌がうまい人だと思います。
そして、コンテンポラリーといいますか、聴きやすいスタイルだとも感じました。
このCDは、リック・トレヴィーノの2枚のアルバムをカップリングしたお得盤になっています。

In My Dreams/Whole Town Blue
Rick Trevino
Rick Trevino
1. Overnight Success (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
2. In My Dreams (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
3. She'll Never Know (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
4. Downside of Love (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
5. Beautiful Day (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
6. Olivia (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
7. Are We Almost There (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
8. Heartaches (Rick Trevino, Raul Malo, Wally Wilson)
9. So Over (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
10. Have You Ever Really Loved a Woman (Bryan Adams, R.J.Lange, Michael Kamen)
11. Better in Texas (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
12. Separate Ways (Bill Anderson, Jimmy Yeary, Wally Wilson)
13. Whole Town Blue (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
14. Fool for Lesser Things (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
15. Cousin Paul (Rick Trevino, Alan Miller)
16. Loving You Makes Me a Better Man (Rodney Crowell)
17. Because of You (Rick Trevino, Raul Malo, Jamie Hanna, Alan Miller)
18. Autumn Rose (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
19. Remember the Alimony (Rick Trevino, Alan Miller)
20. Matter Much (Rick Trevino, Raul Malo, Alan Miller)
サウンドの印象としては、難しいところですが、あえてアーティストで例えますと、ジョージ・ストレートよりも、ガース・ブルックス寄りかも知れません。
フィドルが目立たないことから、トラディショナル度があまり強く感じられないせいでしょう。
かといって、ポピュラー一辺倒という感じでもなく、バランスのとれた音だとも感じました。
ラップ・スチールのトロピカルなフレーズと、トワンギーなギターが耳に残る、なかなか好感が持てる音づくりです。
ただ、この傾向は、この時期のアルバムだけの可能性もあります。
声の感じはドワイト・ヨーカムに似た印象を受けます。
曲は、自作中心ですが、ラウル・マロとの共作が多いです。
アルバム・プロデュースは、両作ともにマロが行っています。
曲調は、全体的には、カントリー・ロックに接近した音だと思いますが、これは現代のカントリーではもはや特徴とは言い難いと思います。
そんな中で、コースト・カントリーといいますか、ずばりベイカーズ・フィールド風の曲も出てきて、うまくはまっていると思いました。
"Heartaches"なんかが、もろにそんなタイプの曲ですね。
ここでは、ドワイト・ヨーカムを通り越して、その先にバック・オーウェンスの姿が見えるかのような、明るく元気で乾いたサウンドが魅力的です。
やはりチカーノ・ルーツが出た曲がこの人のアイデンティティなのだと思いますが、うれしいことに、パブ・ロック風のフックを持った曲もあって、耳を惹きます。
冒頭の"Overnight Success"は、ニック・ロウを連想させるサビを持った曲で、好感度アップです。
そして、"Better in Texas"では、メキシカン・トランペットの高らかなトーンからスタートして、チカーノ・ルーツを明らかにしています。
"Because of You"は、珍しくフィドルが活躍する伝統的なホンキー・トンク・スタイルの曲で、この流れの中ではむしろ新鮮に感じます。
クラりネットのような、あるいはミュートしたトランペットのようなサウンドを配した仕上げも曲にマッチしています。
"Remember the Alimony"もそれに近いホンキー・トンク・スタイルの曲です。
安酒場の喧騒が思い浮かぶような、ウキウキ感が好きです。
そして、ラストの"Matter Much"は、エヴァリー・フラザーズの名作、"Walk Right Back"を思わせるメロデイを持った曲で、感傷的な雰囲気がたまりません。
この感じは、プロデューサーのラウル・マロの好みが出ているような気がします。
前半よりも後半のアルバムのほうが、若干トラディショナルな印象があるかも知れません。
とはいえ、全体的にはとても聴きやすいサウンドだと感じました。
あえて、欲をいいますと、はちゃめちゃさがもっとあっても面白いかと思います。
このへんは、単に私がバー・バンド好きだからでしょう。
追記
ここまでタイプして、以下のことを思い出しました。
"Matter Much"は、ラウル・マロが最新作、"Sinners & Saints"に収録していた曲です。
そのアルバムでは、"Matter Much To You"というタイトルになっていました。
よければ、関連記事をご覧ください。
Matter Muchです。
関連記事はこちら
罪人と聖者のはざ間で